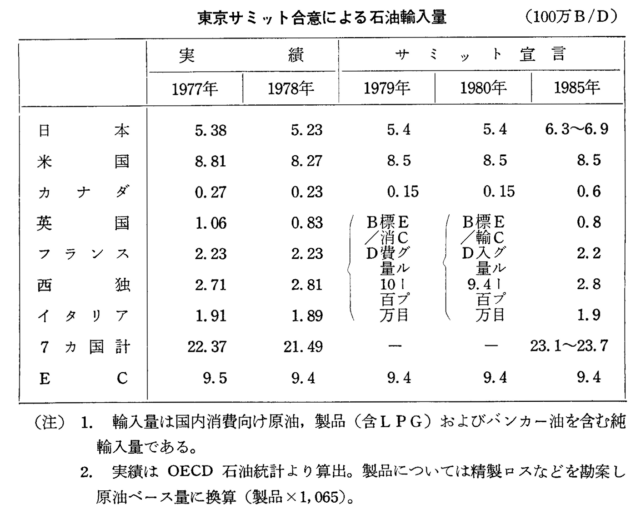
2. 国際経済社会における国際協調
(1) 主要国首脳会議
(イ) 第5回主要国首脳会議(東京サミット)は79年6月28日,29日の両日,東京の迎賓館で開催され,日本,米国,フランス,西ドイツ,英国,イタリア,カナダの首脳及びEC委員会委員長が参加した。同会議では,(a)一般経済政策,(b)エネルギー,(c)貿易,(d)国際通貨・金融,(e)開発途上国との関係などの諸問題について討議が行われ,会議最終日にこれらの諸問題の合意を盛つた「東京サミット宣言」が採択された。この東京宣言のほか,「インドシナ難民問題に関する特別声明」が採択され,また,29日の共同記者会見の際,議長として大平総理大臣より,「航空機ハイジャックに関するステートメント」が発表された。この東京サミットは,わが国外交史上前例のない国家的行事であつたが,会議の成果については参加各首脳より満足の意が表明され,多大の成功を収めることができた。
(ロ) 東京サミットとほぼ平行して6月26日から28日まで,ジュネーヴにて石油輸出国機構(OPEC)の総会が開かれ,原油価格の大幅引上げが決定された。これに象徴されるような厳しいエネルギー情勢のもとで,東京サミットでは多くの時間を費やしエネルギー問題で真剣かつ熱心な討議が行われた。その結果,大胆かつ具体的な「共通戦略」,なかんずく具体的数値を明示した石油消費・輸入上限目標について合意に達したことは,過去5回のサミット史上画期的なことであり,東京サミットが「エネルギー・サミット」と往々称される由縁である。
以下,このエネルギー問題をはじめとして東京宣言の主要合意点を列記してゆくこととする。
(ハ) 最初に,エネルギー問題については,世界的インフレ下における石油価格の大幅な上昇,石油需給の不安は,工業国はもちろんのこと・非産油開発途上国の経済成長にも深刻な影響を及ぼすとの認識から,石油消費の削減,他のエネルギー源の開発の促進が合意された。まず,石油消費の減少をはかるために石油輸入を抑制することとし,79年,80年の輸入・消費目標を合意するとともに,85年の石油輸入の上限目標の具体的数値について合意をみた(別表参照)。
また,石油市場の動きを公開するために,石油の国際取引について登録制を導入することとなつた。次に,代替エネルギーの開発促進では,石炭および原子力の利用拡大,新エネルギー技術の開発および商業化のための国際エネルギー技術グループの創設などが合意された。なお,産
〔別表〕
東京サミット合意による石油輸入量(100万B/D)
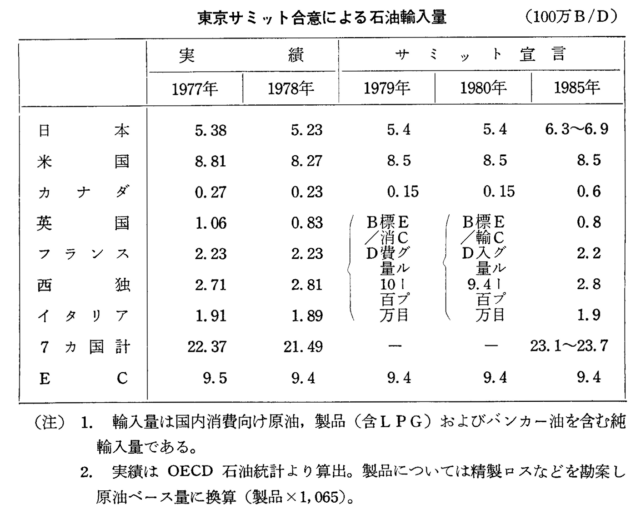
(注)1. 輸入量は国内消費向け原油,製品(含LPG)およびバンカー油を含む純輸入量である。
2. 実績はOECD石油統計より算出。製品については精製ロスなどを勘案し原油ベース量に換算(製品×1,065)。
油国との関係について,OPEC総会における価格引上げ決定を遺憾とする旨表明する一方,産油国と協力して需給見通しにつき検討する用意があることを表明した。
(ニ) 一般経済政策については,各国の経済運営に関し,前回のボン・サミットで合意された政策を,現状に即して調整しながら継続すべきであることに合意をみた。さらに,中・長期的観点から各国経済の生産効率および柔軟性を向上させ,経済体質を強化するため一層努力すべきことが合意された。
(ホ) 貿易については,東京ラウンド(ガットにおける多角的貿易交渉)での諸合意が評価され,保護主義とたたかう決意が確認された。
(ヘ) 国際通貨・金融については,前回のボン・サミットに引き続き,世界経済の発展のためには,通貨の安定が必要であるとの認識が再確認された。さらに今後,国際通貨基金(IMF)とも緊密な協力を続けていくことが確認された。
(ト) 最後に,開発途上国との関係,いわゆる南北問題についてそのグローバルな重要性が認識されたことは,エネルギー問題に劣らぬ重要な成果として指摘できる。すなわち,宣言では,建設的な南北関係は,世界経済の健全化のためにも欠かせない条件であり,南北問題は責任の分かち合いとパートナーシップによつてのみ解決できると述べられており,また,開発途上国に対する経済開発援助の増大,食糧援助,エネルギー分野の協力強化,人造りを含む技術協力の拡充などの合意が掲げられている。また,責任分担という意味で,宣言はOPEC諸国の果たすべき役割の重要性,コメコン(共産圏の経済相互援助機構の略称)諸国による援助勧奨をもあげているのが注目される。
(チ) 以上のサミット宣言とは別に,インドシナ難民及び航空機ハイジャックの二つの問題についても特別声明が発表された。まず,インドシナ難民問題に関する特別声明においては,難民問題解決の緊急な必要性を強く確認するとともに,国連の場における本問題の解決を提案している。
次に航空機ハイジャックに関するステートメントにおいては,ボン・サミットにおいて発表された航空機ハイジャックに関する宣言への支持を確認した。
(リ) なお,東京サミットでの以上のような諸合意の実施状況を検討するために,各国首脳の個人代表などが出席して,12月21日,ワシントンにてレヴュー会合が開かれた。
(2) 経済協力開発機構(OECD)
第18回OECD閣僚理事会は,6月中旬に開催されたが,5月末に終了したばかりのUNCTADVを先進国側としていかに評価するか,また2週間後に控えた東京サミットに対して政策面でいかなるインプットを与えるか,という意味においても広く関心を集めるところとなつた。まず同理事会では,経済成長に対する主要な制約要因はインフレ及びエネルギーであるとの認識のもとに,78年に合意された「協調的行動」(Concerted Action)を若干修正のうえ継続することが確認された。特に,エネルギーについては,事態の重大さを認識し,石油の節約及び代替エネルギー源の利用と開発が不可欠である旨が強調された。次に,構造調整の促進による供給面の改善,貿易プレッジの延長をはじめとする保護主義防遏の決意表明など中期政策についてのガイドラインが合意された。南北問題については,UNCTADVに関し全般的成果は限られたものであつたが,特定の諸分野では貴重な進展があつたと評価される一方,IDS策定や開発のための国連科学技術会議の重要性を指摘するとともに,開発途上国との間で相互に関心を有する分野でOECDがなし得る役割につき検討すべきことなどについて合意をみた。
(イ) 経済政策
5月の経済政策委員会(EPC)は,78年来のOECD諸国による「協調的行動」につき日独の内需拡大,経常収支の不均衡縮小などを評価したのち,今後12~18ヵ月間,米国は景気冷却期間をおきインフレを抑圧する,日独などは内需の伸びの停滞を回避するなど,「協調的行動」を若干修正のうえ継続することとし,これは,前述のとおり,6月の閣僚理で採択されるところとなつた。また,エネルギー情勢のマクロ経済への影響に対する関心は大きく,石油の価格上昇の消費者への転嫁の必要性及び賃金・物価のスパイラル回避の重要性などが強調された。
また,エネルギー政策とマクロ経済政策との連関を探るEPCエネルギー情勢アドホックグループ会合が7月及び9月に開催され,OECD諸国による幅広い政策手段の調和の必要性を強調するとともに,エネルギー問題への中期的政策対応としては総需要抑制や自由放任よりもエネルギー政策が望ましく,かつ,エネルギー政策では価格メカニズムが主要な役割を果たすべきことなどを述べた報告書が11月のEPCに提出された。
11月のEPCでは6月の閣僚理で合意された短期需要管理政策に焦点があてられ,特に米国の金融,財政両面における引締め措置に対して理解が示されるとともに,各国ともインフレ抑制を最優先すべきことにつき意見の一致をみた。なお,米国の高金利傾向に対する懸念も一部の国から表明された。
(ロ) 積極的調整政策(PAP)
78年6月の閣僚理事会で採択されたPAP一般方針に基づき,その後1年間の検討作業が行われたが,その結果をまとめた報告書が6月に公刊された。さらに,EPCのもとにPAP特別グループを設置し,2年間にわたるプログラムを遂行することとなつた。同グループの第1回会合は11月に開催され,今後2年間の作業計画及び政策措置のトランスパレンシーに関する検討を行うテクニカル・サブグループの設置が合意された。また今後の作業の進め方としては,(a)産業政策,労働政策など政策分野別のレビュー,(b)各国の経験についての意見交換,(c)造船,鉄鋼などのセクターに関するレビュー,(d)PAPに関する情報の改善(トランスパレンシー),といつた四つのエレメントからなる活動を通じて,PAPをいかに各国の実際の政策運営に結びつけていくかという観点から検討が行われることとなつた。
(ハ) 貿 易
74年に採択された貿易プレッジは6月の閣僚理で5回目の更新が行われたが,その際かかる形での毎年の延長はプレッジのクレディビリティを低下させるものであり,これ以上単純延長を行うべきでないとの意見が大勢を占めた。
これを受けて貿易委員会は11月の会合において今後のプレッジの取扱いにつき検討を行つたが,何らかの簡潔かつ力強い文書でプレッジを代替させることが望ましく,かつ,新たなプレッジは期限を設けるべきでないとの意見が支配的であつた。本会合においてはこのほか,サービス分野の貿易問題が貿易委の新しい作業対象として本格的に採り上げられることとなつた。
(ニ) 農業委・貿易委合同作業部会
また,6月の閣僚理コミュニケでは,農産物貿易問題についてスタディを行うことが合意されたが,これを受けて9月の本件合同作業部会会合において,農産物貿易問題に関する研究作業手順・検討概要などが討議された。
(ホ) 南北問題
80年の国連特別総会に向けて各種の南北対話のフォーラムの会合が予定されていることを背景に,OECD南北問題を総合的に扱う場として,南北経済問題グループが,9月の理事会において設立された。同グループの第1回会合は10月に開催され,9月末の新執行委員会における議論をも踏まえ,今後の作業計画のほか第19回UNCTAD・TDB及びUNIDOIIIの各準備,及び国連総会で討議されるグローバル・ネゴシエーションについての検討が行われた。
また,一次産品ハイレベルグループも,共通基金交渉へむけての先進国間の準備の場として活用された。
(ヘ) 中進国問題
78年10月の中進国問題専門家会合での議論を踏まえ,新執行委員会,首席代表者会議などの場で検討が行われ,その結果は6月に新興工業国(NICs)レポートとして公表された。
(ト) インターフューチャーズ
わが国の提唱により76年に発足し,西暦2000年を目途に「開発途上国の発展と調和のとれた先進工業社会の将来の発展」について研究する本プロジェクトは,7月に最終報告書を公表した。なお,作業の最終段階において,2月にベルサイユで,宮崎外務審議官(当時)を議長として,本件プロジェクトの掲げる長期的問題について意見交換を行うためのハイレベル会合が開催され,種々の有益な示唆がなされた。
(チ) 主要セクターの問題
造船部会は一般ガイドラインの各国による実施状況を中心に検討を行つたが,造船セクターにおいては,不況の深刻さを反映して,西独・英の助成措置の導入ないし延長など,当座をしのぐための短期的措置が先行した感が強く,この点に問題が残つている。
78年10月の理事会決定により設置された鉄鋼委員会は,79年には,5回の本委員会と4回の作業部会を開催,7月には鉄鋼アウトルックを公表するなど活発な動きを見せた。
(リ) その他
OECDの活動は以上の分野のほか多岐にわたつており,科学技術政策委員会,環境委員会,労働力社会問題委員会,国際投資,多国籍企業委員会,制限的商慣行委員会,海運委員会などの場で幅広い検討を行つている。特に科学技術政策委の枠内の通信政策グループは,78年より個人データのプライバシー保護に関するガイドラインの策定作業を続けており,また,海運委ではOECD加盟国と非加盟国との海運関係についても検討を行つている。