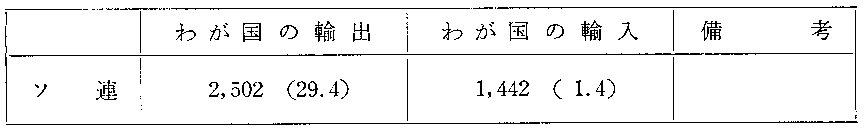
-ソ連・東欧地域-
第6節 ソ連・東欧地域
(イ) 内 政
(a) 1978年のソ連内政においては,前半期に77年10月に制定された新憲法に基づく選挙法,大臣会議法,条約締結・廃棄手続法などが採択され,また,連邦構成共和国,自治共和国レベルの新憲法制定が行われた。その過程でグルジャ共和国においては深刻な民族問題が露呈されて注目をあびた。また,年末新憲法制定後最初の連邦最高会議選挙を79年3月4日に実施することが公表された。
(b) ブレジネフ書記長は,その健康状態が種々取沙汰されたが,78年3月末から4月にシベリア・極東旅行を行つたほか,西独,チェッコスロヴァキアを訪問するなど積極的な活動がみられ,また,最高指導者としての地位には,動揺の兆候は看取されず,むしろこれまで着々と進めてきた人事政策を更に推進してブレジネフ色を強めるなど,今後も政策を担当する意欲を示した。
党指導部においては,7月,若手有力指導者の1人と目されていたクラコフ党政治局員・書記が急逝し,11月には,マズロフ政治局員・第一副首相が解任され,チェルネンコ書記とチホノフ第一副首相がそれぞれ政治局員と同候補に選出されるなど,指導部の大幅な異動があつた。その結果,ブレジネフ書記長の地位は,更に強化されたとの印象を受けるが,同時に,最近西欧諸国が指摘している党指導部(特に政治局)の老令化はむしろ更に深まつたといえる。
(c) 社会面では,ソ連指導部は,米国や西欧諸国の強い非難にもかかわらず,オルロフ,シチャランスキー,ギンスブルグなどの体制批判活動家に対する裁判を強行し今後とも体制批判の動きには厳しい態度で臨むことを示した。
このほか,社会文芸面では,6月に第6回連邦作家大会と全ソ教員大会が開催され,また,ブレジネフの回想録3部作「マーラヤ・ゼムリヤ」「復興」及び「処女地」が発表された。
(ロ) 外 交
ソ連の外交は,その強大な軍事力を背景に,社会主義共同体の強化,西側諸国との緊張緩和,平和共存及び反帝,民族解放闘争支援などを旗印として,世界的規模において弾力的に進められている。ソ連の外交において,当面の最重要課題は,米国・西欧諸国とのいわゆる「緊張緩和外交」の推進及び自国の安全保障にとつて重要性を有する東欧諸国との関係にあると見られるが,78年においては,中国の欧米接近の動き,日中平和友好条約の締結,中・越,越・カンボディア紛争の激化,イラン政変,エジプト・イスラエル和平の動きなどに関連して,アジア,中東における外交が活発化した。
ソ連国内における人権問題,ソ連の軍事力の不断の増大,中東,アジア,アフリカなどにおけるソ連の進出は,東西関係に否定的な影響を与える要因ともなつているが,他方,米ソ間のSALT・II交渉には,ソ連は,積極的姿勢を示している。
(a) 対東欧関係
東欧諸国との関係は,ワルシャワ条約機構,コメコンを通じて,また2国間の関係発展により,政治的,軍事的及び経済的統合の強化が進められており,東欧諸国における体制批判運動,ユーロコミュニズムの影響,経済協力問題など潜在的な問題要因が存在するが,本質的な変化は見られない。ただルーマニアとの関係は,同国の自主独立外交,中国との友好路線のため,特異なものとなつており,ワルシャワ条約諸国ないしコメコン諸国の共同の中国非難にルーマニアが加わらないという事態が続いている。独自の道を行くユーゴースラヴィアとの関係は,ルーマニアとともに行われた華国鋒主席の訪ユや中越紛争に対する同国の立場などにより冷却している。反中国に転じたアルバニアに対して,ソ連は関係正常化を呼びかけているが,同国の反ソ的立場は不変である。
(b) 対西側諸国関係
78年の米ソ関係は,カーター政権の人権外交とこれに起因する対ソ輸出規制,「アフリカの角」やザイール紛争におけるソ連の役割に対する米国の批判,米中国交正常化,中東和平及びイラン政変に際するソ連の対米非難などにより,冷たい空気に包まれ,SALT・II交渉にも若干の影響を及ぼした。しかし78年半ば頃より,SALT・II交渉は進捗し,ソ連は妥結への楽観的態度を示している。
西側諸国とは2国間あるいは欧州安保フォローアップなどを通じて,いわゆる「緊張緩和外交」を進めているが,西側の人権外交攻勢に対しては内政干渉であると反発しつつ,自国の経済発展促進のため西側との経済協力及び貿易関係発展に多大の関心を示している。78年5月のブレジネフ書記長の西独訪問においても,ソ連のかかる意図が窺われた。
ソ連は今後とも西側諸国に対して,軍縮提案,経済協力促進などを中心とする従来の外交路線の展開をめざすものと見られるが,他方,中国の最近の西側諸国への接近政策を警戒し,特に西側諸国の中国に対する武器輸出の動きについて強い関心を示している。
(c) 対アジア関係
中国との関係について,ソ連は日中平和友好条約の締結,米中国交正常化とこれに続くトウ小平副総理の訪米などを極めて警戒的に捉え,これらの動きは中国が米国やわが国との関係を強化して,ソ連に対抗せんとする動きであると対中非難を高めており,更に中越紛争の激化により更に関係は悪化している。
中越の対立激化に伴い,ソ連はヴィエトナムに対する支援を強化し,78年11月,ヴィエトナムとの間に友好・協力条約を締結した。カンボディア紛争では,ソ連はヴィエトナムを強く支持し,国連安保理で拒否権を行使,ラオスを含むインドシナ全域への影響力を強め,ヴィエトナムのソ連艦船の入港などこの地域への軍事的進出の動きを見せた。
前述のようなアジア情勢の新たな動きに伴い,ソ連のアジアにおける外交活動が活発化している。ASEAN諸国に対しては,2国間ベースで諸分野の関係発展を図るとともに,グループとしてのASEANとの関係についても前向きの姿勢を示すに至つている。
インドとの関係は,デサイ政権の対中国関係修復の動きをけん制しつつ,経済協力などを通じてソ印友好関係の維持強化を図つている。
(d) 対中東関係
78年4月クーデターにより成立したアフガニスタンの親ソ政権に対してソ連は強く支援し,78年12月同国と友好・善隣・協力条約を締結した。イラン政変とエジプト・イスラエル和平の動きによる中東情勢の流動化に対応して,ソ連は対中東外交を積極化しており,エジプト孤立化と中東における米国の影響力の減退傾向を助長すべく努めている。またイラン情勢の激動に伴い,トルコとの関係緊密化を図つている。
(e) 対アフリカ関係
アフリカに対しては,ソ連は反帝,民族解放闘争支援,植民地主義,人種差別反対などを旗印に,影響力の浸透を図つている。「アフリカの角」やザイールの紛争とも関連して,エティオピア,アンゴラ,モザンビークなどの親ソ政権に対する支援を強化し,エティオピアとは78年11月友好・協力条約を締結した。
南部アフリカにおいても,ローデシア問題,ナミビア問題について西側諸国が共同で解決に努力している中で,ソ連は周辺諸国や解放勢力との関係強化を図つている。
(ハ) 経済情勢
78年(第10次5カ年計画第3年度)は"突撃労働の年"として増産キャンぺーンが行われたが,計画目標が前年に比し,一段と低めに設定されていたにもかかわらず,一部が僅かにこれを上回つた(鉱工業生産の伸びが目標の対前年比4.5%に対し4.8%)以外は,計画どおりか又は以下に留まり,他方,現行5ヵ年計画の主目標たる「質と効率の向上」のキメ手となるべき労働生産性の向上目標は,同5ヵ年計画の初年度以来,引き続き未達成(78年は目標の3.8%に対し3.6%)となつている。例外は穀物生産で,記録的な豊作(235百万トン)に恵まれたが,これも主として自然条件が幸いしたことによるもので,畜産の不調はじめ農業面にはなお種々の困難を抱えており,農業生産全体としては目標未達成(目標の6.8%増に対し,実績は4.1%増)の状況にある。また,国民所得(支出)の伸びは計画どおり(4.0%)であつた。
内政は,年頭に内部告発的体制批判文書の発表などがあつたが,概して安定基調が続いた。
経済については,社会政策の実施及び原・燃料価格上昇による負担の増大,天候不順などのために全体として計画を若干下回つた。
外交面では,社会主義諸国との結束強化を図りつつ,経済面における西側諸国との交流拡大と対中近東・アフリカ外交の活発化などの政策を進めた。
78年を通じジフコフ政権の安定性は引き続き揺るぎなく,経済面では,77年の農業不振もあつて,78年においても,実績は国民所得成長率(6%)をはじめとして,計画を下回つた。このため79年~80年の変則的な2カ年計画を策定する結果となつている。外交面では,アフリカ諸国との間の活発な首脳レベルの訪問招待外交を行つた。
78年を通じカーダール政権の安定性は引き続き揺るぎなく,経済面でも他の東欧諸国に比して着実に実績を上げている。
対外面ではソ連の方針に沿つた政策を展開したが,カーダール第一書記の訪仏,その他一連の訪問外交を展開した。対米関係には格別の改善がみられなかつた。
「プラハの春」事件10周年を迎えたチェッコスロヴァキアでは,フサーク大統領の地位は揺るぎなく,内政的には安定的に推移した。
経済面では一応量的には計画目標を達したが,更新投資の不活発,対外経済の不振という基調に大きな変化は見られなかつた。
外交面では,ブレジネフ ソ連書記長の来訪など引き続きソ連・東欧諸国との連帯強化に努めるとともに,フサーク大統領は懸案の西独訪問を果たし,西側諸国との関係促進の姿勢も示した。
76年より繰り越された基礎食料品値上げ見送りによる食管会計への財政負担の肥大化,5年続きの農業不振,対西側債務の増大など連年の経済的課題は77年から持ち越されたまま年内に改善をみなかつた。他方,ポーランド人のローマ法王の選出は国民に明るい話題を提供した一方,ギエレク政権はこれによつて複雑微妙となつた教会との関係の対応に苦慮しているやに看取される。
外交面においては,前年にも増して国連及び訪問外交を積極化した。
チャウシェスク大統領の訪米,訪中,華国鋒中国主席のルーマニア訪問など,ルーマニアの自主独立外交は積極的な展開を示した。また11月のモスクワでのワルシャワ条約政治諮問委員会においては,ソ連の軍事費増大要求などに反対し,ルーマニアの対ソ連関係は一時緊張した。
内政面では,チャウシェスク政権は安定しているものの,経済面では,これまでの中央集権的経済計画に基づく量的拡大にも限界がみられ始め,企業の自由裁量を若干とも増大させる方向で,質的転換を志向し始めた。
内政面では平穏裡に推移し,基本的な変化はなかつた。6月に開催された第11回党大会では党執行委員会を廃止し,党幹部会員の人数を縮小するとともに10月には1年任期の党議長代行制を新設するなど集団指導制を目指す党機構の整備が行われ,初代議長代行者にミクリッチ党幹部会員が選出された。チトー大統領は5月に86才の誕生日を迎えたが,第11回党大会など大きな行事をこなして,その健在ぶりを内外に示した。
経済面では前年の順調な経済発展のあとをうけ,年度生産目標を達成したが,貿易収支の赤字縮小,物価上昇率の抑制は未解決に終つた。
外交面では,チトー大統領の訪米(3月),華国鋒の訪ユ(8月)が行われ,特に対中関係では党関係が回復したことによつて完全に正常化され,ユーゴースラヴィアはその国際舞台における足場を強化したとみることができよう。ユーゴースラヴィアが力を入れている非同盟運動については,非同盟諸国間の対立緩和のため,調整の努力を続けた。
ホッジャ第一書記の地位は依然極めて強固であるとみられる。
7月中国の対アルバニア援助打切りを契機として,アルバニアは名指しの対中非難を開始し,ア中関係は事実上決裂の状態となつた。これに伴い,ホッジャ第一書記は「自力更生」路線をさらに強く打ち出すとともに,近隣諸国,北欧諸国などとの関係強化に努めているが,中国からの援助打切りのため国内経済は困難に逢着している模様である。
また,ソ連からは,例年にも増して関係改善の働きかけが行われたが,アルバニアはこれに応ずる姿勢を示していない。
(a) 政府の基本的立場は歯舞,色丹,国後及び択捉の4島の一括返還を実現して平和条約を締結することである。園田外務大臣は1月8日から11日までソ連政府の招待により訪ソし,グロムイコ外相と平和条約締結交渉及び外相間定期協議を行つた(昭和53年版参照)。2月22日ポリヤンスキー ソ連大使は福田総理大臣(当時)にブレジネフ書記長の親書を手交したが,その中で同書記長は日ソ関係を発展させるため「善隣協力条約」を締結したい旨の希望を表明した。翌23日ソ連は善隣協力条約ソ側案を一方的に公表したが,前記日ソ外相会談においてわが方が平和条約案の骨子をソ側に提示したのは,日ソ間で正式に合意されている平和条約交渉の一環として行つたものであり,わが方としてはかかる文書の公表は行つていない。
(b) 78年3月6日ソ連外務省は,日本政府の北方領土返還要求を非難した口頭声明を在ソ日本大使館に対し行ったところ,これは,わが国として全く認めることができない内容を含むものであつたため,同20日政府は,(i)北方4島がわが国固有の領土であることは歴史的,法的にも明白であること,(ii)北方領土返還要求は国民の総意であること,(iii)ソ連側が日ソ間の真の平和と善隣のために,北方4島一括返還により平和条約を締結すべく決断することを強く期待すること,などを内容とする反論を行つた。
(c) 9月25日国連総会に出席した園田外務大臣はグロムイコ外相と会談した。その際,同外相は,日本が善隣協力条約の締結に踏みきるならば,日ソ関係は改善されるであろうとの見解を表明したが,これに対しては園田大臣より,領土問題を解決して平和条約を締結することについてソ連側が前向きの態度を示すことが大前提であり,かかる前提が充たされないまま同条約の検討に入る考えはない旨わが国の立場を述べた。
(d) ソ連が国後島及び択捉島の両島に新たな軍事力の配備及び施設の構築を進めている事実が判明したので,政府は,79年2月5日付でソ連政府に対し,かかる軍事的措置に抗議し,速やかなる撤回を求め,領土問題の早期解決を再度要請する申し入れを行つた。
日ソ間でこれまで具体化したシベリアの資源開発を中心とする経済協力案件は第1次及び第2次極東森林資源開発,パルプ・チップ開発,ウランゲル港建設,南ヤクート原料炭開発,サハリン島陸棚石油探鉱及びヤクート天然ガス採鉱の7件で,このうち第1次極東森林資源開発及びウランゲル港建設の2件は終了しているため,現在実施中のものは5件となつているが,これらは全体として順調に進んでおり,このうち、サハリン探鉱については78年9月,サハリン島北東部大陸棚においてガス層の発見をみるに至つているほか,また,ヤクート天然ガス探鉱に関しては,同年9月,日米の専門家による現地視察が行われた結果,ガスの探査目標の1兆立方米に対し,8,250億立方米が確認されている。
(a) 78年の日ソ貿易は輸入は前年並みの水準に留まつた反面,輸出が大幅な伸びを示したため,貿易規模は日ソ貿易始つて以来の最高を記録した(輸出の増大は主として,従来からの中心品目たる機械・設備はじめ鉄鋼,特に鋼管,化学品の増加による。この反面,繊維品は減退。また輸入の停滞は主として中心品目たる木材,原料炭,繊維原料などの不振又は伸び悩みによる)。
この結果,わが国対外貿易総額に占める比率も前年並みの2.2%に留まつた。
<日ソ貿易>
(1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年増加率(%))
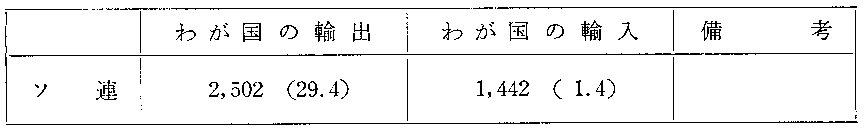
(大蔵省・通関統計)
(b) 第3回日ソ沿岸貿易会議の開催
76~80年日ソ沿岸貿易に関する交換書簡に基づくもので,9月,東京で開催され,沿岸貿易の実績検討及び今後の増進についての意見交換が行われた。
(c) 第21回日ソ貿易年次協議の開催
76~80年日ソ貿易支払協定に基づくもので,10月東京で開催され,両国間貿易の実績検討,今後の増進についての意見交換が行われた。
(a) 日ソ漁業協力協定の締結
200海里漁業水域の設定に関する76年12月10日付のソ連邦最高会議幹部会令の発布及び77年5月2日付のわが国の「漁業水域に関する暫定措置法」の施行に伴い,両国の漁業秩序は大きな転換期に入つたが,このような中でソ連側は77年4月,過去20年間にわたり北西太平洋における日ソ漁業関係の基本的な枠組みとなつていた日ソ漁業条約の廃棄通告を行つたため,78年4月29日をもつて同条約は失効し,これに代わる新たな取極を締結する必要が生じた。
このため77年9月29日からモスクワで交渉が開始されたが妥結に至らず,78年2月15日から再開された。交渉では,特にさけ・ます漁業の取り扱いをめぐり難航したが,大詰めの段階で中川農林水産大臣(当時)が4月11日から訪ソし,イシコフ漁業相との間で精力的な交渉を行つた結果,同21日,日ソ漁業協力協定及び78年度のさけ・ます操業に関する議定書(漁獲割当量42.5千トン)が署名された。なお,日ソ漁業協力協定に基づき両国間の漁業協力を発展させる目的で日ソ漁業委員会が設置されることとなつた。
(b) 「日ソ」及び「ソ日」両漁業暫定協定の延長議定書の締結
77年の「日ソ」及び「ソ日」両漁業暫定協定を78年に向けて1年間延長するための議定書の有効期限が78年末日で満了するに伴い,79年以降の日ソ両国の相手国200海里内の操業を取り決めるための交渉が11月18日から東京で開始され,12月15日,前記の両暫定協定の有効期間をそれぞれ79年に向けて1年間延長する2本の議定書が日本側園田外務大臣,ソ連側ポリヤンスキー大使の間で署名された(漁獲割当量,日本側75万トン,ソ連側65万トン)。両議定書は同26日発効した。
78年1月に開かれた日ソ科学技術協力第1回委員会の議事録に基づき,同年7月原子力と農業の2分野につき専門家会合がモスクワで開催され,原子力分野では高速炉と核融合につきセミナーを開催することを中心とする79年度の協力計画が作成され,農業分野では協力の将来の方向及びテーマにつき合意された。79年3月には第2回専門家会合が開催され,更に協力の具体化につき話し合われる予定である。
78年1月,園田外務大臣訪ソの際,園田大臣よりグロムイコ外相に対し,78年度における北方4島及びソ連本土墓参についてソ連側の特別の配慮を要請した。
4月,政府は78年度の北方4島,ソ連本土及び樺太への墓参実施につき,ソ連政府に対し,日本側の希望どおり実現されるよう申し入れた。
これに対し,8月ソ連側は樺太(真岡,本斗,豊原)への墓参を認めること及びそれ以外の諸地点への墓参については同意できない旨回答してきた。
政府は北方4島及びソ連本土への墓参について,人道的見地からこれが実現されるようソ連側の再考を求めたが,ソ連側は上記の回答を最終回答として確認した。
上記の結果,78年度においては8月24日から同31日に樺太墓参が実施された。
政府は,日本への帰国を希望する在ソ連未帰還邦人に対し帰国指導を行うとともに,機会あるごとにソ連側がこれら未帰還邦人に対し遅滞なく日本への帰国を許可するよう要請してきたが,78年1月,園田外務大臣訪ソの際にもグロムイコ外相に同様の要請を行つた。
78年においては,1名が一時帰国し,2名が(家族を含め6名)が再度一時帰国した。