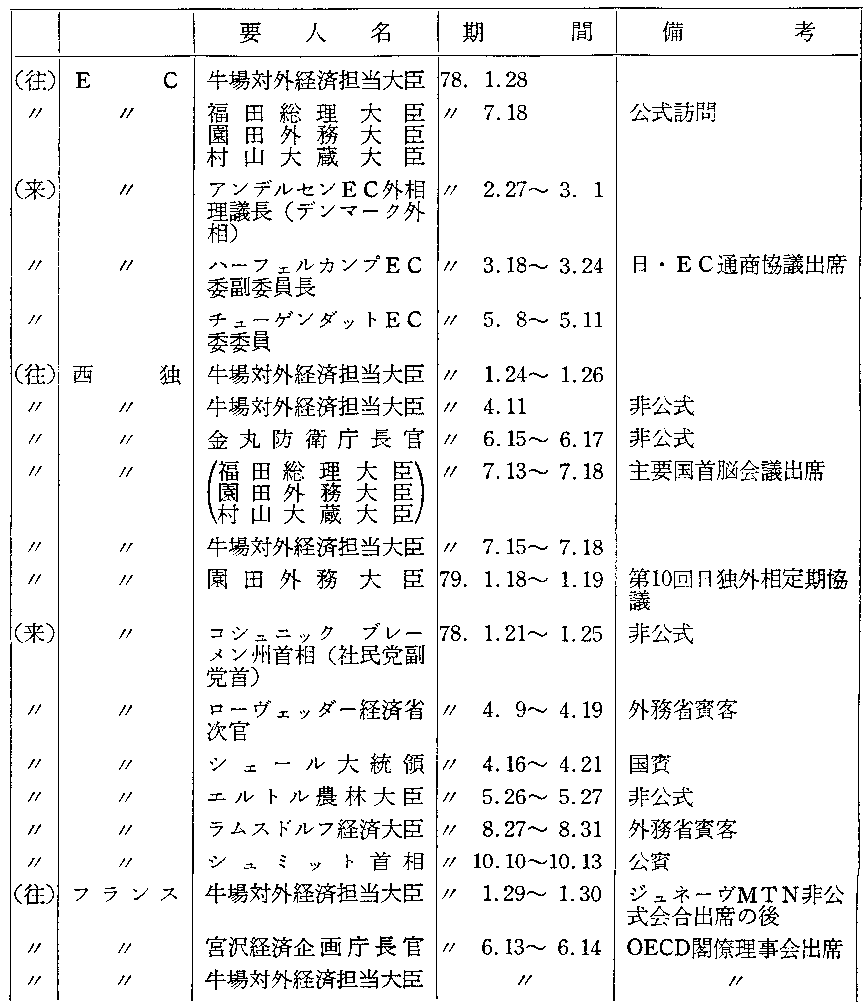
-西欧地域-
第5節 西欧地域
(イ) 1978年の西欧情勢は,77年同様多くの国で与野党間の伯仲状況が続き,全体として困難な政権運営を強いられた国が多かつたが,経済面ではようやく停滞を脱し,景気の回復過程をたどりはじめた国が多く,全体的には明るさをとり戻した。治安面では依然不安定な動きを示した国もあり,テロ行為の激化が懸念された。
(ロ) 78年にはフランス(3月)及びベルギー(12月)で総選挙が行われたが,左翼連合(社・共)の政権獲得可能性が取沙汰されていたフランスでは結果的には左翼連合内部の対立のため,与党派の圧勝に終つた。ベルギーでは選挙後組閣工作が難航し,長期間空白が続いた。
(ハ) 77年に頻発した極左テログループの活動は,78年には大きな動きは示さなかつたものの,イタリアにおいてはモーロ別首相の殺害事件に発展し,政治・社会問題として深刻な波紋を投げかけた。
(ニ) 経済面では景気刺激策が効を奏した国(英,独,伊など),国際収支が改善した国(英,仏,伊など)など緩やかながらも全体としては景気の回復傾向がみられた。しかしながら,多くの国において失業問題の改善はみられず,これが依然大きな社会問題となつている。
(イ) 欧州安全保障協力会議(CSCE)
77年10月4日より78年3月9日までCSCEのフォローアップ会議がベオグラードで開催されたが,実質的内容を有する結論文書の採択には至らなかつた。右結論文書に基づき6月20日から7月28日まで西独ボンで科学フォーラム準備会合が,10月31日から12月11日までスイスのモントルーで紛争の平和的解決のための制度に関する専門家会議が開催された。
(ロ) 中欧相互均衡兵力削減交渉(MBFR)
交渉開始以来5年余を経た本件交渉は78年に入り東側が一部歩み寄りを示したかにもみえたが,兵力データなど基本的問題において依然双方に見解の相違があり,早期妥結の可能性は小さい。
(ハ) NAT0
5月のワシントンNATO首脳会議では長期防衛計画が承認されたほか,加盟国より国防予算の年実質3%程度増額の意向が表明された。また12月の冬季ブリュッセル閣僚理事会では経済困窮国に対する援助などの必要性及びAWACSの導入計画が承認された。
(イ) 政治・経済両面において,各々欧州議会直接選挙実施期間の決定,欧州通貨制度(EMS)の発足と注目される動きがみられた。
(ロ) 政治協力
各国の国内法制整備の遅れにより,その実施が遅れていた欧州議会直接選挙を79年6月7~10日に実施することが4月の欧州理事会において合意された。
(ハ) 経済統合
7月の欧州理事会において設立構想が打ち出された後検討が続けられていた欧州通貨制度の設立が12月決定された。その後,EC共通農業政策をめぐる独・仏間の利害調整に時間を要し,発足は一時遅れたが,79年3月13日より正式に発足した。
(ニ) 対外関係
加盟申請を行つていたギリシャ,ポルトガル,スペイン3ヵ国のうち,ギリシャは年末加盟交渉が実質的妥結に至り,79年5月に協定に署名し,81年のEC加盟が見込まれている。
(a) 連邦参議院における野党の優勢及び連邦議会における与野党伯仲の政治情勢を背景に苦しい議会運営を強いられてきた第2次シュミット連立内閣は,78年前半には更に党内の対立,5月の北部2州の州議会選挙における連立与党自民党の敗退により,一時その存立が危ぶまれた。しかし,10月の州議会選挙において自民党の退潮傾向に歯止めがかかり社民党も票を伸ばすことに成功して以来,ボン・サミットの成功などを通じる経済運営面におけるシュミット首相の手腕に対する国民の信頼の高まりと相まつて,連立政権はその安定度を取り戻しており,80年秋の総選挙に向けての体制と結束を固めつつある。
(b) 西独経済は,78年に入り政府の経済刺激策がようやく効を奏し始めたことにより停滞を脱し,78年の経済成長率は政府目標の3.5%を達成した。更に消費者物価上昇率が2.4%と安定する一方,失業者数(年平均)が4年ぶりに100万台を割つたこともあり,景気は明るさをとり戻した。
(c) 外交面では,経済政策を中心として一時米国との間に意見の相違などがみられたが,7月のカーター大統領の訪独により関係を調整する一方,5月にはブレジネフ書記長の訪独が行われ,ソ連,東欧諸国に対する西独の東方政策がなお健在であることが示された。また,欧州統合面では78年後半にはEC議長国として欧州通貨制度(EMS)の実現に積極的に貢献するなど欧州の強化のために指導的役割を果した。その他第3世界に対する積極的な外交姿勢が注目された。
(a) 内政面では,3月の国民議会選挙において左翼政権誕生の可能性が注目されたが,結局左翼連合(社会党及び共産党)は72年の共同綱領改訂をめぐって意見の対立を露呈したため,与党派(仏民主連合及び共和国連合)の圧勝(89議席差)に終つた。しかしながら総選挙後,与党派内部においては欧州政策,経済政策などをめぐり意見の対立が見られるようになつた。また,左翼連合も事実上崩壊し,社共各党内における党首と執行部との対立が激化した。
(b) 経済面では個人消費を中心とする内需が立直りをみせ,鉱工業生産も全体としては上昇傾向を示した。78年の実質成長率は,政府見通しの3.2%を若干上回り3.3%となった。雇用情勢はなお改善傾向を示さず,失業者数は12月末には123.8万人(失業率5.6%)に達した。物価は依然上昇傾向にあり,特に公共料金の引上げ,工業製品価格の統制解除などの影響もあり,78年全体の物価上昇率は対前年比9.5%であつた。他方,貿易収支は約20億フランの黒字(77年は110億フランの赤字)を計上し,大幅な改善を示した。政府は失業及び物価問題を最重要課題とし,4月,失業対策を中心とする第3次バール・プランを実施した。
(c) 外交面では,ECの強化,西欧諸国の団結を背景とした対ソ・デタント政策の推進に努めた。EMSについては,西独とともに関係諸国との間に原則的合意をとりつけたことは,仏外交の成果であつた。他方,対米関係では,カーター米大統領の訪仏(1月),ジスカールデスタン大統領の訪米(5月)を通じ,良好な関係の維持に努めた。また,対ソ関係では,アフリカにおけるソ連の軍事介入により一時緊張をみせたが,グロムイコ ソ連外相の訪仏(10月)により,両国関係は好転をみた。なお,中東和平問題では,仏は引き続き積極的態度を示した。
(a) キャラハン労働党内閣は,少数党政権として不安定な議会運営を強いられつつも,77年3月以降の自由党との政策協定によりこれを乗りきり,重要懸案となつていた欧州議会議員直接選挙法及び地方分権法を,それぞれ5月,7月に可決成立せしめた。また,経済の再建面でも,インフレの抑制などに一応の成功をおさめた。このため労働党政権の人気が高まりを見せたが,7月に自由党との政策協定が解消され,労働党の議会対策は困難に直面した。このため,にわかに10月総選挙説が有力視されるに至つたが,キャラバン首相は9月7日これを公式に打ち消した。
他方,政府は7月,第4次所得政策として5%賃金ガイドラインを発表したが,英国労働組合会議及び野党はこれに強く反対の意を表明した。12月の国会審議では,ガイドライン及びそれに伴う制裁措置の是非をめぐつて内閣信任案の採決にまで事態が紛糾した。同案は辛うじて可決されたものの,キャラハン首相は,結局制裁措置の撤回を表明せざるを得なくなつた。この結果12月以降労組の賃上げ攻勢が激化し,年末から79年1月末にかけて,ストが相次ぎ,折りからの寒波とあいまつて英国内には相当の混乱がみられた。
(b) 経済面ではインフレの鎮静化,ポンドの安定,国際収支の改善,北海石油の増産など明るい材料が出はじめ,4月の78年度予算では減税を中心とした25億ポンドの景気刺激策が打ち出され,78年度の実質GDP成長率は3%程度になるとみられている。
(c) 外交面では,労働党内に根強い反EC派を抱えているため,労働党政権は慎重な対EC政策をとつた。共通農業政策,漁業水域問題,分担金問題などをめぐつて他のEC諸国との間に利害の対立はあるものの,一般的には対EC外交は順調といえる。なお78年は中国との要人往来の増加など対中国関係緊密化の努力がみられた。
(a) 78年のイタリア政治は,キリスト教民主党(基民党)少数単独のアンドレオッティ内閣を共産,社会,民社,共和,自由の各党が当初「棄権野党」として(第3次「ア」内閣)次いで「閣外与党」として(第4次「ア」内閣,ただし自由党は離脱)協力するという多数派体制による政権運営を特徴とした。
しかしながら,あくまでも入閣を要求する共産党と同党との協力関係を閣外支持の線に留めようとする基民党の立場は相容れず,結局,第4次「ア」内閣は79年1月31日,総辞職のやむなきに至つた。
なお,内政面でのその他の重要な動きとして,モーロ前首相の誘拐・殺害事件を契機とする治安の悪化,レオーネ大統領の辞任,ペルティーニ新大統領の就任などの国政の動きが注目された。
(b) 経済面では,政府の景気刺激策が年半ばに至つて効を奏し,工業生産は上向きに転じ,経済は緩やかな回復期に入つた。しかし失業問題の改善は見られず,依然として7.5%の高失業率が続いており,また,物価上昇率も12.1%まで下降した(77年17%)ものの,依然2桁台に停まつている。他方,輸出は好調に推移し,78年の国際収支は,約83億ドルの大幅黒字を記録した。78年の国内総生産(GDP)実質成長率は2.6%で,77年の2%を上回つた。
(c) 外交面では,政治危機のためもあり,EMS参加決定(12月13日)を除き,特に注目すべき動きはなかつた。
ヴァチカンにおいては10月22日,ポーランド人のヴォィティワ枢機卿が第264代目のローマ法王に就任した。イタリア人以外から法王が選出されたのは456年振りであり,特に共産圏出身の法王として注目を集めた。スペインでは12月の国民投票を経て新憲法が成立した。また,ポルトガルでは第2次ソアーレス内閣が崩壊し、11月モタ・ピントを首班とするテクノクラート政権が誕生した。
伝統的友好関係によつて結ばれている西欧諸国とわが国は,近年,先進民主々義国の一員として米国とともに世界経済の発展に多大の貢献を行うことが期待されており,政治,経済,科学・技術などの諸分野において交流及び協力の顕著な動きがみられる。特に78年は要人の往来が極めて活発に行われ,日・西欧間の相互理解を促進する上で大きな貢献を行つた。
わが国からは7月の主要国首脳会議(ボン)への福田総理大臣(当時),園田外務大臣,村山大蔵大臣(当時)の出席及びその後のEC委員会訪問などが行われ,西欧からはハーフェルカンプEC委副委員長(3月),シエール西独大統領(4月),ティンデマンス ベルギー首相(9月),シュミット西独首相(10月)などの訪日が行われた。また,第12回日英定期協議のための園田外務大臣の訪英,第15回日仏定期協議のためのドギランゴー仏外相の訪日,第4回日伊定期協議のためのフォルラーニ伊外相の訪日などが行われた(詳細については別表参照)。
(日・EC関係)
(a) ECはかねてより域内の経済困難を背景として,対日貿易不均衡の拡大傾向に強く懸念を表明し,EC産品の対日輸出上の各種困難につき改善を求めてきていた。これに対し,わが国は具体的な問題に則しEC側と日・ECハイレベル協議などの場において話合いを通じ問題の解明・解決を図つてきている。
(b) 78年においては,3月に行われた日・EC通商協議が日・EC共同コミュニケの発表をもつて妥結に至つたことが,まず特記すべきことであつたが,その後も6月及び12月の日・ECハイレベル協議あるいはMTNなどの場において,通商関係改善のための双方の努力が行なわれ,数多くの分野において,進展がみられた。EC側が最大の懸案としている貿易不均衡問題については,わが国はEC側の対日輸出拡大を通じ,徐々に改善を図つていくとの方針を有しているが,78年においては,EC側の対日輸出がわが国の対EC輸出の伸びを上回る好調な伸びを示したこともあり,ドルベースでは若干黒字幅は増加したものの,その黒字の増加幅は従前に比し縮小し,また,円ベースでは不均衡幅は減少し,過去数年間の不均衡拡大傾向に改善の兆しがみられた。EC側はかかる状況のもと,今後の事態の推移を見守るという基本的姿勢をとりつつ,引き続きわが国市場の一層の開放のため輸入検査手続の簡素化などにつき要請越している。
<要人往来>
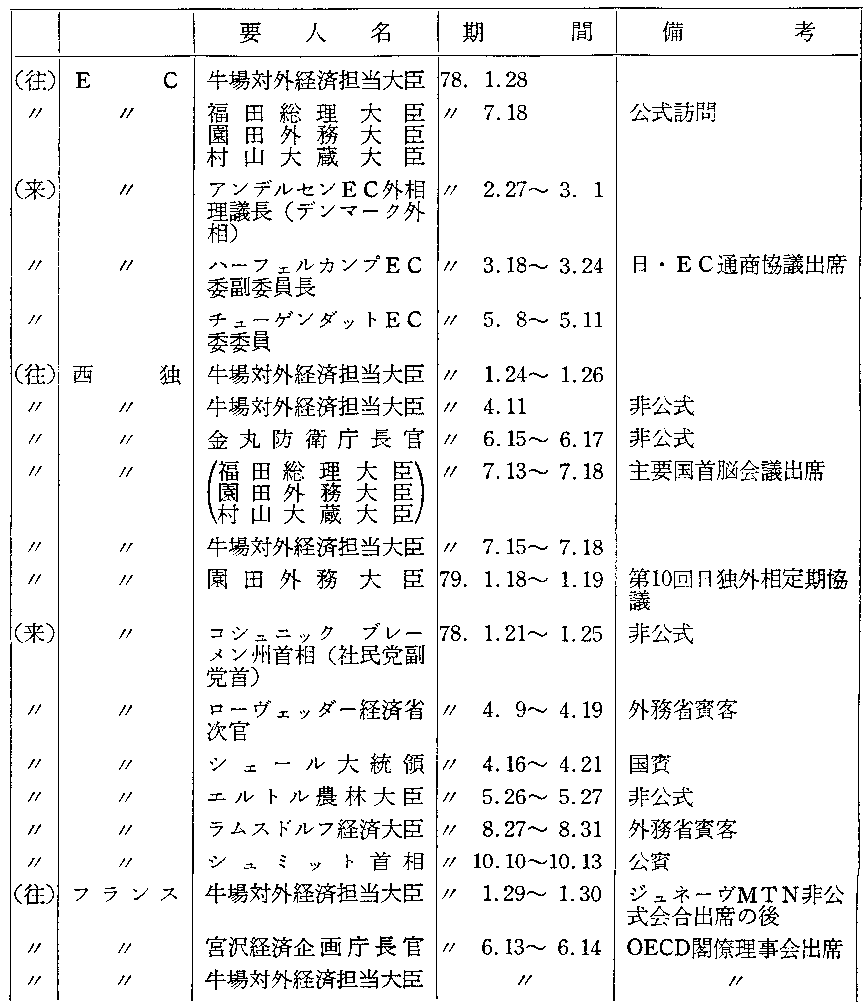
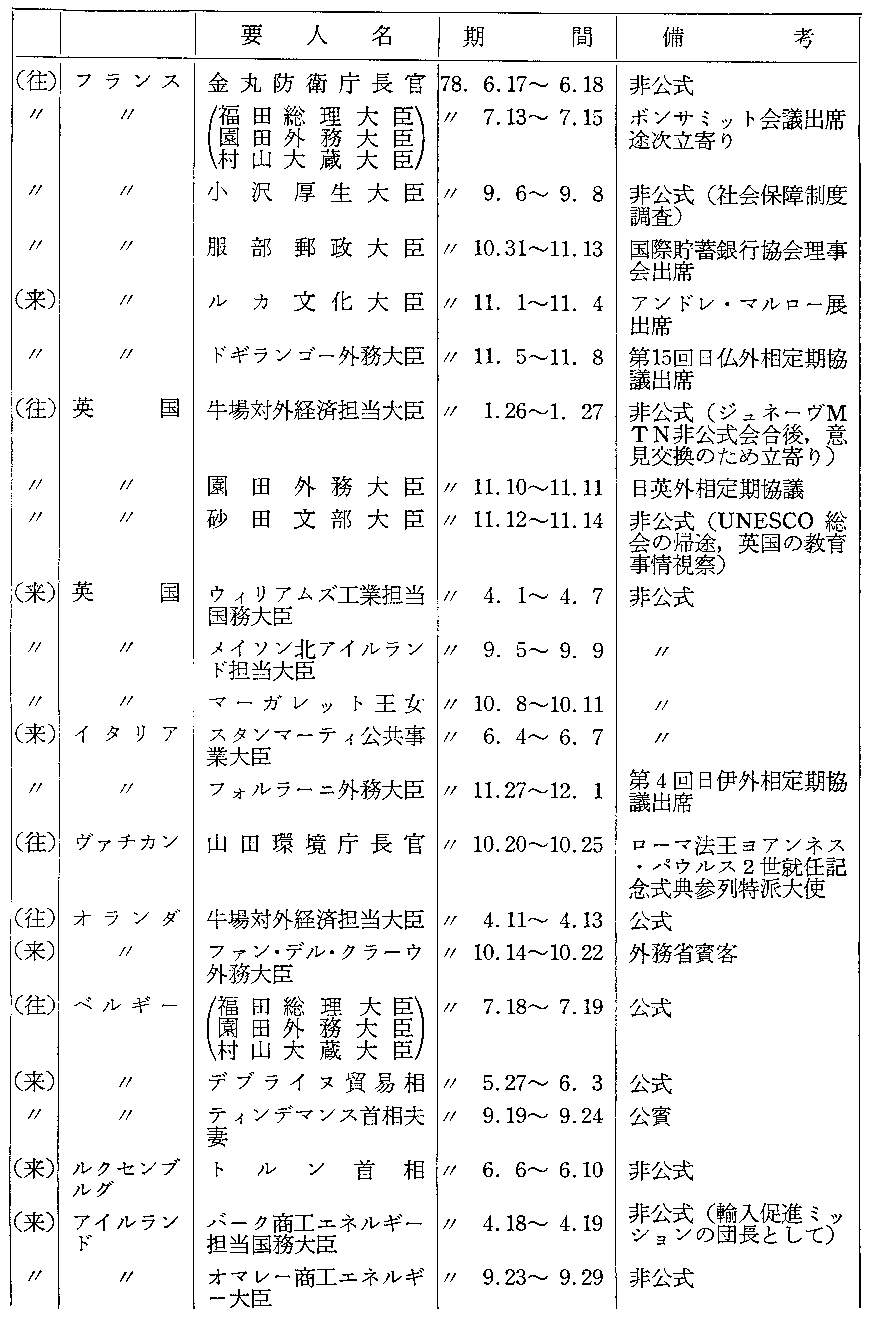
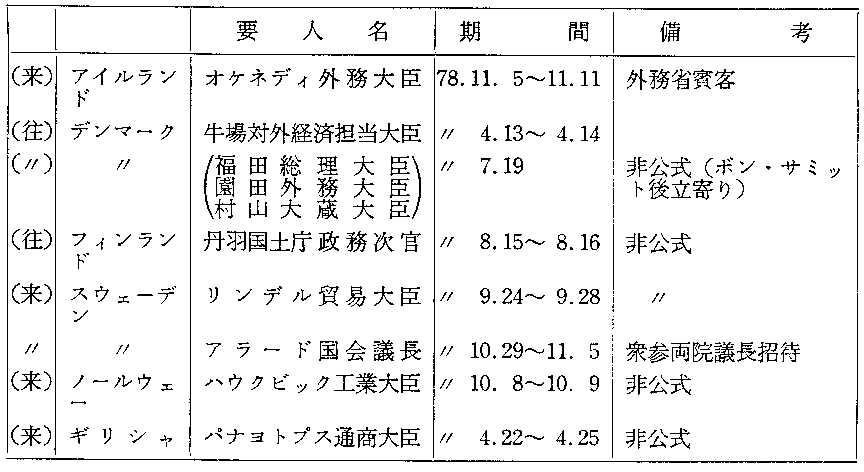
<貿 易>
(1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年増加率(%))
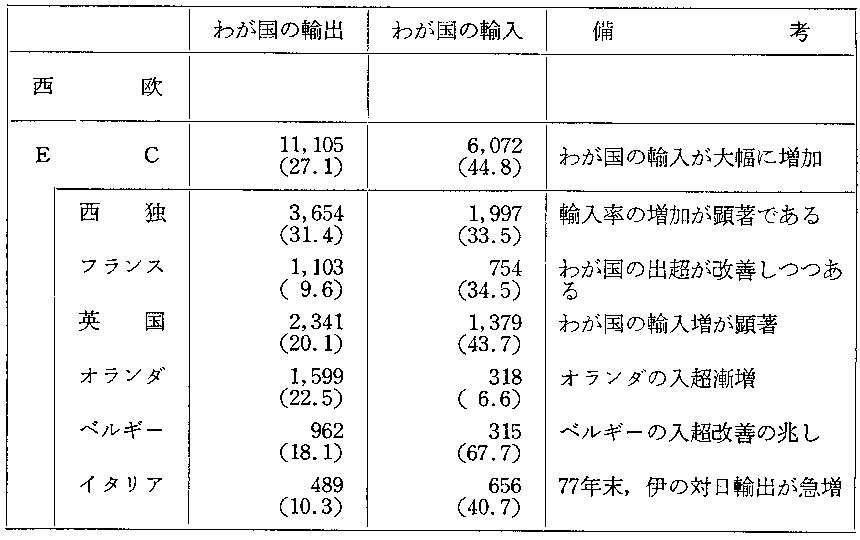
(輸出はFOB,輸入はCIFベース)
(出所:大蔵通関統計)
<民間投資>
(あ) わが国の対西欧直接投資
(単位:百万ドル)
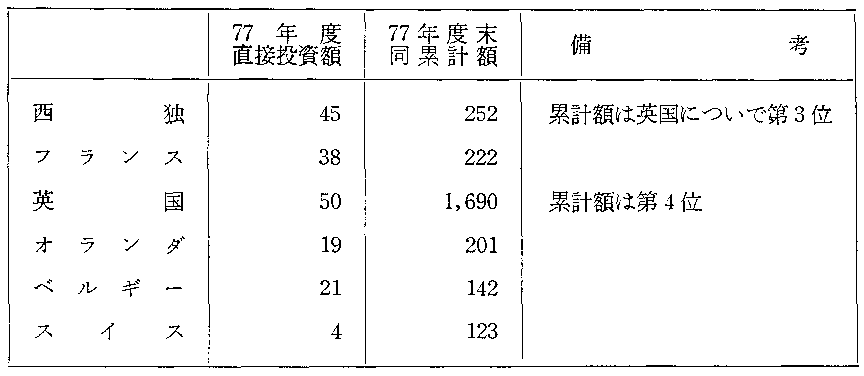
(日銀許可額ベース)
(い) 西欧諸国のわが国に対する直接投資
(単位:百万ドル)
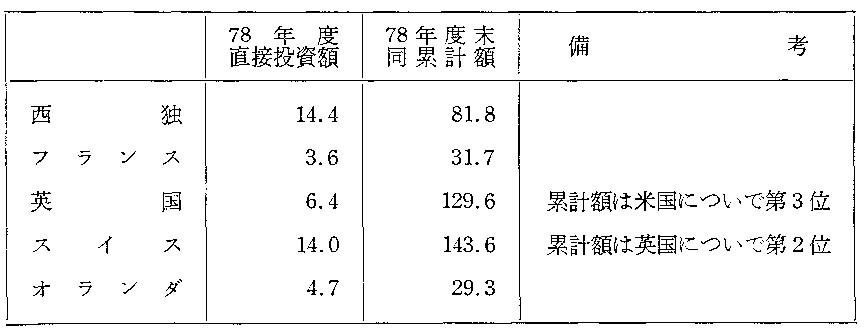
(日銀許可額ベース(経営参加的株式取得))