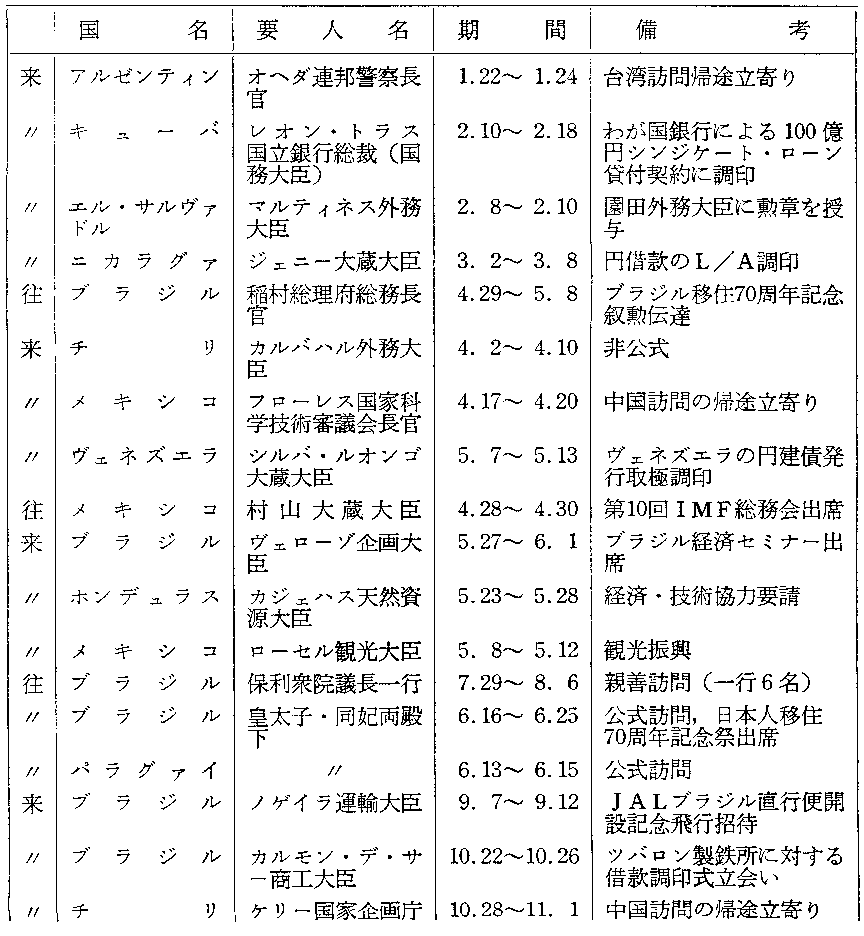
-中南米地域-
第4節 中南米地域
中南米は,従来よりクーデター,テロなどが頻発し,政情が必ずしも安定的でない地域として一般に理解されてきたが,ニカラグァなど一部の諸国を除き,近年,全体として比較的安定した状態が続いている。
かかる状況を背景に,1978年は中南米28ヵ国のうち10カ国(コスタ・リカ,パラグァイ,コロンビア,グァテマラ,ドミニカ共和国,ボリヴィア,エクアドル,パナマ,ブラジル,ヴェネズエラ)において大統領選挙・国会選挙をはじめとする各種選挙が実施され,その多くの国において新政権が発足することとなった。その意味では,78年は中南米における政権交替の年であつたと言えよう。しかしながら,新政権の多くは前政権の築いてきた政策路線をおおむね引き継いでいくものとみられている。
他方,中南米地域では,軍部が直接・間接的に政権を掌握している国,あるいは軍部の政治に対する影響力が極めて強い国などが多く見受けられるが,近年,これら諸国の間に民政移管への動きが現われ始めており,エクアドル,ペルー,ホンデュラスなどの諸国では民政移管のための具体的諸手続が進行中である。ちなみに,78年にはペルーで制憲議会選挙が実施され,憲法草案作成手続が進められたほか,ホンデュラスで「選挙及び政党組織法」が施行された。79年には,エクアドル及びボリヴィアで民政移管のための総選挙が予定されている。
中南米諸国の間では,政府首脳間の相互訪問が近年とみに増加している。78年においてはカイゼル ブラジル大統領のメキシコ訪問,ヴィデラアルゼンティン大統領とピノチェット チリ大統領の相互訪問,ヴィデラアルゼンティン大統領のボリヴィア訪問,ストロエスネル パラグァイ大統領のブラジル訪問,モリーナ ペルー首相のアルゼンティン訪問などがその主なものとして注目された。
アンデス地域統合,ラテン・アメリカ自由貿易連合(LAFTA)に代表される経済統合は,特に目立つた動きを示さなかつたが,ラテン・アメリカ経済機構(SELA)は,78年11月,19ヵ国代表の参加のもとに第1回諮問会議を開催し,SELA・EC関係強化の方途につき協議を行つたほか,79年2月には,国連貿易開発会議第5回総会(UNCTADV)に向けた中南米グループ調整会議の事務局として活躍するなど,地道な活動を継続している。また,78年7月には,アマゾン河流域の開発・環境保全のための協力を謳つたアマゾン協力条約が,流域8ヵ国(ブラジル,ヴェネズエラ,コロンビア,ペルー,ボリヴィア,エクアドル,スリナム,ガイアナ)の間で調印され,新たな域内協力関係の基盤となつた。
しかしながら他方,ビーグル海峡問題をめぐるチリとアルゼンティンとの対立,国境線及び海口取得問題をめぐるチリとボリヴィア間の対立など,領土をめぐる域内諸国間の対立・抗争も小規模ながら後を絶たなかつた。
チリ,アルゼンティン両国は,77年2月以来,同問題に関する合同委員会を設置し問題解決の糸口を見い出す努力を重ねてきたが,同委員会が結論の提出を義務づけられた11月のタイム・リミットが近づくにつれ,一時は両国とも臨戦体制に入るなど極めて緊迫した空気が漂つた。その後,同問題はローマ法王庁特使による調停活動の結果,79年に入つてから本件紛争の調停を正式にローマ法王に依頼することが両国間で合意され,最悪の事態は一応回避された。
他方,チリ・ボリヴィア間では,78年8月,国境線の標識が意図的に動かされるという事件が発生し,両国間で非難の応酬がなされたほか,軍隊が警戒体制に入るなど一時緊迫した空気が流れたが,武力抗争には発展しなかつた。
また,中米においては,ニカラグァの内乱を中心とした情勢の展開が,単にニカラグァ一国の国内問題にとどまらず,コスタ・リカなどの近隣諸国及び米州機構などの国際機関をも巻き込みつつ,国際問題に発展した。
(イ) 対米関係:中南米諸国にとつて米国との関係は地理的・歴史的理由により依然として大きな比重を占めているが,全般的傾向としては,近年,経済開発を基盤とした中南米諸国の国際社会におげる比重の相対的な向上を背景として,これら諸国は米国に対しより対等な関係を求めるようになつてきており,また,米国としても従来の家父長的な関係を改めるべく努力してきている。78年3月に行われたカーター大統領のヴェネズエラ,ブラジル両国訪問及び79年2月のメキシコ訪問は,いずれも米国が中南米諸国との友好協力関係の維持・発展を再確認するものであった。
また,78年6月には米国・パナマ間においてパナマ運河条約批准書の交換が行われ,長年の懸案に終止符が打たれた。
米・キューバ関係については,カーター政権発足後,米国人のキューバ渡航制限解除,漁業協定の締結,利益代表部の相互設置,政治犯の釈放など,注目すべき進展がみられたが,78年初頭よりキューバ兵のアフリカ進出が米国の世論を硬化させ,両国間の正常化の動きは現在中断されるに至つている。
カーター政権発足以来中南米諸国との間で波乱を生じてきた人権問題は,78年6月の第8回米州機構総会において再度議論の対象となつたが,人権外交を内政干渉として強い反発を示してきた一部中南米諸国も前回総会の時ほど強い対立の姿勢はみせなかった。
(ロ) 対西欧・カナダ関係:西欧諸国及びカナダは,一方で自国の工業製品の輸出促進を図りつつ,他方で必要資源の安定的供給を確保するとの見地から,特にブラジル,メキシコ,ヴェネズエラに重点をおいて,通商関係の緊密化及び企業進出の促進などに外交的努力を傾注しつつある。特に最近の動きとしては,ジスカール・デスタン仏大統領のブラジル(78年10月)及びメキシコ(79年2月)訪問,カルロス スペイン国王の中南米諸国歴訪(78年11月),並びにシュミット西独首相のブラジル訪問(79年4月)に象徴される首脳外交の活発化が注目される。
右に対し,中南米諸国の側も外交の多角化を推進するとの見地より西独,仏をはじめとする西欧諸国及びわが国との関係強化に努めており,かかる外交努力は,特に科学技術協力,技術移転,外資導入,中南米産品の市場アクセスの拡大などの諸分野において顕著である。例えば,伯・西独原子力協力協定の締結,ガイゼル大統領の訪西独(78年3月),シャーベス次期副大統領の欧米諸国歴訪(78年12月)などの一連の動きは、いずれも多極化世界のバランスを巧みに利用したブラジルの多角化外交の一環であつたと言えるし,また,78年秋のポルティーリョ大統領の訪日もメキシコの外交多角化の表われと言えよう。
(ハ) 対共産圏関係:共産圏諸国は,中南米地域における政治的な影響力の拡大に重点をおいている。ソ連は,キューバとの関係推進を除き,特に目立つた動きをみせていない。中国は,78年6月の姫鵬飛外相によるヴェネズエラ・メキシコ訪問,同年7月の耿飈副総理によるカリブ諸国歴訪などにみられるように中南米諸国との人的交流を進めている。
右に対し,中南米諸国の側では,78年のロペス・ポルティーリョ メキシコ大統領の訪中(ただし,同大統領は同年ソ連も訪問),クビリョス チリ外相の訪中,アルゼンティン,ブラジルによる経済使節団の中国派遣,ブラジル,チリによる中国との長期貿易取極の締結などにも窺われる如く,最近中国に対するアプローチを積極化しつつある。
(イ) 76年,77年と穏やかながら概ね順調に回復基調を辿つた中南米経済は,全体としては,78年においてもその回復基調には基本的な変化が見られなかつた。しかし,旱ばつ・水害などの自然要因に根ざす農業部門での好不調が,一次産品に依存するモノ・カルチャー型経済の国々の経済成長に少なからぬ影響を与え,国によつては厳しい経済運営を余儀なくされた諸国もあつた。
(ロ) 中南米諸国における最大の経済問題の一つであるインフレの昂進に対しては,域内諸国の多くが景気引締策などのインフレ対策を強化したが,依然として高いインフレ率に悩んでいる国が少なくない。
(ハ) 中南米地域の貿易は,近年恒常的な入超を続けているが,78年の貿易収支は77年を上回る大幅な入超となつた。
外貨事情は,海外からの借款取入れ,投資の増大などの要因もあり,多くの国々で好転しており,中南米地域全体でも76年,77年に引き続き外貨準備高は大きく増加した。このような事情を反映して,アルゼンティンなどでは対外債務の繰上げ償還が進められたほか,その他の国においてもペルー,ニカラグァを除き債務償還が順調に行われた。
(イ) アルゼンティン
78年8月,ヴィデラ大統領が陸軍を退役し,81年3月の任期終了まで大統領職に専任することとなつた。また同時にヴィデラ体制の基礎固めが行われたが,反面実質成長率(推定)がマイナス4%,インフレ率(推定)が170%と経済情勢は非常に厳しいものであつた。
(ロ) ヴェネズエラ
ペレス政権は,石油をもとに野心的な経済開発政策を進めてきたが,78年には,OPECの石油価格据置などのため石油収入が減少したこともあり,国際収支の大幅な悪化などを生じた。78年12月の大統領選挙では第1野党のエレラ候補が当選したが,新大統領がこれに如何に対処するか注目されている。
(ハ) キューバ
政治的動向には基本的変化はなかったが,経済面では輸出の85%を占める砂糖の価格が低迷したこともあり,困難な状況から脱出できなかつた。
(ニ) コロンビア
78年6月の大統領選挙でトルバイ(自由党)が選出され,8月に新政権が発足した。また与党自由党は議会(上下両院)においても過半数を占めた。新政権は,当面の政策目標として,(a)インフレ抑制,(b)司法・行政・教育制度などの改革,(c)治安対策の強化,などをかかげている。
(ホ) チ リ
ピノチェット軍事政権の現実的な政策運営の下で,貿易自由化も一応軌道にのり,外貨事情も改善し,またインフレも比較的収まり,経済的には安定化へ向かい大きく前進した。また,人権問題についても,国連人権委員会調査ミッション受入れに合意するなど,柔軟な姿勢を示した。
(ヘ) ブラジル
78年11月に大統領選挙が実施され,ガイゼル大統領の後任としてフィゲイレード将軍が選出され,79年3月,新政権が正式に発足した。経済面では天候異変による農業生産の不振がみられたが,他方,旺盛な投資意欲を背景に工業部門は6%の成長率を達成した。
(ト) ペ ル ー
経済危機打開のため,モラーレス政権は,緊縮財政措置をとり財政建直しを図ろうとしたが,必ずしも満足すべき成果が上がらず,失業率の増加,賃金の低下などのため国民の不満が昂じる結果となつた。また,労働組合の全国的ストライキも増加しており,今後の政府の経済運営如何が注目されている。
(チ) ボリヴィア
78年7月に民政移管のため大統領選挙が実施されたが,選挙管理委員会により選挙結果の無効が宣言され,結局,ペレダ将軍の無血クーデターによる政権交替という結果に終つた。その後,同年11月,クーデターによりパディリャ新政権が成立し,79年7月に民政移管のための総選挙を実施する旨公約している。
(リ) メキシコ
ロペス・ポルティーリョ大統領は,前年に引き続きインフレ抑制,緊縮財政政策をとるとともに,石油資源の積極的な開発を図ることで,76年の前政権末の経済混乱を脱却し,経済を回復基調の軌道に乗せることに一応成功したものとみられている(78年の経済成長率は,77年が3.2%であつたのに対し,5%以上となつたことが確実視されている)。また,同大統領は,国内における指導力をほぼ確立し,それを基礎として政治改革,行政改革を遂行しつつあり,今後の政治,経済,社会発展の基礎固めを行つたと言えよう。
わが国と中南米との間には困難な政治問題はなく,両者の関係は要人の相互住来の頻繁化,経済交流の活発化,経済・技術協力の拡充などを通じますます緊密の度を深めてきている。
78年には,皇太子・同妃両殿下がブラジル,パラグァイ両国を公式訪問され,特にブラジルにおいては移住70周年記念式典に御出席され,在伯日系人から熱烈な歓迎を受けられた。他方,中南米からはロペス・ポルティーリョ メキシコ大統領を国賓として本邦に迎え,首脳会談などを通じ両国の相互補完的関係促進のための地固めが行われた。
78年のわが国と中南米諸国との貿易は,輸出6,621百万ドル(対前年比+5.2%),輸入3,047百万ドル(対前年比△0.6%)を記録し,貿易総量でやや増加がみられたが,71年以来続いているわが国の出超はさらに増大する結果となつた(77年32億ドル,78年36億ドルの出超)。また,わが国の貿易量全体に占める対中南米貿易量のシェアは,輸出で6.8%(77年7.8%),輸入で3.8%(77年4.3%)と若干縮小した。
78年12月末現在のわが国の対中南米直接投資許可実績は,累計ベースで2,193件,4,208百万ドルとなつており,わが国の投資総額に占めるシェアは16.4%とアジア,北米に次いで第3位となつている。また,78年4~12月の投資許可実績でも,185件,451百万ドル(シェア13.0%)と北米,アジアに次ぐ高い実績を記録した。
(イ) 技術協力協定の締結
わが国は従来よりいくつかの中南米諸国と技術協力協定の締結交渉を行つてきたが,78年3月ボリヴィアと,同年7月チリと,79年2月パラグァイと各々交渉が妥結し,技術協力協定が締結された。これら協定は,いずれもわが国が相手国に対し専門家派遣,機材供与などの各種技術協力を行い,他方,相手国側が,わが国専門家に対し特権免除の供与など必要な国内的諸措置をとることを主な内容としている。
(ロ) 民間レベルの経済協力
78年はアルゼンティンとの間で,パタゴニア沖における試験操業とのパッケージとして,わが国調査船による水産資源調査の実施をはじめとする漁業協力が行われた。また,ブラジルとの間では,日伯農業開発会社の設立,ツバロン製鉄所建設計画融資契約の調印などに窺われるように,大型協力案件が順調な進展ぶりをみせた。
(ハ) 政府開発援助(別表参照)
<要人往来>
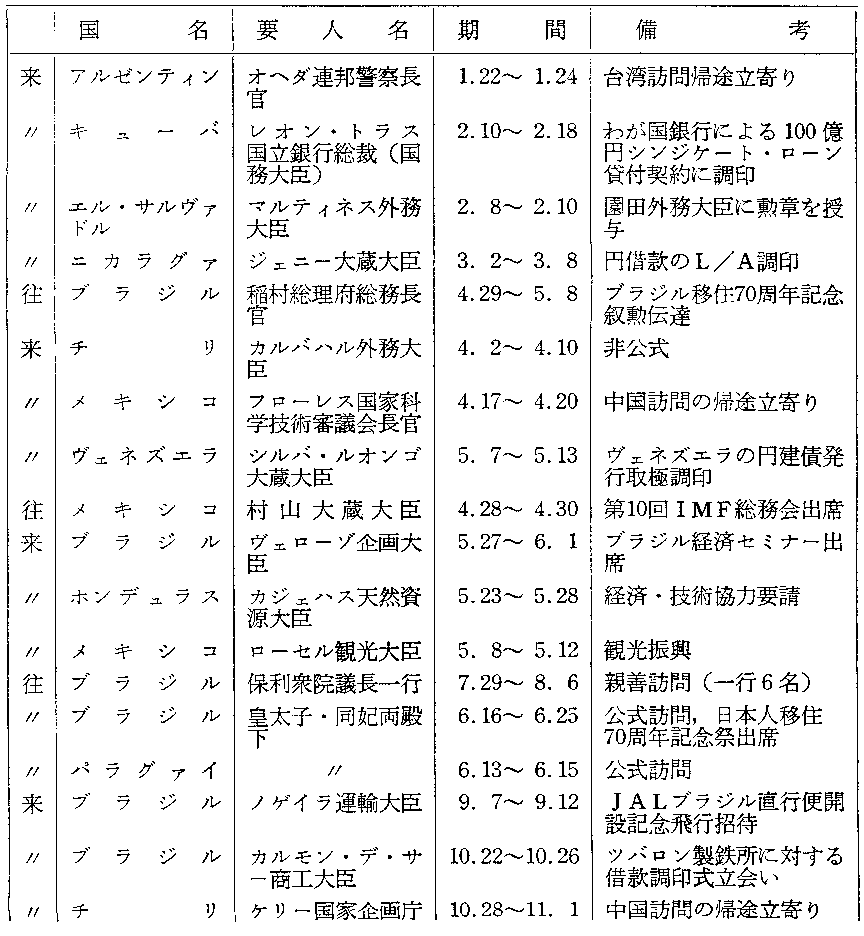
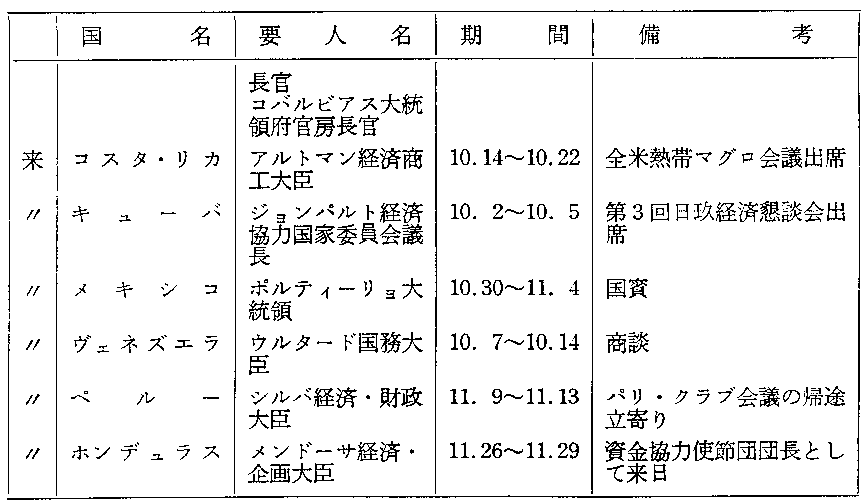
<貿 易>
(1978年;単位:百万ドル:( )は対前年度増加率(%))
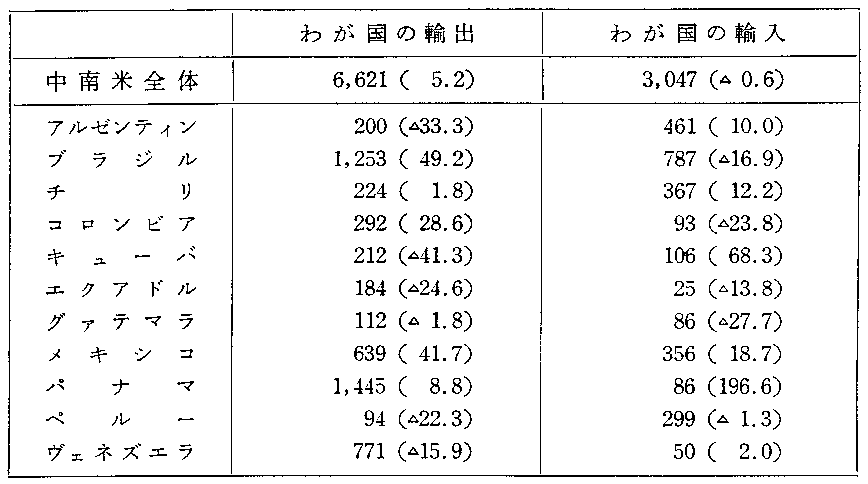
<民間投資>
(単位百万ドル)
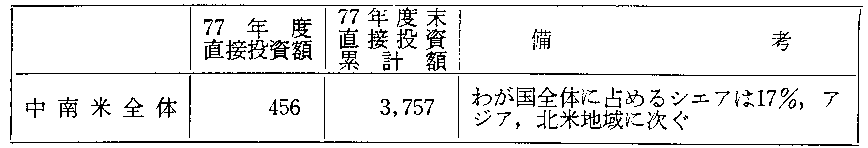
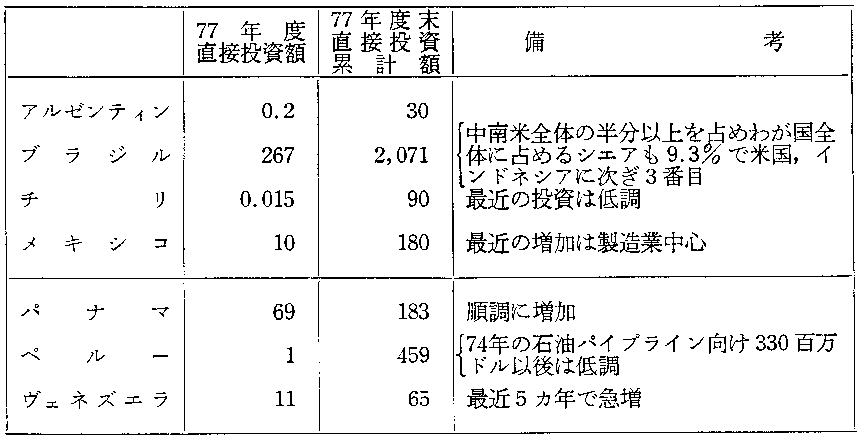
(日銀許可額ベース)
<経済協力(政府開発援助)>
(1978年;単位:百万円,人)
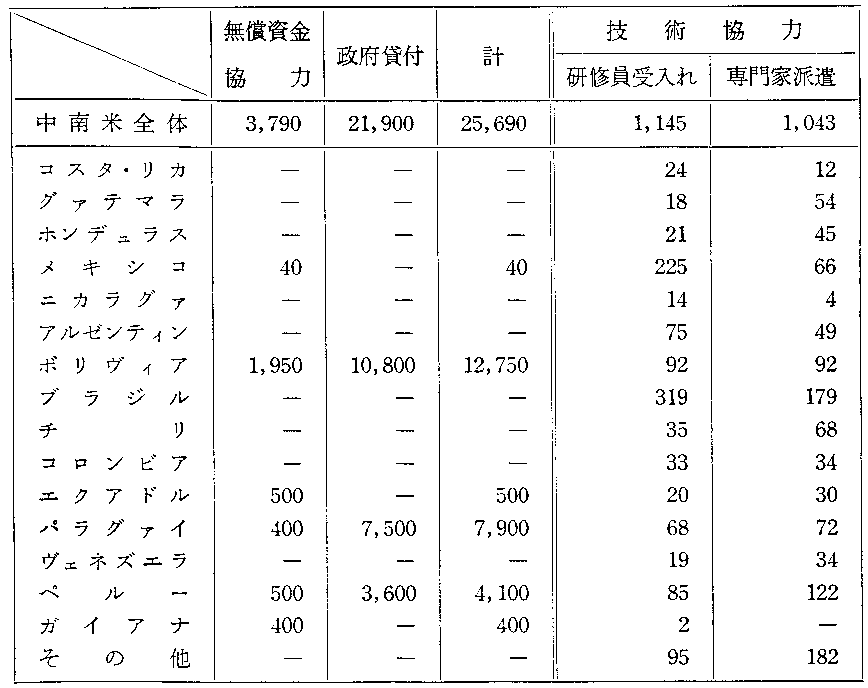
(約束額ベース) (DAC実績ベース)