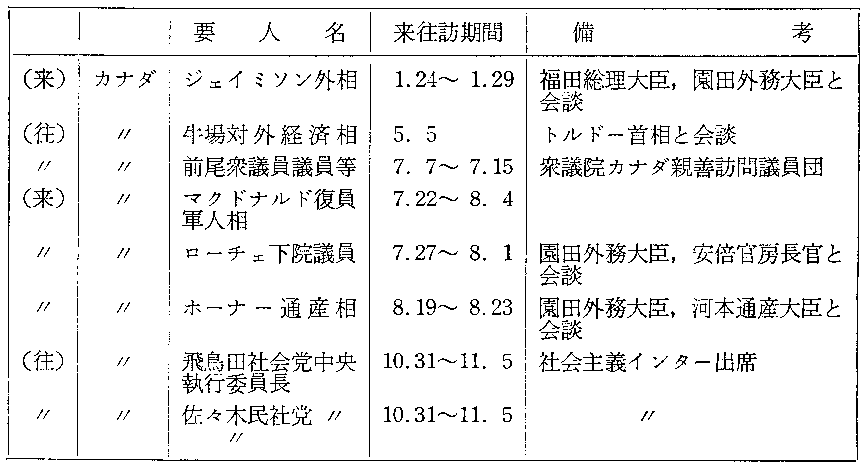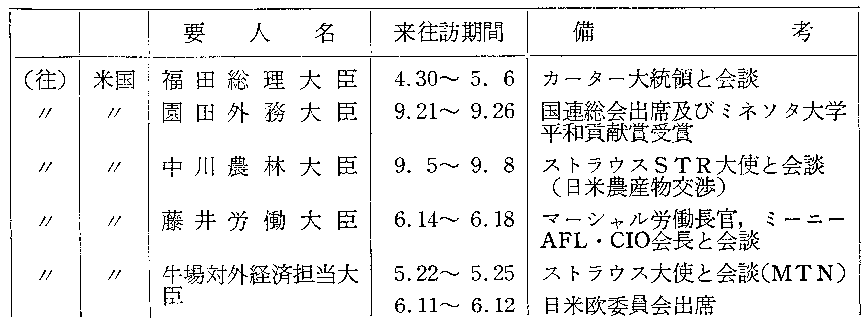
-北米地域-
第3節 北米地域
(イ) 内 政
(a) 1978年の米国内政における最大の行事は11月7日投票が行われた中間選挙であつた。その結果,共和党が若干勢力を伸ばしたものの,民主党の圧倒的優位は変わらず,上院においては共和党の3議席増で,新勢力分野は民主党59,共和党41,下院においては共和党の11議席増で,新勢力分野は民主党277,共和党158となつた。政党間の勢力分野の変動こそ小さかつたが,上院で20名,下院で77名の新議員が当選し,前回選挙に引き続き大幅な議員の交代が生じた結果,上下両院とも過半数が74年以降登場の若手議員によつて占められることとなつた。他方,同時に行われた地方選挙の結果,共和党知事が12名から18名へ増え,また,州議会においても共和党がかなり勢力を伸ばしたことが注目された。
現在の米国民の最大の関心事は,インフレの抑制,減税,政府支出の削減など国民生活に密接に関係する経済問題であるといわれる。今回選挙も主としてそれらの問題をめぐつて戦われたが,それが民主,共和両党の立場を明確に分ける争点とはならず,選挙戦は低調で,投票率も近年では最低の35パーセント強にとどまつたとみられている。そのような選挙を通じてみられた特徴の一つは,カルフォルニア,ミシガン,イリノイ,テキサス,マサチューセッツなど多くの州で減税,政府支出削減関係の住民投票案件が支持され,また,上院における民主党リベラル派の勢力が若干後退するなど,ここ数年来の米国社会の保守化の傾向が今回選挙にも反映されたことである。
(b) 第2年目に入つたカーター政権は,初年度に掲げた広範な分野における諸公約の中から重点事項を絞り,また優先順位を明らかにして逐次実現を図つていくとの現実的姿勢をとるとともに,初年度から問題とされてきた議会との関係の改善に努力した。
その結果議会との関係は次第に改善され,78年4月,新パナマ運河条約の批准承認という外交面での大きな成果を挙げたのを皮切りに,内政面においても,公務員制度の改革,エネルギー法の成立をはじめとして多くの実績を残した。公務員制度改革は,上級管理職の自動昇給廃止などを内容とする上級管理職制度の導入と,連邦人事委員会の連邦人事管理局と公務員資格保護委員会への分割・改組を主な柱とする画期的なものである。
(c) カーター大統領は,79年1月23日議会において年頭一般教書を発表し,78年に続いて「米国の状態は健全である」と報告するとともに,施政方針として,健全な経済,効率的行政,信頼できる政治及び安定した平和の追求を内容とする「新しい基盤作り」を提唱した。同教書は,政権担当2年間の実績を踏まえて全体的に着実な調子で貫かれており,当面の優先事項としてインフレ対策と行政改革に取組むことを明らかにしている。
(d) カーター大統領に対する世論の支持については,誠実・勤勉といつた人格評価面では依然として極めて高いが,全体的支持率は78年においても下降線をたどつた。9月キャンプ・デーヴィッドにおける中東和平会談の成功後に56パーセントに上昇した支持率も,年末には43パーセント(いずれもギャラップ調査)へ低下した。この背景には経済情勢に対する国民の不満があり,この点からも経済問題がカーター政権にとつての最大の課題とされている。
(ロ) 外 交
(a) カーター政権は,78年においても引き続き軍事的安全保障増進,同盟国との紐帯強化,南北問題解決,東西関係改善,地域紛争解決の援助,核拡散や武器移転のもたらす脅威への対処,人権尊重などを外交の基本目標に掲げ,77年から持越された問題の解決を図ることを中心に,積極的な外交努力を行つた。
そのなかでも,パナマ新運河条約や対中東武器供与及び対トルコ武器禁輸解除で議会の承認確保に成功したのをはじめ,中東和平,米中国交正常化など外交の諸分野で着実な成果を挙げたことが注目される。
また,大統領の2度にわたる歴訪(77年12月29日から78年1月6日までポーランド,イラン,インド,サウディ・アラビア,エジプト,仏,ベルギーを,78年3月28日から4月3日までヴェネズエラ,ブラジル,ナイジェリア,リベリアを訪問)やキャンプ・デーヴィッドにおける米,エジプト,イスラエルの3国首脳会談開催などは,上記の外交目標実現に対する大統領自身の意欲を内外に示したものと言えよう。
(b) ソ連との関係では,78年前半には,ソ連のアフリカでの行動や反体制活動家に対する裁判などをめぐつて再び摩擦がみられ,カーター大統領のアナポリスにおける対ソ強硬演説(6月)を経て,米政府による政府高官の訪ソ延期措置などがとられるに至つたが,その後ソ連側が対アフリカ政策や人権あるいはユダヤ人移民問題などで一定の抑制を見せたことから,夏を境に一応の落ちつきを取りもどした。また,この間にも米側は,第2次戦略兵器制限交渉(SALT・II)を始めとする軍縮諸交渉を米ソ間の他の案件とは連携させないとの方針で推進し,全体として米ソ関係の基調は維持された。なお,SALT・IIについては,12月の米ソ外相会談(ジュネーヴ)で主要問題につき基本的合意に達し,両国の首脳会談開催についても合意に達したと発表されたが,最終的妥結には至らなかつた。
(c) 同盟国との協力拡大はカーター政権の主要外交目標の一つであり,78年においてもNATO首脳会議(5月,ワシントン)などを通じ,主要同盟国との協調努力がなされた。特に軍事面では,NATO首脳会議で他の加盟国とともに実質年3%の国防費増加を約束したほか(この約束は79年1月発表の国防予算に反映された),75年以来の対トルコ武器禁輸を解除するなど,NATO強化のための努力がなされた。
(d) アジアについては,米国は,アジア・太平洋国家としてアジアにとどまるとの基本的立場をとつているが,78年にはモンデール副大統領のアジア太平洋諸国訪問(フィリピン,タイ,インドネシア,豪州,ニュー・ジーランド)やブレジンスキー大統領補佐官の北東アジア訪問(日本,中国,韓国),ワシントンでの米・ASEAN閣僚協議などを通じて引き続きその立場を強調した。この点で79年1月発表された国防報告は,前回(78年2月発表)の報告がNATO重視-いわゆるアジア離れという印象を一般に与えたのに比し,アジアでの米軍の軍事態勢問題に多くを費やし,アジアにおける米軍の重要性を示したものとして注目される。
米中関係については,両国は12月15日(米国時間)に,79年1月1日から外交関係を樹立すると発表した。両国関係は,78年に入つて相次く要人訪中(ブレジンスキー大統領補佐官,シュレジンジャー・エネルギー長官,バーグランド農務長官ら)や貿易,科学技術交流の活発化など飛躍的拡大をとげ,外交関係樹立が実現した。79年1月にはトウ副総理の訪米も実現した。
在韓米地上軍の撤退については,77年の第10回米韓安保協議会で大筋が決つていたが,米国議会での補完措置法案審議遅延のため(8月に議会を通過),一部手直しの上,結局78年末までに3,400人の地上軍が撤収された。
(e) 中東和平は,米国外交の最重要課題の1つであるが,カーター大統領は,9月にサダト・エジプト大統領とベギン・イスラエル首相をキャンプ・デーヴィッドに招致し,膠着状態にあつたエジプト・イスラエル間の交渉に打開の目途をつけ,79年3月には自ら中東に赴き,これら両国の平和条約締結を導いた。
(f) カーター政権は,また,OPEC諸国を始め中南米やアフリカなどの新たに影響力を持つようになつた国々や発展途上国との協力拡大を重視しているが,カーター大統領が2回にわたる歴訪で中南米やアフリカ,中東,アジア各地を訪問したことは,同地域の国々の国際的役割に関する米国の認識が増大していることを示すものとして受取られた。
なおカーター政権がその発足時より道義的立場からも解決に努力してきた南部アフリカ問題については,ローデシア,ナミビアいずれについても進展がなかつた。
(ハ) 経済情勢
(a) 米国経済の現状
(i) 78年全般の概要
米国経済は景気回復4年目の78年にもかなりの勢いの拡大を続け,実質GNP成長率は4.4%となつた。これに伴い失業率も77年12月の6.4%から78年12月の5.9%へとかなりの改善をみせたが,反面,インフレは悪化し,78年12月の消費者物価上昇率(前年同月比)は9.0%にも上つた。これは,食料価格の高騰,ドル安による輸入品価格の高騰,社会保障税などの引上げなどの各種の物価圧力が重なつたのが主因であるが,より基本的に重要なものとして生産性の伸び悩みによる労働コストの高騰があげられている。即ち,生産性の伸び悩みと賃金上昇率の高まりという両要因による労働コストの高騰がインフレ圧力をさらに強めたといわれている。
(ii) 四半期別動向
78年第1四半期の米国経済は厳冬並びに石炭ストの影響を受け,個人消費支出の落ち込み,住宅投資の減退,経常海外余剰の減少及び政府支出の不足などから,実質成長率は1.9%(年率)という低率の伸びに留つた。
しかし,第2四半期には,かかる落ち込みからの反動もあつて,年率8.3%という急成長を示し,自動車を中心とする耐久財消費支出,民間設備投資,州地方政府支出,輸出,在庫投資などが目立つた増大を記録した。
その後,第3四半期には個人消費,設備投資などをはじめとしてかなりの伸率鈍化を記録し,年率3.5%の実質成長率となつたが,第4四半期には再び自動車など耐久財に対する個人消費支出の大幅拡大,設備投資の拡大,などから年率5.6%という高率の成長を実現した。
以上,年間を通じてみると,78年全体では個人消費支出が堅調な伸びを見せたほか,従来出遅れていた構築物に対する投資の伸びがようやく高まつて設備投資(実質)が実質GNP成長率の2倍近い伸び(8.4%)を示したのが目立つている。
(iii) 79年年初の動向
79年に入つてからの米国経済は1,2月ともスローダウンを示しているところ,それは住宅建築,小売販売などの個人部門が中心となつており,企業部門の受注,在庫投資などは強さを維持している。一方物価情勢は一段と悪化しており,また,国際収支は改善基調を続けている。
(b) 78年にみられた米国政府の主な経済政策
78年の当初,米国政府はインフレ問題の重要性を認識しながらも,持続的成長の確保による失業削減に引き続き重点をおき,250億ドルにのぼる減税などを提案した。しかし,その後インフレ情勢の悪化が明らかになるとともに,4月のインフレ対策推進のための大統領声明の発表,5月の減税規模削減提案などを経て漸次インフレ重視の姿勢を強めて行き,10月,11月にはそれぞれ新たなインフレ対策及びドル防衛策を発表し,インフレ防止最優先への転換が完全に行われることとなつた。このインフレ対策は,緊縮財政,金融引締め,インフレ助長的政府規制の削減,賃金・物価に関する自主協力ガイドラインの設定などより構成されている。
(c) 79年の米国経済見通し
79年1月に発表された予算教書などにみられる米行政府による79年の米国経済の見通しは概ね次のとおりである。
(i) 78年来実施されているインフレ対策の効果により,79年の米国経済は漸次スローダウンしてゆくものと予想されている。したがつて失業率は微増しようが,物価は安定的なスローダウンの中で鎮静化の方向に向かうものと見込まれている。
(ii) また国際収支については,主要貿易相手国との成長率格差の逆転,ドル下落の効果の発現などにより,かなりの改善が見込まれるとされている。
(イ) 内 政
78年は選挙の多かつた年であつた。10月に15議席をめぐる連邦下院補欠選挙が行われ,与党自由党がケベック州で2議席しか確保できなかつたのに対し,第1野党の進歩保守党は10議席獲得した。78年には,4州の州議会選挙が行われたところ,全般的に自由党の退潮と進歩保守党の躍進が目立つた。連邦総選挙については,77年秋以降選挙ムードの高まりが見られ,下院議員の任期が満4年目を迎えた78年中に実施されるのではないかとの予測もあつたが,結局79年5月に行われることとなつた。つぎに,76年のケベック分離派政権の出現により緊急性を増した国家統合問題は,経済問題と並びカナダが直面する内政上の重要課題であるが,トルドー首相は国家統合問題の重要な一環として78年6月憲法改正に関する政府提案を公表し,引き続き145条に及ぶ憲法改正法案を連邦議会に提出した。
ケベック問題に関しては,レベック ケベック州首相は,民主的手続を経て独立を達成すべく,独立に関する州民投票を実施する意向を明らかにしてきており,州民投票の質問内容が注目されてきたが,78年10月同首相は「主権連合」構想について州議会で正式に発表した。
(ロ) 外 交
(a) 米国との関係
カナダは政治,経済,安全保障,文化など多くの分野において隣国米国と緊密な関係にある。78年カナダではこの圧倒的な対米関係の重要性を再認識する動きがみられた。米加両国は,78年は,1月にモンデール副大統領が訪加しトルドー首相と会談したほか,11月にはヴァンス国務長官が訪加するなど緊密な関係の維持強化に努めた。
(b) ECとの関係
ECとの関係では,78年9月にオタワでハイレベル協議が行われ,航空,通信などの分野における協力関係について協議が行われた。
(c) 中国との関係
中国との関係では,77年秋の黄華外交部長の訪加に対する答礼として78年1月ジェイミソン外相が訪中し,6月には中国議員団が訪加した。
(d) ソ連との関係
ソ連との関係では,78年1月ソ連原子力衛星のカナダ領域墜落事故,2月にはスパイ容疑による在カナダ・ソ連外交官の大量の国外追放事件をめぐつて問題が生じた。
(e) そ の 他
このほか,カナダは78年安保理西側5ヵ国の一員としてナミビア問題の解決のため精力的な活動を行つた。
(ハ) 経済情勢
(a) 78年のカナダ経済を概観すると,引き続き,(あ)潜在成長力を下回る低成長,(い)8%を超える高失業率,(う)8~9%の高インフレ,(え)経常収支の赤字という種々の課題を抱えたまま推移した。
(i) 78年の実質GNP成長率は3.4%となり,当初見通しの5.0%をかなり下回ることとなつた。成長率が予想を下回つた主因は個人消費支出の伸びが予想を下回つたことなどにあるといわれている。
(ii) 雇用情勢については,かなりの雇用増があつたにもかかわらず,他方,労働力人口も大きく伸びたため,失業率は78年1月の8.3%から78年12月の8.1%へと若干低下するにとどまつた(ただし79年2月には7.9%へと低下した)。
(iii) 消費者物価上昇率は,食料品価格の高騰及びカナダドル下落に伴う輸入品価格の高騰などにより,78年通年で9%という高率を記録した。なお,75年以来とられてきた賃金・物価統制策が78年4月から12月にかけて段階的に廃止されたこととの関連で賃金上昇率の動向が注目されたところ,同上昇率は,右統制の効果及び高失業率の影響などにより,75年の15%から78年には6%台にまで低下したが,78年第2四半期を底として再び上昇傾向を示した。
(iv) 国際収支の面では、貿易収支はカナダドル下落の効果などから黒字を拡大させたものの貿易外収支が利子配当収支及び旅行収支などを中心として大幅赤字を続けたため,経常収支は依然として改善をみずに推移した。(77年は43億ドルの赤字。78年は53億ドルの赤字)。
(b) 78年7月のボン・サミットにおいて「インフレを抑制し軽減する必要性と両立する限度内で雇用の拡大及び5%までの生産の増大をはかる」との意図を確認したトルドー政権は,同年8月以降,売上税減税,研究開発促進及び投資促進税制の拡充などの措置を講じてきている。これら政策の早期の奏功が期待されているが,78年には賃金上昇率の鈍化及びカナダドル下落の効果によりカナダの企業の競争力は回復し始め,その結果,輸出関連の製造業を中心に設備稼動率の上昇,企業収益の改善,雇用の増大が目立つようになつた。
日米両国の友好協力関係は,国際社会が政治,経済,安全保障の諸分野で複雑化するにつれ,ますますその重要性を増しつつある。
このような中で日米両国は,78年においても先進国首脳会議や日米首脳会談(5月3日)を始め政府,民間両レベルで活発な接触,交流を図り,相互理解と諸問題解決のための協力に努め,両国の関係は貿易経済関係上の問題にもかかわらず良好であつた。
(a) 日米両政府は,77年秋以来,2国間の貿易不均衡問題の解決のみならず保護主義の台頭を防ぎ,世界経済全体の安定的拡大を図るとのグローバルな観点から,一連の協議を行い,その結果,78年1月,牛場・ストラウス共同声明の発表をもつて一応の結着をみた。
(b) 同共同声明に盛られた諸事項については,わが国は各種の政策努力を通じて迅速に実行に移した。即ち,内需拡大のため大型予算,公定歩合の引下げ,関税の前倒し引下げ,輸入金融の拡充,輸入促進ミッションの派遣,輸出の自粛要請などである。
(c) 5月初め福田総理大臣(当時)とカーター大統領との間で行われた日米首脳会談では,わが方は,世界経済の安定と拡大に寄与するため,引き続き内需拡大,経常収支黒字幅の縮減に努める旨改めて確認し,米側は,インフレ対策,効果的なエネルギー政策の実現,輸出促進策の強化に努め,ドル価値の安定に寄与するとの考えを表明した。
(d) 一方,日米貿易の動向は,わが国の諸努力にもかかわらず,円レートの断続的上昇によるいわゆるJカーブ効果の連続的発生,米国のインフレが輸出価格の上昇を容易にしたなどの事情から,78年第1及び第2四半期とも月平均10億ドル以上のわが方の黒字を示した。
(e) このような不均衡の継続を背景に,特に米議会の対日批判が高まり,その一端として7月にはヴァニック議員ほかの下院議員が大統領に対し,通商法に基づき輸入課徴金などの発動を真剣に考慮すべき旨述べた書簡を発出した。
(f) 他方,秋に入つてわが国の対外不均衡改善の兆候が現れ始め,その一環として対米貿易黒字幅も縮小傾向を見せ始めた。また,政府は,9月初めに公共投資を中心とする総合経済対策を発表するなど,経常収支黒字幅削減の努力を続けた。
(g) しかし,日米の貿易収支不均衡が続いていることを背景に米国内の対日批判には根強いものがあり,日米両政府は引き続き緊密な協議を通じて,相互の経済政策の理解に努め,経済問題をめぐつて対立関係に陥らないよう相互の努力を続けた(例えば10月初めのワシントンにおける日米高級事務レベル協議,10月末のフロリダ州オルランドにおける牛場・ストラウス会談など)。
(h) 更に,日米両国政府は具体的案件についても鋭意解決に努め,12月には牛肉,オレンジ輸入拡大などをめぐるMTN日米農産物交渉の実質的妥結をみたほか,なめし皮の輸入拡大問題についても長期間にわたる交渉を経て,79年2月に決着をみるに至つた。また,日米通商円滑化委員会(TFC)に提出された案件のうち,多くの部分について進展をみた。
(i) 日米貿易動向は,79年初めにかけて不均衡改善の傾向を強めているものの,78年全体では,わが国の116億ドル(米側統計)の黒字となつたために,米側,特に米議会の対日「いらだち」が根強く残つた。また,同不均衡を背景に,日本の市場が閉鎖的であるとのイメージが米側に強く,そのため,MTNの政府調達問題(特に電々公社問題)を始めいくつかの案件が,市場閉鎖性のシンボルとしてみなされる傾向が強まつた。
(j) かかる事情を背景に,わが国は,79年2月に,前年12月に成立した大平内閣の経済運営の基本方針を説明し,相互理解を深めるため安川政府代表を派米するなど,引き続き米国との緊密な協議を続け,また,当面の個別問題についても,早急な解決を図るため努力を続けた。
78年の日米漁業関係は,77年11月に発効を見た「アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の下で,77年に引き続き順調に推移した。
79年のわが国に対する漁獲割当量は,米国との一連の協議において従来の実績確保のため積極的な努力を払つた結果,当初の割当総量において78年の約94%(約111万トン)が確保されるとともに,79年中における再配分の可能性につき米側により十分な配慮が与えられることとなつた。
(a) 緊密な協議・協力
日米安保条約は,わが国のみならず,極東の平和と安全の維持に大きく寄与してきている。78年においても,日米安保条約の円滑かつ効果的な運用を図るため,日米間において引き続き緊密な協議及び協力が行われた。
5月に福田総理大臣(当時)が訪米してカーター大統領と会談した際,福田総理大臣より,アジア・太平洋地域の平和と安定にとつての米国のプレゼンスの重要性を指摘したところ,カーター大統領は,日米安保条約をはじめとするアジア・太平洋地域における安全保障上の約束を守り,そのため,必要な米軍のプレゼンスを維持する決意を表明した。
11月には,ブラウン国防長官が防衛庁長官との協議のため来日し,大平総理大臣及び園田外務大臣とも会談を行つたが,双方とも現在日米安保関係が良好であることを認めた。
また,11月末に開催された第17回安全保障協議委員会で,「日米防衛協力のための指針」が了承された。同指針は,緊急時における日米防衛協力の基本的枠組みを示すものであり,現在,自衛隊と米軍との間で同指針に基づき共同防衛計画を中心とする研究が進められているが,かかる防衛協力の進展は,日米安保条約の抑止効果を高め,わが国の安全及び極東の平和と安全を一層効果的に維持することに資するものと思われる。
(b) 地位協定の円滑な運用
政府は,日米安保条約・地位協定の目的達成と施設・区域周辺地域の経済的・社会的発展との調和を図るため在日米軍施設・区域の整理統合を推進してきたが,78年においても施設・区域の全面返還と一部返還が数多く実現した。
また,79年度の在日米軍関連予算は,在日米軍のより円滑な駐留に資するよう前年度に引き続き増額された。
78年においては,77年の東海村再処理交渉のように,原子力問題に関して日米関係を緊張させるような問題は存在しなかつた。
しかし,原子力平和利用に対しては,核拡散防止のために厳しい規制を加えるべきだとする米国と,核拡散防止の重要性は認めつつも不必要に厳しい規制は課すべきではないとするわが国及び西欧諸国との間の見解の相異は依然として存在しており,これを調整するための各種協議は,78年中も続行された。
なお,78年3月に発効した米国の新核拡散防止法は,米国産核物質などの受領国と米国との間の原子力協定の改正を要求するものであり,日米原子力協定の改正に関する協議も79年2月に東京で行われた(原子力平和利用の項参照)。
新エネルギー研究開発を骨子とする日米科学技術協力の構想は,78年5月3日ワシントンでの日米首脳会談においてわが方から提案し,米側もこれに全面的な賛意を表明した結果,早急に事務レベルで具体化を図ることとなつた。9月及び11月の事務レベル協議の結果,本件協力の大綱が合意され,対象分野としては,核融合,石炭転換,光合成,地熱エネルギー及び高エネルギー物理の各分野をとりあげることとし,さしあたり,核融合及び石炭転換の両優先分野から6つのプロジェクトを実施することとなつた。
なお本件協力の枠組を定める基本協定を締結することも合意され,両国の事務レベルでそのための作業が進められた。
本件協力の目的は,21世紀を展望しつつ日米両国が協力してポスト・オイル時代の課題である新エネルギーの研究開発を行うことにあるが,この協力が十分な成果をあげ新エネルギー源の開発は勿論のこと両国間の連携関係の一層の強化にも寄与することが強く期待される。
わが国は,日米間に存する路線権,以遠権などの面における航空権益の不均衡を是正するため,76年10月以来米国政府との間で日米航空交渉を行つてきており,78年3月には第6回協議を行つた。これまでの数次にわたる協議において日米双方の立場はほぼ明確になつてきているが,78年8月に米国政府がチャーター航空業務の自由化,低運賃の導入を中心とした自由競争の拡大を目指す新国際航空政策を発表するなど双方になお相当の隔りがあるため,更に折衝を続けることとなつた。わが国としては,最近の世界の民間航空情勢におけるチャーター航空業務の自由化,低運賃導入などの動向をも十分勘案しつつ,日米協調の見地から双方に満足すべき解決が得られるよう鋭意努力を続けていく考えである。
<要人往来>
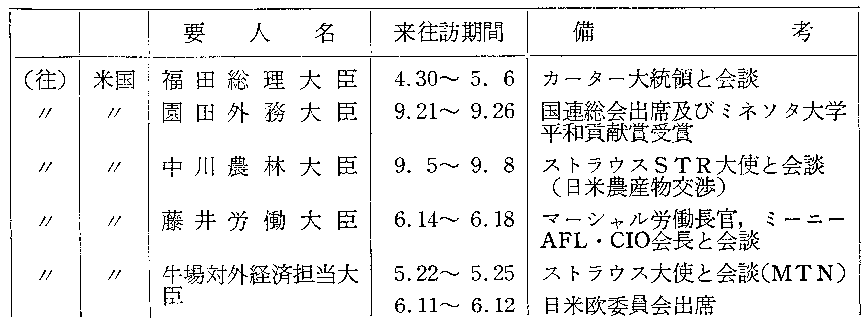
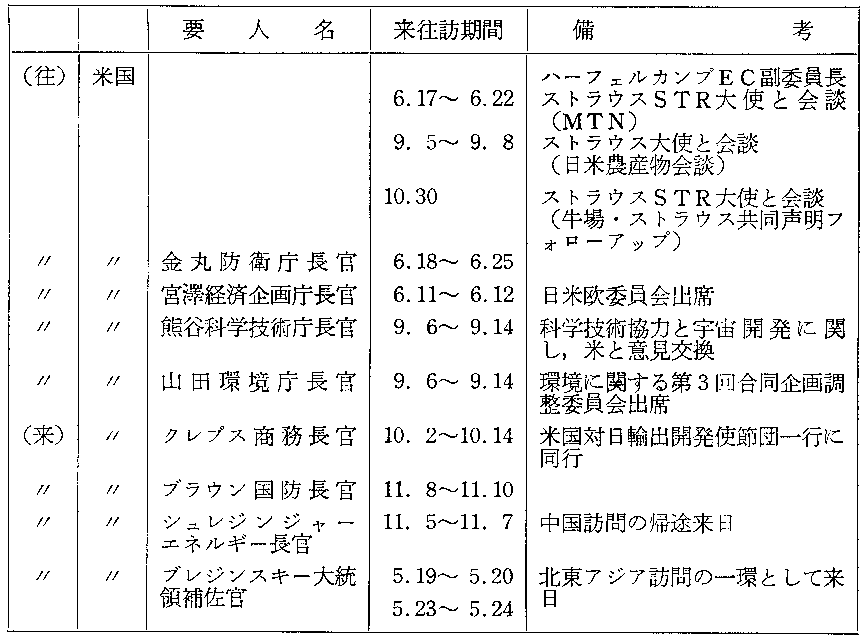
76年のトルドー首相の来日,77年の日系移民百年祭によつて高まりをみせた日加関係であるが,78年は政治,経済,科学技術などの分野で一層幅広く深みのある関係とする上で意義深い年であつた。政治面では,78年1月ジェイミソン外相,8月ホーナー通産相が訪日したばかりでなく79年1月にはクラーク進歩保守党々首が来日してわが国政府首脳と意見交換を行つた。78年は,わが国よりは牛場対外経済担当大臣が訪加したほか,日加間の国会議員交流として前尾衆議院議員一行が訪加した。経済面では,76年にわが国よりの経済使節団が訪加したことを契機に設立の気運が高まつた民間の日加経済人会議の第1回会合が78年5月東京で開催された。科学技術の面では,最近懸案となっていた日加原子力協力協定の改訂交渉が78年1月妥結した。
また,文化交流の分野でも活発な活動がみられた。
(a) 78年は,77年6月にヴァンクーヴァーで開催された第1回日加経済協力合同委員会での対話を踏まえ,種々の分野で両国間の経済協力関係に進展が見られた。
科学技術の分野においては,6月に第3回目の日加科学技術協議が開催され,宇宙・通信,海洋開発など広範な分野で具体的協力案件につき話し合いが行われた。
漁業分野においては,4月に日加漁業協定が締結され,政府間協力の枠組が確立し,この下でカナダ200海里水域内でのわが国漁業の安定的操業が行われることとなつた。
農林業分野では,7月に日加なたね会議が催され,なたねの需給動向について有益な意見交換が行われたほか,7月には,政府関係者,林業関係者,住宅産業関係者からなる林業物スタディグループがブリティッシュ・コロンビア州を訪問し加側関係者との間で有益な意見交換を行つた。
(b) 他方,かかる政府レベルでの対話に加え,民間レベルでの交流において,同年5月第1回日加経済人会議がわが国で開催されるなど注目すべき進展があつた。
わが国の原子力発電容量は,既に総発電容量の1割に達しているが,この原子力発電に必要な天然ウランのかなり多くは,カナダから輸入している。
しかるにカナダは,日加原子力協定の改正交渉がカナダの望むとおり進捗していないとの理由で,77年1月より加産ウランの対日供給停止を(対EC,対スイスなどと同時に)行つた。
しかしこの供給停止措置は,78年1月東京で開かれた第3次交渉がわが国外交当局の最大限の努力により妥結したことにより,解除された。
なお,この交渉により作成された日加原子力協定改正議定書は,78年8月,カナダのホーナー通産大臣来日の際に,園田外務大臣との間で署名された。
<要人往来>