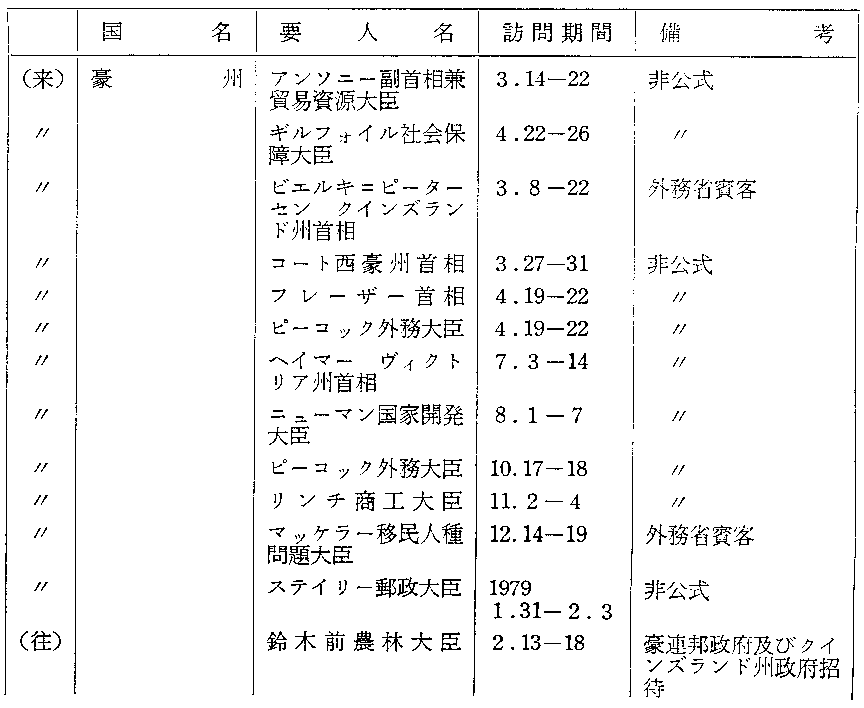
-大洋州地域-
第2節 大洋州地域
(イ) 内 政
77年12月の総選挙での大勝により,フレーザー首相の地位は一層固まり,同首相の指導力は各方面において強力に発揮された。また,ニュー・サウス・ウェールズ州(労働党政権)で州議会選挙が行われ,与党が勝利を収めた。8月,200海里水域設定のため漁業法が改正されたが,各州との権限調整の準備遅延などのため同水域の実施は79年に持ち越された。
(ロ) 外 交
78年においても,豪州はわが国との関係増進,対米協調,ASEAN諸国との関係強化及び南太平洋諸国に対する施策に努めるとともに対中国関係重視の姿勢が顕著に示された。また,豪州は,自国が農,鉱産品など第一次産品の主要輸出国であるとの立場に基づき,国際経済諸問題の解決のために積極的な外交を展開し,特にECなどの保護貿易傾向に対する警告を強く唱えた。
ASEAN諸国との関係では,インドネシアと東チモール問題の解決など2国間関係の強化に努めるとともに,第4回豪・ASEANフォーラム,投資セミナー及び見本市の開催などを主催して対ASEAN関係の促進を図つた。
南太平洋地域では経済協力を中心にパプア・ニューギニア重視策が維持され,同国と永年の懸案であつたトレス海峡の境界画定問題を解決した。
また,中国との関係では主要閣僚などの相互訪問及び貿易の拡大など対中国協調姿勢が顕著に示された。
(ハ) 経済情勢
(a) 概 説
豪州経済は依然として停滞局面を脱しきれず,高インフレ,失業率の増大,国際収支の赤字に悩まされてきているが,豪州政府は,豪州経済の発展を図るためにはまずインフレ抑制を通ずる経済の基盤強化が急務であるとの方針により,財政支出及び賃金の抑制などの緊縮政策を実施してきている。そのため,78年の9月期の消費者物価上昇率が対前年比で7.9%に下降した。他方,国際経済の停滞に伴う輸出の不振を主因として国際収支は悪化し,また住宅,民間設備投資などの内需項目は停滞傾向が続いたため,経済成長率(実質GDP)は2.9%にとどまつた。雇用情勢も,かかる経済情勢を反映し依然として高水準の失業率(78年10月5.7%)で推移した。
(b) 主要経済事項
政府は,国内産業の保護と雇用機会の確保のために製造業に対する保護政策を継続するとともに,6月には国内経済の浮揚を図るため外資導入に関するガイドラインの緩和を図つた。
ウラン開発に関しては,土地の権利をめぐる原住民との間の交渉が12月に決着をみ,北部特別地域レインジャー鉱の開発は79年乾期からの着工が可能となつた。
10月には,鉱物資源(鉄鉱石,石炭,ボーキサイト及びアルミナ)の民間輸出契約に関する連邦政府の承認手続きの強化を図る政策を発表し,資源輸出に係る連邦政府の権限強化を図る指針を示した。
なお,77/78年度の豪貿易収支は,輸出120億豪ドル,輸入112億豪ドルと黒字を示し,資本収支でも黒字となつたが,貿易外収支で赤字となつたため,総合収支では5.5億豪ドルの赤字となつた。
(イ) 内 政
任期満了に伴う総選挙が11月25日に行われた結果,与党である国民党が総議席数92のうち50議席を確保し,再び政権を担当することとなつたが,敗れた労働党は前回選挙に比し10の議席数を伸ばし善戦した。
なお,78年4月1日より200海里経済水域が施行された。
(ロ) 外 交
英国のEC加盟後狭隘化しつつある西欧市場との結びつきを再構築するための努力が払われる一方,米国,豪州及びわが国との関係強化が図られ,また南太平洋島嶼国との関係強化が引き続き重視された。
なお,78年11月に発表された国防白書には,向う10年間はNZに対する直接的脅威は予想されないとし,南太平洋地域など重点地域の平和と安全の確保を主眼とする政策を打ちだしている。
(ハ) 経済情勢
(a) 概 説
NZ政府は,78年11月の総選挙対策も考慮し,従来の引締め策を緩和する経済政策を実施したが,引締め策の影響が尾を引き,失業者も5万2千人(12月)と戦後最高の水準に達した。消費者物価上昇率は鈍化したが年間上昇率は10.1%と依然高い率を示した。
(b) 主要経済事項
引締め緩和策として個人所得税の大幅減税,農家所得対策などの内需促進を意図した赤字予算の編成,及び金融緩和措置の導入を行うとともに,直接的な輸入制限措置である輸入担保金制度の廃止及び輸入ライセンス枠の3年ぶりの拡大を行つた。
78年の貿易収支は,輸出36億7千万NZドル,輸入30億6千5百万NZドルと77年に続き黒字を示したが,貿易外収支が大幅に悪化したため,経常収支で約3億9千万ドルの赤字となつたものの,総合収支では3千2百万ドルの黒字を示した。
(イ) 内 政
78年のPNGの政局は,新指導者倫理要綱法案の国会提出問題(2月)から閣僚交代問題(11月)を契機に人民進歩党が連立内閣から脱退して野党にまわり,代わりに野党であつた連合党がソマレ首相の率いるパング党と新たに連立内閣を成立させるなど大きな変動があつた。
また,PNG独立以来の重要課題であつた地方自治政府の樹立が78年に完了した。
(ロ) 外 交
PNGは,普遍主義を外交政策の基本理念として引き続き堅持する一方,78年は,トレス海峡条約の締結など対豪協調の維持,わが国,NZなどとの協力関係の増進及び南太平洋地域協力の推進を行つた。また,西イリアン問題との関連で対インドネシア外交を重視しており,ASEANとの関係も外相会談(8月)に出席するなど関係強化を図つている。
(ハ) 経済情勢
(a) 概 説
78年6月末においては,77年9月期のコーヒー,ココアの国際価格の高騰による収入増の影響で貿易収支は黒字となつた。輸出の増加を背景に,個人消費の活発化及び小売,流通事業拡張のための設備投資,建設業の活動が目立つた。
(b) 主要経済事項
政府は,1月(対豪4%切上げ)に続き4月にキナの対豪ドル2.03%の切上げを行つた。11月の新連立内閣の経済政策は前連立内閣の政策を踏襲し,従来のインフレ抑制,通貨の安定及び堅実なる投資促進などを重点に経済の安定に努める方針を掲げている。
国際収支では,77/78年度で輸出が572百万キナ,輸入475百万キナと貿易収支は97百万キナの黒字を示し,78年9月期の外貨準備高は301百万キナとなつた。
(イ) 78年4月のナウルの総選挙においてドウイヨゴ大統領が再選されたが,燐鉱石関連法案の採択に失敗し辞職した結果,ハリス大統領が就任した。しかし,同大統領も法案の議会通過などに失敗し,辞任したため5月にデロバート元大統領が大統領に就任した。
(ロ) 78年7月7日にソロモン諸島が,また10月1日にトゥヴァルが各々英国より独立した。
(ハ) 78年には南太平洋諸国が次々に200海里水域設定のための準備を進め,ソロモン諸島(1月),パプア・ニューギニア,ギルバート諸島(4月)が200海里水域を実施した。
(ニ) 南太平洋地域機構の動きとして,9月にニウエにおいて第9回南太平洋フォーラム会議が開かれ,南太平洋漁業機関設立問題が話し合われたが,加盟国の範囲などにつき意見が分かれたため当分はフォーラム諸国だけからなる漁業機関の設立が検討されることとなつた。また,10月にはヌメアにおいて第18回南太平洋委員会が開かれ,経済,社会開発問題などにつき協議された。
3月にはアンソニー副首相が訪日したのに続き4月にはフレーザー首相が訪日し,首脳会談において国際経済問題につき意見交換が行われた。
6月に,キャンベラで第5回日豪閣僚委員会が開催され,両国間の貿易,経済関係を中心に意見交換が行われ,豪州における資源加工の振興のため,またエネルギーの研究,開発のためにそれぞれ共同研究グループの設置が合意された。
8月,豪州政府は200海里漁業水域設定のための漁業法の改正を行つたため,わが国は予定される同水域内での操業の確保を計るため,漁業協定締結のための交渉を9月及び12月に行つたが合意を見るに至つてない。
78年には鉄鉱石,原料炭に関する貿易上の問題が生じた。豪州よりわが国の不況を背景とする引取削減につき懸念が表明され,貿易量,価格の安定化が要請されたが,10月には上記2品目に加えアルミナ,ボーキサイトの資源輸出手続を強化する政策を打ちだした。
なお,78年に豪州政府は,対日政策の体制整備,強化を計り,5月には豪日関係特別作業委員会の報告書(マイヤー報告)に基づき,対日関係各省次官会議などの開催を行つてきている。
NZ政府の対日政策である「総合的経済関係」(NZ産農林産品の対日アクセス改善と本邦漁船のNZ沖操業などとを関連付ける政策)は78年にも維持され,4月1日のNZ200海里水域実施に伴い本邦漁船は同水域から撤退することとなつた。6月末の中川農林大臣(当時)の訪NZにより,マルドウーン首相との間で対日アクセス改善に関し合意が成立したため,NZもわが国との漁業交渉に応じ,9月1日に漁業協定が署名され操業も同日より再開された。
日・PNG貿易関係も,PNG独立後順調に推移し,78年は前年比13.6%増となつた。
上下水道,水力発電計画に対する第1次円借款(35億円)の交換公文が8月4日に署名され対PNG援助も技術協力を中心に積極的に行われた。
PNGは4月1日より200海里水域を施行したため,わが国と漁業交渉を行い,5月に79年1月末まで9ヵ月間の漁業暫定取極を結んだが1月以降の操業継続に関し11月に行つた漁業交渉において合意は成されなかつたため,79年2月以降本邦漁船はPNG水域で操業を行つていない。
7月7日,ソロモン諸島の独立に際し,わが国は特派大使を派遣した。200海里水域を施行したソロモン諸島(1月)及びギルバート諸島(4月)と数次にわたり漁業交渉を行い,各々漁業協定を締結し,本邦漁船の操業を確保した。
南太平洋島嶼国は,経済・社会開発を推進してきているため,わが国も応分の協力を行つてきており,78年度には水産無償(対ソロモン5億円,西サモア4億円),かんづめ供与のための無償資金協力(対トンガ2億円,西サモア2億円)及び技術協力を実施した。
<要人往来>
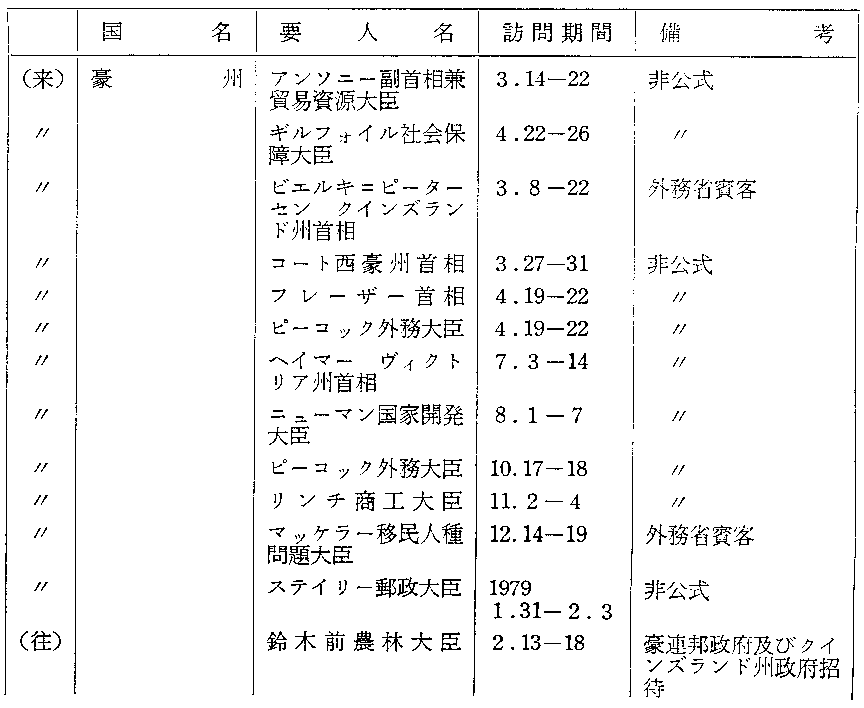
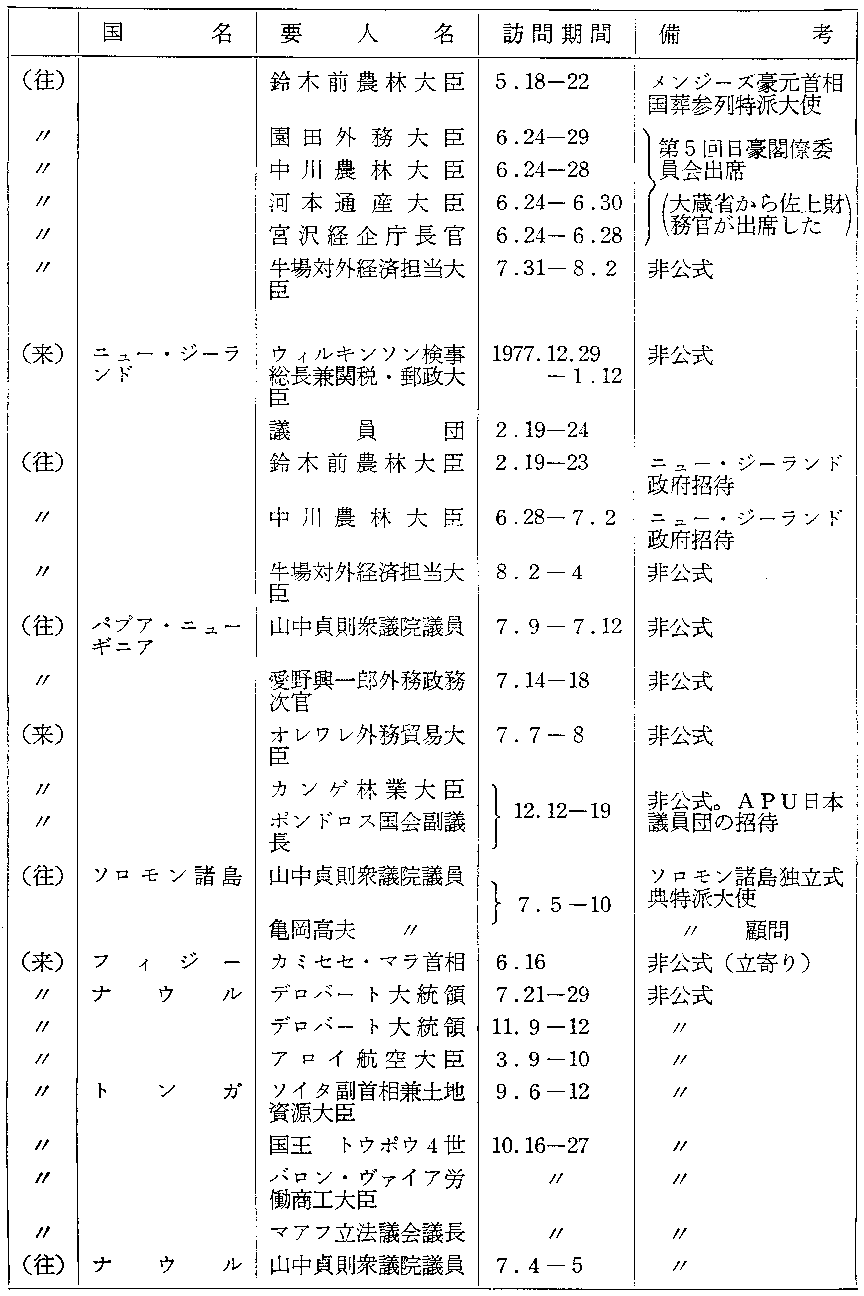
<貿易関係>
(単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率(%))
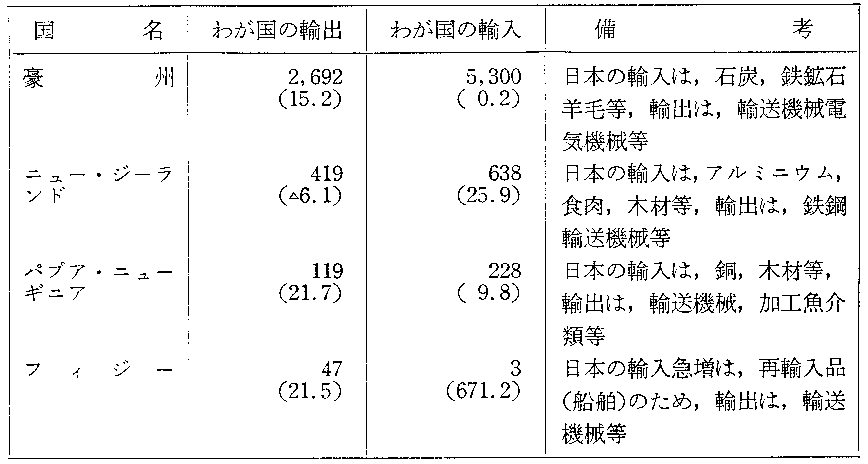
(出所:大蔵省通関統計)
<民間投資>
(単位:百万ドル)
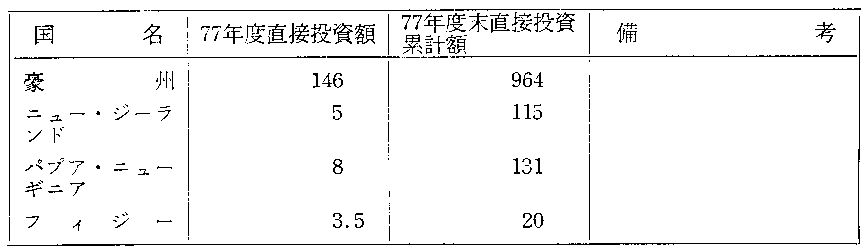
(日銀許可額ベース)
<経済協力(政府開発援助)>
(1978年;単位百万円,人)
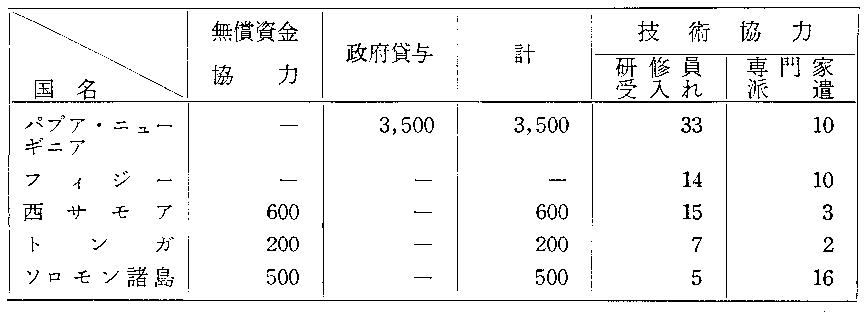
(約束額ベース) (DAC実績ベース)