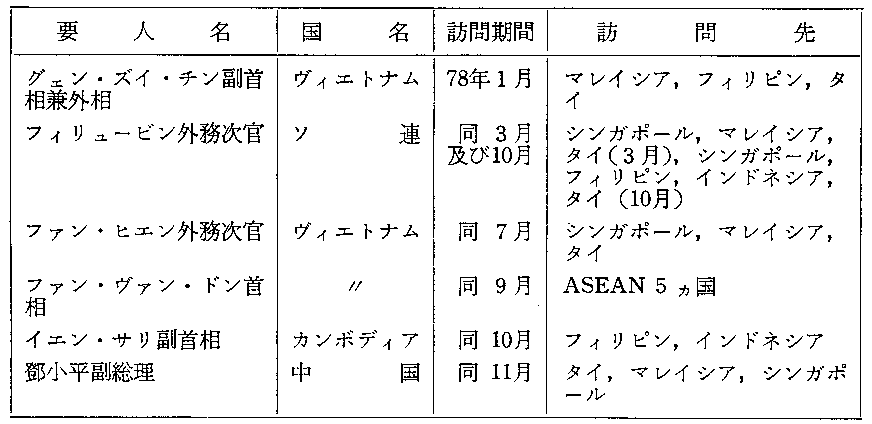
第 2 部
各 説
ASEAN(Association of South East Asian Nations=東南アジア諸国連合)とは,東南アジアに位置するインドネシア,マレイシア,フィリピン,シンガポール及びタイの5ヵ国が地域の平和と発展を図ることを目的として創設した地域協力機構である。
1967年8月に発足したASEANは,76年2月のバリ島での第1回首脳会議以来,加盟国間の連帯を強め機構としての基盤を強化する気運の盛り上りをみせており,域内協力の推進と域外先進諸国との対話強化が進められている。
78年から79年初頭におけるASEANの動きのなかで最も注目すべき点は,東南アジア情勢,特にインドシナ情勢の新たな展開を背景に,加盟国相互間で政治的結束強化の動きがみられたことである。この動きは,特に78年9月及び11月に行われたファン・ヴァン・ドン ヴィエトナム首相,トウ小平中国副総理などのASEAN諸国訪問の際の対応,また79年1月のカンボディア情勢の急変に対するASEAN諸国の共同歩調などに顕著な表われをみせた。
他方,ASEANの経済面における協力については,域内経済協力が着実に進展し,また,日本,米国,ECとの閣僚レベルでの会議開催にみられる通り域外先進諸国との関係強化にも成果をあげ,ASEANの安定的基盤はますます強固なものとなつた。
ASEANは76年には前年のインドシナ情勢の激変を契機として,インドネシアのバリ島でASEAN創立後初の首脳会議を開催するなど政治的結束を強化する動きをみせたが,78年においても再度このような政治面での協力強化を指向する動きをみせた。
すなわち,78年は,越「カ」紛争,中越関係の悪化などのインドシナ情勢の変化を背景に,以下のとおり,中国,ヴィエトナム,カンボディア,ソ連などの社会主義諸国要人のASEAN諸国訪問が活発に行われた年であつたが,ASEAN諸国は,加盟国相互間の緊密な意思疎通を通じ共同歩調をとりつつこれに対処し,これら諸国のいずれにもかたよらぬ姿勢を堅持した。
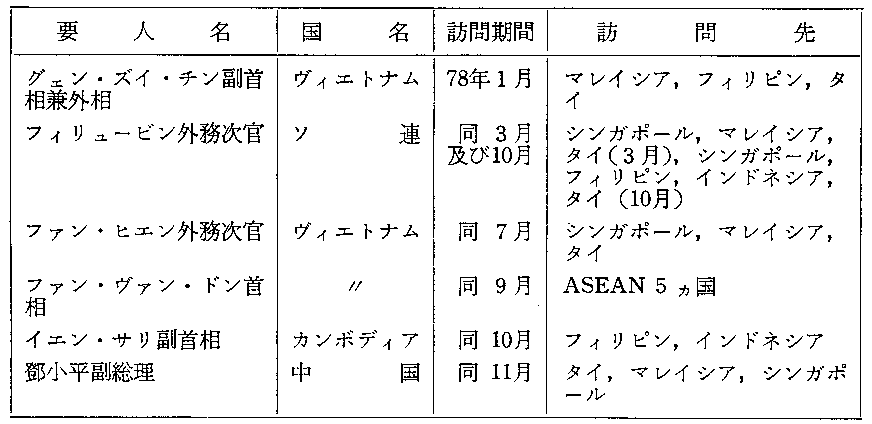
また,後述するとおり,79年1月のカンボディアにおける武力紛争の生起に対しては,ASEAN諸国は,バンコックで特別外相会議を開きASEAN外相声明を発出し,さらに,2月の中・越武力衝突に際しても,ASEANとして共同歩調を取りASEAN常任委員会議長声明を発出するなど,共同して平和のための外交努力を行つた。
またASEAN諸国は,ヴィエトナム難民問題に対しても共通の認識の下にこれに対処した。
ASEANの域内経済協力は,78年においても76年のバリ首脳会議で採択された「ASEAN協和宣言」の行動計画に沿って,引き続き着実な進展が見られた。他方,このような協力の進展に伴い,いくつかの協力案件について加盟国間の意見の対立が伝えられるなど,問題を残す点もあつた。
(a) 産業面での協力
6月,ジャカルタで第6回経済閣僚会議が開かれ,マレイシアの尿素プロジェクトがインドネシアの尿素プロジェクトに次いで第2のASEANプロジェクトとして承認され,また,ASEAN5大工業プロジェクトに関する基本協定案と,インドネシア,マレイシアの尿素プロジェクトに関する補足協定案が原則的に合意された。他方この会議ではシンガポールのディーゼルエンジンプロジェクトをめぐり,インドネシアとシンガポールの対立が表面化した。
さらに同年12月の第7回経済閣僚会議ではタイのソーダ灰プロジェクトが新たにASEANプロジェクトとして承認されるとともに本プロジェクトに関する基本協定及び補足協定がイニシャルされた。
(b) 貿易面での協力
76年2月のバリ首脳会議で合意されたASEAN域内特恵については,77年2月に「ASEAN特恵貿易協定」が署名され,これに基づき,米,原油などの基礎物資,ASEAN工業プロジェクト製品,ASEAN域内貿易拡大のための商品,その他加盟国の関心品目に対して域内特恵が適用されることになつた。具体的な品目については,まず,77年6月の第4回経済閣僚会議で決定された71品目が78年1月1日から域内特恵対象品目として実施されたが,これに加え,6月の第6回経済閣僚会議においては755品目が新たに対象品目として合意され9月1日より実施され,さらに12月の第7回経済閣僚会議で更に500品目が追加され,79年3月15日より実施されることになつた。この結果,現在の本制度の対象品目は1,326品目となつている。
(c) 基礎産品,特に食糧及びエネルギーにおける協力
77年1月の第3回経済閣僚会議では米と原油の緊急時における域内優先供給,買付について合意を見たが,78年6月の第6回経済閣僚会議では米の国家備蓄制度の即時設立が合意され,12月の第7回経済閣僚会議で5万トンの備蓄を行うこととなつた。その内訳は,インドネシア1万2千トン,マレイシア6千トン,比1万2千トン,シンガポール5千トン,タイ1万5千トンとなつている。
(d) 国際経済問題などに関する協力
ジュネーヴでのガット多角的貿易交渉(MTN)・東京ラウンドあるいは,UNCTADにおける共通基金及び個別商品協定交渉さらには豪州の新航空政策に関する交渉などにおいてASEANは内部の意思疎通を密に行い,グループとして一致した姿勢で臨んだ。
ASEANは加盟国間の連帯を強める一方,日本,EC,豪州,ニュー・ジーランド,米国など域外先進諸国との協力関係の強化に努めているが,78年は,日本,米国,ECとそれぞれ閣僚レベルの会議を開き協力関係の強化に努めた。78年に開かれた域外諸国との会議は以下のとおりである。
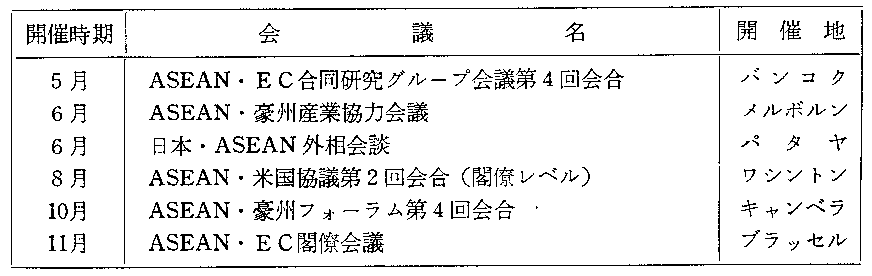
77年8月のクアラルンプールでの日本・ASEAN首脳会議を契機としてわが国とASEANとの関係は飛躍的拡大をみたが,わが国は,日・ASEAN首脳会談共同声明で打ち出された各種の協力措置を着実に実行に移すことをはじめとして,78年においても以下のとおり幅広い分野で引き続きASEANに対する協力を積極的に推進した。
日・ASEAN間の閣僚レベノレの交流については,まず6月に,タイのパタヤで園田外務大臣とASEAN5カ国外相が一堂に会し外相会議が行われた。この会談は,わが国とASEANが外相レベルで会する初めての機会であり,日本とASEANの心と心の触れ合いの具体化に大きく寄与するものであつた。このほか,日本とASEANの間では閣僚レベルで以下のとおり活発な交流が行われた。
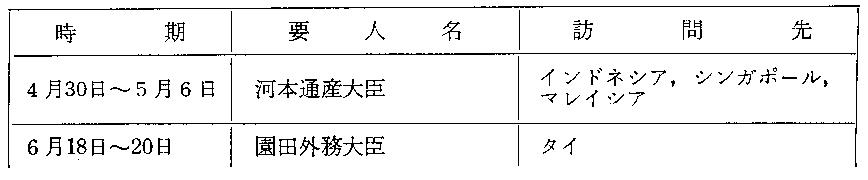
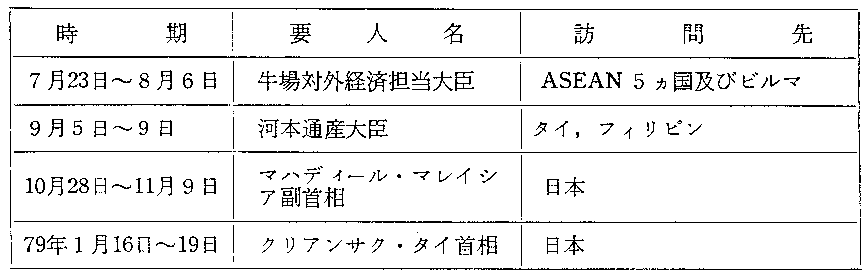
わが国は,日米首脳会談などの機会に米国などの主要先進諸国にASEANの重要性を認識せしめるべく働きかけを行つた。また,わが国は7月に開催されたボン・サミットにおいてASEANの希望などを踏まえて先進国の保護主義抑制,共通基金の検討,援助倍増など積極的に発言するとともに,同サミットの成果については,牛場対外経済担当大臣(当時)のASEAN諸国及びビルマ歴訪の際,各国に対し説明を行つた。
さらに,越・「カ」紛争及び中越武力衝突についてもわが国は,国連その他の場でASEANと緊密に協力して対処し,インドシナ難民問題に対してもASEANの要望を踏まえて積極的な協力を行つている。
わが国は貿易面でもASEANとの関係は緊密化しており,貿易額も大きく拡大しているが,78年4月よりASEAN累積原産地制度を導入し,更に対ASEAN輸入の拡大をはかつた。
一次産品問題においてもわが国はASEANの意向を踏まえ前向きに取組んでおり,特にASEANの関心の強い共通基金の早期成立のため積極的に努力し,ASEAN側もこれを高く評価している。わが国は,また,国際すず理事会に対し70億円を限度とする資金供与を行う用意がある旨通報し,78年8月に基礎的供与分として26億2千5百万円を拠出した。さらに天然ゴム協定,国際砂糖協定についてもその成立のために積極的協力を行い,後者については78年6月わが国の本協定受諾を国際砂糖理事会に通告した。
78年8月の日・ASEAN共同声明で共同研究を約したASEANスタベックス(輸出所得安定化制度)については9月に日本とASEANの専門家レベルでの協議を行つた。
また,資金協力,技術協力の分野でもASEANは引き続きわが国援助の最重点地域となつているが,上記ASEAN共同声明で約したASEAN工業プロジェクトに対する協力も着実に進展している。
文化面での協力についても,日・ASEAN共同声明で約束されたASEAN文化基金に関し,78年3月合同研究グループにおいて50億円を限度とする基金供与を誓約したが,12月には20億円を拠出し,残り30億円も近く拠出を予定している。また青年指導者招へい計画文化施設援助計画など79年度新設予定の文化協力事業もASEANを対象としている。
(イ) 南北朝鮮関係
(a) 南北対話の状況
72年に開始された南北対話は,73年夏北朝鮮側が対話に応じなくなつたため中断され,以後実質的対話はみられていない。
離散家族捜しを目的とする南北赤十字会談は77年12月を最後としてその後開かれないままであり,また南北調節委員会の運営正常化を目的とする副委員長会議も75年3月を最後として中断されたまま,78年中も開催されるに至らなかつた。
韓国側は73年6月23日南北対話の再開を呼びかけるとともに,南北間の経済協力促進のための協議機構の設置を提案したが,北朝鮮側は従来どおりの厳しい態度を変えることなくこれに応じなかつた。
しかしながら,78年後半に至り日中平和友好条約の締結と米中国交正常化という新たな情勢の展開がみられたことを背景として,79年1月19日朴大統領が対話再開を提案したところ,北朝鮮側はこれに積極的な反応を示し,2月17日双方の代表による接触が板門店で行われるに至つた。このように国際情勢の進展に伴う南北間の新たな動きには大きな期待が寄せられたが,会談に臨んだ南北間の基本的姿勢には大きな隔りがみられ,韓国側が責任ある当局者間の対話を主張したのに対し,北朝鮮側は南北の政党,社会団体などの代表者が参加する全民族大会の開催を目指すべきであるという立場をとつている。
なお,上記南北政治会談とは別に,79年2月には第35回世界卓球選手権大会(平壌)への参加問題をめくり,板門店において南北体育関係者の接触が行われた。
(b) 軍事情勢
78年の朝鮮半島の軍事情勢は概して落着いた状況で推移した。しかしながら,4月から6月にわたつて,武装スパイ船事件が連続して発生し,10月17日には,板門店南方4kmの地点で北朝鮮が構築したとみられるトンネル(74年11月15日及び75年3月19日に発見されたものについで3つ目のもの)が発見された。更に11月には韓国内の広範な地域にわたつて,北朝鮮武装スパイが出現し住民を殺害する事件が発生し,朝鮮半島の軍事情勢が依然厳しいものであることをあらためて印象付ける出来事として注目を浴びた。なお3月7日から17日の間,米韓連合演習(チームスピリット78)が史上最大規模で韓国全土にわたつて行われた。この演習は在韓米地上軍撤退問題に関連して米国の対韓防衛公約を誇示するものとして注目されたが,北朝鮮は,朝鮮の緊張状態を激化させるものとして激しく非難した。
(ロ) 韓国の情勢
(a) 内 政
(i) 維新体制の継続
78年は,いわゆる維新体制第1期(72年~78年)の最後の年に当つたため,統一主体国民会議代議員選挙(5月),大統領選挙(7月),国会議員選挙(12月)が行われた。これらの各選挙を通じて,維新体制の継続が確定し,朴正煕大統領が更に6年間政権を担当することとなつた。
この間学生デモを含め若干の反政府運動の動きはみられたものの,政府が国民総和を目指す諸政策の運用に意を用い,経済面でも種々の問題をかかえつつも成長路線を継続し得たこともあつて政情は安定した状況で推移した。
(ii) 大統領選挙
大統領の選出は,統一主体国民会議代議員により選挙される間接選挙制である。5月の選挙で新たに構成された統一主体国民会議(代議員2,583名)によつて,7月6日単独候補の朴現大統領がほぼ全会一致で第9代大統領に選出された。
(iii) 国会議員選挙
国会議員(定数231)の3分の2に当たる154名の総選挙が,12月12日行われた。今次選挙の特徴としては,議席数で与党民主共和党が68をとり,第1野党新民党の61議席を上回つたものの党別得票率で新民党が上回つたことがあげられる。このように,野党が善戦したことについては,インフレ,所得格差拡大など高度経済成長に伴うひずみに対する批判が背景にあると言われている。
ただ,残る77名の国会議員は,12月21日朴大統領の推薦に基づき統一主体国民会議で選挙され,与党系に属する院内交渉団体(維新政友会)を構成したため,全体として与党側の安定性には変化がなかつた。
(iv) 内閣改造
朴大統領は,12月22日経済閣僚を中心とする11閣僚を更迭した。これは,韓国経済がますます厳しい国際経済環境を迎え大きな転機におかれていること,インフレなどの高度経済成長のひずみにあらたに対処する必要があつたことなどを念頭に置いたものと言われている。
(V) 大統領就任に際する特別赦免
12月27日,朴大統領は第9代大統領に就任したが,就任に際し,5,378人の受刑者の特別赦免が行われ,この中で金大中は刑の執行停止の措置がとられた。
(b) 外 交
韓国は,78年中も日米など西側諸国及び非同盟諸国と友好協力関係を維持発展させることを基本としつつ,互恵平等の原則に基づいてあらゆる国に門戸を開放するとの基本方針のもとに,社会主義諸国との関係改善をはかるとの姿勢を示した。
(i) 対米関係
前年来,韓米間の懸案となつていた朴東宣による対米議会工作事件は,朴東宣が米議会において証言することにより解決の方向に向つたが,米議会内に本事件と関連し,金東作元駐米大使の米議会での証言を求める動きが起り,この結果米国機関の青瓦台(大統領府)盗聴問題(4月)ともあいまつて米・韓関係は再び試練をむかえることとなった。しかし,8月に至り金東作証言問題も書簡により回答することで合意し,盗聴事件もそのような事実はないとの米国政府の説明により一応の落着をみ,両国関係は修復の局面に入り,審議が棚上げされていた在韓米地上軍撤退に伴う補完措置法案が米議会を通過し(9月),11月には韓国が希望していた米・韓首脳会談を79年中に行う用意がある旨のカーター大統領の親書が朴大統領に伝達された。
在韓米地上軍の撤退問題については,4月21日,カーター大統領による撤退計画の一部修正(第1陣撤退規模の縮小)が行われ,補完措置法案(在韓米軍所有の約8億ドル相当の装備を韓国軍に無償で移管するもの)も紆余曲折はあつたものの,米議会で承認され成立した(9月26日)。次いで11月には,米韓連合軍司令部の創設及び在韓米空軍の増強が行われ,12月末までに,1コ戦闘大隊を含む約3,400人が第1陣として撤退を完了した。他方,米側においてかねて北朝鮮の軍備状況について検討した結果,従来に比し大幅に増強されている兆候が見られたことに基づき,米政府は,(あ)北朝鮮の軍備増強状況,(い)米中国交正常化の影響,(う)南北対話など南北朝鮮間の動きにつき検討作業を開始し,79年2月9日,カーター大統領は,これらの検討結果が得られるまで撤退を一時見合せる旨表明した。
(ii) 社会主義諸国との関係
ソ連との関係では,大韓航空機ソ連強制着陸事件に際し,ソ連政府がとつた乗客釈放措置に対し,朴大統領が謝意を表する異例の談話(4月)を発表したほか,ソ連で開催されたWHO関係の国際会議に保健社会部長官が現職長官として初めて訪ソ(9月)するなどの動きがみられた。
他方,社会主義圏で開催されたスポーツ大会(5月世界アマチュアボクシング大会[ユーゴースラヴィア],同国際ホッケー連盟総会[チェッコスロヴァキア],9月世界バレーボール選手権大会[ソ連]など)に,韓国代表団が参加したが,9月から10月にかけてソウルで開催された国際射撃大会には,社会主義諸国は参加しなかつた。
(iii) 非同盟諸国との関係
経済力の増大を背景にした開発途上国,非同盟諸国に対する積極外交が継続され,78年中,ギリシャ,ソロモン諸島など5ヵ国と新たに外交関係を樹立した。
他方アフガニスタンとは外交関係が断絶し外交関係設定国数は4ヵ国の増加にとどまつた。
(c) 経 済
第4次経済開発5ヵ年計画の2年目に当たる78年の韓国経済は,実質成長率が12.5%に達し,目標の10.5%を上回る成長を示し,この結果1人当りGNPも初めて1,000ドルを越え,1,242ドルに達した。
産業別の成長率は農林漁業部門が米穀生産及び漁業部門の不振などにより-2.3%とマイナス成長となつたが,鉱工業部門は,19.1%,社会間接資本及びその他のサービス部門は14.6%とそれぞれ伸びており,このうち,29.5%増を示した建設業の伸びが注目されている。
輸出面では国内需要の活況による輸出誘因の相対的低下,先進諸国の輸入規制などにより伸び悩みの兆候を示したが一応目標の125億ドルを越える127億ドルを達成した。輸入面では重化学工業化の進展による資本財,原資材の増加,及び輸入自由化などにより目標の135億ドルを大幅に越える146億ドルとなり,この結果,貿易赤字は約19億ドル(経常収支ベースでは約10億ドルの赤字)となつた。
他方,韓国経済の大きな課題となつている物価安定については,韓国政府の物価安定施策にもかかわらず,消費者物価は10%内外という当初目標を大幅に越え16.4%の上昇を示した。このほか,大幅な賃金上昇,所得格差の拡大,企業の資金難,労働力不足(特に高級技術者)なども今後の問題点として指摘されるに至つている。
(ハ) 北朝鮮の情勢
(a) 内 政
北朝鮮は,金日成主席の強力な指導権の下で三大革命(思想,技術,文化)運動を展開し,いわゆる「主体思想」を基本理念として政治の自主,経済の自立,国防の自衛を骨子とする自主独立路線を標榜する行き方を続けている。
78年は北朝鮮の共和国創建30周年に当たり,金日成主席は外国代表92ヵ国,109代表を招き,9月9日祝典を催した。この式典において金日成主席は演説を通じ,(i)国家活動における主体思想の徹底的具現と三大革命の強力展開,(ii)2つの朝鮮策謀の粉砕と祖国の平和統一の達成,(iii)新興勢力諸国との連帯強化と支配主義との闘争などこれまでの主張を改めて強調した。
(b) 外 交
(i) 北朝鮮の外交の基調は,「反帝,反植民地主義」,「内政不干渉」,「自主路線」を柱としており,共産圏以外の諸国との関係についても自主,独立,平等の原則が尊重されれば,自由主義諸国を含むあらゆる国との国交を樹立するとしている。特に北朝鮮は非同盟諸国との連帯をその国際的地位の向上の見地より重視している。
北朝鮮は,76年8月のコロンボ非同盟諸国首脳会議において,予期した成果をあげられなかつたことに鑑み77年以来訪問及び招待外交を再び活発化している。
78年中には朴成哲,康良イク両副主席,許淡副総理兼外交部長,孔鎮泰副総理兼対外経済事業部長,鄭準基副総理などの率いる政府代表団をアフリカ,中近東,アジア諸国に派遣する一方,華国鋒中国主席,トウ小平副総理,チャウシェスクルーマニア大統領,ボカサ中央アフリカ皇帝,ルネセーシェル大統領,マシエルモザンビーク大統領など多数の政府首脳を北朝鮮に招待した。
(ii) 外交関係の新規設定については,78年には西サモアと外交関係を樹立したが,76年以来伸びなやみとなつてきている。78年末現在の外交関係樹立合意国は93カ国(韓国は107カ国)で,このうち韓国とも外交関係を有しているのは54カ国である。
(iii) 中国及びソ連との関係においては,北朝鮮はいずれとも友好関係を保持することを基本的立場としているが,78年中は5月に華国鋒主席が,また9月にトウ小平副総理が各々北朝鮮を訪問するなど中国側からの要人の訪問が目立ち,またカンボディア・ヴィエトナム間の武力紛争問題では中国が支持するポルポト政権を支持し,ヴィエトナムの行動を批判した点が注目された。他方ソ連との間では軍事的,経済的協力関係が引き続き維持されているとみられている。
(iv) 米国との関係では,北朝鮮は再三米朝会談を呼びかけ,軍事休戦協定を平和協定に代えるよう提案しているが,米国は韓国の同席なしには北朝鮮との話し合いには応じられないとの態度を堅持した。
(c) 経済情勢
(i) 金日成主席は,79年1月の新年の辞において,78年の経済の業績を評価し,「第2次7ヵ年計画の初年度を勝利で飾り,社会主義建設のすべての分野で輝かしい成果を収めた」とし,工業総生産額は77年に比べ117%,電力110%,鋼鉄127%,化学肥料123%,セメント132%それぞれ増大した旨述べた。これは77年は早魃により水力発電能力が低下し,稼動率の低下した工場が相当あつたと言われているのに対し,78年はこのような状況がかなり改善されたことが作用しているものとみられる。金日成主席は78年度の重点施策として鉱業部門の重視,輸送力,機械工業の強化を既存設備の稼動率上昇とともにうたつたところ,これらの面でも成果があつたと言われている。しかしながら,これらの部門は77年の新年の辞において「経済建設が支障を受けている」旨指摘された部門であり,また,79年の新年の辞でも引き続き重要施策として掲げられていることから,なお引き続き改善の努力が求められているとみられる。
(ii) 対外債務問題
北朝鮮は,73年以来西側諸国から近代技術,装備の大幅な導入をはじめたが,石油危機の影響を受けたこともあり,対西欧諸国貿易は毎年大幅な赤字となり,76年末までに西側諸国を含む諸外国に対し約24億ドルに達する債務を抱えていると言われる。
(イ) 概 観
65年の日韓関係正常化以来,両国政府及び国民の努力によつて,両国は既に緊密な友好協力関係を築きあげている。
この間韓国は世界の注目を集める程の経済発展を遂げ,また78年6月22日には「日韓大陸棚協定」が発効し,両国は今後長期にわたり大陸棚エネルギー資源の共同開発に従事していくこととなつた。78年9月に開催された第10回日韓定期閣僚会議においては,このような両国関係の進展を「新しい協力関係の時代を迎えた」と表現し,今後は,相互理解の増進を一層図ることにより,広く国民的基盤に立脚した善隣友好協力関係を発展させていくことが合意された。
78年中における各分野での主な動きは次のとおりであつた。
(ロ) 日韓大陸棚共同開発
74年1月30日に署名された「日韓大陸棚協定」は78年6月22日の批准書交換により発効し,これにより,共同開発は実施段階に移ることとなつた。
まず,9月20日両国開発権者の認可が行われ,続いて11月16日及び17日の両日,東京において日韓大陸棚共同委員会の第1回定例年次会議が開催され,本共同開発の実施に関連する基本的な問題に関して意見交換が行われた。
(ハ) 通商関係
日韓両国間の貿易は,77年の日本側19.7億ドル出超から78年には同34.1億ドル出超へと更に拡大しており,両国間には上記傾向を生み出す構造的問題もあるが,両国貿易を拡大均衡させる方向で不均衡を是正していく必要が認識されている。
他方,生糸及び絹製品貿易に関し,2国間の秩序ある貿易を確保するために,78年3月東京で専門家レベルの協議を行つた後,4月ソウル,7月東京と協議を重ね,両国政府間の了解が成立した。
(ニ) 漁業問題
韓国は,78年4月30日に領海12海里を施行した。同年5月には竹島12海里内で操業していたイカ釣漁船が韓国側警備艇によつて12海里外に退去するように警告される事態が発生し,同島周辺水域における安全操業の問題が両国間の重要な懸案となつた。
また,北海道沖についてはわが国関係漁民が操業を自主規制している水域において韓国大型オッタートロール漁船の操業が続いており,漁具被害,資源減少などの問題が大きな問題となつている。政府レベル及び民間レベルで円満解決のため話合いが行われている。
(ホ) 竹島問題
わが国は,韓国による竹島不法占拠に対し,従来繰り返し抗議してきており,78年11月にも,同年8月に行われた海上保安庁巡視船の調査結果に基づき,竹島における韓国側各種建造物の設置及び官憲の滞在につき抗議し,これらの撤去を求める口上書を発出した。
また,前記わが国漁船に対する退去要求についても抗議の口上書を発出した。
<要人往来>
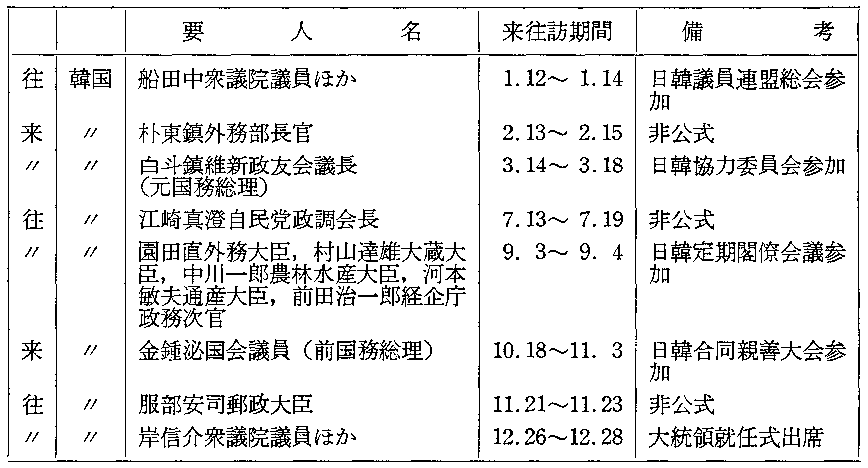
<貿 易>
1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年増加率(%))
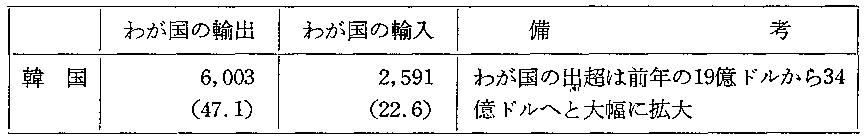
(大蔵省通関統計)
<民間投資>
(単位:百万ドル)
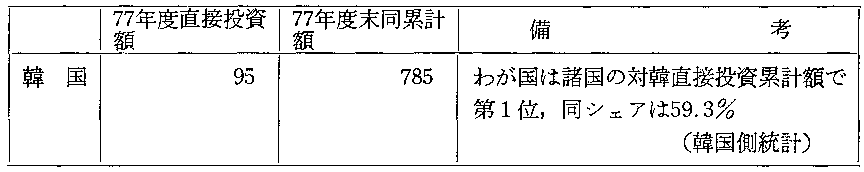
(日銀許可額ベース)
<経済協力(政府開発援助)>
(1978年;単位:百万円,人)
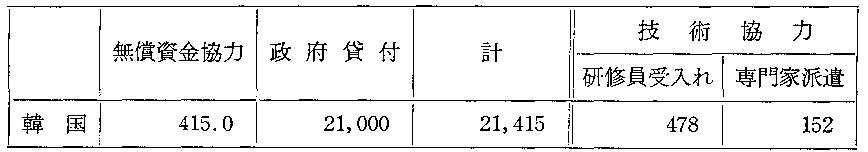
(約束額ベース)(DAC実績ベース)
(イ) 漁業関係
北朝鮮の200海里経済水域の実施(77年8月1日)に対して,わが国日韓漁業協議会と北朝鮮側当事者との間で77年9月に,「暫定操業水域」内でのわが国零細漁業者の漁撈活動が保証される旨の暫定的合意が成立していたが,78年7月1日右合意を2年間延長することが両者間で合意された。
(ロ) 人的交流
(a) 78年中の邦人の北朝鮮への渡航は,年間旅券発給数によれば639名で,77年の408名に比し,大幅に増加した。
また渡航目的別には,商用が90%を占めている。
(b) また,同期間中の北朝鮮からの入国者数は262名で,76年の94名,77年の124名より著しく増加した。
(c) 在日朝鮮人の再入国は,北朝鮮への里帰りをはじめ,スポーツ,学術文化,商用,教育,祝典参加を目的とするものなどがみられている。
<貿 易>
(1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年増加率(%))
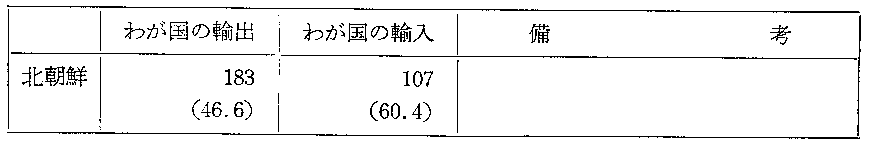
(大蔵省通関統計)
(イ) 概 観
78年の中国内政においては,従来の内政上の最大課題であつた「4人組」摘発,批判運動を収束させ,「4つの現代化」に象徴される国内建設に全力を傾注することに大きな努力が払われている。
外交面ではソ連との対立関係には基本的に変化はなかつたが,他方日中平和友好条約の締結,米中関係正常化,党・政府首脳による外国訪問外交の推進更に先進工業国との経済関係の強化など従来に比し,より積極的かつ開放的な対外政策が展開された。
また,経済面では,「4つの現代化」を具体的に進めるため第5期全国人民代表大会において,「経済発展10カ年計画」が打ち出され経済建設推進のための諸施策がとられることになった。
(ロ) 内 政
(a) 第5期全人大会の開催
第5期全国人民代表大会(以下全人大会)第1回会議は,78年2月より3月にかけて開催され,全人大会常務委員会(委員長・葉剣英),国務院(総理・華国鋒)をはじめ中央の国家・政府機関における指導体制が整備確立された。同大会において華国鋒総理は「政府活動報告」を行い,第1次文革の終了によつて中国が新たな時期に入つた旨宣言するとともに,「経済発展10カ年計画」を具体的に提示するなど,「4つの現代化」を大きく推進する方針を明らかにした。
さらに,同大会において採択された新憲法は,「4人組」時代の75年憲法に比べ,国家,政府機関の権限及び民衆の権利・義務を詳記するなど,中国が「法治国家」としての体裁を整えていく方向を示した。
(b) 国内体制の整備
その後,中国指導部は,全国科学大会(3月),全国教育工作会議(4~5月),全軍政治工作会議(4~6月)など各種全国会議を開くかたわら,9月,10月には婦女連合会,共産主義青年団,総工会の全国大会を召集して,これら組織を全国的に再建し,国内体制の一層の整備をはかつた。
(c) 毛思想の見直しと旧幹部の復活
他方,78年夏以来,故毛沢東主席の考え方をいかに取り扱うかをめぐり,「事実に基づいて真理を求める」,「実践こそが真理を検討する唯一の基準である」とのキャンペーンが進められ,その結果たとえ故毛沢東の指示であつても事実に即して解釈していくとの考え方が大勢を占めるに至つた。
この流れを受けて,11月中旬以降,76年4月「反革命事件」と断定されていた「天安門事件」の再評価が行われたほか,国内の民主化及び文革などにより失脚させられた諸要人の復活(故人であれば名誉回復)が進められた。
(d) 第11期三中全会の開催
これに続き11月中旬より12月中旬にかけて中国共産党中央工作会議及び同党三中全会(第11期中央委員会第3回全体会議)が開催された。この結果これまで内政上の重点課題とされていた林彪・「4人組」批判の大衆運動がすでに終了し,今後,従来のような大衆的階級闘争は行わない旨が明らかにされるとともに,今後の施策の重点を社会主義の近代化建設に置く旨が宣明された。
また,三中全会は,故毛沢東の無謬性を否定し,文革の過程における誤ちの存在を認めたが,他方毛沢東の功績を肯定し,文革の見直しを急がないとの方針を示し,「党内民主」の徹底と法律制度の整備の必要性を強調するなど,「安定団結」を最前面に押しだした。
三中全会を人事面から見ると壁新聞などにより非難を受けていた一部要人は党中央政治局にとどまつたが,陳雲全人大会常務委員会副委員長はじめ実務派4名が補充されるなど調整が行われ,更に58年に失脚した彭徳懐(元政治局委員兼国防部長),文革初期に失脚した陶鋳(元党副主席兼政治局常務委員)など大物幹部の名誉回復も行われた。以上要するに,建国30周年を79年秋に控えた中国は,三中全会を経て,国家建設に総力を挙げて当るべく大きく踏み出したものといえよう。
(e) 台湾に対する呼びかけ
12月16日の米中正常化に関する共同コミュニケ発表以後,中国は台湾に対する祖国統一の働きかけを盛んに行い始めた。79年1月1日に発表された「台湾同胞に告げる書」においては台湾の現状の尊重に言及し,台湾当局との話し合い,郵便などの通信関係,航空・運輸関係などの実現を呼びかけ,また同月末のトウ小平副総理の訪米の際も,同副総理は柔軟な対台湾政策を明らかにし注目された。
(ハ) 外 交
(a) 対ソ関係
中国は上記全人大会「政府活動報告」などあらゆる機会にソ連を激しく非難しその対決姿勢に変化は見られなかつた。しかしながら他方イデオロギー面は別として国家関係は改善したいとの意向を明らかにしており,5月から6月にかけて中ソ国境交渉が行われた。また5月黒龍江省においてソ連軍による国境侵犯事件が発生した際も中国は慎重な対処振りを見せ,国家関係は冷静に維持していく姿勢を見せた。
(b) 対米関係
5月のブレジンスキー米大統領補佐官の訪中をきっかけに夏以降,米中関係正常化の問題につき急速な進展がみられ,12月16日米中両国は共同声明を発表し,79年1月1日より外交関係を樹立する旨が明らかにされた。米国はこれにより,同年1月1日をもつて台湾との外交関係を終了させ,また米華相互防衛条約の終了通告を行うとともに,4ヵ月以内に台湾より残存軍隊を撤退させることとなつた。他方米台関係は,文化,商業その他非公式な関係が維持されることとなつた。
米中正常化を機にトウ小平副総理が79年1月から2月にかけ訪米し,カーター大統領と会談したほか,科学技術協力協定,文化協定及び領事関係樹立と総領事館開設に関する協定などが署名された。
(c) 対アジア関係
(i) インドシナ地域との関係では中国は,ヴィエトナム,カンボディア紛争の激化に対しカンボディア支持の姿勢を極めて明確にしたが,他方,ヴィエトナムとの関係は,4~5月に発生した在ヴィエトナム華僑大量帰国問題をきつかけとして急激に悪化した。中・越両国は8~9月次官級会談を開いたが,何ら成果を挙げないまま9月26日中断され,その後中越国境付近において軍事的緊張の高まりが伝えられた。
79年1月越軍の深い関与のもとに大攻勢が行われ,カンボディア人民共和国の樹立宣言をみた後,2月17日,中国側は,ヴィエトナム側による中越国境侵犯を理由に対越進攻を行い,中越間に武力衝突が発生した。
(ii) ASEANとの関係において,中国は,ASEANの中立化構想を支持する旨明らかにし,3月には李先念副総理がフィリピンを,11月にはトウ小平副総理がタイ,マレイシア,シンガポールをそれぞれ訪問するなどASEANに対し積極的な善隣外交を推進した。また中国はシンガポール,インドネシアとの外交関係の樹立ないし回復の意向がある旨を表明した。
(iii) 北朝鮮との関係では,5月に華国鋒主席が訪朝し,9月の北朝鮮成立30周年式典にはトウ小平副主席が訪朝するなど北朝鮮を重視する姿勢を保つた。
(d) 対欧州関係
東欧との関係では,8月華国鋒主席がルーマニア及びユーゴースラヴィアを訪問し両国との友好関係の強化が進められた。特に,ユーゴースラヴィアについては,党関係の回復が行われたことが注目された。アルバミニアとは,近年関係が冷却していたが,7月,中国は対アルバニア援助を停止するに至つた。
西欧に対しては,中国は「4つの現代化」促進の観点から経済・技術・軍事面で積極的外交を展開し,4月ECとの貿易協定,12月仏との経済協力協定などを締結した。
(e) 対中近東・アフリカ関係
中近東との関係では,5月オマーン,8月リビアと外交関係樹立,8月末華国鋒主席のイラン訪問などが行われた。
対アフリカ関係については,各国首脳の招待外交,中国要人の訪問外交を積極的に行つた。
(ニ) 経済情勢
(a) 78年に入り,中国は,全人大会において前述の「国民経済発展10カ年計画」を,また,3月の全国科学大会において,全国科学技術発展計画要綱をそれぞれ制定し,国をあげて現代化計画達成に取組む姿勢を明らかにした。
(b) 農業面では機械化,基本建設の推進がはかられたほか農民の積極性を引き出すための諸措置がとられた。工業面では企業内の革命委員会の廃止,工場長制度の復活などがすすめられたほか労働者の勤労意欲促進のため奨励金制度も復活された。
(c) 78年の穀物生産は2億95百万トンと前年に比し10百万トン増産となり,綿花,採油用種子など経済作物も前年に比し増産となつた。また,工業生産においては,78年1~11月の工業総生産額が前年同期の12%増となつた旨発表された。
なお上記農工業生産の伸びから国民総生産の伸びを試算すると10%弱の伸長,総額40.7百億米ドルと推計される。
(d) 78年の中国の対外貿易総額は208億米ドルと前年比38%増,うち,輸出は102億米ドルと28%増,輸入は106億米ドル,49%増と推計されている。
78年1~8月の商品別実績についてみると中国の輸出では原油,石炭,繊維製品などの工鉱業製品が大幅に伸長し,輸入面では新技術プラントが77年同期に比し62.9%増と報ぜられた。(但し西側推計によるとプラント輸入は年間合計で77年の81百万米ドルに対し,69億34百万米ドルとされている)。中国の外貨収入については輸出による収入は28.6%増,貿易外収入は40%増と報ぜられている。
(イ) 日中平和友好条約の締結
72年の日中共同声明において言及されていた日中平和友好条約は,78年7月以降北京において16回に亘る実務レベル交渉及び3回に亘る園田外務大臣・黄華外交部長との会談を経て,8月12日署名・調印され,10月23日発効した。この条約の締結により,日中両国間の平和友好関係を一層発展させるための基礎が築かれた。日中間の平和友好関係がこのように長期にわたり安定的なものとして確保されることは,アジア及び世界の平和と安定に貢献するものと期待される。
(ロ) 日中経済貿易関係
78年の日中貿易は往復50億79百万米ドルと50億米ドルの大台を越えた。2月には78年から85年までの8年間に往復200億米ドルの取引きを行うことを定めた民間の長期貿易取決めが署名され,8月の日中平和友好条約の署名・調印以後,日中間の経済貿易関係,人的交流はますます緊密なものとなつている。9月には河本通産大臣(当時)が訪中し,長期貿易取決め拡大などの問題が話し合われ,また,12月には単一のプロジェクトとしては最大の上海宝山製鉄所(総額4千億円)の起工式が行われた。78年後半にはプラントの成約も進められたが他方,輸銀,市中銀行による資金協力は年内にまとまるに至らず,79年に持越しとなつた。
78年の日中貿易を商品別にみると,わが国の輸出では金属,機械・設備の伸長が顕著であり,他方,輸入では繊維・同製品の伸長が大きかつた。
(1978年;単位:百万米ドル,( )は対前年増加率%)
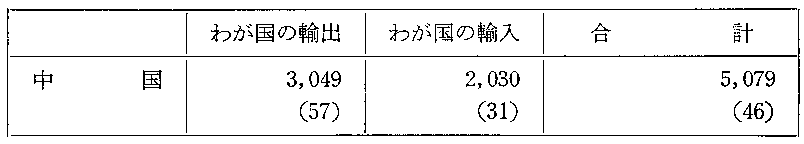
(通関統計)
(ハ) 実務関係
(a) 第3回日中貿易混合委員会
78年11月末北京において開催され,日中両国経済,日中貿易についての最近の動向と見通し,日中貿易実務上の諸問題につき意見交換が行なわれた。
(b) 日中漁業協定附属書の修正交渉
日中漁業協定は,78年12月,当初の有効期限3年の満了を迎えた。同月,日中漁業共同委員会臨時会議が開催され,その結果同協定の自動延長,協定附属書の修正が行われることとなつた。
(ニ) 人的交流及び文化などの交流
(a) 78年における日中間の人的交流は政治,経済,学術,文化,スポーツの各分野に及んだが,特に国家指導者間の往来が顕著であつた。即ち,中国側から,10月にトウ小平副総理,蓼承志中日友好協会会長,黄華外交部長らが,また翌79年2月に,トウ小平副総理,方毅副総理,黄華外交部長らが訪日し,わが国から8月に,園田外務大臣,9月に河本通産大臣,11月に三宅衆議院副議長が,翌79年1月には安井参議院議長がそれぞれ訪中した。
78年における日中間の人的交流
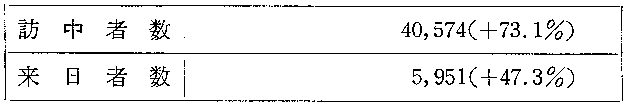
( )内は前年比
(b) 教育面での交流については,留学生多数を訪日させたいとの中国側の要請に応え,わが方教育代表団が12月に訪中し,話し合いを行つた結果,79年4月以降,わが国は相当数の中国留学生を受けいれることとなつた。
その他,11月には囲碁訪中団が訪中し,79年1月には歌舞伎が訪中し北京,上海で公演を行い,大きな反響を呼んだ。
なお,78年度の引揚者及び里帰者は次表のとおり。

(イ) 内 政
78年6月の蔣経国の総統就任に伴い,台湾における指導体制は更に整備され,また指導部では従前の党務官僚に代つて実務官僚の台頭が顕著となった。また島内においては順調なる経済発展により,生活の安定向上がみられた。
(ロ) 外交関係
12月に発表された米中正常化による米台断交は,台湾に大きな衝撃を与えたが,米台両者において実務関係維持の努力がなされるに伴い落ち着きをとり戻しはじめている。なお,米台断交により台湾を承認している国は21カ国となつたが,台湾は国交関係の無い国々との貿易・文化など実務関係の維持に意を用いている。米中正常化以来一層盛んとなつた中国の台湾への「祖国統一」の呼びかけに対しては,台湾は中国との話し合いに応じない方針を示している。
(ハ) 経済情勢
78年の台湾経済は,鉱工業生産額が前年比28%,貿易総額が前年比33%の伸びを示し,GNP実質成長率も12.8%と発展を遂げた。しかしながら,これに伴い物価上昇をきたし,インフレの悪影響が懸念されている。
(ニ) わが国との関係
72年の外交関係終了後も,わが国と台湾との間の経済・文化などの民間ベースの関係は,続けられており,また日本側・交流協会,台湾側・亜東関係協会を通ずるチャネルも維持されている。78年の日台間貿易額は往復53億米ドルで,わが国の対外貿易中の約3%を占めた。
(イ) インドネシア
(a) 内 政
77年5月の総選挙を受けて78年3月には国権の最高機関である国民協議会(5年に1回開かれ,向う5年間の国策の大綱の決定及び正副大統領の選出を行う)が開催され,大統領にはスハルト大統領が3選され副大統領にはアダム・マリク国民協議会兼国会議長(元外相)が選出された。
続いて,スハルト大統領は内閣改造を行い,第3次開発内閣を組閣し79年4月より始まる第3次開発5ヵ年計画実施の基礎固めを行つた。今次内閣改造においては軍人閣僚の重用,野党出身閣僚の廃止,調整大臣の新設,社会開発分野を担当する副大臣の新設などが特徴となつている。一方総選挙以来78年3月の国民協議会総会直前まで続いた学生を中心とする反政府運動も,多数の逮捕者を出し,下火になつた。
このような情勢下にあつて,78年11月16日より実施されたルピア切下げは,物価上昇及びそれに伴う一般大衆の購売力の落ちこみももたらしており,その影響が注目された。
(b) 外 交
78年のインドネシア外交は,社会主義諸国からの要人の来訪も盛んで極めて多角的に展開した。特に,9月のファン・バンドン越首相の来訪は,スカルノ失脚後,初めての越指導者の訪「イ」であり,相互理解を深める上で一応の成果を挙げたとみられるほか,10月のイエン・サリ カンボディア副首相の来訪によつてインドネシア・カンボディア両国間で,外交関係再開につき合意をみた点も,特に注目された。
また,9月にはフィリュービン ソ連外務次官の来訪,8月と9月には,それぞれポーランドからオルシェスキー対外貿易・海運相及びボイタシェック外相の来訪などが相つぎ,「イ」国外交の基調たる非同盟中立外交の積極的展開がはかられた。
他方,中国との関係では,昨年に引き続き「イ」国商工会議所代表が,5月広州交易会に派遣され,北京にも赴き中国側と直接貿易取引を行うことで合意をみたと報じられたが,これは「イ」国の対中関係正常化のための布石ではないかとの憶測を呼んだ。しかし「イ」国政府の正式発表により中国との間で直接貿易取引をする考えのないこと,対中正常化にはなお慎重を要することなどが明らかにされ,正常化には,なおかなりの時間がかかるとの印象を一般に与えた。また欧米諸国との関係は,従来どおり緊密で5月のモンデール米副大統領の来訪は,カーター政権誕生以来懸念されていた米国の「アジア離れ」を払拭するものと歓迎され,他方EC諸国からは,8月のラムスドルフ西独経済相,9月のギランゴー仏外相およびコーニング オランダ海外開発協力相などの来訪が相つぎ,これら諸国との関係強化が注目された。
また「イ」国外交の最重要課題であるASEAN内の連帯強化のため各種協力の進展をはかるとともに対外的にも結束を強めており,これは8月のワシントンでの米・ASEAN閣僚会議及び11月のブラッセルでのEC・ASEAN閣僚会議などに示されている。
(c) 経済情勢
(i) 78年のインドネシア経済は,総体的に順調に推移したが,他方11月15日に発表され翌16日より実施されたルピア貨大幅切下げなどの措置は経済界及び一般大衆に大きな影響を与えた。
(ii) 輸出は,石油及び非石油ともに若干前年より減少し総額110億ドル,一方輸入はほぼ前年並みで,総合収支は1億ドル余の黒字であり,78年末の外貨準備は26億ドルであつた。
(iii) 78年の石油生産は163万バーレル/日と前年を4%下回り,生産の停滞と国内需要の急速な伸びは,輸出を圧迫しており,新規油田の開発及び代替エネルギーの開発が急がれている。
(iv) 農業面では,78年の米生産は,1,750万トンという史上空前の記録を達成したが,自給の域に達せず130万トンを輸入した。
(v) 物価については引き続き抑制策を取り78年は6.7%の石油危機後最低の上昇率に留つた。
(vi) 外国援助(78年度は歳入の18%を援助に依存している)については,78年5月の対インドネシア政府間協議グループ(IGGI)会議において,インドネシア政府は,78年度分として25億ドルの外国からの資金需要があるとして,そのうちの一部について援助要請を行つた。これに対してIGGI諸国及び国際機関は78年度中に合計16億3200万ドルの資金協力の意図表明を行つた。
(vii) 対インドネシア民間直接投資は,引き続き低迷しており,78年は3656百万ドル(12月末現在同国政府許可額)であつた。
(viii) インドネシア政府は,11月15日より,ルピア貨の対米ドルリンク制を止め管理変動相場制を採用するとともに,対米ドル為替レート1ドル=415ルピアから1ドル=625ルピアに切下げる(IMF方式33.6%の切り下げ)とともに,輸入原材料に係る関税などの50%軽減及至免除の措置を発表した。
この一連の措置は,輸出の促進,79年4月の第3次開発5ヵ年計画開始を控えて外国投資の誘致,財政基盤の強化などを狙いとするものであるが,これまでのところ物価上昇,企業活動の停滞などのマイナス面の影響も少なくないとみられている。
(ロ) マレイシア
(a) 内 政
77年9月からの汎マラヤ回教党の内紛から生じたクランタン州における政情不安に対し,中央政府は同年11月に非常事態宣言を発出し,同州を直轄統治していたが,治安の回復に伴い,78年2月12日に同宣言を撤回,翌13日に同州議会を解散,翌3月に選挙を行つた。この結果,与党統一マレイ国民組織が圧倒的勝利を収め,59年以来同州議会の過半数を占めてきた汎マラヤ回教党の当選は2名にとどまつた。
またフセイン首相は,6月に国会下院を解散して7月に首相就任後初の総選挙を行つたが,投票の結果,与野党の勢力分布は解散前と同数の131対23となり,引き続き与党側が圧倒的優位を維持することになつた。同選挙の結果を受けて,フセイン首相は7月28日に新内閣を発足させたが,新内閣の顔振れは,旧内閣に比し大幅な変化は見られず,わずかにこれまでフセイン首相が兼任してきた国防相のポストにタエブ前第一次産業相が任命されたこと,連邦区省を新設してフセイン首相がこれを兼任することになったことなどが注目された。
9月には,連立与党中最大の勢力たる統一マレイ国民組織(UMNO)の党大会が開催された。同党大会は,3年に1度の党総裁を含む役員選挙の年にあたつたが,フセイン首相が党総裁に,マハディール副首相が副総裁に選ばれるなど有力者が順当に選出された。
この結果,政府・与党レベルにおいて名実ともにフセイン-マハディール体制が確立されたものとみられている。
(b) 外 交
78年のマレイシア外交は,従来と同様ASEAN外交を基調としつつも,回教国,英連邦諸国及び非同盟諸国との友好関係の増進を目指して展開されたほか,インドシナ諸国,中国,ソ連など共産諸国との活発な交流も行われた。すなわち,2月にクリアンサック タイ首相,5月にスハルト インドネシア大統領,6月にフレーザー豪首相並びにリー シンガポール首相がマレイシアを訪問してフセイン首相と会談した。またリタウディン外相は1月にアラブ首長国連邦,4月にクウェイト及びバングラデシュ,5月にパキスタンを訪問したほか,4月にセネガルで開催された回教国外相会議に出席,回教諸国との連帯強化に努めた。
また対共産圏諸国との関係では,1月にグエン越外相,2月にコー北朝鮮副首相,3月にフィリュービン ソ連外務次官,5月にプーン ラオス副首相,7月にファン・ヒエン越外務次官,10月にファン越首相,11月にトウ小平中国副総理がマレイシアをそれぞれ訪問した。
(c) 経済情勢
78年のマレイシア経済は,先進諸国の景気回復の遅れの影響を受け,前年に引き続き輸出収入の伸びが小幅にとどまり,また77年に続く旱魃の影響による農産物生産の低迷もあつてGDP,GNPとも前年の伸び率を幾分下まわつた。しかし政府の積極的な財政及び金融政策による民間投資の刺激策と公共投資の推進によつて国内需要を喚起できたことにより,7%台の経済成長率を維持した。
物価上昇率は,政府の積極的インフレ防止策により,5%程度にとどまつた。
(ハ) フィリピン
(a) 内 政
72年9月に発布された戒厳令の下で治安回復,経済開発,汚職追放などの施策を強化してきたマルコス大統領は,77年夏に現行憲法が採用する議院内閣制の形を整えるべく「正常状態への復帰」を追求する姿勢を打ち出し,78年4月に暫定立法議会議員(地域代表)選挙を実施した。この結果,与党連合(KBL)が定数165議席中150議席を獲得した。その後,セクター代表議員及び閣僚議員が間接選出及びマルコス大統領により現職閣僚の中から任命され,同議会は78年6月12日,国政レベルの議会としては5年9ヵ月ぶりに召集され,右に伴いマルコス大統領は現行憲法の規定に基づき大統領兼内閣総理大臣に就任した。なお,同大統領は78年6月11日付をもつて後継者問題に関する大統領令を発し,同大統領が恒久的に無能力者となるか,死亡又は引退した場合には暫定立法議会議長が大統領に,副首相(現在に至るも未任命。複数の場合は首席副首相)が内閣総理大臣となるとしたが,右は同大統領が自己の後継者につき初めて公に明らかにしたものとして注目される。
また,マルコス大統領に批判的な人物の1人で,戒厳令発動と同時に逮捕されたアキノ元上院議員は前記の暫定立法議会議員選挙に獄中より立候補し次点で落選したが,その国民的人気は依然根強いものがあると伝えられている。
南部回教徒問題はその後もミンダナオ島を中心に非政府軍とモロ民族解放戦線(MNLF)との間で散発的な衝突がくり返されているが,最近の動きとしては,MNLF内部でその主導権をめぐり抗争が激化しているといわれている。
(b) 外 交
フィリピンは75年春のインドシナ情勢の急変後はより多様化した外交を展開しているが,マルコス大統領は78年6月23日の比外務省80周年記念式典において,フィリピン外交が立脚すべき6本の柱として(1)独立と主権の体現としての外交政策の追求,(2)フィリピンの発展と進歩への貢献,(3)イデオロギーの如何によらず全ての国との有益な関係の維持,(4)互敬,互恵,独立の尊重などを基礎とする諸外国との関係設定,(5)国際経済秩序改定を目ざした外交活動の実施及び(6)国連の目的及び活動の支持を発表した。
対米関係では,フィリピンは前述の如く多角的外交を旨としつつも,対米友好協力関係を基軸としており,79年1月には懸案であつた比米軍事基地協定改訂交渉が合意を見るに至つた。
ASEAN内の協調外交は同国外交の支柱の一つであり,特に最近の東南アジア情勢の中でASEANの更なる結束強化を唱えている。
対共産圏外交では,中国との関係で,78年3月に比国軍によるパナタ環礁占拠事件が発生したが中国政府は慎重な態度で事態の沈静化を図り,またその直後の李先念中国副総理の訪比に際しては比政府は前例のないといわれる厚遇ぶりを見せた。このような両国の相手国に対する配慮ぶりは今後の両国関係の方向をある程度示すものといえよう。ソ連との関係では,78年6月にイメルダ・マルコス大統領夫人が訪ソし,10月にフィリュービン ソ連外務次官の訪比が行なわれ,対ヴィエトナム関係では78年1月にグェン・ズイ・チン ヴィエトナム副首相兼外相及び9月にファン・ヴァン・ドン ヴィエトナム首相が訪比した。
(c) 経済情勢
78年のフィリピン経済は新5ヵ年開発計画(78年~82年)の下に成長率5.8%の拡大を見せた。最大の問題は貿易収支の赤字で,78年は,輸出不振と上記5ヵ年開発計画を推進するにあたつての資本財を中心とする輸入の大幅増に起因し,14億ドルという史上最高の赤字幅に達した。消費者物価は7.7%増,財政赤字は新税導入などにより前年比5%の改善を見せた。また従来より注目されていたパラワン島沖合での石油生産は79年2月より開始された趣で,同年末までには日産4万バレルに達しこれによりフィリピンの石油消費量の約17%が自給されているといわれている。なお,対外債務は78年末現在77億82百万ドルに達しその急増ぶりが注視されている。
(ニ) シンガポール
(a) 内 政
78年のシンガポール政情は,政治的にも経済的にも大きな波乱はなく平穏に推移した。すなわち,経済的には77年から引き続いて比較的高い成長率を維持して石油ショックからの立直りを示した。このような経済分野の好調な推移を背景に政治的にも安定を持続,これがまた経済的安定を持続強化させるという好循環を生んでいる。政治的には,63年のいわゆる「冷凍作戦」で逮捕されたリム医師並びにザハリ元ウトウサン・ムラユ紙編集長(11月)及び73年に政府の教育政策を批判して逮捕された元南洋商報社長(2月)など著名な政治犯5名が釈放されたのが目立つた。
また,現在のシンガポールにおける最大の課題とも言える2言語主義政策推進のために,8月にゴー副首相を長とする特別タスク・フォースを創設,2言語主義を一層推進するための方途を探ることになつた。
(b) 外 交
シンガポールは,外交的には,米,中,ソの多角的勢力均衡の上に立って,ASEAN内での協調を主軸としつつ,日本,豪州,ニュー・ジーランド,ECなどの域外国に働きかける戦略をとつている。またシンガポール外交の特色のひとつはリー首相による首脳外交である。同首相は,78年においても,2月に豪州,4月に香港,台湾,スリ・ランカ,6月にバハレーン,イラン,マレイシア,インドネシアを,9月下旬から10月にかけてベルギー,EC,仏,米などを訪問したほか12月にはタイ及びインドを訪問するなど精力的な首脳外交を展開した。
また,外国からは,9月にラーマン バングラデシュ大統領,10月にはシュミット西独首相がシンガポールを訪問したほか,7月にはファン・ヒエン越外務次官,10月にファン・バン・ドン越首相,11月中旬にはトウ小平中国副総理,同月下旬にはフィリュービン ソ連外務次官がシンガポールを訪問した。
(c) 経済情勢
78年のシンガポール経済は,世界的な景気停滞という悪条件にもかかわらず,引き続き順調に推移した。すなわち石油精製,電子・電気,運輸・通信,観光など業界の好調を軸に前年を上まわる実質8.6%の成長率を達成した。雇傭も対前年比で4万1,000人増加し,失業率は3.6%とこれまでの最低水準となつた。しかし消費者物価は年率4.82上昇した。
対外貿易は,輸入(対前年比16%増)の伸び率が輸出(対前年比14.4%増)の伸び率を上まわつたため貿易収支は,1,183百万シンガポール・ドルの赤字となつたが,海外からの投資が好調であつたため,外貨準備高は12月末で114億シンガポール・ドルに達した。
(ホ) タ イ
(a) 内 政
78年は,政変の相次いだタイにとり,久々に政治的安定を取り戻した1年であつた。
77年10月のクーデターにより軍の支持を背景として政権の座に就いたクリアンサック内閣は,暫定憲法に規定された79年4月までの総選挙実施に向かつて,恒久憲法の制定,安定した国内基盤造り,経済振興をその主要課題とした。
同内閣は新聞検閲の廃止,労働組合との関係改善,左翼学生の大学復帰呼びかけなど一連の柔軟路線を打ち出し,前政権の強硬な反共路線により対立を深めていた国内各派との協調,宥和を図つた。
また政権維持に不可欠な軍部の掌握についても,クリアンサック首相は,8月内閣改造を行い自ら国防相を兼任するとともに,10月の軍の定期移動を手堅くこなして,引き続き軍と良好な関係を維持した。
恒久憲法起草は国家立法議会で6月開始され,12月22日公布された。新憲法は,任命制の上院の設置や首相・閣僚は国会議員たるを要しない点,また選挙による小党乱立を防ぐための諸規定などを含み,安定した政権誕生を目指した憲法となつた。
新憲法制定により79年4月22日に下院選挙及び上院議員の任命が行われ,その結果,第2次クリアンサック内閣が成立した。
(b) 外 交
78年のタイ外交は引き続きASEAN諸国との連帯強化に努める一方,前ターニン政権時代に冷却化した対共産圏関係の修復,なかんずく対インドシナ関係の改善及び中国との関係正常化を積極的に推進した。
対インドシナ関係では,まずヴィエトナムとの間で大使を交換し,ファン・ヴァン・ドン越首相の訪タイ(9月)により,越はタイの共産ゲリラを支援しないとの約束を取り付けた。またラオスやカンボディアとの間では,外相の相互訪問により相互理解の気運が醸成され,国境での衝突事件発生も減少するなど関係正常化が進められた。しかし,79年1月,プノンペン陥落などのカンボディアにおける武力紛争及び中越武力衝突などインドシナにおける紛争に対してはタイは安全保障上の観点からかかる事態を憂慮し,自国の国防の強化に努めるとともに「中立」の立場で臨んでいる。また,タイには約15万人以上のインドシナ難民が滞在しており,タイ政府はその対策に苦慮している。
対中関係では,クリアンサック首相の訪中(3月),トウ小平副総理の訪タイ(11月)により経済交流も含め両国の友好関係が確認された。
他方,対自由主義圏外交として,クリアンサック首相は2月ASEAN諸国を歴訪し,タイの対外政策に対する各国の支持を取り付け,また,6月にはパタヤでASEAN外相会議を開催して,ASEANの域内協力関係緊密化に努力した。
更に対米,ソ関係ではモソデール米副大統領の訪タイ(5月),フィリュービン ソ連外務次官の訪タイ(3月)により両国の東南アジア,なかんずくタイに対する関心が表明された。なお,クリアンサック首相は,79年2月及び3月にそれぞれ米国及びソ連を訪問し,一連の全方位外交の総仕上げを行つた。
(c) 経済情勢
78年のタイ経済は当初先行き不安感のなかでスタートしたが,前年に引き続く製造業及び建設業の高度成長,農業生産の回復,民間投資の伸長などを背景にして,国内実質総生産は前年比8.7%の高い成長となつた。
前年の旱魃に引き続き,洪水に見舞われた農業生産は,一部地域では豊富な水量もあつて米,メイズ,砂糖などの増産となり,実質成長率9.4%の豊作となつたほか,工業生産は高水準の国内消費,輸出の堅調により食料品,建設資材,繊維の各産業を中心として実質12.2%の成長を遂げた。
物価は農産物の豊作により食料品価格の安定をみたものの,非食料品価格の一貫した上昇基調,公共料金及び最低賃金の引上げ,輸入品の価格上昇により対前年比9.6%の上昇率となつた。
対外貿易は輸出入ともに対前年比15.7%の伸びとなつたが,貿易収支は14.8億ドル(推計)と史上最高の赤字を計上した。また総合収支も赤字を続け,外貨の純準備高は12月末で856百万ドルに低下した。
78年は政権が安定し,労働運動も平穏に推移したことから,投資環境は総じて改善し,78年の投資奨励法に基づく申請及び許可件数はかなり増勢を示した。しかし投資規模は依然小さく,輸入代替的なものが中心で,実際の投資活動が大幅に伸びるまでには至らなかつた。
(ヘ) ビ ル マ
(a) 内 政
78年のビルマは,比較的平穏に推移した。内政面における最大の出来事は,3月初旬第2回人民議会第1会期が開催され,民政第2期(78~82年)を迎えたことである。同議会においては,国家評議会議長(大統領)及び同書記,首相の顔ぶれに異動がなく,向う4カ年についてもネ・ウィン=サン・ユ体制の継続が確認されるとともに,中央及び地方の国家並びに党機関への現役軍人の多数進出が注目されたが,これはネ・ウィン統領が政権の基盤として軍の重要性を再認識したためとの見方が一般的に行われている。
他方ビルマ共産党(BCP)少数民族並びにウ・ヌ派亡命グループなどの反乱軍は,辺境地区を中心に国内各地で蠢動を続け,ビルマの経済開発を阻害しているが,特にBCP反乱軍はトウ小平副総理の訪緬(1月)直後の2~3月に,シャン州北部で政府軍に活発な攻撃を加えたが,その後その活動はかなり鎮静化した。
(b) 外 交
外交面においては,78年を通じ,ビルマの首脳外交は77年に比し概して不活発であつた。すなわち,ネ・ウィン大統領による海外訪問は,健康診断のためのオーストリア訪問(8月末-10月中旬)のみにとどまつた。しかしながら,トウ小平中国副総理の訪緬(1月及び11月),ミエソ・マウン ビルマ外相の訪中(9月)のほか緬・中軍事使節団の相互訪問(6月及び11月)など中緬両国友好関係の進展をみたほか,ビルマ・北朝鮮両国間でも,第2工業相(8月)及び外相(9月),孔沈泰副首相(2月)及び外国貿易相(11月)など要人の交流が深められた。また,ASEAN諸国との交流については,クリアンサック タイ首相がビルマを公式訪問(5月)した。なお,3月,バングラデシュと国境を接するアラカン州で,ビルマ政府が実施した住民確認調査に端を発して20万人に達するべンガル出身回教徒がBD側に流出したいわゆるビルマ・BD国境難民問題は,両国間の外交交渉の結果,円満解決し,ビルマ側による難民引取りが開始された。
(c) 経済情勢
ビルマ経済は,75/76年度から引き続き拡大傾向にあり77/78年度にはGDP実質経済成長率6.4%に達した。また,米の需給状況は77/78年度産米の政府買上げが目標値を下まわるなど,78年中盤に一部地域で米の不足及び米価の高騰をもたらしたが,78/79年度産米の生産が,好天候に恵まれたこと,高収量品種(HYV)の普及が広がつたこと及び近隣諸国のような洪水被害を受けなかつたことなどの好条件により,かなりの増収が期待されている。他方,外国借款による産業基盤の整備も徐々に進展しており,ビルマ経済として順調な動きを見せた。しかし実質国民所得が依然低いレベルにあることに加え,消費者物価が高値安定で,国民生活には依然として諸困難が伝えられている。
(イ) インドネシア
日本とインドネシアの2国間関係は,安定的に推移しており,特に日本・ASEANの関係緊密化を反映し,近年一層の緊密の度を加えている。
インドネシアは,78年にはわが国にとつて第5位の貿易相手国であり,援助対象国としては第1位,投資先としては第2位の地位を占めている。
日・イ間の官民各層の対話の場である日・イコロキアムは78年10月第6回会合を東京において開いたほか,12月には,両国財界人の間の意思疎通促進のため,新たに「日本・インドネシア合同経済委員会会議」の設置がわが国経団連及び日本商工会議所とイ側商工会議所との間で合意され(日本側では79年1月このための母体として「日本インドネシア経済委員会」が発足),79年3月にはその第1回会議がジャカルタで開催された。これにより日・イ間に2つの定期的な対話の場が設けられ,両国間の関係を一層強化するものとなつている。
(ロ) マレイシア
わが国とマレイシアの関係は,全般的に良好で,78年においても両国間要人の相互訪問,経済・技術協力,文化面での協力を通じて更に親善の度合いを深めつつある。
すなわち,78年にはマレイシアから3月に国王夫妻,10月にはマハディール副首相が訪日し,またわが国からは5月に河本通商産業大臣(当時)6月に砂田文部大臣(当時)及び7月に牛場対外経済担当大臣(当時)がマレイシアを訪問し,両国間の意思の疎通が図られた。
両国間の貿易問題では,76年以来わが国の入超となつており,78年においても約7.4億米ドルの入超となつている。
(ハ) フィリピン
78年は,6月のタイにおける園田外務大臣とASEAN外相との協議及び7月の砂田文部大臣,8月の牛場対外経済担当大臣,9月の河本通商産業大臣(いずれも当時)などの一連のわが国要人の訪比を通じ両国関係の一層の緊密化が図られた。また11月の第7次円借款(325億円)及び12月の特別円借款(70億円)の供与をはじめとし,わが国対比経済協力,並びに文化交流・協力も積極的に行われた。
一方,78年の両国間の貿易収支は約4.9億ドルの比側赤字となり,貿易不均衡問題は前年に引き続き比側の重要な関心事となつた。かかる貿易インバランスを背景に懸案となつていた通商航海条約改定交渉は,79年1月に第6次交渉が行なわれたが交渉は妥結の方向に向つた。また租税条約締結交渉も78年6月に第4次交渉が行われたが妥結するに至らなかつた。
(ニ) シンガポール
シンガポールとわが国の間には,わが国側における大幅な輸出超過という貿易上の不均衡の問題はあるものの,日本からの投資が順調なこともあり,両国間の関係は極めて良好である。ここ数年来の懸案であつた日本・シンガポール合同技術訓練センターについても両国間で協力の概要についての合意がみられ,実現に向つて進み出している。
78年における両国間要人の往来としては,5月及び7月に河本通産大臣及び牛場対外経済担当大臣(いずれも当時)がシンガポールを訪問,シンガポール政府要人と会談を行い,両国の友好親善関係の一層の強化が図られた。
(ホ) タ イ
園田外務大臣の公式訪問(6月)クリアンサック首相の訪日(79年1月)をはじめ官民各層の緊密な交流を通じて日タイ間の相互理解と協力は一層深まった。特に「ク」首相の訪日は,大平内閣成立後初の公賓であり,インドシナ情勢を中心とする東南アジア情勢などにつき大平総理大臣,園田外務大臣と意見交換を行うとともに,わが国は,新農村開発計画を含む第6次円借款の意図表明を行つた。また,両国の貿易不均衡問題(78年約6億8,000万ドルのわが国黒字)については,上記「ク」首相訪日の際双方が本問題の長期的見地からの解決に向け努力する旨合意され,わが国からは79年3月輸入促進ミッションが訪タイし,所要の成果を挙げた。
(へ) ビ ル マ
78年においては,日緬関係は引き続き着実な進展を見せた。特に77年の福田総理の訪緬以来懸案となつていた産業視察団(9月)及び文化使節団(11~12月)の訪日が実現し,またわが国から牛場対外経済担当大臣(当時)が訪緬(7月)するなど両国間の相互理解が一層増進された。他方,経済協力の分野においては,商品借款(旧4プロジェクト用部品・原材料及びシリアム製油所拡張計画のための機械設備並びに一般商品)135億円及び河川輸送増強計画に協力のための円借款27.5億円の交換公文が締結されたほか,一般無償援助として総額32億円(生物医学研究センター,地域短期大学職業訓練用各機材,橋梁建設計画のための小形捧綱及び学童制服用繊維の供与)及び食糧増産援助として総額19億円(肥料及び農業用機材)が決定された。
<要人往来>
インドネシア
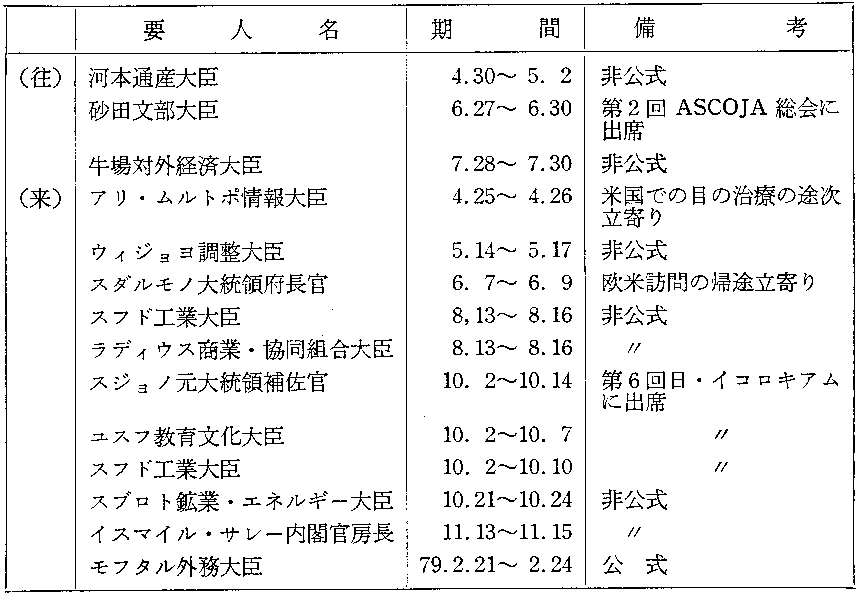
<要人往来>
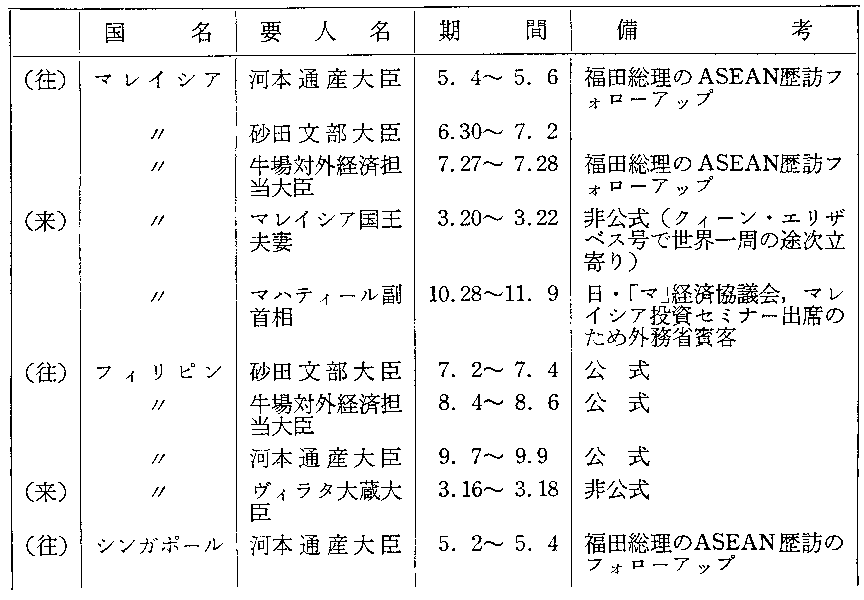
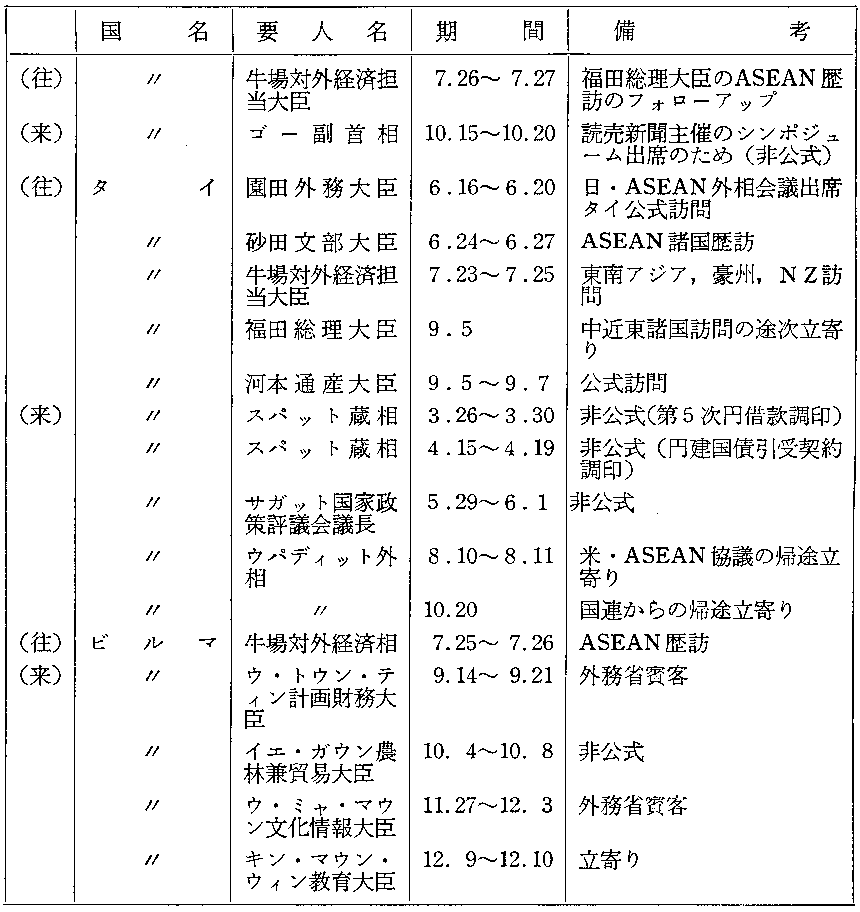
<貿 易>
(1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年増加率%)
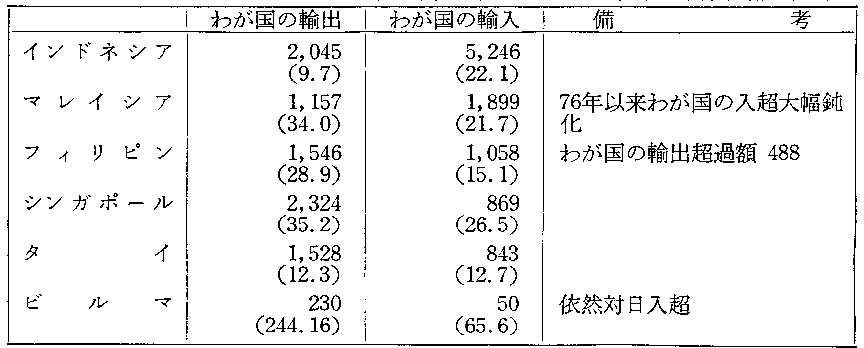
(大蔵省通関統計)
<民間投資>
(単位:百万ドル)

<経済協力(政府開発援助)>
(1978暦年;単位:百万円,人)
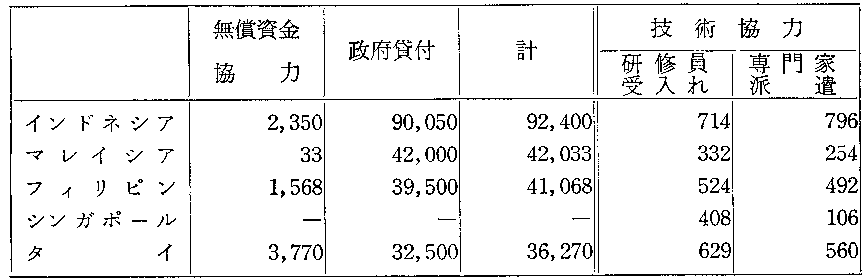
(イ) ヴィエトナム
(a) 内 政
レ・ズアン党書記長以下の党政治局員の顔振れには変化なく,78年2月,ヴォ・チ・コン副首相の農業大臣兼任が解かれ,その他林業大臣などの更迭がみられたものの,指導体制全般には大きな変化はなかつた。
南部ヴィエトナムにおいては,商工業,農業部門の社会主義改造が強力に進められ,私営資本主義的商工業の廃止(3月),農村搾取階級排除のための農地調整,などの措置がとられた。
79年2月の中国・ヴィエトナム武力紛争の発生に伴い同年3月,全国総動員令が発令され国内体制の強化が図られるに至つた。
(b) 外 交
最大の問題は中国との対立,武力紛争であつた。
78年4月以降表面化したヴィエトナム在住華僑の帰国問題を契機として,中国との関係が急激に悪化し,在中国ヴィエトナム総領事館(広州,南寧,昆明)の閉鎖(6月),中国の対ヴィエトナム援助の全面停止(7月)へと発展した。
華僑問題解決のためハノイで両国外務次官級会談が開催(8月~9月)されたが,何らの成果も上げ得ないまま中断され,他方,中越国境における紛争件数は増加の一途をたどり,両国間の対立は一層深刻化した。
この間,ヴィエトナムは6月コメコンに加盟したが,11月にはソ連との間に友好協力条約を締結し,ヴィエトナムの対ソ接近姿勢が明確に打ち出された。
79年1月に入つて,中国ヴィエトナム国境方面への中国軍兵力の増強,国境方面の情勢緊迫化がしきりに伝えられたが,2月17日中国は国境地帯におけるヴィエトナムの敵対行動に対する「自衛の反撃」としてヴィエトナム領に進攻した。
ヴィエトナム領国境地帯では激しい戦闘が展開されたが,同進攻を「限定作戦」とする中国側は3月5日撤退開始を発表し,同16日に撤退完了を発表した。その後,両国間には,両国関係の正常化,国境問題解決などのための外務次官級会談の開催に向つて接衝が続けられた。
またカンボディアとの関係にも大きな変化がみられた。78年を通じカンボディアとの国境紛争は継続したが,12月ヴィエトナムが全面的に支援するカンボディア救国民族統一戦線が樹立された。その後ヴィエトナム軍の深い関与のもと大攻勢が開始され,カンボディア人民共和国の成立が宣言され,79年2月ファム・ヴァン・ドン首相一行のヴィエトナム代表団はプノソペンを訪問し,ヴィエトナム・カンボディア平和友好協力条約が締結された。
他方,ヴィエトナムのASEANに対する外交は引き続き積極的に進められた。
7月にファン・ヒエン外務次官がわが国訪問のあとオーストラリア,ニュー・ジーランド及び東南アジア諸国を訪問したが,その後,ファム・ヴァン・ドン首相がタイ,フィリピン,インドネシア(9月),及び,マレイシア,シンガポール(10月)を歴訪した。
ドン首相の訪問においては各国との間に,独立・主権・領土保全の尊重,などの原則に基づき,内政に干渉せず,直接・間接の破壊活動を行うことなく,問題の平和的解決により両国関係を発展させるなどの趣旨を盛り込んだ共同声明が発出され,タイとの間においては,郵便通信協定の締結をみた。
米国との関係においては,7月わが国などを歴訪したファン・ヒエン外務次官が米越関係正常化について「ヴィエトナムの戦後復興に対する協力などの前提条件を一切付さない」旨言明し,また9月には,ニューヨークにおいて国連総会出席のグエン・コ・タック・ヴィエトナム外務次官とホルブルック米国務次官補との間に話し合いが行われたが,その後ヴィエトナム・カンボディア武力紛争の激化,越難民の大量流出などの問題もあり交渉は中断されたままである。
(c) 経済情勢
78年の優先課題として,食糧,消費物資,輸出産品の増産などが謳われていたが,77年の冷害,かんばつ,台風などの自然災害による米作不振に続いて,78年も秋に大洪水に見舞われたため,78年の食糧生産は,目標(籾換算1,600~1,650万トン)を300万トン下まわるに至つたといわれる。
連続する自然災害がもたらした食糧生産の不振はヴィエトナムの国内経済にとつて大きな問題であるが,こうしたところから,79年の国家計画においても,農業生産,とくに食糧生産の増強が第一の任務とされている。
他方,5月には,南北経済の統一,国内経済交流拡大を図るため南北通貨の統一が行われた。
(ロ) カンボディア
(a) 内 政
ポル・ポット共産党書記兼首相を中心とする指導体制は,その独自の国造りを図つてきたが,ヴィエトナムとの関係については,77年末の外交関係断絶以降悪化を続けた。12月2日,ヴィエトナムの全面的支援を受けたカンボディア救国民族統一戦線の結成,12月25日ヴィエトナム軍の深い関与の下大政勢が開始され,1月にはプノンペンの陥落(7日),カンボディア人民革命評議会の設立(8日),カンボディア人民共和国の樹立が宣言(10日)された。以後,ヘン・サムリンを議長とする「人民革命評議会」は,プノソペンはじめ国内の主要都市,幹線道路及びヴィエトナム国境地帯などの地域を掌握したのに対し,民主カンボディア政府側は,主にタイ国境地域のジャングルや山岳地帯を根拠地としてゲリラ戦を展開している。
(b) 外 交
(i) 民主カンボディアはトウ頴超中国全人民代常務委員長(1月),汪東興副主席(11月)の「カ」訪問,イエンサリ副首相の国際会議出席の途次の中国立寄りなどをはじめ,中国との関係強化を図る一方,越との対決姿勢を強めていつた。また諸外国との交流を徐々に拡げ,在中国の各国大使による信任状捧呈のための訪問のほか,チャウシェスク ルーマニア大統領(5月)をはじめ各国の要人,使節団,ジャーナリストなども相次いでカンボディアを訪問した。更にイエン・サリ副首相は,国連軍縮総会(6月)非同盟外相会議(7月),国連総会(10月)に出席しユーゴースラヴィア及びルーマニア(7月),フィリピン,インドネシア(10月)を訪問した。79年1月プノンペン陥落に先立ち北京へ移つたシアヌーク殿下は,民主カンボディア政府を代表し同月国連での緊急安全保障理事会に出席した。
(ii) 他方,救国民族統一戦線側は,プノンペンを訪問した越代表団との間に2月18日に平和友好協力条約を締結した。次いで3月スパヌウォン ラオス大統領がプノンペンを公式訪問し,インドシナ3国間の連帯強化,反中国姿勢を明確にした共同声明が22日発表された。カンボディア人民革命評議会を承認している国はソ連及び東欧諸国など17ヵ国であり(54年3月31日現在)ヴィエトナム,ラオス,東独,キューバの4ヵ国がプノンペンに大使館を開設した。
(c) 経 済
77年のカンボディアの生産計画は全国的に大成果を達成,特に農業部門では,党政府の設定した計画を100%達成した旨の発表が行われ,78年はヴィエトナムとの国境紛争,またメコン河大洪水により,生産活動は阻害されたが,民主カンボディア政府は,カンボディアの抱える諸問題はカンボディア自身で解決可能であり,援助を仰ぐ必要はないとしていた(9月27日ポル・ポット首相演説)。貿易については,統計は発表されておらず不明であるが,77年に西側諸国からの輸入が前年の皆無から2,000万ドル近くに急上昇したが,78年は,逆に大幅に減少した模様である。
(ハ) ラ オ ス
(a) 内 政
人民共和国成立後3年を経たラオスでは,カイソン人民革命党書記長兼首相を中心とする指導体制が堅持され,越との連帯強化,ソ連などの社会主義諸国との協力,国内の社会主義化を進めた。しかし経済面では3ヵ年経済開発計画(78~80年)の初年度であつたが,76,77年の旱魃に続いて78年もラオスは稀有のメコン河の大洪水に見舞われ農業生産の不振から,開発計画の発足はつまづく結果となり,かかる食糧難を背景として新体制になじめずメコン河を渡河するタイヘの難民の数は依然高水準に達した(月平均約2,000人,在タイラオス難民約13万人)他方,国内治安面では山岳少数民族など反政府運動の掃討が進められ,11月には,反政府メオ族の根拠地は一掃されたと伝えられた。なおラオスに於ける外交官を含む外国人の滞在規制も強化された。
(b) 外 交
非同盟・中立・中ソ等距離外交を標榜してきたラオスは越・ラオス友好条約締結1周年における越支持の明確化(7月),カンボディア救国民族統一戦線の結成支持(12月),ヘン・サムリン政権の早期承認(1月),中越武力衡突に際しての越支援の表明(79年2月)スハヌウォン大統領のプノンペン訪問(79年3月)など越更にはカンボディア(救国民族統一戦線)との連帯を強化した。他方中国との関係は,78年を通じ著るしく悪化するには至らなかつたが,ラオス政府は,79年3月にはラオス北部国境における中国軍の集結を非難する政府声明の発出,中国の道路建設要員の引揚げ要求などにより対中対決姿勢を強めた。またソ連との関係では,実務レベルの代表団の相互訪問などを通じ協力が強められた。チャウシェスク ルーマニア大統領が外国元首としてはじめて5月ラオスを訪問した。ASEAN諸国特にタイとの関係は77年11月のタイのクリアンサック内閣の成立とともに好転し,シパスート外相タイ訪問(3月),ウパディット外相のラオス訪問(6月)に続き79年1月及び4月にはクリアンサック首相及びカイソン首相の相互訪問が実現し両国関係の著しい改善が図られたほか,5月シパスート外相がマレイシアを訪問した。西側諸国との関係では,2月及び6月に非友好的活動をしたとの理由で在ラオス仏大使館員を追放したことから仏との関係は悪化し,7月両国の大使館がそれぞれ閉鎖された。米国との関係は,8月米上院議員団(モンゴメリー団長)が来訪しヴィエトナム戦争で死亡した米人4遺体引き取り,また10月ホルブルック国務次官補がラオスを訪問したが,両国関係には大きな進展は見られなかつた。
(c) 経 済
ラオスは食糧の自給自足を第1の経済目標とし(食糧100万トン)78~80年の3ヵ年経済開発計画の第1年目にこれを達成することを予定していたが,上述の如くメコン河の大洪水によつて未達成に終つた(もみ生産で達成率89%)。ただし1,600の農業協同組合が増設され,農民の16%が参加したと伝えられる。ラオス経済全体としては依然として生産の不振(国営企業の稼働率30%)物資不足,国際収支の大幅赤字という状況下にあるが,78年には政府の財政支出運営が改善された結果,新体制成立以後のインフレは抑制され,自由市場価格は初めて下落した。また11月,ナムグム発電所の第2期工事が完成したことにより,今後タイに対する電力輸出供給量の大幅な増加が期待されており,更にはまた,木材の輸出振興などのため5月に対米ドルレートが200キープから400キープに切り下げられるなど,今後の経済安定のために積極的な要因も見られた。
(イ) ヴィエトナム
ヴィエトナムとの関係では,ヴィエトナムの統一以来の懸案であった債権債務問題が4月解決され,新たな経済協力として,40億円の無償援助(4月)及び100億円の円借款供与(7月)の交換公文がそれぞれ締結された。また,ファン・ヒエン外務次官(7月),及びグエン・ズイ・チン外務大臣(12月,レ・カッタ国家計画委副議長及びヒエン次官など同行)が外務省賓客として訪日し,インドシナ情勢及び2国間問題などにつき意見交換が行われ,日越間の相互理解が増進された。なお,越の水害に際しては,1億円の緊急災害援助を行った(10月)。
(ロ) カンボディア
わが国は,佐藤駐中国大使を兼任発令し,同大使一行は9月に信任状捧呈のためカンボディアを訪問した。また,カンボディア側からはイエン・サリ副首相が6月及び10月に,国連からの帰途日本に立ち寄つた。
(ハ) ラ オ ス
53年度8億円の無償資金援助を行い,また10月には,カムパイ・ブッパー外相臨時代理が国連よりの帰途訪日した。
<貿 易>
(1978年;単位:千ドル,( )内は対前年増加率%)
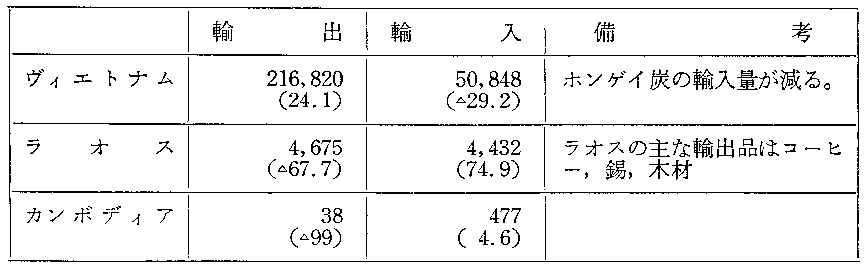
(大蔵省通関統計)
<経済協力(政府開発援助)>
(1978年;単位:百万円,人)
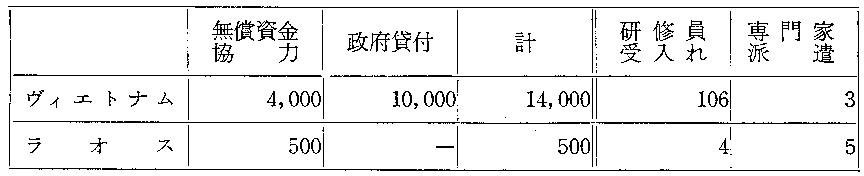
(約束額ベース) (DAC実績ベース)
(イ) 域内関係
インド亜大陸をとりまく国際情勢に大きな変化が見られた中で,インドのジャナタ党政権は77年に引き続き善隣外交を推進し,かなりの成果を上げた。
インド・パキスタン関係は,ヴァジパイ インド外相のパキスタン訪問(2月),懸案のサラール・ダム問題の解決(4月),領事館相互開設の決定などにより,両国関係正常化は一層の進展をみせた。
インド・ネパール関係は3月に懸案の貿易・通過協定問題が解決し,4月にはビスタネパール首相が訪印,10月にはヴァジパイ外相がネパールを訪問するなど両国関係は良好に推移した。
また,インド・スリ・ランカ関係は10月にジャヤワルダナ スリ・ランカ大統領が訪印し,一層強化された。
インド・バングラデシュ関係も良好であつた。
(ロ) イ ン ド
(a) 内 政
発足後2年目を迎えたジャナタ党デサイ政権は種々の問題を抱えつつも,基調としては一応安定した1年であつた。
ジャナタ党は2月の地方選挙及び4月の上院一部改選において,その勢力を全国,特に南部諸州に拡大することを得ず,全国政党たり得るにはまだ道が遠いことが明らかになつた。他方11月及び12月北部諸州で行われた補欠選挙ではジャナタ党候補が勝ち,北部では依然ジャナタ党勢力の強いことが示された。
ジャナタ党については党内の意見対立が表面化したことが目立つたが,かかる党内の内紛は,党のイメージを損つている。
他方野党陣営はコングレス党が1月,2派に分裂するなど混迷状態が続いた。ガンジー夫人は11月のチクマガルールの補選において当選したが,翌12月に入り,非常事態宣言下に議会の活動を妨害したとのかどにより,下院によつて議席を剥奪され,同夫人の中央政界復帰は頓挫した。
(b) 外 交
「純正非同盟」と「善隣友好」の2つの政策を旗印として2年目に入つたインドの外交は,周辺諸国における急激な政治環境の変化にも拘らず,着実にその幅を拡大した。
印米関係では,1月のカーター大統領訪印と6月のデサイ首相訪米を通じて両国間の信頼関係が回復された。
対ソ関係では,5月のラーム国防相,9月のヴァジパイ外相の訪ソにより円熟した関係への移行努力が行われ,経済,貿易及び軍事援助面における協力関係の維持強化が図られた。
対中関係では,77年の貿易再開に引き続き,3月の王炳南の訪印,5月のインド人ジャーナリストの訪中などがあり,10月には両国関係改善への第1歩としてヴァジパイ外相の訪中が予定されていたが,同外相の健康上の理由により79年2月に延期された。
(c) 経済情勢
電力・石炭の不足,雇用問題,労働争議の頻発,輸入の急増と輸出の不振による貿易収支の悪化など問題はあるも,食糧穀物生産は77年の1億2,500万トンを越す史上最高の収穫を上げ,鉱工業生産も対前年比で8%増の政府目標に近い水準に伸び,外貨準備も60億ドルに達するなど,基本的には好調であつた。しかし,デサイ政権が打ち出した農村開発,中小企業振興重視の経済政策は,未だ具体的成果を挙げるには至らず,経済政策の充実が79年以降の課題として残された。
(ハ) パキスタン
(a) 内 政
78年8月,ハック戒厳令総司令官(9月に大統領に就任)の下に,すべて文民よりなる連邦内閣が発足したものの,ハック軍事政権が約束していた総選挙の実施と民政移管は行われず,実質的な軍事政権体制には大きな変化はなかつた。
78年の内政面の最大の問題はブットー裁判であった。3月,ラホール高裁においてブットー前首相は74年11月のアーマッド・ハーン殺人事件に関与したとして死刑判決を受けた。同人は直ちに最高裁に上告した。最高裁は,明けて79年2月,上告を棄却し,3月には再審請求も却下され,4月4日処刑が行われた。
(b) 外 交
ハック大統領は,1月と9月にイラン,4月にサウディ・アラビアを訪問,また6月にはパキスタンと中国を結ぶカラコラム・ハイウェイの開通式に出席するため耿飈中国副首相が訪パするなど,中近東諸国と中国との友好関係の維持というパの外交路線に大きな変化はみられなかつた。
米国との関係では,パの仏よりの核燃料再処理プラント購入問題をめぐる意見の対立から,過去1年停止されていた米国の対パ経済援助が9月より再開された。
インドとの関係では2月にヴァジパイ外相が訪パし,4月には懸案となつていたサラール・ダム問題が解決した。
(c) 経 済
政治・経済面で混乱を極めた77年のあとを受けた78年のパキスタン経済は,ここ数年の停滞を脱し,GNP成長率9.2%を達成した。これは,綿花生産が前年にくらべ大幅に回復したことによる農業面での回復,繊維工業が依然停滞したものの,食用油,セメント,砂糖などの工業部門の好調によるものであった。
貿易収支は,輸入増勢が依然衰えなかつたため,14.2億ドルの赤字を記録したが,海外労働者よりの本国送金が11.8億ドルにのぼつたため,経常収支赤字幅は4.77億ドルにとどまつた。
(ニ) バングラデシュ
(a) 内 政
78年のバングラデシュ政情は,民政移管及びゼアウル・ラーマン大統領政権の長期化への動きが顕著であつた。ゼアウル大統領の提唱によるJAGODAL(民族主義者民主党)の創設及び同党を中核とする政治戦線"Nationalist Front"の結成に続き,同大統領は6月,大統領選挙を行い,これに大勝するとともに,内閣に代わる役割を果してきた政策評議会を廃止し内閣を組織した。更にゼアウル大統領は9月,自らが党首となつてBNP(バングラデシュ民族主義者党)を設立し,上記JAGODALもこれに加わり,来たるべき総選挙対策及び選挙後の国会掌握への地盤を固めた。総選挙は2度延期された後,79年2月に実施されBNPは総議席300中207議席を獲得した。
(b) 外 交
77年にインド亜大陸諸国との関係改善を果したバングラデシュは,78年には全方位外交を目指す活発な訪問外交を展開した。すなわちゼアウル大統領は3月にアラブ首長国連邦,4月に日本,7月にインドネシア,9月に北朝鮮,シンガポール,10月にトルコ,ルーマニア,11月にユーゴースラヴィアを公式訪問した。また国連など国際機関においても活発な活動を行い,バングラデシュは11月,国連安保理非常任理事国に選出された。
(c) 経済情勢
78年のバングラデシュ経済は農業部門,工業部門ともに順調な伸びを示したが,工業部門の生産水準は未だ独立前の水準を若干上回つた程度である。また,貿易収支は,活発な国内経済活動を反映して輸入が増えたため,その赤字幅を一層拡大した。
(ホ) スリ・ランカ
(a) 内 政
施政2年目を迎えたジャヤワルダナ政権は,議会で圧倒的多数を占める与党勢力を背景に,国内政治の長期的安定を狙いとする基礎体制作りに全力を挙げた。77年10月に可決された憲法改正法により,2月には行政権を有する大統領制が施行され,その初代大統領にジャヤワルダナ自らが就任し,9月には新憲法(スリ・ランカ民主社会主義共和国憲法)が制定された。同憲法により国会議員選挙制度が従来の小選挙区制から比例代表制に改められ,将来における極端な政権変動の可能性は小さくなつたといえよう。
(b) 外 交
ジャヤワルダナ政権は,「真の非同盟中立」を標榜し,非同盟会議議長国として5月の調整ビューロー会議(於ハバナ),7月の外相会議(於ベオグラード)などを通じ,穏健派諸国と急進派諸国との対立の中で非同盟諸国の分裂回避に大きな役割を果たした。他方,経済開発の必要上欠くべからざる外国援助確保という観点から,わが国を含む自由主義諸国との関係を一段と強化するとともに,隣国インドとの関係も78年10月のジャヤワルダナ大統領訪印,79年2月のデサイ インド首相の訪スなどを通じ,着実に緊密化した。
(c) 経済情勢
78年のスリ・ランカ経済は,77年に引き続き史上最高の豊作となつた米作を中心とする農業生産の好調に加え,鉱工業・建設部門も生産性回復の兆をみせたため,68年以来最高の経済成長率8.2%を記録するなど,やや好転した。
ジャヤワルダナ政権は,77年同様,開発重視の経済自由化政策を推進しているが,物価騰貴(消費者物価は約10%上昇)や失業問題など,国民生活に直結する難問は未解決のまま残されている。
(ヘ) ネパール
(a) 内 政
ビレンドラ国王の親政体制は7年目をむかえ,旧ネパール会議派を中心とした反王制勢力の沈滞を踏まえ,親政体制安定化の努力が行われた。こうした情勢のもとで政治犯の釈放,投票による選挙の復活など一連の自由化・統制緩和策を推進し,民主的政治環境の醸成につとめた。また,国王・王妃の年3回に及ぶ地方巡察旅行,国民帰郷運動の推進などを通じ王家と地域住民との連携をはかりパンチャーヤット制度を拡充強化しつつ,王制の基盤固めに努力した。
(b) 外 交
ネパールは国王・王妃がバングラデシュ,日本を,ビスタ総理がインド,中国を各々公式訪問し,ネパール平和地帯宣言を基軸とした中立非同盟外交を積極的に推進した。中印両隣国との関係も,ヴァジパイ外相やトウ小平副首相の訪ネにみられるように良好に推移した。
(c) 経済情勢
78年の農業生産は,77年に引き続く異常天候のため対前年度比約2%の減産を記録し,2年連続のマイナス成長を記録した上,物価も上昇した。国際収支面でも,貿易収支の赤字幅拡大,観光収入,外国援助の伸び悩みにより,総合収支でも若干の赤字を記録した。
(ト) モルディヴ
(a) 内 政
任期満了を迎えたナーシル大統領の辞意表明に伴い,78年6月,国会により次期大統領候補に指名されたガユーム運輸相は,7月に実施された信任投票において国民の圧倒的多数により信任された結果,11月11日新大統領に就任した。ガユーム政権は,民主的政治環境の醸成に努めている。
(b) 外 交
モルディヴ近海の豊富な漁業資源と同国のインド洋上に占める戦略的位置に鑑み,開発援助を中心として諸外国の働きかけが活発化した。ガユーム政権は,非同盟中立を基本政策としつつ,積極的に外交に取り組む姿勢を示し,一時冷却していたスリ・ランカとの関係も改善されつつある。
(c) 経済情勢
漁船の動力化,海運業及び観光業の開発促進などにより経済の近代化に進展がみられた。ガユーム政権は,国民大衆のための経済開発に努力を払つた。
(チ) ブータン
(a) 内 政
国王・皇太后を中心とした王家は,国民議会とインドとの支持を背景に,全国的に均衡のとれた開発計画を推進し,国内治安の維持と王制の基盤強化につとめた。
(b) 外 交
外交面においては,インドのジャナタ党政権の善隣友好外交に支えられ,従来インドとの間で有していた政府代表部を大使館に昇格させ,またネパールへ貿易使節団を派遣したほか,外国人入国制限を緩和し,観光客の誘致につとめるなど,徐々に門戸を開放する動きが見られた。
(c) 経済情勢
LLDCであり,内陸国でもあるための経済的悪条件をかかえ,インド,コロンボ・プラン,UNDPなど国際機関からの援助を得て第4次5ヵ年計画を推進し,農業・運輸通信などインフラ部門の整備に努力した。
78年は南西アジア諸国からの要人の訪日が活発化した年であった。
1月,ヘグデ下院議長を始めとするインド国会議員団がわが国衆・参両院議長の招きで訪日し,わが国国会議員との親善を深めた。
4月にはゼアウル・ラーマンバングラデシュ大統領が国賓としてわが国を訪問し,福田総理と2回にわたり会談を行い国際情勢及び両国関係につき意見交換を行つたほか,100億円を限度とするプロジェクト借款の供与につき合意をみるなど両国の友好関係は大きく増進された。
翌5月にはビレンドラ ネパール国王が国賓としてわが国を訪問し,両国の友好関係は大きく促進された。その際行われた両国外相会談で,わが国の78年度対ネパール無償援助額23億5,000万円がプレッジされた。
8月にはヴァジパイ インド外務大臣が外務省賓客としてわが国を訪問し,第1回日印外相協議が開催された。
また,10月にはイスラマバードで第5回日本・パキスタン事務レベル定期協議が開催された。
<要人往来>
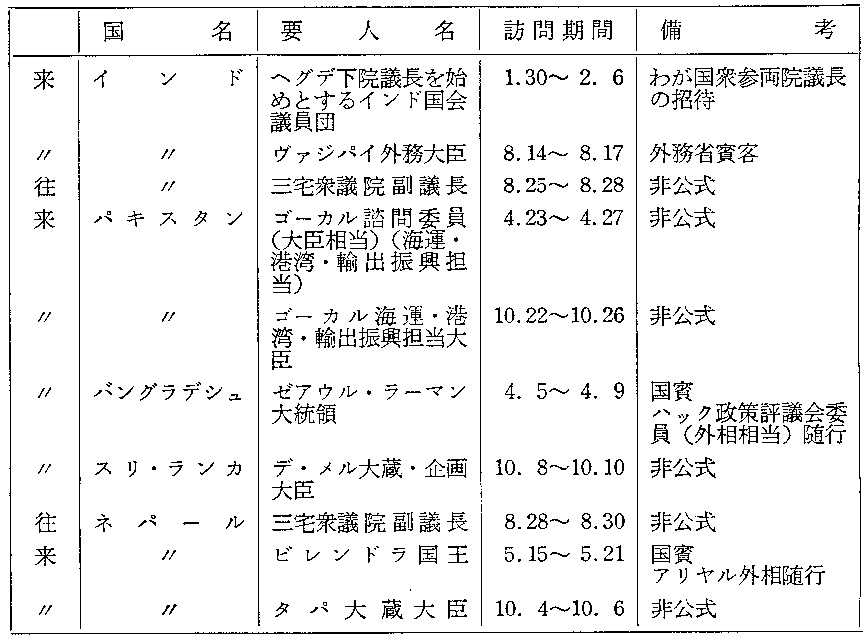
<貿易関係>
(1978年;単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率)
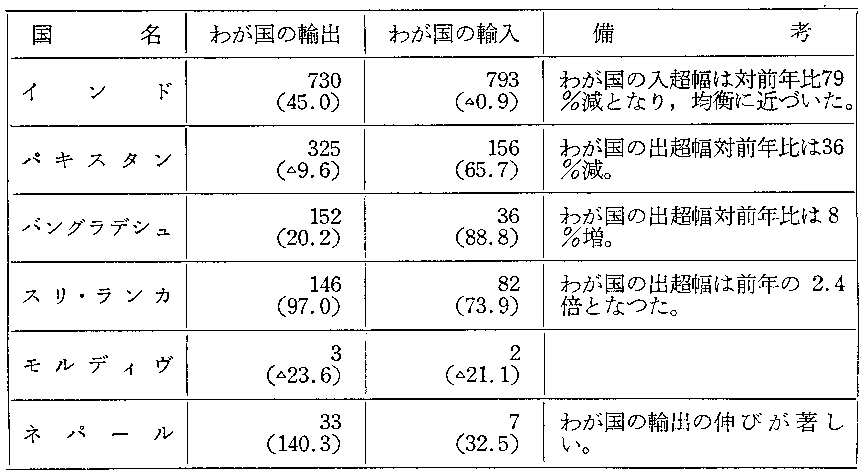
(大蔵省通関統計)
<民間投資>
(単位:百万ドル)
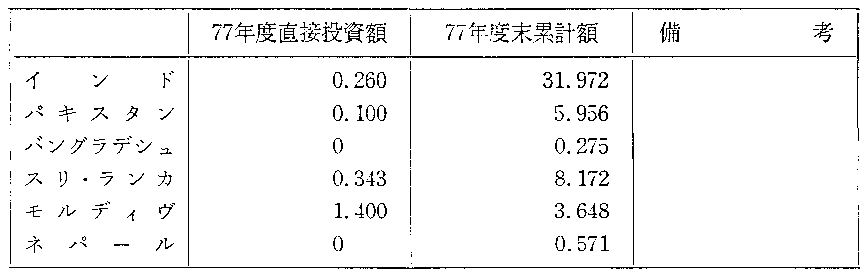
(日銀許可額ベース)
<経済協力(政府開発援助)>
(1978年;単位:百万円,人)
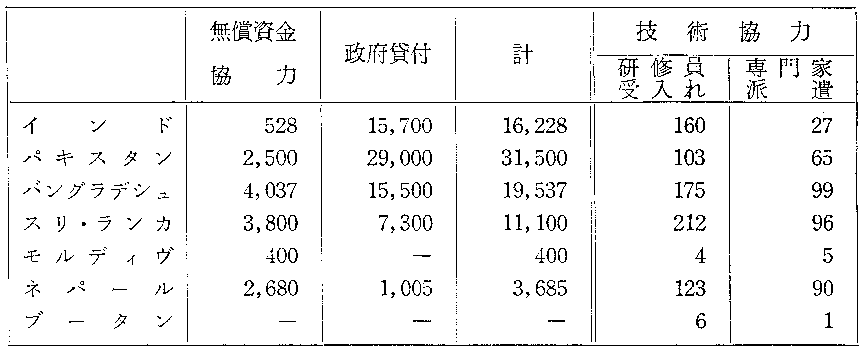
(約束額ベース) (DAC実績ベース)
(イ) 内 政
77年6月19日の第9期人民大会議選挙においてツェデンバル人民大会議幹部会議長が再選されツェデンバル指導体制は大きな異動もなく引き続き維持されている。
(ロ) 外 交
モンゴルは78年11月1日現在,85ヵ国と外交関係を有するが,78年もソ連を積極的に支持する外交政策を堅持している。他方,中国との関係では貿易,国際列車の運行などミニマムの実務的関係を除き,みるべき進展を示していない。
(ハ) 経済清勢
農業は77年に引き続き不振であつたが,牧畜業は目標を上回る成果があつたとされている。工業総生産は前年比5%増を達成し,目標を0.5%上回つた。
77年3月に署名された「経済協力に関する日本国とモンゴル人民共和国との間の協定」に基づきカシミア・ラクダ毛加工工場建設が始まつたが(完成は81年を予定),これはモンゴルの経済建設に寄与すると同時に今後の両国間友好関係の促進に多大の貢献をなすものと期待される。このほか,わが国政府はモンゴル政府に対し医療機材の贈与,医療研修員の受入れなどを行つた。文化面では「日本・モンゴル文化取極」に基づく交流が引き続き行われた。
<要人往来>
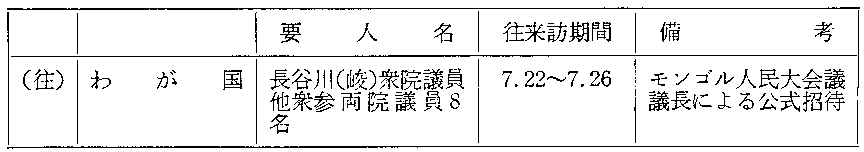
<貿 易>
(1978年;単位:千ドル)
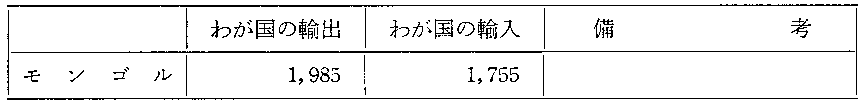
(通関統計)
(イ) 政 治
(a) 78年11月までとなつていたマクルホース総督の任期は80年4月まで延長され,香港の行政は安定しているが,他方中国からの入境者の著しい増加,ヴィエトナム難民の滞留が深刻な問題となつている。
(b) 中国との関係については近代化を進める中国が香港の重要性を再認識する姿勢を示したのを受けて,香港・中国関係は良好に推移した。すなわち9月には例年の新華社香港支社主催の国慶節祝賀レセプションに初めて総督が出席し,また11月に行われた総督施政方針演説では,香港・中国間の友好・協力関係が強調された。更に,12月には中国の李強対外貿易相が閣僚級要人としては初めて香港入りした。これらと並行して,香港・広州間に航空路,フェリー便が開設され,また,広東省からの香港に対する給水量増量についても合意がみられた。
(ロ) 経 済
78年の香港経済は輸出増大(前年比20%増)及び内需の高まりを主要因としてGDPで実質10%程度の成長を示した。
78年における香港とわが国との関係は,6月の園田外務大臣の一時立寄り,9月の福田総理大臣の一時立寄り,更に11月のマクルホース総督の来日により一段と深まつた。香港の貿易量全体のうち,わが国との貿易量は米国に次ぎ第2番目(15.2%)であり,わが国は香港の貿易において重要なパートナーとなつている。12月にはわが国・香港双方において経済界トップレベルのメンバーによる日本・香港経済委員会が発足した。
(1) インドシナ難民の増加は近隣のタイ,マレイシア及びその他の東南アジア諸国に深刻な経済・社会上の負担を課しており,今やこれら諸国の内政及び外交上の極めて重要かつ緊急な課題となつた。
75年のインドシナ3国の政変から79年3月末までの海上難民(ほとんどがヴィエトナムから)の総数13.2万人のうち7.3万人が一時滞在国(うち5.2万人がマレイシア)に残留しており,また,同期間の陸路難民(ほとんどがラオス人)の総数22.0万人のうちタイに14.5万人が残留している。
かくしてこの問題は,人道上放置しえないのみならず,周辺諸国の社会的・経済的負担を増大させ,アジア・太平洋地域の不安定要因となるに至つた。
(2) わが国としては,この問題が上記の如くこの地域の深刻な政治問題となつたことに鑑み,78年度において次の如き措置をとり,この問題解決に対する貢献を行つた。
(イ) 資金協力
国連難民高等弁務官(UNHCR)事務所のインドシナ難民救済計画に対する財政的支援78年度における同計画に対するわが国の拠出額は1,023万ドルであつたが,これは米国に次いで第2位の額である。
(ロ) 難民の一時受入れ
わが国は,南シナ海などの洋上において外航船舶に救助され,同船舶の本邦入港に伴つて到来するヴィエトナム難民(いわゆるボート・ピープル)に対し,人道的見地から一定条件の下にその一時上陸を認めているが,78年12月にその入国条件の一部緩和を行つた。
わが国が一時的に受け入れた難民の数は,75年から79年4月末までに2,000名強にのぼつている(国連統計)が,そのうち約1,500名が既に再定住のため第3国(3分の2は米国)に出国しており,約500名が残留している。
(ハ) 一定条件を満たす難民の本邦定住許可
わが国は78年4月28日の閣議了解において,日本に一時滞在するヴィエトナム難民のうち,次のいずれかの条件を満たす希望者に対して日本への定住を許可することとした。
(a) 日本人または日本に在留し安定した生活を営んでいる外国人の配偶者もしくは親子(養子を含む)であること。
(b) 適格な里親があること。
(c) 安定した職業につき,かつ確実な身元引受人がいること(当該者の配偶者及び親子を含む)。
78年9月にはこの条件に該当するものとして1家族3人の定住が初めて決まつた。
(3) その後,インドシナ難民問題の深刻さが度を増すに伴い,対東南アジア外交上及び人道上,わが国として従来の諸措置に加え,更に抜本的対策をとる必要性が増し,このため79年2月に臨時の措置としてアジア局に東南アジア難民問題対策室を設けて鋭意検討を行つている。