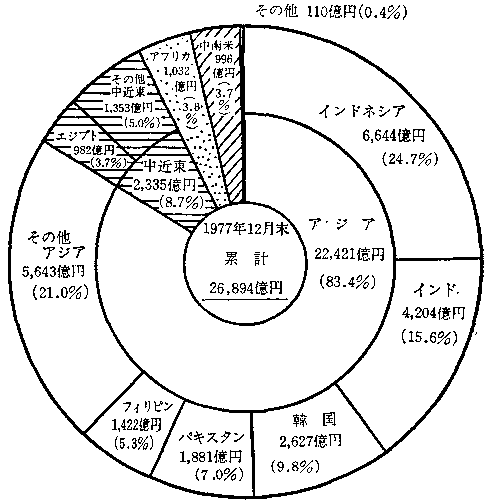
-資 金 協 力-
第3節 資 金 協 力
開発途上国に対する資金協力のうち,相手国政府に返済義務を課さない,いわゆる2国間無償資金協力は,技術協力を除く一般無償援助(一般の無償資金協力),食糧援助(国際小麦協定の一部を構成する食糧援助規約に基づき実施されるもの)及び77年度より新規に開始された食糧増産援助から成っている。なお,賠償・準賠償は76年度をもつて終了した。
2国間無償資金協力の目的は開発途上国の経済・社会の発展,住民福祉の向上及び民生の安定に寄与することにあり,わが国と開発途上国との友好関係の増進に大きな貢献をなしている。
わが国が77年において行った無償資金協力の支出額は約165億円である。これを前年の支出額約120億円と比較すると約38%の増加となった。
なお,食糧援助及び食糧増産援助は,いずれも大蔵省所管予算に所要経費が計上され,支出委任を受けた外務省がこれを実施している。
一般の無償資金協力は,一部の例外を除き外務省所管経済開発等援助費に計上される予算を外務省が支出することにより実施しているものであり,69年度に始まって以来,毎年開発途上国の社会開発関連分野を中心として拡充の一途をたどってきたが74年度以降は横ばいの傾向を示し,77年度は若干の漸増となっている。
本援助の具体的対象分野としては,医療・保健分野,教育・研究分野,農業分野,民生・環境改善分野,交通・運輸分野そして,近年わが国にとっても援助の重要性を増している水産分野である。
また,経済開発等援助費に含まれるものとして台風,地震,早越などの災害に見舞われた国に対する緊急の援助を実施するための災害関係援助及び文化面での援助を行う文化関係援助がある。
食糧援助は,ガットのケネディ・ラウンド(KR)関税一括引下げ交渉の一環として成立した国際穀物協定を引継いだ国際小麦協定の中の食糧援助規約に基づき,67年以降毎年1,430万ドル相当の米及び被援助国が希望する場合には農業物資を,食糧不足国に無償供与してきたものである。
わが国としては,開発途上国の食糧問題は基本的には農業開発により解決されるべきであるとの立場をとつているが,開発途上国の食糧問題の重要性は十分認識しており,食糧援助自体の必要性をも否定するものではないので米を含む食用穀物又は,受益国の要請により農業物資(肥料,農機具,農薬など)の形態で援助を行ってきた。なお,77年度より食糧増産援助が開始されたことにより本援助は77年度以降,事実上,専ら米を援助の対象としている。
本援助は規約上,海上輸送費などは含まない建前となっているが,被援助国の中には,これらがかなりの負担となり,財政上困難となることがあることにかんがみ,わが国は,これらの国に対しては,輸送費などの分野においても応分の協力を行っている。
本援助は,食糧生産の増大を急務としている開発途上国の食糧増産のための自助努力を総合的・計画的に支援し,今後深刻化が予想される食糧不足問題の解決に長期的に寄与することにより,開発途上国の経済・社会の発展と国民の福祉及び民生の安定に貢献することをその目的とし,77年度より新規に開始されたものである。
本援助の対象品目は肥料,農薬,農具,及び耕転機,トラクターなどの農業用機械であるが,わが国は,これら援助物資を相手国の具体的食糧増産計画などに基づき供与している。
政府直接借款とは,通常「円借款」と呼ばれている二国間政府借款(有償資金協力)であり,わが国政府開発援助の過半を占め,開発途上国への重要な協力手段となっている。
政府直接借款の供与実績(交換公文締結額)は74年に3,000億円台に達してから76年まで減少の一途をたどつてきたが,77年は3,807億円と76年実績2,342億円を約1,500億円(62.6%増)上回つた。この結果,わが国が政府直接借款を開始した58年から77年末までの供与額累計は2兆6,894億円となった。
77年の借款供与額の大幅な増加は主として(イ)77年6月に関係省庁間でディスバース促進のため新規借款の供与方針(注)を策定し,積極的に借款の拡大に努めたこと,及び(ロ)77年8月の福田総理大臣のASEAN諸国及びビルマ歴訪もあつてわが国にとつて重要な同地域への供与額が大幅に伸びたことなどによるものであるが,右増加は77年6月に終了した国際経済協力会議(CIEC)閣僚会議でわが国が意図表明した「今後5年間でわが国ODAを倍増以上に拡大する。」との国際約束実現のための第一歩といえよう。
しかしながら,平均供与条件については,条件のより緩和された債務救済が少なかったこともあり,グラント・エレメント(以下G.E.p.196の注参照)51.2%と前年(52.0%)をやや下回り,未だ国際水準に至つていない。
なお,わが国は上記会議で同じく意図表明した貧困国に対する特別援助措置(114百万ドル)の一環として,77年中にインドネシア及びスーダンに対し通常より緩和された条件で追加的に50億円を供与している。
(イ) 供与形態別
政府直接借款は供与形態上プロジェクト借款(発電所,道路,港湾,通信施設,化学肥料工場の建設などの個々のプロジェクトを対象に供与されるもの),商品借款(国民生活の維持に必要な基礎的物資や経済運営に必要な物資の輸入資金を補助する目的で供与されるもの)及び債務救済(過去に受入れた借款の債務負担が過重となり,著しく国際収支が悪化していると判断される場合に,その借款の支払い条件を緩和する,いわゆる債務繰延べ)の3形態に分類される。近年の形態別供与状況は図1のとおりである。
ディスバースメント促進のためのガイドラインの効果もあって,商品借款が前年の2.8倍と急増し借款全体に占める割合も16%から27%に高まつているが,依然としてプロジェクト借款がその大宗(72%)を占めている。なお,債務救済については,これまで主な対象国であつたインドの経済好転に伴い,同国への実施を見合せパキスタン1カ国となったため急減している。
(ロ) 地域別及び所得水準別
わが国は,従来より地理的,歴史的,経済的に密接な関係にあり,加えて1人当り援助受取額が他の地域のそれに比べて低いアジア地域を重点に借款を供与してきている。
しかし,近年わが国と中近東,アフリカ,中南米諸国との関係の緊密化及び世界的な規模での多角的外交の推進とのわが国外交の基本方針に沿って,アジア以外の地域への拡大にも努力している。
この結果77年は,図2のとおりシェアーではASEAN諸国を中心としたアジア地域が全体の78.2%と依然として大宗を占めているが,中近東,中南米及びアフリカ地域に対しても供与絶対額は著しい伸びを示した。
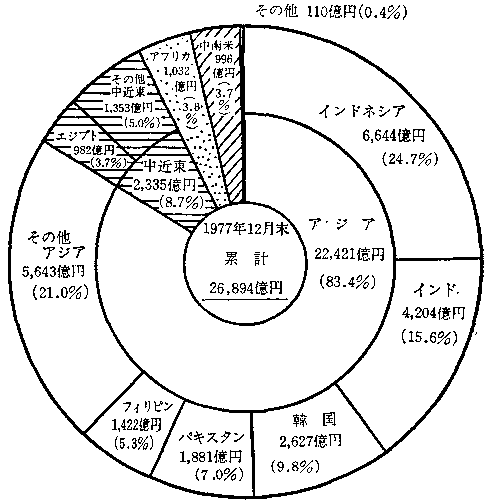
また,所得水準別では,図3のとおり中進国への供与量が増えているものの,依然として援助対象の中心であるより貧しい諸国(1975年の1人当りGNP520ドル以下)に対し全体の約8割を供与している。
なお,77年にはチュニジア,イエメン,ニカラグアの3カ国に対し,はじめてわが国の借款が供与され,この結果,同年末までのわが国の借款供与国は50カ国となった。
(ハ) 実施機関別
75年6月に輸銀と基金との業務分野の調整が行われ,継続案件などを除き75年7月1日以降の新規借款は全て基金が担当することとなった。その結果,基金への実施業務の一元化が一層促進されており,77年には94%が基金案件となっている。
(イ) 平均供与条件
77年の平均供与条件は図4のとおり全般的に条件の緩和が図られたにもかかわらず(あ)条件のより緩和された債務救済が前年の約1/5に減少したこと,及び(い)借款の量的拡大の一環として,条件がより厳しい中進国への供与割合が増えたため,全体としてはG.E.で51.2%と前年をやや下回っており,国際水準には程遠く,なお相当の条件緩和努力が必要とされる。
(ロ) アンタイイング(注)比率
わが国は,既に国際機関への拠出については全面的にアンタイド化しているが,政府直接借款についても74年6月に締結されたLDCアンタイイングに関するDAC了解覚書に従い,75年1月から新規にコミットする案件については原則としてLDCアンタイドで借款を供与する一方,ケース・バイ・ケースにて一般アンタイド借款を供与してきた。この結果,77年では図5のとおりLDCアンタイド借款が全体の76%を占め,タイド借款(いわゆる「ひもつき援助」)は前年の42%から17%と大幅に減少している。
なお,78年1月の日・米通商交渉の共同コミュニケでは「今後わが国の政府資金協力については一般アンタイドを基本方針として遂行する。」旨の意図表明が行われており,今後は従来のLDCアンタイド借款から更に進んでより調達先の開かれた一般アンタイド借款を中心とした借款のアンタイド化が促進されて行くこととなろう。
国際協力事業団による資金供給業務は,わが国民間企業などが開発途上地域などで行う経済協力に対する財政支援制度である。それは,政府ベースと民間ベースの経済協力の連携の強化及び資金協力と技術協力の結びつきの強化を図るものであり,融資対象事業が相手国の経済,社会の発展と民生の安定向上に資することを直接の目的としている。
国際協力事業団の資金供給の対象は,開発途上地域などの社会の開発並びに農林業及び鉱工業の開発に資する次の事業であつて,日本輸出入銀行あるいは海外経済協力基金からの貸付などを受けることが困難と認められることなどの要件を満たすものである。
(イ) 関連施設の整備
開発事業に付随して必要となる関連施設であつて,周辺地域の開発に貢献する施設の整備事業,例えば,道路,橋梁,港湾施設,上下水道,市場,学校,病院,公民館,教会,訓練所などである。
(ロ) 試験的事業
開発事業のうち試験的に行われるものであつて,技術の改良又は開発と一体として行われなければその達成が困難である事業。
資金供給の態様は,関連施設の整備の場合は貸付及び債務保証,試験的事業は貸付,債務保証及び出資である。
資金供給業務の中心である「貸付」の条件は,国際協力事業団業務方法書に規定されており,日本輸出入銀行,海外経済協力基金に比し,相当ソフトなものとなっている。
77年度における資金協力業務の実績は,長期にわたる経済清勢の停滞に伴うわが国民間企業の海外投資の落込みを反映し,新規案件の伸びは低く,新規融資承諾は12件,27億円(76年度は13件,44億円),融資額35億円(76年度は24億円)である。
国際協力事業団の発足の意義の一つは,資金協力と技術協力の連携であり,融資対象となる事業に必要な調査及び技術指導を実施している。すなわち,融資対象となる事業が相手国の経済発展,地域開発,民生の安定向上などにどの程度資するか,あるいは当該事業が採算に乗り得るかどうかなどの必要な調査を実施するとともに,開発途上地域で実施している開発事業で民間企業が自力で対処し得ない技術的問題に対し必要な技術の指導を行っている。
(注) ・商品借款を拡大する。 ・開発資機材へも借款を供与する。 ・中進国に対しても借款を供与する。 ・新規優良プロジェクトの発掘に努める。
(注) 援助のアンタイイソグとは,一般的に,ある資材及び役務の調達先を援助供与国に限定しないことを意味する。援助がアンタイド化されることにより,被援助国にとっては,国際競争価格による調達が可能となり,援助資金を効率的に使用できるほか,開発途上国が落札した場合には,当該国の輸出促進にもつながるので,従来より開発途上国から強い希望が出されているものである。
LDCアンタイドとは,調達先を全ての先進国及び開発途上国に開放する(いわゆる一般アンタイド)ための中間的措置として考えられたもので,調達先を援助国及びDACの定める開発途上国又は地域とするものである。