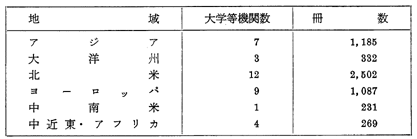 |
―国際文化交流の現状―
第4章 情報文化活動
第1節 国際文化交流の現状
わが国の対外文化交流の行政および実施は,外務省文化事業部と国際交流基金が中心となつて進めているが,このほか,文部省,文化庁および関係特殊法人等も文化交流を担当している。国際交流基金は,外務省が所管する特殊法人で,各種文化交流事業を行つており,同基金の海外事業は,海外2カ所の文化会館と5カ所の駐在員のほか,全世界のわが在外公館を通じて行われている。外務省文化事業部は,在外公館を通ずる直接の文化事業(在外公館との関係が密接なもの)を行うほか,国際交流基金の監督を所掌し,同基金事業について企画調整に参画し,在外公館との連絡調整等にあたつている。
文化事業部は,以上のように,わが国政府の国際文化交流の総合的企画調整を行う立場から,諸外国との間に文化協定を締結し,その実施として,混合委員会等の開催によつて協定実施のための外国政府との協議を行つている。
(1) ハンガリーとの文化交流取極の締結
73年4月9日,東京で,大平外務大臣とハンガリーのヤーノシュ・ぺール外務大臣との間で,日本とハンガリー両政府間の文化交流に関する書簡が交換された。
この取極は,政府機関発行の広報資料の配布,政府機関を通ずる学者,科学者,学生およびその他文化活動に従事する者の交換,美術展覧会等の文化的性質を有する行事の政府機関による実施,公の刊行物の交換等の分野における相互主義の原則に基づく両政府間の協力について定めており,また,両政府間の文化交流の諸問題に関し,両政府が随時協議することを規定している。なお,この取極は,書簡交換の日から2年間効力を有する。
(2) ベルギーとの文化協定の署名
73年5月4日ブラッセルで,ベルギー訪問中の大平外務大臣とベルギーのヴァン・エルスランド外務大臣との間で,日本・ベルギー文化協定の署名が行われた。
本協定は,本文12条から成り,戦後わが国が締結した他の文化協定とほぼ同様,文化,科学,教育,スポーツの各分野における両国間の交流を奨励し,これを促進するため相互に便宜を供与することを規定している。
ベルギーとの間には,従来,留学生,学者,研究員などの人物交流,各種催し物を中心とする芸術交流,公の刊行物の交換,姉妹都市提携等種々の分野で文化交流が行われているが,本協定締結に伴い,あらゆる分野での文化交流がさらに促進されることが期待されている。
(3) 日ソ文化交流実施三取極の締結
わが国とソ連との間には,既に72年1月27日,両政府間の文化交流に関する取極(注)が締結されており,その後,同取極の実施細目に関する取極について交渉が進められてきた。公の刊行物の交換,政府派遣の学者および研究者の交換,政府機関発行の広報資料の配布の三分野における協力につき取極を締結することにつき合意したので73年10月10日,モスクワで大平外務大臣とグロムイコ外務大臣との間で,三分野の交流に関する3つの交換公文が締結された。
3.文化協定に基づく文化混合委員会(注)等の開催
(1) 第3回日伊文化混合委員会の開催
日伊文化協定(55年11月22日発効)に基づく日伊混合委員会の第3回会合が,73年4月17,18日の両日,ローマで開催された。同委員会では,在東京イタリア文化会館の建設計画,日伊両国における相手国語の教育問題,相手国の留学生に対するスカラシップの供与,研究者交換等による科学技術協力の態様,美術展開催等の芸術分野における交流,書籍の相互寄贈,ラジオ・テレビ放送の分野での協力,スポーツ交流の問題等が話し合われた。
(2) 第7回日英文化混合委員会の開催
日英文化協定(61年7月8日発効)に基づく混合委員会の第7回会合が,73年5月22日に東京で開催された。同委員会では,英国の大学における日本研究に対する国際交流基金からの援助に関する問題および英国の個人または諸機関に対する同基金の援助事業,日本の諸大学における英国人講師の地位に関する諸問題,両国間の学者,研修教員,芸術家,留学生等の人物交流,奨学金の供与,美術展示会の開催等について,それらの実績および計画等を中心に話し合いが行われた。
(3) 日仏科学小委員会の開催
日仏文化協定(53年10月3日発効)に基づく日仏混合委員会の下部機構として,特に,両国間の科学技術協力の態様について検討するため,日仏混合委第6回会合(72年6月於パリ)で日仏科学小委員会の設置が決まつた。第1回会合が73年7月3,4日の両日東京で,また第2回会合が11月15,16日の両日バリで開催された。これら2つの会合を通じ,両国間の科学技術協力を発展させる可能性および協力の実際的態様につき話し合いが行われ,両政府間の科学技術揚力協定を締結する必要性につき合意するとともに,この協定の下にさらに基礎および応用科学,医学,海洋開発などの分野について,両国の科学関係機関の間で協力取極を締結することが了解された。また,同委員会は,両国間の科学技術交流の状況を検討し,今後の交流のバランスのとれた拡大と組織化の必要性を確認した。
(4) 第6回日墨文化委員会の開催
日墨文化協定(55年10月5日発効)に基づく文化委員会の第6回会合が,73年10月3,4日の両日,東京で開催された。同委員会では,両国間の文化交流実績に対する検討と語価,今後の文化交流計画,現行文化協定の運用に関する検討,科学技術協力の問題等につき話し合われた。
(5) 第2回日印文化混合委員会の開催
日印文化協定(57年5月24日発効)に基づく混合委員会の第2回会合が,73年10月23,24日の両日,ニューデリーで開催された同委員会では,両国間の文化交流の実績の検討を行うとともに,将来の事業計画に関する両国の提案について意見交換が行われた。
田中総理大臣は,73年8月の米国訪問,同年9月10月の独仏英3カ国訪問に際し,それぞれの国での共同声明,またはプレス・コミュニケにより,これらの国における日本研究を促進し,拡充するため国際交流基金を通じて米国については1,000万ドル,欧州三カ国については,それぞれ邦貨3億円相当の現地通貨の資金の寄贈を発表した。
この資金の寄贈は,米欧諸国の大学における日本研究の促進拡充は,米欧の対日理解の増進,日米,日欧間の友好協力関係の進展に資するとの長期的な観点より行われたものであり,本件資金は,基金として運営され,その運用益が日本研究促進のため使用されるものであるが,本件基金運用益の使途,管理方法等につき,各国の関係当局と話し合いを重ねた結果合意をみ,各寄贈先の大学ないし機関(注) の代表者と今日出海国際交流基金理事長との間でそれぞれ書簡交換を行い合意事項を確認した。上記4カ国に対する資金の贈与は,73年度中に完了した。
(1) アジア地域文化政策会議
73年12月10日から19日まで,ユネスコの主催による「アジア地域文化政策会議」がインドネシアのジャカルタで開催され,アジア,大洋州のユネスコ加盟国21カ国から約200名の代表が参加した。同会議は,70年8月ヴェニスで開かれた文化政策に関するユネスコ政府間会議と同年11月の第16回ユネスコ総会の決議に基づき,ユネスコが,アジアの加盟国に呼びかけて,アジア地域各国の文化発展のための政策に関する共通の問題を閣僚レベルで討議し,相互間の協力関係促進に資することを目的としたもので,アジアでは初めてのものである。なお,同様の会議が,72年6月にヘルシンキで開かれたが,75年にはアフリカで,77年には西半球で,79年にはアラブ地域で,それぞれ開催の予定となつている。
本件会議では,アジアにおける伝統的文化の価値を,とくにいわゆる近代化との関係でどうみるかこれをいかに発展させていくべきか,まだ,各国間の文化協力についてどう考え,これをどうすすめていくべきかなどの諸点を中心に討議が行なわれたが,最初の会議でもあり,テーマが非常に多岐かつ広大にわたつたため,突込んだ議論には至らなかつた。しかし,アジア文化の比較研究促進,「アジア青年機構」設立や「アジア芸術祭」の可能性等に関する決議32と今後の文化政策のあり方に関 する基本的ガイドラインについての宣言が採択された。この会議で注目すべき点としては,アジア各国の発言中,文化交流にあたつて開発途上国の文化的独自性が守られなげればならないとする議論が強かつたことなどが挙げられる。また,ソ連のほか,大洋州地域から豪州とニュー・ジーランドが参加し,アジアの国として自らを定義つげ,アジアの問題に対し積極的理解と参加の態度を示したことも印象的なことであつた(中国は参加しなかつた)。
なお,わが国代表団は,村山文部事務次官,清水文化庁次長,西宮外部省文化事業部参事官ほか計11名であつた。
(2) アジア教育事情調査団の派遣
アジア諸国の文化,教育事情を調査し,将来の文化,教育協力に関する基本的方針のための基礎資料を整備するため,外務,文部両省派遣によりスリ・ランカおよびヴィエトナムにそれぞれ次のとおり教育事情調査団が派遣された。
スリ・ランカ班 73年11月26日~12月8日
団長 小川芳男 日本国際教育協会理事長
ヴィェトナム 74年1月28日~2月11日
団長 平塚益徳 国立教育研究所長
(3) アジア太平洋地域文化社会センター(注1)
68年10月ソウルに設置された本センターは,現在第6事業年度に入つているが,73年4月以降,74年3月までの間に,各国民族美術展,国際映画祭,博物館会議等の開催,域内の学者,ジャーナリスト,教育者,芸術家等の域内自由研究旅行,青少年の親善体験旅行に対するフェローシップ供与,域内都市開発問題文献・研究者リストの刊行等の事業を行なった。なお,前年度からの継続事業として,域内文学作品アンソロジー(詩と短篇 劇の2点),児童向け各国事情紹介書等の刊行準備も進行中である。
(4) 東南アジア文相機構(SEAMEO)への協力
58年に発足した本機構(注2)は,現在,理数教育センター(RECSAM,在マレイシア),英語教育センター(RELC,在シンガポール),熱帯生物学センター(BIOTROP,在インドネシア),農業教育・研究センター(SEARCA,在フィリピン),教育革新・教育工学センター(INNOTECH,在サイゴン),の各センターと,熱帯医学公衆衛生計画(TROPMED,バンコックの中央調整理事会のほか,各国にそれぞれ特定研究テーマを分担するナショナル・センターがある。)の6プロジェクトが実施されている。さらに,73年,考古学・美術応用研究センター(ARCAFA)のプノンペン設置が正式決定され,現在同地に準備事務所が設けられている。これらのプロジェクトは,各分野での教育者,研究者等の養成訓練,調査,研究,情報交換等を主な事業内容としており,国際的評価が高まり,各国との協力関係も密接になっている。同機構事業の所要経費の半分は設立当初の経 緯から米国政府の援助(73年6月までの支出実績は1,550万ドル)によっているが,米国以外の各国も資金援助や人員,機材の提供等の協力を行つている。
SEAMEOは東南アジアの教育・文化開発上有力な国際機構であり,わが国としても,今後一層協力を強化拡大すべきものと思われる。
(5) ボロブドゥール遺跡復興協力
政府は,ユネスコの呼びかけに応じて,インドネシアが誇る世界的文化遺産であるボロブドゥール(8~9世記頃に建造され,ヒンヅー・ジャワ文化に属する石造の仏教建築物)の復興用資金推定必要額775万ドルの一部として,年間10万ドル6年間計60万ドルの拠出金を計画し,これまでに20万ドルをユネスコに設けられた信託基金に払込んでいる。
なお,ボロブドゥール以外にもパキスタンのモヘンジョダロ,アフガニスタンのバーミヤン,カンボディアのアンコール・ワット等の文化遺産について国際的な救済・復興の努力が期待されており,わが国としても今後このような国際運動に積極的に参加していく必要があろう。
(6) その他の無償援助
以上のほか,開発途上諸国の文化・教育・学術の水準向上のための無償援助需要は急速な増大傾向をみせており,わが国も,71年タンザニア向け文盲撲滅用教科書5万冊の寄贈や,東南アジア向け小学校理科スライドの寄贈を行なつたほか,73年には国際交流基金がインドネシア教育文化省に対し,小・中学校向け理科教材としてスライド投影機120台,スライド720 冊を寄贈した。
72年10月2日に発足した国際交流基金は,国際交流基金法(昭和47年法律第48号)に基づく外務省所管の特殊法人として設立されたものであるが,わが国の国際文化交流事業を実施する機関として重要な役割を果してきている。
基金に対する政府出資は,設立時に100億円(72年度50億円,73年度50億円)であつたが,73年にすでに50億円の追加出資をしており,74年度予算ではさらに100億円の追加出資が認められた。
政府出資金とは別に,47年度(6ヵ月)に3億1,941万円,48年度に7億2,420万円の補助金を交付しており,49年度には7億2,540万円の補助金交付が決定している。
基金事業は,人物交流,日本研究援助,日本語普及,国際文化行事,文化資料,視聴覚資料などの分野が中心になつており,各分野ですでにかなりの実績をあげてきており,73年には,田中総理訪米訪欧の際に約束された欧米各大学への日本研究促進のための資金の贈与も基金を通じて行なわれた。
基金の理事長は,今日出海氏(前文化庁長官)で,理事3名,監事1名,計5名の役員のほか,定員109名の職員が,内外で活動している。
海外には,在ローマおよび在ケルンの2つの日本文化会館のほか,ニュー・ヨーク,ロンドン,ブェノス・アイレス,ワシントンおよびジャカルタに駐在員を配置し(さらにバンコック,パリおよびロス・アンジェルスに駐在員を配置の予定),海外への基金の発展は着実に進められてきた。
しかしながら,国際交流基金の組織や事業の規模は,ブリティッシュ・カウンシル,ゲーテ・インスティテュート,アリアンス・フランセーズ等に比べれば,まだ小規模であり,文化交流の重要性に鑑み,今後益々拡大されねばならない。
(1) 在外公館主催の文化事業
各在外公館は各所在地域の事情を勘案し,講演会,音楽会,展示会等の催し物を企画し,実施し,或は現地諸団体のイニシャテイヴにもとづく文化的行事に参加し,日本紹介,相互理解の増進に努力している。73年度には,各地域を通じて生け花(生け花教室,講習会等)42回,講演会23回,日本紹介展17回,現代版画展11回,カラー写真展(人形展との併催を含む)10回,茶道実演7回,日本文化紹介の夕べ7回,音楽会5回,人形製作指導4回,造花実演会4回,囲碁大会4回,その他各種の展示を行うとともに,現地各種機関,団体主催の催しに参加した。
これら催物の各地域における実施状況は,別図のとおりである。
(2) 日本紹介のための公演
わが国伝統文化および現代芸能の海外への紹介は,わが国についての理解を増進するための重要な事業として,国際交流基金が活発に行なっているが,このような事業は,一般に多額の経費がかかるとともに長期の事業準備が必要であり民間団体のみでは,なかなか実施しにくい事情がある。このため,今後とも国際交流基金の自主的事業または国際交流基金の一部資金援助による民間団体の事業として積極的に推進していく必要がある。73年に各地域で国際交流基金により実施されたこの種の事業は,次の通りである。
(3) 日本紹介のための展示会
国際交流基金は,わが国の美術,工芸,現代版画,写真等を通じて,日本文化を海外に紹介しているが,73年に行われた事業は,次の通りとなつている。
(4) 図書出版物による日本紹介
(イ) 従来,外務省が行つてきた海外の大学,研究機関,図書館等に対する図書寄贈の業務は73年度以降国際交流基金に移管されたが,同基金の同年度中に行つた地域別図書寄贈の実績は次の表のとおりである。
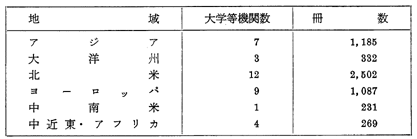 |
このほかに同基金はシンガポール,エル・サルヴァドルで開催された国際図書展に日本関係図書を出品し,また,ペルー,アルゼンティンにおける日本学童生活紹介展図書を寄贈した。
(ロ) 上記の図書寄贈の他,同基金は現在海外の日本研究機関等に対する配布用として英語,仏語,インドネシア語によるわが国文学・学術・美術書等10種の翻訳・出版を行つている。
また,これらに加えて8種の日本紹介出版物を買い上げ配布している。
(5) 映画およびテレビによる日本紹介
映画,テレビは,文化,社会その他の国情を紹介する手段としては,直接視聴覚に訴えるだけに極めて効果的であり,外務省および国際交流基金は,わが国の国情紹介,国際理解の増進のため映画,テレビを有効的に利用している。
73年度中外務省は,各在外公館を通じ次の通り,映画会開催とフイルム貸出し,国際映画への参加等を行つた。
(イ) 在外公館主催映画会
73年には,255回の在外公館主催劇・文化映画会を開催した。
73年度に新たに購入したフィルムのうち特に好評を博した劇映画は 「男はつらいよ」「影の車」「愛つて何だろう」「青幻記」、で,文化映画は「京菓子」「色鍋島」「蒔絵」等であつた。
なお,これら映画フィルムの購入は,国際交流基金が行つている(73年度には劇映画24本,文化映画58本を購入)。
(ロ) 日ソ映画祭
60年6月,日ソ両国政府の合意に基づき相互に映画祭が毎年1回開催されることになつたが,この企画により映画芸術を通じて,日ソ両国の友好親善と相互理解を深めるとともにわが国の国情・文化を紹介する上に非常な効果をあげている。
73年度は,モスクワ,アシハバード,ナホトカの3都市で劇・文化映画の上映が行われ大好評を博した。またこれと対応して10月に東京,京都,松江の3都市でソ連映画祭が開催された。
(ハ) 国際映画祭
各種国際映画祭より各在外公館を通じ,劇映画あるいは文化映画作品参加招へいを受け,わが国から39の国際映画祭に積極的に参加した。
このうち,とくに6月にモントリオールで開催された「第1回人間環境に関する国際映画祭」では長篇映画「ミナマタ」が最優秀賞を受けた。
(ニ) テレビ番組放映
「姫路城」「港長崎の少年たち」「装身具」等多数を各在外公館で放映した。
なお73年度から,英語に加え,新たにスペイン語への吹替も行われることとなつた。テレビ用映画として購入されたのは27本であつた。
(ホ) 日米放送番組交流
日米間でテレビ番組を互に交換,放映しあい,相互理解と親善を深める目的で,国際交流基金と米国公共放送協会(PBS)との間で日米放送番組交流についての合意が成立し,74年度から実施されることになつた。先ず,基金がNHK,民放製作の番組を英語版に改訂,送付し,PBSを通じ米国の公共テレビ局で放映する。
(6) アジア「日本文化週間」
外務省は,73年11月25日から12月10日までの間,ラングーン,クアラ・ルンプールおよびシンガポールの東南アジア3都市でアジア「日本文化週間」を開催し,国際交流基金が派遣した宝塚歌劇団の公演,文化劇・映画会を実施,ラングーン各地で大好評を博した。
(1) 文化人の海外派遣
国際交流基金は,わが国の芸術,学術,思想,スポーツ等を紹介し,国際親善を促進するため,前年に引き続いて文化人,学者,茶道,生け花および柔道師範等合計108名を派遣した。
(2) 文化人招へい事業
国際交流基金は,次の招へい事業を行つた。
(イ) 文化人等短期招へい事業
外国の文化人,学者等をわが国に招き,わが国の事情を認識させ,わが国関係者と意見交換の機会を与えることを目的とし,73年度は63名を招へいした。
(ロ) 日本関係研究者長期招へい事業
諸外国から日本関係研究者を本邦に招き,研究者のわが国での実地研究に役立たせるため,73年度は60名を招へいした。
(3) 第2回アジア中学・高校教員招へい事業
アジア諸国で中学・高校の教育に当つている教員および教育関係者をわが国に招き,教育を中心としたわが国の実情を視察する機会を与えることにより対日理解の促進と相互理解の増進を図ることを目的として,昨年に引続き第2回アジア中学・高校教員招へい事業を文部省協力の下に下記の要領で実施した。
1 対象国および招へい人数
タイ,インドネシア,フィリピン,シンガポール,マレイシア,ヴィエトナムおよびビルマの7カ国より計125名
2 期 間
(i) 10月2日~10月16日(タイ,インドネシア)
(ii) 10月17日~10月31日(フィリピン,ヴィエトナム)
(iii) 11月10日~11月24日(マレイシア,シンガポール,ビルマ)
(4) 青少年交流
外務省では従来から日本語普及事業をすすめてきた地域を対象に,日本語学習,日本研究の奨励,対日理解の促進を図るため,国際交流基金を通じ「海外日本語講師の招へい」および「日本語講座成績優秀者の招へい」計画の実施を決定した。
73年は海外日本語講師を10月1日~12月15日の間,アジア,中南米,大洋州および北米各地域から9名,日本語成績優秀者を3月12日~25日の間,アジア,中南米,中近東,大洋州,北米の各地域から50名を日本に招いた。
そのほか総理府,地方自治体および世界青少年交流協会等民間ベースでの対外青少年交流事業に対し,便宜供与を行なつた。
(5) スポーツ団体,登山隊および学術調査隊に対する便宜供与
外務省は,73年度もわが国から派遣される各種スポーツ団体(アジア・太平洋・欧州・北米・中南米・中近東向け27団体),登山隊(アジア・中南米・北米向け18隊)および学術調査隊(アジア・太平洋,中近東,アフ リカ,中南米,欧州向け24隊)に対する便宜供与を行なつた。
(1) 国際学友会による事業
財団法人国際学友会は,昭和10年創立され,外国人留学生に対し宿舎を提供するとともに,日本語学校を運営し,日本語等を指導するほか大学進学のあつせんを行なつている。
宿舎の収容能力は東京本部154名,京都支部48名,仙台支部51名および 関西国際学友会(大阪)66名の合計319名であり年間を通じほとんど満室の状況である。
日本語学校は,東京本部および関西国際学友会で運営されており,学生定員は前者200名,後者60名であるが,73年度は,これらの日本語学校で387名の留学生に対し,日本語をはじめ,数学,理科,社会などの基礎学科を教授し,これら課程の修了者に対し進学をあつせんした。
(2) パリ大学都市日本館
パリ大学都市日本館は,パリ大学で学ぶ日本人留学生,外国人留学生およびフランス人学生のための学寮であり,館長は,日本館に居住する学生および大学都市内の各館に居住する日本人留学生の補導にあたつている。
また,日本館内には,日本関係の図書を収集して日本研究に便宜を与えている。
外務省は,館長を推せんし,派遣しているほか,同館建物の内部修理および若干の備品費などに対し,援助を行なつている。
(3) 外国人留学生等の来日
わが国に留学を希望する外国人は著しく増加しているが,73年度にわが国の国費留学生制度(文部省主管)により採用した外国人留学生は359名である(地域別実績は下巻12(4)の表の通り)。
また,科学技術庁では,73年度に,外国人研究者7名(米2,仏1,西独1,英1,豪1,大韓民国1)を招へいしている。
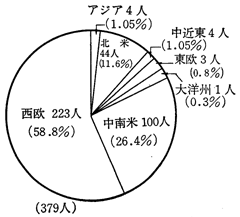
(4) 日米教育交換計画(フルブライト計画)
73年度の本計画に基づく両国間学生,教授,研究員の交換実績は,来日米国人28名(客員講師11名,研究員6名,教員4名,大学院学生7名)および渡米日本人40名(講師および研究員14名,大学院学生26名)である。
(5) 日本人学生の海外留学
73年度に外国政府または準政府機関の奨学金を受けて海外へ出発した者の数は,379名である(地域別内訳は前頁図の通り)。
(6) 日本研究事業
海外の大学の日本研究講座および大学,学術研究所の日本研究を助成するため,国際交流基金は73年中に次のとおり日本人学者,研究者または専門家を派遣した。
(イ) アジア地域における寄贈日本研究講座への援助
わが国はアジア諸国で,日本研究について関心度の高い主要大学に日本研究講座を寄贈開設することとし,65年度に,タイのタマサート大学(のちにチュラロンコン大学を含める。),66年度に,フィリピンのアテネオ大学,香港の中文大学(のちに香港大学も含める。),マレイシアのマラヤ大学およびインドネシアのインドネシア大学,さらに68年度に,インドのデリー大学に,それぞれ日本研究講座を開設した。講座の開設に当つて,日本側と相手国側との間に取交された文書により講座の目的および運営(図書,教材,器材の寄贈を含む。),派遣教授陣の構成,地位,待遇等について合意された。73年における上記各関係大学への派遣教授陣の現状は教授7名,講師12名,計19名である。
(ロ) 欧米,大洋州の日本研究への援助
わが国は,73年度に,イギリスのシェフィールド大学,メキシコのコレヒオ・デ・メヒコ大学,アメリカのハワイ大学,ワシントン大学およびプリンストン大学・フランスのパリ第7大学,イタリアのナポリ東洋大学,デンマークのオーフス大学,オーストラリアのオーストラリア国立大学およびニューサウスウエルズ大学に別表のとおり計11名(うち教授5名,講師6名)を派遣し,それぞれの大学における日本研究の発展促進に協力した。
(7) 日本語普及事業
国際交流基金は,日本語普及のため73年中下記事業を実施した。
(i) 日本語講師の派遣
(ii) 海外現地日本語講師の謝金援助
(iii) 現地日本語講師および日本語講座成績優秀者の本邦招へい(上記8. (4)参照)
(iv) 日本語教材の寄贈
(8) 米国・カナダ11大学連合日本研究センターへの資金援助
73年度において,国際交流基金は,米国,カナダの11の有力大学が東京に設置している日本語訓練センターの運営に対する資金援助を行なつた。
(9) 日ソ学者研究員の交流
65年以降,わが国はソ連との間に,政府間取極により,相互主義に基づく学者,研究員の交流を行なつているが,73年度には日本側から長期派遣研究員5名,短期派遣学者4名,ソ連側から長期派遣研究員4名,短期派遣学者3名の交換を行なつた。
なお,73年10月10日モスクワで「日本政府の関係機関とソ連科学アカデミーの研究機関との間の学者及び研究者の交換に関する交換公文」が交換され,日本側各省庁所管の研究機関および大学とソ連側ソ連邦科学アカデミーおよび連邦構成共和国科学アカデミーの研究機関との間で毎年長期10名(10カ月を越えない),短期10名(2カ月を越えない)の範囲で学者および研究者の交換を行なうことになつた。
(注) 日ソ文化交流取極は,74年1月26日にその2カ年の有効期間を終了することになつていたが,日ソ両政府とも,この取極に基づく両国間の文化協力を継続することが有意義であると認め,74年1月25日モスクワで,同取極の有効期間を76年1月26日までさらに2年間延長するための書簡交換を行つた。 戻る
文化協定は,締結国政府が両国間に行われる各種文化交流事業の促進をはかり,これを奨励することを主な内容とする協定であり,わが国は現在,13カ国と文化協定を締結している。
混合委員会は,文化協定の適用を確保し,また,協定の実施条件を具体化すること等を主要な任務として,同協定により設置される両国の協議機関である。これまで開かれた委員会では,一般に両国間の文化交流の実績をフォローし,さらに,今 後の文化交流計画に関し双方関係者により検討が行われている。各委員会の日本側委員として,外務省代表者のほか,文部省等関係省庁の代表者や民間有識老が任命されている。 戻る
本件基金の寄贈先は次の通り。
米国 :
(1) カリフォルニア大学(在バークレー),(2) シカゴ大学,(3) コロンビア大学 (4) ハーバード大学,(5) ハワイ大学,(6) ミシガン大学,(7) プリンストン大学 (8) スタンフォード大学,(9) ワシントン大学(在シアトル),(10) エール大学
ドイツ : 日独文化学術交流振興会(独法人)
フランス : フランス財団 該当
イギリス : シェフィールド大学(英国の大学の代表として)
なお,基金の運用は,各大学の運用委員会,または,各機関の下に設置される運用委員会により行われる。 戻る
(注1) わが国のほか豪州,台湾,韓国,マレイシア,ニュー・ジーランド,フィリピン,タイ,ヴィエトナムの計9カ国が加盟。ただし,73年11月,豪州,ニュー・ジーランドの2カ国は1年後に脱退する意向をセンター事務局に通告した。 戻る
(注2) 加盟国は,カンボディア,インドネシア,ラオス,マレイシア,フィリピン,シンガポール,タイ,ヴィエトナムの8カ国 戻る