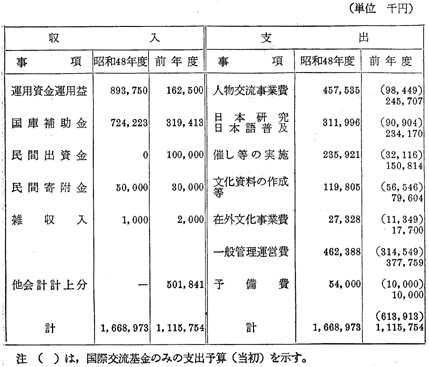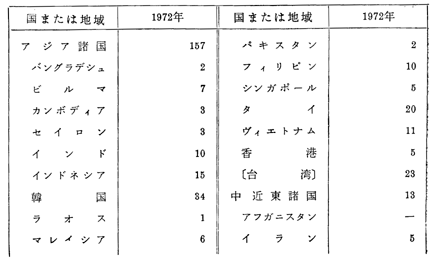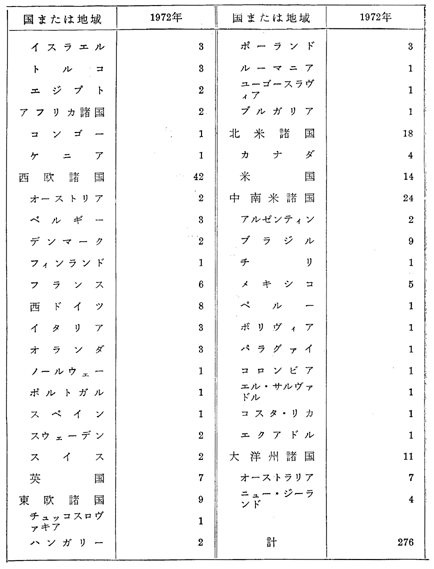|
-文化関係- |
|
総 額 11,067,952 総予算対比 12.6% 内 訳 国際交流基金への出資 10,000,000 国際交流基金への補助金 724,233 国際学友会への補助金 161,267 文化事業部直轄 182,462 米 国 163億24百万円(1973年7月~1974年6月要求額) 英 国 153億94百万円(1972年4月~1973年3月) フランス 642億45百万円(1973年1~12月) 西ドイツ 379億83百万円(1973年1~12月) イタリア 94億44百万円(1972年1~12月)
(1972年度) 極東及び北東アジア地域 韓国,モンゴル等4カ国より 12名 東南アジア地域 タイ,インドネシア等9カ国より 24名 南西アジア地域 インド等5カ国より 11名 中南米地域 ブラジル,パラグァイ等8カ国より 8名 中近東地域 サウディ・アラビア等4カ国より 4名 アフリカ地域 ケニア等5カ国より 5名 その他 オーストラリア,国際連合,国際機関等より 1O名 計74名
I 使節団の構成 団長 宮沢 喜一(衆議院議員,元通商産業大臣) 団員 盛田 昭夫(ソニー株式会社杜長) 黒田音四郎(国際学友会理事長) 衛藤 藩吉(東京大学教授) 三浦 朱門(作家,日本ペンクラブ理事) 犬丸 直(国際交流基金常務理事) 金子 太郎(大蔵省証券局総務課長) 随員 伊集院明夫(外務省文化事業部事務官) 山崎 正親(国際交流基金職員) II 日 程 東 京 発 1973年3月25日 インドネシア着 3月25日 〃発 3月30日 タ イ 着* 3月30日 〃発 4月1日 ビ ル マ 着 4月1日 〃発 4月4日 ベトナム着 4月4日 〃発 4月7日 香 港 着 4月7日 〃発 4月10日 東 京 着 4月10日 *タイは,非公式訪問 III 会見・視察先 A インドネシア(3月25日~3月30日) 会見先 マリク外務大臣 マスフリ情報大臣 スジョノ大統領特別補佐官 内外記者との会見 ☆文化交流に関する日・イ共同セミナー出席 視察・訪間先 ボロブドール遺跡 プランバナン遺跡 B ビルマ(4月1日~4月4日) 会見先 ネ・ウィン首相 工―マウン文化副大臣 ラ・ハン教育大臣 チョウ・ソウ外務大臣 ウ・サン・タ・オン教育省高等教育局長 党中央青少年指導部幹部との懇談 文化省幹部との懇談 ニュース・定期刊行物分杜幹部との懇談 視察・訪問先 ビルマ古典舞踊鑑賞 シュエタゴンパゴダ 文教施設 外国語学院所属目本語夏季講座視察 C ヴィエトナム(4月4日~4月7日) 会見先 タン外務省官房長 Mai Tho Truyen 文化大臣 Tran Van Tanサイゴン大学院長 Ngo Khac Tinh 教育大臣 Dam Trung Phapサイゴン大学附属外国語学校長 Tran Thien Khiem 首相 Tran Van Huong 副大統領 ヴィエトナム経済界・学界との懇談 ヴィエトナム・ペンクラブ,新聞界,国際問題研究会との懇談 邦人記者との会見 視察・訪問先 文化センター日本語クラス視察 サイゴン大学附属外国語学校の授業参観 国立図書館 国立博物館 越米協会 仏文化センター D 香港(4月7日~4月10日) 会見先 在留邦人代表との懇談 中文大学季卓敏総長との懇談 香港大学童嶺松総長との懇談 日本研究講座派遣講師等との懇談 マクルホース総督 市政府A. De Oサレス議長との懇談 視察・訪問先 中文大学 CITY HALL
|
IV 東南7シア文化使節団報告
1 文化交流の基本
(1) 文化交流のあり方
国家間の交流には,種々の側面があるが,かりにこれを政治,経済及び文化の三局面に分けて考えてみると,政治面での交流は,当事国の政治的意図や目的に従って行われ,また,経済面での交流は経済上の計画及至事業の達成を直接の目的とする。これに対して文化の交流は,本来当事国問の相互理解を終極の目的とするものであって,政治的ないし経済的活動に従属すべき性格のものではない。文化交流を他の局面の国家利益に奉仕せしめることは,純粋な意味での相互理解のさまたげになるおそれがある。
日本文化を海外に紹介することの目的は,日本の本質を理解してもらうことにある。換言すれば,それは,日本を良く知ってもらうことにより友好の実をあげる努力であるべきである。また,文化交流はそれが「交流」である限り一方交通に終るべきものでないことは言うまでもない。従って,東南アジア諸国と日本と
の文化交流に際しては,これらの国に日本を知ってもらうと同時に,日本及び日本人が東南アジア諸国の文化の特質について理解を深め,かつ,これを日本に紹介する努力も併行して行われなければならない。日本及び日本人が東南アジアの文化を積極的に評価し,あるいは日本文化との対比におけるその特色を明らかにすることは,それだけ相互の親近感を増すゆえんであり,更にこれら諸国の自国文化の確認と発展に役立ち,ひいてはその刺激によって日本文化の発展にも寄与することになる。
他面,独立間もない東南アジア各国は自らの歴史的,文化的identityの確認と教育・文化面での社会基盤の充実に努めつつあるが,そのための人的・資金的欠乏に悩んでいる事実に注目するとき,わが国としても主要先進国と同様,先方の求めに応じてそれらの努力に積極的に協力する姿勢が必要と考えられる。
(2) 文化交流と経済進出
日本の東南アジア諸国に対する急速な経済進出の結果,現在各地で種々の摩擦が生れているが,この問題は,それ自体としての解決の努力を必要とするのであって,その努力に代えて文化交流の促進によってこれらの摩擦要因を緩和しようとする試みは,既に述べたように文化交流の本来の目的ではない。もちろん,文化交流の促進が反射現象ないし副産物として他の分野での事態の改善に資する場合があるのは事実であるが,それは文化交流活動の本来の目的とは云い難い。だが,現実には,日本の東南アジアにおける文化面での活動が経済面での活動に比較して極めて貧弱である現状からみて,文化交流が促進されれば,偏よった対日イメージを改善する効果が大きいことは期待してよいであろう。
なお,東南アジアにおける日本の所謂「経済的Over Presence」の問題については,本使節団の中に,(イ)わが国の経済進出を 純に経済的「0ver Presence」と断じ,日本と東南アジア諸国との間の経済関係が一定水準以上にならないように制限すべきであるとの議論は,自ら経済交流を否定する考え方であって賛成できないとする意見(盛田団員),(ロ)日本の経済進出が香港においては問題とならないのに対し,インドネシア,タイにおいて問題となるのは,後者において日本の経済進出のスピードが極めて速かったため,日本の市場シェアの急速な拡大が対日警戒心を生んだと思われるので,経済進出が相手側に与えるインパクトを小さくすることが必要になる場合がある点は否定できないとする見方(衛藤団員),(ハ)日本の経済進出が,現地人のParticipationが可能な形で行なわれることが大切である,即ち,現地人の購売力の及び得るような商品を輸出し,また,進出企業の重要ポストに現地人を登用できるように配慮すること,他面たとえば小売面に進出することによって現地人の商権と雇傭を侵すようなことは慎むべきである,とする見方(宮沢団長,三浦団長),(ニ)日本商品に対する需要は増大しており,従来の欧米商品に日本品がとってかわったからといって,日本に反感を持つということはないのではないか,むしろ日本品の優秀性は買った者に日本に対する好感を持たせるのではないか,また,東南アジア諸国における日本商品の広告に行き過ぎがあることを批判する向きもあるが,果して,現地の人達の反感が,本当にこれら広告のみに起因するのか否かは疑問であるとする見方(盛田団員),(ホ)いわゆるOver Presence論は,日本人のある種の優越感の裏返しであり,問題が日本と現地の双方にとって誇大に受け取られているのではないか,とする見解(三浦団員)等があった。
(3) 文化交流鉱夫の必要性
文化面に関する限り,現在のところ,東南アジア地域における日本の活動は,米,英,仏,独等の欧米諸国のそれに比較してはるかに見劣りするものであり,日本の文化的Over Presenceや文化侵略をうんぬんされるような状況にはないが,本使節団が訪問した諸国の中でも,例えばインドネシアにおいて,一部の知識人より「日本が経済進出に加えて日本文化の一方的売り込みのようなことをするのは困る」といった危惧が表明されたことからみて,文化交流の促進に当っては,その手段,方法について慎重な配慮を加え,日本文化を性急に押しつげるようなことは努めて避けるべきであろう。一般的に,欧米諸国が日本の伝統文化のパフォーマンスに興味と好意を示すのに対して,東南アジア諸国にはそれが日本文化の押しつけととられやすい環境があることは留意して置く必要がある。
勿論これは,文化交流活動の量的拡大を差L控えよという意味ではない。上記の危倶が表明されたのは,文化交流に関する日・イ共同セミナーの席上であったが,このセミナーを通じ,インドネシア側は,日・イ間の文化交流の一層の拡大が重要であることを強調しており,上記の慎重論も,日本側の一方的な押しつけではなく,インドネシア側の希望に沿うような形での文化交流を促進すべしとの議論であった。日本の文化交流活動は,経済活動に比較し不均衡に遅れており,今後飛躍的拡大が必要であるが,その際,各々特異な文化を持ち事情の異なった相手国側の風土と心情に適合するようなきめ細かな配慮を伴なった文化交流活動を行なうことが必要である。相手国側の希望にそう限り,文化交流活動はなお大幅に拡大すべきである。
2 文化交流の具体的方途
次に具体的な問題として,文化交流は如何なる方法で推進すべきであろうか。以下,日本文化を東南アジア諸国に紹介する場合,及び,東南アジア諸国の文化を日本に紹介する場合に分けて検討し,後に,東南アジア諸国に対する文化・教育協力の問題,日本の東南アジア研究者に対する支援体制の問題,及び,東南アジア諸国に滞在する日本人のビヘイヴィアの問題に言及することとしたい。なお,留学生の受入と日本語の普及問題及び日本文化会館設立の問題については項を改めて論ずることとしたい。
(1) 日本文化の紹介
i) フィードバック体制の必要性
まず,日本文化を東南アジア諸国に紹介する場合については,相手国側の求めるものを提供することが基本であるが,単に受動的に相手国側から要望が出てくるのをまって,これに応えるだけにとどまらず,積極的に日本側から打診しつつ相手国側の反応をきめ細かく分析,察知し,必要とするものを提供するという形で行なわれるべきである。その為には,日本側で現地文化を知しつした専門家を養成することが必要であり,また,実施された文化交流活動の効果を測定し,今後の活動計画策定に反映し得るような一種のフィードバック体制が必要である。
i) 日本の近代化に対する関心
本使節団が訪間した諸国においては,いずれも日本の近代化の過程について学びたいとの要望が強かった。これら諸国は現在,近代化のために西欧文明という異質の文明を採り入れることを余儀たくされているわけで,過去に於て同じ問題に直面しそれをこなしてきた日本の経験から学ぶものは多いと考えているようである。特に近代化の過程で日本が直面した政治・.経済上の問題の他,法制,経営技術面での経験に関心が持たれているので,先ずかかる要望に応えることが必要であろう。かかる要望に応えることがわが国文化交流事業の当面の大きな柱の一つである。また,近代化の問題については,日本の経験から学ぶことともに,東南アジア諸国が相互の経験から学ぶことが必要であり,そのために日本が国際会議を開催することを希望する声が強かった。
iii) 大衆娯楽の紹介
大衆映画,ダンシングチーム,少女歌劇などの大衆娯楽を輸出すべきか否かについては,(イ)相手国々民が日本に対するある種の親近感を持つことが文化交流の第一歩であるとすれば,かかる親近感を創り出す上でこの種の娯楽は効果がある,(ロ)この種の娯楽は,これら諸国のエリート層にとっても充分楽しめるものであり,必ずしも相手国の「大衆」のみを対象とするものではない,(ハ)シンガポールの反日感情が強かったころ,日本のダンシングチームが同国を訪問したのが大いにうけて,反日感情を宥和するきっかけとなった例もあること,等からみて,東南アジアにおけるこの種公演を助成することには充分な意味がある,というのが本使節団の多数意見である。但し,(イ)文化交流のための予算が限られている現状においては,この種の娯楽の持ち出しは,商業べ一スにゆだねるべきである,あるいは,(ロ)現地の人が本当に望みエンジョイしてくれるものなら,商業べ一スでも持ち出し可能な筈で,費用持ちの提供は,押しつけの印象を与えることをおそれる,とする少数意見もあった。
iv) 西欧的文化の紹介その他
日本からオーケストラのような西欧的なものを紹介することについては,例えばビルマ,ヴィエトナムにおいては先方より否定的な見解も出たが,純日本的なものよりは多少西欧化されたものの方が異和感が少なく受け入れ易い可能性もあり,また,香港の場合のように,日本からのオーケストラ指揮者や絃楽器の指導者の派遣等を求められた例もあるので一率に論ずることはできない。さらに進んで考えると,今や世界の人々の共有物となっている西欧近代文化においてもわが国がかなりの水準を保持していることを東南アジアの人々に理解してもらい,この方面の発展に努力することも意義があると考えられる。
なお,スポーツの分野では特に空手に人気があり,インドネシアにおいては,東南アジア地域の諸国が持っている伝統的な自衛の技術の交流を行なったらどうかとの提案があった。
(2) 東南アジア文化の紹介
次に東南アジア諸国の文化の日本への受入れについてであるが,これについても,貝本文化を紹介する場合と同様の努力が必要である。これら諸国の文化を日本に紹介することは,第一に,従来欧米に向きがちである日本人の目をアジアに向けさせる良い契機になるからであり,第二に,これら諸国が,自らの文化を再発見し,これに誇りを持つようになるきっかけともなるからである。本使節団は,ビルマ古典舞踊を観賞する機会を得たが,東南アジア諸国の民族舞踊や民族音楽の中には,日本人一般に紹介されれば充分関心をよぶに相違ないと見られるものも存在する。ついては,まず,この種の民族舞踊,民族音楽をテレビジョンを通じて日本に紹介する(例えば,舞踊や音楽に造けいの深い専門家を東南アジアに派遣し,その専門家が,興味を持つたものを録画し,解説をつけて紹介する)こと,東南アジア民族舞踊・民族音楽フェスティヴァルといったものを開催すること,東南アジアの民族舞踊,民族音楽を日本のものと比較研究してみること,等も一案であると考える。
(3) 東南アジア諸国に対する文化・教育協力
なお,本使節団は,ビルマ,ヴィエトナムにおいて,これら諸国の歴史に関する資料の蒐集につき協力を求められたが,これら諸国にとって自国の歴史の再発見は,自己のidentity確立のためにも極めて重要な意味を有するものと考えるので,従来から行われている歴史的文化財の保存事業への協力と並んで,できる限り協力すべきであろう。また,これら諸国においては,教育の拡充が急務となっており,わが国よりの教育面での協力に期待する声が強く,特に視聴覚メディアによる教育につきわが国よりの技術面及び器材面での協力が強く求められている。従って,わが国としては,この面での協力にも力を入れるべきであろう。
(4) 東南アジア研究者に対する支援
東南アジア諸国との文化交流には,わが国の専門研究者の協力が不可欠であるが,これら研究老はそのためには,旧宗主国語及び現地語を習得せねばならず,また,研究が地味で大学,研究所などのポスト,研究費などが少ないという不利な条件のもとにある。
米国等に於ては,このような不利な条件に鑑み「地域研究者」に対しては特別に有利な奨学金を与える等の優遇措置がとられている。我国に於てもこれら地域研究老に対し,特別な研修及び特殊研究の助成方策の拡充について検討すべきであり,更にたとえば京都大学東南アジア研究センター,東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所など,大学におけるこの方面の研究体制の充実拡大をはかり,近現代についてのアジア関係の講座を増やして大学における教育体制を整備すべきである。また,現在だとえばアジア経済研究所に多額の政府補助金が投入されているが,これら「地域研究者」にその一部なりともふり向ける方が効率的ではないかとの意見も出た。
(5) 日本人のビヘイビア
日本人旅行者及び現地在留邦人の行動は対日イメージ形成の上で極めて重要である。特に問題になるのは,現地の社会や文化に対するこれら日本人の認識の程度であり,短期の旅行者は別として,現地への赴任者及びその家族に対する事前教育の充実が望まれる。この点で欧米の企業が実施している周到な事前教育を参考にすべきであり,わが国企業においても,その様な努力が払われることが望ましい。海外赴任者の夫人向けに行なわれている各種のセミナーの積極的な活用を期待したい。この他,現地赴任者やその家族が現地語の習得や現地文化の勉強,特に現地人との積極的な交際に努めるようにすることが必要である。さらに根本的には,青少年時代から東南アジア諸国に対する理解と認識を植えつけることが必要であり,この点から,初等,中等教育でアジアヘの理解を深めることと共に,青年の船等の青少年交流事業を一層促進させることが望ましい。
3 留学生の受入と日本語の普及
(1) 留学生の受入
日本への留学生受入れにあたっては日本語の難しさ,大学側の受入れ体制の不備及び日本人家庭の閉鎖性が問題となっている。
日本に留学するに当っては,事前に最低限の日本語を習得することが基本的には必要であるが,その次の段階では日本語又は一般的な日本研究を志す者と特定の専門分野について日本において研究を志す者とを区別し,後者については英語による授業体制をとることを検討すべきであろう。例えば東南アジア諸国に於ては日本近代化の過程を専門分野について学びたいとする者が多いが,彼等のすべてが専門分野に必要な日本語を完全に習得することは期待し難く,これらの授業を英語で行い,あるいはその為の英語の出版物が利用できれば研究の能率を向上することができよう。
留学生の数が年々増加しているにもかかわらず大学側の受入体制がととのっていないのは問題である。留学生の受入れために指導教官は時間と労働に多大の犠牲を払うこととなるがこれを補償する体制は必ずしも充分であるとはいえない。一般に日本の大学は外国特に欧米の文化をとり入れる姿勢はあるが,日本ないし日本文化自身の客観的な研究の場を外国人の研究者や学生に提供する体制に欠けるところが多く,この点を根本的に反省する時期が来ている。また,一般的な日本語及び日本研究者のためには現代日本語科あるいは日本事情ないし日本文化科といったものが必要であると考えられるが,これらについても逐次拡充を図る必要があろう。
なおまた東南アジアの留学生達は日本家庭の閉鎖性を訴え,日本家庭にとけ込むことの出来なかったことをさびしく思いながら帰国したと訴えるものが多い。
(2) 回本語教育の拡充
本使節団が訪問した諸国に於ではいずれも日本語学習熱が高いように思われたが,日本語自体の難しさの他に日本語教授の方法論が確立していないこと,日本語教師の育成体制が整っていないこと,教育器材の不足,現地に日本から派遣されている日本語教師の待遇が充分でないこと等種々の問題をかかえているようである。外国人に対する効果的な日本語教育の体制・方法の確立及びその諸条件の整備充実は,いずれかの機関により早急にその実現の方途が講ぜられるべきである。
本項を通じて言えることは従来我国は他国から学ぶための体制の整備には苦労して来たが,今や日本から学びたいという海外からの需要に直面してその為の人材,施設,研究,情報,方法論が甚だ立遅れているということである。
4 日本文化会館の設置
日本文化会館をジャカルタ又はバンコックに設置するとの構想については,建物を立派なものにするだけに終ってはならず,充分な人員,施設と事業費を用意することが特に重要である。又国によっては日本文化の押しづけといった非難を受ける可能性も全くないとは言えないので,現地の風土と意見を十分尊重すべきであり,必要な場合には現地の各界代表者を含む運営審議会といったものを設置することも一案であろう。更にこの種の会館は必ずしも画一的なものである必要はなく各国の事情に応じて異った性格のものにすべきであろう。例えばジャカルタに於てはUSISその他の欧米諸国の文化交流機関はlowprofiIe政策をとっており我国が文化会館を設置する際にもあまり派手なものはのぞましくたいかもしれない。他方バンコクについては多少目につくものを作って日本の文化面での活動を充分に理解してもらう努力が必要であるといえるかもしれない。但し,団員の中には,開発途上国にはわが国側の押しつけと受け取られるような派手な文化会館をおくべきではなく,それだけの金は,相手国の大学に無償供与するか,または人物交流に使うべきであるとする少数意見もあった。
なお,日本文化会館の設置と同時に重要なことは,既存の在外公館付属の情報文化センターを人員,資料及び資金面に於て一層充実したものにし,その機能を充分発揮せしめることであろう。
(参 考)
訪問先各国での要望事項
1 インドネシア
 空手専門家の派遣及び大衆向けの映画,テレビ番組等マス・メディアを通ずる交流から始めてもらいたい。(ジャーナリスト)
空手専門家の派遣及び大衆向けの映画,テレビ番組等マス・メディアを通ずる交流から始めてもらいたい。(ジャーナリスト)
 大学教授を3ケ月ないし6ケ月日本に招へいし,最新の学説や教授法を学ぶ機会を与えてほしい。(文部省員)
大学教授を3ケ月ないし6ケ月日本に招へいし,最新の学説や教授法を学ぶ機会を与えてほしい。(文部省員)
 イスドネシア語による大学用教科書の作成に関連し,欧米の教科書の翻訳等につき技術的アドバイスを受けたいので,関係者を日本に招へいしてほしい。(文部省員)
イスドネシア語による大学用教科書の作成に関連し,欧米の教科書の翻訳等につき技術的アドバイスを受けたいので,関係者を日本に招へいしてほしい。(文部省員)
 インドネシアにおける合弁企業についての法律上の問題点に関する日・イ共同研究を実施してほしい。(弁護士)
インドネシアにおける合弁企業についての法律上の問題点に関する日・イ共同研究を実施してほしい。(弁護士)
 青少年交流を促進してほしい。
青少年交流を促進してほしい。
 近代化の諸問題につき各専門分野別の日・イ共同セミナーまたは国際セミナーを開催してほしい。(大学教授)
近代化の諸問題につき各専門分野別の日・イ共同セミナーまたは国際セミナーを開催してほしい。(大学教授)
 学位の相互承認を検討してほしい。(大学教授)
学位の相互承認を検討してほしい。(大学教授)
 日本において英語による教育を行なってほしい。(大学教授)
日本において英語による教育を行なってほしい。(大学教授)
 文化財の保存,博物館の建設・管理,美術品の複製々造等につき専門家の派遣及び招へいを検討してほしい。(文部省員)
文化財の保存,博物館の建設・管理,美術品の複製々造等につき専門家の派遣及び招へいを検討してほしい。(文部省員)
 文化協定締結の可能性を検討してほしい。(外務省員)
文化協定締結の可能性を検討してほしい。(外務省員)
 日本文化会館は,日本文化の一方的売り込みの場にならないようにしてほしい。
日本文化会館は,日本文化の一方的売り込みの場にならないようにしてほしい。
2 ビルマ
 西洋的なものよりも,日本の伝統文化の紹介を希望する。(文化省)
西洋的なものよりも,日本の伝統文化の紹介を希望する。(文化省)
 日本美術展の開催を検討してほしい。(文化省)
日本美術展の開催を検討してほしい。(文化省)
 科学実験器材の供与を希望する。(ラングーン文理大,ラングーン工科大学等)
科学実験器材の供与を希望する。(ラングーン文理大,ラングーン工科大学等)
 L.L装置の供与を希望する。(外国語学院)
L.L装置の供与を希望する。(外国語学院)
 ビルマの歴史に関する文献の日本における蒐集に協力してほしい。また,そのために専門家を招へいしてほしい。(文化省)
ビルマの歴史に関する文献の日本における蒐集に協力してほしい。また,そのために専門家を招へいしてほしい。(文化省)
3 ヴィエトナム
 留学生の受入数を増やしてほしい。(外務省)
留学生の受入数を増やしてほしい。(外務省)
 ヴィエトナムの歴史に関する文献の日本における蒐集に協力してほしい。また,そのために,専門家を招へいしてほしい。(文化省)
ヴィエトナムの歴史に関する文献の日本における蒐集に協力してほしい。また,そのために,専門家を招へいしてほしい。(文化省)
 古ヴィエトナム語辞典の印刷・出版に関し日本の援助をお願いしたい。(文化省)
古ヴィエトナム語辞典の印刷・出版に関し日本の援助をお願いしたい。(文化省)
 L.L装置の供与を希望する。(外国語センター)
L.L装置の供与を希望する。(外国語センター)
 日・越両国の児童文学の翻訳・出版につき援助を得たい。(大学教授)
日・越両国の児童文学の翻訳・出版につき援助を得たい。(大学教授)
 東南アジア文化に関する国際会議,セミナー等の開催を検討してほしい。(大学教授)
東南アジア文化に関する国際会議,セミナー等の開催を検討してほしい。(大学教授)
 東南アジア文化研究センターの設置を検討してほしい。(大学教授)
東南アジア文化研究センターの設置を検討してほしい。(大学教授)
 科学・技術書のヴィエトナム語への翻訳につき協力を得たい。(大学教授)
科学・技術書のヴィエトナム語への翻訳につき協力を得たい。(大学教授)
4 香 港
 日本研究講座への講師派遣を今後5年間継続してほしい。(中文大学)
日本研究講座への講師派遣を今後5年間継続してほしい。(中文大学)
 理工系実験器材及び施設の援助を得たい。(中文大学)
理工系実験器材及び施設の援助を得たい。(中文大学)
 日本関係図書の寄贈を希望する。(中文大学)
日本関係図書の寄贈を希望する。(中文大学)
 絃楽器の教師を派遣してほしい。
絃楽器の教師を派遣してほしい。
 オーケストラ指揮者を派遣してほしい。
オーケストラ指揮者を派遣してほしい。
 香港Arts
Festiva1に参加,協力してほしい。
香港Arts
Festiva1に参加,協力してほしい。
 日本研究講座のため講師を派遣してほしい。(香港大学)
日本研究講座のため講師を派遣してほしい。(香港大学)