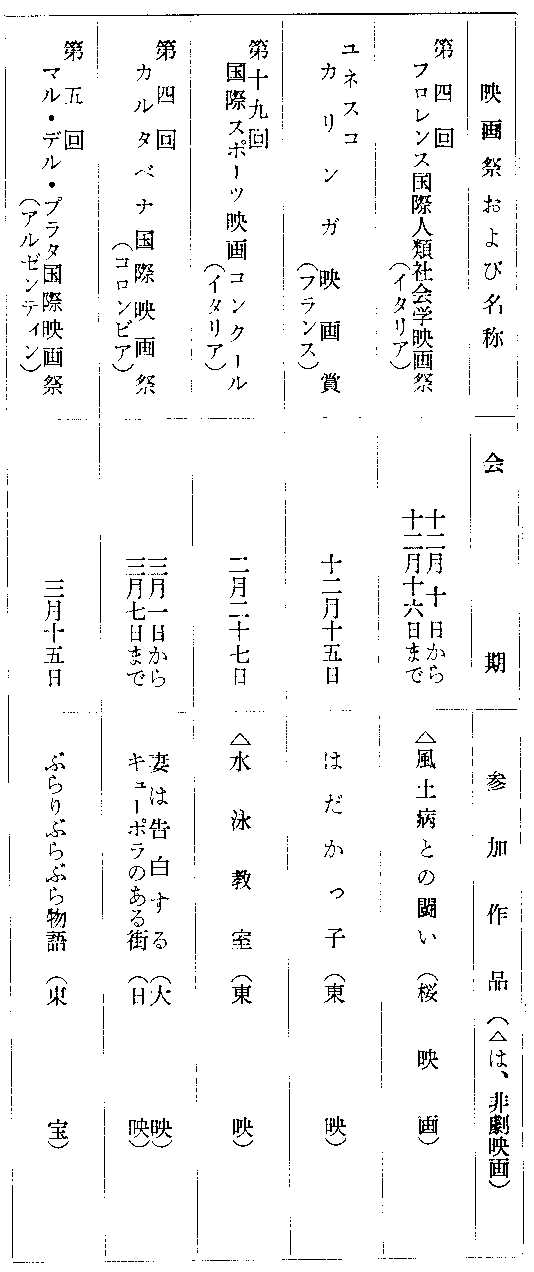 |
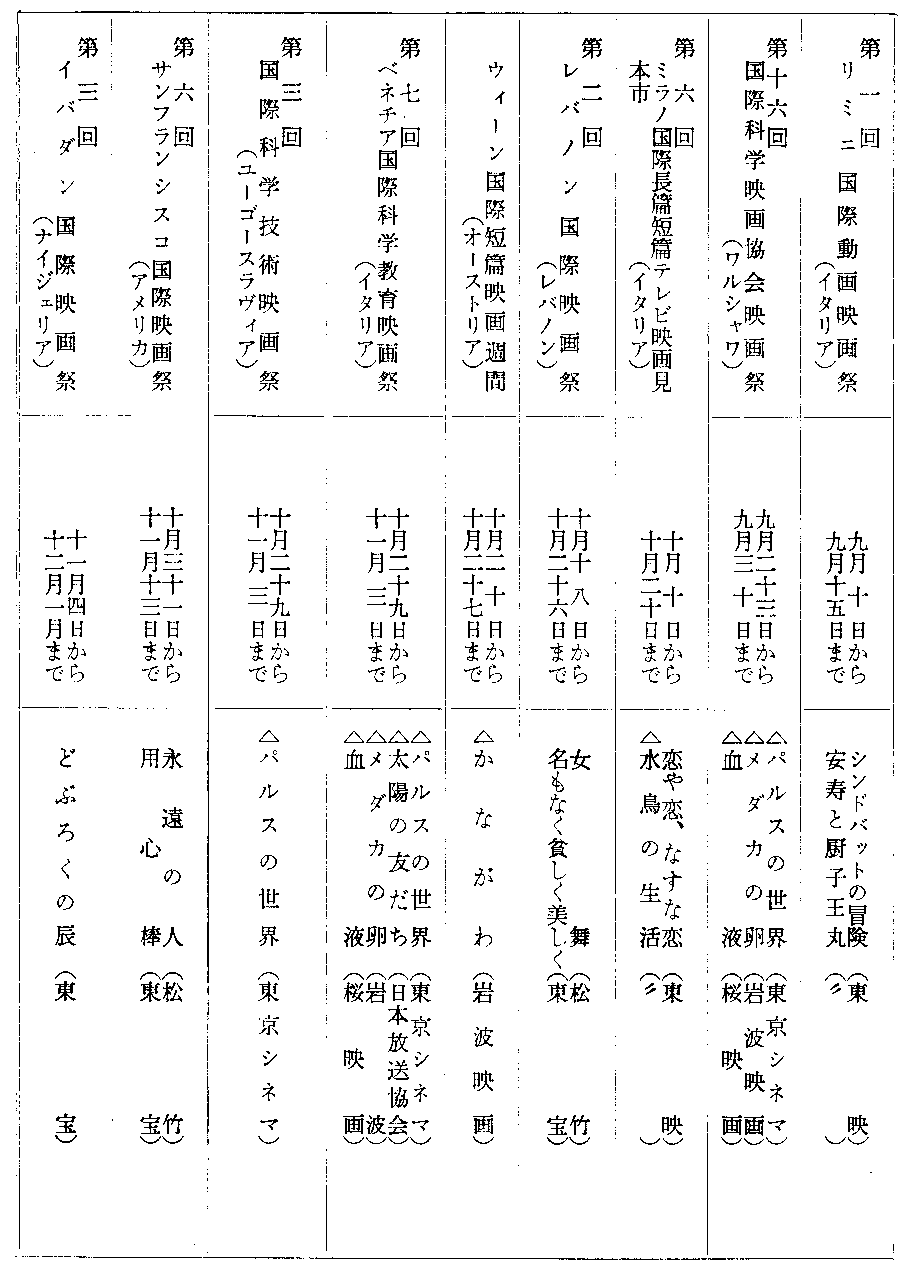 |
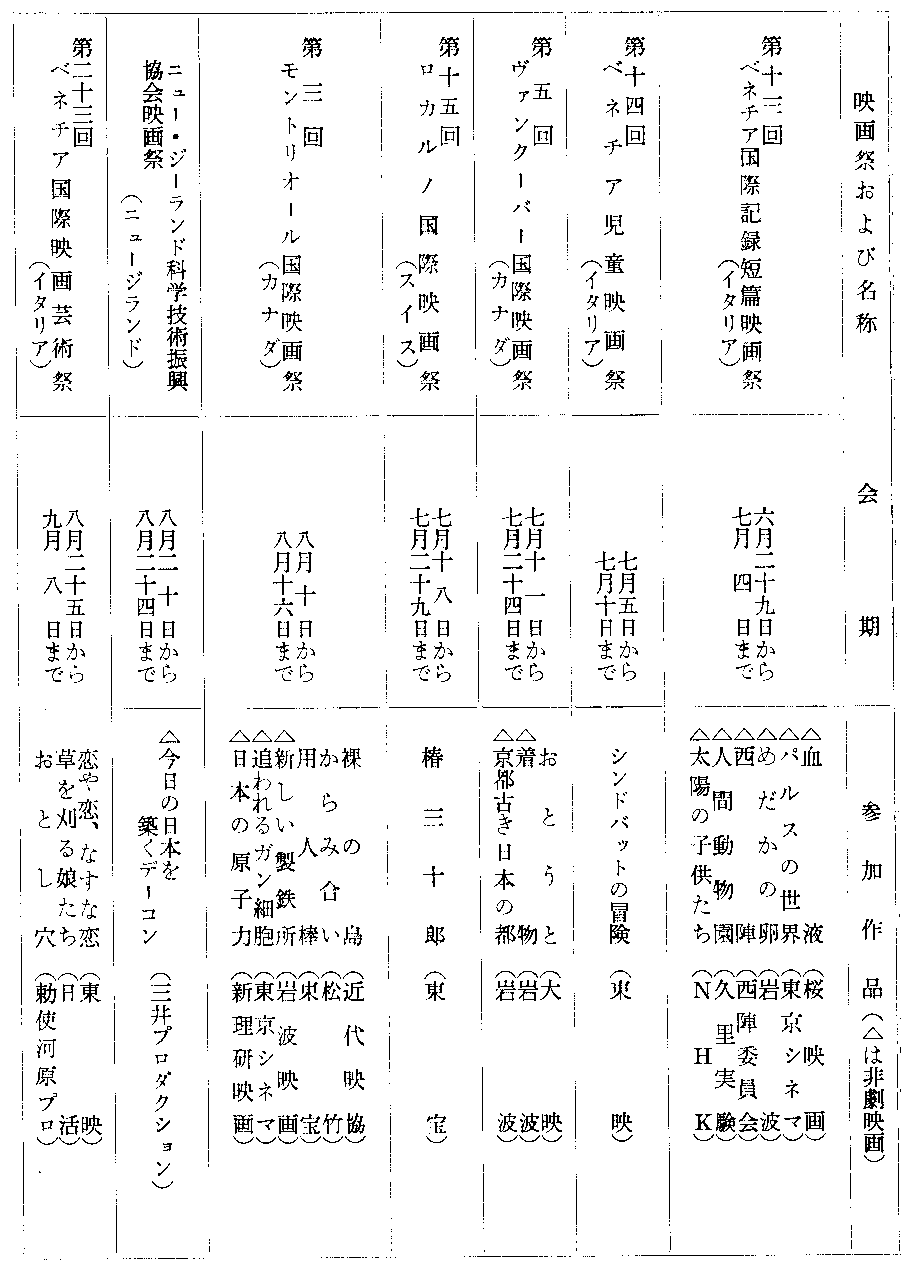
|
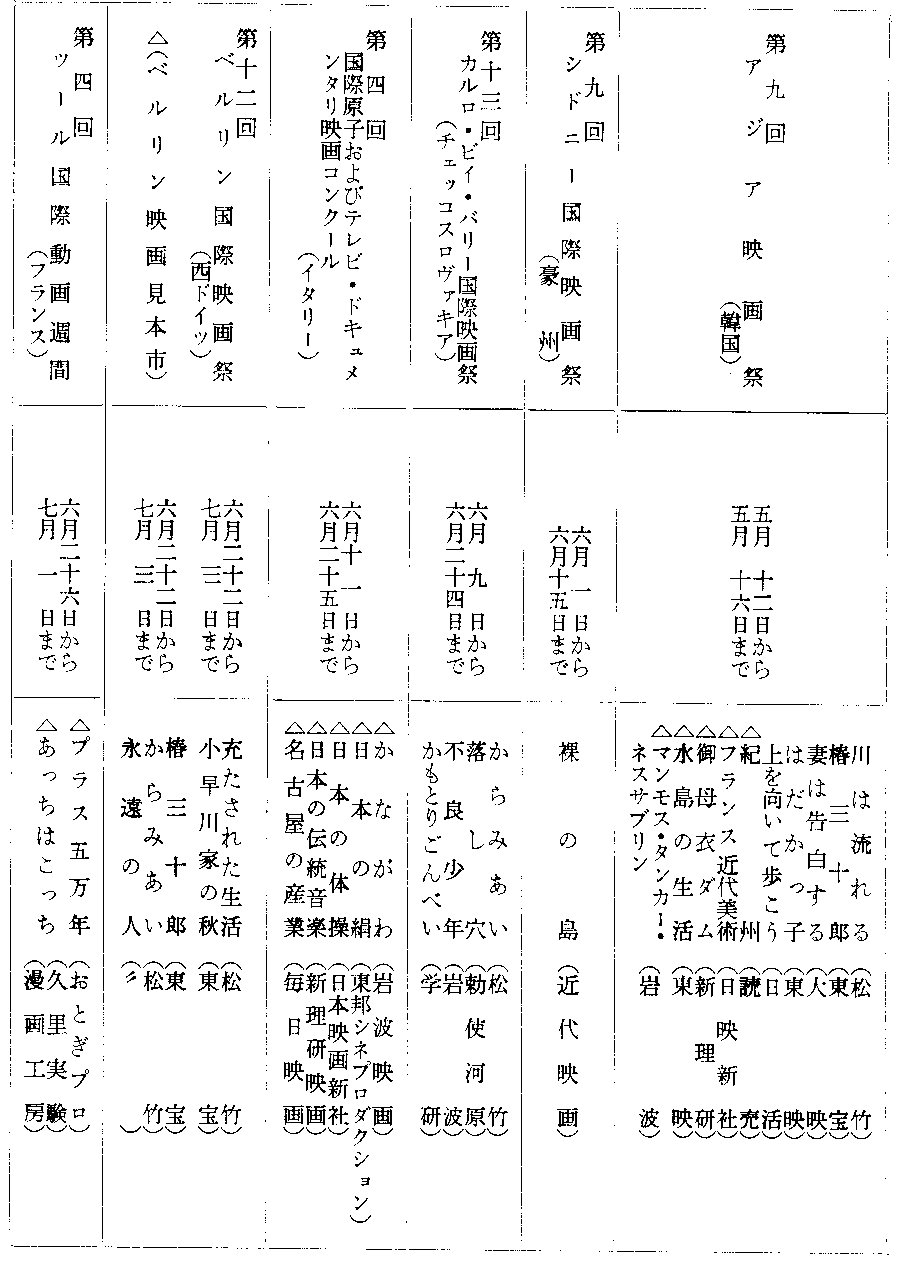
|
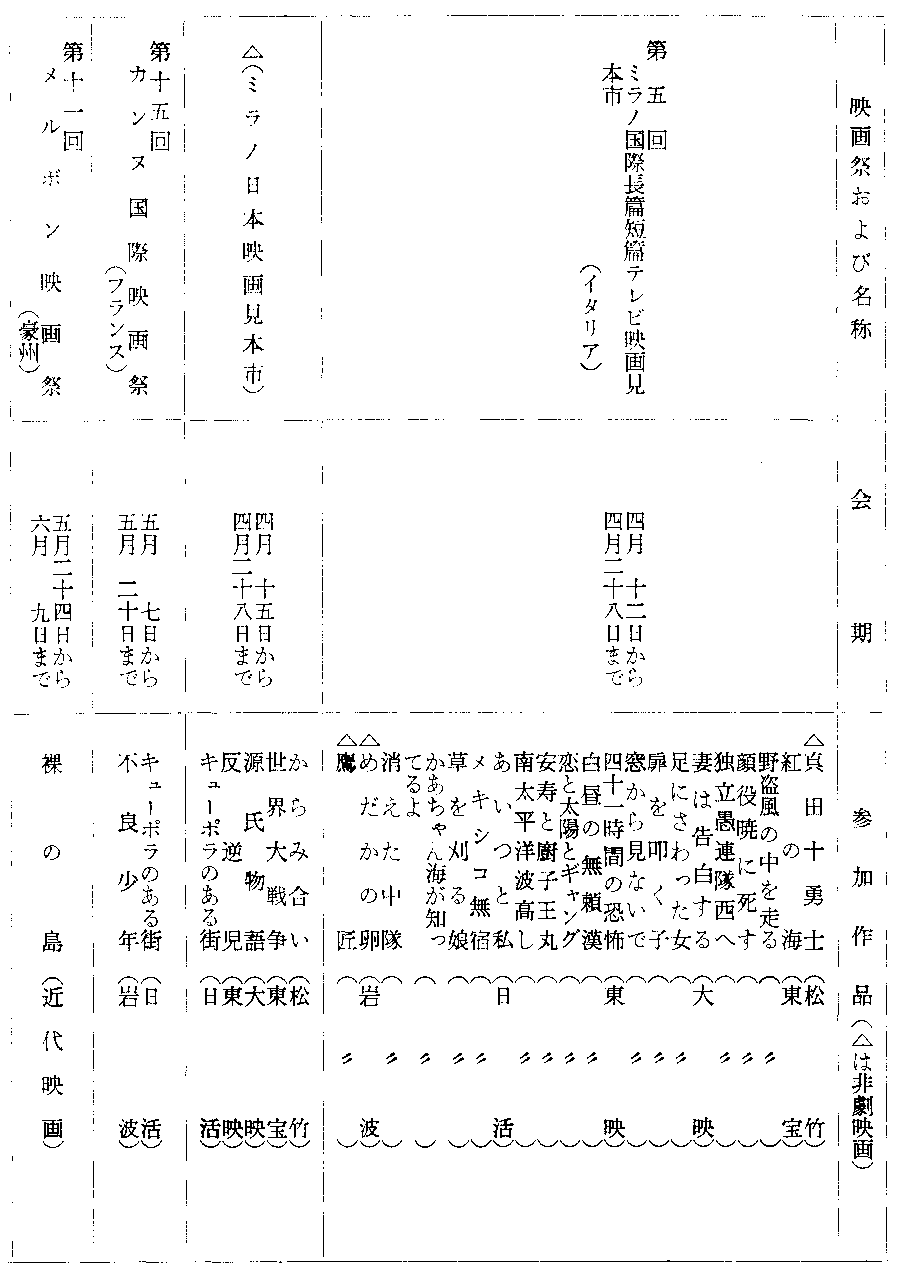
|
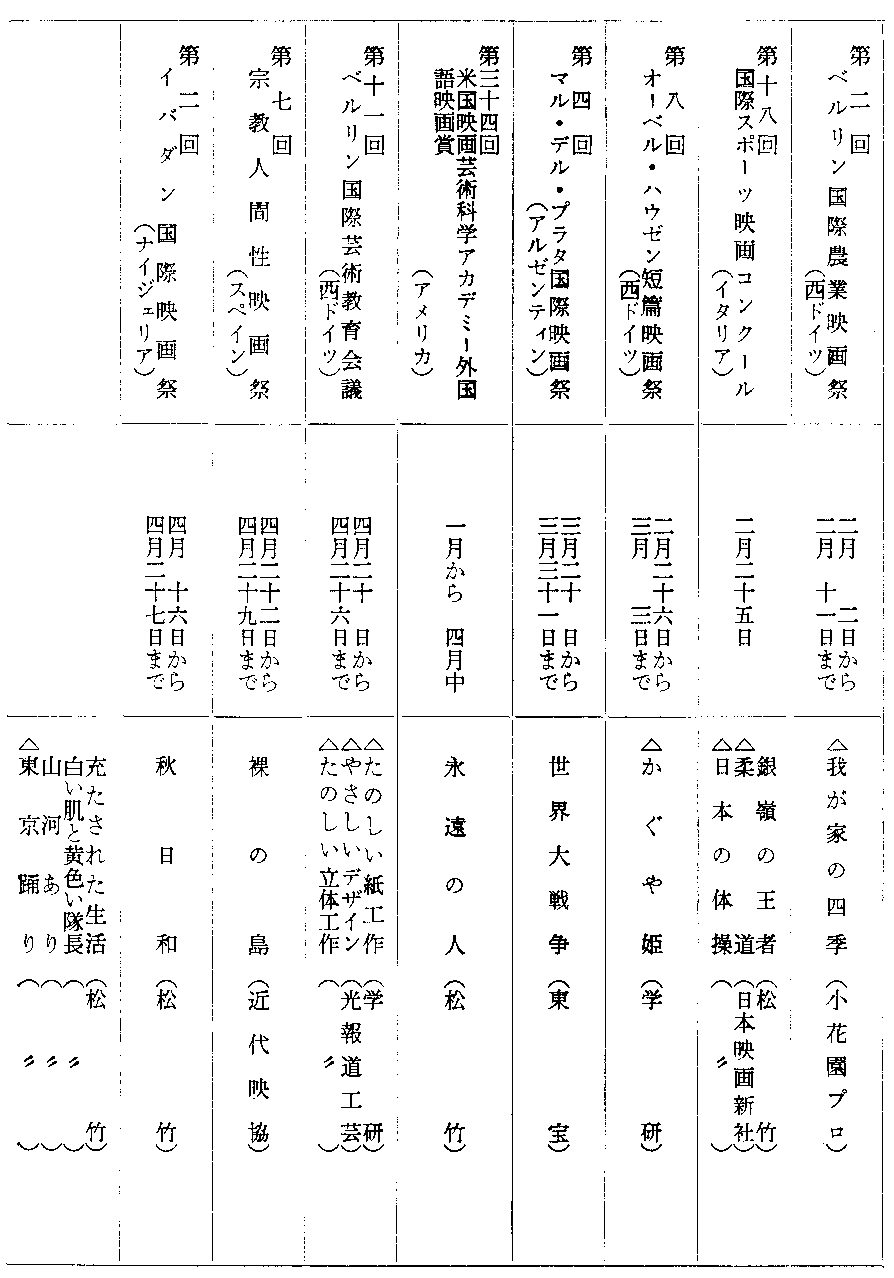
|
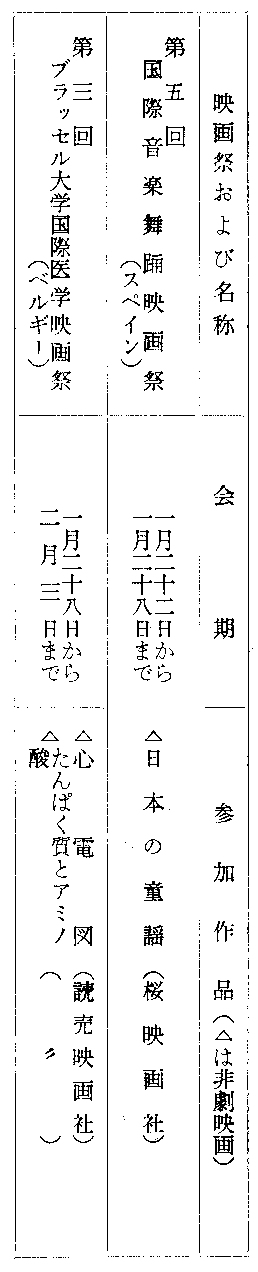
|
国際文化交流の現状
わが国と諸外国との間の文化交流は、民間の創意によって最近とみに活発になってきている。情報文化局では、この民間の事業を奨励するのみならず、できる限り便宜を与えてその拡大をはかっているほか、日本文化の紹介にきわめて有意義であるが、民間事業としては実現が困難なものに重点を置いて、あるいは政府自身の事業として、あるいは国際文化振興会または国際学友会に委託して、文化交流事業を行なっている。
例えば、付表(三〇二ぺージ参照)の主要文化交流事業は、図書の寄贈、文化人の招へいと派遣、巡回劇映画会開催および日本政府の国費による留学生の受入れをのぞいては、ほとんどが民間の事業であって、政府は、これら民間事業に必要に応じてできるかぎりの便宜を与えるほか、文化協定の締結、文化協定に基づく混合委員会の開催、文化および教育の交流に関する日米合同会議の開催、海外の日本文化関係団体の援助、国内補助団体、すなわち国際文化振興会ならびに国際学友会の指導、監督などを通じて、直接、間接に民間事業が円滑かつ効果的に行なわれるよう努力している。
なお、外務省は、右のほか、在外公館に日本文化紹介用の各種展示品(人形、陶器、日本絵画複製品、日本版画など)を送付し、在外公館に随時日本紹介展示会または展示会・劇映画会などを含む日本デー、日本週間を開催させている。
わが国は、戦後、フランス(一九五三年十月三日発効)、イタリア(一九五四牢十一月二十二日発効)、タイ(一九五五年九月六日発効)、メキシコ(一九五五年十月五日発効)、インド(一九五七年五月二十四日発効)、エジプト(一九五七年七月十五日発効)、西ドイツ(一九五七年十月十日発効)、パキスタン(一九五八年十月二十一日発効)、イラン(一九五八年十一月二十日発効)、イギリス(一九六一年七月八日発効)の一〇カ国との間に文化協定を締結した。また、ブラジルとの間にも一九六一年一月二十三日新しい文化協定が署名され、日本側ではすでに国会の承認を得たが、ブラジル側の議会承認の終了を待っている。
これらの文化協定は、締約国政府が両国間に行なわれる各種文化交流事業に対して便宜を与え、また、これを奨励することを規定したもので協定により多少相違はあるが、その概要はつぎのとおりである。
(1) 書籍、講演、演劇、展覧会、映画、ラジオなどによる文化の相互理解の増進に対し、便宜を与える。
(2) 学者、学生、その他文化活動に従事する者の交換を奨励する。
(3) 相手国国民の修学、研究、技術修得に対し、奨学金その他の便宜を与える方法を研究する。
(4) 大学などで、相手国の文化に関する講義の拡充および創設を奨励する。
(5) 相手国の学位および資格をたがいに認めるように、その方法および条件を研究する。
(6) 相手国の文化機関の設立および運営に便宜を与える。
(7) 相手国国民の博物館、図書館の施設の利用に対し、便宜を与える。
(8) その他協定によっては、文学および美術の著作物の翻訳または複製の奨励、文化団体の間の協力の奨励、国際的運動競技の奨励などを規定したものもある。
(1) 文化協定の規定の円滑な履行をはかるため、日仏、日伊、日本・メキシ((附属交換公文による)、日印、日独、日英、日本・ブラジル(未発効)の各文化協定は、それぞれの国の首府に両国の代表五、六名によって構成される混合委員会の設置を規定している。(その他の諸国との文化協定は、単に、両締約国代表が必要に応じて協議することを規定している。)
(2) 一九六二年五月二十九日および同年十月三十日には、日英文化協定に基づく在ロンドン混合委員会が、協定発効後の第一回および第二回の会合を開いた。この両会合には、英国側から、前駐日大使でロンドン・ジャパン・ソサエティ会長のサー・エスラー・デニング(委員長)、英国文化振興会監査役のA・J・S・ホワイトおよびロンドン大学教授のW・G・ビースリーの各氏、また、日本側からは、在英日本国大使館一等書記官の宮川敬と在英実業家でロンドン・日本クラブ文化委員長の藤瀬清氏が参加した。
また、同年六月二十九日には、前記協定に基づく在東京混合委員会の第一回会合が開かれ、日本側から外務省文化参事官の針谷正之(委員長)、文部省調査局長の天城勲および日英協会理事で国際文化振興会評議員の松方三郎の各氏、英国側からは、在日英大使館文化担当官E・W・F・トムリンおよび在日実業家で日英協会理事のP・W・ヒーウェットの両氏が参加した。
これらの会合では、両国間の従来の文化関係の実績が検討され、ついで今後の問題として、大学教授および各分野における専門家の交流の増大、日本語および英語の普及ならびに演劇の交換上演、美術展覧会など開催について意見が交換された。
(3) 一九六三年三月十九日および二十二日の両日、日独文化協定に基づく在ボン混合委員会の第二回会合が、一九六〇年の第一回会合についで開かれ、ドイツ連邦共和国側からは、外務省文化局次長のウォルフガング・ガリンスキー氏(委員長)、連邦内務省文化課長のルッゲ女史、および在日ドイツ大使館一等書記官のタルト・フリーゼ氏、また日本側からは、在ドイツ日本国大使館一等書記官の鹿取泰衛および同三等書記官の川出亮が出席した。この会合では、まず第一回会合以来の文化交流の実績および現状が検討され、ドイツ各地にある独日協会の活動の調整、日独間の学術交流の増大、その他音楽、映画、スポーツ、図書などの交流の増大などについて討議された。
一九六一年六月訪米した池田総理大臣はケネディ大統領との間で文化および教育の交流に関する日米合同会議を設置することに合意した。この会議は、日米両国の代表的学識経験者が一堂に会し、両国間の交化および教育の交流に関するあらゆる問題を自由に討議するとともに、その拡大方法について勧告を行なうことを目的としたものである。
本会議の第一回会合は、一九六二年一月二十五日から同二十一日まで東京で開かれ、日米両国の文化および教育の当面する諸問題、学者・留学生など人物の交流、図書・資料の交換、芸術の交流、日米両国での相手国に関する研究、日本語および英語の語学教育、日米両国の教育文化団体の活動などの諸問題について討議された。これらの問題については、勧告が採択され、さらに、勧告を実現させるため、日米政府ができる限りの措置を講じ、また会談へ参加した民間人も各自の専門分野で、できる限り政府に協力するよう希望が表明された(詳細は、「わが外交の近況」第六号三三六ぺージおよび同資料欄の四九ページ参照)。
本会議の第二回会合は、一九六三年十月中旬ワシントンで開かれることとなっている。
(1) 在ローマ日本文化会館
在ローマ日本文化会館(通称ローマ日本アカデミア)は、日伊文化交流促進のため日本文化の紹介を行ない、かつ、イタリアの学術文化の研究に資することを目的として、外務省が一九五九年から建設していたが、一九六二年十一月完成し、同年十二月開館式が行なわれた。
開館式は、在イタリア門脇大使および国際文化振興会岸信介会長の連名の下に開催され、イタリア政府、外交団、文化団体などの関係者一、五〇〇名を招待し、盛大に行なわれた。
同会館の運営は財団法人国際文化振興会があたり、会館の総長には前国際文化振興会会長岡部長景氏、館長には元東京大学教授でキリシヤ・ラテン文学の権威者である呉茂一氏が就任した。総長は、日本で会館運営委員会の委員長として運営方針の決定を行ない、館長は、ローマでの館務を統轄する。会館の職員は、国際文化振興会から派遣される職員二名、現地採用職員五名で構成されている。
同会館の具体的事業としては、(イ)映画会、講演会、各種展覧会、音楽会、日伊両国学者のゼミナール、図書閲覧、その他による日本文化の普及を行ない、(ロ)イタリアの学術、歴史、美術、宗教、音楽などの文化に関する調査研究に赴く日本人学者、学生または日本研究に従事するイタリア人学者、学生などに対し、便宜を供与することとなっている。
(2) パリ大学都市日本館
パリ大学都市日本館は、通称薩摩会館ともいわれ、一九二七年薩摩治郎八氏によってパリ大学に寄贈されたものであるが、フランス留学中の日本人学生に対する宿舎の提供を主たる任務とし、また、構内に日本関係の図書を蒐集して日本研究に便宜を与えている。外務省は、従来から民間有識者の中から館長を推せんして派遣しており(現館長は、木内良胤氏)、また同館建物の内部修理費などに対し、援助を行なっている。
(3) 株式会社パリ日本館
一九五六年以来パリにおいて文化宣伝、観光宣伝、日本商品の展示即売、ホテル、レストランなどの活動を総合的に行なう機関を設立することを目標として政府および民間で研究が行なわれていたが、民間側では、一九五九年秋、わが国財界の有力者を中心とするパリ日本館建設準備委員会を結成し、政府民間共同出資案に基づいて種々具体的計画が検討された。しかし、一九六〇年十二月にいたり、同準備委員会は、民間資本のみによる株式会社を設立することとなり、一九六一年六月、株式会社パリ日本館が正式に発足した。
同株式会社は、同年九月パリにあるクイーン・エリザベス・ホテルの買収を終り、さしあたって同ホテルをそのまま引継いで経営しているが、一九六三年二月日本料亭「きょうと」および日本商品の展示室を開設した。また、文化宣伝などを行なうため、シャンゼリーゼ通りに建物を物色中である。外務省としては、同館が文化活動などを行なう場合には、これに協力して種々便宜を与える予定である。
(4) その他の海外の文化団体
右に挙げたような団体のほか、諸外国には、わが国との文化交流を主な目的とし、主として現地の国民を中心とする団体が多く設立されている。これら団体は、各種の文化展、映画会、講演会あるいは機関誌の発行などの方法により、日本文化の紹介を行なっており、わが国との友好親善関係の増進に貢献している。このような団体の育成強化は文化交流の促進上きわめて有効なので、外務省は、在外公館を通じてできるかぎりの援助を行なっている。
(1) 国際文化振興会
国際文化交流事業は、政府が直接行なうよりも、政府から独立した機関に委託して行なう方が適当であり、効果があがる場合が多い。現に英国では、英国文化振興会(ブリティッシュ・カウンシル)が公の機関として設立され、政府から六七億円(一九六一年)の補助金を受け、人員一、三〇〇名を擁して、強力な対外文化活動を行なっており、フランスでは、政令により設立された公の機関であるフランス芸術振興会が、六億六、○○○万円(一九六一年)の政府補助金を受けて芸術的催物の国際的交流を行なっている。
わが国の国際文化振興会(略称KBS)は、国際間の文化交流、特に日本文化の海外紹介をはかることを目的として、一九三四年(昭和九年)四月創設された団体であるが、戦前は現在の価格で約三億円の政府補助金と多額の民間寄附金により活発な文化活動を展開し、KBSの名は、海外の文化団体、学界、日本研究家などの間に広く知られていた。戦後になってからも、政府は、一九五三年度から補助金を交付して同会の国際文化活動の拡大をはかってきた。しかし、政府補助金は、戦前の水準に比べてはるかに少額だったので、同会の活動も活発とはいえなかった。
しかし、諸外国、とくに欧米諸国の文化活動が極めて盛んであり、わが国としても、国際文化振興会を通ずる国際文化交流事業の強化拡充の必要が痛感されてきたので、外務省は、関係者と協力して同会の改組強化に努力している。一九六二年二月岸信介新会長を迎え役員の陣容を一新し、その後も、政府補助金の増大、民間からの積極的協力の確保ならびこれにともなう機構の整備と事業の拡大に努力している。
なお、同会の主な事業を挙げれば、つぎのとおりである。
(イ) 文化資料の作成、収集、交換および配布
(ロ) 日本人の海外派遣および外国人の招致ならびにその斡旋
(ハ) 外国人の日本文化研究に対する便宜供与
(ニ) 海外における各種文化関係展覧会などの開催、参加および出品の斡旋
(ホ) 講演会、展覧会、映画会および演奏会などの開催
(ヘ) 内外文化に関する知識の普及
(ト) 図書室、資料室、研究室の設置および運営
(チ) 在ローマ日本文化会館の運営およびニューヨーク駐在員の派遣と活動指導
(2) 国際学友会
日本に来る外国人留学生は日本語を解さず、また、日本人と風俗習慣、宗教、食生活などをいちじるしく異にしていることから、学業、生活などの点で、とくに来日当初は困難を感ずる者が多いが、国際学友会は、これら留学生に宿舎と大学進学前の準備教育を与えることを目的として、一九二一年十二月財団法人として創立されたものである。
政府は、同会の発足当初から補助金を与えこれを援助してきた。戦後も、平和条約の発効とともに諸外国から留学生の来日が急増したので、一九五二年以来国際学友会の事務所および運営組織の充実ならびに宿泊施設および東京本部日本語学校施設の整備、拡充に重点を置いて、補助金を与えてきた。
宿舎は、現在、東京本部だけで収容能力一六五名に達しているが、一九五六年には収容能力六〇名の関西支部が大阪市北区に、また、一九五八年には収容能力一三名の福岡支部が福岡県粕屋郡古賀町に、それぞれ開設され、さらに近く京都に収容能力約五〇名の京都支部が開設されることになっている。
戦後、同会は、国費留学生(日本政府が招致し、奨学金を給与しているもの)、私費留学生を問わずすべての留学生を前述の宿舎に受入れて世話をしてきた。しかし、一九五七年、文部省の外郭団体として日本国際教育協会が発足し、国費留学生の受入団体となったので、学友会本部の国費留学生は同協会の宿舎に転宿し、現在、学友会本部は専ら私費留学生を収容している。
国際学友会東京本部は、宿舎、食堂を設けているほか、日本語学校も運営している。日本語学校は、日本で高等教育または技術研修を受けようとする外国人留学生(学友会在泊者には限らない)に対し、一年乃至一年六カ月を期間として日本語を教授し、併せて基礎的な日本事情を知らせることを目標としており、毎年四月、十月、一月の三回新規学生を受入れている。そのほか、大学進学希望者に対しては、数学、理科、社会などの基礎学科も教授しており、これら課程の修了者には進学をあっ旋している。同校の学生定員は二九五名である。
付表 最近の主要文化交流事業一覧(一九六二年一月から一九六三年三月まで)
美術関係催物
(1) 国内関係
一九六二年
一 月 読売新聞社主催「イタリア彫刻家エミリオ・グレコ展」(三月まで広島、福岡、名古屋、大阪で開催)
一 月 朝日新聞社主催「フランス美術展(第二回ルーブル展)」(三月まで京都で開催)
二 月 文化フォーラム社主催「汎太平洋青年美術家展」(東京で開催、五カ国参加)
二 月 産経新聞社主催「第一回世界児童画展」(三月まで東京で開催、一四カ国参加)
四 月 読売新聞社主催「イスラエル現代絵画展」(東京で開催)
五 月 日本経済新聞社主催「タイ古代美術展」(六月まで東京、名古屋、大阪で開催)
九 月 毎日新聞社主催「サロン・ド・メ展」(十月まで東京、大阪、名古屋で開催)
十 月 国立近代美術館、読売新聞社共催「第三回東京国際版画ビエンナーレ展」(一九六三年二月まで東京、大阪で開催、四四カ国参加
十一月 朝日新聞社主催「ジャン・コクトー芸術展」(一九六三年四月まで大阪、福岡、札幌など全国主要都市で開催)
十一月 朝日新聞社主催「ピカソ・ゲルニカ展」(一九六三年三月まで東京、京都その他主要都市で開催)
十一月 朝日新聞社主催「アメリカ・今日の美術百二人展」(十二月まで東京で開催)
一九六三年
二 月 産経新聞社主催「第二回世界児童画展」(≡月まで東京で開催、二三カ国参加)
三 月 毎日新聞社主催「世界の巨匠名作版画展」(五月まで大阪、名古屋で開催)
三 月 朝日新聞社主催「エジプト美術五千年展」(七月まで東京、京都で開催)
(2) 国外開催
一九六二年
一 月 国際文化振興会、出光興産共催「欧州巡回仙ガイ展」(現在までに、イタリア、フランス、スペインを終了し、引続きスイス、イギリス、オランダ、ドイツで一九六四年三月まで開催の予定)
一 月 リオ近代美術館主催「第六回サンパウロ・ビエンナーレ展日本出品作品展示会」(二月まで開催)
二 月 アーガス・ギャラリー主催「日本現代版画展」(メルボルンで開催)
二 月 フィリピン美術協会主催「第十五回フィリピン美術展」参加(マニラで開催)
四 月 スイス・ルガノ市主催「ルガノ国際版画展」参加(六月まで開催、二九カ国参加)
五 月 石橋財団主催「ブリヂストン美術館展」(パリで開催)
五 月 国際文化振興会主催「米国巡回現代書道二十人展」(一九六三年末まで米国各地で開催)
六 月 ヴェニス市主催「第三十一回ヴェニス・ビエンナーレ展」参加(十月まで開催、三三カ国参加)
七 月 国際文化振興会主催「米加巡回墨絵展」(ヴァンクーヴァー、ワシントンで開催後、一九六四年四月まで米国各地で開催)
七 月 フォルマ・ビヴァ主催「ユーゴー彫刻家シンポジウム」に日本から二名参加(リュブリアナで九月まで開催)
九 月 教育美術振興会主催「日本教育美術展」(シンガポールで開催)
十 月 国際文化振興会主催「中南米巡回学童版画展」(リオ、サンパウロ、ポルトアレグレ、ウルグァイで一九六三年四月まで展示後、パラグァイ、アルゼンティンなどで開催)
十 月 「第一回サイゴン国際美術展」参加(十一月まで開催、二一カ国参加)
十 月 ユーゴー・ザグレブ市主催「国際児童画コンクール」参加
十一月 読売新聞社主催「日本文人画名作展」(一月までパリで開催)
十一月 インド・インドール市主催「国際児童展」(十二月までインドール市で開催)
十一月 シャンカー誌主催「国際児童画展」参加(十二月までインド各地巡回開催)
十一月 在デンマーク日本大使館・日本航空共催「日本人形展」(十二月までコペンハーゲンで開催)
一九六三年
三 月 「第七回イタリア・フォルテ・デ・マルミ児童画展」参加(ローマで八月まで開催)
音楽関係(カッコ内は主催者または招へい者)
(1) 国内公演
一九六二年
一 月 指揮者、サーモ・フーパード(ユーゴー)(東京交響楽団)
四 月 指揮者エドワルド・ヴァン・ルモーテル(白)(日本フィルハーモニー交響楽団)
四 月 アムステルダム・コンセルト・ヘボウ管弦楽団 (蘭)(大阪国際フェスティバル協会)
四 月 ヴィトルオージ・デイ・ローマ (伊)( 〃 )
四 月 ニカノール・ザバレタ(ハープ) (西)( 〃 )
四 月 クリステル・ゴルツ(ソプラノ) (独)( 〃 )
四 月 フリッツ・ウール(テノール) (独)( 〃 )
四 月 ジョゼフ・メルテルニッヒ(バリトン) (独)( 〃 )
四 月 アンドレ・ナヴァラ(チェロ) (仏)( 〃 )
四 月 パブロ・カザルス(チェロ)(西)(東京放送)
九 月 ヤナチェック弦楽四重奏団(チェッコ)(日本経済新聞社)
十 月 バイエルン舞踊団(独)(読売新聞社)
十一月 ベルリン室内管弦楽団(独)(吉田音楽事務所)
十一月 ベルリン国立バレエ団(独)(読売新聞社)
一九六三年
二 月 北京曲技団(中共)(アート・フレンド・アソシエーション)
三 月 デットモルト管楽合奏団(西独)(読売新聞社)
(2) 国外公演
一九六二年
二 月 大谷例子(ソプラノ)、シンガポールおよびマニラでの演奏会開催
二 月 指揮者朝比奈隆、サンタ・チエテリア音楽院管弦楽団、北ドイツ放送交響楽団、ベルリン国立歌劇場管弦楽団スロヴァキアン・フィルハーモニー、ドレスデン・フィルハーモニー客演指揮のため渡欧
二 月 藤原義江、砂原美智子など、韓国日報社の招待により訪韓
四 月 ソ連作曲家大会へ作曲家間宮芳男の参加
四 月 歌劇「修善寺物語」の米国の初演に作曲家清水脩参加
四 月 第二回国際チャイコフスキー・コンクールでヴァイオリニスト久保陽子三位入賞
五 月 イタリアにおける第二十二回作詞作曲家国際連合会議に日本音楽著作権協会会長西條八十参加
五 月 指揮者山田和男、アルゼンティン国立放送管弦楽団、チリ・フィルハーモニー客演指揮
六 月 ダーク・ダックス一行のソヴィエト各地での三三回の公演開催
八 月 第五回スペイン国際音楽講習会へ日本人音楽家八名参加
九 月 米国のヴァン・クラィバーン国際ピアノコンクールで弘中孝、および中村紘子八位入賞
十 月 ジェノアのパガニーニ・ヴァイオリン国際コンクールで広瀬悦子二位入賞
十 月 パリにおける作詞作曲家協会国際連合に日本音楽著作権協会会長西條八十参加
十 月 N・H・K交響楽団、東南アジア各地(香港、シンガポール、マラヤ、フィリピン、沖縄)で演奏会開催
十 月 ミュンヘンの第五回国際教育音楽会議に武蔵野音楽大学学長福井直弘参加
十一月 東京都とアムステルダム市との日蘭交歓放送音楽会開催(日本側録音をアムステルダムで放送)
十一月 ニューヨーク・リンカーン・センターで作曲家衛藤公雄演奏会開催
十二月 ニューヨーク・カーネギー・ホールで木琴奏者平岡養一演奏会開催
一九六三年
二 月 指揮者朝比奈隆、ボン市立交響楽団客演指揮のための渡欧
三 月 開西学院グリー・クラブ、台湾各地で演奏会開催
三 月 ヴァイオリニスト辻久子、西独およびスイス各地で演奏会開催
芸能関係
一九六三年
一 月 日本舞踊団の東南アジア巡回公演
期 間 一月九日-二十三日
公演地 タイ、マラヤ、インドネシア。
この公演は国際文化振興会が外務省と協力して、日劇ダンシング・チームを派遣して行なったもので、往復旅費、諸準備費は振興会が負担し、現地で要した費用は現地受入団体が負担した。
二 月 花柳秀実舞踊団のアジア巡回公演
期 間 二月八日-十五日
公演地 香港、カンボディア
往復旅費、諸準備費は花柳舞踊団が負担し、現地で要した費用は現地の受入団体が負担して行なわれ、国際文化振興会はこれを後援した。
スポーツ関係
(1) 国内開催
一九六二年
四 月 ハンガリー水泳コーチの来日(滞在費、日本水泳連盟負担)
四 月 米国水泳選手団の来日( 〃 )
四 月 西独サッカー・チームの来日(往復航空賃および滞在費、日本蹴球協会負担)
五 月 ポーランド・バレーボール・チームの来日(滞在費、日本バレーボール協会負担)
六 月 米国高校レスリング・チームの来日(滞在費、日本アマチュア・レスリング協会負担)
六 月 米国バスケットボール・チームの来日(滞在費、日本バスケットボール協会負担)
六 月 韓国高校バスケットボール・チームの来日(滞在費、日本バスケットボール協会負担)
八 月 ニュー・ジーランド庭球チームの来日(滞在費、日本庭球協会負担)
八 月 米国水泳選手団の来日(滞在費、日本水泳連盟負担)
九 月 インド・サッカー・チームの来日(滞在費、日本蹴球協会負担)
九 月 豪州水泳選手団の来日(滞在費、日本水泳連盟負担)
十 月 第三回世界アマチュア・ゴルフ選手権大会の開催(川奈)(滞在費、日本ゴルフ協会負担)
十 月 スウェーデン庭球選手の来日(往復航空賃および滞在費、日本庭球協会負担)
十 月 韓国済州島高校サッカー・チームの来日(滞在費、日本蹴球協会負担)
十 月 中共卓球選手団の来日(滞在費、日本卓球協会負担)
十一月 チェッコ、ハンガリー、スイス、フランス体操選手の来日(往復航空賃および滞在費、日本体操協会負担)
十二月 ソヴィエト・サッカー選手団の来日(滞在費、日本蹴球協会負担)
十二月 スウェーデン・サッカー選手団の来日(滞在費、日本蹴球協会負担)
一九六三年
二 月 ソヴィエト・レスリング・チームの来日(滞在費、日本レスリング協会負担)
二 月 ノールウェー、フィンランド、スウェーデン・スキー選手の来日(往復航空賃および滞在費、日本スキー連盟負担)
三 月 フランス・スキー選手の来日(往復航空賃および滞在費、日本スキー連盟負担)
三 月 世界スピード・スケート選手権大会の開催(軽井沢)(滞在費、日本スケート連盟負担)
(2) 国外開催
一九六二年
一 月 インド国際庭球選手権大会に選手派遣(航空賃および滞在費、インド側負担)
一 月 水泳選手団の豪州、ニュー・ジーランド訪問(航空賃および滞在費、水泳連盟および豪州、ニュー・ジーランド側折半負担)
二 月 体操選手の西独、南アフリカ共和国訪問(航空賃および滞在費、西独および南アフリカ側負担)
二 月 男子体操選手団のユーゴー、イタリア、西独訪問(滞在費の一部、先方負担)
二 月 女子水泳選手のハワイ訪問(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
二 月 ポーランド、フランスでの世界スキー選手権大会に選手派遣(航空賃および滞在費、日本スキー連盟負担)
二 月 フィリピン庭球選手権大会に選手派遣(航空賃および滞在費、フィリピン側負担)
三 月 水泳選手団の南アフリカ共和国訪問(航空賃および滞在費、南アフリカ側負担)
三 月 ユニバーシアード冬期大会(スイス)に選手団派遣(航空賃および滞在費、日本スキー連盟負担)
三 月 チェッコスロヴァキア世界フィギュア・スケート選手権大会に代表派遣(航空賃および滞在費、日本スケート連盟負担)
三 月 ノールウェー・ホルネンコーネン・スキー大会に選手派遣(滞在費、ノールウェ一側負担)
三 月 女子体操選手の西独訪問(航空賃および滞在費、西独側負担)
三 月 ボクシング・チームのフィリピン訪問(航空賃および滞在費、日本ボクシング連盟負担)
四 月 水泳コーチを米国へ派遣(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
四 月 水泳コーチをタイへ派遣(航空賃および滞在費、タイ側負担)
五 月 ウィンブルドン庭球選手権大会に選手派遣(滞在費、英国側負担)
六 月 水泳コーチを韓国へ派遣(航空賃および滞在費、韓国側負担)
六 月 アラブ連合へ日本女子水泳選手団派遣(航空賃および滞在費、アラブ連合側負担)
六 月 水泳コーチを米国へ派遣(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
六 月 チェッコ世界体操選手権大会に選手派遣(滞在費、チェッコ側負担)
六 月 世界卓球選手権大会(北京)に選手派遣(滞在費、中共側負担)
七 月 マラヤ庭球選手権大会に選手派遣(滞在費、マラヤ側負担)
七 月 カナダ・ジュニア庭球選手権大会に選手派遣(滞在費、カナダ側負担)
八 月 マラヤ独立記念祭サッカー大会に選手派遣(滞在費、マラヤ側負担)
八 月 選抜高校バスケットボール・チームの韓国訪問(滞在費、韓国側負担)
八 月 ミラノの世界自転車選手権大会へ代表派遣(航空賃および滞在費、日本自転車競技連盟負担)
八 月 水泳選手(飛込)を米国へ派遣(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
八 月 水泳選手団(競泳)を米国へ派遣(〃)
八 月 アジア競技大会、インドネシアで開催(航空賃および滞在費、日本体育協会負担)
八 月 水泳コーチをハンガリーへ派遣(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
八 月 サッカー・コーチを西独へ派遣(滞在費、西独側負担)
九 月 ハンガリーの世界ウェイト・リフティング大会へ選手団派遣(滞在費、ハンガリー側負担)
九 月 ポーランドのバレーボール大会へ選手団派遣(滞在費、ポーランド側負担)
十 月 モスクワの世界バレーボール選手権大会へ代表派遣(滞在費、ソ連側負担)
十 月 モスクワの日ソ体操対抗競技会へ代表派遣(滞在費、ソ連側負担)
一九六三年
一 月 オーストリア・インスブルグのプレ・オリンピック大会へ日本選手団派遣(滞在費、オーストリア側負担)
一 月 マニラのアジア・アマチュア・ゴルフ選手権大会へ選手派遣(滞在費、フィリピン側負担)
一 月 水泳コーチなどを西独へ派遣(航空賃および滞在費、日本水泳連盟負担)
二 月 マニラ庭球選手権大会へ選手派遣(滞在費、フィリピン側負担)
二 月 オーストリア、アルペン・スキー選手権大会へ選手派遣(滞在費、オーストリア側負担)
二 月 北米スキー選手権大会へ選手派遣(滞在費、米国側負担)
二 月 ノールウェー、ホルネンコーネンのスキー大会へ選手派遣(滞在費、ノールウエ一側負担)
二 月 オーストラリアへ水泳選手団の派遣(航空賃および滞在費、水泳連盟および豪州側折半負担)
三 月 チェッコの世界卓球選手権大会へ選手派遣(滞在費、チェッコ側負担)
三 月 イタリア世界フィギュア・スケート選手権大会へ選手派遣(滞在費、イタリア側負担)
三 月 モスクワの第六回ウェイト・リフテイング世界選手権大会へ代表派遣(滞在費、ソ連側負担)
図書展示および寄贈
(1) 国内関係
一九六二年
四 月 第四回東京国際書籍展示会開催(二二カ国から約一万冊出品、展示委員会代表者は日本出版貿易株式会社社長望月政治)
一九六三年
一 月 ドイツ外務省から国立国会図書館に対し図書五三四冊寄贈
一 月 日本巡回「ソ連邦学術図書雑誌展」開催(六月まで、在京ソ連大使館および出版文化国際交流会共催、出品数一、五〇〇冊)
(2) 国外関係
一九六二年
一 月 エル・サルヴァドル大学に外務省から文化紹介英文資料五一冊寄贈
一 月 ベルギー国ガン大学に外務省から文化紹介英文資料一〇四冊寄贈
一 月 インドネシア大学に外務省から文化紹介英文資料九七冊寄贈
二 月 ベルギーのブラッセル大学に外務省から文化紹介英文資料九六冊寄贈
二 月 アラブ連合のカイロ市長に外務省から庭園関係資料五冊寄贈
三 月 デンマークのコペンハーゲン市立図書館に外務省から文化紹介英文図書一〇七冊寄贈
三 月 英文「美術大観」(Art Treasures of Japan)上、下巻合計五二八冊を外務省から各国の大学、図書館などに寄贈(六一年十一月の事業の追加)
三 月 ブラジル大学での第二回国際技術図書展に出版文化国際交流会から学術書二三冊を展示し、その後同大学に寄贈
三 月 タイの農学生物学会に外務省から農業関係図書一二冊寄贈
五 月 ハンガリーの東亜美術館に対し外務省から文化紹介英文図書九冊寄贈
五 月 ネパールの日本文化協会に外務省から文化紹介英文図書二二冊寄贈
六 月 米国南カリフォルニア大学に対し外務省から文化紹介英文図書七五冊寄贈
八 月 ペルーの中央日本人会に外務省から小・中・高校教科書一、六〇冊寄贈
八 月 ニュー・ジーランドで開催の児童書籍展に外務省から児童図書二四冊展示、展示会終了後パルマーストン・ノース公立図書館に寄贈
九 月 インド国際美術図書展に外務省から英文美術図書一七冊展示
九 月 ブラジルの日伯文化協会参考図書館に外務省から文化紹介英文図書六一冊寄贈
十 月 外務省から文化紹介英文図書一〇七冊提供し、デンマークのコペンハーゲン市立図書館で日本図書の展示を行ない、展示終了後は同図書館へ寄贈
十 月 サラワク中央図書館に外務省から文化紹介英文図書七七冊寄贈
十 月 カナダのトロント大学に対し外務省から古典文学を中心とした図書二〇六冊寄贈
十 月 米国の南カリフォルニア日系人商業会議所に外務省から文化紹介英文図書一三五冊寄贈
十一月 米国のシカゴ定住者会図書館に日本出版貿易株式会社から文化紹介図書四九冊寄贈
十一月 トルコの世界児童図書展に外務省から児童図書六〇冊展示
十一月 ユーゴースラヴィアのベルグラード国際図書展に出版文化国際交流会の寄贈により文化紹介図書八二冊展示
十一月 インドのインドール国際児童展に外務省より児童図書二九冊展示
十一月 シンガポール国立図書館に外務省から文化紹介英文図書八九冊寄贈
十一月 ドイツの一九六二年フランクフルト国際図書展に代表的新刊図書二三二冊出品(日本側代表は出版文化国際交流会)
十一月 池田総理の訪独を記念して、外務省からドイツ三大学に古典文学を中心とした図書六一八冊寄贈(フランクフルト大学一五七冊、マールブルグ大学三四六冊、ボン大学二五冊)
十一月 タイの世界図書展に外務省から文化紹介英文図書三〇〇冊展示
十二月 パキスタンの国際図書展に出版文化国際交流会の協力により外務省から図書一四九冊展示
十二月 ブラジルのサンパウロ日本文化センターに外務省から文化紹介英文図書一一六冊寄贈
一九六三年
一 月 アフガニスタン文部省および同国カブール大学に対し外務省から文化紹介英文図書をそれぞれ四三冊寄贈
一 月 タイ国プラサン・ミトル・カレッジに外務省より文化紹介英文図書八冊、文部省から文教関係資料六冊寄贈
三 月 イタリア中亜極東協会に外務省から文学関係資料一八冊寄贈
三 月 ブラジルのゴヤス大学主催国際図書展に外務省から図書一三冊を展示し、展示会終了後は同大学に寄贈
三 月 エティオピアのハイレ・セラシー大学に外務省から基本的日本紹介英文図書二四一冊寄贈
三 月 デンマークのオーフス大学に一九六二年フランクフルト国際図書展出品図書二二〇冊を一括出版文化国際交流会から寄贈したほか、外務省から文化紹介英文図書三七冊寄贈
三 月 米国のニュー・オルリンズ市立図書館に外務省から英訳日本文学八冊寄贈
三 月 アルゼンティン俳優協会に外務省から演劇関係英文図書十二冊寄贈
三 月 英国シェフィールド大学に外務省から日本研究英文図書八冊寄贈
三 月 カンボディア王族などに外務省から美術、演劇関係図書一〇冊寄贈
三 月 エクアドル土木省に外務省から建築関係図書七冊寄贈
三 月 アフガニスタン婦人協会に外務省から家事関係図書一〇冊寄贈
柔道教師派遣
一九六二年
十 月 サウディ・アラビアのファラーハ学校の招きにより柔道教師一名派遣(期間十月-六三年三月)
一九六三年
二月から三月 外務省から講道館六段池田幹氏をアフリカ諸地域に派遣(セネガル、コンゴー、南アフリカ共和国、南ローデシア、ケニヤ、エティオピア、アラブ連合)
華道使節派遣
一九六二年
十 月 外務省事業として草月流山中阿屋子、吉田とみ両師範を豪州、ニュー・ジーランドおよびインドネシアへ派遣(十二月まで)
十一月 外務省の援助による草月流勅使河原蒼風のフランス、チェッコスロヴァキア、オーストリア、ベルギー、イタリア訪問
一九六三年
一 月 外務省事業として池坊の渡辺芙紗子、奥山喜美子両師範をパキスタン、インド、セイロン、シンガポール、香港、中国に派遣(二月まで)
一 月 外務省事業として小原流の平賀豊英、藤田桂子両師範をビルマ、マラヤ、タイ、ラオス、ヴィエトナム、カンボディア、フィリピンに派遣(二月まで)
人物交流
(1) 海外訪問
一九六二年
一月~三月 東京工業大学永井道雄助教授(社会学)の外務省派遣による香港大学訪問
二 月 森戸辰男広島大学学長の国際大学協会理事会(インド)出席
二 月 山口県立萩高等学校教諭ほか一名の欧米各国教育事情視察旅行
三 月 中央青少年問題協議会委員の欧米各国視察旅行
四 月 小原流藤原豊芽女史のケルンにおける生花講座開設(四月から約三カ月)
五 月 文部省天城調査局長および国際学友会金沢理事のインドネシア、シンガポール、マラヤ、香港における日本留学生応募状況および留学生帰国後の実情視察
七 月 日本私立幼稚園連合会員(八名)のロンドンでの第九回幼年教育国際会議出席および欧州諸国の教育事情視察
七 月 日本私立中学・高等学校連合会代表の世界教育者会議出席
七月-八月 チェッコスロヴァキア政府の招待による日本学術会議桑原副会長ほか五名のチェッコおよび欧州諸国訪問
八 月 総理府中央青少年問題協議会の派遣による日本青年代表団の中南米諸国(一五名)および欧州諸国(一六名)訪問
八 月 アラブ連合共和国政府の招待による鹿児島大学今田教授(水産学)の同国訪問講義
九 月 スウェーデン赤十字社主催による「スウェーデンお伽の国への旅」へ崎田少年の招待
九 月 総理府中央青少年問題協議会の派遣による日本青年代表団の東南アジア各国(第一班一八名)および北米(二八名)訪問
九 月 公立の小・中および高等学校長(計四九名)の米英両国の教育事情視察
十 月 総理府中央青少年問題協議会の派遣による日本青年代表団(東南アジア第二班一八名および第三班一五名)の東南アジア諸国訪問
十 月 昭和三十七年度海外婦人教育事情視察団の米国、カナダおよび欧州への派遣
十一月 ニューヨーク・ミラー紙主催の少年討論会に日本代表木村少年の参加
十二月 日本ボーイ・スカウト連盟久留島理事長ほか六名の第三回極東地域スカウト会議への参加
十二月 イラクのバグダッドおよびアル・キンディ千年祭に東京大学江上教授の出席
一九六三年
一 月 山口県教育委員会派遣教員二名の欧米の小・中・高等学校教育事情視察
一 月 インドの玩具贈与協会提案による日本子供使節の同国訪問
一 月 東京大学岡津助教授(教育学)の教育学者の相互連絡をはかるための東南アジア、中近東諸国訪問
二 月 早稲田および慶応両大学学生一〇六名の中米(エル・サルヴァドル、グァテマラおよびメキシコ)親善旅行
三 月 東大、東工大、早大および慶大の四大学工科系学生(計六三名)のフランスエ業事情見学旅行
三 月 東京教育大学内藤農学部教授のインド農業事情調査
三 月 外務省派遣東京大学中屋健弌教授の中南米七カ国巡回講演
(2) 日本訪問
一九六二年
一 月 シンガポール南洋大学学生一八名の来日
三 月 イギリス・ベッドフォード公爵(美術蒐集家)の来日
三 月 ガーナ大学アシュヘーネ教授の来日
三 月 外務省招客、フランス原子力庁サクレー原子力研究所長ジャン・ドビエス博士の来日
三 月 外務省招客、イギリス建築評論家ジェームズ・モード・リチャーズ氏の来日
三 月 外務省招客、デンマーク・オーデンセ市博物館長スベン・ラーセン氏の来日
五 月 外務省招客、ニュー・ジーランド・ウェリントン師範学校ブルムハルト女史の来日
五 月 ヴィエトナム芸術使節団(計一八名)の来日
六 月 パリ高等鉱山学校学生団の来日
七 月 スペイン・マドリッド高等建築学校教授および学生(三〇名)の日本建築事情視察
八 月 全国市長会とフランス青少年交換共同管理委員会との間の日仏青少年交歓協定による第一回フランス青年団(二〇名)の来日
八 月 外務省招客、インドネシア・バンドン外国語大学学長スルジャマン氏の来日
八 月 ドイツの日本見学学生団(八○名)の来日
八 月 ドイツ・ケルン日独協会副会長ラインボーチ博士の来日
九 月 ニュー・ジーランド、オークランド大学地理学主任教授カンバーランド氏の来日
九 月 フィリピン、ユニバーシティ・オブ・イーストのアキノ教授の来日
九 月 ロンドン大学ハンスフ才ード教授の来日
九 月 タイ文部省視学官カセムスリ・ナ・アユジャ女史の日本初等教育状況視察のための来日
十 月 外務省招客、ドイツ・フンボルド財団事務局長プアイファー氏の来日
十 月 南アフリカ共和国ウイトワータスランド大学リチャード・ダニール教授の来日
十 月 スウェーデン建築家協会会員日本視察団(四〇名)の来日
十一月 外務省招客、フィリピン演劇家ニカノール・アグド氏の来日
十一月 外務省招客、デンマーク王室芸術院教授グンナル・ピーターセン博士の来日
十二月 外務省招客、イタリアの日本文学研究家マリ才・テーティ氏の来日
一九六三年
一 月 英国文化振興会(ブリティシュ・カウンシル)会長ポール・シンカー卿夫妻の来日
二 月 エル・サルヴァドルから科学使節団(二三名)が同国親善使節団の一部として来日
三 月 米国ユタ大学オルピン学長夫妻の来日
三 月 外務省招客、ドイツ学術交換奉仕会(DAAD)シヤィベ事務局長の来日
三 月 外務省招客、フランス給費外国人留学生受入事務局長ラブルース女史の来日(夫君のパリ大学経済史学教授ラブルース氏と同行)
三 月 外務省招客、ドイツのノーベル賞受賞者アドルフ・ブテナント博士(生化学者)の来日
三 月 外務省招客、アルゼンティンのノーベル賞受賞者ベルナルド・フーサイ博士(医学者)の来日
三 月 総理府の第一回東南アジア諸国青年招待計画による各国青年運動代表者一三名の来日[内訳は、中華民国(一名)、インド(二名)、フィリピン(二名)、シンガポール(一名)、タイ(二名)、ヴィェトナム(二名)、インドネシア(二名、ただし在日留学生)およびカンボディア(一名)]
学術探検および登山隊派遣
一九六二年
一 月 京都大学のアマゾン上流地域学術調査隊派遣(隊長徳田喜三郎コロンビア国立大学教授以下三名)(期間一月-五月)
二 月 亜細亜大学のアジア・アフリカ諸国踏査隊派遣(隊長深沢実同大学助教授以下七名)(期間二月-五月)
二 月 全日本山岳連盟の一九六二年ヒマラヤ遠征隊派遣(隊長高橋煕連盟常任理事以下八名)(期間二月-七月)
三 月 日本大学のムクト・ヒマル学術調査隊派遣(隊長同大学OB石坂昭二郎以下四名)(三月-八月)
五 月 北海道大学の東北ネパール学術調査隊派遣(隊長中野征紀同大学教授以下七名)(期間三月-六月)
三 月 明治大学のアラスカ第二次学術調査隊派遣(隊長岡正雄同大学教授以下五名)(期間三月-八月)
三 月 大阪府立大学のネパール・ヒマラヤ学術調査隊派遣(隊長中尾佐助同大学教授以下九名)(期間三月-十一月)
四 月 東京農業大学のネパール・アルン川流域農業調査隊派遣(隊長栗田匡一同大学講師以下六名)(期間四月-六三年三月)
四 月 早慶両大学学生交流会の早慶学術調査隊派遣(隊長慶大学生坂東健史以下六名)(期間四月-十二月)
四 月 京都大学山岳会のサルトロカンリ登山隊派遣(隊長四手井綱彦同大学教授以下一〇名)(期間四月-九月)
五 月 早稲田大学のペルー・アンデス遠征登山隊派遣(隊長同大学OB吉川尚郎以下五名)(期間五月-十一月)
五 月 東京大学の全アフリカ踏査隊派遣(隊長同大学OB立本尉夫以下七名)(期間五月-十二月)
六 月 慶応大学のメキシコ経済学術調査団派遣(隊長同大学助教授安原基輔以下一一名)(期間六月-九月)
六 月 京都大学の同大学学生によるカナダ学術調査隊派遣(隊長同大大学院学生栗本武以下三名)(期間六月-八月)
七 月 北海道大学の北米大陸国立公園学術調査隊派遣(隊長同大学学生上原鉄造以下六名)(期間七月-九月)
七 月 慶応大学の中近東学術調査研究団派遣(隊長土屋健三郎同大学助教授以下一〇名)(期間七月-九月)
七 月 慶応大学のインド学術調査隊派遣(隊長西岡秀雄同大助教授以下九名)
八 月 京都大学山岳部のパンジャブ、ヒマラヤ遠征隊派遣(隊長小野寺幸之進同大学教授以下七名)(期間八月-十一月)
九 月 名古屋大学および名城大学のアフリカ調査隊派遣(隊長諏訪兼位同大学助手以下五名)(期間九月-十二月)
九 月 早稲田大学のイシド・ネパール農村調査隊派遣(隊長同大学学生松沢憲夫以下二名)(期間九月-十二月)
十 月 大阪市立大学および京都大学のカンボディア学術調査隊(隊長同大学石井健一助手以下七名)(期間十月-六三年二月)
十 月 慶応大学の東南アジア民族美術調査団派遣(隊長同大学学生湊邦彦以下五名)(期間十一月-十二月)
十一月 名古屋大学の茶樹の起源に関する学術研究調査団のインド、ビルマ、セイロン各国への派遣(隊長志村喬同大学教授以下三名)(期間十一月-六三年二月)
一九六三年
二 月 大阪外国語大学のメキシコ学術調査団派遣(隊長山田善郎同大学助手以下六名)(期間二月-五月)
三 月 東京農業大学の東部ネパール学術調査隊派遣(隊長同大学OB日本山岳会織内信彦評議員以下七名)(期間三月-六月)
三 月 神戸大学の中(台湾)日親善学術調査隊派遣(隊長田中薫同大学名誉教授以下九名)(期間三月-四月)
三 月 千葉大学のロールワリン・ヒマール学術調査隊派遣(隊長沼田真同大学助教授以下六名)(期間三月-七月)
三 月 全日本山岳連盟のヒマラヤ遠征隊派遣(隊長日本電信電話公社勤務善行久親以下七名)(期間三月-五月)
留学生関係
日本政府の外国人留学生招致
(1) 文部省予算による国費外国人留学生招致制度
この制度により、昭和三十七年度、九八名の外国人留学生が招かれた。この制度による留学生は、学部留学生(アジア、中近東地域諸国からの留学生のみを対象とし、期間五カ年、ただし、医科および歯科は、七カ年)と研究留学生(期間ニカ年)の二種類がある。いずれも月額二万五、○○○円の奨学金が支給されており、このほかに、アジア中近東地域諸国からの留学生に対しては往復航空賃(ツーリスト・クラス)が、また、研究留学生に対しては年額二万五、○○○円の国内研究旅費がそれぞれ支給されている。招致留学生の国別内訳は、つぎのとおりである。
(イ) アジア、中近東地域諸国七九名
パキスタン九、セイロン五、ビルマ八、タイ一九、カンボディア四、ヴィエトナム七、フィリピン六、中華民国四、インド一一、マラヤ三、シンガポール四、イラン三、アラブ連合二、イスラエル一、イラク一、トルコ一
(ロ) 米州および大洋州地域九名
豪州一、ブラジル四、ペルー一、メキシコ一、カナダ一、アメリカ合衆国一
(ハ) 欧州地域一〇名
ドイツ二、イタリア一、フランス一、英国一、オーストリア二、スウェーデン一、ユーゴースラヴィア一、チェッコスロヴァキア一
(2) 科学技術庁予算による外国人研究者招致制度
この制度によりに昭和三十七年度にオーストラリアから二名、オランダ、フランスからおのおの一名が招かれた。これら研究者に対しては、往復旅費のほか、滞在費月額四万円ないし六万円が支給されている。
日米教育交換計画による米国人の来日
この計画により、一九六二年度にはつぎのとおり米国人学者および学生などが招かれた。右のうち、カッコ内は前年度来日し、滞日期間を延長した者の数である。
訪問教授一八、研究学者一〇、英語教師八(三)、大学院学生一二(四)、合計四八(七)
外国政府などによる日本人留学生の招致
一九六二年度に、外国政府または準政府機関の給費生として海外に留学したわが国の学者、学生はつぎのとおりである。
(イ) 米州および大洋州地域四七九名
豪州二、ブラジル三、カナダ三九、ニュー・ジーランド一、アメリカ合衆国四三四(日米教育交換計画によるもの二五〇、ハワイ大学東西文化センターの招きによるもの三二、アメリカン・フィールド・サービスによる高校生の留学一五二)
(ロ) 欧州地域二一四名
オーストリア八、ベルギー四、デンマーク一、フランス四八、ドイツ八四、イタリア一八、オランダ七、スペイン三、スウェーデン一、スイス五、連合王国一二、ソ連二三
(ハ) アジア中近東地域一〇名
インド三、タイ二、アラブ連合五
映画祭の開催
(1) 国内関係
一九六二年
二 月 アラブ連合大使館主催アラブ連合映画会
八 月 近代美術館主催日仏交換映画祭
十 月 日本映画教育協会主催第九回国際短編映画祭
十一月 国際文化振興会主催第三回東京国際アマチュア映画コンクール
(2) 国外関係
一九六二年
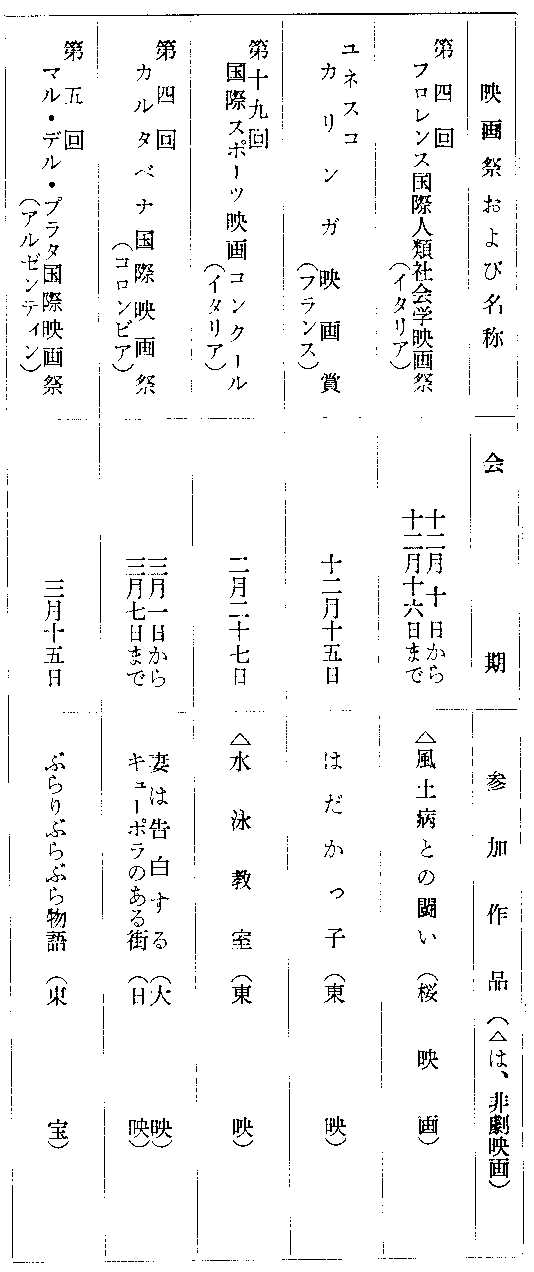
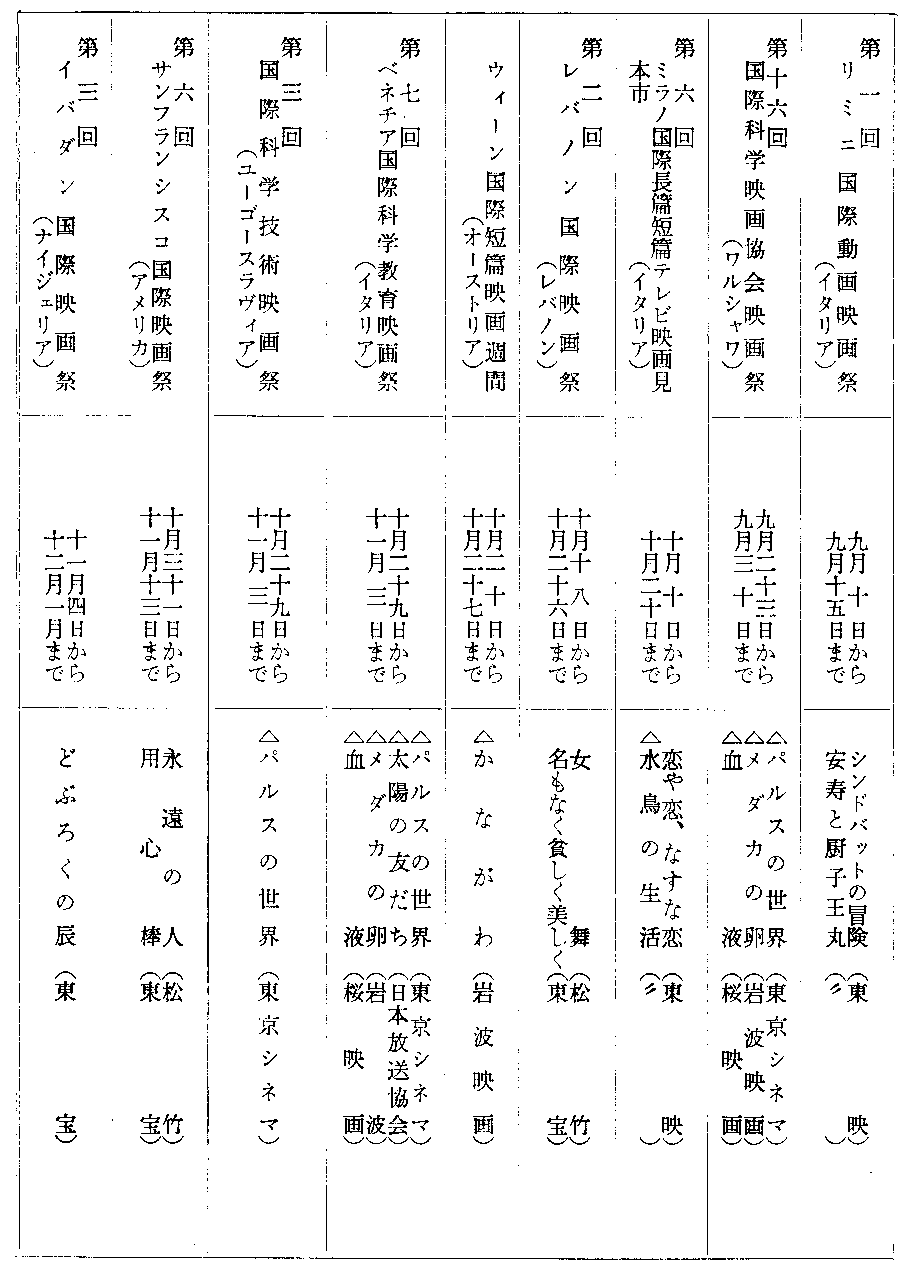
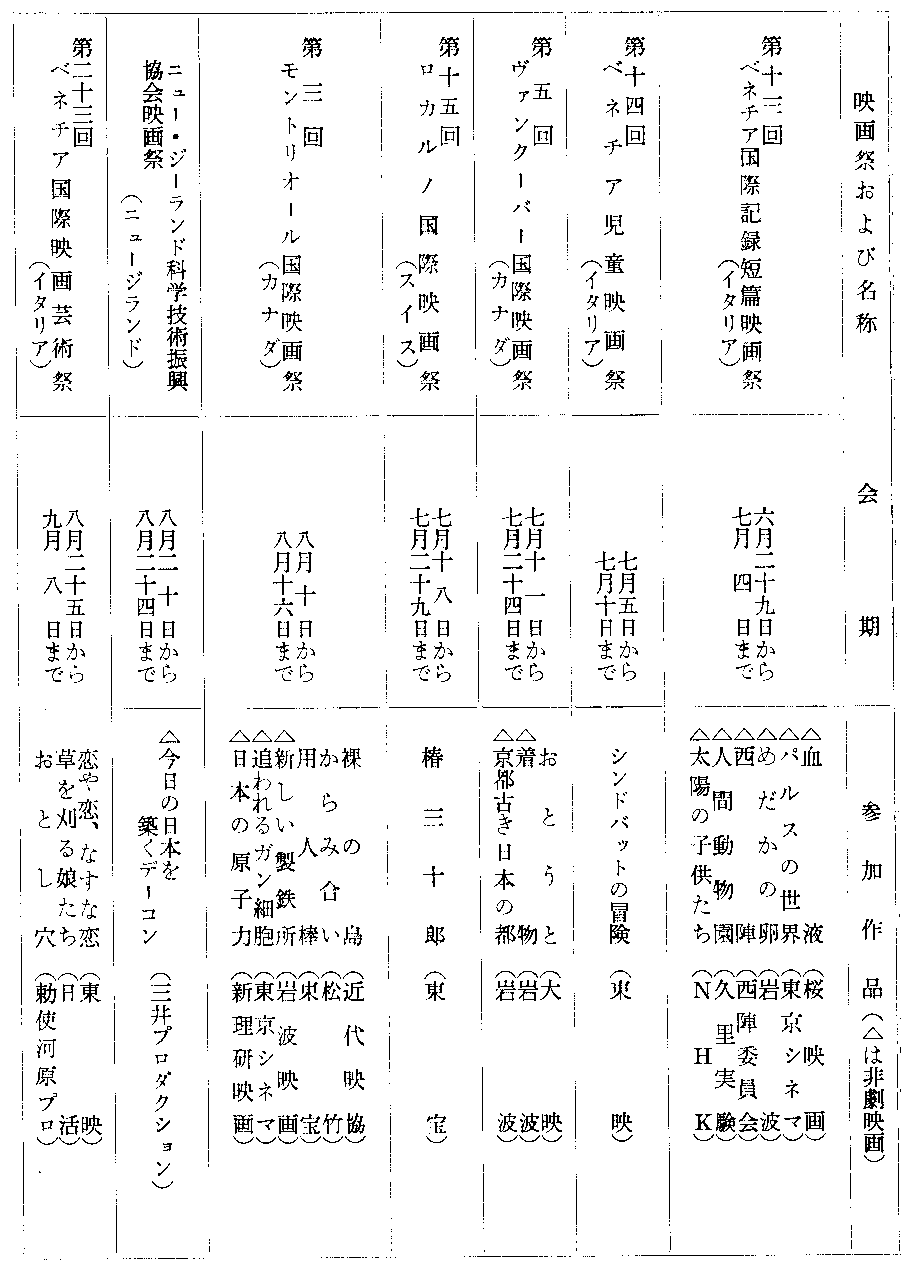
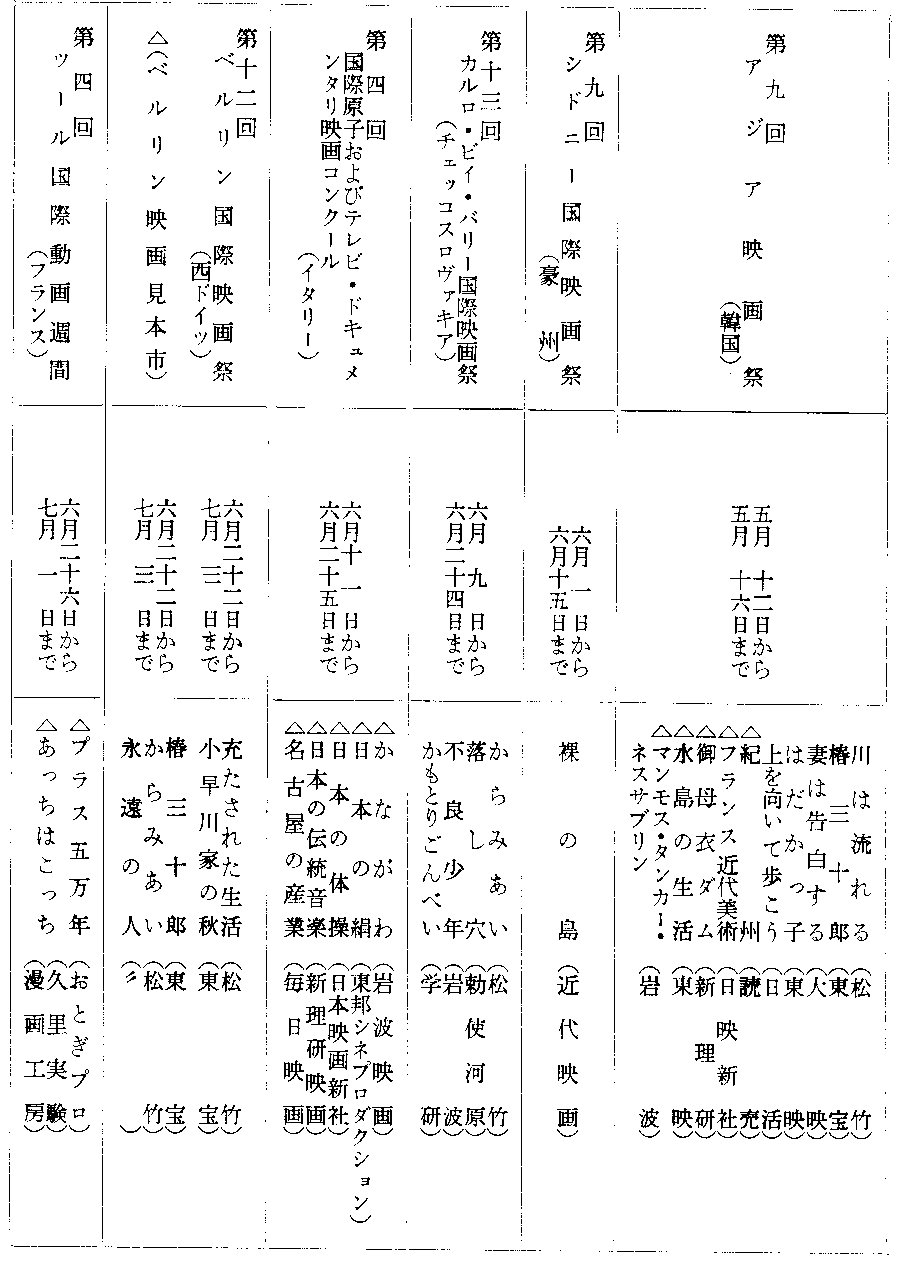
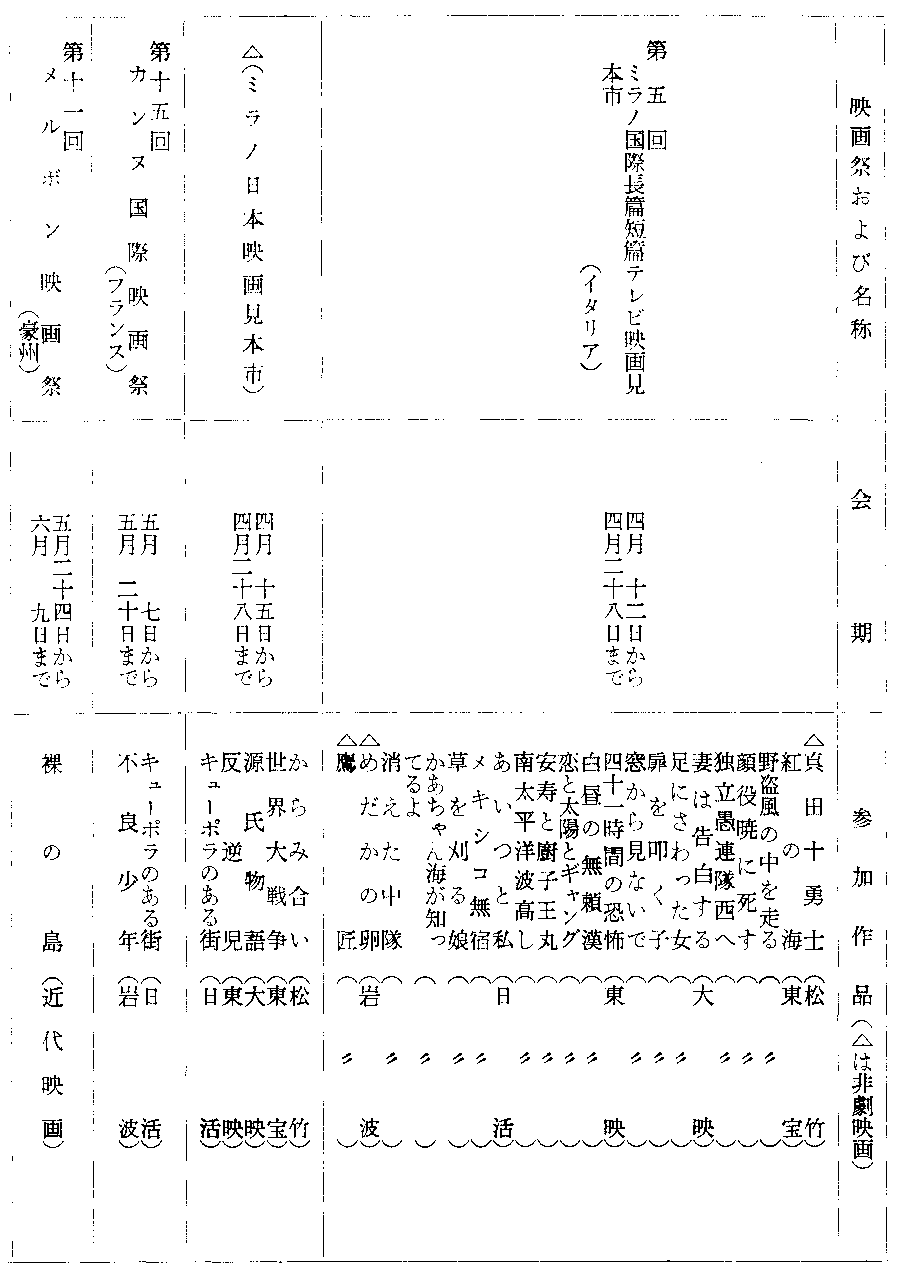
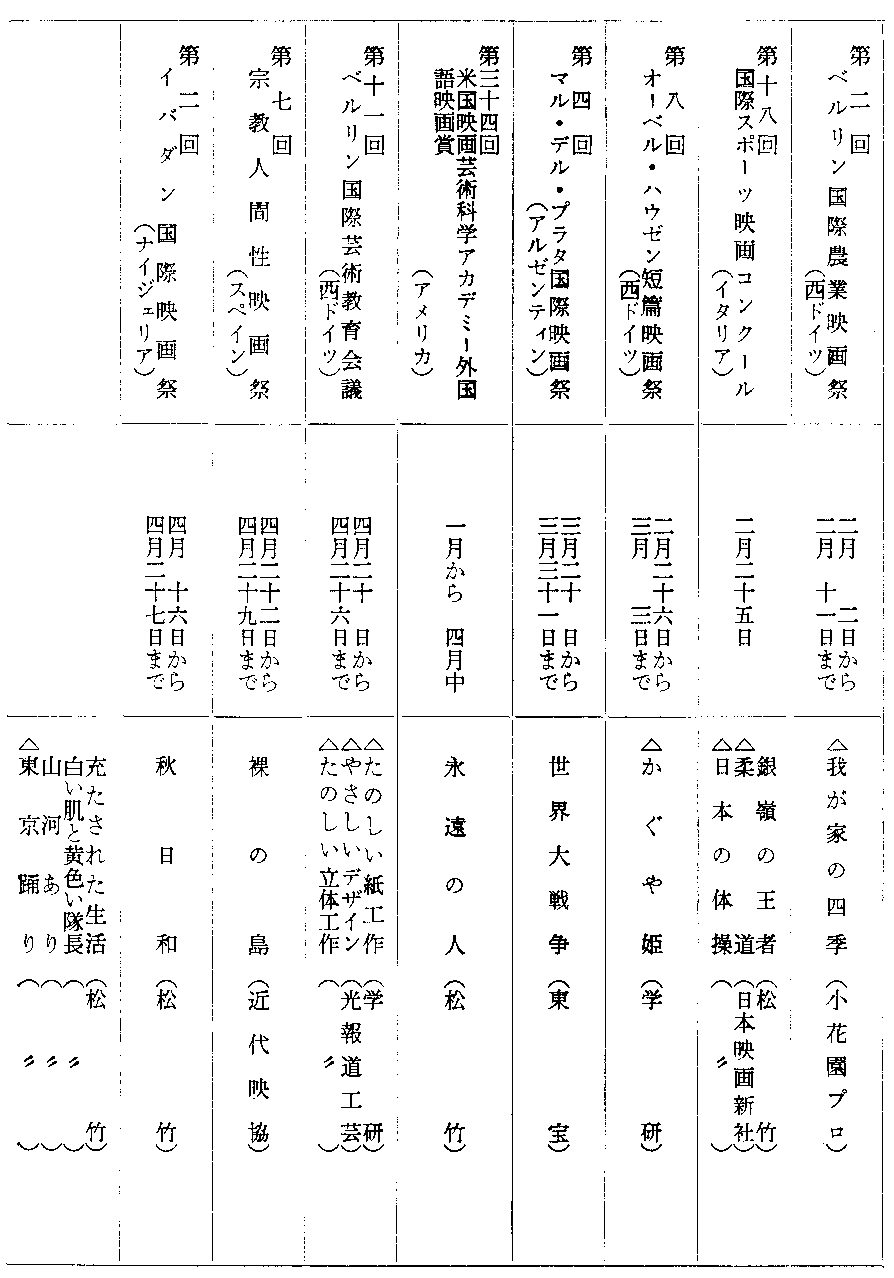
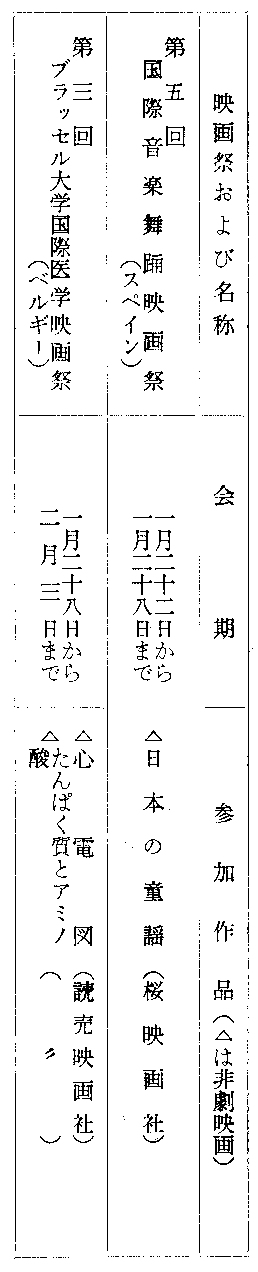
海外での映画上映
(1) 劇 映 画
「名もなく貧しく美しく」(英語版) 豪州、ニュー・ジーランド、レバノン、イラン、デンマーク
「氷壁」(英語版) カナダ、ポルトガル、アラブ連合、タイ、スイス、サウディ・アラビア、スペイン、アフガニスタン、ナイジェリア、(ロシア語版) ポーフンド、チェッコ
「女舞」(英語版)タイ、ビルマ、セイロン、レバノン、イラク、パキスタン
「彼岸花」(英語版) ノールウェー、オーストリア、スイス、イラク、タイ、サウディ・アラビア、ケニヤ
「地の涯に生きる」(英語版) 英国、ノールウェー、カナダ
「風速四〇メートル」(英語版) セイロン、パキスタン
「秋日和」(英語版) ナイジェリア、ガーナ、エティオピア、英国、ポーランド、チェッコ
「「黄色いカラス」(英語版) ドイツ、(スペイン語版) ウルグァイ、アルゼンティン、ペルー
「この天の虹」(フランス語版) イタリア、スイス、オランダ、フランス、カンボディア、ラオス、(スペイン語版) ブラジル
「路傍の石」(ドイツ語版) ドイツ
「花の慕情」(ドイツ語版) ドイツ
(2) 文化映画
「パルスの世界」(英語版) デンマーク
「巨船ネスサブリン」(日本語版) ビルマ、セイロン、レバノン、イラク、パキスタン、(英語版) ナイジェリア
「日本の音楽」(英語版) カナダ、ポルトガル、タイ、スイス、サウディ・アラビア、スペイン、アフガニスタン
「日本の庭園」(英語版) ノールウェー、オーストリア、スイス、サウディ・アラビア
「横山大観」(英語版) ドイツ、英国、スペイン
「新しい製鉄所」(英語版) セイロン、パキスタン
「マリンスノー」(英語版) ドイツ
「チョゴリザ」(英語版) ナイジェリア、ガーナ、エティオピア、パキスタン、南アフリカ、イラク、
「日光」(英語版) 豪州
「日本の手工芸」(フランス語版) イタリア、スイス、オランダ、フランス、カンボディア、ラオス
「日本・一九六二年」(スペイン語版) ウルグァイ、アルゼンティン、ペルー
「日本の童謡」(ドイツ語版) ドイツ
「日本の家庭生活」ドイツ語版) ドイツ