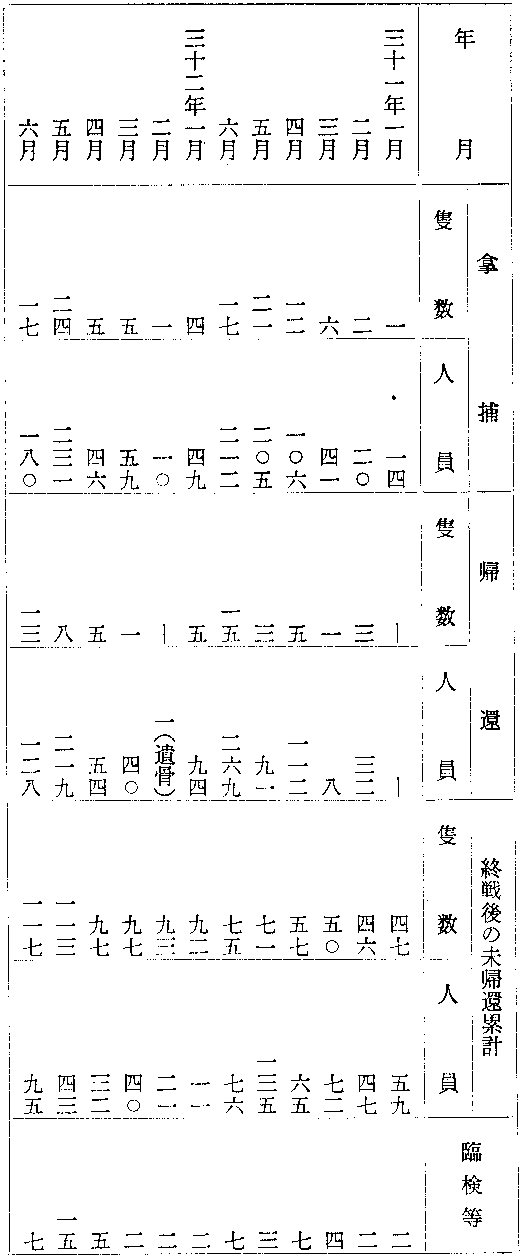
| ソ連及び東欧関係 |
昨年十二月十二日外務省で日ソ共同宣言の批准書が交換された結果、戦後十余年にわたつて断絶していた日ソ両国の国交はついに回復した。日ソ両国は批准書交換と同時にそれぞれ新関在スウェーデン公使館参事官および在東京チフヴィンスキー公使を臨時代理大使に任命し、両国大使館の開設を行つた。
ついで、十二月二十日ソ連側はイ・エフ・テヴォシャン・ソ連大臣会議議長代理の駐日大使任命についてのアグレマンを求めてきたので、同月二十七日わが方はこれに同意を与えた。また、同二十七日当時の門脇外務次官を在ソ大使に任命するためのアグレマンを求め、ソ連側は三十一日これに同意した。
テヴォシャン大使はアドィルハエフ、イヴァノフ両参事官らの館員を伴い、二月十日着京、十三日岸外務大臣に挨拶を行い、二十日天皇陛下に信任状を捧呈した。わが門脇大使は三月八日モスクワに着任、十六日ヴォロシーロフ最高会議幹部会議長に信任状を捧呈した。
両国大使の着任に伴い、両国大使館の館員数も逐次充実された。
なお、両国間にそれぞれ領事館を開設する問題は、日ソ共同宣言第二項に外交機関を通じて処理されると規定されているが、今までなんら話合いが行われていない。
日ソ国交回復は戦後長く閉されていた対共産圏外交への扉を開いたものとして、戦後のわが国の外交の劃期的な挙といつても過言ではないであろう。ソ連との国交回復は単に日ソ共同宣言第一項の規定するような日ソ両国間の平和および友好善隣関係を発展させるのみならず、アジアひいては全世界の平和に寄与するものでなくてはならない。この意味において日ソ復交の意義はきわめて大きい。
しかしながら日ソ復交の結果、このような理想が一挙に実現されたと考えるのは尚早である。日ソ両国の復交は完全な平和条約による国交回復ではなく、最も重要な懸案である領土問題の解決を、国交回復後交渉を継続する平和条約の締結にゆだねており、それまではわが国固有の領土である南千島の返還はもとよりソ連側がわが国に引渡すことに同意した歯舞群島および色丹島の引渡しも実現しない。すなわち日ソ共同宣言においては、その第九項で「日本国およびソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。ソヴィエト社会主義共和国連邦は日本国の要望にこたえ、日本国の利益を考慮して、歯舞群島および色丹島を日本国に引渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引渡されるものとする」と規定されている。
南千島がわが国固有の領土であるということはあらゆる観点から自明のことであり、わが国はいかなることがあつてもこの主張をまげることはできない。これにたいして、さる六月十六日のフルシチョフ・ソ連共産党第一書記の朝日新聞広岡編集局長にたいするインタヴューからも察せられる通り、ソ連側は相変らず態度をかえていない。
わが国としては、ソ連がわが方の正当な主張を認めれば何時でも平和条約締結の交渉を開始する用意があるが、ソ連がこのような態度をとつていては問題にならず、その結果、日ソ関係の最も重要な懸案がいつまでも未解決で、その他の懸案の解決にさえ影響をおよぼすことはまことに遺憾といわざるをえない。
結局、わが国としては、このような困難な状況にある以上、平和条約の締結は国際情勢の推移を注視し、わが国の主張の実現に最も有利な時機を捉えて取上げる他ないが、ソ連が一刻も早く日ソ友好善隣関係の樹立の第一前提が領土問題の解決にあることを理解するよう希望せざるをえない。
なお、米国は千島、南樺太の最終的帰属は主な連合国の合意により決定されるべきものであるとの立場をとつており、さる五月二十三日B二九撃墜事件に関する対ソ抗議で、ソ連が明らかに日本の固有の領土である国後、択捉、歯舞、色丹を占拠しているのは不法であるとの態度を明らかにした。
漁業問題は、その主要栄養供給源を漁業資源に仰いでいる日本国民すべての深い関心事でり、迂余曲折を経た日ソ交渉の基本問題の一つであつた。このような漁業問題の重要性は戦争後十二年の今日に至つても減少するどころか、いよいよ増大している。
日ソ間の漁業問題を規制するために昭和三十一年五月十四日モスクワにおいて「北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約」(日ソ漁業条約)が署名され、同年十二月十二日日ソ共同宣言第八項の規定により、効力を発生した。同条約第三条に基く北西太平洋日ソ漁業委員会の第一回会議が本年二月十五日から四月六日まで東京で行われた。
日ソ漁業委員会の仕事は多くの諸問題を含んでいるが、そのうちで最も重要な仕事はさけ・ますの年間総漁獲量を決定することであり、本年の日ソ漁業委員会第一回会議においても本問題は日ソ論争の焦点であつた。しかしこのさけ・ます年間総漁獲量決定の問題は、今回は結局日ソ漁業委員会内において科学的根拠にもとづいて解決されたとはいえ、むしろ日ソ漁業委員会の外で政治的に解決されたというべきであろう。会議の経過は次の通りである。
二月十四日日本側からは首席代表井出農林大臣、平塚、岡井、法眼の各委員が、ソ連側からはクーテレフ首席代表、モイセーエフ、パーニン、チフヴィンスキーの各委員が出席して開会式を行つた後、翌十五日、日ソ漁業委員会第一回会議の第一回本会議が外務省において開かれ、議事日程が採択された。ついで十九日の本会議において仮議事手続規則が採択され、すべての手続問題を了した後、同日の本会議において、さけ・ます年間総漁獲量に関し、日本側の提案は差当り一九五七年より四箇年間は豊漁年(西暦奇数年)一六万五千トン、不漁年(西暦偶数年)十三万五千トンとすべきだと提案したが、ソ連側は、「日本の沖取による乱獲と未成熟魚の漁獲により、さけ・ます資源は急速に減少しつつあるので、さけ・ますの総漁獲量を増加しようという日本側提案に同意することが出来ない、日本のさけ・ます漁獲量は昨年五月の河野・イシコフ協定により豊漁年十万トン、不漁年八万トンというふうに決定済みである」と主張した。日本側は過去におけるさけ・ます漁獲に関する各種統計資料に基いて、さけ・ます資源は減少してはいないと反駁したが、日ソ双方とも極め手となるような完全な科学的統計的資料を持つておらず、引きつづき論争を続け、日ソ両国の主張は全く対立したまま、事態は一歩も進展しなかつた。そこで、二月二十六日の第九回本会議で一たん本会議を打切り、(一)北西太平洋におけるさけ・ます資源の状況 (二)さけ・ます資源に対する沖取漁業の影響 (三)五七年度さけ・ます来游状況、の諸問題の検討を科学技術小委員会に付託した。
科学技術小委員会は二月二十七日から三月七日まで六回の会議を開き、前述の諸問題を審議し、これらの諸問題に関する日ソ双方の対立した見解を整理して「科学技術小委員会の報告」を作成した。このように日ソ漁業委員会においては日ソ双方の主張が鋭く対立して、解決の見透しがきわめて困難な状況にあつた。そこで井出農林大臣と河野前農林大臣のクーテレフ代表との政治的交渉によつて事態の解決を図ることになつた。井出農林大臣はクーテレフ代表に対して、日本側の漁獲量を暫定的に昨年の実績を下廻らない一四万五千トンに増加する代りに規制海域を拡大することおよび今後は科学的共同調査の結果によつて漁獲量を定めることを骨子とする暫定的取極を提案した。
しかし、クーテレフ代表は日本側の提案を承諾し得ぬ旨を回答して来たので、岸外務大臣は三月十五日テヴォシャン大使を招き、さけ・ます総漁獲量決定の問題は日ソ関係正常化後の最初のケースであり、今後の両国関係の発展上きわめて重大な意義を有している事実にかんがみ、ソ連側も大局的見地より考慮して欲しく、国交を正常化した本年の漁獲量が昨年を下廻るようなことは日本国民の容認することができないところであると申入れた。
これに対してテヴォシャン大使は三月二十一日になつて豊漁年としての五七年度に対し条約水域におけるさけ・ます漁獲量を「例外措置」として一二万トンまで認めると同時に、オホーツク海におけるさけ・ます漁業は「将来全く中止されるべく本年度は著しく削減する」ことを条件とする旨のソ連政府の正式回答を伝達した。
しかしわが国としてはソ連側の二条件即ち(一)五七年を豊漁年とし、同年に対して「例外措置」を認めようとすることおよび(二)オホーツク海の公海においてさけ・ます漁業を制限しようとすることは同意できないので、三月二十二日以降、井出農林大臣と河野前農林大臣は繰返しクーテレフ代表と交渉し、前述の二条件の撤回を申入れた。
四月二日、岸外務大臣は再度テヴォシャン大使を招き、「例外措置として」という表現を変更すること、オホーツク海における出漁を二船団、漁獲量を一万三千トンとすることを申入れた。これに対しテヴォシャン大使は四月四日、日本側の主張を概ね受容れる旨申越した。そこで四日夜さらに井出農林大臣とクーテレフ代表との間で細目について折衝を重ね、五日早朝実質上の合意が成立した。
そこで日ソ漁業委員会は、四月五日さけ・ます年間総漁獲量とオホーツク海のさけ・ます漁業の制限に関して成立したこの日ソ間の合意を採択した。なおそのほかに委員会においては、べにざけの資源保護と漁業規制の問題、小にしんの混獲許容限度の問題、めがに小がにの混獲許容限度およびかに網の設置の問題、距岸四十海里のさけ・ます禁漁区域についての問題、科学的調査の調整の問題および統計その他の資料の交換に関する問題についても決定をみた。日ソ双方の間に合意された前述の諸点はすべて、「北西太平洋日ソ漁業委員会第一回会議の議事録」の形で採択され、四月六日日ソ両国国別委員部委員(日本側から平塚、法眼、岡井各委員、ソ連側からモイセーエフ、パーニン各委員)によつて署名された。かくて二カ月にわたつた日ソ交渉はここに幕を閉じた。
日・ソ両国の間でまた領土問題が解決していないことと、領海の幅の問題(日本側は三海里、ソ連側は十二海里を主張している)が解決していないこととのために、北海道東北方のわが国漁業水域は著しく狭められており、ことに歯舞群島、色丹島、千島諸島および樺太の近海漁業は著しく制限をうけている。これら近海漁業は主として北海道の零細漁民や上述の諸島からの一部引揚民によつて営まれているが、昆布、帆立貝、かに、たら、すけそうだら、伊谷草、めぬけ、かれい、にしん、さめ等の漁獲があげており、これらの魚貝類および海藻類は陸岸に接近するほど多いため、もし歯舞、色丹、千島諸島および樺太の距岸十二海里以内の公海の水域で操業しうるならば、漁獲高は現在に比し加倍すると思われ、その経済的価値はきわめて大である。そこでこれら漁民は自然距岸十二海里から三海里の海の公海で操業しがちであるが、これにたいして、ソ連側は領海十二海里主義に基き、快速巡視船によつてこれら漁船を容赦なく拿捕し、漁民を抑留している。この結果零細なわが国の漁民は、大切な船を奪われ、働き手を奪われて、困窮している。後に述べるように、わが方はその都度ソ連政府に拿捕漁船の釈放を要求しているが、この種事件を防止し、この方面の安全操業をはかるためには、釈放交渉だけでは到底目的を達しえない。わが国は領海三海里説をとつており、ソ連の十二海里説を承認してはいないから、ソ連側が日本の漁船を拿捕するのはもとより不法であると考えているが、領海の幅の問題が日ソ間で未だ解決されていない今日、同様に三海里説をとる英国が一九三〇年以来、英ソ漁業協定においてソ連側と交渉して北海の特定水域において三海里と十二海里との間で英国の漁船が操業することをソ連側に認めさせた前例もあるので、政府は六月三日在ソ連門脇大使を通じて歯舞、色丹、国後、択捉および千島諸島の周辺水域(十二海里以内)において、零細漁民の生計のため小規模漁業および昆布採取の自由を認めるよう、ソ連政府にたいし申し入れた。なお同時に水晶島と根室間のゴヨマイ水道の航行上必要な貝殻島燈台を航行安全のために点燈することを申入れた。
在ソ日本大使館は以上の申入れをさらに六月十日文書にしてソ連側に提出した。なおその中で千島引揚者の墓参りを許可するようソ同時に連側に要請した。
元来わが国の北洋漁業の一部は千島、樺太、カムチャツカ半島、沿海州の近海で行われるが、ソ連が領海の幅員について十二浬説を採つているため、ソ連側に掌捕される漁船があとを断たない。
前述のようにわが国は領海十二海里の主張を法的に認めるものではないが事実上紛議を避けるため政府は漁業者に対し十二海里内に立入らぬよう、国内指導を行う一方、ソ連側に対しては、拿捕漁船の返還、漁民の釈放を随時強力に要求してきた。
ソ連側は、わが方漁船を拿捕した場合、取調べの上、領海の侵犯、時にはスパイ容疑をもつて起訴し、裁判の結果、大部分の漁船には船体没収処分、責任者たる船長または漁撈長には二年ないし三年の刑を課している。船長または漁撈長以外の乗組員は、取調べの結果、容疑の晴れた他の漁船を釈放する際、同乗させて送還するか、時にはわが海上保安庁巡視船の派遣を求めて洋上引渡しを行つてきている。
昨年十二月国交が回復されてから、いわゆる第十一次引揚げにおいて、復交前ソ連に抑留されていた漁民も送還されてきたが、復交前に拿捕された九十二隻の船舶は返還されていないので、本年二月四日在京ソ連大使館あて口上書をもつて、この九十二隻について返還を求めた。この要求は昨年七月十一日、十一月十二日の対ソ要求につぐ三度目のものであるが、これに対するソ連側の最終的回答は未だ寄せられていない。
さらに日ソ間の国交回復後もソ連官憲によるわが国漁船の拿捕は例年に比較して決して減少しておらず、かえつて増加しているくらいであり、ソ連側の態度は復交後といえども決して好転していないかに思われる。本年一月から六月までの間にソ連に拿捕された船、乗組員数を昨年同期に比較し、表示すれば次の通りである。
(海上保安庁調)
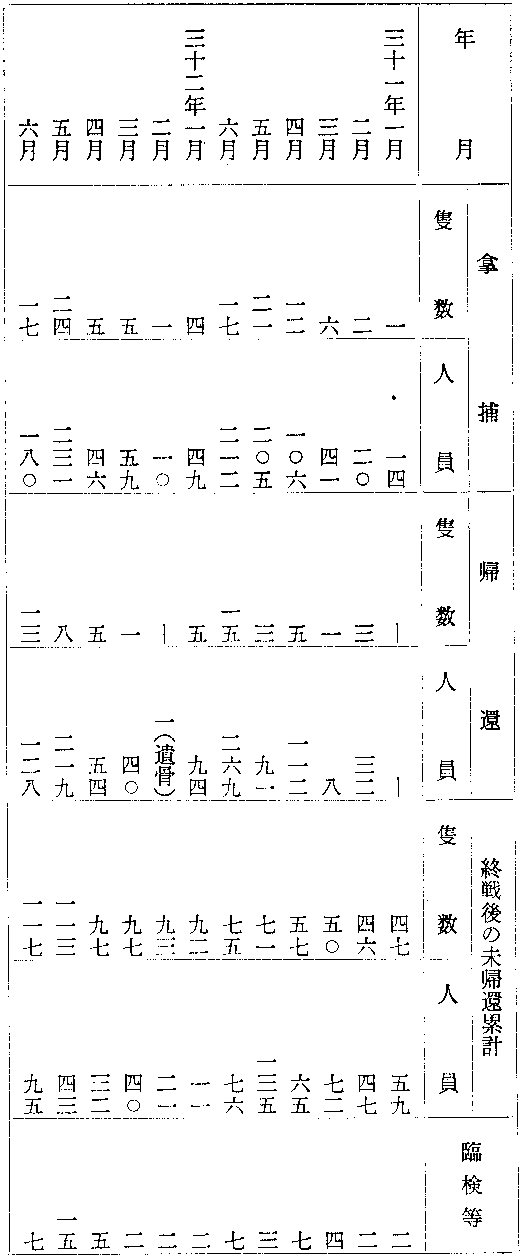
政府は拿捕事件発生後直ちにソ連にたいし拿捕船舶と抑留漁夫の返還釈放を求めており、例えば、五月上旬、樺太亜庭湾内で起つた十四隻のわが国のにしん刺網漁船の拿捕に際しては、門脇大使を通じ何回にもわたり厳重に抗議したが、遺憾ながらソ連側より満足な回答に接していない。
ピョートル大帝湾は南部沿海州、ウラジオストック前面の海域であつて、かれい、たら、すけそうの有望漁場として古くから知られ、戦前から本邦漁船は同水域に機船底曳網操業を行つていた。戦後は本年四月十日から十九日まで第一次試験操業を行い、成功裡に終了した。引続いて第二次試験操業として、石川県水産試験場漁業調査船白山丸を含む秋田、新潟、石川各県の底曳船八隻と水産庁漁業監視船第五竜宝丸が同海域に出漁したが、四月二十四日東経一三二度八分、北緯四二度三一分三〇秒の公海で操業中、白山丸は約四〇〇トンのソ連船第三七〇号によつて投錨と書類提出を命ぜられる事件が起つた。白山丸は日本政府の許可証を提示して操業継続の交渉を行つたが、全船直ちに帰国しなければ船と乗員を拿捕抑留するといわれたので、紛糾を避けるため全船帰国の途についた。
そこで政府はこの事件をとりあげ、五月四日在ソ門脇大使を通じソ連側が不当にも操業中止を命じた理由を訊し、厳重に抗議した。
これにたいし五月二十七日ソ連外務省クズネツォフ次官は門脇大使にソ連側の文書による正式回答を手交した。
ソ連の回答内容はおよそ次の通りであつた。
「日本漁船が漁撈したピョートル大帝湾水域にはかつて機雷敷設区域が存在し、この区域が船舶航行に危険なものであることは、一九四五年十月二十七日付ソ連海軍水路部の航海者に対する告示をもつて布告された。
掃海後、この区域は水上航行のためにのみ開放されていることは一九四六年の告示で通報され、この理由からこの区域でとくに底曳船による漁掛を行らことは海床に残存する機雷の爆発の可能性が排除されていないため勧めることができない。
ソ連側巡視船は漁撈に伴う機雷爆発の危険があるために、日本漁船に対して不幸な事件を避けるため、この区域から退避するよう提議したのであつて、いかなる威嚇も、日本への帰船提議も行わなかつた。この点からみて、日本政府の提議が根拠あるものとは認めない。しかし、日本官憲が日本の漁業者に対して、右区域内での漁撈の危険なることを通達し、不幸な事件を避けるために、同区域において漁業に従事しないよう措置をとることを期待する」
門脇大使はこれにたいし直ちに、戦後十年以上を経過した現在、ソ連政府が当然機雷を清掃すべきものであつて、いつまでも機雷の危険を云々することは国際常識上不可解であり、ソ連側が右の危険に籍口して日本漁船の公海上の漁撈を阻害することには日本側は到底承服できないところで、たとえ、同区域が危険であるにせよ漁業者が自分のリスクで操業するものであるから、これに対し、阻害しないよう出先官憲に必要な訓令を出すよう要望した。
この事件の勃発によつてピョートル大帝湾は日ソ関係においてクローズ・アップされてきたが、ソ連政府機関紙イズヴェスチヤ紙は突然七月二十一日、ソ連大臣会議はピョートル大帝湾区域におけるソ連の内海境界問題を検討し、テユメニ・ウラ(豆満江)河口とパヴァロトヌイ岬とを結ぶ線をもつて右区域におけるソ連内海の境界およびソ連領海の幅を算定する基線となすべきこと、ピョートル大帝湾区域における外国船舶の航海ならびに外国飛行機の飛行はソ連当該官憲の許可を得てのみ行うべきものとすること等を決定した旨報じ、大きな波紋をおこした。
ソ連閣僚会議の決定は国際法の一般原則に反する不法措置であるので、政府は七月二十六日在ソ門脇大使にたいし、「右海域は国際法上内海の要件を具備していないこと明らかで、国際法の一般的原則に反し、不法であるからて日本国政府は本件ソ連大臣会議の決定を容認しない。とくに同海域は日本国民の伝統的漁場であり、今回のソ連政府決定は日本国民の漁業および航行の自由を不法に侵害するものである。よつて日本国政府は本措置に拘束されないことを宣言し、本件に関しあらゆる権利を留保するものである」旨の口上書を以つてソ連側に厳重抗議するとともに、右措置がいかなる根拠に基くものであるかにつき説明を求めるよう訓令した。門脇大使は七月二十六日ソ連外務省セミョーノフ次官と会見し、口上書を手交して厳重抗議を行つた。
ソ連側はピョートル大帝湾は地理的にも、経済的にも、また軍事的にも久しい以前から歴史的なソ連領と認められているものであつて、ソ連の歴史的湾との立場をとつているごとくであるが、この主張は国際法的に根拠なく、不法なものといわざるをえない。すなわち、一定の海域を内海とする国際法上の要件としては、湾口を結ぶ線の長さが従来の通説によれば一〇マイル(国連の国際法委員会の海洋法案では一五マイル)であり、ソ連の主張する領海の幅員の二倍説によるとしても二四マイルである。しかるにピョートル大帝湾口は一〇〇マイル以上であり、右のいずれの基準にも反している。さらに、歴史的湾として内部の海域を内海とするためには、その慣習が長年にわたつて行われ、かつ一般に承認されたものでなければならないが、ピョートル大帝湾については、ソ連自身今まで歴史的湾として主張したことをきかない。いずれにしてもソ連の今回の一方的措置はきわめて不法であるといわざるをえない。
ソ連は戦前から外国人にたいし広汎な立入禁止地域を設けていたが、戦後も外国外交官にたいしモスクワから四〇キロ以上遠くへ旅行する場合には許可を要する旨を通告して現在にいたつている。そこで米英仏伊独等の各国は報復として、それぞれ自国に駐在するソ連外交官に同様の旅行制限を課しているが、わが在ソ大使館の開設とともに、ソ連はわが方大使館にも旅行制限を課する旨通告してきたので、政府も相互的な立場から在京ソ連外交官に旅行許可制度を実施することが必要であると考え、七月二十六日外務省から在京ソ連大使館にあて口上書をもつて在京ソ連外交官にたいする旅行許可制度の実施に関する通告を行つた。
この許可制度は、在京ソ連外交官と、その家族とを対象とし、これらの者の旅行自由地域は、日本橋から直線距離で約四〇キロの八王子、桶川、久喜、水海道、佐倉、南総および鎌倉の各市町を直線をもつて連ねた多角形内の地域で、その他の地域への旅行を行うためには四十八時間前に許可申請を必要とするが、軽井沢、日光、箱根、逗子および葉山への旅行は十二時間前に届出ればよいことになつている。
世界平和確立を希念するわが国にとつては、世界のすべての国々との国交の樹立は、その外交政策に合致するものであり、したがつてソ連との国交回復とともに、同じ共産圏諸国である東欧諸国との復交問題は当然解決せられるべきものとして、本年早々まずポーランド、チェッコスロヴァキア両国との間の国交回復交渉を行い、国交回復の手続をすすめた。
東欧は一見わが国には関係の薄い地域のように考えられるが、昨秋のポーランド政変やハンガリー動乱が国際情勢に及ぼした影響を考えただけでも判るように、国際政治上重要な地位を占めており、両国にわが政府の代表機関を設け、東欧の事情を観察することはわが国の外交政策の樹立に寄与するところ少なからざるものがあろう。
ポーランドとの国交回復
ポーランドは戦前わが国との間に大使を交換し、両国関係はきわめて友好的であつたが、昭和十四年九月独波開戦にともない、独ソ両国にその領土を分割されたので、わが国は在ポーランド大使館の廃止と在京ポーランド大使館の閉鎖を行つた。わが国の対米英宣戦後ロンドンのポーランド亡命政権は昭和十六年十二月十一日に対日宣戦を行つたが、事実問題としては両国の間に戦争行為はなんら存しなかつた。
戦後、昭和二十六年のサン・フランシスコ会議にはポーランド代表も出席したが、平和条約には署名しなかつた。
その後昭和二十九年十二月、ポーランド側はパリにおいてわが在仏大使に対し、国交回復について公式に申入れて来たが、わが国は東欧諸国との復交は日ソ交渉成立後にこれを考慮する方針を持し直ちにこれに応じなかつた。
しかるに昨年十月十九日に日ソ共同宣言が署名された直後の十月二十二日、ポーランドは国連において再び公式に国交回復の申入れを行つて来た。そこでわが国は、十二月十二日日ソ共同宣言の批准書交換の結果日ソ国交が回復するのをまつて、ポーランドとの国交回復の交渉を行うこととし、一月八日閣議の了承をえた後、加瀬国連大使をしてポーランド国連大使との間に折衝を行わしめたが、二月八日にいたり交渉が妥結し、同日ニューヨークにおいて「日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定」(日波復交協定)が署名された。
協定は四月十九日の国会で承認され、二十三日批准のための諸手続を完了した。ポーランド側も四月十八日に国家評議会が批准を完了した。批准書交換式は盛大に行いたいとの交渉当時のポーランド側の希望もあり、政府は園田直衆議院議員を特派大使としてワルシャワに派遣し、五月十八日批准書交換を行わしめた。かくて日波復交協定は効力を発生した。
チェッコスロヴァキアとし国交回復
チェッコスロヴァキアは戦前わが国との間に行使を交換していたが、同国は昭和十四年三月ドイツに占領され、ドイツの保護領ないし保護国となつたので、わが国は在チェッコ日本公使館の廃止と在京チェッコ大使館の閉鎖を行つた。昭和十六年十二月八日わが国が連合国に対して宣戦を布告したのに伴い、ロンドンのチェッコ亡命政権は同月対日宣戦を行つたが、事実問題としては両国の間に戦争状態はなんら存しなかつた。
戦後昭和二十六年のサン・フランシスコ会議にチェッコ代表も出席したが、平和条約には署名しなかつた。
その後昭和三十一年六月にいたり、チェッコはまずロンドンにおいて国交回復交渉の開始を申入れ、さらに同年十月にもモスクワにおいてもわが方日ソ交渉全権団にこの申入れを繰返えした。しかしわが国はチェッコとの復交は日ソ交渉成立後にこれを考慮する方針を持してきたので、交渉の即時開始を見合せた。
しかるに昨年十二月十二日日ソ共同宣言が発効して、日ソ国交が正式に回復し、同国との国交回復を遅延する理由もなくなつたので、一月八日閣議の了承をえた後、チェッコとの復交交渉をロンドンで開始することになり、わが国は、在連合王国西大使をして在連合王国チェッコ大使との間に種々折衝を行わしめたが、二月十三日に至り交渉が妥結し、同日ロンドンにおいて「日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書」(日・チ復交議定書)が署名された。
日本側は四月十九日に日・チ復交議定書を国会で承認し、二十三日批准のための諸手続を完了した。またチェッコ議会は三月六日議定書の承認を終つた。そこで五月八日、ロンドンにおいて議定書の批准書交換が行われ、復交議定書はここに効力の発生をみた。