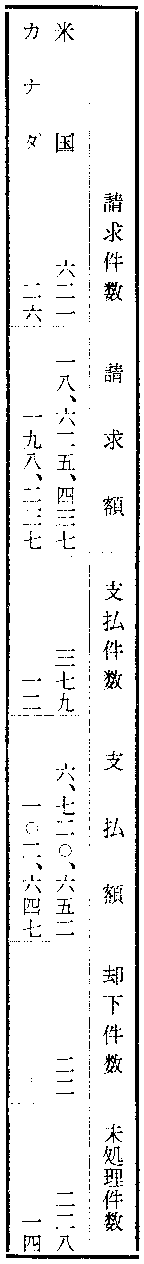
| 北米関係 |
本年五月岸内閣は国防会議を開催し、国防方針および長期防衛計画を策定した。すなわち「民主主義を基調とするわが国の独立と平和を守る」という至高目的を達成するため、「国際連合の活動を支持し、国際間の協調を図り、世界平和の実現を期する」ものであるが、「外部からの侵略に対しては、将来国際連合が有効にこれを阻止する機能を果し得るにいたるまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する」方針を明らかにした。
六月、岸総理は米国を往訪、三日間にわたりアイゼンハワー大統領ならびに米国政府要人と懇談し、日米間の諸問題および国際問題について隔意のない意見の交換を行つた。その際わが国の安全保障についても論ぜられ、在日米軍の配備と使用、日米安全保障条約によりとられる措置が国際連合憲章の諸原則に合致するよう確保すること、安全保障に関する日米間の関係を調整することなどを討議するため政府間委員会を設置することに意見の一致がみられるとともに、近い将来において在日米軍の大幅撤退が行われる旨が明らかにされた。ここに日米共同防衛は新らたなる段階に入つたものといえよう。
元来わが国の安全保障は、日米安全保障条約とこれにもとづく日米行政協定、日米相互防衛援助協定等により日米共同防衛を基本として確保されてきたのである。周知のように右条約は、日本の独立回復にあたり無防備の日本を他国の脅威から守る趣旨のために結ばれたのであるが、在日米軍の使用と配備問題、基地問題等をめぐり再検討の気運が高まり、かつまたわが国自体の自衛力の漸増に伴い、日米共同体制の再検討を要する段階に達したわけである。
先般の岸総理訪米の際の岸・アイゼンハワー共同声明に述べられた原則に従い、米地上軍はすでに漸次日本を撤退しつつあり、ウィルソン国防長官の言明によれば、その大部分は今年のクリスマスまでに撤退を完了することとなつており、残留部隊も来年八月頃までには引揚げる予定といわれる。
八月一日、米国陸軍当局は在日第一騎兵師団(約一万五千名)の日本からの撤退を発表、同月七日、米国海兵隊は在日第三海兵師団第九連隊(約五千名)の沖縄移駐開始を公表し、さらに同月十九日、在日米陸軍司令官は第一騎兵師団の撤退準備が完了し、二十日を期してその兵力は零となる旨、および防空部隊(約一万名)が解散した旨を報じた。
右の結果、在日米地上軍は、管理補給部隊約(一万七千名)が五つの地区司令部に統合されて残留するのみとなつた。
このほか第五空軍を主軸とする空軍関係兵員約五万名が千歳、三沢、横田、立川、小牧、板付を中心として各地区に駐留しており、また海軍としては航空部隊関係をも含み約二万名が横須賀、佐世保、厚木、岩国、追浜等に駐留している。
従つて、現在日本に駐留する米軍総数は約八万七千名とみられ、これに対し約四割と推定される人員が家族として滞在している。
六月の岸総理訪米の結果、安全保障問題に関する日米間の協議機関として政府間委員会を設置することとなつたが、八月六日、日本側は外務大臣、防衛庁長官ならびに必要に応じ他の関係官が委員として出席し、米国側は駐日米大使および太平洋軍総司令官(在日米軍司令官が代理を務める)が委員となり、この委員会を発足させることを取極めた。委員会討議事項として日米共同声明に言及された三点、すなわち
(イ) 米国軍隊の日本における配備および使用につきできうる限り協議することを含み、安全保障条約に関して生ずる諸問題を検討すること。
(ロ) 安全保障条約に基いてとられる一切の措置が、国際連合憲章の諸原則に適合することを確保するために協議すること。
(ハ) 安全保障の分野における日米両国の関係を両国々民の必要と願望に適合するように今後調整することを検討すること。
が挙げられる。
なお本委員会の審議に当つては、一方において、安全保障に関する日米協力体制におけるわが方の役割を明確ならしめて、わが方の自主的立場を強化するとともに実効的な協力体制を確立し、将来安全保障条約改正を含む新情勢に適応すべき体制に移行することを目途とし、あくまでハイ・レヴエルにおいて広汎な視野にたつ研究を進め、安全保障問題に関して相互の理解と意思疏通をはかることになつている。
本委員会の第一回会合は、八月十六日外務省で行われ、日本側からは藤山外務大臣および津島防衛庁長官、米国側からはマックアーサー大使および太平洋軍総司令官スタンプ大将の代理として在日米軍司令官スミス中将が出席し、また日本側は大野外務次官および今井防衛庁次官、米国測はホーシー公使、キャラウェイ在日米軍参謀長およびクイグル同次長が陪席した。
冒頭藤山外務大臣およびマックアーサー大使から、安全保障の分野における諸問題を、両国民の必要と願望に沿つて解決して行くため、日米両政府が此の委員会に期待することが大であり、また両政府が委員会の運営に効果あらしめるため極力努力する意図である旨が明らかにされた後、まず委員会の運営方法が討議され、今後委員会は、日米いずれかの要請により随時、原則として外務省において会合することとなつた。
ついで、米軍の日本撤退に伴つて生ずべき諸問題につき隔意のない討議が行われ、また第一騎兵師団と第三海兵師団の撤退計画が検討された。
わが国においては従来しばしば基地六百と称せられ、狭隘な国土にかくも多数の基地を米軍が占有しているとの非難があつたが、その実態は次の通りである。
米軍に提供される施設、区域はすべて、行政協定に基き、日米合同委員会を通じて提供されるものである。手続としてはまず米側より理由を付した要請が書面により合同委員会に提出され、日本側はこれに対し、防衛上の必要、民生への影響等を慎重討議の後却下すべきは却下し、合意すべきは合意するもりである。なお提供が最終的に合意されるためには閣議決定を必要とし、同決定を経たものには各件毎に件数が付されるわけである。
昭和三十二年七月現在の総件数は約四四〇件となつており、これらの施設の内容としては、米軍および軍家族の使用している事務所、アパート、病院、住宅、倉庫が含まれるのはもちろん、防火施設、排水所、自動車置場等の諸施設、さらには米軍専用の洗濯工場等すら含まれており、いわゆる"基地"としては飛行場、演習場、兵舎等わずかに九一件にすぎない。
なおこれら演習場ないし飛行場は一方米駐留軍の撤退により漸次返還されており、他方わが国の防衛力の漸増に従い日本自衛隊が共用している場所も多く、陸上演習場の如きは約半数を自衛隊が使用している状況である。
講和条約発効以来約二九〇件に達する施設が解除されているが、解除件数は今明年度中には逐増するものと予想される。なお解除にあたつては、できうる限り民間所有の建物、土地等に優先的取扱とするよう努力しており、政府としてはいわゆるリロケーション計画、すなわち東京、大阪、横浜、名古屋、神戸等の大都市の中心部の民間施設の解除のため、郊外地方に米軍を移転させる計画にもとづき、大都市所在の民有施設についてはその大部分の解除を実現している。
これを提供施設の土地、面積の面から比較すれば講和条約発効当時は民公有約二億坪、国有約二億一千万坪であつたものが現在では民公有約一億坪と半減しておりまた、国有についても約一億七千万坪と減少を見ている。
事件の発生と審議
本年一月三十日、相馬ケ原における米軍の演習中、被告ジラード他一名は、演習場内移動中の部隊に属する機関銃その他を守るよう命令を受けて演習場に在つた際、たまたま弾拾いのため附近に来た被害者他一名に対して空薬莢を投げ与えてこれを拾わせ、さらに傍の穴を指してその中に拾いに行くように誘引し、被害者が穴の中にある際にわかに出て行けと呼号しながら、被害者の方向に向けて銃に備付けの手榴弾発射装置に空薬莢を詰めて空砲を発射し、もつて被害者を死にいたらしめたというのがいわゆるジラード事件の事実の概要である。
この事件後、米軍側から被告の行為は公務遂行中の行為なりとする証明書を発出したが、日本側はこれに反証ありとし、よつて三月六日本件は行政協定に基く日米合同委員会に附託された。合同委員会においては、(1)米側は、被告の行為は命令の範囲に属する時間と場所の限界内の行為であるから、行為自体は甚だ適当を欠いているが、公務上(on duty)の行為であり、故に米側に第一次裁判権ありと主張したのに対し、(2)日本側は、被告の行為は与えられた命令の遂行の範囲を実質的に逸脱しているから行政協定にいう公務遂行中(in the performance of official duty)の行為ではない、したがつて日本側が第一次裁判権を有すると主張した。こうして公務内外について日米間に意見の一致を見られないとの結論に達したので、五月十六日にいたり、合同委員会は、右の点に関する双方の立場は留保したまま、米国から「本件に付裁判権を行使せず」との通告を日本側にすることとして解決することに合意を見て、翌十七日米軍からわが方の法務当局に対して右の通告が行われ、検察庁は十人目起訴手続をとつた。
米国における反響
前記合同委員会の決定が発表されると、被告を日本側の裁判に委ねることに対して米国内に強い反響があり、国防長官は五月十七日逸早く本件の詳細な再審査を行うまで被告を日本側に引渡さないと声明した。米国内の非難は、法律的には主として米当局は前記のように事件は公務遂行中のものであるとの立場をとつたまま日本側に裁判を譲つた点に向けられるとともに、次第に感情的になつて、海外駐留軍将兵の地位に関する関係国との取極め自体が攻撃され、六月四日国務国防両長官が合同委員会決定にしたがつて解決しなければならないと発表した後も、米政府に対する非難は一向鎮静の兆を見せなかつた。
米国法延における経緯
このような情勢の下に、被告ジラードの家族から米国連邦裁判所に対し、ジラードに対する人身保護令状発出請求の訴訟を提起した。これに対する六月十八日の同裁判所の判決は、人身保護令状はその理由がないとして発出を拒否したが、被告が米国の軍法会議に付せられることがあるべきなのに鑑み、その身柄を日本側に引渡すことを禁ずる、というものであつた。すなわち右判決は、合同委員会の決定を尊重するという米国政府の決定を実行不能にするものであり、日本側においても本件裁判の実行を不可能にするものとしてきわめて重視したのであるが、米政府は即刻米大審院に控訴し、大審院は暑中休暇を取り止めて緊急審理の末、七月十一日、安保条約および行政協定は適法に成立せるもので、本件に関する軍当局の裁量は、右条約協定に規定された範囲内の適法の裁量であり、これに対し憲法上法令上なんらの障害は存せずとの決定を下し、前記連邦裁判所が日本側に引渡を禁じた判決を棄却した。このようにして一時は日米間に非常に困難な事態を招来するかと憂えられた本件も、日本の法廷の裁判により解決する方向へ進むこととなつたのである。
平和条約第十五条(a)の規定にもとづいてわが政府は、戦時中日本国内にあつて敵産管理に処せられた連合国およびその国民の財産を返還し、または、開戦時日本国内に所在し、かつ、返還することができず、戦争の結果損害を受けた連合国人およびその国民の財産に対しては補償をすることになり、すでに返還可能なものはほぼ返還を完了したが、補償を必要とするものに対しては、現在、連合国財産補償法にもとづきその補償の支払いが行われている。この補償請求期限は平和条約発効後十八カ月以内と規定されているのですでにその補償請求提起は打切られているが、米・加両国関係の補償請求件数、金額および昭和三十二年六月末日現在の事務処理状況は左のとおりである。
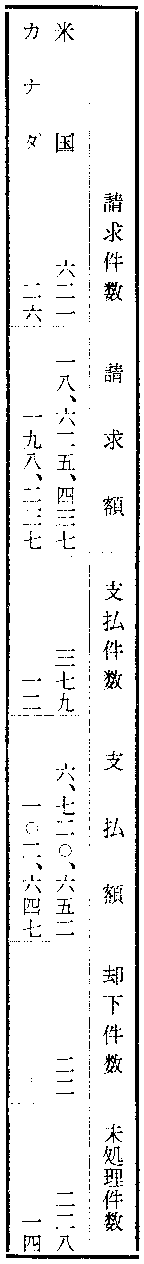
(単位千円)。
この補償に関しては、関係法規の解釈、事実の認定、補償額の査定などにつき日本国政府と連合国側との間に見解の相違が存在する場合があり、それが両国間の話し合いによつても解決し得ないときには「日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定」に基き、両国政府が単独で任命する各々一名の委員に両国政府の合意により任命される第三の委員を加えた三委員によつて構成される財産委員会に最終的解決のため付託することができることになつているが、昭和三十二年六月末現在カナダからすでに三件を同委員会に付託する旨を通報して来ている。しかし、まだ同委員会は実際に設置される段階にはいたつていない。
なお右に述べた連合国財産の返還に伴い、当該財産の接収後日本側により改良ないしは修復工事が行われて価値が増加していた場合、または被返還者が当該財産の返還と併せて日本銀行の管理する特殊財産管理(S・P・A)勘定からその財産の売却代金を引き出していた場合には、日本国政府は右財産の被返還者に対し昭和三十一年十月から超過利得額の返済請求を行つているが、昭和三十二年七月二十日現在の右請求件数および金額は左のとおりである。(単位千円)。
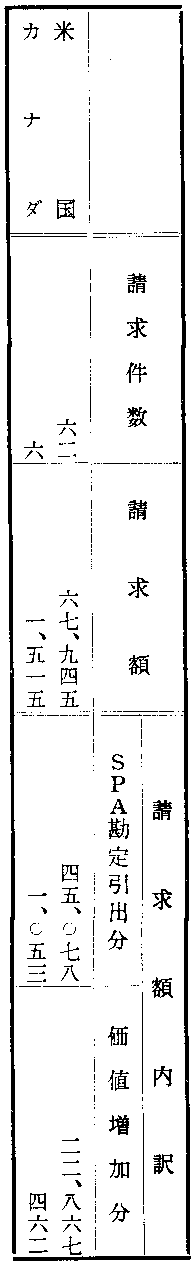
しかしこれに対し米加両国政府より、返還財産の価値増加による超過利得額の返済請求は、平和条約第十五条(a)および第十九条(a)ならびに(b)違反するとして異議が唱えられているので、本件の解決にはなお相当の時日を要すると思われる。
昭和三十年四月七日重光外相とアリソン駐日米国大使との間に、生産性向上計画に関する日米両国政府の協定が締結されたが、右計画は、米国の対日技術援助資金およびわが国内資金(政府および民間)の醵出によつて、国内諸産業の経営者、技術者、労働者代表等の米国および第三国視察、米国の専門家の招聘を行い、米国より技術情報の提供を受けて企業の経営、生産、労務の面における科学的管理方式の普及を行い、これによつてわが国産業の生産性を向上せしめんとするものである。
右協定に基く実施機関として、協定の締結に先だち、財団法人日本生産性本部(Japan Productivity Center- 経営者、学識経験者、労働者代表の三者構成)が設立され、昭和三十年三月一日から発足した。
同本部は視察団の海外派遣事業として、昭和三十年度中に一五チーム、同三十一年度に二七チームを米国に派遣し本年度は七月一日現在までに九チームを米国に、また一チームをヨーロッパ諸国に派遣している。昭和三十一年十二月以降出発したチームは次表のとおりである。
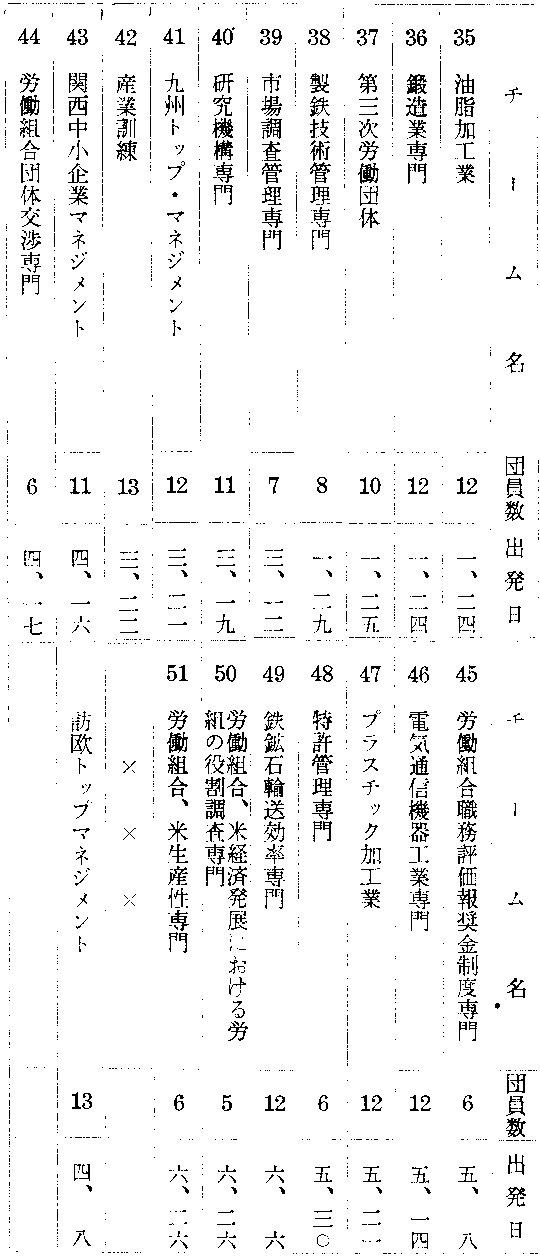
一九五二年八月に締結された日米民間航空運送協定(五三年九月十五日発効)によって、両国は互いに相手国の民間定期航空機の自国乗入れを認めているが、現在この協定の実施に関連して解決の望まれる問題としてつぎのようなものが挙げられる。
キャパシティー・クローズの解釈
民間定期航空の運航回数の決定にあたつては、関係国は各路線上の輸送サービスの量(運行数)と輸送サービスに対する需要との間に一定のバランスを保つことを考慮すべきであるとの原則は、すでに国際的にみとめられているところであるが、現実に運行する回数が需要に比較して果して過大(小)であるか適当であるかを、判定する方式については、かならずしも各国の考え方が一定していない。
強力な民間航空網をもつ米国は、つねに二国間航空協定の締結に際してキャパシティー・クローズに関しては自由主義(運航数の変更については事前に乗入相手国政府の許可を必要としないとする)を主張するのに対し、自国民間航空の保護を必要とする国では事前審査主義を主張する結果となつており、日米航空協定のキャパシティー・クローズ(第十二条)においてもこの点についてはいずれをとるかを明らかにしていない。現在までのところ、実際的解決案として、米側各民間航空会社は運航数変更の際は一応日本政府に日本の国内法に基く申請書を提出し、日本政府は審査の上これを全部許可しているが、(ただし期間を限つて許可している)今後NWA・PAAなどの東京乗入れ便の増大が予想されるので、本件キャパシティー・クローズの解釈についてはいずれ日米間の交渉の対象となるであろう。
日本航空のロスアンゼルス乗入れ問題
現在日米航空協定の附表によつて認められている日本側航空機の米国本土乗入れ地点は、サン・フランシスコ、シアトルの二点に限られているが、南カリフォルニアと日本との間の交通量の増大に伴い、日航のロスアンゼルス乗入れが望まれている。このため一九五四年ワシントンにおいて、日米航空協定の附表を修正し日本側航空機のロスアンゼルス乗入れを認めさせる(日本側はその代償として、米航空機の大阪乗入を提案した。)ための予備交渉を行つたが、米側はロスアンゼルス、サン・フランシスコのいずれか一方のみしかみとめ得ないとの主張を固執し、ついに交渉は不成立のまま無期休会となり現在にいたつている。
北太平洋漁業国際委員会は、一九五二年五月に締結された北太平洋の公海漁業に関する国際条約(一九五三年六月十二日発効)に基き日米加三国政府代表によつて構成されている委員会であるが、条約の附属書によつて現在委員会が資源保存措置の対象としているのは北太平洋のサケマス、オヒョウ、ニシンの三魚種であり、また調査研究の対象としては上記三魚種の他に東部べーリング海のタラバガニが加えられている。
条約は、北太平洋の豊富な漁業資源もこれを無統制な濫獲に放任すれば涸渇を来すおそれがあるので、これら資源から長期に亘つて最大の生産量を得られるように、三国が協同して必要な保存措置をとることを目的として締結されたものであり、特定水域における前記サケ・マス、オヒョウ、ニシンの三魚種について締約国の一または二が自発的に漁獲抑止をしている点に特色がある。
委員会の第一義的任務は、右の抑止魚種が果して継続して抑止の条件を具えているかどうか、またその他の魚種で抑止魚種に追加すべきものがあるかどうかを決定するための調査研究を行い、その結果に基いて必要と思われる措置を各締約国に勧告することにある。
現在三国の関心の焦点となつているのは、日本が条約に基きその東側ではサケマスの漁獲を自発的に抑止している西経百七十五度線の問題である。すなわち北太平洋水域には、この条約で抑止の対象となる北米大陸系のサケと抑止の対象とならないアジア系のサケとがあるが、この附近の海面におけるサケの分布状態等に関する科学的調査が十分になされていないため、本件条約締結のための三国漁業会議においてはこの両者も最もよく分つ線を決定することができなかつたので、将来の科学的調査研究をまつて一そう公平に両者を分つ線を決定することとし、一応前記の西経百七十五度線に暫定的によることとしたのである。したがつて、将来この線の変更を妥当づけるような科学的資料が得られれば当然その変更が討議されることとなるので、三国とも各自国に有利な結果の得られることを期待しつつこの種の科学的調査の実施に意を用いている。
なお現在附属書に記載されている抑止魚種については、条約発効後五年間、すなわち一九五八年六月までは委員会は抑止の条件の存否についての決定勧告は行わないことになつているが、それ以後の時期には抑止の条件のなくなつた魚種を抑止の枠から外すことを勧告することもできるわけであり、現在これら抑止魚種の抑止条件について研究調査を行うため委員会の中に特別小委員会が設けられている。
したがつて、来年東京において開催予定の委員会の一九五八年度年次会議では右の特別小委員会の報告に基いて抑止魚種の抑止条件についての討議が行われるとともに、前記西経百七十五度線の改訂問題も併せ審議されるものと予想され、本件委員会発足後最初の緊迫した零囲気の中に討議が行われるものとみられている。
北太平洋のおつとせい資源については、一九一一年日、英(カナダ)、米、露四カ国の間におつとせい保護条約が結ばれ、おつとせい海上猟獲の禁止を約するとともに、おつとせい繁殖島を有する国は他の締約国へ一定の獣皮分配を行うことになつていた。しかしその後めざましい繁殖によりおつとせい資源が増大するに伴い、かえつて北洋漁業資源に対する食害の傾向がみられたので、一九四〇年わが国は同条約の廃棄を宣言し、条約規定にしたがつて翌一九四一年同条約は失効した。
戦後わが国は、一九五一年の漁業に関する吉田ダレス書簡に基きおつとせいの海上猟獲を自発的に抑止していたが、一九五五年の十一月からワシントンにおいて日、米、加、ソ連四カ国の間に新しいおつとせい条約締結の交渉が始められた。右交渉においては、おつとせいの商業的海上猟獲の再開を主張する日本と、大規模な商業的海上猟獲は資源に害ありとする米国およびすベて海上猟獲は禁止すべしとするソ連とが対立して容易に妥結に達しなかつたが、結局妥協案として、条約発効後六年間は暫定的に商業的海上猟獲を禁止し、この間締約国政府による年間数千頭の試験的海上猟獲を行い海上猟獲の資源に及ぼす影響について調査を行うとともにこの間繁殖島を保有する米ソ両国は日、加両国に対して、各々その陸上捕殺獣皮の十五パーセントを分配することを約した。
この条約は本年二月署名を終り、本年末までには締約各国の批准が得られ発効の見込であるが、条約が発効すれば、毎年一回北太平洋おつとせい委員会を開き、おつとせいに関する海上猟獲を含む各種の協同科学調査の細目、獣皮分配の手続等を議することになつており、さらに六年後にはこの暫定条約の実施の結果を考慮した新しい条約の締結が議せられることになろう。