開発協力トピックス
ミャンマーの少数民族に対する ODAを通じた支援
1.少数民族問題とは
ミャンマーには、135の民族が存在するといわれています。そのうち、ビルマ族が人口の約7割を占め、中央平原部を中心に居住しています。残りの約3割の少数民族は、主に国境の山岳地帯等に居住しています。少数民族は大きく分けて、カチン、カヤ-(カレンニー)、カレン(カイン)、チン、モン、シャン、ラカイン(アラカン)の7民族があり、それらがさらに134の民族に細分化されます。
ミャンマーにおける少数民族問題は、英国植民地時代の分割統治に起因する根深い問題です。1948年のビルマの独立後も、一部の地域では、60年にわたって国軍と少数民族武装勢力との間で戦闘が続き、戦渦に巻き込まれた多くの人々が居住地を追われ、国内で避難民となったり、隣国に逃れて難民となったりしました。特に、カレン州においては40万人以上の国内避難民が発生し、10万人以上がタイの難民キャンプで暮らしています。また、長年にわたる戦闘の結果、少数民族地域は開発から取り残され、農村などの荒廃が進みました。経済的困窮は、麻薬の生産や取引への関与等の問題も引き起こしています。また、一部の地域では、戦闘の中で、政府側、少数民族側双方によって大量の地雷が埋められたといわれています。
2.現政権の取組と今後の課題
2011年に発足したテイン・セイン政権は、国内の民主化、経済改革を進めるのと同時に、少数民族勢力との和解についても、早急に和平を完了させることを宣言して積極的に取り組み、カチン族を除く、ほとんどの民族と基本的な停戦合意に達しています。しかし、少数民族問題の解決のためには、多くの課題が残されています。今後は、政府側と少数民族側双方の信頼関係を醸成し、和平プロセスを進めるとともに、荒廃した少数民族居住地域のコミュニティを開発し、農業などの産業を振興していく必要があります。国内避難民や難民の帰還も、受け皿となるコミュニティと生計の手段がなければ進みません。これらを実現するためには国際社会からの支援が不可欠です。
3.日本の支援
日本は、最近のミャンマーにおける少数民族勢力との和平プロセス等、国民和解に向けた取組を高く評価しており、地域開発と平和の定着を促進し、ミャンマーの安定と持続的発展に貢献するため、少数民族地域に対する支援を積極的に実施していく方針です。
日本はこれまで、少数民族地域に対しては、主要産業である農業分野での支援を中心に、各州の課題やニーズに応じて支援を実施してきました。
具体的には、シャン州北部における麻薬代替作物の普及・流通等の支援を通じた農村開発支援(技術協力)、シャン州南部での循環型農業による生産・流通支援(NPO法人地球市民の会との連携による技術協力)、チン州での高付加価値の植物(薬用植物等)の栽培技術普及支援(高知県牧野記念財団との連携による技術協力)などを行ってきました。
その他の分野においても、保健分野で、シャン州コーカン自治地域における母子保健の改善支援(NPO法人AMDA(アムダ)社会開発機構に対する日本NGO連携無償資金協力)、ラカイン、シャン等6州・地域における食糧支援(国連世界食糧計画(WFP)との連携による無償資金協力、8.14億円)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じた国内避難民支援(2億円)などを行っています。 さらに、タイに逃れた難民に対しても、草の根無償資金協力によって、タイ側難民キャンプ9か所への防火施設設置・防災教育支援(980万円)や職業訓練施設の建設支援(1,400万円)などを実施してきました。
また、2013年2月には、日本はミャンマーの国民和解の進展への貢献と具体化するため、笹川陽平日本財団会長を、ミャンマー国民和解担当政府代表(注1)に任命しました。
今後は、住民が和平の配当を実感することにより、和平プロセスを促進するため、同プロセスが進展しているカレン州やモン州をモデルとして、難民の帰還・再定住のための開発計画の策定を支援するとともに、道路整備やコミュニティ・インフラ整備、生計向上支援を行い、それらの事例を各州に広めていくことを目指しています。また、引き続き、国際機関やNGOとも連携して、各州のニーズに応じた支援や人道援助を積極的に実施していきます。
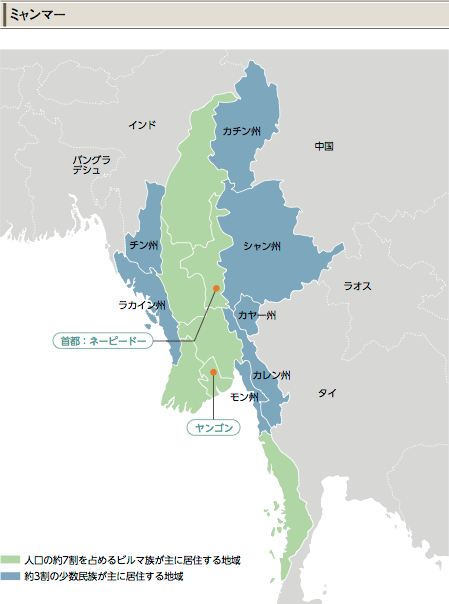

シャン州コンジャンにあるマーケット

マーケットに向かう人々
注1 : 正式名称は、「ミャンマー国民和解に関し、関係国政府と交渉するための日本政府代表」