(6)内外の援助関係者との連携
日本は、民間企業、NGO、大学、地方自治体、国際機関や他の援助国とも連携しながら国際協力を行っています。
(イ)NGOとの連携
近年、NGOは環境、人権、貿易、軍縮など、主要外交分野における政策提言などを通じて、国際社会において重要な役割を果たしています。日本のNGOは、教育、保健医療、水供給、難民支援、地雷処理など様々な開発協力分野において質の高い援助活動を実施しているほか、大規模災害や紛争の現場で迅速な人道支援活動を展開しています。地域住民のニーズに知見を有するNGOは、政府では手の届かない地域での活動が可能であり、日本の「顔の見える援助」にもつながります。日本は、ODA大綱やODA中期政策においてNGOとの連携推進を掲げており、NGOによる援助活動への資金協力、能力強化への支援、対話の促進など、様々な連携推進策を実施しています。
(a) NGOが行う事業との協力
日本は、NGOが円滑に援助活動を実施できるように様々な協力を行っています。たとえば、NGOの草の根レベルの経済社会開発事業に資金を供与する日本NGO連携無償資金協力を通じて、2008年度に45団体が、学校建設、保健診療所の運営、職業訓練、井戸の建設など計72件の事業を実施しました。また、2000年にNGO、政府、経済界の連携によって設立された緊急人道支援組織であるジャパン・プラットフォームには、2009年12月時点で32のNGOが参加し、事前に拠出されたODA資金や企業・市民からの寄付金を活用して大規模災害発生時などに迅速に生活物資配布、医療支援などを行っています。2008年度には、ミャンマー・サイクロン被災者支援、中国四川地震被災者支援、スーダン南部人道支援、イラク人道支援など、9か国・1地域において57件、総額約16億5,000万円の事業を実施しました。また、2009年度には、インドネシアで起こったスマトラ島沖地震や、フィリピンにおける水害の被災者支援のための活動を行いました。
JICAは、2007年度以降、NGOなど民間団体のノウハウを活用するため、プロジェクト形成段階において調査内容の提案を広く募集する「民間提案型」プロジェクト形成調査(注81)を行っています。また、業務実施契約に基づく技術協力プロジェクトなどにより、2008年度は、211件のプロジェクトの実施を民間団体に委託しました。近年、NGOや大学が委託先となり種々のプロジェクトが実施されるなど、様々な団体のノウハウが活用されています。さらに、JICAはNGOや地方自治体などが提案する案件で、開発途上国の地域住民の生活向上に直接貢献し、政府が定める国別援助計画に沿っているものについて事業の委託を行う草の根技術協力を実施しています。特に、この協力制度の中の草の根パートナー型では、国際協力に一定の実績を有しているNGOなどが蓄積してきた経験や技術を活かした開発途上国への支援を行っています。

2009年12月23日、西村智奈美外務大臣政務官は、ビエンチャン特別市(ラオス)を訪問中、日本のNGO「IV-JAPAN」が運営する女性職業訓練センターの模様を視察しました。IV-JAPANは1988年に設立され、これまでタイやラオスにおいて農村開発・職業訓練への支援事業や国際文化交流等を行っています。ビエンチャン特別市における女性職業訓練センターでは、JICA草の根パートナー事業として、調理、裁縫、理容といった職業訓練が行われ、ラオスの少女たちの起業と自立促進に貢献しています。上記の写真は、縫製の初級コースで学ぶ女子生徒が、ラオス風ブラウスの製図を行っているところです。作成した製図をもとに、布を使用してブラウスを製作します。上級コースに進むと、制作した作品を実際に販売することもできるようになります。職業となる技術を身に付けて、自分の手で未来をつかむために日々頑張っている彼女たちが、将来のラオスの発展を支える原動力となっていくことでしょう。
注81 : 2008年10月1日以降、協力準備調査の一部として整理。
(b) NGO活動環境の整備
NGO活動のさらなる支援策として様々な活動環境整備事業を実施しています。たとえば「NGO相談員制度」では、外務省の委託を受けたNGOの職員がNGOの設立、組織運営や活動、国際協力活動などに関する市民やNGO関係者からの照会にこたえています。そのほか、国際協力イベントなどで相談に応じたり、出張して講演を行うサービスを行っており、NGO活動の促進およびNGO活動に対する理解促進を図っています。また、NGOのアカウンタビリティー向上を促進するためのセミナーや、企業との連携推進などのテーマごとにNGOが自ら学習会やシンポジウムを実施する「NGO研究会」を主催するなど、NGOの組織運営能力や専門性の向上を支援する取組も行っています。
JICAは、NGOスタッフのため様々な研修を行っています。たとえば、開発途上国でのプロジェクトの実施能力の向上を図るプロジェクト・マネジメントや国内での広報・資金調達能力を強化する組織マネジメントに関して研修を行うNGO人材育成研修、草の根技術協力などの事業計画立案・評価手法の習得を図るプロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)研修、NGOが団体ごとに抱える問題に対し個別にアドバイスを行うための国内外へのアドバイザー派遣などを行っています。

ヨルダンにおける土嚢建築ワークショップ(写真提供 : (社)日本国際民間協力会(NICCO))
(c) NGOとの対話と連携
1996年以降外務省は、NGOとの対話および連携を促進するため、NGO・外務省定期協議会を開催し、日本の援助政策や日本NGO連携無償資金協力などのNGOを対象とした資金協力制度に関する協議を活発に実施しています。2002年以降は開発途上国でのNGOとの意見交換の場として通称「ODA大使館」を開設し、これまでネパールやスリランカをはじめとする13か国で、大使館、援助実施機関、NGOがODAの効率的・効果的な実施について協議を行っています。JICAは、より効果的な国際協力を実現するため、NGOを含む市民の理解と参加を促進するNGO-JICA協議会を開催しています。
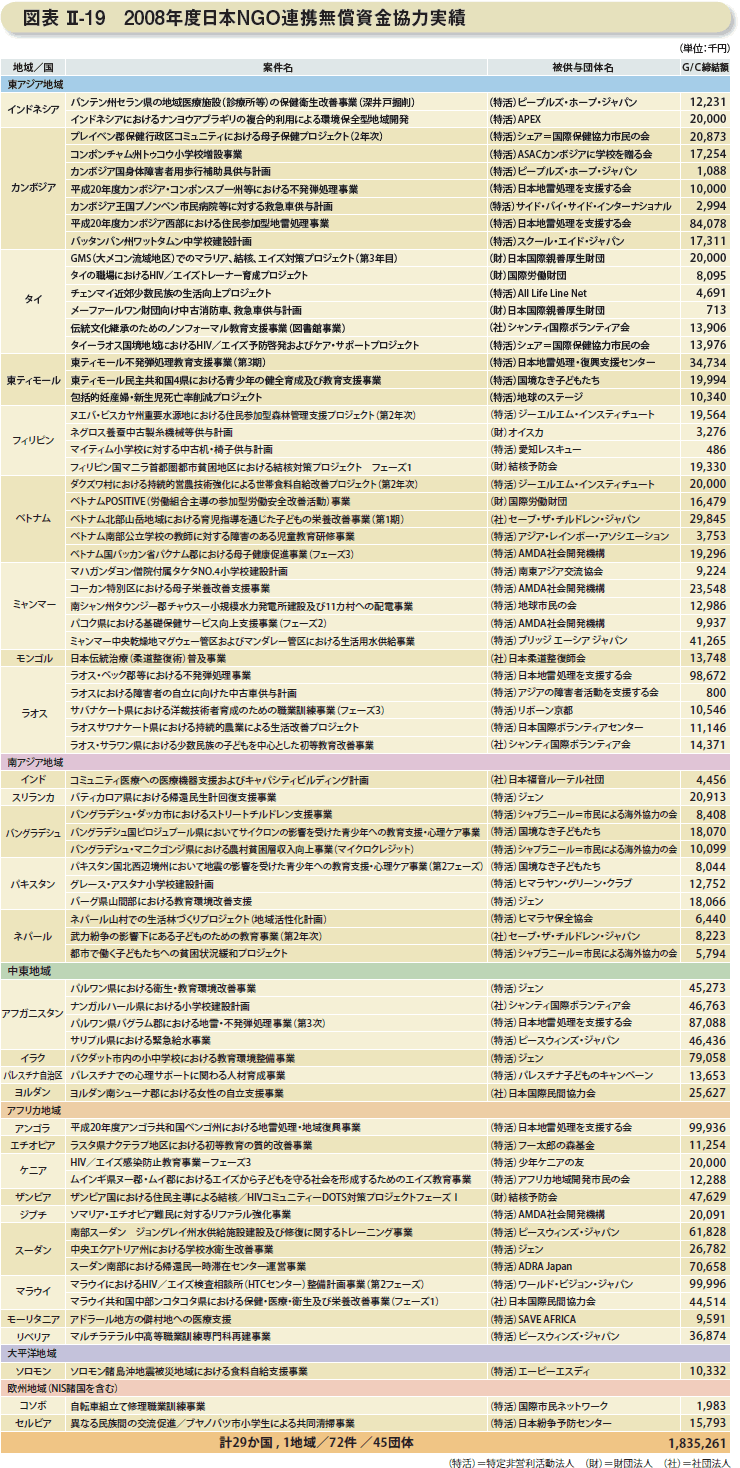
(ロ)民間企業との連携
(a) 成長加速化のための官民パートナーシップ
民間企業の活動は、雇用促進や技術移転、貿易投資の拡大など、ODAだけでは達成できない規模の開発効果を開発途上国にもたらすことができます。2008年4月には、国際協力に関する有識者会議による中間報告や最終覚え書き、経済団体などからの各種提言などを受け、官民連携促進など「成長加速化のための官民パートナーシップ」を発表しました。この施策は、官民双方に有意義なパートナーシップを構築し、官民連携を通じて対外政策を共有し、開発問題に官民一体となって取り組むことを目的としています。
具体的には、<1>官民連携に関して民間から提案された案件の採択・実施(官民連携相談窓口を外務省、財務省、経済産業省、JICAに設置)、<2>ODA関係省庁およびJICAなど援助実施機関と日本経済界の間で定期的な政策対話の実施、<3>開発途上国における官民連携の促進(現地日系企業が参画する「拡大現地ODAタスクフォース」の設置)を柱としており、具体的な成果が出てきています。
(b) 円借款の迅速化
開発途上国への開発支援に取り組むにあたり、官民連携の必要性が広く認識され、円借款と民間事業の実施とを効果的に組み合わせた迅速な開発効果発現が求められており、効果的な官民連携推進の観点からも、円借款の迅速化を一層進展させる必要があります。
日本は、借入国側のオーナーシップ、不正・腐敗防止や環境社会配慮など、説明責任や適正な手続の確保に留意しつつ、平成19年の「円借款の迅速化について」を踏まえた更なる迅速化策として、平成21年に「官民連携推進等のための円借款の迅速化」を発表し、民間セクターなどとのスケジュールの情報共有、本邦技術活用条件(STEP(注82))案件におけるJICAの詳細設計支援による迅速化などを定めました。
注82 : 日本の優れた技術やノウハウを活用し、開発途上国への技術移転を通じて日本の「顔の見える援助」を促進するため、2002年7月に本邦技術活用条件(STEP: Special Terms for Economic Partnership)を導入している。
(ハ)大学・地方自治体との連携
日本は、より効果的なODAの実施のため、大学や地方自治体が蓄積してきたノウハウを活用しています。JICAは、大学が持つ知的財産を活用すべく、大学との契約により包括的な技術協力の実施や円借款事業を推進しています。大学にとっては、JICAと連携することで開発途上国の現場にアクセスしやすくなり、実践的な経験を得られるという利点があります。また、地方自治体とも、事業の質的向上、援助人材の育成、地方発の事業展開の活性化において連携しています。
(二)開発途上国の地方自治体・NGOなどとの連携
開発途上国の地方自治体やNGOとの連携は、開発途上国の経済社会開発に有益なだけではなく、開発途上国の市民社会やNGOの強化にもつながります。日本は、主に草の根・人間の安全保障無償資金協力を通じて、これら援助関係者が実施する経済社会開発事業を支援しています。この資金協力は、草の根レベルに直接利益となるきめ細かで足の速い支援として開発途上国でも高く評価されています。
(ホ)国際機関や他国との連携
近年、援助効果を促進するとの観点から、MDGs、パリ宣言(注83)、アクラ行動計画(注84) (AAA)など国際的な開発目標および合意事項の達成のため、様々な援助主体が援助政策の協調を図っています。現在、多くの被援助国において、保健や教育など分野ごとに作業部会が形成され、その国の分野別開発戦略に沿って、プログラム型の支援が実施されています。日本はタンザニアにおいては農業、イエメンにおいては水など、多数のプログラムに参加しています。また、バングラデシュにおいては、アジア開発銀行(ADB)、英国国際開発省(DFID(注85))と同国の貧困削減戦略(PRS)支援のための共通戦略パートナーシップを策定し、セクター横断的により効果的、効率的な援助を実施するための協調・連携を進めています。また、現在は、より多くのドナー間での共通援助戦略を策定するための作業部会にも参加し、援助協調に積極的に関与しています。
また、世界銀行などの国際機関との間において、幹部の来日の機会などを捉え、援助政策のあり方などについて政策対話を行っています。さらに日本は、2007年にアジア開発銀行(ADB)との連携の一環として、「アジアの持続的成長のための日本の貢献策(ESDA)」を発表し、投資の促進および省エネの促進に取り組んでいます。
これまで国際社会では、経済開発協力機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)の加盟国が中心となって援助を行ってきましたが、近年、東欧諸国、中東諸国、中国、ロシア、南アフリカ、ブラジル、シンガポールやマレーシアなどの東南アジア諸国などDAC加盟国以外の国による援助活動が顕著になっています。日本を含むDAC加盟国は、これら諸国が責任ある援助国として世界の課題の解決に向け連携して取り組むよう、必要に応じてこれまでの援助経験を共有し、協力していくことが大切です。
注83 : 援助の質の改善及び効率の向上のために必要な措置について、援助国と被援助国双方の取組事項をとりまとめたもの。2005年にパリで開催された「第2回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム」で採択された。
注84 : 2008年9月にガーナで開催された「第3回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム」にて採択された行動計画。パリ宣言の目標達成に向けて、援助効果の更なる向上への決意及び2010年までの取組が記載されている。
注85 : DFID:Department for International Development