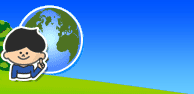| ■国際協力(国際機関) |
 |
 |
 |
 |
 |
国連児童基金(UNICEF)
世界158の国や地域で子どもの健やかな成長と発達を守るため1946年に設立されました。子どものニーズを専門に担当する国連では唯一の機関として、保険、栄養、水と衛生、教育などの事業を、政府やNGOと協力しながら実施しています。とりわけ、1990年9月に国際法となった「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」の履行促進を図るとともに、途上国の子どもを支援し、また女性の社会参加にも力を注いでいます。
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
国連開発計画(UNDP)
1996年1月に技術協力活動を推進する国連システムの中心的資金供与機関として発足しました。その任務は、開発途上国および市場経済移行国における持続可能な開発を多角的に支援することにあります。
<現在の重点分野>
(1)貧困の削減 (2)民主的ガバナンスの確立 (3)情報通信技術(ICT) (4)HIV/AIDS (5)環境保全と持続可能なエネルギー開発 (6)紛争後等の開発及び自然災害の軽減
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)
難民を保護し、難民問題の恒久的な解決を促進するために1951年、国連総会によって設立されました。世界で2,100万人以上に上る難民・避難民等に援助活動を行っています。主な任務は、人道的な立場から、国籍国の保護を失った難民に「国際的な保護」を与え、住居・食料・医療などの援助を行い、そして難民問題の解決をはかることです。
UNHCRは、国際的な貢献が認められ、これまで1954年と1981年に2回の「ノーベル平和賞」を受賞しています。
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
国際連合教育科学文化機関(UNESCO)
第二次世界大戦が終わった1945年に、人類が二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにとの願いを込めて、国連の専門機関として創設されました。
ユネスコの役割は、様々な人々の異なった文化や思想を理解し(相互理解)、国や民族を越えて相互に認め尊重しあい、人々が協力しあうことを学び(国際理解・国際協力)、友情と連帯の心を育て、ともに生きる平和な地球社会をつくっていくことです。
現加盟国は188カ国。加盟各国内にはユネスコ国内委員会が設置されています。
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
世界銀行(WORLD BANK)
世界銀行とは一般に、国際復興開発銀行(IBRD)と国際開発協会(IDA)の2つの機関を意味します。これに、姉妹機関である国際金融公社(IFC)、多数国間投資保証機関(MIGA)、投資紛争解決国際センター(ICSID)の3機関をあわせて、「世界銀行グループ」と呼びます。
世銀グループは、開発途上国の経済・社会発展を促進し、人びとの生活水準の向上を助け、各国が自らの力によって発展するように支援することを使命としています。
開発途上国の経済・社会発展、生活水準の向上、各国の自助発展を支援するための主な活動として、貸付・融資、技術協力、調査・研究などを推進しています。
|
 |
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
世界保健機構(WHO)
世界のすべての人々が最高水準の健康を維持できるようにすることを目的とし、その取り組みは、保険教育、適正な食料供給と栄養、安全な飲料水と衛生設備、家族計画を含む母子保健、主要伝染病に対する免疫対策、風土病の防疫と管理、一般的な疾病と傷害の適切な治療、基礎医薬品の常備の8つの分野で構成されています。
特に、保険関係の人的資源、必要不可欠な医薬品や物資の供給などにより、保健制度の強化を図るための援助を行っています。また、保健すべての分野で、適切な技術開発に必要な研究を促進しています。
|
 |
 |
 |
 |
|