| 1.国際交流の推進 |
今日の国際社会は、政治、経済、文化、社会等のあらゆる面において相互依存を深めている。また、冷戦の終結とともにイデオロギーの対立に替わって、民族や文化の違いが国際関係の前面に押し出されてきた。こうした状況の中で、国際社会の安定的発展を確保する上で、各国がお互いの民族、文化、社会の多様性を認め合い、相互理解を深めていくことが益々重要になってきている。また、貧困、エネルギー、人権、環境問題等地球的規模の問題が多数生じてきており、これらの問題に取り組むための国際交流が活発化している。
国際交流の推進は、88年の竹下総理大臣のロンドンでの演説の中で国際文化交流が日本の外交政策の三本柱の一つとして位置づけられて以来、積極的に行われてきた。97年1月のシンガポールにおける橋本総理大臣の政策演説では、「文化交流、文化協力の推進」が3つの提言の一つとしてうたわれた。また、途上国との関係においても、これまでの経済面での協力だけでなく、文化面での協力が求められている。こうした中で、二国間、多国間を問わず、首脳会談、外相会談等において、文化交流や文化協力がテーマとして頻繁に取り上げられるようになってきている。
近年、国際交流の担い手は、国や国際交流基金の他に、地方自治体、民間団体、教育・研究機関、企業、個人など、多様なレベルに広がってきている。特に、「国際化」と「文化」という共通のキーワードの下に、国内各地方の草の根交流の進展がめざましい。今後、官民の連携を含め、国内関係組織のネットワークを作り、国際交流をより効果的に進めていくことが重要である。
また、これまでの相互交流を中心とした文化交流のみならず、途上国の文化の振興や文化財保存に協力することもますます重要になってきている。各国の文化財の中には、急激な経済発展や社会の変化に伴い、失われる危機に瀕しているものが少なくない。日本は、こうした「人類共通の遺産」を救済するために、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の枠組みやユネスコに設けた日本信託基金を活用しながら、カンボディアのアンコール遺跡などの文化財保存協力を実施している。また、途上国の文化の振興に協力するため、文化無償協力により資機材を供与している。
国際交流の分野においても、各国、地域の特性や日本との関係を踏まえて、きめ細かな施策を行っていくことが重要である。
北米との交流は、日米間の緊密な関係を反映して、地方自治体や民間のあらゆるレベルで活発な人的交流が行われてきている。例えば、「JETプログラム (Japan Exchange and Teaching Programme)」(海外青年を日本の各地方自治体に招聘し、中・高等学校の外国語指導や国際交流活動に従事してもらうプログラム)では、発足以来、2万人を超える米国、カナダの青年が来日し、地域レベルでの国際交流に大きく貢献している。また、国際交流基金の日米センターでは、日米の学者・研究者間のセミナー、シンポジウム、共同研究等を通じた知的交流を促進しているほか、草の根交流を支援している。
欧州との交流は、従来より、お互いの伝統文化に対する高い関心に基づく交流が行われてきたが、近年、交流の幅が広がりをみせ、相互の文化を総合的に紹介する大型文化事業が多数行われている。日仏両国首脳間の意見の一致により、97年4月から1年間は「フランスにおける日本年」と位置づけられ、日本の伝統文化から現代日本を幅広く紹介する種々の文化事業が行われ、98年4月からは「日本におけるフランス年」が幕を開ける。また、97年5月にはパリ日本文化会館が開館し、日仏のみならず日欧の文化交流の拠点となることを目指し、多様な文化事業が展開されている。
アジアとの交流は、従来、日本の文化をアジアの諸国へ紹介することが中心であった。これに対し、最近、アジアの一部の国々の間では、日本との間でより対等な関係を基盤とする交流が行われるようになってきている。例えば、インドネシア政府は民間の協力を得て、97年8月から11月にかけて、日本で古代王朝宝物展を始めとする総合的な文化紹介事業(インドネシア日本友好祭’97)を行った。また、ASEAN諸国との間では、橋本総理大臣の提案による多国籍文化ミッション(日本とASEAN各国の有識者からなるミッションが日・ASEAN間の文化交流に関する提言を行う)など、多面的、多角的な交流を促進する新たな試みも見られるようになった。また、アジアと欧州間の対話と交流を促進すべく、アジア欧州会合(ASEM)のフォローアップとして、第一回アジア欧州ヤングリーダーズシンポジウムを3月に東京及び宮崎で開催した。
97年に設立25周年を迎えた国際交流基金は、国際交流の実施に当たり、中核的役割を担っている。しかし、国際交流基金の現在の体制(97年度の予算:206億円、海外事務所:18ヶ所)は、国際交流の重要性の高まりに比べて、必ずしも十分とはいえない。ブリティッシュ・カウンシル(英国)やゲーテ・インスティテュート(ドイツ)等の海外の類似機関と比較しても不十分である。今後、一層の効率的、効果的な事業実施を図るとともに、実施体制の更なる強化を図ることが重要な課題である。
また、国際交流基金の主要な事業の一つである海外での日本語普及については、日本語国際センター(浦和)に加えて、5月には関西国際センターの活動を開始し、日本語普及の強化を図っている。
留学生交流については、21世紀初頭における「留学生受入れ10万人計画」のもとに、積極的に取り組んでいるが、近年、私費留学生数が伸び悩んでおり、国内外の受入れ体制の整備等に努めていくことが重要となっている。また、知日家を形成する方途の一つとして帰国留学生の同窓会作りの支援も重要である。
| 2.国内世論と広報及び諸外国の対日理解 |
近年、通信・情報システムの急速な発展に加え、経済・文化面の交流の深まりや海外渡航者及び海外在留邦人数の増加など人的交流の拡大を通じ、世界各地の動向や外交に対する国民の関心は高まっている。
内政と外交は不可分一体であり、日本政府は、世論を十分に踏まえた外交政策の策定を図りつつ、これと並行して、日本の外交政策について広報活動などを積極的に行うことにより、国民の更なる理解を図り、その支持を得る努力を続けている。
例えば外務省は、1976年以来、30年を経過した外交記録を公開することとし、審査の終わったものから順次公開してきたが、97年2月24日、第13回目の公開を行った。同公開では、「阿波丸請求権処理のための日米協定関係一件」など主要な案件のほか、各国内政、外交、経済など2800件あまりを公開した。外務省では記録公開を外務省の重要施策の一つに据え、できる限り多くの記録を公開するように努めている。
さらに、インターネット「外務省ホームページ(日本語版)」及び自動FAX送信システム(「MOFAX」)を用い、国民が自宅や職場から国際情勢や外交問題についての最新の資料・情報を手軽に入手できるシステムを整備してきている。特に、「外務省ホームページ(日本語版)」は、近年のインターネットの普及に伴い利用件数が急増してきており、外務省の持つ最も重要な情報提供・広報手段の一つに成長してきている。
また、国民の関心も高いと思われる重要な問題については、定期刊行物での特集やパンフレットの作成並びにTVの広報番組の作成などを通じて、できる限りわかりやすく広報し、国民の関心に応えるよう努力している。さらに、大学や高校における省員による講演会の拡充や、「外交の窓」、「外交クラブ」及び「国際フォーラム」など、地方での講演やシンポジウムを通じて、直接国民と対話する機会を増やし、外交政策に対する一層広範な支持が得られるよう努力を行っている。
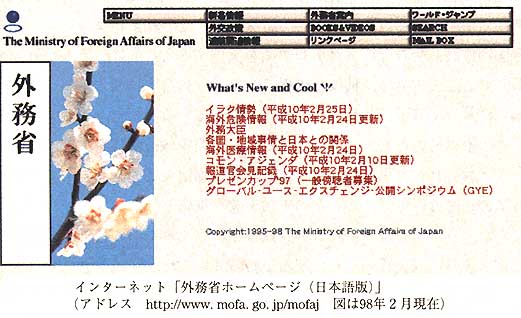
諸外国の人々が日本の姿及び外交政策を正しく理解し、信頼と好感を抱くことは、外交政策の推進にあたり欠くことのできない要素である。政府としては、こうした目標の達成のため、大使館や総領事館などを通じて様々な広報事業や働きかけを展開してきている。
具体的には、政府のすすめる6つの改革や環境問題への日本の取組を海外に説明したり、第2回アフリカ開発会議(TICADⅡ)を機とした対アフリカ広報やアジア金融不安と日本の対策に焦点をあてるなど、その時々の時宜にかなった問題を取り上げ、各地域ごとにきめの細かい広報活動を展開している。また、日本の社会事情及び一般事情については、日本についての正しい理解を得られるよう、特に海外の青少年層を対象とした広報を重視している。これらの広報を実施するに際しては、主要諸国において対日世論の調査・分析を行い、その結果に基づいて、地域、各国別に講演会などの各種広報事業を実施するとともに、要人が外国を訪問する際の内外報道機関への働きかけ並びに日本に関する誤解ないし偏見に基づく報道への反論などを行ってきている。
その他の努力として、外国のテレビ・新聞等報道関係者や、海外のオピニオン・リーダーを日本に招待したり、講演会等の講師として日本の有識者を海外へ派遣するなどの人的交流を推進している。
また、日本の一般事情及び外交政策を紹介するための各種印刷物資料、ビデオ等の作成、買い上げ、配布を行っているほか、インターネット上の「外務省ホームページ」などを通じて、日本外交全般に関する情報を英語、仏語、スペイン語、ドイツ語、アラビア語、中国語、ロシア語等の多言語で発信してきている。