| 4. 欧州 |
(1) 欧州における統合の進展
[EUの拡大と深化]
EUは欧州の中核として求心力を一層強めつつあり、統合の深化と拡大を続けている。
深化については、3月にマーストリヒト条約(欧州連合条約)見直しのための政府間会合(IGC)が開始され、「市民に身近な欧州」、「民主的かつ効率的なEU諸機構」及び「EUの対外行動における能力強化」の3分野につき議論され、12月のダブリン欧州理事会において同条約改正のための議長国案が提出された。IGCは、97年6月のアムステルダム欧州理事会における同条約改正最終案のとりまとめをもって終了する予定であるが、今後の欧州統合の進展の青写真を策定する意味合いがありその動向が注目される。
拡大については、96年に新たにチェッコとスロヴェニアが加盟申請を行い、加盟申請中の国は中・東欧、バルト諸国など14か国にのぼっている(マルタは11月に申請を凍結)。IGC終了後6か月後にサイプラスとの加盟交渉が開始されるほか、中・東欧諸国との加盟交渉開始の時期が決定される予定となっている。
中・東欧諸国は、国内の民主化・市場経済化を推進しつつ、西欧への統合を目指しており、EUとの間では、既に多くの国が「欧州協定」(将来のEU加盟をも明記した協力協定)を締結し、関係強化を図っている。
なお、北欧においては、フィンランド、スウェーデンが95年1月にEUに加盟したが、ノールウェーとアイスランドはEU加盟の意思を有さず、EUと欧州自由貿易連合(EFTA)で形成する欧州経済領域(EEA)を通じての欧州協力の強化を図っており、EU拡大に与しない動きとして注目される。
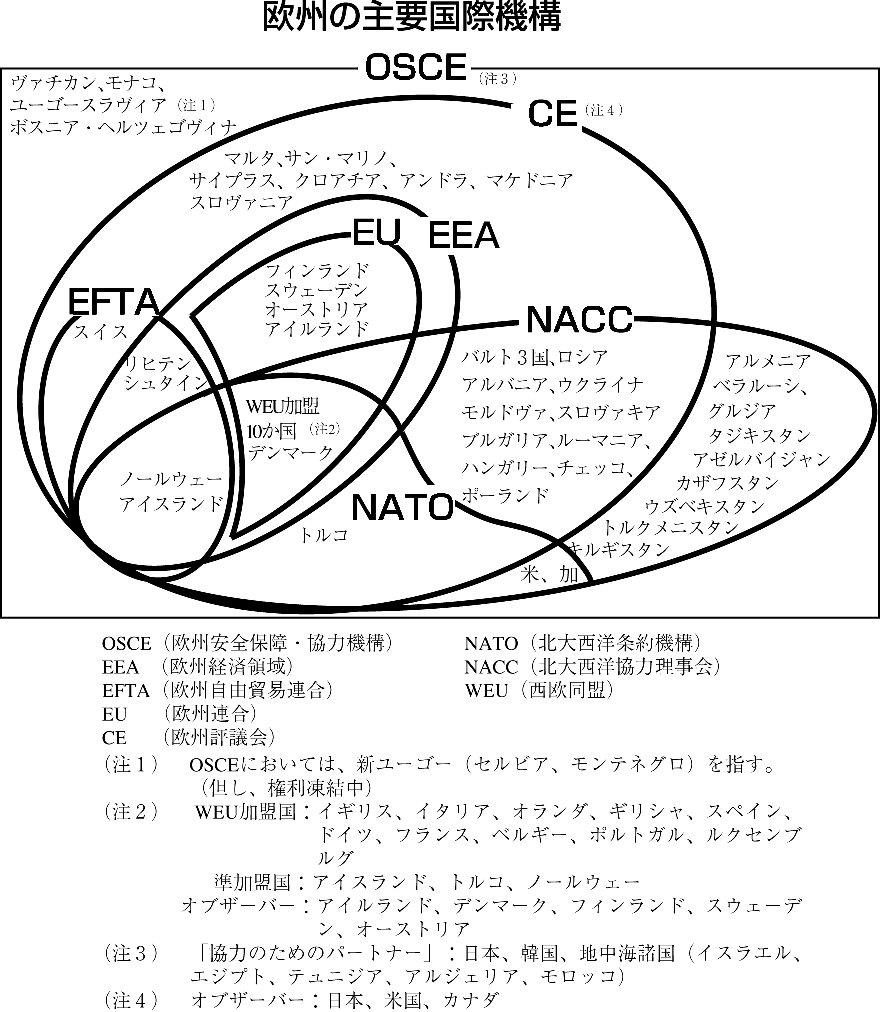

[新たな安全保障秩序の模索]
欧州においては、地域の更なる安定化に向けて、新たな安全保障の枠組みを構築する努力も続けられている。
〈NATO拡大問題〉
95年秋以降、NATO(北大西洋条約機構)は、加盟を希望する諸国との間で個別対話を実施してきたが、12月のNATO外相理事会ではその進捗状況について報告がなされるとともに、拡大の具体的日程として、97年7月にマドリッドでNATO首脳会議を開催し、加盟交渉対象国を招待すること、NATO創設50周年の99年までに新メンバーの加盟を実現すること、加盟の門戸は引き続き開放することなどが決定された。
NATO側は、拡大をNATO・ロシア間の協力関係の構築と同時並行的に進めるとの立場をとっている。ロシアはNATO拡大に反対を続けており、特に、ウクライナ、バルト諸国のNATO加盟と、新規加盟国へのNATO軍及び核兵器の配備を絶対認めないとの立場をとっているが、他方でNATOとの協力関係強化の協議には応じる姿勢を見せている。NATO側は、ロシアの懸念に配慮して、12月の外相理事会では新規加盟国への核配備は行わない旨を公式に表明し、さらに、ロシアとの関係を包括的にまとめた「憲章」の策定をロシア側に提案しており、ソラーナNATO事務総長とプリマコフ・ロシア外相との協議を開始することが決定された。97年7月のNATO首脳会議に向けて、NATO・ロシア間で調整が進められることが期待されている。
また、12月の外相理事会では、拡大の進行と並行して、「平和のためのパートナーシップ(PFP)」の拡充や大西洋パートナーシップ理事会の設置により、NATO諸国との関係強化を図ることが決定された。また、NATO内では、指揮系統の見直しや共同統合任務部隊(CJTF)の設置に向けた具体的作業も進められている。
〈OSCE、WEU〉
OSCE(欧州安全保障協力機構)は、9月に実施されたボスニア・ヘルツェゴヴィナでの選挙の準備・実施において中心的な役割を果たした。OSCEと、NATOを中心とした和平実施部隊(IFOR)等との協力体制は、今後の欧州における安全保障機構相互間の協力の一つのモデルケースとなった。12月のOSCEリスボン首脳会議においては、「共通の安全保障空間の創設」を盛り込んだ安全保障宣言モデル及びリスボン宣言が採択され、ロシアを含む欧州全域の安定化への流れが確認されるとともに、92年の発効後、欧州安全保障の基礎となっている欧州通常戦力条約(CFE)を、新たな安全保障環境に適合させることが確認された。
「EUの防衛面の不可欠な要素」であると共に、「NATOの欧州の柱を強化するための手段」として、その役割が位置づけられているWEU(西欧同盟)は、11月の閣僚理事会において、オペレーション能力の向上及び装備協力を規定したオーステンデ宣言を採択し、NATOとの協力・協調を更に発展させていくこととされた。
(2) 経済の動向
[EU諸国の経済動向]
欧州経済は、95年半ば以降足踏みを続けている(11月の欧州委員会経済見通しによれば、EU全体の実質GDP成長率は、95年の2.4%に対し、96年は1.6%に落ち込む見込み)。しかし、96年後半からは徐々に回復傾向を示しつつあり、97年以降は、各国の財政・金融政策のバランスの改善等による長短金利の低下、力強い域外需要に支えられた域外輸出の堅調な推移、良好な投資収益等に基づく供給面の堅調さ、外国為替相場の安定等を背景に、底堅い推移が見込まれる。
一方、失業問題は依然として深刻であり、EU諸国の平均で10.9%(96年見通し)にも達している。しかも長期失業者が、全失業者の5割近くを占めており、雇用対策はEUの最優先課題の一つである。
EUの経済通貨統合については、99年1月から統合の第三段階(欧州中央銀行による金融政策の実施、単一通貨「ユーロ」の導入等)に移行するとのタイムスケジュールは引き続き維持されている。しかし、マーストリヒト条約が経済通貨統合参加の条件としている経済収斂基準を達成することは容易ではなく、各国は、大幅な財政赤字の削減やインフレ抑制、為替の安定に向けた努力を懸命に続けている。
[中・東欧諸国の市場経済化]
中・東欧諸国経済は、94年から2年連続で全ての国の経済成長率がプラスを記録するなど、全体としてはおおむね安定している。しかし、95年のチェッコに続き、96年にはハンガリー、ポーランドがOECDに加盟するなど、経済改革が順調に進展している国がある一方、改革の動きに停滞が見られる国もあり、地域内において経済改革の進捗状況の格差が顕著になりつつある。