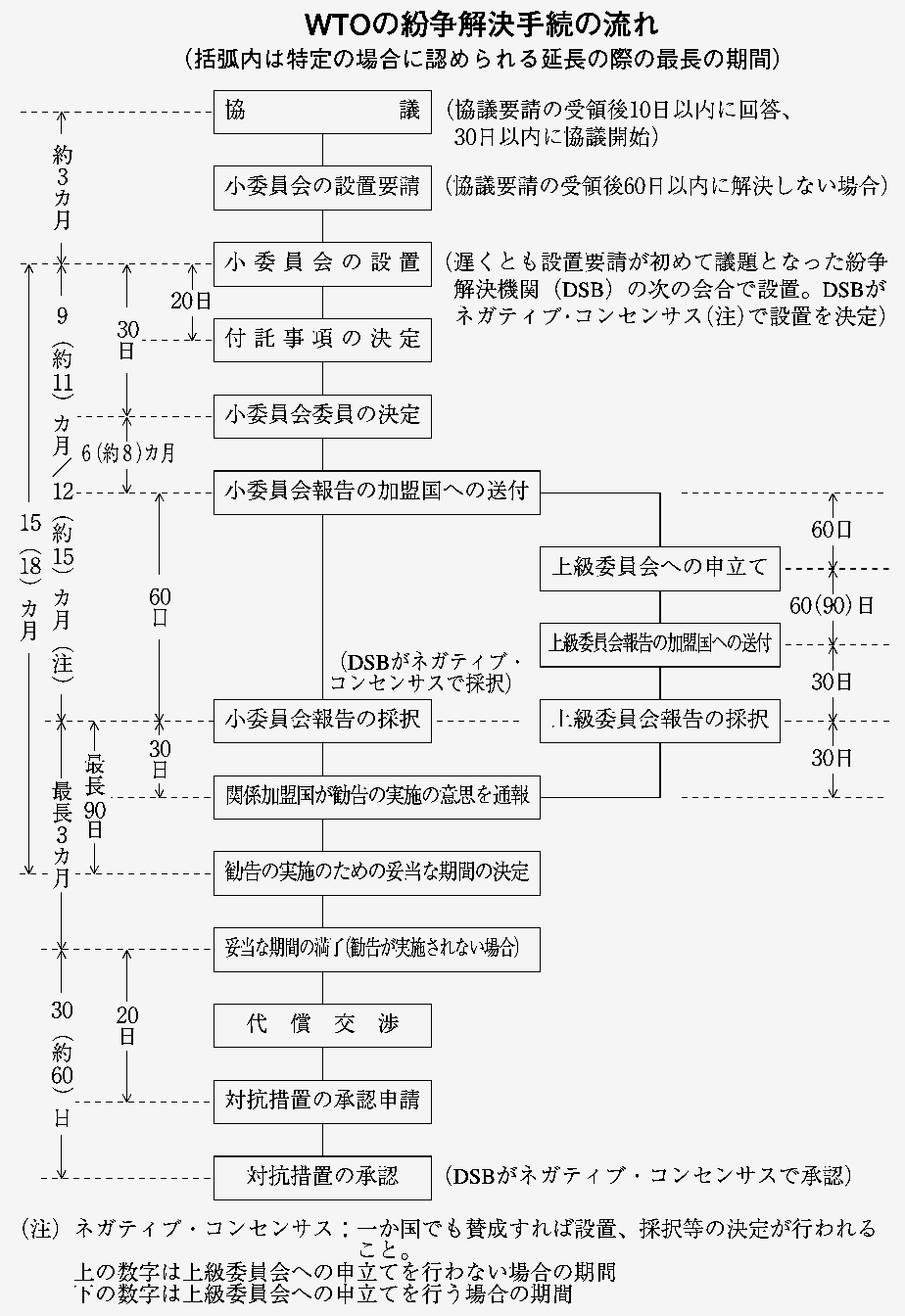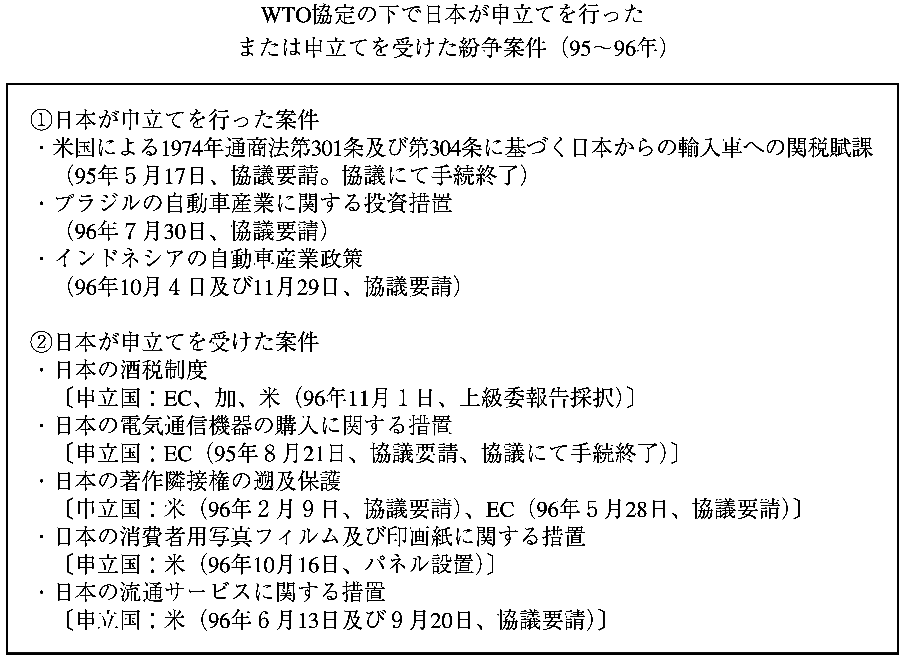| 1.世界経済の繁栄の確保と日本の政策努力 |
(1) 概観
[グローバリゼーションの進展]
世界経済は、米国の景気拡大が6年目に入るなど好調を維持し、また高成長を続けてきたアジアなどの開発途上国経済が総体として引き続き拡大していることから、拡大基調を保持している。しかしながら、米国に見られる賃金格差の拡大や、通貨統合の収斂基準を念頭においた欧州主要国の慎重な財政運営がもたらす成長への制約、さらには一部アジア NIES が輸出市場の一時的縮小のみならず構造的要因から成長の減速に直面しているなどの懸念材料があることを見逃してはならない。
こうした中で、近年の経済の急速なグローバリゼーションの進展に伴い、世界の貿易は急激に拡大を続けている。世界の実質経済成長率は、IMF(国際通貨基金)の推計によると、96年は対前年比3.8%増、97年は対前年比4.1%増と持続的・安定的な成長を続けるものと見られているのに対し、世界の貿易額(物品及び商業サービス、輸出ベース)は、WTO によると、95年には対前年比18%急増して6兆ドルを突破し、96年も拡大を続ける見込みである。
グローバリゼーションは、市場経済の大幅な広がり、情報通信技術の飛躍的発展によってもたらされたものであり、国際競争を激化するという意味で「挑戦」である。他方、これは世界経済の一層の原動力となるとともに、各先進国経済の構造的行き詰まりを打開する契機となる「機会」でもあり、前向きに捉えていかなければならない。同時に、グローバリゼーションに伴う競争に敗れた人々や、市場化の流れから取り残される人々がいることも事実であり、こうした人々への適切な配慮をすることは、グローバリゼーションへの前向きな姿勢に対する国民的支持を得る上で必要である。96年のリヨン・サミットや APEC 非公式首脳会議においてもグローバリゼーションが主要テーマとして取り上げられたところであり、日本としてはこうした考えを繰り返し強調してきた。

[日本の対応:21世紀を見据えた政策努力]
日本としては、引き続き日本経済の国際経済との調和を一層深めるとの視点に立ちつつ、グローバリゼーションの流れに積極的に対応するよう、21世紀を見据えた政策努力を続けていくことが必要である。
<経済構造改革の推進>
まず、国内的には、市場の力をできるだけ積極的に生かすことのできる経済構造にするための改革を積極的に進めていく必要がある。そのためには、経済・社会の柔軟性を高めるために、これまで以上の思い切った規制緩和、市場アクセスの改善等の政策努力を行っていかなければならない。規制緩和については、95年に11分野、1,091項目からなる「規制緩和推進計画」を策定し、96年には新規569項目を追加するなど、その改善・改定を続けている。また、自由かつ透明な金融システムの構築に向けて、金融市場の構造改革などにも取り組んでいく必要がある。
<多角的な貿易・投資の枠組みの整備>
次に、グローバリゼーションに対応して、多角的な貿易・投資の枠組みを一層整備していく必要がある。日本は、WTO が従来の国境措置の削減・撤廃を中心とする自由化の更なる推進に加え、グローバリゼーションの加速化に伴って生じている新たな課題に積極的に取り組むよう強く働きかけてきた。12月の WTO シンガポール閣僚会議では、ウルグァイ・ラウンド合意の着実な実施の確保にとどまらず、情報技術製品の関税撤廃に関する合意(ITA)などの更なる自由化、「貿易と投資」「貿易と競争政策」を始めとする新たな課題への取組など、前向きなメッセージが発出された。こうした成果を受け、日本は、引き続き WTO の中心的メンバーとして重要な役割を担っていく方針である。
また、多角的自由貿易体制を強化するためには、開発途上国や市場経済移行国を国際経済システムに一層統合していくことが重要であり、日本としては、加盟申請中の国・地域の WTO 加盟を促進するために今後とも努力していく方針である。
さらに、日本は、経済協力開発機構(OECD)における多数国間投資協定(MAI)の策定に向けた交渉に積極的に参加しているほか、国連貿易開発会議(UNCTAD)などその他の多角的なフォーラムにおける議論にも積極的に取り組んでいる。
<開かれた地域協力の推進>
こうしたグローバルな貿易・投資の枠組みの整備と並行して、近年は欧州連合(EU)、北米自由貿易協定(NAFTA)など地域統合・地域協力を推進する動きも見られる。地域統合・地域協力の進展は、域外経済にもその効果が均霑されれば、規模の経済、産業の競争力強化と構造調整の進展などによる域内経済の活性化を通じ、世界経済の発展に貢献し得るものである。その一方で、こうした地域統合・地域協力の進展が域外差別的となるおそれもあり、日本としては、地域統合などが WTO 協定に整合的であり、かつ多角的自由貿易体制を強化・補完するものであることを確保する必要がある。アジア欧州会合(ASEM)においても、地域統合が国際社会全体の利益となることが必要であるという認識が共有されている。日本は「開かれた地域協力」としての APEC を積極的に推進しているが、APEC は、自由化の成果を WTO 協定に従って域外にも均霑することとしている。11月の APEC フィリピン会合では、各メンバーが自由で開かれた貿易と投資の達成のための個別行動計画を提出し、本格的な自由化行動が開始された。今後は2010年/2020年までの自由で開かれた貿易・投資の達成という目標に向けて、着実に行動計画を実施・改善していく必要がある。
<長期的課題への取組>
また、世界経済の持続的発展を確保するためには、伝統的な経済・貿易分野にとどまらず、食糧、人口、エネルギー、環境などの地球規模の長期的課題や社会問題との接点となる新しい分野にも取り組んでいく必要がある。APEC において、日本は、アジア太平洋地域における人口増加と急速な経済成長が食糧、エネルギー、環境に与える影響を長期的課題として取り上げることを提案し、96年から具体的な検討作業が開始された。また、日本は、リヨン・サミットにおいて、社会保障の分野で各国が知見や経験を分かち合い、持続可能な社会保障制度を確立する「世界福祉構想」を提案し、各国の賛同を得て、そのフォローアップを着実に行っている。(「世界福祉構想」の詳細は第3節7.参照。)
<二国間経済関係の発展>
こうしたグローバルな枠組みや地域的な枠組みに加え、日米経済関係を始めとする二国間の経済関係にも引き続き取り組んでいくことが重要である。二国間の個別経済問題、紛争処理などについては、多国間の紛争解決をも視野に入れつつ、可能かつ望ましい場合には、まず二国間の協議を通じて解決していく必要がある。日米経済関係については、米国の対日貿易収支赤字が大幅に縮小するなか、基本的に極めて良好となっている。既に日米包括経済協議の下での優先交渉分野は決着済みであり、96年は半導体、保険分野で決着を見たが、今後とも残された個別経済問題の解決に努める必要がある(日米経済関係については、第1章2.(1)及び第3章2.を参照)。