| 1.概 観 |
冷戦の終結は、国際関係にも、また、日本の政治・経済にも大きな影響を与えたが、冷戦構造に代わる新たな国際秩序が現れているとは未だ言い難い。それでも、国際社会は、様々な経験を通じて、新たな時代の国際社会のあるべき姿について、徐々にイメージを形成しつつあるように見える。「冷戦後の世界は不透明で流動的である」と言われるが、それだけに一層、国際社会に現れつつある動きや特徴を的確に把握し、それに基づいて外交政策を策定していくことが重要である。
その際、留意すべきことは、日本にとって国際情勢は所与のものではなく、自らがその形成に深く関わっていると同時に、日本の行動が新たな国際秩序の構築にも大きな影響を与えているという事実である。10月の国連安全保障理事会非常任理事国選挙を始めとする96年のほとんどの国際機関などの多くの選挙において日本が圧倒的多数の支持を得て選出されたことは、新たな国際秩序の構築において日本が果たすべき役割に対する国際社会の期待の大きさを如実に物語っていると言えるであろう。
日本外交の目標が、究極的には、日本の安全と繁栄を確保し、国民の豊かで平和な生活を実現することにあることは言うまでもない。他方、後に触れるように国際社会の相互依存関係が深まっている今日、いかなる国も、世界全体の安定や繁栄と切り離して自国の安全や豊かさを追求することはもはや不可能となっている。今日、国内では、日本社会のシステムそのものが問われており、政府は六つの改革(行政、財政、社会保障、経済、金融システム、教育)に真剣に取り組んでいる。内政と外交がますます一体化している現在、日本としては、外交面でも、「自国及び世界の安全と繁栄の実現」という、当然ではあるが、達成することは極めて困難な目標に向かって努力していく必要がある。
この第一章概観部分では、こうした目標の達成に向けて日本が96年一年間にいかなる外交努力を行ってきたかを概観するが、それに先立ち、まず、現在の国際社会の特徴について簡単に考察してみたい。
[現在の国際情勢の基本認識]
現在の国際社会を概観した場合、その特徴としては、おおむね以下の6つが挙げられるであろう。
〈グローバリゼーションの進展と相互依存関係の深まり〉
第一の特徴としては、経済のグローバリゼーションの進展と国際社会の相互依存関係の深まりが挙げられる。
貿易・投資などを通じた市場の一体化や情報通信・運輸手段の飛躍的な発展によって、世界がますます狭くなるとともに、経済面、軍事・安全保障面を含む様々な分野において、多様な主体の間の相互依存が深まっている。世界全体の名目 GDP にしめる貿易総額の割合の急激な増大(70年は約18%、80年は約32%、95年は約40%)や、世界の市場間の連動が強まっている金融市場、並びにリアルタイムでの情報の伝播がその象徴ないし典型であり、今やいかなる分野においても、また、国家を含むいずれの主体にとっても、周囲の世界の出来事から超然として無関係でいることは難しい。
グローバリゼーションの進展と相互依存の深まりにより、人々はより良い製品をより安く手に入れることが可能となるし、また、世界中の出来事の多くを瞬時に知ることができるようになる。これらは一例であるが、グローバリゼーションと相互依存の深まりは、人々に多くの新しい「機会」を提供するものであり、このことは、「グローバリゼーション」が主題となった6月のリヨン・サミットにおける共通の認識であった。
他方、グローバリゼーションと相互依存の深まりは、基本的には好ましい動向であるとしても、それが競争の激化などを通じて国内政治上の新たな問題を惹起し、それが国際的な摩擦や対立につながり得ることにも注意が必要である。国際社会としては、相互依存の深まりを、摩擦や対立でなく、世界の安定と繁栄に結びつけるような規範と枠組みを構築していく必要がある。様々な形での国際交流を推進し、国際社会における各国民同士の相互理解、連帯、協力を図っていくこともまた、こうした必要に応える努力の一つの側面と言えるであろう。
〈統治原理としての自由・民主主義、市場経済原理の普遍化〉
第二の特徴としては、冷戦の終結、対立イデオロギーとしての共産主義の挫折により、自由・民主主義、市場経済原理といった理念・制度の体系が、統治機構を支える基本的原理としての普遍性を高め、その浸透力を強めているという傾向が挙げられる。
特に、計画経済システムが破綻した現在、国民の豊かな生活を実現するための経済原理は市場経済システム以外にはあり得ないことが明らかになり、中国やヴィエトナムなどの社会主義国においてすら、市場経済原理に基づく経済の発展が図られている。同時に、一般的には、市場経済システムが円滑に機能していくためには、個人の財産権や自由権の保障を含む制度的基盤(「法の支配」)が必要であり、歴史的にも、市場経済システムの発達と自由・民主主義の普及は密接に関連してきている。従って、自由・民主主義、市場経済の体系は、今後とも、その正統性・普遍性を高めていくと予想されるが、他方で、この体系の導入プロセスや制度化については国や地域ごとの多様性があることや、制度化の試みが上手くいかない場合に生じうる反動の危険性にも常に注意していく必要があろう。
〈国際政治構造の重層化と多角化〉
第三の特徴としては、国際政治構造の重層化と多角化が挙げられる。
冷戦構造は米ソを両極とする二極構造であったが、冷戦後の世界が米国中心の一極構造なのか、それとも米国、欧州、アジアなど複数の中心をもった多極構造の世界なのか、そしてそのような世界の中で国連を始めとする国際機関がいかなる役割を果たすのかなどについては議論は尽きない。また、かつて南と分類された開発途上国の内部においても多様化現象が見られ、「北」と「南」の分類が曖昧になりつつあるとともに、地域統合・地域主義の動きも顕著である。
現実の世界は単一の見方で整理するにはあまりに複雑多様であるが、現在の国際社会では、[1]国連、世界貿易機関(WTO)、G7、経済協力開発機構(OECD)などのグローバルな枠組み、[2]アジア太平洋経済協力(APEC)、ASEAN地域フォーラム(ARF)、欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)、欧州安保協力機関(OSCE)、北米自由貿易協定(NAFTA)などの地域的な枠組み、[3]アジア欧州会合(ASEM)や「新大西洋アジェンダ」などの地域間協力の枠組み、[4]日米関係など主要国間の二国間協力関係の枠組みが重層的・補完的に重なり合い、その中で、ある程度以上の力を持った主要国が協調しつつ指導力を発揮して秩序を構築・維持していくという体制ができつつある。4月のクリントン大統領訪日の際の日米安保体制の重要性の再確認や、97年の世界において最重要の外交課題の一つとなると予想される NATO 拡大問題の意義なども、そうした大きな流れの一環としてとらえられる必要があろう。
〈地球規模問題の重要性の高まり〉
第四の特徴として挙げられるのは、第一の特徴である国際社会のグローバリゼーションの進展や相互依存の深まりとも密接に関係するが、いわゆる地球規模問題への関心が質量ともに増大しているという事実である。6月のリヨン・サミットにおいては、従来からの経済問題、政治問題に加えて、地球規模問題がこれまで以上に幅広く議論され、議長声明では、「地球的規模の問題」という項目が立てられ、「重要な問題は、地球的レベルで取り扱われる必要がある。(中略)我々は、効率及び連帯の精神の下でこれらの地球的規模の問題のために、我々の間で、また、他のパートナーとともに、積極的に協力することにコミットしている。」と述べられた。
「地球規模問題」に関しては、必ずしも明確な定義が存在するわけではないが、地球温暖化などの地球環境問題、エイズを始め新たな種類の感染症、麻薬、国際犯罪、テロ、原子力安全、難民問題など、地球全体または広範な範囲にわたって影響を及ぼし、適切な対応のためには、国境を越えた国際協力が不可欠であることがその共通した性質である。狭くなった世界においては、そもそも地域問題と地球規模問題の区別を行うこと自体が難しくなっている側面も指摘できる。
地球規模問題の重要性が高まってきた理由としては、第1に、冷戦時代には、東西対立に関心が集中し、国際社会全体の課題として意識されにくかった問題にも関心が向けられるようになったこと、第2に、大量破壊兵器の拡散、地域紛争の深刻化とこれに伴う難民の大量発生など、冷戦構造の崩壊自体が原因となり深刻化している問題があること、第3に、エネルギー問題、環境問題などは、冷戦構造の崩壊と直接の因果関係はないとしても、経済活動の増大などを背景に、近年とみに深刻化が懸念されていること、第4に、先に述べた国際政治構造の変化の中、効果的な対応のためには全世界的な協力体制の構築がますます必要となってきていることなどが指摘できよう。
〈民族意識の高まり〉
第五の特徴としては、冷戦後の世界における民族意識の高まりを指摘することができよう。
東西対立の終結により、イデオロギー的な対立は国際社会を動かす主たる要因ではなくなったが、これに代わり、民族としての意識・一体感の影響力が国際社会で高まりつつあるように見える。冷戦終結後に頻発化する地域紛争が、主として民族的ないし宗教的な対立を背景とすることは広く指摘されている。また、民族主義が愛国主義に向かう場合がある一方で、多民族国家で国民を統合する明確な理念が欠如している場合などには、民族意識が国家を相対化し、解体する方向にすら作用し得ることは、旧ユーゴーや旧ソ連邦の例にも明らかである。冷戦構造の重しが消失するとともに、相互依存の深まりに起因して異なる民族間の接触が増大する中で、民族意識の高まりを巡る動きからは引き続き目が離せない。
〈「国家」の役割の相対化〉
以上、現在の国際社会を性格づける5つの特徴に言及したが、これらの特徴の反映として、「国家」あるいは「国家主権」という存在の持つ意味が変化し、相対化されつつある面も見逃せない。もちろん、現在においても、人々の生活の中で「国家」の存在は圧倒的に重要であり、国際関係においても主権国家間の関係が依然として国際関係の中心であることに変わりはない。他国、特に近隣諸国との関係をいかに処理していくかは、ほとんどの国にとって依然として最も重要な課題である。
その一方で、前述した通り、グローバリゼーションの進展や地球規模問題の重要性の高まり、さらには一部における民族意識の高揚などの結果として、「国家」の持つ意味や役割が、かつてのような絶対的かつ万能なものから相対的なものへと変化している場合もある。「国家」の持つ意味や役割の変化が最も先鋭的な形で見られるのはおそらく欧州であろうが、そこでは、市場統合を中核として統合が進み、今や単一通貨や共通外交安全保障政策までが具体的な政治課題として浮上している。統合が進んだ欧州において、それぞれの「国家」がいかなる機能・役割を果たすのかは、まさに、欧州統合を巡る議論の中心である。主権国家システム発祥の地であると同時に、主権国家間による幾多の悲惨な戦争を体験してきた欧州において、このような取組が進展してきていることは、21世紀の国際社会のあり方を考える上で示唆に富んでいる。他方で、一部アフリカ諸国のように、相対化以前の問題として、「国家」そのものの確立がままならない地域も存在することは、今日の「国家」を巡る状況を一層複雑なものとしている。
[96年の日本外交]
以上、現在の国際社会の特徴を六つの切り口から概観した。そこで次に、このような国際社会の中で日本がどのように外交を展開し、どのような役割を果たしていくべきなのか、これらの特徴が外交の展開に有する意味合いも考慮しながら考えてみたい。
|
(1) まず、冒頭で述べた通り、相互依存の深まる現在、日本自らの安全と繁栄は、世界全体の安定と繁栄と密接に結びついており、日本としては、世界全体の安定と繁栄に向けた国際社会の努力への協力を通じて、自らの安全と繁栄を確保していくことがますます必要となっている。地球規模問題の重要性が一層強く認識されつつあることも、こうした国際社会の一体化傾向の中でとらえるべきであり、その克服に向けた国際的な努力に協力することが、日本の利益にもつながることを明確に認識すべきである。この意味から、日本が政府開発援助(ODA)を通じて途上国が抱える様々な問題に対処していることは、回り回って日本国民の生活を支えていることに留意し、国民の理解と支持に裏打ちされた質の高い ODA を積極的に展開していくとともに、他の援助国に対しても開発援助に関する働きかけを行っていくことが重要である。 また、様々な主体が様々な関係を結ぶ中、いかにしてあり得べき摩擦や対立を適切に処理、回避し、協調的かつ安定したシステムを維持・構築していくかが問われている。国際経済分野でWTOを始め多角的で公正な枠組みの構築に向けて努力が続けられていることはその典型であり、日本としても、こうした国際社会の努力に主体的に参画していく必要がある。 (2) 次に、自由・民主主義、市場経済原理という理念・制度が世界全体で普遍性を増しつつあることについて指摘したところであるが、その背景には、これら理念や制度の追求と実践が、各国の国民の精神的及び物質的豊かさにつながるものであるという歴史的な経験がある。また、「民主主義国家同士は戦わない」との主張は近年ますます説得力をもって語られている。豊かで安定した民主主義国家が増えていくことは、国際社会の安定化に資するものであり、日本としても、こうした基本的価値観を外交理念に据え、これを共有する諸国と連携しつつ、その普遍化の流れを助長し、確実なものとしていくよう働きかけていく必要がある。 他方で、前述の通り、これら理念、制度の適用と実践は、各国・地域ごとに多様であり、また、その過程には長い時間を伴う。こうした働きかけを行うにあたっては、現実を見据えたアプローチをとると同時に、忍耐強く理想を見失わないことが重要である。さらに、歴史的に見ても、こうした理念や価値観がそれぞれの国で定着するためには、その国が経済的な基盤を整えることが不可欠である。この意味でも、途上国の開発の問題は極めて重要であり、日本として ODA などを通じた一層の協力を行っていく必要がある。 (3) さらに、日本の安全と繁栄の確保という外交目標を実現していくにあたり、日本としては、先に述べた国際政治構造の変化に対応し、アジア太平洋を中心とした重層的、多角的な枠組みの構築を図っていく必要がある。すなわち、[1]日本外交の基軸である日米関係を一層充実させつつ、中国、韓国等近隣諸国との友好協力関係の増進を図るなど、二国間の協力関係を引き続き外交の基盤としつつも、これと並行して、[2]日本の位置するアジア太平洋の地域協力の枠組みを補完的に活用することにより域内の信頼の向上と繁栄の維持に努めていくこと、[3]それと同時に、相互依存関係が深まる中、国際社会全体の課題の解決に協力し、自らにとり好ましい状況を地球レベルでも実現していくことである。 (4) こうした外交努力は、目的で見れば、(イ)平和と安定の確保、(ロ)繁栄の確保、(ハ)地球レベルでの市民の安らぎの確保の三つの柱に整理することができよう。橋本総理大臣は、9月、第51回国連総会の一般討論の際に行った演説において、「未来のためのよりよい世界の創造」のための外交政策の柱としてこの三つを挙げ、日本として、これらいずれにおいても十分な役割を果たすことが必要であると説いた。この三つの柱はそれぞれが密接に関連しており、いずれの柱を欠いても他の柱の目標の追求が困難となり、また、個々の外交課題が全ての目的に関連している場合も多い。そのため、一つ一つの課題に対応するにあたり、この三つの目的を総合的に考慮に入れた包括的な施策をとる必要性が強く認識されつつある。 (5) 以上の三つの枠組みと三つの目的を、日本が関係する典型的な事例を中心に整理すると、次の表となるであろう。(この表は網羅的なものではなく、かつ既に述べた通り、三つの目的は密接に関連し、個々の政策事項の目的をいかに分類するかは特定が困難であるため、かなり便宜的なものとなっているが、一つの目安として参考にはなると思われる。) |
以下では、この整理に沿って、96年一年間に日本がどのような外交を展開してきたかを回顧したい。
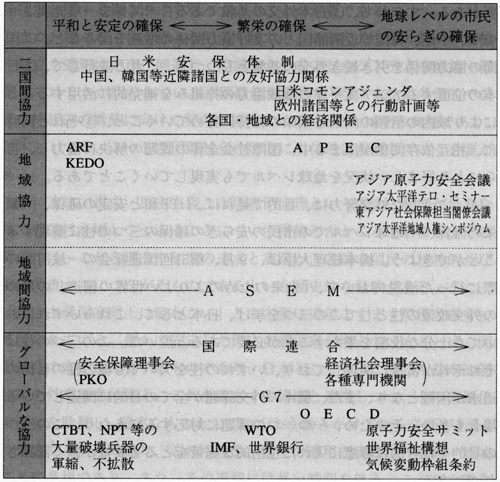
〈主要二国間関係の強化〉
日本にとってより好ましい周辺環境を実現する上で、米国との関係を始め、主要先進諸国並びに近隣アジア諸国との二国間関係の強化は何よりの基本となる。
[日米関係]
|
太平洋をはさんで向かい合い、自由・民主主義・市場経済原理といった価値観・制度を共有するとともに、現在においても圧倒的な国力を誇る米国との関係は、日本外交の基軸である。日米両国は、政治・安全保障面で堅い絆で結ばれ、経済面で強い相互依存関係にあるとともに、最近では、「コモン・アジェンダ」と題し地球規模の問題への協力を打ち進めている。 96年は、こうした関係の充実に向けて顕著な動きが見られた年であった。特に、4月のクリントン大統領の訪日は、日米両国の協力関係が、両国のみならずアジア太平洋さらには世界の安定と平和にとり極めて重要な関係であることを改めて確認するとともに、今後の両国の関係強化に向けての様々な方向性や計画を打ち出す意義深いものとなった。この訪問の際に日米両国首脳により今後の日米関係を規定する二つの文書が発出された。「橋本総理大臣とクリントン大統領から日米両国民へのメッセージ」は、日米両国がより良い世界を構築するために協力していく決意を明らかにしたものである。また、「日米安全保障共同宣言」は、日米安保体制が日本の安全さらにはアジア太平洋の安定と平和に重要な役割を果たしていることを改めて確認するとともに、将来に向けた両国の安全保障分野の協力の出発点となるものであった。この共同宣言において、両国の緊密な防衛協力関係をさらに増進させる目的で、78年に策定された現行の「日米防衛協力のための指針」の見直しを開始することが表明されたが、この作業は97年秋までに終了することを目途に進められている。 これに関連し、国内における努力の一環として、「指針」見直し作業と連携しつつ、日本に対する危機が発生した場合やそのおそれがある場合にとるべき対応につき、起こりうる種々のケースを想定し、政府として必要な対応策を予め具体的に十分検討、研究する作業が進められている。具体的には、(イ)在外邦人等の保護、(ロ)大量避難民対策、(ハ)沿岸・重要施設の警備等、(ニ)対米協力措置等につき、関係省庁が協力して検討を行っている。 また、沖縄に所在する米軍の施設・区域を巡る諸問題については、政府として、沖縄県民が負ってきた負担は本来国民が等しく負うべきものとの基本的姿勢に立ち、最重要課題の一つとして取り組んでいる。沖縄に関する特別行動委員会(SACO)の中間報告が4月に、そして12月には、普天間飛行場の全面返還を始めとする米軍施設・区域の返還などの具体的計画・措置をとりまとめた最終報告が発表され、一つの区切りがつけられたが、この報告の着実な実施を含め、引き続き真剣に取り組んでいく必要がある。 経済面では、日米包括経済協議が二国間の経済関係の運営に大きな役割を果たしており、既に協議の各分野の決着内容を日米双方で確実に実施する段階に入っている。96年は、米国の国内経済が好調で、かつ対日貿易収支赤字が大幅に減少したことなどから経済関係は基本的に良好であり、また、個別問題についても、半導体、保険分野で決着が図られた。 さらに、麻薬、人口、エイズ、子供の健康などの地球規模の課題への取組としては、日米両国の官民が共同で取り組む「日米コモン・アジェンダ」が、世界で最も成功している二国間協力の形態として、両国関係の幅を拡大・強化する一つの基盤となっている。
|
[日中関係]
|
96年、中国との関係は、台湾「総統」選挙を巡る台湾海峡情勢の一時的緊張、中国の核実験に対する日本の抗議、尖閣諸島を巡る事態、日本における歴史認識への中国側の懸念、日米安全保障体制の再確認に対する中国側の「疑念」表明などを巡り、困難な局面に立つことが多かった。しかしながら、両国政府には、日中関係が両国のみならずアジア太平洋全体にとり有する重要性を踏まえ、両国関係を引き続き発展させていく必要があることについて共通の認識があり、11月の APEC の際に行われた首脳会談においても、こうした認識に立って日中関係を発展させていくべきであることが確認された。 97年は、7月の香港返還や秋の党大会という内政面で重要な行事が予定されている。中国が今後とも現在の改革・開放路線を維持し、国際社会に建設的な役割を果たしていくことは、日本にとっても極めて重要であり、中国の建設的な姿勢を奨励していく必要がある。さらに、アジア太平洋の平和と安定にとって、日米中三国の安定的な関係が極めて重要であり、こうした観点から、日本としても、96年後半から見られる米中関係の進展に向けた動きを歓迎している。 |
[朝鮮半島]
| 朝鮮半島に関しては、日本は、韓国との友好協力関係を基本とし、この地域の平和と安定に向けて努力している。食糧・エネルギー事情の悪化などが伝えられる北朝鮮の情勢は今後とも注視していくことが必要である。日本は、米国及び韓国との連携の下、北朝鮮の核兵器開発問題の解決にとり重要な枠組みである朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)の活動に積極的に取り組んでいるほか、朝鮮半島の平和と安定の実現のためには南北当事者間の対話が重要との観点から、4月に米韓両国により示された「四者会合」提案を一貫して支持している。韓国との間では、3月(ASEMに際し)、6月(韓国済州島)、11月(APECに際し)の首脳会談を通じて両国間の友好協力関係を一層発展させていくことが確認された。また、二国間関係及び朝鮮半島情勢に加えて、日韓両国が97年ともに安保理非常任理事国を務めること、また96年に韓国が OECD に加盟したことなどを踏まえ、国際社会における両国の協力も進めていくことが重要であることについても認識の一致を見た。 |
〈アジア太平洋を巡る地域協力〉
アジア太平洋地域では、東アジアを中心に、ダイナミックな経済発展が見られ、それが域内全体の相互依存関係を深めるとともに全般的な政治的安定をもたらしている。また、この地域における開発途上国の発展は、「豊かな北と貧しい南」という従来からの図式を打破する活力に満ちたものであり、歴史的な意義を持っている。このような好ましい動向を更に確実なものとし、潜在的な不安定要因に対処するために、最近進展している地域協力の動きを一層推進していくことが重要である。
[ARF]
| 平和と安定の確保の分野では、ASEAN地域フォーラム(ARF)がこの地域の信頼関係の向上のために重要な役割を果たしており、7月の第3回閣僚会合では、率直かつ活発な意見交換を通じ、具体的な協力措置の実施につき意見の一致が見られた。日本は、種々の具体的協力措置の実施を通じて ARF の活動が定着、発展するよう、信頼醸成に関する政府間会合を1月及び4月にインドネシアと共催するなど、様々な協力を行った。 |
[APEC]
| 経済的な繁栄の維持・確保の分野では、11月の APEC フィリピン会合において、日本を含め各メンバーが自由で開かれた貿易と投資の達成のための個別行動計画を提出し、 APEC の自由化プロセスが本格的な行動の段階に入った。今後は、97年のカナダ会合に向けて、各メンバーが計画を着実に実施するとともに、その更なる改善を図ることとなっており、日本としても、このプロセスに積極的に取り組んでいく必要がある。また、太平洋の海洋環境の保全及びインフラ整備を含む経済・技術協力分野の強化や、民間部門との連携強化などの課題への対応も重要である。 |
[ASEM]
| さらに、アジア太平洋という地域を超えた対話も進展している。3月には、アジア、米国、欧州の三者関係の中で相対的に希薄であったアジアと欧州両地域の関係強化のため、両地域から26の首脳が集まり、バンコクで初のアジア欧州会合(ASEM)が開催された。ASEM の開催は、経済発展を背景とした東アジアの国際的地位の向上を象徴的に示す出来事であり、会合では、両地域間の対話と協力を通じて相互理解と相互利益を増進させるとともに、新たな国際秩序の構築に向けて両地域が協力していくという姿勢が確認された。日本も、様々な具体的フォローアップ活動を提案するなどして、ASEM の成功に貢献したが、アジアと欧州の相互理解と協力が深まることは、先進民主主義国であり、かつ、アジアの一員である日本にとっての利益であると同時に、日本が目指す冷戦後の新しい国際秩序の構築の観点からも重要であり、今後とも建設的な役割を果たしていく必要がある。 |
[中南米諸国との協力]
| 東アジアに次ぐ世界の成長センターとなっている中南米地域は、アジア太平洋地域の発展にとって、また、地球規模問題の解決においても重要な役割を果たすことが期待されており、8月の橋本総理大臣の中南米5か国歴訪も、このような認識の下に実施された。96年末に発生した在ペルー日本国大使公邸占拠事件は極めて遺憾な事件であるが、日本としては、今後とも中南米諸国の長期的な安定と発展を重視し、これら諸国が抱えている諸問題の解決に向けて支援を強化していくこととしている。 |
〈グローバルな取組〉
主要な二国間関係を堅固なものとしつつ、アジア太平洋を巡る地域協力を推進すると同時に、近年重要性を増している「地球規模問題」への対応を含め、国際社会の共通の課題の克服に向けて積極的に協力していくことが重要である。以下では、まず国連を巡る動きに言及し、三つの目的ごとに、国際社会の動きを踏まえつつ、日本がとってきたイニシアティヴを回顧したい。
[国 連]
|
96年、日本は国連加盟40周年を迎えた。日本は、加盟以来一貫して、国連重視を外交の基本方針の一つに据え、その活動全般に貢献してきた。 10月21日に行われた安全保障理事会非常任理事国選挙では、日本は有効投票数180票のうち142票(当選に必要な投票数は120票)を獲得し、当選を果たしたが、このように日本への圧倒的支持が示された背景には、国連の財政面並びに平和維持活動、軍縮・不拡散、開発など、幅広い分野において日本が行ってきた活動に対する国際社会の評価と、今後の日本の役割に対する期待がある。日本としては、この期待に応えるためにも、安全保障理事会非常任理事国として、国連の機能強化や地域紛争の解決などに向けて、これまで以上に積極的な役割を果たしていく必要がある。安全保障理事会の改革については、日本としては、国連の作業部会における議論に積極的に参加しつつ、自らの常任理事国入りについては、憲法の禁ずる武力の行使は行わないとの基本的な考えの下で、多くの国々の賛同と国民の理解を得て、安保理常任理事国として責任を果たす用意があるという立場を表明してきている。 |
[平和と安定の確保]
|
-軍備管理・軍縮、不拡散- 大量破壊兵器の軍縮・不拡散の問題は、現在の国際社会が直面する最重要の課題の一つであるが、96年の特筆すべき動きとして、9月の国連総会において、包括的核実験禁止条約(CTBT)が国際社会の圧倒的支持を得て成立したことが挙げられる。日本は、核兵器のない世界を実現するためには現実的な核軍縮措置を着実に実施することが重要であるとの認識の下、国際社会が核軍縮に真剣に取り組むよう訴えてきた。CTBT の採択にあたっても、軍縮会議における交渉の過程から国連総会における採択に至るまで、交渉の取りまとめや条約への支持の各国への働きかけ、国連総会への共同提案国となるなど、積極的な働きを行った。また、通常兵器の軍縮の分野でも、例えば、効果的な対人地雷の全面禁止に向けて関係国と努力しつつ、その除去や犠牲者のリハビリなどに関する国際会議の開催についてもイニシアティヴを発揮した。
-地域紛争- |
[世界全体の繁栄の確保-開発の推進と国際経済分野における協力-]
|
-開発問題- 冷戦の終了直後には、それまで東西対立に費やされていた様々な資源が「平和の配当」として解放され、途上国の開発などの目的に使用できるのではないかという期待が国際社会の一部に存在した。しかし、現実には、依然として多くの途上国が貧困や低開発に起因する諸問題に苦しんでいる中、先進国側には「援助疲れ」といわれる現象も見られ、途上国の健全な開発を如何に確保していくかは国際社会にとって一層切実な課題となっている。 日本の歴史的、政治的、経済的な諸事情を勘案した場合、日本の経済力、技術力を活かした政府開発援助(ODA)は、日本が成し得る貢献の最も重要な柱である。戦後の日本の経済発展は、日本自身の努力のみならず、米国を始めとする国際社会からの政治、経済面の力強い支援があったからこそ実現したものである。今や自他共に認める世界の主要国となった日本の責務は、積極的なリーダーシップと責任ある行動を通じ、国際社会を支える側に回ることであり、また、こうした行動を通じてこそ、日本の考えを理解し支持してくれる「友人」を増やしていくことが可能となる。日本として引き続き、ODA の一層効率的・効果的な実施を図っていく必要があり、こうした努力の積み重ねを通じて国際社会の平和と安定の維持・確保に貢献していくことは、貿易などを通じ途上国を含む国際社会に大きく依存する日本自身の利益にも資するものである。また、ODA は、極度の貧困に喘いでいる途上国にとって極めて重要であるのみならず、発展目覚ましい一部の開発途上国が、貧富の格差の拡大、成長から取り残された人々の教育や医療の問題、工業化に伴う環境問題などに対処する上でも重要な役割を果たしている。 このような状況の下、新しい時代における開発のあり方を示す「新開発戦略」が5月に OECD 開発援助委員会(DAC)で採択され、リヨン・サミットにおいても歓迎されたが、日本はこの「新開発戦略」の策定に主導的な役割を果たした。「新開発戦略」は、開発における途上国の主体性を重視し、その上で先進国と途上国がパートナーとして協力することを中心的な理念としつつ、2015年までの貧困人口の割合の半減、乳幼児死亡率の低下、初等教育の普及、環境保全国家戦略の策定などの成果重視型の目標を掲げており、今後その実現に向けて途上国と先進国が共に努力することが重要である。 また、アジアや中南米の開発途上国の一部が目覚ましい経済発展を遂げている中、アフリカの開発の問題が緊急かつ重要な問題となっている。日本としてもこれを重視しており、4月末から5月にかけて南アフリカ共和国で開催された国連貿易開発会議(UNCTAD)総会において、池田大臣より、「対アフリカ支援イニシアティヴ」を発表し、93年に日本が、国連及び「アフリカのためのグローバル連合(Global Coalition of Africa)」とともに東京で開催した「アフリカ開発会議(TICAD)」によって生み出されたモメンタムを維持するために、「第2回アフリカ開発会議(TICAD II)」を98年を目途に、その準備会合を97年に本邦で開催する予定である旨を表明した。
-国際経済- |
[地球レベルでの市民の安らぎの確保]
|
96年は、この分野の取組として特に、テロ対策と原子力安全についての関心が高まった。 テロについては、頻発するテロ事件を受け、3月の平和創設者のためのサミット、6月のリヨン・サミット、7月のG7及びロシアによるテロ閣僚会合など多くのハイレベルの国際会議を通じ、テロ対策に関する国際協力を一層強化させていくことが改めて確認された。テロの再発を防止するためには、国際社会が一致団結して毅然たる態度を示すことが不可欠である。また同時に、貧困、麻薬などテロを生む背景要因の克服に向けて、それぞれの国々並びに具体的な国際協力措置の実施を通じて努力することが重要である。日本としても、12月にアジア太平洋地域のテロ対策の専門家を招いてセミナーを開催するなど、テロ問題に大きな関心を寄せているが、こうした国際的な取組に主導的に参画することは、ひいては日本自らの安全につながることを認識すべきである。なお、12月に発生した在ペルー日本国大使公邸占拠事件については、次項で特別に言及することとしたい。 原子力安全については、4月にモスクワ・サミットが開催され、旧ソ連・東欧地域などにおける民生原子炉の安全性の向上、核物質や放射性廃棄物の安全な管理などの課題に関する国際的な協力の重要性が確認された。このサミットの理念を原子力発電の導入に活発な動きが見られるアジア地域で確認し、具体的な行動に移すことを目的として、日本は、11月にアジア原子力安全東京会議を開催した。 さらに、この分野での特筆すべき事項として、橋本総理大臣がリヨン・サミットにおいて提唱した「世界福祉構想」が挙げられる。社会保障の問題は、世界各国の政府にとって重大な関心事項となっており、社会保障分野における日本の経験を途上国と共有し、これら途上国がより効率的な事業の推進を図ることが出来るようにすること、及び、先進諸国が共通して直面している課題について、相互の経験や知恵を分かち合うことを目的とした橋本総理大臣の構想は、時宜を得たものとして各国首脳の支持を受けた。日本は、その具体化の一環として、12月に沖縄において、東アジア社会保障担当閣僚会議を開催したが、この構想は、97年のデンバー・サミットなどを通じ、さらに推進されることになっている。 以上、テロ、原子力安全、福祉について、96年における動向を述べたが、97年は、地球規模問題の典型ともいうべき地球環境の分野において、6月に国連特別総会が、12月に気候変動枠組条約第3回締約国会合(於:京都市)が予定されるなど、環境分野での重要な国際会議が目白押しであることから、「環境の年」とも言われており、日本の果たすべき役割も大きい。 96年、日本は以上にみたように様々な外交イニシアティヴをとってきた。各国が日本に抱く期待は高まる一方であり、日本がこれに応えた活動をしているか否か、国際社会が日本を見る目はこれまで以上に厳しくなっている。日本としては、今後とも新たな国際秩序の担い手という明確な自覚の下に、一層積極的なイニシアティヴを発揮していかなければならない。 |
[在ペルー日本国大使公邸占拠事件]
概論を終えるにあたり、96年末に発生した在ペルー日本国大使公邸占拠事件に言及することとしたい。
日本政府は、12月18日(日本時間、以下同様)にこの事件が発生して以来一貫して、テロに屈することなく、また、人命尊重を最優先とし、平和的解決に向けたペルー政府の取組を信頼しつつ、一刻も早い本件の平和的解決及び人質の全面解放に向けて全力を傾注するとの基本的立場をとってきている。こうした立場は、ペルーのフジモリ政権さらには国際社会全体の考え方と軌を一にするものである。
外務省では、事件発生直後に緊急対策本部を設置し、現地(リマ)対策本部との連絡にあたり、24時間体制で情勢把握や関連情報の収集・分析にあたってきた。また、事件発生当日に総理官邸に設置された対策室とも緊密に連絡をとっている。事件発生の翌日には、内閣総理大臣を本部長とする対策本部が設置され、必要に応じ会合が開催されている。さらに、人質となっている方々の企業、家族その他関係者等との緊密な連絡にも努めている。事件発生翌日には、池田外務大臣が現地(リマ)に発ち、現地対策本部の体制立ち上げ、日本の基本的考え方のペルー側への伝達、主要関係外交団との意見調整、在留邦人・日系人との面談などの所期の目的を達成し、23日夜に帰国した。
この事件に関連した国際的な動きとしては、まず国連安保理議長の記者声明(12月19日)が、その後、G7にロシアを加えた8か国による議長声明(12月27日)が発出された。97年1月上旬の橋本総理大臣の ASEAN 諸国訪問の際には、各国首脳より、ペルー政府の対応振りや日本の立場の全面支持が表明されたほか、日・ASEAN 間でテロに対処し国民生活の安全を守るための情報・意見交換のネットワークを構築していくことにつき賛同が示された。さらに、97年2月15日の ASEM 外相会合では、犯人(MRTA)側を強く非難する議長声明が採択された。
その後もペルー政府との間では、現地対策本部を通じフジモリ大統領及びペルー政府側交渉役のパレルモ教育相などと情報交換を行っている。橋本総理大臣とフジモリ大統領との間でも、2月1日にトロントで首脳会談を行ったほか、電話連絡を通じ、緊密な連絡・情報交換に努めている。また、保証人委員会のオブザーバーとなった寺田現地対策本部顧問(駐メキシコ大使)が、保証人メンバーとともに、ペルー政府と犯人側との間の予備的対話の促進を側面から支援している。さらに、3月17日から23日まで、高村外務政務次官がペルー、キューバ及びドミニカ共和国を訪問し、ペルーにおいてはフジモリ大統領に対し対話の加速を要請し理解を得たほか、キューバ及びドミニカ共和国においては、MRTA メンバーの受け入れにつき、両国首脳より内諾を取り付けた。
トロント首脳会談を受けて実施されることとなったこの予備的対話は、97年2月11日以降3月末まで10回にわたり開催されており、ペルー政府等による平和的解決に向けた努力が続けられている。
テロ対策は、冷戦後の国際社会にとっての大きな課題である。今回の事件は、国際社会がテロに対する断固たる姿勢を貫く一つの試金石となっている。97年3月末現在、ペルーでの事件が未だに解決していないことは極めて遺憾であるが、政府としてペルー政府の努力を支援し、この問題の平和的解決に向けて、引き続き全力を傾けていく方針である。
追記:その後、日本時間4月23日早朝、ペルー軍特殊部隊が救出作戦を実行し、この結果、人質1名及び軍関係社2名が犠牲となったが、日本人人質全員を含む71名の人質が救出された。