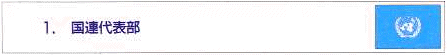
VII.国際機関等
(1)総論
94年は、国連が平和維持機能のみならず、開発問題、難民支援等経済社会分野においても重要な役割を果たすことを期待されると同時に、財政難等の制約要因が依然深刻な状況下で、国連改革に向けての厳しい議論が進展した年であった。
経済社会分野では事務総長が11月に「開発のための課題」に関する勧告を発表し、今後開発分野において国連が果たすべき役割及び他の開発機関との調整、更には経済・社会理事会の機能強化等幅広い提言を行った。世界的にODAの額が減少している中で、国連が冷戦後の開発問題に新たな観点から光を当てた点は大きな意義があった。また、難民問題に対し、国連が積極的に人道的支援を展開した実績は高く評価される。
政治分野では、安保理改組へ向けての各国の関心には引き続き高いものがある。また、国連PKOの設立・展開及び今後の在り方につき包括的見直しが行われた。
日本との関係では、6月に天皇皇后両陛下が国連を御訪問され、第49回国連総会には河野副総理兼外務大臣が出席した。また、7月にインサナリ総会議長が、9月にブトロス=ガーリ務総長がそれぞれ来日した。また、核兵器の究極的廃絶決議、南南協力、ミャンマーの人権に関する決議等における外交努力や国連PKOあるいは人道的な救援活動への参加実績は、国連における日本の評価と期待を高めることに貢献した。
なお、総会において「旧敵国条項」削除についての検討を求める決議が通過し、同問題が具体的一歩を踏み出したことは日本の年来の懸案解決に向けての大きな前進として評価できる。
(2)安全保障理事会の動き
主要地域問題としては、北朝鮮の核開発問題をめぐる米朝枠組み合意への対応(11月)、ハイティ問題に関する多国籍軍の承認(7月)、エルサルヴァドルや南アフリカにおける選挙監視の実施など国際の平和と安全の確保に向け一連の措置が打ち出された。旧ユーゴー情勢については、国連保護隊(UNPROFOR)の駐留を維持するなど、紛争の政治的解決のため側面支援を行っている。
PKOについては、ソマリアなど必ずしも効果的ではなかった例や国連の財政難に照らし、増強や新規設立については慎重な対応が大勢を占め、94年中に新設されたPKOは2件に留まった。また、日本の自衛隊も参加した国連モザンビーク活動(ONUMOZ)は12月成功裡にその任務を終了、第2次国連ソマリア活動(UNOSOM
II)についても95年3月末までに撤退を完了する決定が11月になされた。
安保理の透明性強化、手続改善については、3月、暫定決議案文を全加盟国に入手可能にする決定が、10月、理事会議長による全加盟国へのブリーフの実施の決定が、11月、安保理と要員提供国と事務局との協議を行うとの決定がなされ、安保理としても独自の改善努力を行った。
(3)安保理改革問題
93年12月の総会決議により、すべての加盟国に開かれた作業部会が設置され、安保理議席数の拡大にとどまらず、安保理審議の透明性の増大、作業手続の改善等も論議されたが、9月のインサナリ総会議長によるサマリーでは、安保理議席数の拡大及び継続・審議につき合意に達した。今次総会一般演説では、134か国が何らかの形で安保理改組問題に言及するなど、この問題に対する各国の関心は引き続き高いことがうかがわれる。95年1月より再開される安保理改組作業部会においては、過去10か月の作業部会の成果をふまえ、審議をいかに加速させていくかが問題である。
(4)平和維持活動(PKO)
PKO特別委員会において、PKOに関する包括的な見直しが行われ、安保理理事国と要員派遣国との協議メカニズムの強化、PKOの指揮統制の強化、財政基盤での強化、広報機能の充実、訓練の充実などを事務局に勧告した。
また、第6委員会で国連要員等の安全に関する条約が採択されたことは、国連及び関連要員の安全強化に資するものとして評価される。
(5)経済分野
既に述べたとおり開発のための課題については、事務総長より幅広い提言が行われたが、今後具体的かつ現実的な勧告を行っていくかが重要な課題となる。南南協力については、日本がG77諸国と共同で決議案を提出し採択された。さらに日本は「国際防災の10年」に関する国連会議を主催(5月、横浜)するなど、この分野で積極的イニシアティヴを発揮し、評価を受けた。9月に開催された国際人口・開発会議(カイロ)にも積極的に参加し、行動計画の作成に尽力した。
(6)社会、人道・人権分野
社会問題分野では、95年に開催される社会開発サミット、及び第4回世界女性会議に向けて準備が着実に進んでおり、現実的かつ実行可能な内容になるよう、日本も積極的に貢献していくことが必要である。
人権分野については、市民的・政治的権利を重視する欧米諸国及び日本と、発展の権利に見られるように、経済的権利の重要性を主張する開発途上国諸国との間に依然大きな意見の隔たりがある。また、ミャンマーの人権問題については、日本が決議案の作成にあたりアジア諸国と欧米諸国との「橋渡し」的役割を果たした。
(7)行財政
行財政分野では、PKOの効果的な実施や加盟国による分担金の滞納などにより困難な状況にある国連財政の基盤の強化が急務となっている。
財政困難への対応については、12月、国連財政問題全般につきハイ・レベルで検討するための作業部会の設置、また、11月、加盟国の分担金負担の在り方につき技術的側面から専門家により検討するための作業部会の設置が各々決定され、95年初より具体的な検討が開始されることになっている。
(8)人的貢献
94年には、明石康旧ユーゴー問題事務総長特別代表兼UNPROFOR代表、緒方貞子国連難民高等弁務官、高須財務官がそれぞれ各分野で活躍するなど、国連のハイレベルでの日本人の貢献が目立った。しかし国連における邦人職員は日本の国連拠出額に比し依然として過少な状況にあり、引き続き邦人職員数増大の努力が必要である。