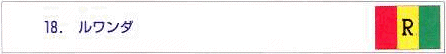
VI.アフリカ
ルワンダでは、73年以来ハビヤリマナ大統領(フツ族)による長期政権が続いていたが90年10月、少数部族であるツチ族の反政府勢力、ルワンダ愛国戦線(RPF)との間に内戦が勃発した。93年8月アルーシャ和平協定が成立しようやく内戦は終結するかに見えた。しかしながら、同協定に基づく和平プロセスの重要な第一歩である新暫定政府及び新議会の発足は困難を極め、94年4月には大統領の搭乗した特別機が撃墜される事件が発生した。その直後より、政府軍の一部、大統領親衛隊及び民兵などのフツ族過激派により、ツチ族及びフツ族穏健派に対する計画的かつ組織的な虐殺が始まり、3か月間に約50-100万人に及ぶ大量殺戮が発生した。これに対し、RPFは、ツチ族及びフツ族穏健派の防衛のため再び戦闘を開始し、7月には仏の設置した人道安全地帯である南西部を除き国土を完全に制圧し、新政権を樹立した。同政権には、多数部族のフツ族が大統領、首相のポストを占める一方、RPFが主要ポストを占め、特にRPFのカガメ司令官が副大統領兼国防相のポストにつき実権をにぎっていると言われる。
RPFの勝利により、旧政府・軍勢力はザイール等の周辺諸国内に敗走することとなり、また、約200万人の難民がザイール、タンザニア、ブルンディ領内に大規模に発生することとなった。特にザイールのゴマではコレラ等により多数の死者が発生し、これに対し国際機関、多数の国際NGOとともに、仏、米、イスラエル、スウェーデンなども軍隊・部隊を派遣し難民救援活動を展開した。日本も、ルワンダ難民問題には国際社会が抱える最大級の人道上の問題であるとの認識に立ち、国際機関や現地で活動するNGOに対しての資金協力(総額約6,600万ドル)、物資協力(約1億9,000万円相当)に続き、「国際平和協力法」に基づき、94年9月から12月までの3か月間、約400名の自衛隊部隊等をゴマ等に派遣し、ルワンダ難民支援のため、医療、防疫、給水、空輸等の救援活動を実施した。かかる国際社会の努力により、難民の状況は当初の危機的状況を脱することができた。一方、難民のルワンダ国内への帰還については、ルワンダ国内の受入れ体制作りや帰還者の安全の保障等の問題があり、現在まで殆ど進展が見られていない。経済については、86年以降世銀・IMFの支援を得て構造調整計画を実施し、経済再建に努力してきたが、内戦の長期化によりルワンダ経済は壊滅的打撃を受けた。こうした状況において、難民帰還、ルワンダ国内の政治的・部族的和解、地域の平和と安定、ルワンダ国内の経済・社会面での復興に包括的に取り組むことが国際社会の喫緊の課題となっている(第1分冊P5~8参照)。