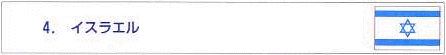
V.中近東
(1)内政
ラビン首相は、前年に引き続き中東和平交渉の推進に最優先に取り組
み、パレスチナとの和平の功績に対してノーベル平和賞を受賞するなど
国際的に高い評価を受けた。一方、国内的には、93年9月に宗教政党シャ
スが連立から離脱して以来、ラビン連立政権はアラブ系政党の閣外協力
を得てかろうじて議会の過半数を確保している状態が続いている。また、
国民の多くは中東和平の進展を好意的に受け止めているものの、ハマス
等によるテロ事件が頻発していることから、和平プロセスの先行きに不
安を感じている。このため、ラビン政権に対する支持率は低迷している。
次回総選挙は96年10月に予定されているが、現状では与党は苦戦が予想
されており、また、総選挙と同時に初めて行われる国民による首相直接
選挙についても、最大野党リクードの党首ネタニヤフが人気を盛り返し
ている。
経済面では、93年に引き続き国内開発、特に、経済・社会インフラの
建設を重視するとともに、経済の自由化・国際化に向けての諸政策を着
実に実施した。国内総生産(GDP)は、設備投資や個人消費の著しい伸
びとハイテク製品等の輸出拡大に支えられて、93年の2倍近くの6.7%の高い成長が見込まれている。失業率も93年の2桁台から7.7%に低下
すると見込まれている。消費者物価上昇率は、約15%と見込まれており、
インフレ対策が今後の課題となっている。
(2)対外関係
パレスチナは5月に、パレスチナ解放機構(PLO)との間でイスラエ
ル軍撤退とパレスチナ機関(PA)への権限委譲を定めるガザ・ジェリ
コ合意、8月にはジョルダン川西岸地域における早期自治権限委譲に関
する交渉が妥結し、教育、社会福祉、厚生、観光、直接税の五分野の自
治権がパレスチナ側に委譲された。また、ジョルダンとの間では、7月
にワシントンで交戦状態の終結宣言が行われたのに引き続き、10月には
平和条約が締結されて、11月には外交関係が樹立された。ジョルダンは
エジプトに次いでアラブ諸国の中でイスラエルとの平和条約を結んだ第
二番目の国となった。シリアとの関係では、米国を仲介とする和平交渉
が継続されている。9月にはモロッコと、10月にはテュニジアとの間で
それぞれ利益代表部及び連絡事務所の相互開設に合意した。米国との緊
密な関係は引き続き維持されている。11月の米国中間選挙の結果、民主
党は大敗したが、同選挙直後に訪米したラビン首相は、95年度も米国の
対イスラエル援助は現状レベルで維持するとの約束を取り付けている。
日本との関係は、政治、経済、文化等の各分野で順調に進展し、5月
に柿澤外務大臣がイスラエルを公式訪問したのに加え、12月にはラビン
首相が公賓として訪日し、村山総理大臣と両国関係史上初めて首脳会談
が持たれた。また、科学技術協力協定、文化教育取極が署名された。
(3)パレスチナ自治
ガザ・ジェリコ合意に従い、パレスチナ機関(PA)が設置され自治 が開始されたが、課題は多い。まず、PAによる自治は資金的裏付けがなく、事実上諸外国の財政支援に頼る運営状態が続いている。また、全 権限を一手に掌握するアラファト議長に対し和平支持派のPLO各派が らも民主化を求める批判が相次いでいる。さらに、和平に反対するパレスチナ各派、特にイスラム原理主義組織のハマスなどによる対イスラエル・テロや、過激派ユダヤ人入植者による暴力行為など治安情勢が悪化している。これに対し、PAは、テロ非難の立場をとりつつも、有効な具体的措置をとれていない。日本政府は、従来から国際機関を通じパレスチナ支援を行ってきたが、パレスチナ暫定自治合意以降、パレスチナ支援のため2年間に2億ドルをめどとする援助を約束し、94年末までに約1億ドルの援助を実施した。