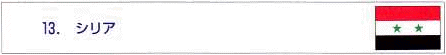
V.中近東
内政は、アサド大統領(95年3月より大統領任期第4期目の4年目)
の強力な指導の下、バアス党・軍を中心とした強固な支持基盤により安
定を保っており、原理主義の脅威も顕在化していない。しかし、一方で
大統領は、中東和平の実現をにらんで、国内の戦時体制を平和体制へ移
行させていく必要に迫られており、細心の舵取りが求められている。なお、
94年1月の大統領長男バーセルの事故死によりアサド大統領の後継者問
題に関心が集まった。経済面では、社会主義的体制から市場経済への段
階的移行が継続している。民営化に対しては慎重な政策が取られている
が、民間セクターは、91年5月の新投資法導入以来、引き続き伸長しており、国内外からの投資額は40億ドル近くに達した(プロジェクト件数
1,000件以上)。経済指標については、石油生産の頭打ち(60万バレル/
日弱)、石油価格の低迷等により、94年は成長が低くなる見通しであり、また、経済自由化に伴い国際収支も悪化しつつある。一方、電力事情は
改善されつつあり、インフラ整備も進んでいる。
対外関係では、中東和平交渉が最優先課題である。シリアは、ゴラン
高原からのイスラエルの完全撤退を実現するとの断固たる立場であり、撤退よりも両国間の国交正常化に関心があるイスラエルとの間で交渉を行っている。94年1月ジュネーヴにおいてクリントン米大統領と会談したアサド大統領が域内のすべての者の間に正常な平和的関係が築かれるべきとの見方を明らかにし、米国が仲介努力を活発化させたことにより、交渉は具体化した。現在、撤退、関係正常化、安全保障、撤退の段階と正常化・安全保障措置のリンケージの4つの要素を含む和平パッケージ案が協議されている。イスラエル・シリア間の交渉での進展はイスラエル・レバノン間の交渉にも良い影響を与えると考えられる。シリアにとってもっとも重要な隣国であるレバノンには依然約4万人のシリア軍を駐留させている。シリアはロシアとの関係改善及び欧州連合(EU)との関係強化にも力を注ぎ始めており、特にEUとの関係では、94年11月に、対シリア武器禁輸措置解除の決定を引き出した。
日本との関係については、5月、柿澤外務大臣がシリアを訪問しアサ
ド大統領と会談したのをはじめ、日本の考古学発掘調査隊が活動を継続、パルシラ遺跡では最大級の地下墓が発掘されるなど目覚ましい成果を達成している。
日本の経済協力は、シリアの社会経済開発に効果的に資する形で増加している。円借款による発電所の建設が順調に進んでいるほか、無償資金協力の案件が着実に実施されており、技術協力分野では個別専門家10人、海外青年協力隊員40人の体制となり、プロジェクト型の協力も増えつつある。