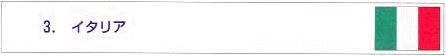
IV.欧州
(1)内政
イタリアの国内政治にとって94年は第1共和制から第2共和制への幕
開けの年として内外から大いに期待されたが、総選挙法の下での最初の選挙の結果誕生した内閣は、社会や国民生活に何の変化ももたらすことができず約8か月間混迷を続けただけで、年末に崩壊して、総選挙後1年たらずで再選挙が現実の問題になっている。
92年4月発足した議会は国民の信任を完全に失い、94年1月繰上げ解
散となり、3月比例代表制から小選挙区多数代表制主体(小選挙区75%、
比例代表区25%)の新選挙法の下で初の上・下両院議員選挙が実施され
た。総選挙の結果、中道右翼連合が下院で大勝利、上院では過半数にわずかに及ばなかったものの中道左翼に大きな差をつけた。
この選挙は、従来の中道左翼連立政権当時の政党を四分五裂させ、大規模な政界再編及び政治家の世代交代を進めたことから、戦後政治の構図を払拭し、いわゆる第2共和制の幕開けを告げるものとして、歴史的に重要な意義を有するものと評されている。
スカルファロ大統領は、選挙で一躍主要勢力となった新興の「がんばれイタリア」の党首で実業家のベルルスコーニを首相に任命、「北部同盟」、「国民同盟」、「キリスト教民主中道」等の協力を得て中道右翼政権
を5月に樹立した。内閣は当初順調な滑り出しを示したが、7月になると与党連合の乱れ、閣内の不統一、首相と司法当局の対立、首相の公私の利益の対立等が表面化するなどして、首相の立場が急に苦しくなった。95年予算案審議が開始された10月頃から、年金改革問題で労組と年金受給者の強硬な反対に遭遇、しばらく鳴りをひそめていたゼネストが全国で打たれ、政府が譲歩して年金問題はひとまず収まったものの、政府は財政政策面でも苦しい立場に陥った。さらに、財務警察の税務調査に関する汚職事件に関連し、首相自身に捜査の手が及ぶに至り、政情が悪化した。加えて、11月の地方選挙において都市部で中道右翼が中道左翼に敗北するなど、中道右翼にははっきりと蔭りが見えていたことなどが重なり、ベルルスコーニ首相は12月22日辞任した。
大統領は12月23日から次期首班任命のための協議を開始したが、人選に難航し、年末までに任命にこぎつけなかった。協議において旧与党は総選挙の結果構成された多数派が喪失したのだから、即時解散・選挙を行うか、または第2次ベルルスコーニ内閣を組織すべしと主張し、他の政党は選挙は避け山積みしている政治・経済・社会問題を処理する緊急内閣を組織すべしと主張している。
93年後半に始まったイタリア経済の回復は、94年に入り、リラ安効果による貿易収支の改善が持続し、鉱工業生産指数が4.5%増(1-10月
の対前年同期比)と順調に推移している上、家計消費等国内需要も回復
しつつあるなど、力強さを増している。94年の実質経済成長率は、政府見通しの1.6%を達成するとの見方が強い。
消費者物価上昇率は94年6月以降4%(対前年同月比)を下回って推移する等落ち着いている。しかし、ベルルスコーニ内閣の不安定さを材料として一段と進展するリラ安及び景気回復によりインフレが再発する
可能性もあることから、8月上旬に中央銀行は公定歩合を7.5%へと0.5
ポイント引き上げた。
財政赤字については、年金改革が後退したこと等により、当初の政府見通し(95年度財政赤字額138.6兆リラ)通り削減が行われるが予断を
許さない状況にある。
民営化については、金融、保険、食品・レストラン等の分野で実現した。
(2)対外関係
94年はイタリアがG7サミット及びCSCEの議長国を務めた年であ
り、その外交が注目されたが、内政が大きな転換期を迎えたことで、こ
こ数年に引き続きイタリアの外交活動は抑制されたものに留まった。ベ
ルルスコーニ政権成立当初は、これがネオファシストの流れをくむ国民同盟の閣僚を一部に有する政権であることから、その外交政策について、特に欧州諸国において警戒心を示す向きもあったが、5月の施政方針演説において、ベルルスコーニ首相は、大西洋同盟や欧州共同体での協調・協力の維持、ヘルシンキ会議の諸原則の尊重等を挙げ、これらの懸念に応えた。
7月のナポリ・サミットに際しては、人道援助タスクフォースの提唱
やサミット議長国としてロシアのサミット参加問題の調整等、一定の役割を果たした。欧州統合については、パラデュール仏首相や独CDUが、仏独を中心とする「中心国」とその他の「周辺国」に分かれると考えを示したことに対してはイタリア政府は激しく反発した。ベルルスコーニ首相はコール独首相より、本件構想は一政党のものにすぎず、独政府の欧州統合に対する基本的立場に変化はないとの説明を得たが、欧州統合の進展におけるイタリアの位置付けについては、今後とも議論になりうるであろう。
(3)日本との関係
経済関係では、第6回日伊ビジネス・グループの開催(10月)、経団
連欧州ミッション(6月)、中小企業投資調査団(6月)、日伊航空路の
充実(モスクワ経由1便増便)等民間ベースの交流は着実に進展し、金
融面でも、大型の円建てイタリア国債の発行(1月)を皮切りに邦人投
資家からの資金調達が活発化した。貿易面では、長年の懸案であった対
日差別輸入数量制限(QR)が撤廃(3月)された。
対日貿易は、対日輸出が底を打ち、94年前半は、前年比40%近い大幅
な伸びを示した。繊維、皮革製品などの消費財に片寄った輸出構成から、機械、化学品という比較優位に基づく、より広範な貿易関係への動きが見られる点が注目される。一方、対日輸入は円高を反映して低い伸びに止まっており、94年前半はほぼ横ばいであった。イタリアへの直接投資は近年伸び悩んでおり、94年に入っても回復の兆しは見えない一方、最近の日本の景気後退に伴うリストラの影響から、いくつかの撤退事例が見られた。