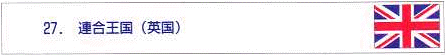
IV.欧州
(1)内政
与党保守党は、94年前半の統一地方選挙と欧州議会選挙で敗退し、大幅に議席を減らしており、経済の順調な回復にもかかわらず、保守党の支持率が労働党に20-30%下回る状況が続き、メジャー保守党政権の政局運営は引き続き厳しいものがある。その背景には、一方では、94年7月、スミス労働党党首の急死後選出されたブレア新党首が、その清新なイメージによって広範なブームを巻き起こしていること、一方では、欧州統合に関する推進派と懐疑派との対立、スキャンダルの続出等により保守党が有権者の信頼を失っていることが指摘されている。次期総選挙のタイミングは予断を許さないが(現下院議員の任期は97年5月まで)、今後の保労両党の対応が注目される。
経済面では、個人消費の牽引力は弱まっているものの、欧州の景気回
復により外需の寄与が拡大したこと等を背景に、94年には前年に引き続
きインフレなき経済成長が達成され、失業率も低下している。今後、生産は拡大を続け、稼働率は上昇し、設備投資の増加も見込まれる。クラーク蔵相は、景気拡大持続のためのインフレ抑制の重要性を繰り返し強調し、9月及び12月に公定歩合(ベース・レイト)を引き上げ、金融政策は引締めに転換した。11月の予算演説では同蔵相は、98年度に財政を均衡させることを目標に、昨年の財政再建計画を踏襲するとしている。インフレなき景気拡大を持続できれば、低インフレの持続、財政の健全化等EUの通貨統合の参加条件が96年中にも達成可能な状況にある。ただし、早ければ97年中にも予定されるEUの通貨統合への参加については、英国は態度を留保している。
(2)対外関係
英国は、国連安保理常任理事国としての地位、米国との伝統的大西洋
同盟関係及び英連邦諸国との連携を基軸とし、グローバルな視点に基づく外交を踏襲しており、近年、経済的・政治的な関係の密接化から欧州への傾斜を高める中にあって、欧州においてユニークな立場を保持している。欧州統合については、その意義を認識しつつも、保守党内部の欧州統合懐疑派の存在もあり、加盟国の主権の尊重、自由貿易主義の堅持等を主張し、中央集権的統合の方向に反対し、急速な統合の深化に慎重な立場をとっており、他の加盟国と時として対立することもある。一方、旧東欧諸国に対するEUの拡大については、これが欧州全体の安定に資するとの判断から、積極的に支持している。
近年、英国は、旧ユーゴー問題への取組に見られるようにEU諸国と
の政策協調を重視する傾向が強まっている。英国は、旧ユーゴー問題を
冷戦後の欧州における最大の問題の一つと位置付け、地上軍の派遣、人道支援の実施、コンタクト・グループへの参画等を通じ右問題の解決に向け積極的に貢献している。英国は、ロシアの経済改革、民主化を一貫して支持してきたが、今やロシアを国際社会の重要なパートナーと位置付けつつあると見られる。94年2月にメイジャー首相の訪露、9月にエリツィン大統領の訪英、10月にエリザベス女王の歴史的な訪露等活発な往来が行われ、現在のところ英露関係は基本的に良好である。
アジアでは引き続き日本、英連邦諸国等との良好な関係の維持発展が
図られるとともに、ヴィエトナム等との一層の関係強化が試みられた。香港をめぐり意見の対立の大きい中国との関係は、依然厳しい情勢にあるが、94年後半より関係改善のための動きが見られる。
(3)日本との関係
94年の日英関係は引き続き良好に推移し、各レベルにおける両国間の政治対話・協議が活発に行われ、ハイレベルの交流としては、7月のナポリ・サミットの際の日英首脳会談、9月に東京で行われた日英外相会談が挙げられる。9月の日英外相会談では、ハード外相より日本を英国の対アジア外交の中心に位置付けていることが明言された。また、1月にロンドンで開催された「日英会議」においては、ハード外相は、日英関係を「戦略的パートナーシップ」と位置付け、グローバルな日英協力の重要性が強調された。対南アフリカ協力等国際的な諸問題について、日英が共通の利害に基づきグローバルな協力関係を構築する機運は高まっている。今後の日英関係の課題は、こうした協力関係を一層進めるとともに、如何なる具体的成果を実現させていくかにある。
経済面では、英国は、日系の製造業者や金融機関の活発な活動を、英国に雇用、技術、競争力をもたらすものとして歓迎している。日本の対英投資は、総額では90年以降減少しているものの、対EU投資総額のシェア(40%以上)は維持しており、生産力や研究開発機能拡大の追加投資は着実に進んでいる。また、英国は94年4月より「アクション・ジャパン」と銘打ち、重点10分野に絞り、これまでよりも更に具体的な対日進出に取り組んでいる。対日輸出は、93年以降大幅に伸びているが、日本からの製品輸入も大きく、対日貿易赤字はなかなか減少しない状況であるも、対日貿易外収支は投資収益を中心に大幅な黒字であり、貿易赤字の相当部分を相殺している。
英国における対日世論は一般的には好意的であり、英国の報道に見られる日本への関心は拡大・深化していることが看取される。一方、戦争捕虜問題、捕鯨問題等の個別問題では対日批判も散見される。