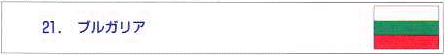
IV.欧州
内政面では、89年11月の民主改革以降では最長政権(22か月)となったベロフ内閣は、94年に入ってからも引き続き民主化と経済改革の推進
に努め、94年夏までに最大の懸案であった対外債務問題を片付け、また国営企業の大衆民営化に向けての民営化法の改正、破産法の成立といった法制度の整備を進めた。しかしながら、同内閣を支えてきた社会党をはじめとする議会の多数勢力との不協和音など政治的支持基盤の脆弱さを露呈し、民営化及び農地返還を十分に達成し得ないうちに、94年9月総辞職した。新内閣組閣への試みもなされたものの、議会内各政治勢力は解散、総選挙を指向し、ジエーレフ大統領は選挙管理内閣を任命した上で議会を解散し、3年振りの総選挙が12月に実施された。同選挙では社会党が圧倒的勝利を収め、絶対多数の議席(240議席中125議席)をも確保し、95年の政策運営を任されることとなった。経済的には、農業の不振が続き、引締め政策(9月には公定歩合を10%引き上げ、72%に設定)が継続され、またインフレ(94年の見通しは約120%)が進む中にあって鉱工業生産が上向いてきており、GDPのマイナス成長にようやく歯止めがかかったと見られる。
対外関係面では、EU、NATO等の欧州政治・経済機構への統合によ
るグローバルな安全保障体制への参加、近隣諸国との関係強化及び経済
協力の拡大によるバルカン全体の平和と安定の確保、旧ソ連各国との政
治・経済関係の再構築等を主軸とした外交が進められた。
日本との関係では、経済協力を中心とする民主化・経済改革支援を引き続き拡充している。5月には貿易保険の引受けを再開し、8月には輸銀からブルガリアへの1億ドル構造調整融資の第1トランシュ(約5千
万ドル)が支出された。94年秋には双方の国内各都市において文化月間が開催された。94年は要人交流が活発化し、日本からは海部元総理、日・ブルガリア友好議員連盟一行ほかが訪問し、またブルガリア側からはマテインチェフ、ツオチェフ両副首相等が訪日した。