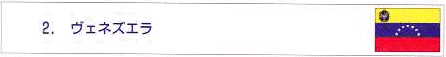
III.中南米
94年2月に発足したカルデラ政権はこの1年、未曽有の金融危機の対応に終始した。1月、国内第2位の預金高を占めるラティノ銀行を始め17行の経営が破綻し(これら17行の預金高は国内全預金高の55%)、国家経済は大混乱に陥った。政府は17行を事実上の国家管理に置き、救済資金として預金保証基金を通じ94年度中央政府予算の71%に相当する約1兆ボリバルを投じたことを始めとする一連の措置を実施し、金融危機は峠を越した感がある。しかし、金融危機は生産活動の著しい減退をもたらし、94年の経済成長率はマイナス3%と93年に引き続きマイナス成長を記録した。失業率も製造業の相次ぐ倒産により93年の7.5%から14%へと増大し、インフレは過剰流動性により72%を記録し、中央政府の財政赤字は約17%に達したと見られている。
一方、腐敗の一掃に取り組むカルデラ大統領に対する国民の信頼と支持は高く国軍とも良好な関係を維持するなど政治的安定を確保している。ただし、中・下層階級の窮乏などの経済困難は切迫しており、カルデラ政権は経済面で具体的成果を上げる必要がある。
外交関係では、グループ3(ヴェネズエラ、コロンビア、メキシコ三国間の自由貿易協定)の創設、及びカリブ諸国連合創設に参加し、また、アンデス・グループ域外共通関税設定に貢献する等、その存在を示した。また、南米共同市場への参加にも強い関心を表明した。
二国間関係では、特にブラジルとの間で、首脳の相互訪問ハイレベル
協議設置、経済補完協定の署名が行われるなど関係緊密化が注目された。
米国との関係では、米国の環境基準を満たしていないことを理由に
ヴェネズエラ産ガソリンの対米輸出を阻止しようとする米国の貿易政策に対する不満をつのらせた。
ハイティ問題については、多国籍軍のハイティ進駐に反対した。
日本との関係では、日刊紙2紙による定期的な日本特集記事の掲載、日本語学習者、日本留学希望者の急増などに見られるように、ヴェネズエラの日本に対する関心は近年とみに高まっており、日本の資本及び技術の導入に対する期待感が強い。一方、石油、鉄鉱石等を始めとする豊富な天然資源開発は、大きな潜在的可能性を秘めており、両国が経済的補完性を有している点は注目に値する。