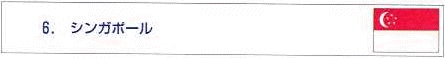
I.アジア及び大洋州
(1)内政
ゴー・チョクトン政権は90年11月に発足以降着実にその地歩を固め、94年においてもシンガポールの内政は安定的に推移した。最近のシンガポールの内政面での課題の一つは、今や先進国なみの所得水準を享受するに至った国民が政治・社会の面でも期待を高めていることにどのように対処していくかという点である。ゴー首相は就任以来「開かれた協調的スタイル」を強調し、国民の一定の支持を集めてきたが、94年には2回にわたり閣僚・公務員の大幅な給与引上げを行うなどの施策をとった結果、一部において政権発足当初の国民の期待を裏切るものとの批判を招くに至っている。
経済面では、93年に実質9.9%増の高い成長を遂げた後もその勢いが弱まることはなく、94年全体は10%程度の成長が予測されている。物価は総じて安定しているものの、車両価格やタクシー料金などの交通関係や食糧品、住宅などの価格上昇もあり、この点で国民の不満が高まってきている。また、失業率が1%台になるなど労働供給も逼迫してきている。貿易依存型、外資依存型であるシンガポール経済にとり、近隣諸国との対比での競争力の維持は重要であり、物価の問題は政府の信任にも関わるものである。
(2)対外関係
シンガポールは従来よりASEAN諸国との緊密な関係の堅持を対外関係における最も重要な柱としている。また、近年シンガポールは、インド、中国、ヴィエトナム、ミャンマー等のASEAN周辺諸国との関係強化を重視しており、自らをこれらの国々の経済発展の中核と位置付け、東アジア地域全体への投資拠点としてのシンガポールの重要性を強調している。さらに、安定的な安全保障環境と自由貿易体制に国の存立を依存するシンガポールは、ASEAN地域フォーラム(ARF)やAPECを通じたアジア太平洋における地域協力の推進にも積極的に取り組んでいる。
シンガポールが、そのめざましい経済発展の下で国際的地位を向上させるにつれて、欧米諸国と価値観の異なる部分がこれまで以上に強調され、このことが対外関係に微妙な影響を及ぼす事例も生じている。5月に国際的論議を呼んだ米国青年へのむち打ち刑の執行問題はその一例である。しかし、こうした傾向が開放的、協調的な対外関係の維持というシンガポール外交の基本姿勢そのものを揺るがすことはないものと思われる。
(3)日本との関係
日本との関係においては、各分野における交流の幅と深みを広げる努力が双方で引き続き払われた。特に、8月に土井衆議院議長と村山総理大臣が相次いでシンガポールを訪問し、政府首脳と意思疎通を深めたほか、第二次大戦中の日本占領期に受難したシンガポール市民の慰霊塔に対し、日本の立法、行政府の長として初めて公式に献花した。
文化面では、6月のシンガポール政府主催シンガポール芸術祭に日本の芸術家が招聘されたほか、民間における文化行事も盛んに行われており、日本の現代文化が一般に受け入れられつつある。シンガポールを対象とする日本の二国間経済協力プログラムの終了を間近に控え、両国関係の中で文化交流の果たす役割は増大してきている。