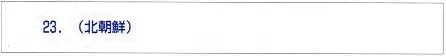
I.アジア及び大洋州
(1)内政
94年7月8日、長年北朝鮮の最高指導者の地位にあった
経済面では、93年12月の労働党中央委員会総会で提示された経済政策
(今後3年間を調整期間とし、農業第一主義、軽工業第一主義及び貿易第一主義の下で経済運営を行うというもの)の貫徹が累次強調されており、北朝鮮が経済問題の解決をその重要課題としていることがうかがえる。北朝鮮経済は、社会主義経済システムの非効率性に加え、過重な軍事費負担、機械設備の老朽化、エネルギー不足、外貨不足のほか、旧ソ連をはじめとする社会主義市場の崩壊による対外貿易環境の悪化等により、生産活動の低迷、食料不足、貿易の減少などの経済的困難に直面しているものと見られる。北朝鮮は経済統計をほとんど発表していないが、93年12月の党中央委員会総会では、第3次7か年計画(87年-93年)が未達成に終わったことを異例に認めている。韓国銀行が推計した93年の北朝鮮のGNPは、対前年比4.3%減の205億ドルで、90年代に入ってか
ら4年連続のマイナス成長となっているほか、北朝鮮の対外貿易総額も、89年の48.0億ドルから93年には26.4億ドルに減少している。
このような持続的な経済の沈滞の中で、北朝鮮は依然として「朝鮮式
社会主義建設」という旗印の下で自立的経済路線を堅持しているが、一方で91年12月に設定した「
(2)対外関係
北朝鮮は、米国との関係改善を第一の目標としていると見られ、このためにも核問題に関する米朝協議には積極的に対応してきた(北朝鮮の核兵器開発問題については第1分冊P19~23参照)。反面、南北対話には未だ前向きな対応は見られない。金日成主席の死去により延期された南北首脳会談については、韓国政府が韓国国民の金日成主席への弔問を不許可としたのを契機に北朝鮮が韓国政府に対する非難を繰り返している状況の下、開催のめどは立っていない。中国との関係は、同国が金日成主席の死後、即座に金正日書記を後継者として認める内容の弔電を送ったほか、北朝鮮からの要請を受けて12月に休戦委員会中国代表団を召還させるなどの行動をとったこと等、良好な関係が維持されているものと見られる。また、韓露国交正常化以後冷却化していたロシアとの関係も、9月にパノフ・ロシア外務次官が大統領特使として訪朝するなど、好転する兆しを見せている。
(3)日本との関係
北朝鮮は過去の朝鮮半島統治に対する補償、賠償を主張するなど、対日批判を続けている。日朝国交正常化交渉については、92年11月に北朝鮮が一方的に交渉の席を立って以来、94年においても中断されたままであり、進展を見ていないが、日本は、第二次世界大戦後の日朝間の不正常な関係を正すとともに、朝鮮半島の平和と安定に資するという二つの側面を踏まえ、韓国をはじめとする関係国とも緊密に連絡を取りながらこの問題に対応することとしている。