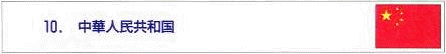
I.アジア及び大洋州
(1)内政
94年は、93年11月の共産党中央委員会第3回全体会議(3中全会)における50項目の包括的な改革措置の決定を受け、新税制や為替レートの一本化など、「社会主義市場経済」確立に向けた改革措置が導入されたが、一方で「改革・発展・安定」の関係の正確な処理が強調され、3月の全国人民代表大会第2回会議もこの基調を継続するなど、「安定」を重視する姿勢がより明確になった。
また、政策の方向性が固まり、
この間、経済面では農産物価格引上げ等による高インフレ(1-11月で24.9%)が継続し、11月末の中央経済工作会議ではインフレ抑制を主眼とする政策の徹底が要求された。また、沿岸部と内陸部の間の経済格差の問題も徐々に顕在化している。95年は国有企業改革が正念場を迎えるが、中国が経済的社会的な混乱を招くことなく、安定的発展を継続できるかどうか、今後とも注視する必要がある。
(2)対外関係
中国は国内経済建設に有利な国際環境づくりを基本方針として94年も積極的な外交を展開した。米中関係は、5月にクリントン政権が中国に対する最恵国待遇(MFN)を更新し、同時に今後は人権問題をMFNと関連づけない旨決定したほか、11月にはジャカルタにおいて米中首脳会談などが行われるなど基本的に改善へと推移している。ただし、両国間には中国における知的所有権の保護問題等摩擦要因が存在するほか、台湾問題をめぐって米側による対台湾政策の調整発表(9月)やペニャ運輸長官の訪台(12月)に中国側が抗議する場面も見られた。アジア諸国との関係については、11月の
他の核保有国が核実験のモラトリアムを継続している中で、中国は6月と10月の2回、地下核実験を行った。その際に中国側は、中国の核は全く自衛目的であり、核実験の回数は核保有国中最も少ないこと、全面核実験禁止条約(CTBT)の96年末までの締結と核兵器の先制不使用を主張している旨表明した。中国は94年末までに関税及び貿易に関する一般協定(GATT)に加入することを目標とし、各国との交渉を行ってきたが、結局これは実現せず、95年も交渉は継続されることとなった。
(3)日本との関係
94年の日中関係においては、引き続きハイレベルの要人往来、会談が行われた。経済面では、輸出入総額が1-11月で419億米ドルに達しており、日本から中国への投資も4-9月の6か月だけで11億米ドルを越す急速な進展を見せている。また、12月には第4次円借款の当初3年分に関し40プロジェクト、5,800億円について日中間の意見の一致が見られ、日本の対中経済協力の重要な柱が固まることとなった。
一方、94年には過去の歴史認識に関して、日本の閣僚による一連の発言をめぐって問題が生じた。また、中国は最近の台湾の動向に懸念を強めており、広島アジア競技大会への台湾からの出席者問題についても最後まで理解を示さなかったという事態も生じている。戦後50周年という節目の年である95年を未来志向の日中関係を構築する新たな契機とするため、日中共同声明及び日中平和友好条約の精神に基づき、両国関係を一層発展させていくことが重要である。