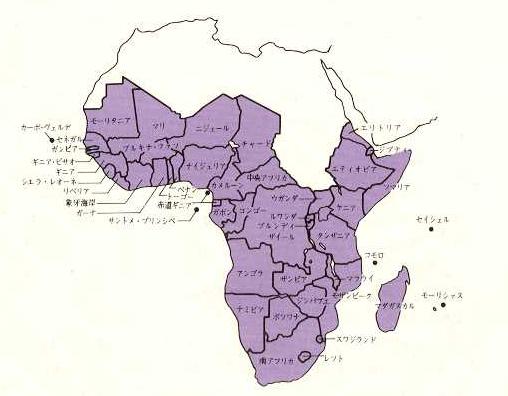
VI. ア フ リ カ
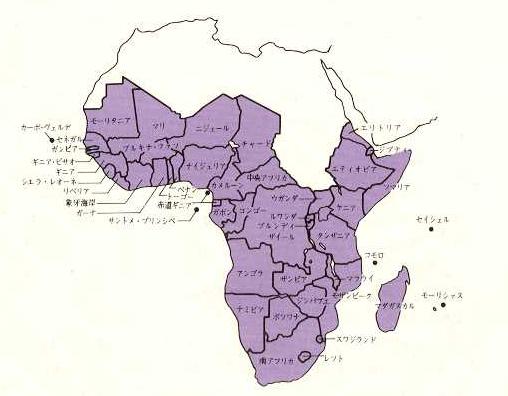
93年1月早々エリトリア独立反対を叫ぶ学生グループと警官隊が衝突したが、事態はすぐ平静化した。4月にはエリトリアが住民投票の結果圧倒的多数の賛成によって独立を達成し、7月にはエリトリアとの間に広範な分野での友好協力協定が締結された。現政権は部族を単位とする地方自治体を結成し、これに大幅な自治権を付与することによって部族問題の解決を図るとの方針で法制を整備し、93年5月頃までに各行政レベルの自治体が、ほぼ全国的に発足した。憲法制定については、2月には92年8月設置された憲法起草委員会が活動を開始、その後、政党登録法及び国政選挙法が制定されたが、12月政府は準備期間の不足などを理由に制憲議会選挙の実施を延期し、94年6月に実施すると発表した。
経済面では、前年スタートした緊急復興再建計画(ERRP)(資金ターゲット6億7,000万ドル)、構造調整支援(新規コミット総額12億ドル)が実施され、降雨に恵まれた92年の農業生産が増大した結果、93年央で終わる92/93年度は前年比でGDPは7.6%伸び、インフレは平価切下げにもかかわらず21%から10%に低下した。他方、旧体制崩壊後の大量解雇、公共部門の整理、政府補助金カットによる食料品等の値上がりなどにより国民、特に都市部の貧困に変りはなく、特に年央以降の降雨不順で93年の農業生産は大幅に低下するものと予測されている。
ソマリア和平問題では、国連事務総長はかの要人が相次いで来訪し、メレス大統領とソマリア問題を協議した。国内に約200万人のソマリア系国民と40万人のソマリア難民を抱えるエティオピアにとりソマリア情勢の影響は大きく、このためメレス大統領はアフリカ統一機構(OAU)首脳会議(6月)でソマリア問題解決のためOAUを代表するマンデートを付与され、アジスアベバにおいてソマリア国民和解会議、同国援助会議などが頻繁に開催された。
93年は民主化の達成と治安面での一層の安定が特筆される。ローリングス大統領に対しては、最近野党支持層からも支持及び評価が出てきている。このような中で野党側の提案を受けた与野党間協議も行われており、国政は非常に安定してきたと言える。
経済面では、92年の厳しい状況からの立ち直り過程にあるものの、93年初頭に行われたガソリン価格の大幅引上げが尾を引き、3年振りに25%を越すインフレを経験する見通しとなったが、夏以降、安定した回復軌道に入っている。また、一層の経済発展のためには外国資本の誘致が不可欠との認識に立ち、投資法の制定を検討している。
外交面では、イスラエルと国交回復交渉を行うなど対外関係で次第に成熟した対応を示しつつある。
日本との関係では、5月に行われた高円宮同妃両殿下のガーナ御訪問は対日理解・関心を高める上で極めて効果的であった。また、10月にはローリングス大統領夫妻が来日し、日本との協力関係に一層の関心を示した。
93年のガボン内政は12月の大統領選挙を中心に動いた。今次大統領選挙は、複数政党からの候補者により争われたガボン史上初めての選挙であり、国民会議の開催、複数政党制による国会選挙の実施、新憲法と政党法の採択など90年以来進行してきたガボン民主化のいわば総仕上げをなすものであった。選挙結果は、ボンゴ大統領が有効投票の過半数の51.07%を獲得して当選したが、野党共闘側の対立候補者であったムンバ・アベソレは、政府の開票結果の不正を唱えて自ら「大統領」に就任を宣言、「首相」を任命するなど一時混乱状態となった。その後緊急警戒令の施行もあり、国内は平静を保っているものの政府側からの政治的休戦の呼びかけに対し、今後野党側があくまで政府との対決の姿勢を示すのか、あるいは政府の入閣の呼びかけに応じるなどの柔軟な態度に出るのか、その去就が注目される。
経済面では、政府は経済再建のため調整努力を続けたが、対外累積債務は依然減少せず、また、外貨収入の80%以上、GDPの30%以上を占める石油は、世界的な原油価格の低迷により大幅な収入の増大とはならなかった。
外交面では、93年は、大統領選挙に焦点が集まり内政に比重が置かれたこともあり、比較的動きの少ない年であったが、1月には在ガボン南アフリカ大使館が開設(外交関係樹立は92年11月)され、9月にはイスラエルとの外交関係が再開(73年の第4次中東戦争後断絶していたもの)された。
92年10月再選されたビヤ大統領は、対立候補(フル・ンデイ)を一時自宅軟禁状態に置き、93年10月、フル・ンデイが警官隊から逃れてオランダ大使公邸に3日間緊急避難するという事態も発生した。カメルーンでは、それまでの一党制を改め、民主化の制度を導入したが、民主主義が確立されていくためには、三権分立の確立(特に、司法権の独立強化と議会の強化)、基本的人権の制度的保障を含む政治改革、及び憲法改正が不可欠とされている。また、旧英語圏と旧仏語圏が合体してできたカメルーンの政治・経済発展のためには、部族主義の克服が課題とされている。
93年カメルーンの経済成長率はマイナスと予測され、93年国家予算は、ここ数年来と同じく、大幅な財政赤字となる見通しである。また、対外累積債務はGDPの50%を超えている。また、為替レートは経済の実勢を上回っているため、平価切下げが課題として出ている。石油の産出量は年々落ちている。その中で現在は、国際通貨基金(IMF)、世銀とも新規融資を停止し、米国も民主化、人権について満足できる状況にないとして、援助を中断している。
ギニアは、90年末の国家基本法(憲法に相当)採択以来、軍政から民政への移行、民主化実現への過程にある。93年は、92年からの懸案であった大統領選挙がようやく12月に実施され、大方の予想どおりコンテ現大統領の当選が決定し、向こう5年間引き続き政権を担うことになった。政策的には従来からの路線(民主化実現、経済構造調整計画の実施、先進諸国との関係強化)が継続されるものと見られる。
経済面では、93年のGDP成長率は5%で、ボーキサイトの生産増大、及び農業部門の生産が4.1%伸びたことにより、92年に設定された目標値(3.5%)を超える数値となり、他方、物価の上昇率は、平均8.5%程度に抑えられる見通しである。
コンテ政権は、前政権時代の社会主義から自由主義経済への移行による経済再建を図り、85年末以来、IMF、世銀の指導の下に経済構造調整計画を実施中で、これにより食糧の自給、経済の自由化、公務員の削減、公営企業の民営化等の措置が採られている。
外交面では、独立以来旧東側寄りの非同盟路線をとってきたが、東西対立の解消した現今では、欧米先進諸国や日本、中国等のアジア諸国との関係強化に努めている。また国民の70%近くがイスラム教徒であることから、アラブ・イスラム諸国との連帯感も強い。また、近隣の西アフリカ諸国との関係は良好である。
92年末の複数政党制下での総選挙・大統領選挙の結果、与党ケニア・アフリカ人国民同盟(KANU)が国会において過半数を維持し、モイ大統領が再選されたが、野党も合計で88議席(国会議員の約4割)を獲得し、複数政党民主主義への一歩を踏み始めた。
経済協力については、4月以来、IMF、世銀の指導の下に経済改革が順調に進捗し、世銀及び日本については輸出促進計画に対する国際収支援助(B/Pサポート)を再開した。また、11月には2年振りに援助国会合が開催され、今後のケニアの経済改革の継続、部族抗争解消などの民主化への取組、汚職の根絶への一層の努力を前提として、既に援助を再開している日本も含め、他の援助供与国についても援助を再開する旨のコンセンサスが出来た。
経済一般では、天候不順による農業の不振が引き続き大きなマイナス要因となっており、実質GDP成長率は、93年は92年の0.4%を更に下回る見込みである。為替レートは3度にわたる切下げの後完全フロート制に移行したため、輸入品、輸入原材料の値上がりをもたらしており、統制価格の撤廃ともあいまって高率のインフレをもたらしている。
外交面では、11月、ケニア、ウガンダ、タンザニアの東アフリカ3国の大統領が、「三国委員会」の設置に合意し、地域間協力へ一歩を踏み出した。
92年には混乱の中にも一応の前進を見たザイールにおける民主化プロセスであったが、93年1月再びキンシャサで兵士を中心とする暴動が発生、その後の政局は、モブツ大統領派と反モブツ派の主導権争いが際限なく繰り広げられており、事態打開のめどは立っていない。このような状況の下、12月のシャバ州知事による同州の自治宣言は、ザイール政局に新たな波紋を投げかけるものとして今後の動きが注目される。
経済面では、インフレが年率20,000%に達するとも言われ、10月には通貨改革が実施され新ザイール札が発行されたものの(発行当時1米ドル=3新ザイール(1新ザイール=3百万旧ザイール))、経済活動の実態の伴わない通貨改革はザイール社会の混乱に一層の拍車をかけることとなった。
外交面では、91年9月のキンシャサ大暴動以来、人道援助を除き欧米諸国よりの経済援助が中断されている中で、国連人権委員会におけるザイール非難決議の採択、ザイール人に対する査証発給の制限、世銀の対ザイール融資停止措置などますます厳しさを増した。
日本との関係では、91年めキンシャサ大暴動の発生に伴い、在キンシャサ日本大使館は現在一時閉鎖中であり、また、ザイールに対する援助が事実上困難な事情にあることから、日本との交流も低いレベルにとどまっている。
27年間の一党独裁の後、91年に民主的な選挙により発足したチルバ政権は、国内外からアフリカにおける民主化の成功例として注目されてきた。しかし政権2年目にして政府指導部内での汚職、麻薬取引問題への疑惑が取りざたされ、民主化、「良い政府」のイメージが急速に曇りつつある。構造調整政策においてはこの1年、特にインフレの沈静化にこぎつけ、マクロ的安定についてもめどを見るなど一定の進展があったが、社会的弱者に対するしわ寄せは依然深刻であり、国民の政権への失望感を深め、政治自体への無関心が一層増している。こうしたことを背景に与党は分裂、新たに国民党(NP)が結成された。
外交面では、チルバ政権発足時に明言されたように経済再建の手段としての実利外交に努めている。ザンビアが引き続き国際的支援を受けていくためには、日本、欧米などの主要援助国が一致して求める民主化、「良い政府」の実行が必要であるが、この点政府指導部内での汚職、麻薬取引問題への疑惑などにどこまで具体的に対処し、指導力を示すかが注目される。
ジンバブエは冷戦構造が崩壊した今日、独立以来の社会主義体制から離脱して、市場経済に移行するための体制づくりを進めている。93年の動向としては、95年の総選挙を控え、議会内で圧倒的多数を占める与党内のポスト争いが本格化したこと及び大干ばつから経済的に回復したことが特筆される。すなわち、政治面では、野党が国民の不満を吸収するような本格的な政策を打ち出せず、現状では与党に代わる勢力とはなっていないため、むしろ、圧倒的多数を占める与党内の世代交代争いの方が活発であった。経済面では、大干ばつの影響もあって、過去2年間マイナス成長、インフレ等に苦しんだジンバブエ経済は93年に入ってからは順調な降雨による農業生産の増大等により好転しつつあり、インフレも鈍化しつつある。他方、世銀、IMFの指導の下、構造調整が進められており公的セクターの活性化等克服すべき課題は数多く残されている。
外交面では、ジンバブエは非同盟を標榜し、独立時に支援を受けた旧ソ連、中国、北朝鮮、キューバ等と緊密な関係にあるが、他方、ジンバブエが南部アフリカの重要国との観点から日本や欧米諸国との関係は深まりつつある。国連平和維持活動(PKO)の分野ではソマリア等に要員を派遣するとともに隣国モザンビークの和平にも寄与しており、また、アンゴラ和平に向けての努力も継続している。また、11月には、9月のイスラエル・PLO合意を受けてイスラエルと外交関係を樹立し、12月には、南アフリカと外相会談が初めて行われ、両国の首脳会議がいつ実現するか注目されている。
与党社会党は、93年2月の大統領選、5月の国民議会選で勝利を収めた。他方、セネガル民主党が躍進し、閣内参加が確実視されていたが、国民議会選挙後に発生したセイ憲法評議会副議長暗殺事件への関与の疑いから、閣内参加は不成功に終わった。南部のカザマンス地方の分離独立を主張する反政府グループ(MFDC)と政府の停戦協定が7月に締結された。
8月、経済再建策が政府により発表され、実施に移されたが、野党及び労働組合が強く反発し、数次にわたるゼネストを実行、対決姿勢が続いている。資本の流出を防ぐため、通貨CFAフランの域外での再買上げ禁止の措置が8月、西アフリカ諸国中央銀行により採られた。
外交面においては、89年以来のモーリタニアとの紛争が実務面で解決したほか、ギニア・ビサオとの海洋資源協定締結、ガンビアとの航空協定締結など近隣諸国との関係改善が図られた。
95年の次期大統領選挙出馬をほのめかしたワタラ首相に対し、憲法上の大統領の後継者であるベディエ国民議会議長の支持派は、強く反発を示してきたが、ウーフエ・ボアニ大統領が首相の経済再建政策支持を表明したため、対立は表面的には沈静化した。12月、大統領が死亡したのを受け、ベディエ議長は自ら大統領就任を宣言し、ワタラ前首相と同様国際経済通のダンカン首相の新内閣が発足した。新政権は発足早々、国内団結の維持、構造調整と経済再建の推進、CFAフラン切下げ問題への対応等を迫られている。
経済面では、92年にGDPは1%のプラス成長に転じ、93年には1.5%が期待されているが、世界経済の不況、主要輸出産品であるコーヒー、ココアの国際価格の低迷などのため、200億ドルに達する債務の返済は重圧となり、また、給料支給の遅滞のため、医療、教育部門等でのストライキも見られた。象牙海岸の外部資金の需要に対して財政支援を行ってきたフランスは、構造調整計画についての世銀及びIMFとの合意達成を援助供与の条件とするようになり、世銀及びIMFは、凍結中の資金を供与するためには、経常財政支出の4分の3を占める公務員給与の圧縮を要求している。
日本との関係では、高円宮同妃両殿下の公式訪問(4月)が、友好関係の強化に大きく寄与した。
政治分野では単一政党制から複数政党制へ移行し、92年関連法案が成立したことに伴い、93年12月政党が政党登録を行った。経済分野では経済再建と経済の自由化、市場経済への移行を目指す構造調整が緩やかながら順調に進められており、86年の経済復興計画、構造調整実施以来、平均年4%の成長を達成している。現在、金融改革、公団公社の整理統合、公務員制度の改革、産業部門改革などを進めている。
外交面では、伝統的に国連及び非同盟外交を重視するとともに、近隣アフリカ諸国との善隣、アフリカ統一機構(OAU)、南部アフリカ開発共同体(SADC)などによる域内協力に重点を置いている。93年タンザニアは仲介国としてアルーシャにおけるルワンダ和平交渉の妥結に重要な役割を果たす等域内平和に貢献するとともに、地域協力分野では東アフリカ協力首脳会議においてタンザニア、ケニア、ウガンダ3国間の常設の「三国委員会」を創設し、旧東アフリカ共同体に代わる政治、経済、社会、文化の広範な分野にわたる域内協力の枠組みを構築した。また、東部南部特恵貿易地域首脳会議において東部南部共同市場(COMESA)条約に署名した。
日本との関係では、日本はタンザニアの主要貿易相手国で、貿易額は輸出約1億1,000万ドル、輸入約3,000万ドルと日本の大幅輸出超過となっている。タンザニアは外貨導入を勧奨しているが、市場の狭隘、基礎インフラの未整備など投資環境が不完全なこともあり、日本企業の新規進出は数少ない。経済協力は年間92億円の規模に達している。
アフリカ諸国においても進展の見られる民主化の波は大陸中央に隔絶したこの国にも及び、93年8月から9月にかけて民主的な大統領、国会議員選挙が行われた結果、軍人出身のコリンバ大統領は経済危機の慢性化と国家財政の破綻を背景に、国民の支持を失い、代わって文民出身のパタセ大統領が登場した。10月同大統領は、議会第1党となった自党中央アフリカ人民解放運動(MLPC)を核としてマンダバ連立内閣を任命、挙国一致で国の再建に当たる決意を表明したが、その成否が国際金融機関や先進諸国からの援助にかかっていることに変わりはなく、したがってこうした援助の前提条件たる民主化の促進とIMFの構造調整計画をどれだけ実現できるかが新政権の課題となろう。
日本との関係では、前記選挙の際、民主化支援の見地からフランスに次ぐ資金援助を行い、国際選挙監視団にも参加したほか、深井戸の掘削、大西洋に通ずる幹線道路の舗装工事など種々の無償援助を実施している。
87年来ババンギダ軍事政権の下で進められてきたナイジェリアの民主化は、93年6月の大統領選挙の無効とその後の政治的混迷の中で8月ババンギダ大統領が退陣し、11月アバチャ新軍事政権が無血クーデターにより成立した結果、振出しに戻った。このため、主要欧米先進民主主義国は直ちに軍事援助の停止と経済協力の見直し意図を中心とする対ナイジェリア措置を発表、日本も民主化後退への遺憾の意、民主化の着実かつ平和的意向への希望、並びに対ナイジェリア関係見直しの意向を表明した。その間政治的混迷に伴い社会不安も増大し、8月ラゴス等主要都市で大規模な暴動が発生、一般治安も著しく悪化した。新軍事政権は、国家の統一保持、治安の回復、「真の」民主化促進のための国民制憲会議の開催を表明し、新政権の一部主要ポストに先の選挙の大統領・副大統領候補や人権擁護派の指導者らを任命したが、民主化実現の具体的日程や行動計画は未定であり、その見通しは立っていない。また、経済活動も低下の一途をたどり、93年1年間で通貨ナイラの価値は半減し、インフレ率も90%(93年10月、対前年比)を超えた。このような状況下で、日本の対ナイジェリア経済技術援助及び民間経済活動も後退を余儀なくされた。
ナイジェリアはアフリカの黒人国家の中で最大の人口と石油資源を有し、その動向は西アフリカ及びアフリカ全体に大きな影響を及ぼしているが、三大部族間の対立が根強く、政治的安定と民主化実現への道は厳しい。同時に、新政権は、経済・財政運営の健全化と汚職追放の意図を表明しているが、その実現は今後の努力いかんにかかっており経済の停滞の打破と発展への道は厳しい。
マダガスカルにとって93年は、2月の大統領選挙第2回投票、6月の国会議員選挙とこれに続く首相指名、組閣を無事終了し、第三共和制が名実ともに樹立され、新体制が経済再建に向けて実質的に動き出した年であった。
経済面では、徐々に回復基調にあるとは言え(92年度成長率1%)、いまだ91年からの内政混乱の影響を引きずっている。ラボニ内閣は、政策のプライオリティーの第1として経済再建を挙げてこの問題に真剣に取り組む姿勢を見せている。まずはインフラ整備に力を入れ、投資環境を整えることから始められよう。またマダガスカルは極端な外貨不足にあり、これを打開するために援助国、援助機関よりの融資及び外国からの投資が重要視されている。
外交面では、経済再建の観点から、より一層西側諸国及びアジア諸国との関係を重視した展開が予想されよう。実際ザフィー大統領は、外交の基本政策として経済的利益という現実的要請に対応した外交の再編成に言及しており、例えば5月、韓国との間の外交関係正式再開に関する共同声明が発出されている。
92年のボイパトン事件を契機に約10か月の中断を経て93年4月に再開された複数政党交渉は、クリス・ハニ南アフリカ共産党(SACP)書記長の暗殺、暴力の激化、各種テロ事件の頻発及びインカタ自由党(IFP)や保守党(CP)等の複数交渉撤退といった困難に直面しながらも、暫定評議会の設置を通じて事実上の黒人・白人共同統治が開始されるとともに、新憲法が制定されるまでの今後5年間を規律する暫定憲法が12月採択され、94年4月の一人一票制の制憲議会選挙を通じた民主体制の確立に向け大きく前進した。他方、このような民主化プロセスは、IFPやCP等の主要政党の賛同が得られないまま見切り発車した形となっているため、選挙の見通しは楽観視はできない。
経済面では、93年は、第4次債務返済繰延べの合意、マンデラ・アフリカ民族会議(ANC)議長の国連での制裁解除の演説、暫定評議会の設置、IMF融資の承認など、南アフリカ経済にとって明るいニュースが続いている。92/93年夏期の降雨量の増加による農業分野の生産改善は93年の経済成長に大きく貢献しており、第1-第3四半期の平均成長率は5.1%に達し、89年以降の長期不況を脱する見込みである。成長の鍵を握る製造業分野も、公共部門の設備投資が堅調で、93年後半にマイナス成長を脱し、景気は回復基調にあると言える。
このように、南アフリカ経済はリセッションを脱しつつあるが、新政権の中核となるANCの一部には、企業の国有化、経営陣にまで及ぶアファーマティブ・アクション(人種を配慮した雇用政策)等を主張する向きもあり、新政権の経済政策いかんによっては、経済情勢が悪化する可能性もあるため、引き続き注意する必要がある。
外交面では、12月のデ・クラーク大統領及びマンデラANC議長のノーベル平和賞受賞に象徴されるように、南アフリカ自体がアパルトヘイトに終止符を打ったことを受けて、国際社会も南アフリカの民主化プロセスを評価し、南アフリカは国際社会における長い孤立を脱却し、正式に国際社会の一員として復帰することとなった。