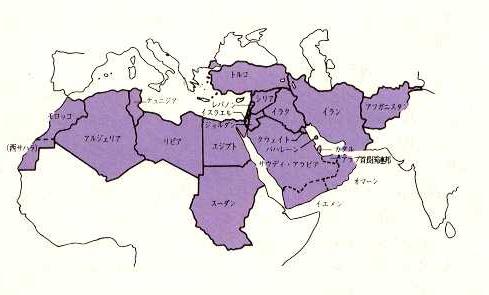
V. 中 近 東
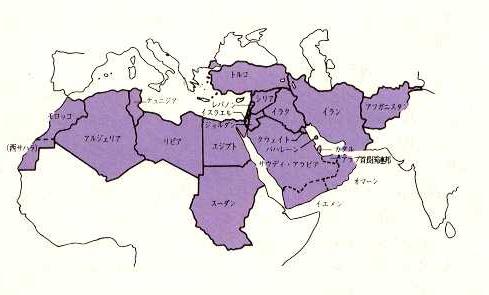
93年、内政は引き続き安定的に推移した。連邦制の強化とその指導体制確立がア首連内政上の重要課題であるが、連邦商標法の制定、領海(12海里)に関する連邦布告、恒久憲法制定委員会の組織など、連邦全体にまたがる法制度・組織の整備が進んだ。1年余にわたり凍結されていた連邦国民評議会が2月に再開されたことも内政の安定度を示すものとして好感をもって受け入れられた。経済面では、石油部門が原油価格の低迷によりGDP前年比3.3%減となったものの、非石油部門は同4.3%増と活況を呈した。従って、経済全体としては1%台の低成長ながら非石油部門の着実な成長に支えられ、安定的に推移するものと思われる。なお、湾岸地域の商業拠点として、欧米、アジア諸国のみならず、中・東欧諸国、旧ソ連邦構成諸国及び南アフリカ等との関係が拡大している。
外交面では、基本的には湾岸諸国との協調を重視し、反イラクの立場を維持したが、いわゆるイラク支援国との関係は徐々に改善した(イエメン、ジョルダン、パレスチナ解放機構(PLO)等)。イスラエル・PLO合意に対しては、早々と支持声明を発し、次いで2,500万ドルの援助拠出を約束した。イランとの関係では、アブー・ムーサ島及び大小トンブ島の問題が最大の懸案となっているが、93年はこれといった進展は見られなかった。
日本との関係は、特に経済面を中心に極めて良好であり、93年においてもア首連は日本の最大原油供給国であると同時に、日本が輸出入ともに最大の貿易相手国であった。5月、ドバイ貿易・観光局派遣の貿易ミッションが訪日、11月には中東協力センター派遣の対中東投資促進ミッションがア首連を訪問する等、経済交流は上向き傾向にある。
92年1月のシャドリ大統領辞任後に成立した最高決定機関たる国家最高委員会(HCE)は任期が93年末までに限定されていたため、右任期の後の政治体制をいかなるものとするかが内政の最大課題であった。HCEは92年9月より主要政党、市民・社会団体と対話を行い、93年1月、カフィHCE議長はHCE後の統治体制を南民投票によって定める意向を表明したが、主要政党等を含む政治対話は進まず、9月頃からはイスラム原理主義過激派によるテロの対象が外国人にまで拡がるなど、治安状況が悪化するに至った。そのため、12月、憲法上の機関である高等安全保障評議会は、HCE後の政治体制を決定するため主要政党等を集めた国民会議を94年1月末に開催すること、及びそれまでの間HCEの任期を延長することを決定した。
経済面では、石油価格が低迷し経済危機が深刻化した状況において8月に誕生したマレク現政権は、貿易収支の悪化のため経済の自力解決は望み得ず、債務救済措置を含めてIMFと融資条件につき合意することを基盤に、経済再建、対外債務問題の解決を図らざるを得なくなっているが、IMFの求める条件は短期的には物価上昇、失業率増加等につながりかねないことから国民各層をいかに説得するかが注目される。
近隣諸国との関係においては、モロッコとは西サハラ問題の存在があり、リビアとも9月のカダフィ大佐がアルジェリアのイスラム原理主義者に好意的な発言を行って以後、関係は改善されていないが、テュニジアとは2月に国境が最終的に画定されるなど良好な関係にある。なお、アルジェリアは94年にアラブ・マグレブ連合の議長国を務める。国内のイスラム原理主義テロリストへの支援を行ったことを理由として、3月、アルジェリアはイランと断行し、スーダンからは大使を召喚した。
93年4月、多党制の下での初の総選挙の結果サーレハ大統領率いる国民全体会議(PGC)、保守的なイエメン改革連合(イスラーハ)及びビード副大統領を長とするイエメン社会党(YSP)の三大政党による連立内閣が発足した。しかし、その後憲法改正問題を契機として、PGCとYSPとの間に従来より存在していた相互不信に基づく不和、対立が激化し、ビード副大統領が8月末アデン(旧南イエメンの首都)に引きこもり、サーレハ大統領に対し、軍の都市部からの撤退、地方分権、治安確立などを柱とする18項目の内政改革案を受け入れなければ首都サナアに戻ることを拒否するとの立場を明確にしたため、深刻な内政危機に陥った。しかし、危機が長引くにつれ、統合と民主化プロセスを維持するため、事態を平和裡に収拾すべしとの内外からの圧力もあり、国内の全政治勢力を統合して対話委員会が結成され、またサーレハ大統領とPGC指導部が上記18項目の提案を受諾し、実施に向けて話し合いが行われており、ひとまず最悪の事態は回避される見通しである。
経済面では、湾岸危機の影響からまだ脱却しきれないイエメン経済は内政危機により高い失業率、高インフレ、イエメン通貨の下落等、ますます悪化したが、他方、石油開発は進展を見せ30万バレル/日の産油国となった。
外交面では、サウディ・アラビア及びクウェイトを除き、湾岸協力理事会(GCC)諸国との関係は改善された。また、米国及び欧州連合(EU)諸国との関係は湾岸危機の後遺症から脱却し、これら諸国はイエメンの統合と民主化プロセスに全面的な支持を与えている。
日本との関係では、11月にイリヤーニ計画・開発大臣の訪日の際、二国間で技術協力協定が調印されるなど両国間の協力関係が進展した。
(1) 内 政
ラビン首相は、92年7月の就任以来中東和平交渉を最優先課題として内外の政策を推進し、9月には、電撃的なPLOとの和解を成立させ、パレスチナ暫定自治原則宣言に署名した。これにより和平実現に対する国民の期待は爆発的に高まり、ラビン首相に対する支持率は一時急上昇した。しかし、その後宗教政党シャスの連立からの離脱、11月の統一地方選挙でのエルサレム、テル・アビブの労働党支持候補の敗北、さらに占領地パレスチナ人及びイスラエル人双方の合意反対派によるテロ、暴動などが激化し、国民の間からは政府の取組に対する批判が高まり、ラビン首相に対する支持率は年末にかけて急速に低下した。他方、和平合意に反対する最大野党リクードも有効的な代替策を示し得ず、低迷している。ラビン首相は、早期にパレスチナ暫定自治を軌道に乗せ、国民の信頼感を取り戻す必要があるが、その一方で、米国の外交的支援の下で対シリア交渉に打開を図ろうとしている。
経済面では、占領地封鎖(3月)の影響は若干あったものの、設備投資やインフラ関連投資の好調とハイテク製品等の輸出の拡大に支えられて、年率3.5%の経済成長を達成する見込みである。しかし、92年9%に下がった消費者物価指数の上昇率は、再び2桁台に戻り10.5%に達すると見込まれており、また失業率は、旧ソ連からの移民が停滞したにもかかわらず10.2%と依然として高率にあるなど不安定要因も抱えている。その中で、政府は、国内開発、特に経済・社会インフラの建設を重視するとともに、イスラエル経済の自由化・国際化に向けての諸施策を着実に実施しているが、国営企業の民営化については国営企業労働組合側の反発が強く、順調には進まなかった。
(2) 外 交
パレスチナとの暫定自治原則宣言署名の後、イスラエルとPLOは、合意実施の第一段階である、いわゆるガザ・ジェリコ先行自治について交渉を行っているが、交渉は地域の範囲、国境管理問題をめぐり難航し、合意に盛り込まれた当初のタイム・テーブルから遅れを見せている。また、ジョルダンとは実質平和条約案である議題案に合意したが、対シリア交渉の進展待ちとなっている。他方、暫定自治の合意は、シリアの態度を硬化させ、また、イスラエルが4交渉のうち、PLOとの合意実施を最優先させたこともあって、対シリア直接交渉は一時中断された。12月のクリストファー長官の中東歴訪の結果、94年1月にはジュネーヴでアサド・クリントン会談が予定されており、対シリア交渉は再開される運びとなった。
また、12月末にヴァチカンとの歴史的な和解が成立し、外交関係が樹立されたことは、イスラエルの国際社会への復帰を象徴する出来事であった。93年末現在、イスラエルはアラブ諸国を除き138か国と外交関係を結び、冷戦時代の外交的孤立からほぼ完全に脱却した。対米関係は、クリントン政権の誕生とともに一層強化され、また、欧州との関係では、1月に欧州自由貿易連合(EFTA)との間で自由貿易協定が発効する等関係強化が図られた。アジアとの間でも関係強化が図られ、93年の中国、インドに続き93年はヴィエトナム、カンボディアと外交関係を樹立したほか、回教国との関係改善にも取り組んでいる。なお、イスラエルはアラブ・ボイコットの廃止を外交上の重点事項として推進してきたが、和平プロセスが大きく進展する中で、アラブ・ボイコットは事実上形骸化しつつある。
(3) 日本との関係
92年12月のパレス外相訪日を受け、両国間の政治対話と相互理解が一層進められた。また、経済関係が進展し、12月に両国間で租税(二重課税防止)条約が発効したのを始め、経団連ミッションのイスラエル訪問(4月)、ハリッシュ貿易産業大臣の訪日(6月)など経済分野においても幅広い交流が活発に行われた。今後、中東和平の進展に伴い日本企業の一層の対イスラエル進出が期待されている。
(4) 占領地情勢
総じて占領地のパレスチナ住民は、和平交渉が念願のパレスチナ民族自決への途を開くものと歓迎しているが、他方ハマース(イスラム抵抗運動)、イスラミック・ジハード等の過激な反対派によるイスラエル市民をねらったテロ活動が激化した。これに対し、イスラエルは3月占領地の封鎖を行うなど断固たる態度で対処したため、イスラエル国内での労働に従事していた占領地労働者の3分の1が職を失った。封鎖措置は占領地経済に大きな打撃を与え、脆弱な占領地経済は更に悪化した。9月、イスラエル・PLO間の相互承認、暫定自治原則宣言合意により、占領地住民の和平への期待は大いに高まったが、その一方で、ハマース等の和平反対派は合同してイスラエル兵士及び入植者に対するテロ活動を強化し、イスラエル側も入植者がパレスチナ人報復殺害を行い、占領軍も強硬な取締まりを実施して、パレスチナ人に多数の死傷者が出るなど占領地の治安情勢は一段と悪化した。
暫定自治合意の後、対イスラエル和平交渉の主導権はPLO指導部が握ることとなったため、占領地パレスチナ人指導者層の間にアラファト議長の独裁体制に対する不満が表面化した。アラファト議長は組織の民主化を約したが、自治の実施へ向け今後同議長の指導力が問われることとなろう。
従来から、日本は国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通ずるパレスチナ難民の支援、国連開発計画(UNDP)の日本・パレスチナ開発基金による西岸及びガザ地区の経済開発支援を行ってきた。9月の合意以降、国際社会によるパレスチナ支援の機運が高まる中で、日本もそのような国際的努力に積極的に参加することとし、今後2年間に2億ドルをめどとする対パレスチナ援助を約束し、12月にはこの支援の一部として、UNRWA、世界保健機構(WHO)、日本赤十字社及びUNDP日本・パレスチナ開発基金を通ずる緊急援助の実施を決定した。
90年8月から継続している経済制裁に起因する経済状況の極度な悪化、なかんずく高インフレに対する一般庶民の不満には強いものがある。これに対し政府は農産物の買入れ価格引上げ、一部紙幣の廃止、物価統制の強化、暴利獲得商人の摘発などの諸措置を打ち出し不満の吸収に努めてきたが、目立った効果は挙がっていない。他方、北部地域への経済封鎖の強化や南部地域への軍の投入を通じ反政府勢力への弾圧を強化するなど治安維持組織や軍を通じた監視・取締まり体制は強化されている。ちなみに、イラク国民会議(INC)に代表される反政府勢力は、いまだ国内に有効な基盤を有さず、フセイン政権を脅かすには至っていない。
イラク外交の最優先課題は、経済制裁の解除にあるところ、11月にイラクは大量破壊兵器の監視・検証を規定した安保理決議715を受諾するなど若干の前向きな対応が見られたものの、いまだ関連安保理諸決議を完全には履行しておらず制裁解除の見通しは立っていない。
また、1月のクリントン米大統領就任を機にイラクは、米国への「一方的停戦」を発表した後、再三関係改善を呼びかけているが、5月に米国は「対イラク封じ込め」政策を発表するなど米国との関係は一向に改善していない。他方、トルコ、エジプト、カタルなど湾岸危機でイラクに敵対した国の一部には対イラク関係修復の兆しも看取される。
6月に実施された大統領選挙の結果再選(第2期目、任期4年)されたラフサンジャニ大統領は、国内経済の自由化を目的とする経済政策の一層の推進を図っている。3月には為替統一を実施したが、石油価格の下落とあいまってイラン通貨の対ドルレートが下落し、対外的な支払遅延問題をはじめ国内の物価上昇など困難な経済運営を余儀なくされている。他方、ハメネイ最高指導者はヴェラヤティ・ファギ(宗教法学者による統治)を体現する最高指導者として国政上の主導権を発揮しようとする姿勢を強めている。経済面では、生産量の増加にもかかわらず、油価下落に伴う原油収入の激減や政府による輸入抑制政策により、93年の輸入額は対前年比大幅な減少が見込まれ、これに伴い経済成長率も鈍化傾向にある。国内物価上昇率も92年に引き続き20%を上回る水準で推移するものと見込まれる。
外交面では、イランは近隣諸国との安定した関係構築を外交政策の重要な柱として掲げ、積極的な動きを見せてきているが、湾岸諸国との関係では、アブー・ムーサ島問題について実質的進展がなく、また、イラクとの関係でも、10月にイラン外務次官がバクダッドを訪問し、戦争捕虜問題やイラクによるイラン反体制派組織(MKO)支援について会談したが、不調に終わったと言われている。中東和平合意に対しては、パレスチナ問題に何ら実質的な解決をもたらすものではないとして、反対の立場を鮮明にしている。他方、イランは、中央アジアの旧ソ連諸国との関係強化に努めており、アルメニアとアゼルバイジャンとの紛争の仲介を行いつつアゼルバイジャン難民の支援も積極的に行っている。また、イランは宗教革命の立場から、イスラム諸国におけるイスラム的政治改革運動を支援する態度を明らかにしており、これら諸国政府との礼轢が生じている。欧米との関係では、米国クリントン新政権はイランに対し強い姿勢を維持しており関係改善の兆しは見られず、また、欧米諸国はイランの人権について批判的立場を継続している。さらに、ロシアからの潜水艦購入などのイランの兵器購入の動きやテログループ支援の疑惑などの強い懸念が国際的に高まっている。
日本との関係では、5月、日本がイランの経済復興を支援するとの見地より、ODA大綱の原則を踏まえカルーン第4ダム建設のために総額約380億円の円借款を供与した。また、イランとの政治対話を推進するとの見地から8月にはニュー・ヨークにおいて羽田外務大臣・ヴェラヤティ外相の会談が行われた。
エジプトでは81年以来ムバラク大統領の指導の下に長期政権が継続しており、93年10月に同大統領は3選を果たした。このように政治情勢は基本的に安定している一方で、92年後半よりイスラム原理主義過激派が外国人観光客をテロの対象とし始め、更にその後も政府要人の暗殺計画が続いており、国内治安の不安材料は払拭されていない。この背景には、生産の停滞、失業、インフレといった経済諸問題を克服するためにエジプト政府が進めている経済改革が十分な成果を上げていないことが挙げられる。現在、従来の統制的経済体制から自由経済体制への移行を主眼とした一連の経済改革が進行中である。
外交面では、エジプトは、中東及びアフリカを中心として、積極的な外交を展開している。中東においては、アラブ地域の大国であり、かつ、イスラエルと和平条約を結んでいる唯一のアラブ国として、イスラエルとアラブ側当事者との間を仲介しつつ、中東和平プロセスを積極的に推進している。また、域内のアラブ諸国間の諸問題や欧米諸国との間に生じる問題につきパイプ役としての役割も果たしている。他方、穏健なイスラムに基づく立場から、スーダン、イラン等に代表される急進的なイスラム原理主義運動には批判的である。アフリカとの関係では、93年よりアフリカ統一機構(OAU)の議長国として、積極的なアフリカ外交を展開している。また、エジプトは米国との関係を基軸に置くとともに、さらにEU諸国とも地中海における協力関係を構築する努力を払っている。
また、日本が中東和平プロセスを積極的に支持し、その推進に貢献していることを評価しており、93年1月にはムーサ外相が訪日するなど様々なレベルでの政治対話も活発に行われている。
オマーンは93年も、カブース国王の強力な指導力の下、国内は安定しており、また恒例の国内巡幸及び諮問議会の活動を通じ民意の吸収にも成功している。
経済面では、石油生産を80万バレル/日まで増加し、インドとの天然ガス・パイプライン計画などの対外プロジェクトを積極的に推進する動きを見せたが、油価の値崩れに伴い、財政引締め措置を採るとともに、12月には油価安定化のため94年初頭よりの5%減産を発表し、他の非石油輸出国機構諸国への働きかけも開始した。
外交面では、引き続きイラン、アラブ首長国連邦などとの善隣外交を推進したが、特に92年に国境協定を締結したイエメンとの関係が著しく発展し、10月にはカブース国王が同国を初訪問した。また、パレスチナ解放機構(PLO)、南アフリカ、スーダンからの要人来訪を受け入れるなど、GCC諸国の中で独特の全方位外交を展開した。中東和平プロセスについては、当初より前向きで、多国間協議への積極的な関与を続けるとともに、9月のイスラエルPLO合意を歓迎した。その他、オマーンは10月国連の安全保障理事会の非常任理事国に選出され、その国際的地位の向上を印象づけた。
日本との関係は経済分野を中心に引き続き良好に推移したが、日本の不況による石油需要減少に伴い、オマーン原油の対日輸出が減少し、円高により日本製品の輸入にもブレーキがかかった。
ハリーファ首長(首相)は最近健康上の理由もあリハマド皇太子(国防相)に閣議を主宰させることが多くなった。92年9月に実施された大幅な内閣改造により、首長一家の重要成員と閣僚出身者との均衡をとりつつ、かつ皇太子の意向を反映しやすい構成で日々の政経運営を行っている。立法の諮問に当たる諮問評議会は、従来よりアラブ的民主主義に寄与してきたが、最近の内外民主化の時流に沿い徐々にその役割を増大させつつある。経済面では、原油から天然ガス依存への移行期を引き続き歩んでおり、日本への液化天然ガス(LNG)輸出計画を中心に、ノースフィールド・ガス利用が国家的大事業として実行されつつある。また、外貨導入促進を主眼に法人税法を大幅に改正し、中小企業振興をねらいとする興業銀行創設を決めた。93年も引き続き、これまでの原油収入を財源とする高度福祉サービスが行き届き、国内安定の強固な基盤となっており、他の中東諸国に見られるような経済不満や過激な原理主義の動きは見られなかった。
外交面では、サウディ・アラビアとの国境紛争とバハレーンとの領土問題処理が二大外交懸案であったが、93年はほとんど進展が見られずに終わった。他方、イラクとは限定的関係を維持し、イランとは友好協力関係を進め両国外相の相互訪問を始め要人交流が相次ぎ、また限定的ながらイラク・イラン間、イラン・アラブ首長国連邦間の仲介にも努めた。また、対ジョルダン関係で一定の成果を見た。域外では、北朝鮮との外交関係樹立や、ハマド外相によるロシア、中国、日本の3国歴訪が注目された。
日本との関係では、93年には、ハマド外相とアティーヤ・エネルギー・工業相の訪日が相次ぎ、また、カタル・ガス社による日本へのLNG輸出事業への準備が進む等関係の緊密化が見られた。
92年秋の選挙で成立した国民議会は活発に活動し、特に政府の公的資金の運用問題等について種々の追及を行ってきている。これに対し政府側は本腰を入れて議会対策に取り組んでおり、両者間では基本的には協調的な関係が保たれている。
経済面では、原油生産能力は順調に回復し、現在の輸出量はイラク侵攻前の水準を上回ってはいるものの、在外資産の大幅な減少を招いていることもあり当面は厳しい財政運営を余儀なくされよう。
外交面では、湾岸戦争を経験したクウェイトにとって最大の関心事は安全保障であり、クウェイトはその一環として米、英、仏及びロシアと防衛協定を結んで合同演習等を行っており、多角的な安全保障体制の確立に努めている。現時点ではイラクが再びクウェイトに侵攻する状況にはないが、イラクとの国境では時折国境侵犯事件等が発生している。クウェイトのイラクに対する基本的懸念は、イラクがクウェイトに対しいまだに領土的野心を抱いていると見られること、国連国境委員会の画定した国境をイラクが認めないこと、さらにイラクによる捕虜の抑留である。イスラエル・PLO合意についてはパレスチナの開発のために世銀を通じ2,500万ドルの拠出を行うことを発表した。
日本との関係では、湾岸危機の際の日本の湾岸平和基金への拠出、掃海艇の派遣、そして国連安全保障理事会等の場で日本がクウェイトの立場を一貫して支持していることに対し度重ねて謝意を表明している。93年中には、首長特使、国民議会議長等4回にわたり閣僚級以上の立場を有する要人が訪日しており、日本政府及び国民に対するクウェイト側の謝意を伝えている。
また、貿易面では日本の対クウェイト輸出額は既にイラクによる侵攻前の水準を回復し、また、原油の輸入量も湾岸危機前の水準を回復した結果、日本は再びクウェイトにとって最大の原油輸出先となった。
92年に公布された政治改革3法(国家基本法、諮問評議会法、地方制度法)を受け、一連の改革措置が実施された。特に国王の諮問機関としての性格を持つ諮問評議会は、92年の議長任命に続き、93年8月に副議長を含む60名の議員が国王により任命され、12月末開会された。その他、宗教省の創設、閣僚の任期を規定する内閣法の制定が行われた。
経済面では、引き続き民間部門を中心に堅調な推移を示しているが、石油価格は6月以降低迷を続けており、93年度の石油収入は大幅に減少する見込みであることから、恒常化している財政赤字は更に拡大するものと見られ、種々歳出抑制の努力が図られている。
外交面では、中東和平について、9月のイスラエル・PLO合意を公正で包括的な和平への第一歩として歓迎し、対パレスチナ支援に94年については1億ドルの貢献を決定した。湾岸の安全保障については、12月リアドで開催されたGCC首脳会議の際、イラクに対し安保理決議の完全な履行を求めるとともに、イランに対しアラブ首長国連邦との領土問題を両国間の話し合いによって解決するよう呼びかけた。
93年年央以降の国際石油価格の下落に対しては、9月石油輸出国機構(OPEC)臨時総会を受けて加盟各国と協調して生産を抑制した。
日本との関係では、日本・GCC協議(東京)や日本・サウディ民間合同委員会(ジェッダ)が開催されたほか、文化面等を含め幅広い分野で交流が行われ、特に74年以来技術協力が続けられてきたりアド電子技術学院等が特筆される。
5月にマジャーリ内閣が成立し、56年以来初の複数政党制に基づく下院総選挙が実施された。前下院で80議席中22議席を占めたムスリム同胞団は、政党「イスラム活動戦線」を結成して11月の下院総選挙に参加したが、16議席の獲得にとどまった。反政府勢力が半数近くを占めた前下院と異なり、新下院では保守中道議員が多数を占めており、当面内政は比較的安定的に推移するものと見られる。
また、92年の経済成長を支えた建設ブームに陰りが出始めたものの経済は依然として堅調であり、93年の成長率は実質5-6%程度と予想されている。しかし、貿易収支の悪化、巨額の累積債務等、経済の構造的問題は未解決であり、今後の課題となっている。
外交面では、湾岸戦争時に悪化したサウディ・アラビア及びクウェイトとの関係修復が依然ジョルダンの課題である。また、フセイン国王は6月に米国、11月にエジプトへそれぞれ湾岸戦争後初の公式訪問を行い、両国との関係修復を印象づけた。中東和平に関しては、9月にイスラエルとの間で交渉議題に調印を行い、10月のハッサン皇太子の訪米時には、ペレス・イスラエル外相、クリントン米大統領との間で米・ジョルダン・イラク三国経済委員会の設置につき合意された。
内政は、アサド大統領の強力な指導の下、安定を保っている。また、現在アルジェリアやエジプトのようにイスラム原理主義を標傍する過激派の問題は少ない。70年以来政権の座にある同大統領にとってゴラン高原の返還を実現し、中東和平交渉を成功に導くことにより、中東地域におけるシリアの重要性を高めることが最大の目標となっている。
経済面では、徐々に統制経済から開放経済への移行を押し進めている。近年の好天による農業生産の増加に伴う輸入食糧の減少と増産に伴う石油輸出の増大により、89年より引き続き国際収支は黒字を計上しており、また実質経済成長率は、92年に引き続き、93年も9%台を維持する見通しである。91年5月に導入した新投資法の下で、民間企業の活動は活発化しつつあり、対シリア投資総額は40億ドル余に達した。これら投資が順調に実を結ぶためには、現在深刻化している電力不足の改善と外国からの投資導入のための環境整備(為替の統一等)が必要となってきている。
外交面では、シリアは、国際社会がこぞって支持を表明したイスラエル・PLO合意に対し、反対はしないが支持もしないとの不明瞭な立場をとっている。シリア政府は、同合意への反対がパレスチナ人自身の間でいかに強いかをアピールしつつ、ダマスカス在住の中東和平交渉反対パレスチナ人10派の政治的な合意反対活動には干渉しないとの立場をとる一方、ジョルダンに対してはイスラエルとの単独和平合意を急がないよう説得に努め、他のアラブ諸国に対してもイスラエルとの関係正常化の動きを牽制した。米国との関係では、シリア・トラックで早急に進展がもたらされなければ和平プロセス全体が損なわれかねない旨強調し、米国のシリア・トラックへの関与を訴え、94年1月にはアサド・クリントン両大統領会談が実現した。欧州連合(EU)との関係では、12月にEUは懸案であった第4次財政議定書の対シリア資金援助を承認した。
近隣諸国との関係では、トルコについては、水問題、トルコよりの分離を求めるクルディスタン労働党(PKK)支援問題が両国の潜在的火種となっている。イラクとは一定の事務的関係は維持している。シリアはイラクの領土保全、統一の維持を主張し、牽制している。また、イランとは戦略的友好関係を維持している。シリアにとって最も重要な隣国であるレバノンについては、依然4万人規模のシリア軍が駐留し、親シリアのレバノン政権は、シリアの影響下で国の再建、復興に当たっている。
日本との関係では、93年前半は、日本・シリア友好議員連盟一行、参議院議員団のシリア来訪による両国議員間交流が実現し、また、日本より大型の経済、武道の各ミッション及び文化使節団が相次ぎ来訪し、両国各界との交流を深めた。
92年12月の国連総会の対スーダン人権侵害非難決議採択を受け、日本を含む主要先進諸国からの相次ぐ援助停止の影響により、93年に入ると深刻なインフレと物資不足に見舞われ、国内各所で大規模な住民運動がしばしば発生するなど、国民生活の面からは極めて不安定に推移した。
しかしながら、政治面では、民族イスラム戦線(NIF)による一党独裁体制が着実に進展し、10月、バシール政権は次の目標である民主化を推進するため、革命評議会を解散し、同議長自ら大統領に就任し、行政権、立法権をそれぞれ内閣及び暫定国民議会に移管した。
今一つの重要懸案である南部内戦処理問題では、一時停戦機運が盛り上がったものの、政府とスーダン人民解放軍(SPLA)各派間との個別和平交渉はことごとく不調に終わり、その間被災民及び難民は増加の一途をたどった。
経済面では、国際的孤立の深刻化に伴い、国外からの資金流入の停止、アラブ開発基金の代表権凍結等が相次いだことに加え、輸出が全く振るわず、結局累積債務残高は160億ドルに達し、8月にはIMFがスーダンの投票権停止に踏み切るまでに事態は悪化した。
93年のスーダン外交は、人権侵害非難及びテロ支援疑惑への対応に明け暮れた。また、92年の米国国際開発援助庁(USAID)及び欧州共同体(EC)事務所職員処刑事件に関するスーダン政府の対応不備や6月にニュー・ヨークで摘発された国連ビル等爆破未遂事件の逮捕者の中にスーダン人が含まれていたこと、スーダン人外交官の関与も取りざたされるなどの経緯もあり、欧米各国は苛立ちを強めており、8月には米国はスーダンを7番目のテロ支援国家として指定するに至った。
このような状況の下で、スーダンは欧米諸国、エジプト、サウディ・アラビア等アラブ諸国との対決姿勢を鮮明にする一方で、イラク、イラン、リビア、ソマリア・アイディード派等同じく国際的に孤立状態にある諸国との関係強化に努めている。
日本は92年10月に対スーダン援助を人道的かつ緊密なものに限定するなど二国間関係は冷却化しているが、日本は対スーダン国内被災民人道援助等には資金拠出等を行っている。
政治面では、原理主義「ナフダ」運動過激派押さえ込みの奏功と順調な経済成長により、政治社会情勢は安定裡に推移した。94年3月予定の国会(一院制)及び大統領(任期5年)同時選挙をにらんだ内政展開となった中で、与党テュニジア立憲民主連合(RCD)を率いるベン・アリ大統領は、良好な治安と経済社会開発の実績を背景に、公約たる選挙法改正、人権擁護への内外世論、市民の行政への不満に配慮し、行政監査を含む一連の改革、最低賃金を含むベースアップ、農業補助政策などを実施した。
経済面では、農業は92年に次ぐ良好な作柄で生産増が予想(前年比5%)される。輸出の伸び(上半期の対前年同期+11.1%)は輸入(同+10.1%)を上回り、輸入カバー率は65%程度へと改善が見込まれる。国内総生産(GDP)は92年開始の第8次5か年計画の目標年率6%をかなり上回るものと予測され、構造調整で生じた人員整理、生活必需品値上げ等国民生活への圧迫要因を経済成長が緩和している。また、対外債務の対GDP比率は更に改善され、46%程度(前年48.8%)になるものと見込まれる。
外交面では、PLO本部を庇護し、PLOの穏健化に一役買ってきたテュニジアは、多国間協議では、10月アラブで最初の難民作業部会を開催するなど和平プロセスへの積極的姿勢が目立った。また、湾岸戦争以来冷却化していたGCCとの関係改善、EU諸国、特にフランスとの関係再構築、アフリカ統一機構(OAU)及びアラブ連盟等への働きかけの強化など穏健・協調の立場からの対応が目立った。
4月のオザル大統領の死去を境に、93年の政情は流動的な様相を呈してきた。それまで党内混乱を繰り返していた野党第1党の祖国党(ANAP)が党内保守勢力(オザル支持派)を一掃し、リベラル派と称されるユルマズ党首の下に結束し、他方、与党第1党の正道党(DYP)においては、大統領に就任したデミレル党首の後継者チルレル党首(トルコ初の女性首相)に批判的なグループが一時的に離党の動きを見せるなど党内の足並みの乱れが表面化した。当面、政局の焦点は94年3月の地方選に移行しつつあり、現連立政権は少なくとも3月までは維持されると見られるが、4月以降については、地方選の結果次第では、かなり大幅な政権の再編成も起こり得ると見られている。ただし、政権担当者の交替があるとしても、政情が著しく不安定化することはないものと考えられる。
外交面では、冷戦下のトルコの対外関係は西側陣営の一員として、西側との協力を主軸としてきたが、冷戦後の現在も、西側との緊密な関係は維持しつつ、よりグローバルな役割を志向するに至っている。旧ソ連の新独立国家(NIS)イスラム系諸国への支援を始め、中央アジア、コーカサス、バルカン、中東、北アフリカといった周辺地域を中心に世界の主要な国際問題に積極的に貢献を果たすべく積極的な外交を行っており、今後この傾向はますます鮮明になっていくものと思われる。
日本との関係では、経済分野を始めとして実体的協力関係の確立がより重視されるようになり、93年には両国政府間でイスタンブル給水計画に係る円借款の交換公文締結が実現したほか、日本よりトルコに対する民間直接投資の動きにも活性化が見られた。なお、右趨勢を促進するものとして、政府間では3月には日・トルコ投資保護協定が発効し、また、同月二重課税防止協定についても署名を了した(未発効)。
1月に諮問評議会が活動を開始し、国内民主化と雇用問題を中心とした民生の安定に取り組んだ。特に、同評議会は労働力の当国人化、そのための職業訓練、外国投資の誘致を通じた産業振興及び雇用促進、国民に対するサービス向上などの重要課題に関する活発な議論を行い、政府に対して種々の答申を提出した。国防面では、米軍との合同演習のほか、シェイク・イーサ空軍基地の供用開始など地道な国防努力が継続されている。経済面では、100%外資企業の設立認可等外国投資誘致策を推進し、また、財政健全化及び民間部門育成のために一部公共事業の民営化及び主要食料品に対する補助金廃止に着手している。さらに、バハレーンのオフショア金融(為替管理等の規制の少ない地域で、国外から資金を取り込み運用する国際金融業務)市場(OBU)総資産額は93年末で700億ドルと推定され、湾岸戦争前の水準をほぼ回復した。
外交面では、アラブの連帯再構築と湾岸の安全保障確保に外交の最重点を置き、米軍との軍事協力を引き続き推進するとともに、「半島の盾」軍を強化、湾岸独自の安全保障体制の構築を目指している。中東和平については、多国間協議に参加するとともに、9月のイスラエル・PLO合意を歓迎した。バハレーンは、自由貿易体制支持の見地からGATTに加盟することを決め、また、GCC国際商事仲裁センター誘致に成功した。
モロッコは、国王が政治上ばかりでなく、宗教上の統率者でもあり、イスラム原理主義の政治的浸透の余地も少なく、他のアラブ・イスラム諸国に比べ、政治・社会は際立って安定している。93年は立憲民主主義制度及び人権擁護の一層の充実を図ることを目的として、92年改正された憲法の下の9年振りの国政選挙(任期6年)の結果いずれの党も過半数を獲得することができず、連合政権樹立が模索されたものの不調に終わり、結局テクノクラートのみで構成する内閣が誕生した。
経済面では、モロッコは83年以降、IMF、世銀の勧告に基づき、貿易自由化、輸出振興、民間投資促進、税制改革、財政健全化を内容とする経済構造調整政策を推進している。経済成長率は年平均3.9%(84-92年平均)、財政赤字(対GDP)は82年の12.3%に対し92年は1.7%、経常赤字(対GDP)は82年の12.9%に対し92年は1.9%、物価上昇率は82年の10.5%に対し92年は4.9%へと改善されている。他方、農業生産は天候の影響を受けやすく、92年、93年は干ばつにより穀物生産が大きく落ち込んだ。これに加え、若年層を中心とする失業問題、貧富格差の問題等は、今後に残された課題と言える。
モロッコにとって最大の外交案件である西サハラ問題は、国連の和平プランに基づく住民投票が93年末までに実施されることとなっていたが、モロッコ・ポリサリオ両者の間に選挙人資格をめぐって合意が見られず、問題は先送りされる結果となった。また、国王はイスラム会議機構(OIC)のエルサレム委員会の議長を務め中東和平の達成のため独自の努力を行っているが、93年9月のイスラエル・PLO合意の成立により、従来よりイスラエルとの強いパイプを持つモロッコの立場が一段と強化される状況が生まれ、モロッコの中東和平プロセスでの役割が一層大きくなった。
日・モロッコ友好協会会長でもあるラムラニ首相の下、モロッコは、日本との関係の一層の増大に意欲を燃やしている。漁業分野において二国間漁業協定による93年6月の年次協議で、93-94年操業条件に合意した。その他、経済、技術協力も着実に進展している。
2年目に入った国連制裁に関しては、11月に在外資産の凍結、石油関連機材の禁輸等を規定する対リビア制裁強化決議883が採択され、12月より発効したが、その内容はリビア石油の大口輸入国等の利害をも考慮しており、結局、リビアにとっても石油禁輸という最悪の事態は回避された。年間100億ドルとも言われている石油による外貨収入にもかかわらず、公務員、軍人等に対する給与の遅配、厳しい外貨規制によるヤミ物資の横行等によるインフレの増大など国内経済の悪化による国民各層の不満を背景として、10月には、大がかりな反体制の動きがあり、カダフィー体制が大きく揺れたが、その直後の制裁強化決議の採択に国民の目をそらし当面の危機を脱することに成功した。
外交面では、対リビア制裁問題の仲介役を演ずるエジプト始め周辺アラブ・アフリカ諸国と92年に引き続き友好関係を維持し、空路が閉鎖されているにもかかわらず元首級の来訪が見られた。ただし、マグレブ連合(AMU)との関係では低調傾向が一段と顕著となった。制裁下にもかかわらず、EU諸国とは経済面で現実的な関係を維持し、特に、貿易面では、イタリア、独、仏、スペイン、英の5か国が輸出入とも92年同様上位を占めている。また労働力の面で、アジア諸国との関係は引き続き良好に推移している。
日・リビア関係は、86年の米国による対リビア経済制裁に加え、92年4月以来の国連制裁との関係で、一段と低調傾向を強め、92年に引き続いて一部企業のリビア撤退も見られた。
レバノンの治安状況は南レバノンを除き順調に改善しており、92年10月ハリーリ政権が誕生してからこの傾向は更に強まり、ベイルートでは住宅建設が進んでいる。復興については世銀、サウディアラビア、アラブ諸基金、イタリア等より約8億ドルの資金が集まったことにより、政府は現在総額23億ドルの3か年緊急復興プロジェクトに取り組んでいく姿勢を見せている。ヒズボラ等による南レバノンでの戦闘、レバノンに居住するパレスチナ人同士の内輪もめ、また、年末のキリスト教徒右派本部の爆破事件など消極的な要素はあるものの、中東全体が和平に向かって進んでおり、レバノン人一般の中に、内戦に後戻りすることはあり得ないとの確信が強まっている。
外交面では、レバノン国家が弱体でシリアの強い影響下にあり、和平交渉についてもシリアの意向を尊重しなければならない立場にある。他方、治安の大幅な改善に伴い、92年まではまれであった西側要人の訪問、商業使節団の来訪があり、西側との関係も強化されつつある。
日本との関係においては、復興プロジェクトの開始に伴い、経済協力を含めた外交関係の強化、邦人企業の活動活発化などのレバノン官民の期待、要請は今後高まるものと予想される。