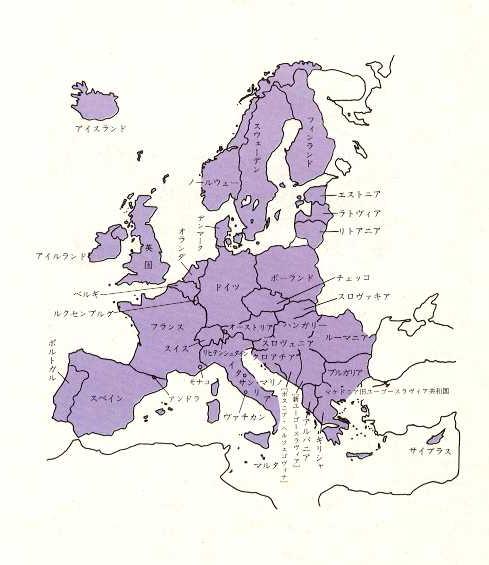
IV. 欧 州
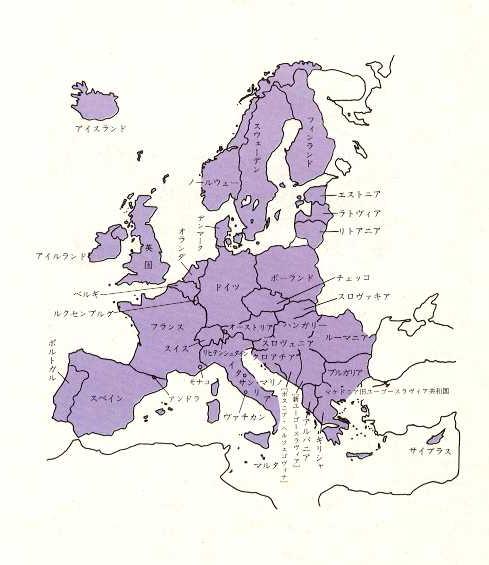
下院の総選挙(92年11月)から2か月もかかって、1月にようやく共和党と労働党の連立政権が誕生、166議席中100議席を占める安定勢力となり、2月の上院選挙でもレノルズ首相(共和党首)、スプリング外相(労働党首)の下、連立与党が勝利を収め、新政府は順調なすべり出しを見せた。
最大の課題である失業問題(失業者30万人(17%))については種々の施策にもかかわらず状況は改善せず、10月には雇用創出にねらいをおいた「国家開発6か年計画」を策定したが、その財源の欧州連合(EU)構造基金の総額をめぐりEU本部から異論も出た。他方、経済成長は約2%、貿易も順調に推移している。また、新政府は社会の法的システムの近代化に積極的に取り組んでおり、長年の懸案である条件付結婚解消(現在はいかなる場合でも離婚は出来ない)を問う国民投票を94年中に行うことが本決まりになった。
外交面では、年末のロンドンでのメイジャー・レノルズ首脳会談で北アイルランド問題に関する、英・アイルランド共同宣言が発表され和平へのプロセスの前進が期待されている。国連平和維持活動(PKO)協力にも引き続き積極的で8月末ソマリアに部隊を派遣した。ロビンソン大統領は英・豪・インドはか10回もの外国訪問を行い、アイルランド大統領としては史上初めてエリザベス英国女王と会見した。
(1) 内 政
92年に始まったイタリアの政治、経済両面にわたる広範な制度改革への動きは、93年も継続し、イタリアの政治情勢は依然として混沌とした状況にある。他方、市民生活は、不況による停滞感及び年央に発生した爆弾テロによる社会不安の増大はあったものの、政治情勢の混乱の割には安定しており、イタリア社会の奥の深さをうかがわせた。
93年は、構造汚職関連容疑が首相・閣僚経験者、与野党の書記長を含む300名以上の国会議員、及び公社・公団、政府関連企業や民間大企業の幹部多数に及び、マフィア関連疑惑の捜査も進展した。これに伴って議会の「正当性」が問われるとともに、パルティートクラシー(主要政党が談合によって国家組織を支配する体制)に代表される旧来の政党支配体制は否定され、政治改革の動きが加速した。アマート内閣の後を受けて4月に成立したチャンピ内閣は、同首相自身非国会議員であり、政党に基礎を置かないテクノクラート内閣である。また、4月に実施された国民投票の結果、上下両院の選挙法が抜本的に改正され、これまでの比例代表制から原則小選挙区多数代表制に移行したほか、政党の活動に対する国庫補助が廃止された。さらに、議員特権に係る憲法の一部改正がなされ、また地方選挙法の改正により首長は公選制となった。統一地方選挙では、左翼民主党を中心とする左翼連合や北部同盟、イタリア社会運動などの右翼政党が躍進し、政界再編・新党結成の動きが顕著となっている。
組織犯罪対策に関しては、アンドレオッティ元首相が捜査の対象とされるなど、政界、司法界等と犯罪組織の癒着にもメスが入れられつつある。一方、ローマ等主要都市で発生した爆弾テロのように、追いつめられた旧来の犯罪組織が社会不安を増大させるテロに走る傾向も見られた。そのほか、政府の情報関連部局の疑惑も捜査の対象とされており、94年には情報機関が改変される見通しである。
チャンピ内閣は年内に選挙法の改正と予算関連法案を成立させ一応所期の任務を終了したと見られており、新選挙法の下で3月頃に繰上げ総選挙が実施される見通しである。繰上げ総選挙は、構造汚職で揺れ動く政情下で、政界の刷新を求めて、抜本的改正を受けた選挙制度の下で実施されるため、その帰趨が大いに注目されている。
以上のような政治情勢の下、93年のイタリア経済は、リラ安による貿易収支の大幅な改善の一方、個人消費、設備投資といった内需の不振により、GDP成長率は政府見通しで0.4%であるものの、マイナス成長となる可能性が高い。消費者物価上昇率は、年平均で4.2%(速報)と、政府の目標値を下回り、財政赤字も、財政収支改善努力、及び92年10月以降10回にわたる公定歩合の引下げの効果により93年末で対GDP比9.7%と低下した。国営企業の民営化も実施され始めた。
他方、為替相場メカニズム(ERM)復帰は極めて困難な状況にあり、いまだ巨額の財政赤字とともに、イタリアが97年の欧州通貨連合(EMU)第3段階において第1グループとして参加する上での最大の障害となっている。
(2) 外 交
93年は、92年に引き続きイタリアの政治が内政中心になったため外交活動は依然抑制されたものとならざるを得なかったが、基本的にはEUの一員として着実な外交を展開した。94年については欧州安全保障・協力会議(CSCE)及びサミット議長国となることもあり、国際場裡におけるイニシアティヴが期待される。
外交面における最大の関心事の一つは隣国である旧ユーゴーの情勢であり、戦争犯罪及び人道に対する罪を裁判するための国際法廷設置を1月に提案したほか、西欧同盟(WEU)及び北大西洋条約機構(NATO)の枠組みの中でアドリア海禁輸監視活動や基地提供などの貢献を行った。また旧ユーゴーの安定化にとってマケドニアを国際社会に統合することは有益であるとの考えから、同国との政治対話を活発化したほか、援助面でも積極的に対応し、12月には他のEU諸国と共にマケドニアとの外交関係を樹立した。
また、イタリアは国連の平和維持活動を通じ国際の平和と安全のために積極的に貢献する姿勢をとっており、モザンビーク、ソマリアを始め世界8地域に、3,649人の人員を派遣している。
(3) 日本との関係
9月に天皇皇后両陛下が御訪問され、イタリアの朝野の歓迎を受けたことは、二国間関係の歴史において画期的なことであった。
経済関係では、第5回日伊ビジネス・グループの開催、両国間の航空路の充実(ミラノ乗り入れ)など民間ベースの交流は着実に進展したが、92年末の対日差別数量制限の撤廃はEUの共通輸入規則の策定の遅れを理由に実現していない。
貿易面では、93年に入って対日輸出は回復基調にあるが、その主因はリラ安にあり、本格的な拡大にはまだ時間がかかるものと見込まれる。文化面では6月に第6回日伊文化混合委員会がローマで開催された。
93年10月をもって即位15周年を迎えた法王は、健康上の問題は若干あるものの、全人類の平和と繁栄のための宗教者としての強い使命感を持って内外での活発な活動を続けている。特にバルト三国訪問は、法王が旧ソ連領域内に初めて足跡を記したという歴史的意義のほかに、宗教的にはロシア正教徒が多数を占め、かつ、民族的には強固なロシア人少数派が存在するラトヴィア及びエストニアにおいて、法王がキリスト教一致(エキュメニズム)の推進と少数民族の権利の理解と保護の必要を強調したことがモスクワのロシア正教会当局者に好感を与え、これまで閉ざされてきた両教会間対話の途が開かれる可能性が生じたことに大きな意味があった。
外交面では、94年には、93年末のイスラエルとの国交正常化を踏まえて法王のエルサレム訪問が実現するのではないかとの見方もある中で、中東和平の動向がヴァチカンにとって最大の関心事となろう。
日本との関係においては、9月に天皇皇后両陛下が初の欧州御訪問をされた際法王と御会見されたことは画期的であった。特に天皇と法王が世界平和の問題につき親しく語り合ったことにより、日本の平和努力の姿勢を世界に強く印象付けることができたと言えよう。今後とも総理大臣、外務大臣のヴァチカン訪問の機会をとらえて、日本の国際貢献の理念と実績を明確にしていくことは意義のあることであろう。
ウクライナは独立達成後は国家としての自己主張を強め、独立国家共同体のリーダーたらんとするロシアとの間でクリミア半島所属問題、軍分割問題、旧ソ連債権債務分割問題、燃料問題などの面で軋轢が強まった。また、ルーブル圏を離脱して以来、慢性的危機にある経済状況の中、92年11月、最高会議はクラフチュク大統領及びクチマ内閣に対し経済運営における非常大権を付与したものの、その後も経済運営はうまくいかず経済改革にも成果が見られなかった。93年6月初旬に消費者物価は3~5倍に引き上げられ、右は炭坑労働者のストを誘発することとなった。その後、8月の経済改革派のピンゼニク副首相の辞意表明を契機として、経済及び政治・社会情勢が急激に悪化した。9月末、クチマ首相の退陣及びスヴャヒルスキーの副首相任命が行われ(内閣はクラフチュク大統領の直接主導)、94年春に最高会議選挙及び大統領選挙を実施することが決定した。ウクライナ経済は1年間のインフレ率が6,000%に達するなど著しく悪化しており、インフレ及び通貨面において政府及び国立銀行はほとんどコントロールを失っているとの非難の声も起こっている。
ウクライナ国防の基本戦略は、領土の保全、国民の生命、財産及び生活権の保護を目的とし、非核・中立を目指すというものである。このため、CIS統一軍の一般目的軍への参加を拒否し、また、戦略軍についても戦略核兵器がウクライナ領土から完全に撤退されるまでの間CIS統一軍に参加するものの、戦略核兵器が撤去された後はCIS統一軍から完全に独立した共和国軍(大統領を最高司令官とし、規模は22~23万人。)の建設が計画されている。なお、93年10月に入り国防大臣、海軍司令長官が更迭されることとなった。
ロシアとの関係では種々の問題があり、93年9月にはクリミアで黒海艦隊の分割及び核兵器撤去に関連する補償問題が話し合われたが、意見の食い違いが表面化し、合意に至っていない。戦術核のロシアへの搬出は終了し、戦略核についてもSTARTI及びリスボン議定書によれば7年以内に領土内から撤去し以後は非核国家となることとなっている。これについては、11月にウクライナ最高会議は、「ウクライナとして将来的に非核国とはなるが、核安全保障、核弾頭補償、財政支援が諸外国と合意されなければSTARTIへの批准はしない。」との決定を行ったが、94年1月14日に米・露・ウクライナ三国間声明によりウクライナ側は核弾頭を解体のためにロシアに渡すことに合意した。
独立2年目を迎えたウズベキスタンでは、政治・経済とも、いまだ、諸手をあげて祝福すべき事態になく、困難を抱えての国家建設の真只中にある。中でも、最大の問題は経済である。経済困難は主として社会主義経済の破綻と、ソ連経済圏の崩壊という二つの要因によって引き起こされた。従来、ウズベキスタン経済は完全にロシア依存の体制にあり、ソ連経済圏の崩壊の影響は深刻である。
この中で、ウズベキスタンが、経済の安定を重視し、段階的市場化政策をとっていることは、十分合理性を有している。経済運営に当たっては、(あ)政治より経済の優先、(い)段階的市場化、(う)中央の指導の必要、(え)福祉の重視、(お)法の重視の5原則を採用しており、この基本路線はこの国の情勢に適しているものと見られる。長期的に見れば、金、綿花、石油・ガスなど豊かな資源を背景に発展する可能性を十分に秘めており、当面の4、5年の経済をどう運営するかが、最大の懸案である。
ウズベキスタンが、経済困難、ロシア人支配からウズベク人支配体制への移行、ウズベク系(トルコ系)とタジク系(イラン系)の対立、イスラムの復活等不安定要素を抱えながらも、旧ソ連の中で最も安定を保ってきたのは、カリモフ大統領の手腕によるものであると評価し得る。同大統領の強い指導体制は西側諸国から見て、批判の対象になるが、既に挙げたような不安定要素を十分勘案して評価すべきである。
経済困難脱却のため、ウズベキスタンは基本的にすべての国との良好な関係を望んでおり、いかなる対外関係をもてるかは相手国によるところが大きい。この中でドイツ企業の積極姿勢が注目される。
日本としては、ソ連崩壊の後2,300万人の人口が試練に直面していること、今の時期を無事乗り越えなければ、政治的、経済的大混乱の可能性があることに注目し積極姿勢を示すことが必要であり、実際この方向で外交が展開されている。現在、日本は、人的・知的交流、文化交流、経済支援、人道支援など各々の分野において、一段と関係を発展させる方向で、事業の展開と調査を行っている。
(1) オーストリア
冷戦終結後の新しい欧州の地図の中で、東西冷戦の狭間で中立を国策として自らの安全保障を図ってきたオーストリアはEU加盟の選択をめぐって1955年の独立回復以来最も大きな岐路に立っている。旧ソ連、中・東欧、旧ユーゴー等の諸国の不安定な状況は、難民の流入とあいまって、オーストリアに多大の影響を与えている。オーストリアでは、二大政権政党、経済界などを中心に、安全と繁栄を確保するには西欧諸国との統合以外に道はないとの考え方が支配的であって、政府は93年初めよりEU加盟交渉を進めており、交渉が順調に進めば、加盟の可否が94年にも国民投票に付される予定である。
オーストリア国民の間では、戦後一貫して中立を維持してきたがゆえに平和と繁栄を確保できたとの考え方が根強い。EU加盟は、伝統的な中立政策を放棄したEUの共通外交・安全保障政策への路線修正をすること、また、オーストリア経済に新しい発展機会を与えると同時に厳しい競争に身をさらすことを意味し、国民投票は国民に構造調整の痛みに耐え競争の試練に立ち向かっていく用意があるか否かを問うことにもなる。国民投票の見通しについては全く予断を許さない。今後、加盟交渉の帰趨、国内経済情勢の推移、94年の下院総選挙との関係など様々な要因が、オーストリア国民の選択に影響を及ぼそう。
外国人問題に関しては、政府は、中・東欧諸国からの難民急増が国民感情の許容限度に近づき、オーストリア社会自体の変容を招きかねない状態となったと判断し、7月に外国人滞在法を施行して、冷戦時代の寛大な難民受容政策から、外国人受入れの大幅抑制へと路線修正を行った。
外交面では、クレスティル大統領が精力的な元首外交を展開した。また6月に国連世界人権会議、10月に欧州評議会首脳会議を主催するなど、人権や少数民族問題などに焦点を当てた外交を進めた。旧ユーゴー紛争については、終始国際社会の更なる関与を強く求める姿勢を維持した。
日本との関係は、引き続き全体として友好的な雰囲気の下で推移している。ただし経済・貿易関係は、世界的不況を背景に停滞気味であった。
CSCEは、92年7月のヘルシンキ首脳会議をうけて、93年も冷戦後の民族紛争、地域紛争に対し予防外交を展開するとともに、包括的な欧州安全保障体制の構築を目指して安全保障対話を進めてきた。両者を推進するための機能強化・構造調整の一貫として、安全保障協力フォーラム、常設委員会、少数民族高等弁務官、事務総長などが相次いで設置され、この過程を通じてCSCEの各種機能のウィーンへの集中度が高まった。
日本は、93年12月のローマ外相理事会を始め、安全保障協力フォーラムや各種セミナーに参画したほか、旧ユーゴー長期ミッションに要員派遣などを行った。
4年目を迎えたルッペルス第3次内閣は、4月に最大の懸案事項であった身体障害者給付制度改正につき連立与党間の妥協が成立したことから、政局の関心は94年5月予定の第二院議員選挙とその後の組閣(連立の組合せ問題)に向けられつつある。次期選挙を契機に、ルッペルス首相からブリンクマン第二院院内総務へのキリスト教民主同盟(CDA)の党首交替を始めとする多くの著名政治家の交替、政治指導層の若返りが見込まれている。また、各党の支持率にも変化が見られ、選挙後の政局に大きな変化を予想する向きが増えている。
経済面では、安定したインフレ率、強いギルダーの維持、貿易収支黒字基調の継続、財政赤字の段階的削減などの安定的運営に努めているが、経済成長は93年0%、94年1%(予想)と低迷しており、失業率も93年8%から94年9%台に増加が予想され、失業問題の克服が最大の課題となっている。
外交面では、コーイマンス外相の下、対米関係、NATO重視の基本的外交姿勢に大きな変化はないものの、対独及び対EU関係の比重の増大が見られる。対独関係では、1月に独首相、外相のオランダ訪問、2月にオランダ・独合同軍団の設立、8月にルッペルス首相の訪独等の進展があった。
日本との関係においては、日本の従軍慰安婦問題への対応に関連し、オランダにおいても、戦争被害者団体の動きもあって、この問題がマスコミで取り上げられ、オランダ政府は同問題に関する文書記録の調査を行っている。
93年1月、審議が難航していた憲法案を最高会議が採択し、焦点であった言語問題では、カザフ語を「国の言語」とし、ロシア語は「民族間交流の言語」と位置付けられた。政府は旧ソ連経済圏の崩壊により困難な状況に陥った経済を立て直すため、経済関係官庁の再編、危機脱出政府プログラムの採択(4月)、民営化計画の一層の促進(7月)などの対策をとったが、エネルギーや日常品は不足し、高インフレとなった。
7月、ロシアにおいて92年以前に発行された旧ルーブル紙幣が流通停止となり、ロシアよりの新ルーブル紙幣供給について首脳レベルでの協議が行われたが、合意に達しなかったため、カザフスタンは11月新通貨「テンゲ」の導入に踏み切った。カザフスタンは、中央アジア諸国の中でも市場経済へ向けて最も積極的な姿勢を示しており、IMFとの間で7月に体制移行ファシリティーについて合意し、さらに、12月にはスタンバイ取極が実質的な合意に達し、これにより、国際的金融支援体制の基礎を作った。
旧ソ連時代に選出された代議員より構成されていた最高会議は、12月開会直後に突然解散を決議し、主要議題の審議を終えて、そのまま解散した(94年3月、新議会選挙が行われる予定)。
外交面では、イラン、トルコ等イスラム諸国からの積極的な接近が見られたが、カザフスタンとしてはこれらの国との経済分野での交流の拡大を望んではいるものの、イスラム原理主義の浸透には警戒感をもっている。欧米諸国からも、ミッテラン仏大統領ほか要人の訪問が行われた。また、10月には、ナザルバーエフ大統領が中国、モンゴルを公式訪問し、各々友好協力協定に署名するなど近隣諸国との関係強化にも努めた。旧ソ連諸国との関係では、新ルーブル経済圏の創設や独立国家共同体の維持に積極的な姿勢を示す一方、アラル海の環境保全やアジア信頼醸成措置の提唱などこの地域での指導権確保にも努力している。
西側諸国が強い関心を示していたカザフスタンの核不拡散条約(NPT)参加については、カザフスタン最高会議により12月、批准された。
日本との関係では、93年1月、在アルマティの日本大使館が開設された。2月の日本政府経済協力ミッションの派遣を皮切りに、日本よりの経済協力が具体化し始め、6月には官民合同経済ミッションが派遣され、双方に経済委員会(日本は民間レベル)が設立された。また、9月には文化交流政府ミッションも訪問するなど、様々な分野での交流が拡大しつつある。
内政については、与党新民主主義党(ND)が一部議員の離反により過半数割れを生じた結果、10月に総選挙が実施され、全ギリシャ社会主義運動(PASOK)が政権に返り咲いた。与党が敗れた主因は経済再建のためにとった同党の緊縮政策が国民、特に労働者層に不人気だったことにあるが、PASOKも政策上有効な代案を示しておらず、今後の動きが注目される。
経済面では、実質GDPは92年には1.5%成長したが、93年の成長率はマイナス0.2%と予想されている(EC委見通し)。国際収支は貿易赤字を観光収入やEU補助金、海外からの借入で相殺している。前ND政権は緊縮政策を続け、財政改善(92年には公債償還や利子支払を除けば黒字)、インフレ低減などを実現したが、新PASOK政権の経済政策は、アテネ市内バスの再国営化を行うなど、ばらまき政策の再現が危ぶまれ始めているが、全体像は今のところ必ずしも明らかでない。なお、発表された94年予算は緊縮志向である。
外交面では、92年に引き続きマケドニア問題が中心であった。前ND政権は比較的柔軟な姿勢をとり、暫定名称「マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国」の下でのマケドニアの国連加盟(4月)の共同提案国となった。しかし国連の調停によるギリシャ・マケドニア対話は実を結ばなかった。政権交替後PASOKはマケドニアに対して強硬姿勢で乗り出したが、EU諸国による外交関係設定の波に押されて後退気味である。
92年12月の国民投票による欧州経済領域(EEA)加盟拒否は長期的にはスイスに大きな影響を及ぼすことは否めないが、今のところスイス国民の生活に顕著な影響を与えてはいない。こうした中で欧州統合に向けた流れを絶やさぬよう連邦内閣を中心に種々の地道な準備作業が行われている。
「中立」の下に安全で高い生活レベルを維持してきたスイスも内外情勢の大きな変化への適切な対応が求められており、かかる対応の一環として連邦内閣の権限・機能強化の試み、内閣と議会及び連邦とカントン(地方)の関係見直し、軍隊改編など種々の制度の一層の改善・強化に向けた動きが見られている。
EEA加盟拒否の影響を最小限に止め、将来のEU加盟という政策カードを引き続き維持するため、93年初め連邦内閣は「経済活性化プログラム」を発表した。しかしEEA不参加の影響として93年は外国からの投資が大幅に減り、国内企業設備投資の海外逃避も増加している。経済は依然低迷し、経済成長率は93年も91年以来のマイナスが続く見通しであるが、94年にはプラスに転じると予想されている。失業率は92年平均2.5%が11月現在5.0%とスイスとしては従来になく高い水準に達し、年内に失業者数は20万人を突破、しばらくは高水準か継続する模様である。財政赤字増大(連邦政府負債総額は年間予算の1.5倍相当)も深刻で、人員削減、付加価値税の導入、各種補助金カットの方策を打ち出している。ただし欧州通貨情勢不安定の中、スイス・フランは比較的堅調で金利もほぼ順調に低下している。対外関係については、孤立化を防ぎ国際連帯・貢献への取組を通して自国の繁栄・安全を追求するとの基本方針から、EEA加盟拒否の後、EU加盟、EEA加盟国民投票再実施のオプションも残しつつ、11月EUとのバイの交渉分野を確定した。さらに、CSCEへの一層の積極的取組や他の欧州安全保障機関との関係正常化への関心表明、スイス軍の平和維持活動参加関係法の議会通過、さらに中立をめぐる議論の高まりなどが見られる。また、従来より赤十字等の民間レベルでの国際貢献は非常に活発である。
保守中道連立少数政権であるビルト内閣は、93年3月、野党新民主党の閣外協力を得られず、発足以来最大の政治危機に見舞われ、あわや国会解散かという状況にまで追いつめられたが、ビルト首相の手腕により任期2年目の国会を乗り切った。財政赤字の削減、福祉政策の見直し、公共部門の削減といった措置は、戦後最悪の国内経済の不振、過去に例を見ない失業率の増大とあいまって、最大の野党社民党に対する支持率を増大させ、また、政権内部でも、94年の総選挙をにらんで、各党とも独自のカラーの売り込みに腐心しており、ビルト首相の政局運営は容易ではない。92年秋以降クローナの変動相場制移行により、その価値は大幅に下がり、これが幸いして輸出が堅調な拡大を見せたものの、依然貯蓄率は高く、国内消費が落ち込んでおり、93年の経済成長率は依然マイナスと見積もられている。今後の景気の回復の度合いは、94年9月の総選挙の行方にも影響を及ぼそう。
外交面では、EUへの加盟交渉とCSCEの議長国という二つの大きな課題に全力が注ぎ込まれた。EU加盟交渉は2月に開始され、95年初頭の加盟実現を目指し94年3月までに交渉を妥結すべく交渉が進められているが、国内世論の動向は加盟反対にシフトしており、国民投票をいつ実施するかが、94年9月の総選挙との関係で、大きな政治問題になっている。また、92年末より11月末まで、スウェーデンはCSCEの議長国を務め、アフ・ウグラス外相は、4月に中央アジア諸国、10月にコーカサス諸国といった旧ソ連共和国を歴訪し、共通の価値観の浸透、紛争の調停の努力を行ったほか、5月には国連事務総長との間で国連・CSCE間の取極に署名するなど、スウェーデンの国際的地位を高める活動を行った。
日本との関係では、93年前半には、アフ・ウグラス外相(3月)、ビルト首相(4月、IDU議長の資格)などの要人の訪日が相次いだ。
92年がスペインの年として華やかな年であったのと対照的に、93年は不況や失業の増大、その最中の総選挙での政府与党の苦戦が色濃く影を落とした年であった。
スペイン経済は86年のEC加盟以来高成長を続けてきたが、90年代に入り減速し、93年はマイナス成長となることが確実であり(政府見込み-0.8%)、また、失業者数も増大を続け、第3四半期には350万人を超えた(失業率23%)。このような状況の中で6月に行われた総選挙の結果、ゴンサレス首相の率いる社会労働党(社労党)は第1党の座は保持したものの、82年に政権について以来、初めて過半数を割り、他方野党第1党の民衆党は大きな躍進を見せた。
経済危機の克服のため、政府は、欧州統合に向けた経済体質改善及び、労働コスト低減などによる競争力強化を推進しようとしている。9月には社会保障制度の合理化、財政赤字の削減を盛り込みつつ、経済の再活性化を目指す94年予算案を成立させ、また、雇用創出のための社会協約の締結を目指して政労使三者間の交渉を進めてきたが、交渉は11月末に決裂し、政府は三者間合意なしで野党との了解による法律制定及び政令制定により労働市場改革を実施しようとしている。
ペセタは5月に3度目の切下げを余儀なくされたが、8月に欧州為替制度の変動幅が拡大されて以降は安定し、これを受けて、金利も近年にない低水準となっており(12月の政策介入金利9.0%)、輸出の伸長も見られる。
外交面では、スペインは旧ユーゴーの国連保護隊(UNPROFOR)に1,000人規模の部隊を派遣しており、これまでに11人の犠牲者が出ているにもかかわらず、国民の広範な支持を受けてその駐留を継続していることは特筆されよう。
日本との関係では、経済面で、対日輸出の拡大、投資促進などを目的とするスペインの「対日関係推進総合計画(プランハポン)」が取りまとめられ、5月に正式に発表された。また、スペイン産レモンの対日輸出問題については、6月に両国専門家の間で合意が達成され、11月に正式に告示されたことにより、両国間の長年の懸案に解決を見た。実際の対日輸出は94年初頭から開始される予定である。
チェッコ・スロヴァキアの連邦解体・分離独立は92年6月の選挙後に急速決定を見たものであったが、「文化的離婚」実現のために、連邦解体作業とともに分離独立後の両国の協力協定の締結が急テンポで行われ、93年1月1日をもってチェッコとスロヴァキアは平和裡に分離独立した。
両国の間にはショックを緩和するために関税同盟及び支払精算勘定が設定され、また、通貨についても当初93年秋頃までは共通通貨を維持することが期待されていた。しかし、投機の動きのために2月に通貨面でも両国は分離を行わざるを得なくなった。分離独立については双方の国民が共に依然釈然としない気持ちを持っているが、不毛な議論が双方の悪感情を生む悪循環から解放され、若干の残存問題はあるものの、両国の関係は良好なものになっている。
チェッコの政治及び経済はクラウス首相の下に安定している。インフレも1月の付加価値税の導入による上昇分(8%)を除けば10%弱であり、失業率も3%である。経済成長は依然マイナスではあるものの、これもリストラに伴う折り込み済みのものであり、94年にはプラスに転じるとの観測もある。
他方、スロヴァキアは与党内の内紛で3月に少数派内閣となり、10月には連立合意が成立したものの、閣僚人事をめぐって首相と大統領が対立する局面もあった。経済の面でも失業率が12%強と高く、これに分離独立による連邦予算を通ずる予算の移転(約10億ドルとも言われる)が無くなったことが影響し、歳入欠陥が発生した。6月以降は通貨切下げを行うなど、慎重な財政運用に転換し、一応の安定を示すに至っているが、しばらくは国民にとって我慢の時期が続くと見られる。
外交面では、両国とも分離独立に伴う諸外国との国交・外交関係の樹立を円滑に処理した。両国はこれまでどおり政治・経済の双方の面で西欧への統合を実現することを目標とする外交を展開している。欧州連合(EU)との連合協定は分離独立に伴い再交渉が行われたが、EU側より人権条項など若干新たな条件が追加された。また、ロシアの動きが不透明なこともあり、特にチェッコのハヴェル大統領は、中欧は西欧と歴史、文化、価値観を共通にするとして北大西洋条約機構(NATO)加盟を熱心に推進している。
なお、日本は93年1月1日に両国を承認、引き続きチェッコとは1月29日、スロヴァキアとは2月3日に外交関係を樹立した。
1月の政権交替によって発足したラスムセン内閣は、まず、マーストリヒト条約批准に全力を挙げ、5月に行われた2度目の国民投票においてマーストリヒト条約が批准され、デンマークはEUからの脱落を免れることができた。右批准の後、ラスムセン内閣は最大の国内問題である失業問題の解決に専念し、7月、経済パッケージ関連法案(税制改革及び労働市場改革が柱)の成立に成功し、また、政権発足後初の予算案編成(94年予算)において、失業対策を主眼においた大幅な財政緩和措置を打ち出している。
外交面では、93年前半、マーストリヒト条約批准の難航や欧州景気の低迷といった暗い状況でEU議長国となったデンマークであったが、北欧などEU加盟申請4か国との正式な加盟交渉開始にこぎつけるとともに、これらの国の加盟目標を95年1月に設定することに成功した。また、国連に対する協力の面では93年においても国連軍への参加、人道的支援の実施などを積極的に行った。国連、NATO、CSCEの活動に広く参加すべきとの立場から、議会は11月、約4,500名から成る国際部隊の創設に関する法律を可決し、右は国連事務総長からも評価されている。他方、欧州新秩序構築の動きに関しては、マーストリヒト条約の安保政策協力などに留保を付している関係もあり、西欧連合には依然として加盟しておらず、受身の姿勢である。その他、1月に新設された経済協力相は活発に活動し、中・東欧、アフリカ、アジアなどと経済協力を通じた関係強化に大きな進展が見られた。
日本との関係については、両国間の貿易において87年以降デンマークの対日黒字が継続していることもあり、両国間には通商摩擦などの懸念も特になく、二国間の政治・経済関係は共に良好に推移している。
(1) 内 政
90年10月の統一から3年を経て、当時の熱気が冷めたドイツにおいては、旧東ドイツ地域の経済的な再建のみならず、旧東西ドイツ間の社会的、心理的な溝の克服をも含む真の統一(いわゆる「内的統一」)が依然として大きな課題となっているが、これに加えて92年後半からは経済の停滞が顕著となり、93年にはドイツ経済は戦後最悪とされる景気後退に陥った。また、このほかにも難民(庇護申請者)の大量流入(93年5月にようやく基本法改正が実現した)、犯罪増加、反外国人事件の発生、介護保険導入などの社会問題や、ドイツ連邦軍のNATO域外への派遣のような外交関係の問題も国民の大きな関心を集めた。他方、こうした諸問題への対応をめぐっては各党間の対立が激しく、協議が難航することが多いため、国内では「政府や既成の大政党は難局にあって実効的な対策を速やかに採っていない」との印象が広まっており、これに伴って既成政党への不信、さらには政治一般への不信の増大が指摘されている。ドイツは94年に連邦大統領選挙、連邦議会選挙、欧州議会選挙、7州の州議会選挙などが予定される「スーパー選挙年」を迎えるが、在任11年を経た「統一の宰相」、コール首相に人気と威信の低下がささやかれる一方、野党の社会民主党(SPD)はシャルピング新党首(ラインラント・プファルツ州首相)を選出して体制固めを図りつつある。同時に、前述のような既成政党不信、政治不信の風潮の中で、果たして既成政党が一連の選挙に向けてこれまでのような支持を確保し得るのが、あるいは極右、環境重視政策を唱える政党、旧東独社会主義統一党(共産党)の後継政党などが支持を拡大していくのかが、選挙後の政権の構成とも絡んで注目されている。
経済面では旧東独の再建コスト、いわゆる「統一のコスト」を担うべき旧西独の経済が92年後半以降大幅に悪化した。この結果、93年は全独の成長率はマイナス1.5%程度となり、94年も良くて1%~1.5%、悪ければ再びマイナス成長と見られている。これに伴って失業も急速に増大しつつあり、93年は370万人(前年は300万人)に、さらに94年には400万人という未曽有の水準に近づく見通しである。こうした中で、政府はコール首相の提唱により連邦、州、与野党、財界、労働界などの参加を得て、旧東独再建の財源を確保するとともに、その負担を各層が分かち合うことを目指す連帯協約と連邦緊縮計画を策定したほか、金融政策においても93年に入り7回にわたって政策金利の引下げを実施、それまでの引締め気味の基本姿勢を慎重な金融緩和へと転換して、国内及び近隣諸国の経済動向への対処に努めた。
(2) 外 交
ドイツは93年においても引き続き、独仏関係を基軸とした欧州統合の推進、NATOを中心とする良好な対米関係の維持、旧ソ連、中・東欧への支援を通じる欧州の安定の確保などを基本方針として外交を展開した。欧州統合についてはマーストリヒト条約の批准は違憲訴訟のため加盟国中最後の93年10月までずれ込んだが、コール首相は欧州統合を自身にとっての最重要課題としてとらえ、更に拡大と深化の双方を推進していく考えである。さらにドイツはアジア太平洋地域を一層重視する姿勢を表明しており、93年中にはコール首相を始め政府要人がこの地域を訪問したほか、主に経済分野を柱とする「アジア外交のコンセプト」が策定され、また、経済界でも「アジア太平洋委員会」が設立されるなどの進展が見られた。
他方、統一ドイツの国際貢献の在り方をめぐる国内の議論は93年に一層活発化し、特に連邦軍のNATO域外派遣問題については、(あ)国連の平和維持活動(PKO)のみならず平和創設活動(ドイツ国内では戦闘行動として理解されている)への参加も認めるべきか、(い)国連のみならず欧州安全保障・協力会議(CSCE)、西欧同盟(WEU)活動への参加といった問題に関し、各党間で激しい議論が続けられている。93年初めに連立与党のキリスト教民主同盟と自由民主党との間ではこの問題に関する基本法改正案につき妥協が成立したが、野党社会民主党は一部指導者の積極的発言はあるものの、国連PKOしか認めないとの立場を崩しておらず、依然として解決のめどは立っていない。この間、4月には国連安保理決議に基づくボスニア・ヘルツェゴヴィナ上空飛行禁止区域の監視のための空中警戒・管制(AWACS)活動への参加をめぐって、社会民主党のみならず連立与党の自由民主党からも、基本法改正が行われないままでの参加は違憲であるとして、憲法裁判所に違憲訴訟が提起されるという異例の事態が生じた。また、第2次国連ソマリア・オペレーション(UNOSOMII)との関係では、ドイツは93年4月に連邦軍派遣を正式決定したが、その決定に対しても社会民主党から違憲訴訟が起こされた(これらの違憲訴訟のうち差止め仮処分の訴えは共に却下されたが、本案の訴えは依然として憲法裁判所に係属している)。
このほか、国連安保理改革との関連では、ドイツは従来は常任理事国化に関心を示しつつも比較的慎重な態度をとっていたが、その後次第に積極姿勢に転じ、国連総会決議に基づいて各国が93年年央に提出することとなっていた意見書ではドイツは「常任理事国としての義務を引き受ける用意がある」ことを明言するに至った。
(3) 日本との関係
93年9月、天皇皇后両陛下がドイツを訪問されたことは日独両国間の交流において特筆すべき出来事であった。特に統一ドイツの首都ベルリンと旧東独のワイマールが御訪問先に含まれたことはドイツ統一に対する日本の祝意の最高の表現としてドイツ側から大きな喜びと感謝をもって受け止められた。デュッセルドルフ及びベルリンで開催された大規模文化事業も御訪問の意義を盛り上げ、対日理解を増進する上で効果があった。また、93年にはコール首相が2度にわたり訪日したのを始め、閣僚など要人の相互訪問も相次ぎ、また、3月には日独対話フォーラムの第1回会合が開催されるなど両国間の対話の強化に大きな成果を挙げた。経済面では日本の対独黒字による対日貿易不均衡が続いている。他方、むしろドイツ全体としては自国の国際競争力強化に努め、さらに両国間の産業協力などの協力・対話を進めていくべきであるとの議論が強い。日本からの旧東独地域投資調査団の招致、コール首相訪日の際の同首相からの「ハイテクと環境技術に関する日独協力評議会」の構想などはかかる方向での新たな取組の姿勢の現れと評価できよう。
93年は総選挙(9月)の年であり、労働党が引き続き少数与党として政府を担当することになった。70年代以来の原油開発に支えられたノールウェーの経済発展は80年代後半に至り過熱の反動として厳しい整理調整期を迎えたが、93年には製造・金融業なども総じて黒字に転じ、回復基調が定着した。マクロ経済指標で見ても欧州は良好な水準にあり、石油依存体質からの脱却の必要性が指摘されてはいるが、基本的には体質は健全である。他方、他の欧州諸国同様、麻薬・難民の流入増と治安の悪化といった問題を抱えているのも事実である。
EU加盟については93年4月から交渉を進めているが、20年前の国民投票で3.5%の僅差で否定されているだけに、政府は拙速を避け慎重に対処している。ノールウェー経済の活性化と競争力の強化のためにはEUに入らずとも、欧州経済領域(EEA)協定が発効すれば十分であるという議論もある中で、最近政府が強調しているのは、ロシアと196kmにわたり国境を接するノールウェーがその政治安保上の立場を維持していくためにはEUに入り、また、その安保上の柱である西欧同盟(WEU)にも加盟する必要があるということであり、欧州安保との関連、対ロシアの政策的考慮が強く打ち出されている。国民の反応は世論調査では加盟反対が過半数を占めており、その背景にはすべてがブラッセルの国際官僚や大国の意向で決定され、自国の独自性を失うことになりかねないとの不安と懸念がある。
ロシアとの関係では軍事安保面での多角的体制を維持強化するとともに、二国間、多国間双方の施策を通じて可能な限り実際的な関係を進める方針をとり、92年3月に両国間で署名された議定書などに沿って協力・交流関係を進めている。また93年1月バレンツ地域協力協議会を発足させ、北欧、ロシアの国境に接する地域での多角的協力の推進を図っている。
国際協力では、4月にストルテンベルグ外相が1月ユーゴー問題のジュネーヴ和平会議共同議長の任につき、また9月には後任のホルスト外相が中東和平秘密交渉の仲介者として一躍世界の注目を浴びた。
対パレスチナ支援問題では主導的イニシアティヴをとり、レバノンを始め、旧ユーゴー、ソマリア等のPKOへの協力も続けた。1人当たりの途上国援助額でもGNPの1%を超え主要先進国中第1位の実績を維持した。
日本との関係では、両国は共に海洋、海運国家並びに漁業、捕鯨国家であり、友好協力関係が築かれている。
ハンガリーは中・東欧地域における「安定の島」として89年の体制変革以降国内政治の安定が維持されているが、93年は94年春に予定されている総選挙を控え、各政党の動きが活発化した。特にインフレ、失業問題など経済状況に対する国民の不満を背景に社会党が支持率を伸ばし、11月の世論調査ではついに第1位の青年民主連盟に並んだことが注目される。しかしながら、94年の総選挙でいかなる政権が誕生するにせよ、民主体制の維持、市場経済への移行という基本方針については与野党にコンセンサスがあり変更はないであろう。また、93年12月アンタル首相の病死に伴い成立したボロッシュ新政権は、94年5月の総選挙まで短期間のこともあり、暫定的性格の政権と見られている。対外的にはNATO、EUへの正式加盟を目標とし、また、国外に約500万人のハンガリー系少数民族を抱えていることもあり、少数民族保護に積極的に取り組んでいる。
経済面では市場経済への着実な移行を進め、東欧で最大の外国投資受入れ国となっている。しかし、旧経済相互援助会議(COMECON)諸国間の貿易関係の崩壊、西欧諸国の経済不振などを背景に、国内総生産は4年連続してマイナス成長となり、93年は輸出の大幅落ち込みなどもあり困難に直面している。対外的には、92年に発効したEUとの自由貿易協定に加え、93年3月にはポーランド、チェッコ、スロヴァキアとの中欧4か国自由貿易協定が、また10月には欧州自由貿易協定(EFTA)との自由貿易協定が発効した。
94年1月の初めての直接選挙による大統領選挙に向けて政局が展開しているが、3年に及ぶ不況はようやく底を打ったとされている(93年GDP成長予想はマイナス2.5%)にもかかわらず、20%に達する失業率は微増を続けており、これが内政上の最大問題となっている。なお、経済収支が黒字に転じたことを受けて政府は12月に景気刺激策を発表した。
外交面では、将来の進路の重大な岐路ともいえるEU加盟交渉に当たって世論も複雑な様相を見せ、最近農業問題についての交渉が厳しいとの見通しが報道されるや、加盟反対が多数を占めるなど揺れ動いている。EU加盟との関連もあって安全保障議論も活発に行われているが、政府及び指導層はEU加盟を当面の課題とし、NATO加盟を含む具体的論議は時期尚早としている。また、12月のロシア議会の選挙の結果がフィンランドの対外関係に及ぼす影響が注目される。
日本との関係ではフィンランドは一貫した親日国であり、貿易不均衡(3対1で日本の輸出超過)以外に特に問題はない。10月にはアホ首相が日本を訪問した。また94年は両国修好75周年であり、各種の行事が予定されており、一層の交流強化が期待されている。
(1) 内 政
政治面では12年に及ぶ社会党長期政権への嫌気と社会党関係者による相次ぐ汚職事件の発生に加え、景気の後退、失業者の増大、移民問題の深刻化などにより、国民の社会党政権に対する支持は低下し、3月の国民議会(下院)議員選挙で社会党は歴史的敗北を喫した。新たな国民議会では全議席の8割を占めるに至った保守陣営(共和国連合(RPR)、仏民主連合(UDF)ほか)を基盤としてバラデュール内閣が成立し、ミッテラン大統領(社会党)の下、2回目のコアビタシオン(保革共存)が開始された。
バラデュール首相は、記録的に高い支持を獲得しており (4月73%、12月65%SOFRES調べ)、また、コアビタシオンも事前に予想された以上に円滑に運営され、現時点において直ちに大統領と首相との間に深刻な政治的危機が生ずるような状況は存在しない。
コアビタシオンの動向や今後の政局を占う上で重要な点としては、バラデュール内閣が失業、景気回復といった国民的に関心の高い問題について一定の成果を収めることができるか否か、エール・フランス労働争議に見られた社会的対立を沈静化できるか否か、さらには大統領候補としてバラデュール首相の支持率がシラクRPR総裁のそれを上回っていることから両者の関係がいかになるか、94年6月に予定されている欧州議会議員選挙に関しRPRとUDFが共闘を保てるか否かなどが指摘し得る。
経済面では、世界的景気後退の中で、仏の実質経済成長率も92年は1.4%、93年(政府見通し)はマイナス0.7%となっており、失業率は93年9月現在11.8%、324万2,200人となっている。貿易収支は、92年にはそれまでの赤字基調を脱し、313億フランの黒字を記録、93年に入っても黒字が続いているが、これは景気悪化に伴う輸入の減少によるところが大きい。
これに対し財政面で、マーストリヒト条約に定める通貨統合第3段階移行基準の一つである財政赤字対GDP比率が、93年は基準の3%を大きく上回る4.5%になるものと見込まれているため、仏政府は赤字削減に努めている。金融政策の面では、通貨危機に起因する93年8月の為替相場メカニズム(ERM)変動幅拡大後、景気に配慮して金利を引下げる余地が増大したものの、「強いフラン政策」を標傍する仏政府は、為替相場の下落を嫌って急速な利下げには慎重な姿勢をとり続けており、短期的な財政政策は手詰まりの様相を呈している。
なお、中長期的に仏企業の国際競争力を増し、仏経済を強化することなどを目的として93年7月国営企業の民営化法が成立し、10月以降第1号のパリ国立銀行とローヌプーランク(化学)が民営化された。
(2) 外 交
第1次コアビタシオン(86-88年)当時のような大統領府と首相府との間の外交の主導権をめぐっての確執はこれまで見られておらず、欧州さらには国際社会における指導的地位の維持・強化を図るとの仏外交の基本目標の下、このために国連安全保障理事会常任理事国の一員としての地位を活用しつつ、仏独協調に基づいた欧州統合の積極的推進を図るとの基本路線にも変化がない。仏独関係は、7月から8月にかけての通貨危機の際やUR交渉に対する対応をめぐって若干ぎくしゃくした点も見られたが、緊密かつ頻繁な調整努力を行うとともに、欧州統合の推進の重要な場面に次々と仏独共同提案を行っていくという路線も継続された。欧州統合という歴史的流れは、不可逆であるという展開に立った上で、仏は、今後とも独との緊密な協調を軸に欧州統合を推進すべく全力を尽くしていくと思われる。
防衛・安全保障分野では、仏は、66年以来NATOの軍事機構から脱退したままであるが、93年に入り旧ユーゴー問題に関し、NATO軍事委員会における発言権が認められた(ただしオブザーバーの地位はそのまま)のを機として、旧ユーゴー問題への対処に際しての国連の平和維持活動の実施に当たっては、NATOの積極的活用に賛成するなどNATOとの関係を強化する傾向が目立った。また、欧州独自の安全保障強化を促進すべく、NATOの既存の枠組みを利用しつつ西欧連合(WEU)強化を図る方向でイニシアティヴを取り、独ほかとの間で欧州軍団の設置準備を進め(95年運用開始を予定)、WEUの枠内で同軍団を使用するほか、93年1月、同軍団を一定の条件の下に、NATOの指揮下に入れることに合意した。核政策については、92年4月以降核実験を中止しており、10月の中国の核実験への対応が注目されたが、当面は、米国、ロシア、英国の動向を見極めることとし、核実験を率先して再開することはないが、再開の場合に備え万全の準備を行うとの選択を示した。また、仏は、旧ユーゴー国連平和維持活動への要員派遣において世界最大の貢献(約6千名)を行っているほか、カンボディア、旧ユーゴー、ソマリア等の地域紛争絡みの国連の平和維持活動に対し軍事要員派遣などの形で積極的に貢献している。
(3) 日本との関係
日仏間では、政治対話が進むとともに、一歩進んで政策協調に及ぶことが強く期待されるが、93年中には、7月の東京サミットにおいて一次産品に係る日仏共同提案が打ち上げられ、また、9月パリで開催されたカンボディア国際復興委員会第1回会合及び10月東京で行われたアンコール遺跡救済国際会議は、日仏両国のイニシアテイヴで開催されたものであり、さらに、ヴィエトナムに対する支援についても、日仏が主導した形で国際的な資金協力が開始されつつあるが、これらは、インドシナ地域における良好な日仏協力を端的に示すものとして注目された。
日仏経済関係は基本的に良好であり、この1年間は、仏産豚肉の輸入解禁、日本における公共事業市場への参入特例措置(MPA)の対仏適用、警察庁による仏製ヘリコプターの調達など個別の懸案事項が着々と解決され、また、仏の対日貿易赤字についても、92年の295億フランから93年の230億フランに縮小する見込みである(仏側統計)。しかしながら、日仏貿易は構造的な仏側の赤字基調にあり、仏側は、これを日本側市場・社会の閉鎖性に起因するものとして、不満を表明していることを、日本として看過しないことが肝要であろう。このような状況にあって、必要なことは、個別懸案事項を着実に解決していくとともに、日仏二国間経済関係を両国が世界において占める経済的地位にふさわしい規模に拡大していく方途を探っていくことではないかと思われる。この意味で、仏の現政権が前政権の対日輸出促進キャンペーン「ル・ジャポン・セ・ポッシブル」をそのまま引継ぎ、仏産品の対日輸出・投資促進及び日本の対仏投資誘致に力を入れていることは、大いに評価される。
文化交流面については、5月に、仏文化省、パリ市等の協力を得て、パリ日本文化祭が開催され延べ約6万人が参加した。また、パリ日本文化会館の建設問題について、大きな前進が見られ94年初めに着工、96年春に竣工の見込みとなった。同文化会館は、日本文化及び日本の政治・経済に関する情報発信基地としての役割が期待されている。
92年末に成立した現ベロフ内閣は社会党、権利と自由の運動及び新民主同盟の3党からなる連立政権であり労組とも融和政策を取りつつ社会各層の微妙なバランスの上に立って政権を運営している。93年夏以降は一部農産品の買上げ価格の引上げ、公務員給与の未払いなどの問題が発生し、財政危機にある政府の対応をめぐって3党間に調和の乱れが見られた。経済的には旧ソ連市場の喪失が主な理由で引き続き工業生産が減少したのに加えて93年夏の干ばつによる農業不振に悩んでいる。国営企業の民営化は数件にとどまったが商店などの小規模資産の所有権返還は着実に進み、また、農地の旧所有者への返還は約30%となっている。緊縮財政と高金利政策によりインフレは低下傾向にあるが(93年インフレ約65%の見通し)、生産減少はいまだ底を打っていないと見られており、また失業率も15-16%の高水準にある。
ブルガリアは、その主要外交政策目標として、対EU関係を軸にした欧米日との関係の強化、旧ユーゴーの内紛への不介入と経済制裁の厳守、黒海沿岸経済協力構想への積極的参加、旧ソ連各国との対等互恵の関係の再構築及びNATOとの連携の強化を挙げている。12月のEU理事会によるEU準加盟のための暫定取極の承認及び11月の対外民間銀行債務に係る交渉の進展(50%債務削減に原則合意)は今後の対外経済関係にとり明るいニュースであった。
日本との関係では、技術協力を中心とする民主化、経済改革支援が引き続き実施、拡充されているほか、毎年恒例の日本文化月間(秋開催)は4回目を数えブルガリア国民に高く評価されている。
(1) ベ ル ギ ー
7月末、1951年の即位以来ベルギー統合のシンボルであったボードワン国王が心臓発作で急逝し、国中が深い悲しみに包まれた。同国王の葬儀は8月上旬、天皇皇后両陛下を始めとする各国国王、王族、元首ほかの参列を得て盛大に執り行われた。後継の新国王には、王位継承順位に従い弟君のアルベール2世陛下が即位した。近年のベルギー最大の内政上の課題であった国家改革(連邦化政策)については、92年9月の政党間合意(いわゆる「サン・ミッシェル合意」)をベースとする憲法改正案が5月に可決成立、その他の関連法律の審議も7月にはすべて終了した。この結果、連邦レベルに残存していた主要権限の移管がほぼ終了するとともに、各地域・共同体議会議員の直接選挙化や条約締結権の移管により、各地域・共同体は名実共に連邦の構成主体としての実態を備えることとなった。他方、地理的にはフラマンの領域に位置しながら仏語化が進展するブラッセルの帰属問題や言語使用問題、社会保障の南北分割問題や財政赤字の分担問題等についての対立は完全に解消するに至っておらず、将来更なる連邦化を進める政策が採られる可能性も否定できない。
国家財政の再建問題も引き続き重要課題であり、3月には財政再建の方法をめぐる連立与党間の対立から一時首相が国王に内閣辞任を申し出るという事態にまで発展した。このような状況の下、デハーネ首相はベルギー独特の社会保障制度、労使協調路線などの戦後社会経済システムの抜本改革による事態打開を目指して、7月に政労使三者による「社会協約」の締結を提唱し、交渉が続いている。
経済状況は、93年の成長率が1.5%と予想を下回るものとなっているほか、失業率も8月時点で14.1%となり失業は引き続き増大している。
外交面については、93年前半はEUトロイカ・メンバーの一員として、また後半はEU議長国として、EU条約の発効、EU拡大の交渉、雇用・成長・競争力の確保という当面の問題の処理及びEUの対外政策に関しとりまとめ役を果たした。
また、ベルギーにとり、アフリカ外交、特に旧植民地であるザイール、ルワンダ、ブルンディとの関係は引き続き大きな重みを有しているが、93年にはこれら3か国中、唯一民主化安定化の道を進んでいるとされていたブルンディにもクーデターが発生し、これら3か国との関係上ベルギー外交は困難な局面に置かれた。
このほかベルギーは小国ながら積極的なPKOを展開しており、ソマリア、旧ユーゴーを中心に、12月現在約1,800名の軍隊を派遣し、世界の平和と安定の維持のために貢献している。
日本との関係においては、93年中にはボードワン国王の葬儀への参列を含め天皇皇后両陛下の2度にわたる御訪問が実現し、93年は日・ベルギー関係上歴史的な年となった。特に、葬送行進に参列されボードワン国王の柩に付き添う両陛下のお姿は、ベルギーの王室関係者、政府関係者はもちろん、広く国民に大きな感銘を与えた。
この日本の皇室とベルギー王室の格別に親密な関係は良好な日・ベルギー関係の基礎となっており、93年日・ベルギー関係は両国要人の往来などを通じ緊密の度を深めた。
経済面では、貿易不均衡はあるが大きな二国間問題として顕在化はしていない。
文化面では、「アントワープ'93」という欧州文化祭典の中で、現代日本文化を紹介する「ECジャパンフェスト」及び草の根レベルで日本の伝統芸能・地方民芸などを幅広く紹介する「ジャパン・ウィーク」がそれぞれ開催され、日本文化の紹介が活発化した。
NATOは93年から94年初にかけて、同盟内の問題、欧州における他の安全保障の枠組みとの関係及び他の欧州諸国との関係を整理し、冷戦後の欧州の安全保障新秩序の中におけるNATOの在り方を模索し、そのための作業を精力的に進めた。具体的には、北大西洋協力理事会(NACC)を通じて旧ワルシャワ条約機構(WP)諸国との間の対話と協力が進展しているほか、中・東欧諸国によるNATO加盟の要望に対して94年1月のNATOサミットで「平和のためのパートナーシップ」を採択した。この構想に基づき、NATOは、NATO非加盟の欧州諸国各々と具体的な協力作業を進めていくこととなる。今回のサミットを通じ、NATOは欧州全体を視野に入れた安全保障の枠組み構築へ向けて新たな役割を担うこととなった。
NATOの大西洋間のパートナーシップに関しては、旧ユーゴーへの対応を教訓として、米欧間の責任と負担を対等なものにしようという議論が高まっており、これは欧州の安全保障・防衛面でのアイデンティティー(ESDI)という概念の下に議論されている。その関連で、西欧同盟(WEU)との関係においても、透明性と補完性の原則を基本とするNATOとWEUの関係緊密化の動きは、93年1月にWEU事務局がロンドンからブラッセルに移転したこともあり急激に進展し、相互に緊密な調整が行われている。また、NATO新戦略に基づくNATO統合軍の改編作業は、緊急展開軍の編成作業、また、欧州軍団が主防衛軍の中の一つに加えられ、さらに主防衛軍の中に米独(司令部米国)、独米(司令部独)、独・オランダの三つの多国籍軍団が新たに編成されるなど、着実に進捗している。さらに、NATOは、国連の平和維持活動を支援するための軍事的手段を保有する唯一の国際組織であるとの認識の下、平和維持活動に対する能力向上に努めている。旧ユーゴーにおける国連の平和維持活動に対してはアドリア海における経済封鎖監視、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ上空の飛行禁止空域の監視及びボスニア・ヘルツェゴヴィナの国連保護部隊(UNPROFOR)司令部に対する司令部機能の支援などの面で支援を行っている一方、国連からの要請があれば、地上への航空攻撃を実施する態勢を整えている。さらに、和平合意が達成した後の平和維持活動に対して約5万人の平和維持兵力を派遣する用意がある旨を表明している。
また、NATOは92年7月に国連及びCSCEの平和維持活動に対する支援を決定して以来、右をNATOの新任務の一つとして積極的に推進する姿勢を明らかにしている。
NATOの中において特殊な立場を保持してきた仏とNATO間の軍事的接触の機会が旧ユーゴー等の活動において多くなったことにより、防衛計画委員会(DPC)及び軍事委員会(MC)でのNATOの協議に仏が参加していないことによる問題が指摘されるようになっている。
日本との関係では93年10月、ブラッセルでNATOとの間の第1回高級事務レベル協議が開催された。
ポーランドの民主化、市場経済化を目指す改革は、93年に新たな局面に入った。すなわち89年来、急激な金融引締め、民営化の推進を柱に、「連帯」政権が続けてきた経済政策が生んだゆがみ(失業、企業倒産、インフレ等)に対する国民の不満が、9月の議会選挙に反映され、旧共産党の流れをくむ左翼連合とポーランド農民党の連立政権、パヴラック内閣が成立した。パヴラック内閣は、早々に改革路線の継続を宣言したが、改革推進の具体的方法については、社会的不満を緩和すべく弱者救済を中心にした政策を推進するとの姿勢を明らかにした。パヴラック内閣は、改革の大枠の中で、政策的調整を行う実務型内閣と位置付けられるが、その一方で、懸案の新憲法制定にも取り組んでいる。
経済面では付加価値税導入、大衆民営化の成立等市場経済の建設、財政の健全化のための基礎作りが進展し、全雇用者の約6割が民間セクターで働くまでになった。また世界的不況にもかかわらず92年秋以来生産増大傾向を堅持し得た。一方、消費財を中心とする輸入の拡大は、為替下落とあいまって経常収支を圧迫し、新たな問題になっている。94年のパリ・クラブ公的債務削減第2段階始動を目指し国際金融機関との関係はおおむね良好に維持されているが、民間債務削減交渉は難航しており、外国からの投資も期待ほどには伸びていない。パヴラック内閣の下での弱者救済策と産業活性化・財政健全化とのバランスが重要とされている。
外交面では、「欧州への回帰」を基本的方向として確固とした欧州の安全保障の枠組みに組み込まれるべくEU、NATOへの早期加盟を目指す一方、中・東欧改革途上国との協力を深め、中欧イニシアティヴにも積極的に参画している。しかし、EU、NATOとも早期加入についてはメンバー国より時期尚早との声が強く、めどが立っていない。西欧市場参加が期待どおり進まない状況下で、経済面ではパヴラック内閣は西欧一辺倒から日本を含む東方への関心を高めている。
その一方で経済面では不況等を反映して貿易縮小、日本からの投資の伸び悩みがあり、ポーランド側の期待感は充足されていない。日本との関係においては、93年は経済協力面では青年海外協力隊の派遣が開始されたほか、文化面では、日本文化週間、文化無償協力等関係進展が目立った。
ポルトガルの政局は、今のところ8年間にわたり政権の座にある中道派の社会民主党(PSD)現シルヴァ政府の下おおむね安定した状況にあるが、12月に行われた地方選挙(全国市長、市議会議員等)では、経済の停滞と失業の増大を背景に、PSDがリスボン等主要都市で野党社会党に敗れるなど、今後、経済の状況次第では政局の流動化もあり得よう。
経済面では、世界経済、なかんずくEU経済の停滞を反映して、景気後退色が一段と鮮明になった。92年来低下傾向を続けてきたインフレは6月以降、一転して騰勢に転じ、また、失業の増大が顕在化し、93年の経済成長はマイナス成長が予想されている。政府は、EUの経済・通貨統合に向けて、金利低下、インフレ抑制、財政赤字削減等の政策を堅持する方針を明確にしているが、その目標値実現は必ずしも容易ではないと見られている。
外交面では、欧州統合への積極的関与と対EU協力を通じ経済の近代化、発展を図っており、またNATOへも積極的に関与しているが、国防・安全保障政策では英米等と共に大西洋主義を標傍しており、現在、欧州軍団には不参加の立場にある。
他方、旧植民地アフリカ諸国との関係も強化しており、米国、ロシアと共にオブザーバー国としてアンゴラ和平に協力しているほか、モザンビークにおけるPKO(連絡通信部隊)に参加している。また、国連事務総長を介入して旧植民地東チモールの問題を解決を図るためにインドネシアと交渉中である。
日本との関係では、長年の懸念であったポルトガルの対日差別割当ての撤廃が見込まれている。文化関係では、93年は日・ポルトガル友好450周年に当たり、両国で活発な交流が行われ、その一環として、日本側から4月に高円宮同妃両殿下がポルトガルを訪問され、ポルトガル側から10月にマリオ・ソアレス大統領(国賓)以下2閣僚が訪日した。
(1) 紛争の継続
旧ユーゴー(ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国)の崩壊に伴って各地で発生した武力紛争は、その解決に向けての国際的努力にもかかわらず93年中も解決を見ず、これにより被災民・避難民の発生(93年末で300万人以上)、それに伴う国際的人道援助、国連保護隊(UNPROFOR)の展開も継続した。武力紛争が続いているのは、イスラム教徒、セルビア人、クロアチア人の間で衝突が続くボスニア・ヘルツェゴヴィナ、及びクロアチア共和国側とセルビア系住民の衝突が続く同共和国クライナ地域である。
(2) ボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争
ボスニア・ヘルツェゴヴィナについては、93年1月に旧ユーゴー和平会議のヴァンス、オーエン両共同議長により、ボスニア・ヘルツェゴヴィナを、中央政府を維持しつつも基本的に民族分布に従った10の自治州からなる「自治州連合国家」とする和平案(いわゆる「ヴァンス・オーエン和平案」)が提示された。しかし、この案は、あくまで民族国家の樹立を目指そうとするセルビア人側の拒否(5月)に遭い、日の目を見ることはなかった。ヴァンス・オーエン和平案に代わって浮上したのが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナをイスラム教徒と、セルビア人、クロアチア人それぞれの3民族ミニ共和国からなる「国家連合」とする案であり、93年半ばからの和平交渉は、オーエン、ストルテンベルグ(4月にヴァンスと交代)両共伺議長の主導の下、3分割を基調として展開されることになった。上記3派は、3分割案につき、その基本的考え方には同意したものの(7月末に3派は「ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国家連合」の憲法草案に合意)、各民族共和国間の境界線の引き方をめぐり話し合いがまとまらない状況が続いている。
93年中にボスニア・ヘルツェゴヴィナ情勢を複雑化させた要因として、従来セルビア人に対し共同で対抗していたイスラム教徒とクロアチア人の間の対立が表面化し、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ中央部及び南西部で戦火を交えるようになったことが挙げられる。これによりこの紛争は文字どおり三つ巴の戦いとなったばかりでなく、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)、赤十字国際委員会(ICRC)等による人道援助活動も輸送ルートの分断により一層困難なものとなった。さらに9月には、イスラム教徒側のうち和平を指向する1派が「西ボスニア自治州」の創設を宣言する動きも見られた。
和平交渉のプロセスと並行して、国際社会からは主としてセルビア人側の譲歩を引き出すための圧力が継続的に行使された。ボスニア・ヘルツェゴヴィナ上空の飛行禁止違反への武力行使容認に関する安保理決議第816号(3月)、サラエヴォなど6都市の安全地域保護のための武力行使容認に関する安保理決議第836号(6月)、及びセルビア人側によるサラエヴォ包囲解除のためのNATOによる空爆論議の高まり(7-8月)などはその例であるが、結果的にこれらはいずれもボスニア・ヘルツェゴヴィナ問題の基本的解決に資するには至っていない。
(3) クライナ紛争
91年6月のクロアチア共和国独立宣言前後の時期から、同共和国のセルビア人居住地域(いわゆるクライナ地域)で激しい戦闘が行われたが、92年3月にUNPROFORが派遣されたことにより、一応小康状態が保たれていた。しかし、93年1月、失地回復を目指すクロアチア共和国側が国連保護地域南セクターに進攻したことにより、本格的武力衝突が再発した。国連安保理は、停戦とクロアチア側の撤退を求める決議(第802号)を行ったものの功を奏さず、その後も緊張が続いたが、7月に至り、停戦及びクロアチア軍撤退などを内容とする合意が成立した。しかしその実現には至らず、9月にはクロアチア軍は再び南セクターに新たな攻撃を行った。
UNPROFORの駐留期限が、94年3月末までとなっている(93年末現在)ことから、旧ユーゴー和平会議及びUNPROFORの仲介により、クロアチア共和国側とセルビア系住民側の和解を目指す努力が急がれている。部分的に停戦合意が行われた地域もあるものの、クロアチア共和国側とセルビア系住民の立場は基本的な隔たりを見せており、クライナ問題の根本的解決にはまだ時間がかかる見通しである。
(4) 新ユーゴーの状況
(イ) ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クライナにおける戦闘の継続は、ユーゴースラヴィア連邦共和国(セルビアとモンテネグロ。いわゆる新ユーゴー。)の状況にも直接、間接に影響を及ぼしている。新ユーゴーには92年5月から国連安保理による広範な制裁措置が課せられているが、政府の経済運営の失敗も重なり、経済的破綻、政治・社会状況の不安定化が進んでいる。特に経済情勢の悪化は著しく、1か月のインフレ率20,000%(93年11月)、失業率70%、制裁導入後1年間の工業生産の低下率44%などの数字に如実に表れている。
(ロ) こうした状況下で、ミロシェヴィッチ・セルビア大統領等の指導部は、対外政策の主眼を制裁解除に置きつつ、和平プロセスに参加してきているが、紛争地域のセルビア人勢力に対する指導部の影響力行使の試みは、現在までのところ目立った成果を挙げていない。
(ハ) また、コソヴォ、サンジャック、ヴォイヴォディナといった少数民族多数居住地域における人権状況に対しても、これが旧ユーゴー紛争の拡大につながりかねないとの観点から、国際社会の厳しい批判の目が注がれており、このことも新ユーゴーの国際的孤立状態の一因となっている。
(5) 日本との関係
日本は、旧ユーゴー各共和国のうち、スロヴェニアとクロアチアについては92年3月に国家承認し、スロヴェニアとは同年10月、クロアチアとは93年3月に外交関係を樹立した。しかし、新ユーゴー及びボスニア・ヘルツェゴヴィナについては未承認の状態が続いている。
なお、マケドニアについては、その国名問題をめぐるギリシャとの対立は解消していないものの、93年4月の同国の国連加盟承認などの動きを踏まえ、日本としても同国が独立国としての要件を具備しており、国際社会の一員となったとの認識に基づいて、12月、「マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国」の名称の下に国家承認を行った。
なお、12月に、明石康国連事務次長が旧ユーゴー問題国連事務総長特別代表兼UNPROFOR代表に任命された。
92年11月に成立したバカロイウ内閣は、経済改革の継続と社会保障の充実を柱とした政策の下、経済改革に伴う社会的コストの増大による国民の不満の高まりを背景に、与党側から経済改革のスローダウンを求める圧力がかかり、8月には小規模な内閣改造が行われた。他方、野党側からは経済改革の加速化の要求が高まっている。
経済面では、89年12月の共産主義政権の崩壊後、工業生産の下落が続いていたが、93年4月以降は対前月比で増加傾向に転じ、順調な農業生産ともあいまって、経済停滞の進行に歯止めがかかった。しかし、インフレは年率350%に達し、国営企業の民営化もほとんど進展せず、本格的な経済改革は今後の課題として残されている。
ルーマニア外交の主要課題は、欧州への復帰と西側諸国との関係の発展であるが、93年2月には欧州共同体との連合協定が署名され、10月には欧州評議会への正式加盟が実現し、さらに、11月にルーマニアに対する最恵国待遇の再付与規定を含む米国との通商協定が発効した。
日本とルーマニアとの間には大きな懸案もなく、また日本の対ルーマニア経済支援は技術協力分野を中心に進展している。
(1) 内 政
92年4月の総選挙において保守党政権の維持に成功したメイジャー首相であるが、引き続く経済情勢の低迷もあり、その政局運営には依然厳しいものがある。そうした中、内政上93年前半の最大の問題は、欧州連合条約(マーストリヒト条約)批准問題であった。当初92年中の批准が予想されていたが、デンマーク国民投票での同条約批准否決以降、英国でも欧州統合強化の意味が改めて論議された。最終的には93年7月に英国議会で批准法案が可決され翌月に批准が行われたが、これをめぐる論争は保守党の団結に影を落とす結果となり、94年前半に予定されている地方選挙、欧州議会選挙の帰趨が注目される。
93年後半になって、北アイルランド問題が再び動きを見せ始めた。12月に発表された英国・アイルランド両国首相の共同宣言はこの問題の解決に向けての新たな一歩とも見られ、今後の関係者による話し合いの行方が注目される。
93年の経済面での課題は、長期不況脱出と財政再建であった。為替相場メカニズム(ERM)からの離脱の機会を利用した金融緩和とポンド安で、インフレが悪化しない程度に景気刺激を図りつつ、3月の予算演説では、ラモント蔵相が、当面は中立的税制、将来は段階的増税との財政再建策を示した。
5月のクラーク蔵相就任以降、30年振りの低インフレと消費主導の緩い回復の両立が実現した。さらに、11月の予算演説では、財政再建を加速する一方、当面の増税を最小限にとどめて、政治的抵抗感を和らげ、今後財政引締めや外需不振の悪影響が表面化した場合には利下げで対応する余地を残すなどの配慮を示し、一応の成功を収めた。ただし、今後の財政再建の進捗はインフレや成長率の動向に相当程度依存しよう。
(2) 外 交
英国は、国連安保理常任理事国としての地位と米国との伝統的大西洋同盟関係を基軸としつつも、欧州が統合の度合いを深める中、欧州への傾斜という方向性は維持された。ただし、欧州統合に関しては、英国としては欧州連合条約批准に際しいくつかの留保を付しているように、急速な統合の深化よりも加盟国の増加による統合の拡大をより重視しているものと見られる。
そのような中で、欧州の直面する困難な問題である旧ユーゴー情勢にどこまで関与するかは英国にとっても大きな試練と言え、ヴァンス・オーエン両共同議長による和平努力を積極的に支持するとともに、EUの一員として人道支援等に貢献してきた。また、ロシア情勢については、その民主化、経済改革を支持すべくG7の一員として対露支援に積極的に貢献してきた。
97年に中国へ返還される香港についてはパッテン総督が提案した選挙に関する改革案が93年4月から11月まで英中間で交渉されたものの合意に至らず、94年の選挙関連事項など一部については英国が一方的立法化に踏み切った。中国の今後の出方が注目される。
(3) 日本との関係
93年の日英関係は、若干の貿易問題はあるものの、引き続き極めて良好に推移した。メイジャー首相も7月の東京サミット出席に続き9月には公賓として訪日し、その際英国が今後とも日本を含むアジア諸国との関係を重視していくことを明らかにし、両国間の対話の重要性が強調された。またハード外相も7月のサミットの際の訪日のほか、4月に外相協議及び対露支援外相・蔵相会合のため2度訪日した。
経済面では、英国は、日系の製造業者(200社、268工場、6万9千人雇用、93年11月英側調べ)や金融機関の活躍を、英国に雇用、技術、競争力をもたらすものとして歓迎するとともに、「プライオリティー・ジャパン」と銘打って対日輸出・投資振興策にも取り組んでいる。日本の対英投資額は90年以降減少したが、対EU投資額の40%以上のシェアは維持しており、生産力や研究開発機能拡大の追加投資は着実に進んでいる。
なお、英国における対日世論は一般的には好意的であるが、捕鯨問題、戦争捕虜問題等個別問題については一部に対日批判的な面も見られた。
(1) 内 政
(イ) 政治状況
ロシア内政にとって93年は大統領と旧議会との対立、右対立が大統領の勝利に終わった「10月騒乱事件」、その後、ロシアでの初の複数政党選挙による新議会の成立と国民投票による新憲法制定という大きな事件のあった年であった。
旧ソ連時代から引き継がれてきた旧憲法は人民代議員大会を最高国家機関と規定しつつ、大統領制を導入するなど、国家権力機関間の権力分立につき、不明確な面があるなど、多くの問題をはらんだものであった。エリツィン大統領としては、このような憲法に代わる新憲法の制定と、新議会の創設を最大の政治課題としていた。議会は92年秋以降93年にかけて反エリツィン色を強め、議会と大統領の関係は極度に悪化し、ロシア内政はいわゆる「二重権力」とよばれる状態に陥った。
このような中で行われた4月の国民投票は、大統領側の勝利に終わり、エリツィン大統領は議会との関係で国民の支持という「正統性」を獲得することになった。
エリツィン大統領は、6月憲法評議会を召集し、7月には強大な大統領権限を謳った草案を得たが、旧憲法上、新憲法制定は人民代議員大会の専管事項であり、議会側の反対により採択の見通しのつかないまま、その後も議会との膠着状態が続いた。また、この過程で連邦の将来という観点から中央と地方の権限分割問題も表面化し、大統領と議会の対立を利用して権限拡大を図ろうとする地方の動きも見られた。
このような事態を一挙に打開するため、エリツィン大統領は、9月に議会の解散と新たな連邦評議会選挙をよびかける大統領令を公布したが、ハズブラートフ最高会議議長、ルツコイ副大統領の率いる議会側はこれにあくまで抵抗し、その結果10月3日モスクワ市内に「騒乱状態」が引き起こされたため、大統領側は非常事態を宣言し、軍を導入して同4日にこれを鎮圧し、大統領と旧議会の対立は大統領側の勝利によって決着した。
その後、大統領令に従って、12月には新連邦議会選挙が行われ連邦院と国家院の上下両院からなる新議会の議員が選出された。選挙においては、「ロシアの選択」をはじめとする改革派の伸び悩みと保守勢力の共産党や極右勢力の自由民主党が躍進するなど94年に向けて予断を許さない国内情勢となったが、同時に行われた国民投票により新憲法が採択され、新しい国家体制が発足することとなった。
ロシア軍の動向については、旧ソ連軍を継承するロシア軍の創設という軍再編成作業は難航しており、234万人のロシア軍を150万人に削減するという当初の予定も、最近グラチョフ国防相が210万人まで人員を削減すると発言するなど、不徹底に終わりそうな情勢となっている。軍指導部は、93年中、再三にわたり軍は政治に関与しないと表明していたが、旧最高会議の制圧作戦(10月)に際してはエリツィン大統領の命令により小規模の部隊を投入した。11月に採択された軍事ドクトリンでは、国内紛争にも軍を投入し得ることが規定された。
(ロ) 経済状況
市場経済へ向けての経済改革の第2年目である93年において、政策面では基本的には緊急財政金融政策の維持による安定化と私有化政策の継続による構造改革を進める努力が払われたが、これは折々の政治状況などの影響を受け紆余曲折が見られた。
92年12月に就任したチェルノムイルジン首相は「93年財政経済プログラム」により緊縮政策を継続する意向を示したが、この政策に反対する最高会議との対立が続き、大幅な財政赤字を伴う産業支援、社会保護政策の拡張を主張する最高会議側と大統領、政府側との確執は秋にかけてますます先鋭化した。加えて8月には政府内でも改革政策に関する意見の不一致が表面化した。後者については9月にガイダール前首相代行が第1副首相兼経済相に就任し調整が図られたが、前者については結局、10月の騒乱事件を通じ旧議会が消滅するという形で決着した。その後、事態が正常に復する中で、政府は緊縮政策の維持を再確認したが、12月の新議会選挙前には緩和策も打ち出された。
93年の経済実績については、年間インフレ率9.4倍、工業生産16.2%減、国内総生産12%減となり、また、「隠れた失業」の増加、所得格差の増大が見られるなど依然として厳しい状況が続いた。ただし、秋以降のインフレ率の段階的低下、年後半のルーブル為替レートの安定、大幅な貿易黒字、民営企業の増加などの成果も見られた。
(2) 外 交
先進民主主義諸国との関係は、1月のブッシュ米国大統領の訪露、3月のミッテラン仏大統領訪露、4月のバンクーバーにおける米露首脳会談、7月の東京サミットの際の「G7+1」会合等を通じ、基本的には国際社会との統合を目指すとの従来の西側協調路線が維持され、日本との関係も10月のエリツィン大統領の訪日を通じた新たな段階に入った。他方で、ロシアは4月の対セルビア制裁強化安保理決議採択に棄権するなど国内世論に配慮したと考えられる立場をとった。また、8月以降高まったポーランド等の中・東欧諸国によるNATO加盟への動きについても、ロシアはNATO拡大問題に対する慎重な立場を表明した。
また、独立国家共同体(CIS)諸国及びバルト諸国との関係は、ロシア系住民の権利保護、紛争のロシア国内への拡大阻止、国境線の維持など内政、経済、さらには安全保障の観点から極めて重要であり、CIS諸国等との外交にかなりの労力を費やした。ウクライナとは、核兵器、黒海艦隊などの取扱いで首脳会談が開催されたが、93年中には両国間では完全な解決を見出せなかった。また、グルジア等コーカサス諸国内の紛争及びタジキスタン国境周辺の紛争等の解決を目指し、ロシアは外交的ないしは軍事的に関与しているが、いずれも解決のめどは立っていない。ロシアは、このような周辺地域での調停・平和維持活動を国連等の国際機関の傘の下で強化したいとの意向を有している。バルト諸国との間ではロシア軍の撤退問題が話し合われてきた。リトアニアからは8月末までにロシア軍は完全に撤退した。エストニア及びラトヴィアはロシア軍の撤退につきロシアと交渉中であるが、これら諸国内のロシア系住民の権利保護問題などをロシア側が提起しており交渉は妥結していない。
(3) 日本との関係
(イ) エリツィン大統領の訪日
92年9月のエリツィン大統領の訪日延期後、1月の日露外相会談のほか4月の対露支援G7閣僚合同会合、7月の東京サミットの際の「G7+1」会合、9月の国連総会などの機会を通じて大統領の訪日が準備され、10月にこれが実現した。
エリツィン大統領訪日の結果、政治面では、東京宣言が発せられ、日露間の最大の懸案である領土問題について、(あ)歴史的、法的事実に立脚し、(い)両国の間で合意の上作成された諸文書及び(う)法と正義の原則を基礎として解決することが確認され、このような成果は今後のロシアとの間での領土問題解決に向けての、新たに前進した土台を確立するものとなった。
経済関係については、経済宣言が署名され、ロシアの改革に向けた決意を踏まえ、両国関係全般を、均衡をとりつつ拡大するとの考えの下、貿易経済分野における両国関係の発展を目指すことが表明された。この他、非核化支援、人道・技術支援、宇宙、原子力などの広範な実務分野で16の文書が署名された。
また、エリツィン大統領は、訪日中、シベリア抑留問題を全体主義の残滓と位置付け、抑留者の遺族の墓参には全面的に協力することを約するとともに、ロシア政府・国民を代表して、この非人道的な行為に対して謝罪の意を公に表明した。
(ロ) ロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄
ソ連邦は従来より放射性廃棄物の海洋投棄を行っていたが、ロシアは92年12月その事実を認め、93年4月に関連の白書を公表するとともに低レベルの液体廃棄物については投棄停止は困難との立場を表明した。そのため日本はロシアに対し、10月のエリツィン大統領訪日時を含め種々の機会に再三放射性廃棄物の海洋投棄の即時停止を申し入れたが、ロシアは再び10月中旬に日本海において投棄を行ったため、日本は種々のレベルで強い遺憾の念を伝えるとともに投棄の即時停止を申し入れ、その後も、合同作業部会等の場を通じ協議が継続されている。
(ハ) ロシアに対する支援
ロシアの民主化、市場経済化を目指す改革努力に対する国際社会の支援は93年も続けられたが、日本は、サミット議長国として、4月に東京でG7閣僚合同会合を開催し、合計約18億ドルからなる日本としての追加的な支援策を発表するとともに、15項目からなる国際的な支援策を取りまとめた。
(ニ) その他実務関係
ソ連邦の崩壊後、日露貿易は大きく落ち込んだが、93年は92年に比べれば回復を見せ、対露輸出が対前年比39.4%増の15.0億ドル、対露輸入が同15.1%増の27.6億ドルとなった。また、92年に続き貿易収支は日本側の大幅な入超(約13億ドル)となった。ロシアに対する日本からの投資については、ロシア側資料によればロシア国内の日露合弁企業数は93年6月末時点で173件とされている。
日本の周辺水域を回遊するロシア系さけ・ますの保存及び管理についての協力等に関するいわゆる日露さけ・ます交渉は、93年3月にモスクワで開催され、日本の同年における許容漁獲量は19,819トンとなった。93年12月には94年の日露双方の200海里水域における相手国の漁獲を決めるいわゆる日露200海里交渉がモスクワで行われ、無償入漁は相互に10万トン、日本側からのみの有償入漁は1.8万トンとなった。
(1) 概 観
93年は、独立国家共同体(CIS)諸国の政治・経済的諸問題の解決のため累次にわたり首脳会議が開催され、加盟国間の協力関係の再構築を目指す動きが見られた。1月には、ウクライナ、トルクメニスタン、モルドヴァを除くCIS加盟7か国によってCIS憲章が署名され、9月にはアゼルバイジャンを加えた全加盟国によって経済的統合の深化を目的とする経済同盟創設宣言が署名された。また、12月のグルジアのCIS加盟決定により、旧ソ連邦解体の際に独立した12か国が全てCISに加盟することとなった。
他方、各国の通貨政策に関しては、7月にロシアが実施したロシア領土内での旧ルーブル還流停止措置を契機として、独自通貨導入に向かう国とルーブル圏に残留する国とが鮮明化していたが、9月ルーブル圏残留を希望する諸国(ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンの6か国)の間で、「新ルーブル圏創設協定」が署名され、各国内の使用通貨を新ルーブルで統一すること、金融・財政など諸政策の協調を図ることが規定された。しかし、右協定は実施に向けた諸条件策定に際するロシアと各国との意見対立の先鋭化により事実上崩壊し、アルメニア、カザフスタン、ウズベキスタンは独自通貨導入に踏み切った。
(2) 欧州地域
ベラルーシ共和国では、経済状況は引き続き低迷している。同国はロシアとの深い経済依存関係を有していることから、経済同盟、通貨統合などを積極的に推進している。モルドヴァ共和国では、「沿ドニエストル共和国」の独立問題等の政治面での大きな問題を抱えており、経済面でも工業生産の停滞、物価の大幅な上昇等、依然困難な状況にあるが、政府は急進的経済改革を逐次進めている(ウクライナはP75、76参照)。
(3) トランス・コーカサス地域
グルジアでは、アブハジア自治共和国・南オセチア自治州の分離運動を原因とする地域紛争やシェヴァルナッゼ国会議長派とガムサフルディア前大統領派との武力衝突が続いたが、現在は小康状態にある。経済面でも生産急減、物価急騰などが生じている。アルメニアでは、テル・ペトロシャン大統領は基本的に国内を把握しているが、ナゴルノ・カラバフ地域の帰属をめぐる民族紛争に関連した深刻なエネルギーの不足や市場経済への移行に伴う物価急騰などの経済的混乱が続いている。アゼルバイジャンでは、6月にアリエフ・ナヒチェヴァン自治共和国最高会議議長が権力を掌握したが、ナゴルノ・カラバフ紛争、施設老朽化による原油生産減少などから、生産減少、物価高騰、難民増加などの諸問題に直面している。
(4) 中央アジア地域
キルギス共和国は、リベラルなアカーエフ大統領を中心に自国通貨導入、価格の全面的自由化など、抜本的な市場化を進めると同時に西側諸国の法体系を参考とする新共和国憲法の制定を行い、法治国家としての体制を整えつつある。トルクメニスタンは、天然ガス、綿化などの豊富な資源輸出から得た外貨収入が裏打ちし、経済情勢は比較的安定しているが、一方改革のテンポは緩慢である。タジキスタン共和国では、政府と野党勢力間の武装対立が長期化した結果、経済は南部地域を中心に壊滅的なダメージを受けており、改革推進の大きな障害となっている(ウズベキスタンはP76、77、カザフスタンはP79~81参照)。