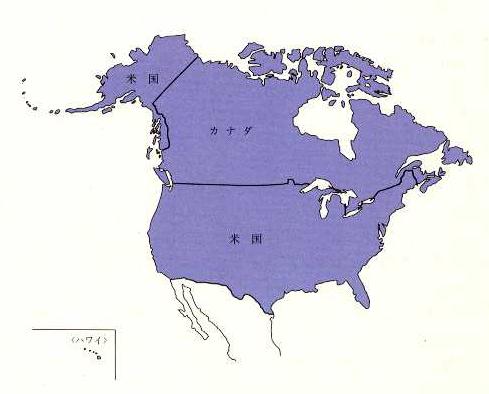
II. 北 米
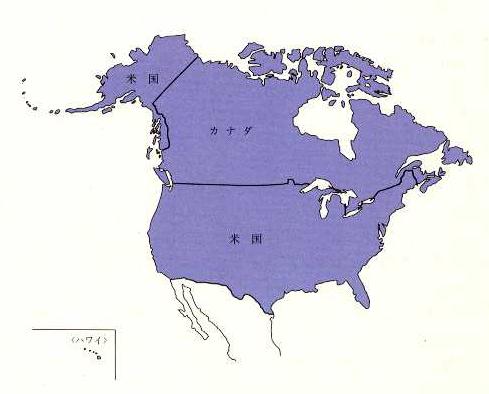
第1分冊P19~25、P35~37参照。
(1) 内 政
マルルーニー首相は93年2月辞意を表明、6月の進歩保守党党首選挙を経て、キャンベル国防相が新首相に就任した。その後、10月の総選挙(小選挙区制)において、景気の低迷と高失業率に対する国民の懸念を背景に進歩保守党は議席数を下院解散前の152からわずか2に激減するという歴史的大敗を喫し、雇用創出を訴える自由党が圧勝、連邦下院で安定多数を獲得し、9年振りに政権に就くこととなった。またケベック州民の利益を訴えるブロック・ケベコワ、及び西部を中心とする改革党といった地域色の濃い政党が躍進した。今後はクレティエン首相率いる自由党新政権が、雇用創出や財政再建等の選挙公約をいかに実現するか、さらには既成政党に批判的な2新党の発言権増大という新状況の中でいかに政局運営をするかが注目される。
経済面では、93年のカナダ経済は堅調な輸出、インフレ抑制が認められたが、民間企業・消費者のコンフィデンス回復が弱く内需が伸び悩み、弱い景気回復過程にあり、失業率も年間を通じ11%台の高水準で推移している。11月に新政権が発表した経済見通しは93年実質2.5%と、前政権時での見通しを下方修正した。
新政権は選挙公約で雇用創出を最優先課題とし、成長と財政赤字削減を同時達成するとしているが、既に11月末には93年度財政赤字見通しの大幅悪化を明らかにし(当初見通し326億加ドルを440-460億加ドルに修正)、今後の道程の厳しさを国民、州政府に訴えている。加えて、連邦財・サービス税廃止による新税制の検討、州間貿易障壁撤廃の実現など、新政権が取組を公約した経済課題は山積しているが、既に財政赤字幅の拡大などを踏まえ、失業保険料の引上げを打ち出している。
(2) 外 交
自由党新政権は、対米依存度を低下し、マルチ外交を重視するとの自主外交を標傍しているが、米加関係が隣国同士の緊密かつ日常的なものであり、米国がカナダの対外貿易の約7割を占める最大貿易相手国であるという実態があるので、両国関係に本質的変化が起きる可能性は低い。
カナダは従来から、サミット、経済協力開発機構(OECD)、欧州安全保障・協力会議(CSCE)、米州機構(OAS)を始めとする様々な国際機関や多国間協議の場で活躍し、国連平和維持活動(PKO)でも指導的役割を果たしている。こうした中、クレティエン政権においては、マルチ・フォーラム重視、国際社会へのコミットメント重視が一層強調されることが見込まれ、特に国連改革、PKO強化等が自由党政策綱領に盛り込まれており、今後の具体的動きが注目される。
さらに、アジア太平洋地域については、米国への貿易依存度低下、カナダの新市場確保の観点からも、新政権の下で従来以上に関係強化を図っていくものと見られる。
北米自由貿易協定(NAFTA)については、自由党は選挙戦中はNAFTA再交渉の立場を表明していたが、その後12月に至り、米国、メキシコとの協議で補助金・反ダンピング定義明確化等のNAFTA実施面での改善が確保できたとの判断の下、NAFTAの94年1月発効のための手続(実施法の公布)を進める旨明らかにした。また、自由党新政権はGATT体制の下での自由貿易推進の立場から、酪農品関税化に伴う内政上の困難にもかかわらず、ウルグァイ・ラウンド終結のため包括関税化受入れを決定した。
(3) 日本との関係
日加関係はこれまで順調に推移しており、両国間経済関係も全体として良好である。また近年日加両国は、G7や国連、アジア太平洋地域でのパートナーとしての協力も進めてきている。
93年は、7月の第3回東京サミットの際に日加首脳会談、外相会談が、11月のAPEC非公式首脳会議の機会に細川総理大臣・クレティエン首相会談が行われた。
92年12月に日加両国首脳に提出された「日加フォーラム2000」提言は政治、経済、国際協力、相互理解の分野で長期的視野に基づく両国のパートナーシップ強化を提唱しており、自由党新政権も同フォーラム諸提言の実現に向け積極的に取り組む姿勢を示している。