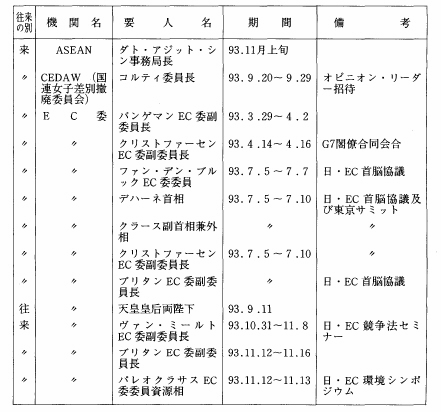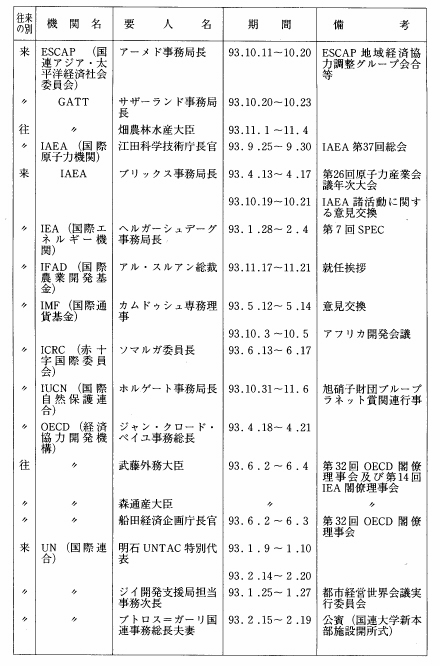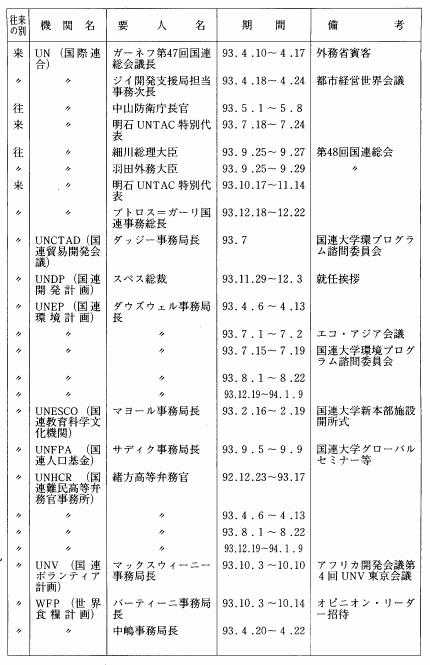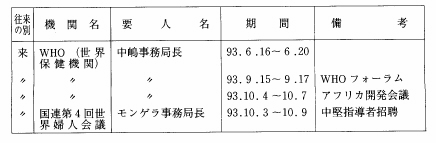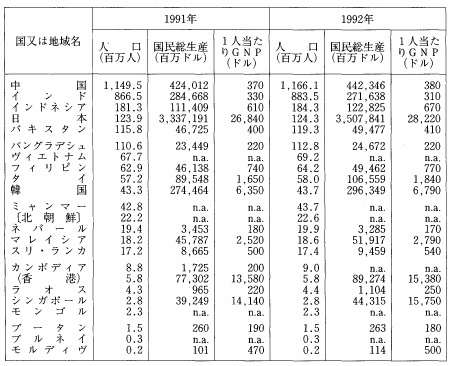
II 付 表
1. 一般的指標
(1) 各国の人口,国民総生産(GNP)及び1人当たりGNPの国際比較
(イ) アジア
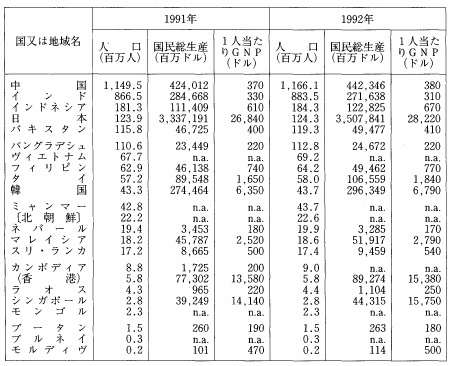
(ロ) 太洋州
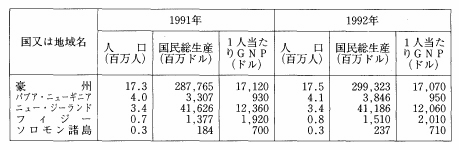
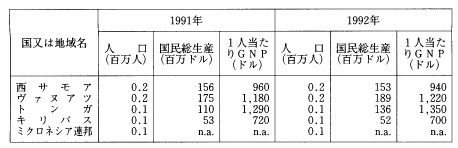
(ハ) 北米・中南米
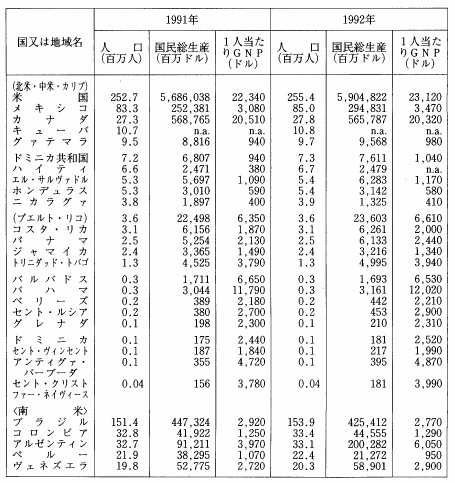
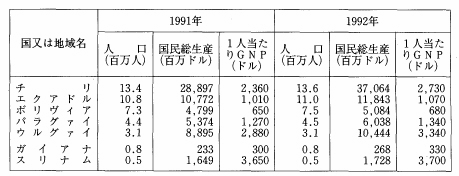
(ニ) 欧州
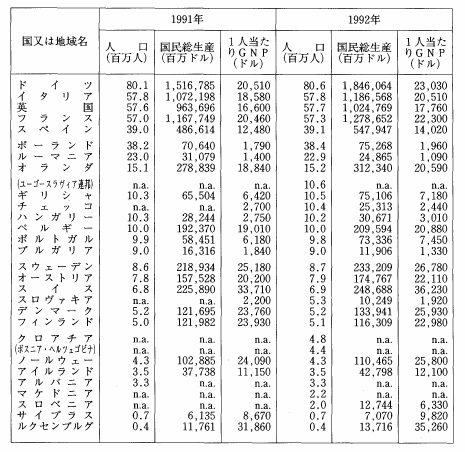
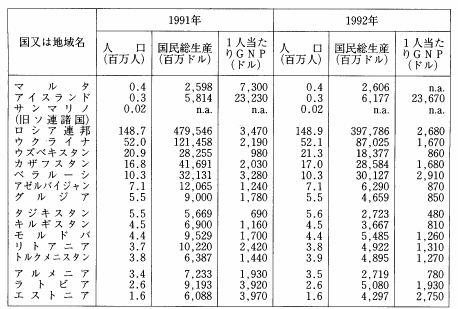
(注) ドイツの91年の国民総生産は西独地域のみ。
(ホ) 中近東
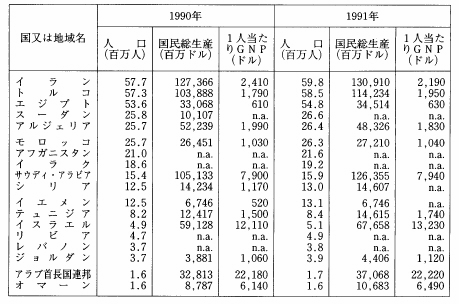
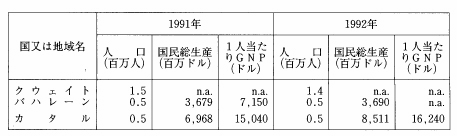
(注) ジョルダンの国民総生産と1人当たりGNPは東岸のみ。
(ヘ) アフリカ
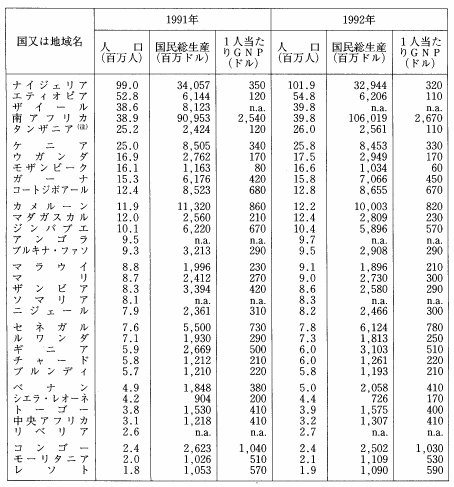
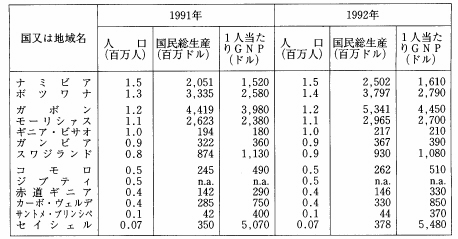
| (注) | タンザニアの国民総生産及び1人当たりGNPは本土のみ。 |
| (出所) | 1991年の人口は「世銀開発報告1993」より。 |
| 1991年の国民総生産の数値は,世銀「ATLAS 25th Anniversary Edition」より。 | |
| 1991年の1人当たりGNP,1992年の全数値は,世銀「ATLAS 1994」より。 |
(2) 主要国の経済指標
(イ) 貿易
(a) 地域別貿易構成(1992年)

| (注1) | 中国を除く | |
| (注2) | 北アフリカ諸国をアフリカに含める | |
| (注3) | NIS,ユーゴスラヴィアを含む | |
| ・四捨五入の関係で構成比の合計は必ずしも100%にならないことがある | ||
| (出所) | OECD「Monthly Statistics of Foreign Trade」 | |
(b) 貿易額の推移
(i) 輸出
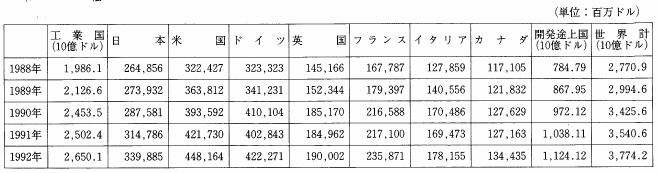
(出所) IMF「International Financial Statistics 94年2月号」
(ii) 輸入
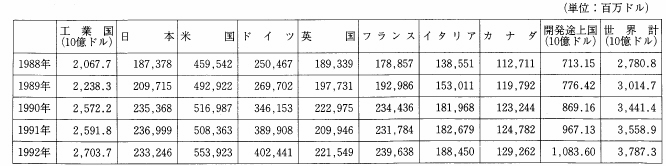
(出所) 同上 注:ドイツは90年7月以降旧東独地域の数値を含む
(ロ) 国際収支の推移
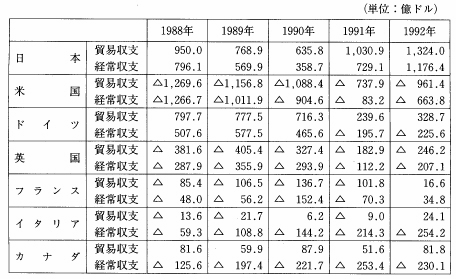
(出所) IMF「International Financial Statistics」
(注) ドイツは90年7月以降旧東独地域の数値を含む
(ハ) 消費者物価上昇率及び失業動向
(a) 消費者物価上昇率
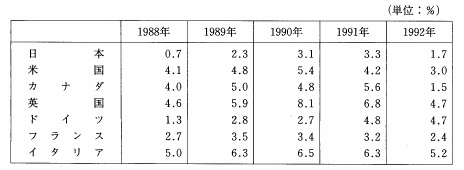
(出所) IMF 「World Economic Outlook」
(注) ドイツは91年以降,統一ドイツ
(b) 失業率
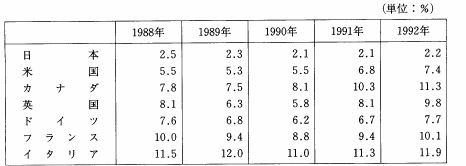
(出所) IMF 「World Economic Outlook」
(注) ドイツは91年以降,統一ドイツ
(ニ) 世界の地域別実質GDP成長率の推移
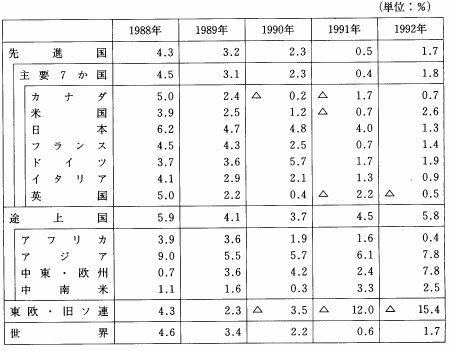
(出所) IMF 「World Economic Outlook」
(注) ドイツは91年以降,統一ドイツ。
2. 日本の貿易
(1) 国際収支の推移
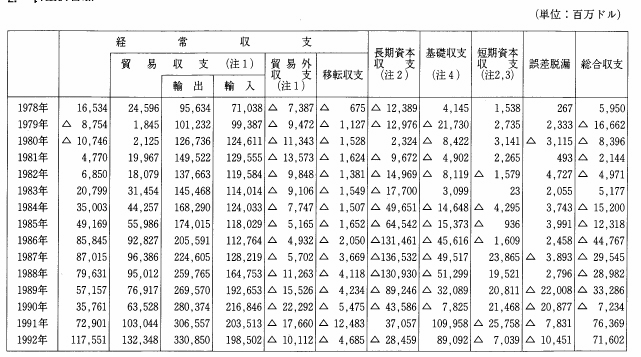
| (注1) | 委託加工費,仲介貿易(ネット受取額)は,1979年6月まで貿易収支へ,同年7月以降貿易外収支へそれぞれ計上。 | |
| (注2) | △は資本の流出(資産の増加および負債の減少)を示す。 | |
| (注3) | 金融勘定に属するものを除く。 | |
| (注4) | 現先取引は,短期資本収支へ計上。 | |
| (出所) | 日本銀行「国際収支統計月報」 |
(2) 主要貿易相手先
(イ) 輸出(1992年)
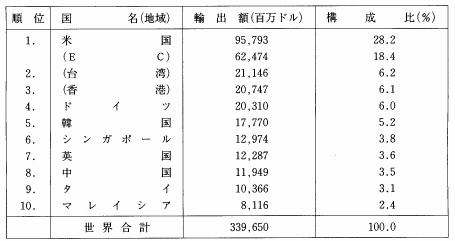
(出所) 通関統計
(ロ) 輸入(1992年)
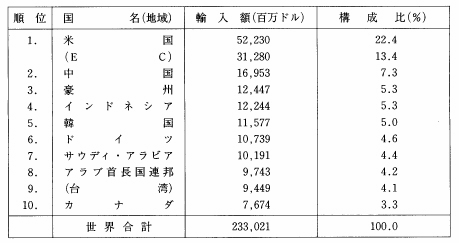
(出所) 通関統計
(3) 地域別貿易
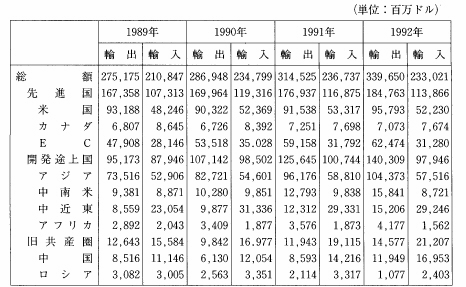
(出所) 通関統計
(注) ロシアの1990年以前は旧ソ連の計数
1. 日本の経済協力
(1) 開発途上国への資金の流れ
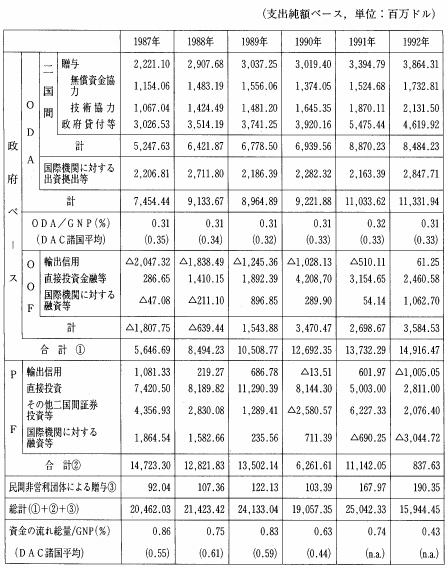
(注1) 国民総生産の額は1991年は確報値、92年は速報値を使用。
(注2) 東欧向けを含む。
(2) 国・地域別援助形態別配分(1992年)
(イ) 地域別
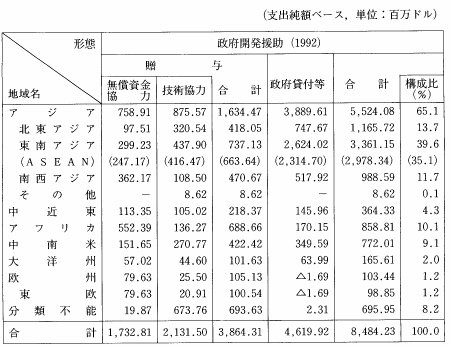
| (注)1. | 四捨五入の関係上,合計が一致しないことがある。また,「一」は実績なし,「△」は回収超過。 | |
| 2. | 無償の分類不能は昭憲皇太后基金及び赤十字国際委員会等への拠出。技協の分類不能は各地域にまたがる調査団の派遣,留学生世話団体への補助金等の他,行政経費,開発啓発費を含む。 |
(ロ) アジア
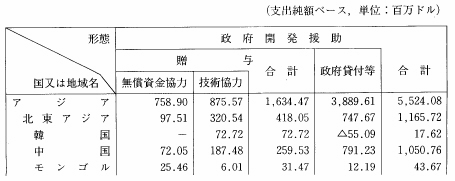
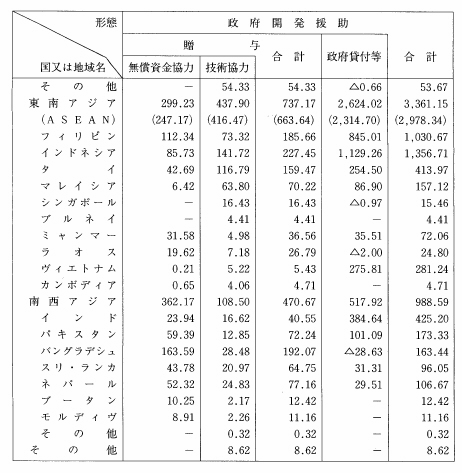
(ハ) 中近東
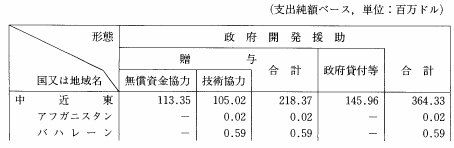
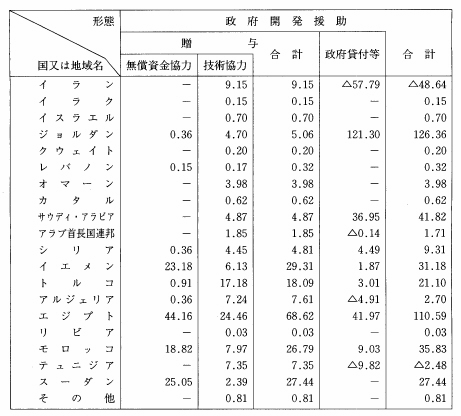
(ニ) アフリカ
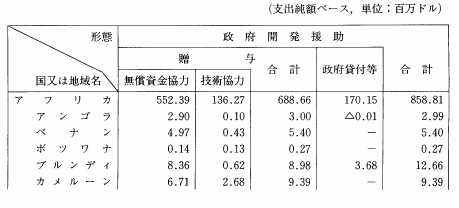
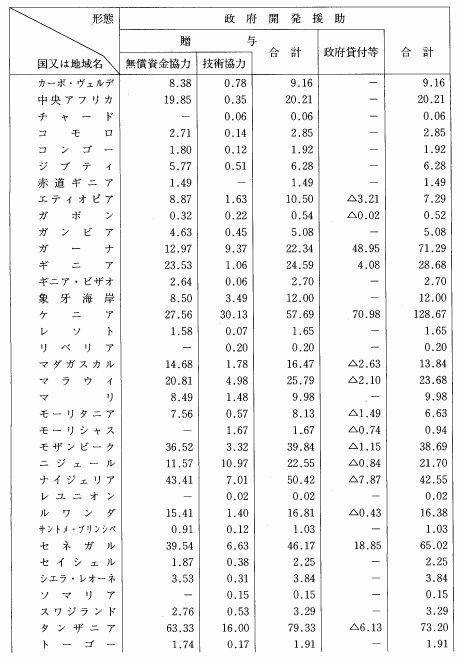
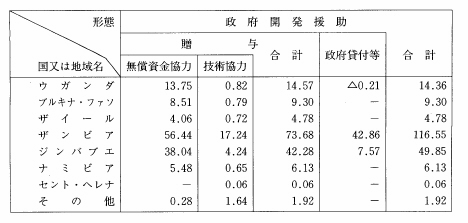
(ホ) 中南米
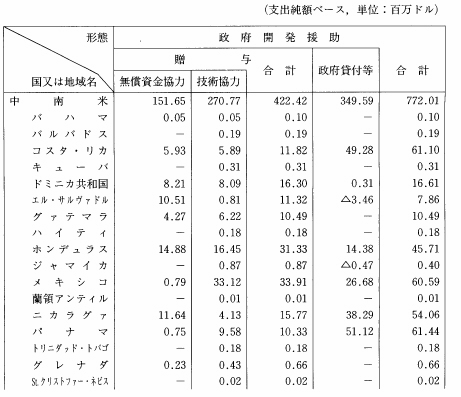
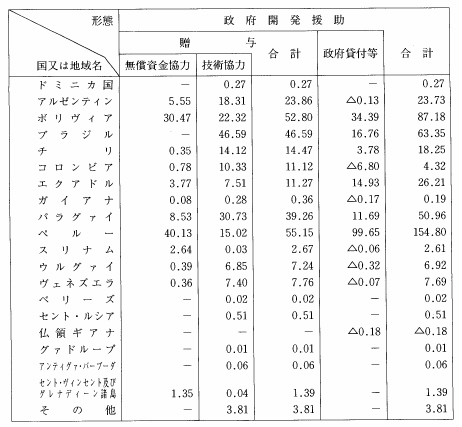
(ヘ) 太洋州
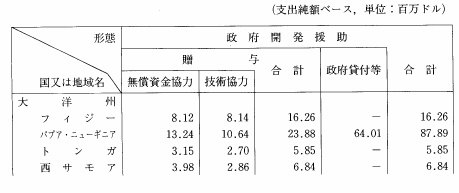
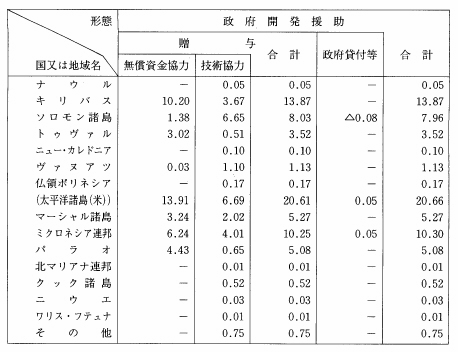
(ト) 欧州
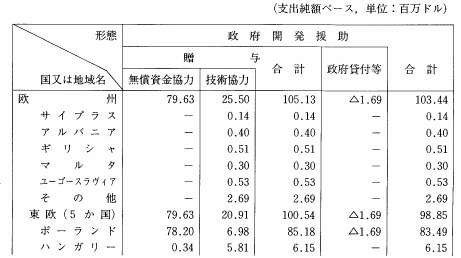
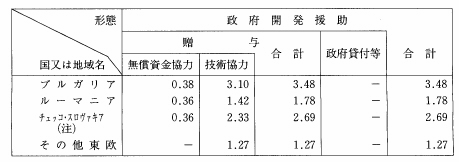
| (注) | 93年1月1日より分離独立し,チェッコ及びスロヴァキアとなっているが,92年実績はチェッコスロヴァキア。 |
(3) 我が国経済協力実績の主要先進国との比較一覧
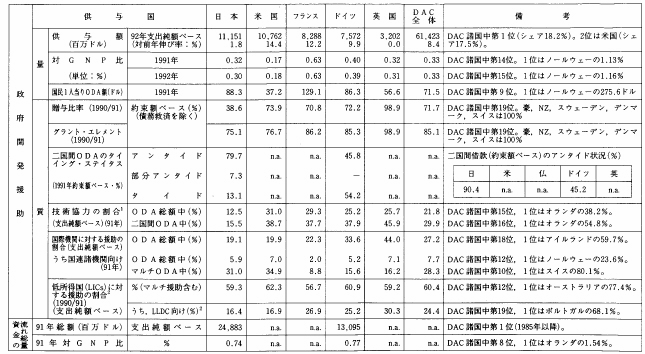
(注)1. 行政経費,対NGO支援及び開発啓発を除く。
2. 国連基準による後発開発途上国47が国。
3. カッコ内は暫定値。
4. 91年の各国データは未判明。
(出典) 92年DAC議長報告
(4) 国際機関に対する我が国のODA実績(1988年~1992年)
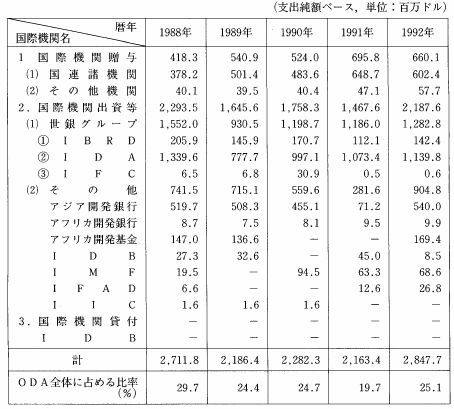
| (注) | 「-」印は実績なし。 | |
| 四捨五入の関係上,合計が一致しないことがある。 | ||
| ポーランド,ハンガリー,チェコ,スロヴァキア,ブルガリア,ルーマニア向け実績も含まれる。 |
2. DAC諸国の経済協力実績(1992年)
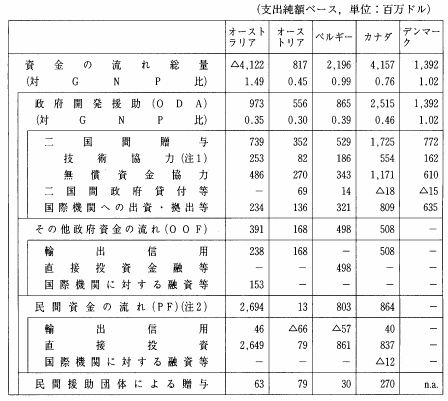
(出典) DAC議長報告。
(注1) 行政経費及び対NGO支援を除く。
(注2) 民間資金の流れは居住者ベース(海外支店分は除く)。
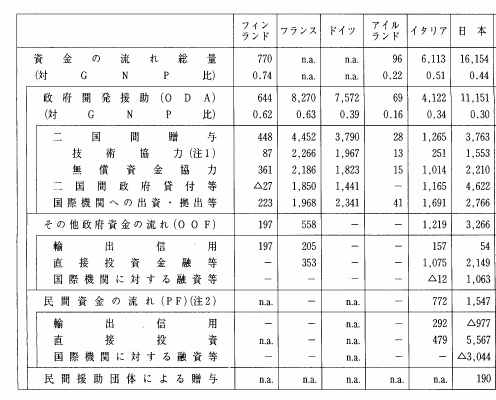
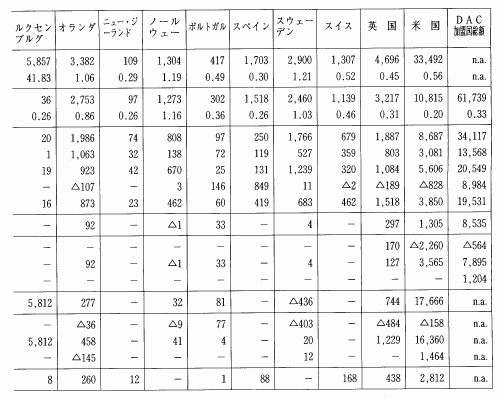
1. 国連・国連専門機関等の加盟国・加盟地域一覧表(1993年12月現在)
◎理事国(UNは安保理事国,UNESCOは執行委員国,WIPOは調整委員国)
○加盟国または地域 ×非加盟国または地域
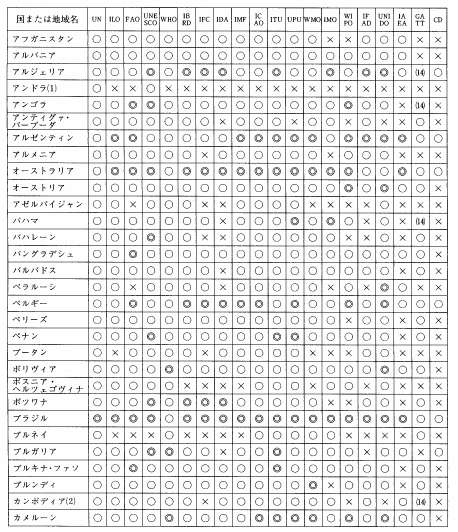
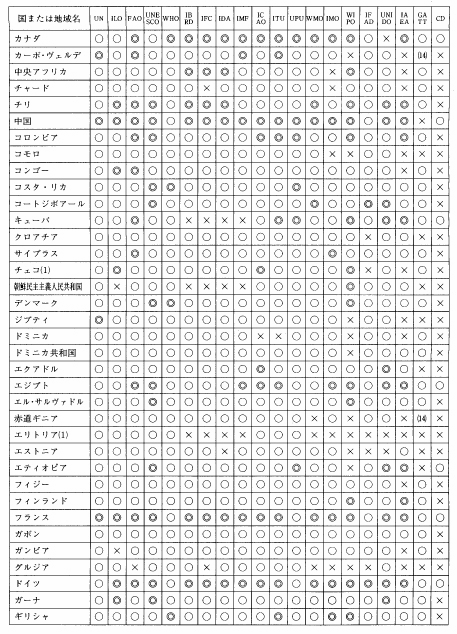
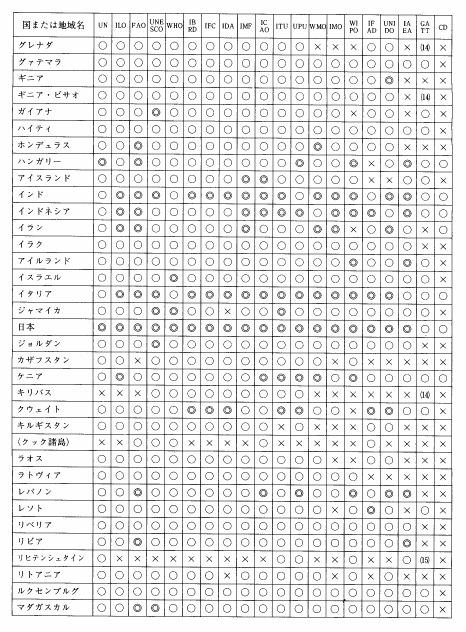
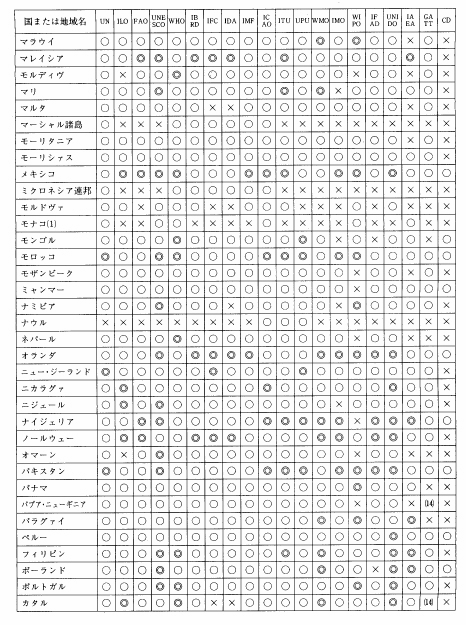
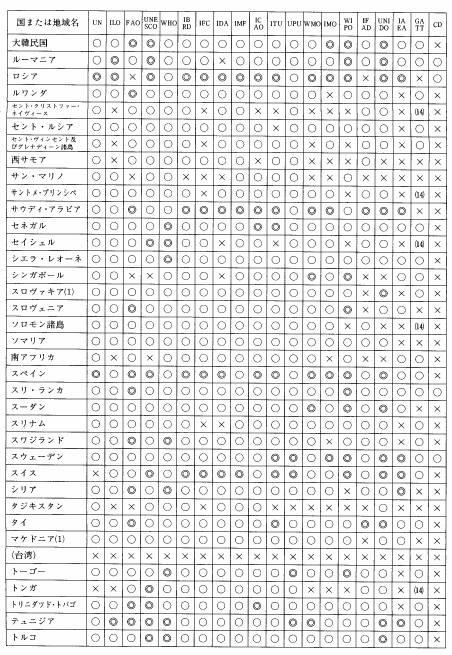
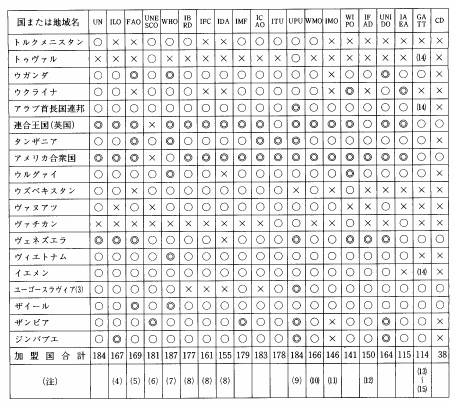
| UN ・・・・・・・・・・・・国際連合 | ITU・・・・・・・・国際電気通信連合 |
| ILO・・・・・・・・・・国際労働機関 | UPU・・・・・・・・・・万国郵便連合 |
| FAO・・・・・・国際連合食糧農業機関 | WMO・・・・・・・・・・世界気象機関 |
| UNESCO・・ 国際連合教育科学文化機関 | IMO・・・・・・・・・・国際海事機関 |
| WHO・・・・・・・・・・世界保健機関 | WIPO・・・ ・・・世界知的所有権機関 |
| IBRD・・・・・・・ 国際復興開発銀行 | IFAD・・・ ・・・・国際農業開発基金 |
| IFC・・・・・・・・・ 国際金融公社 | UNIDO・・・・・・・国連工業開発機関 |
| IDA・・・・・・・・・・国際開発協会 | IAEA・・・ ・・・・・国際原子力機関 |
| IMF・・・・・・・・・・国際通貨基金 | GATT 関税および貿易に関する一般協定 |
| ICAO・・・ ・・・・国際民間航空機関 | CD・・・・ ・・・・・・・・軍縮会議 |
| (1) | 1993年中にはチェッコ共和国、スロヴァキア共和国(1月19日)、マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国(4月8日)、エリトリア及びモナコ(4月28日)、アンドラ(7月28日)がそれぞれ国連に加盟し、これにより国連加盟国総数は184となった。 | |
| (2) | 国連を始めとする国際機関においてカンボディアを代表するのはカンボディア王国政府(SNC)である。 | |
| (3) | 旧ユーゴースラヴィアが事実上解体した後,セルビア及びモンテネグロは新たに「ユーゴースラヴィア連邦共和国」(新ユーゴー)を編成したが,国際機関における旧ユーゴースラヴィアの地位は継承していない。 | |
| (4) | ILO理事会は,政府代表理事28人,労働者および使用者代表理事各14人から成っているが,◎は政府代表理事を出している国のみに付した。 | |
| (5) | EEC(欧州経済共同体)は総会,理事会等の会議には参加できるが,選挙活動には参加できない。 | |
| (6) | ニウェの加盟により,UNESCOは181の加盟国・地域を有することとなった。この他に,3の準加盟地域(オランダ領アンティル,英領ヴァージン諸島,アルバ)を有する。 | |
| (7) | WHOは,187の加盟国または地域のほかに,1つの準加盟国(トゥヴァル)及び1つの準加盟地域(プエルトリコ)を有する。 | |
| (8) | IBRDの理事は,職権上,IDA,IFCの理事を兼務することになっている。 | |
| (9) | UPU連合員184には,リストに記載されていない「連合王国政府がその国際関係を処理する海外領土」及び「オランダ領アンティル及びアルバ」が含まれる。 | |
| (10) | WMO構成員としては,加盟国166のほかに,リストに記載されていない香港,仏領ポリネシア,ニュー・カレドニア,オランダ領アンティル(キュラサオ),英領カリビアの5つの領域がある(英領カリビアは執行理事国)。 | |
| (11) | IMOは,146の加盟国のほかに,2つの準加盟地域(香港,マカオ)を有する。 | |
| (12) | IFADは理事18人および理事代理の17人から成っているが,◎は理事を出している国のみに付した。 | |
| (13) | GATT加盟国111には2地域(香港,マカオ)が含まれる, | |
| (14) | 事実上GATTが適用される国(地域) | |
| 新たな独立国などで従来宗主国がGATTを受諾し,適用していたものは,GATT第26条5項(C)に基づき,その対外通商関係につき完全な自治権を取得した旨の通報が旧宗主国により行われ,GATTに正式加盟するまで,相互主義に基づき事実上GATTの適用を受けている(ただし,上表中,カンボディアは,1962年6月5日にGATT第33条に基づき加入を認められていたが,まだ加入議定書を受諾しておらず,1958年11月17日の決定により事実上の適用を受けている)。 | ||
| (15) | リヒテンシュタインは,経済同盟国(スイス)が代わってGATTを受諾し,GATTが適用される。 |
2. 国際連合機構図(1992年12月現在)
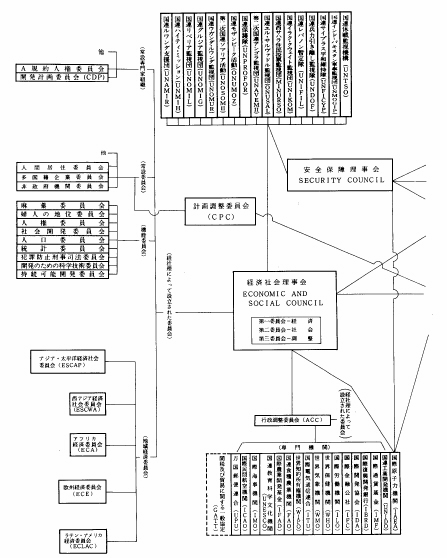
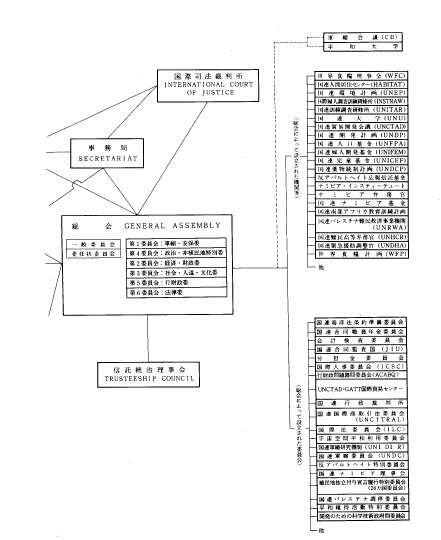
| ※ | 12月20日に人権高等弁務官(UNHCHR)の設立が総会で承認された後,1994年2月14日,総会において初代の人権高等弁務官の就任が決定された。 |
3. 安全保障理事会非常任理事国一覧表
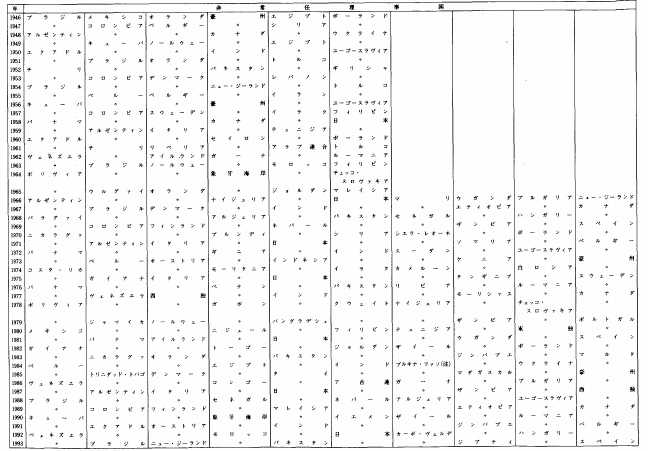
(注) 上ヴォルタは1984年8月4日をもって国名を「ブルキナ・ファソ」と変更した。
4. 国連通常予算の推移
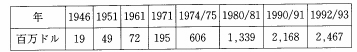
(注) 1974年以降は2年間予算をとっている。
5. 主要国の通常分担率の推移
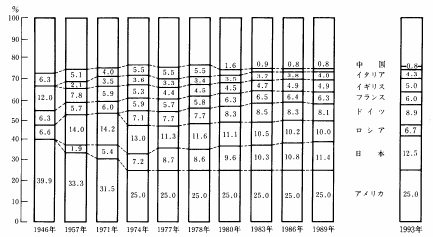
(注) 通常3年間は分担率を変更しない。また,本グラフ中の数字は小数点2位を四捨五入している。
ドイツの分担率については,89年までは西独の分担率で示した。
ロシアの分担率については,89年まではソ連の分担率(ウクライナ,白ロシアを含まない)。
6. わが国の難民等救済援助実績(援助対象別)
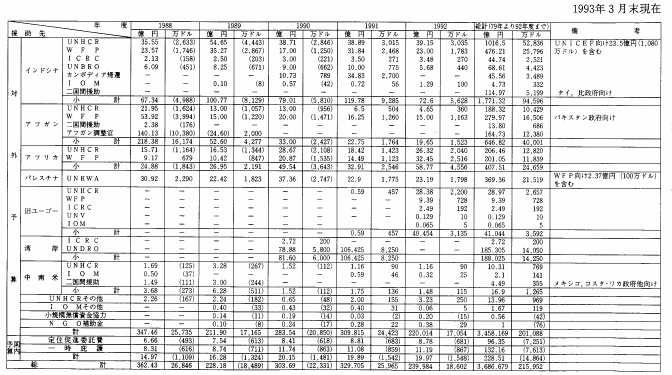
| (注) | ( )の内数字の換算は,その年の支出官レートによる。88年度:1ドル=135円,89年度:1ドル=123円,90年度:1ドル=136円,91年度:1ドル=129円,92年度:1ドル=129円で換算。 |
1. 留 学 生
出身国(地域)別留学生数(92年5月1日現在,( )内は国費留学生数で内数)
| 1. | 中 国 | 20,437人 | ( 1,299人) | 7. | タ イ | 894人 | ( 450人) | |
| 2. | 韓 国 | 11,596人 | ( 672人) | 8. | フィリピン | 503人 | ( 293人) | |
| 3. | 台 湾 | 6,138人 | ( - ) | 9. | 香 港 | 496人 | ( 55人) | |
| 4. | マレイシア | 1,934人 | ( 252人) | 10. | バングラデシュ | 479人 | ( 294人) | |
| 5. | 米 国 | 1,245人 | ( 145人) | そ の 他 | 3,685人 | ( 1,872人) | ||
| 6. | インドネシア | 1,154人 | ( 367人) | 計 | 48,561人 | ( 5,699人) |
(出所) 文部省調査
2. JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)国別招致数
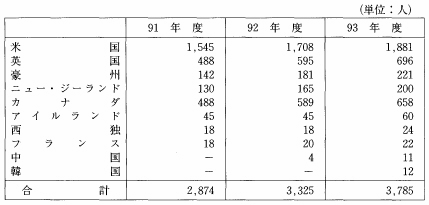
3. 世界の日本語学習者数とその推移
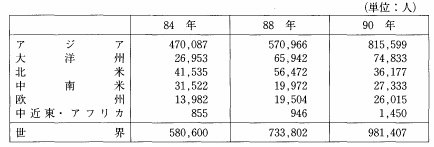
| (出所) | 国際交流基金資料 |
| (注) | 93年度資料は94年秋に発表される予定。 |
4. 主要な日本文化紹介行事(93年1月~12月)
| 日印国交回復40周年事業 | 92年6月~93年3月 |
| チューリッヒ国際6月祭(日本がテーマ国) | 93年3月~10月 |
| パリ日本祭 | 93年4月~5月 |
| モスクワ日本週間 | 93年5月~6月 |
| デュッセルドルフ日本週間 | 93年9月 |
| ベルリン芸術週間(日本がテーマ国) | 93年9月 |
| 日本とヨーロッパ1543-1929展(於ベルリン) | 93年9月~12月 |
| ヴィエトナム日本月間 | 93年10月 |
| アトランタ・ジャパン・フエスト | 93年10月 |
| シンガポール日本月間 | 93年11月 |
| アントワープ'93(欧州文化首都) | 93年 |
| 日本・ポルトガル友好450周年記念事業 | 93年 |
5. 外国紹介大型文化行事(93年1月~12月)
| ルーブル美術館展 | 93年3月~7月 |
| メトロポリタンオペラ | 93年5月 |
| 第4回アセアン漫画家展『変わりゆくアジア』 | 93年5月 |
| 上海美術館展 | 93年6月~11月 |
| 日本・シンガポール現代美術展 | 93年7月 |
| 『カオウと向きあう絵画の諸相』 | |
| アジア国際舞踊フェスティバル | 93年8月 |
| ウォーマッド・コンサートプラザ | 93年8月 |
| アジアマンス | 93年9月 |
| 第38回アジア太平洋映画祭 | 93年9月 |
| 国立カンボディア舞踊団日本公演 | 93年9月~10月 |
| ベルリン ドイツ オペラ | 93年9月~10月 |
| ヴァチカンのルネッサンス美術展 | 93年9月~10月 |
| 東京国際映画際 | 93年9月~10月 |
| フィリピン国立文化センター劇団ミュージカル | |
| 『エル・フィリー愛と反逆』 | 93年10月 |
| 『メコンの響き一タイのモーラムとポップス』 | 93年11月 |
| インドネシア映画祭 | 93年11月 |
| 日本・タイ現代美術展 | 93年12月 |
6. 文化無償協力
地域別実績(予算ベース)
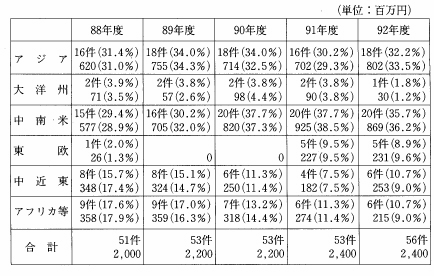
7. 国際交流基金の活動
※ 外務省主管の特殊法人である、国際文化交流の中核的実施機関。
(1) 国際交流基金事業別実績額
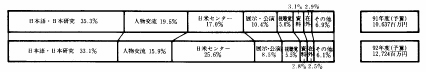
(2) 国際交流基金地域別実績額比率
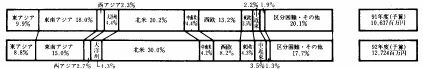
(3) 国際交流基金93年度予算
![]()
(4) 国際交流基金事業実績表(72~92年度)

注. 日本語能力試験は国外のみ基金が実施。ただしうち台湾における実施は(財)交流協会による。
1.(1) 地域別在留邦人数
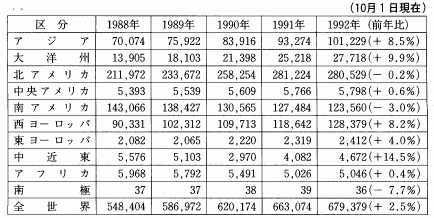
(出所) 外務省「海外在留邦人数調査統計」
(2) 地域別在留邦人数の推移
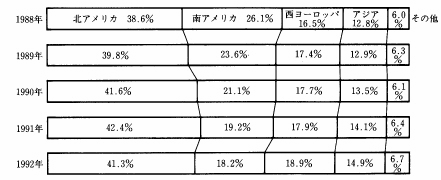
| (注) | 「その他」とは,中近東,アフリカ,太洋州,中央アメリカ,東ヨーロッパの合計である。 |
| (出所) 外務省「海外在留邦人数調査統計」 |
2. 外国人入国者数・日本人出国者数
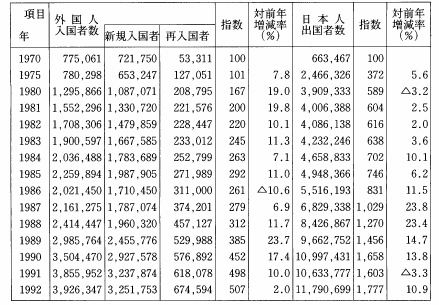
(出所) 法務省「出入国統計年報」
3. 一般旅券発行数の推移
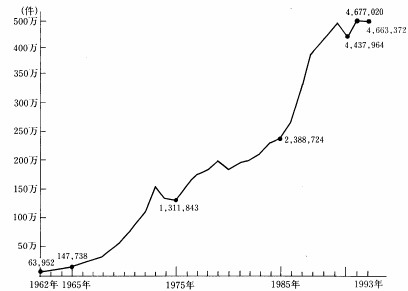
(注) 在外公館分を除く
4. 1993年の主要緊急事態事例※
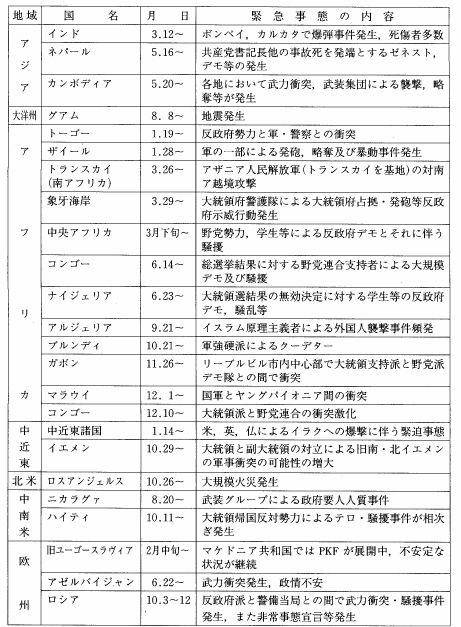
※ 緊急事態:海外における日本人の身体,生命,財産等に重大な危険を及ぼす事態。
5. 事件・事故等援護関係統計(92年度)全世界
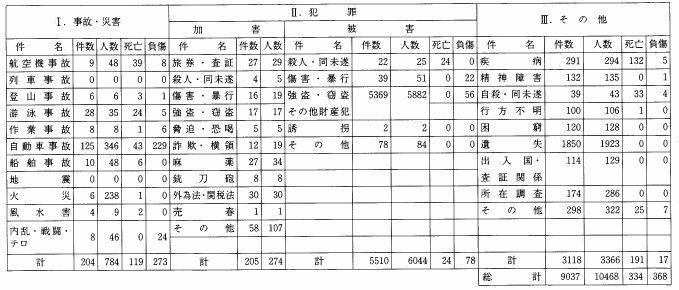
注:「件名」の説明
| 1. | 内乱・戦闘・テロ・・・・ | 本項目は特定邦人が巻き込まれたケースについてのみ集計し,不特定多数の邦人を巻き込む緊急事態については別途集計。 | |
| 2. | 犯罪加害(旅券・査証)・・ | 不法滞在,不法就労等。 | |
| 3. | 行方不明・・・・・・・・ | グループツアーからはぐれた者,旅行の帰国予定日に帰らない者,留学中の子弟と音信不通になった者などの消息調査等。 | |
| 4. | 困窮・・・・・・・・・・ | 旅行中所持金を紛失,費消した旅行者への本邦親元からの送金援助など。 | |
| 5. | 出入国・査証関係・・・・ | 犯罪に分類されないもので,再入国トラブルの援助等。 | |
| 6. | 所在調査・・・・・・・・ | 不動産の相続登記手続き等に係る海外の在留邦人の住所調査等。 |
6. 海外邦人援護件数の推移
(1) 海外邦人援護件数の推移(強盗等財産犯)
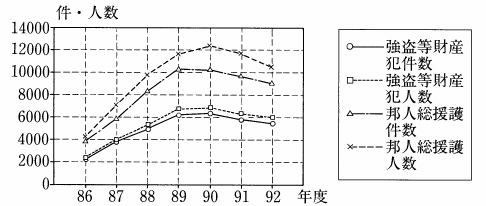
(2) 海外邦人援護件数の推移(凶悪犯罪被害,事故・災害)
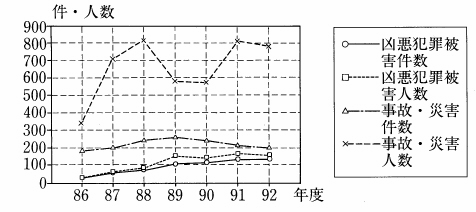
7. 1992年査証発給件数
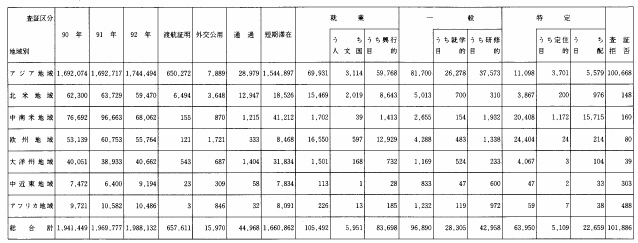
(注) 人文国:人文知識・国際業務
日配:日本人の配偶者等
8. 就学形態別在留邦人子女調査
(1986年から1993年度)
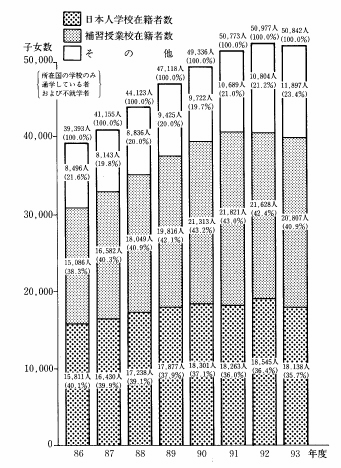
(93年1月~93年12月)
1. アジア
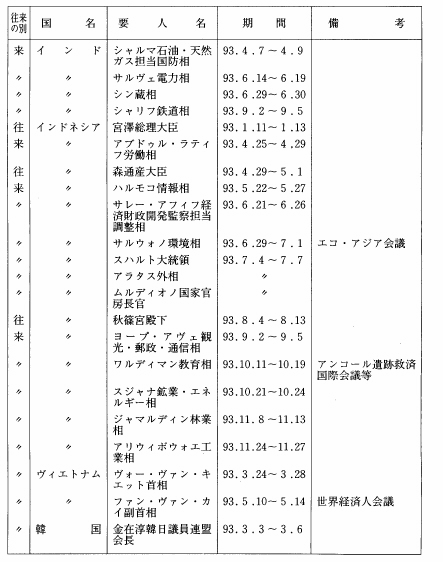
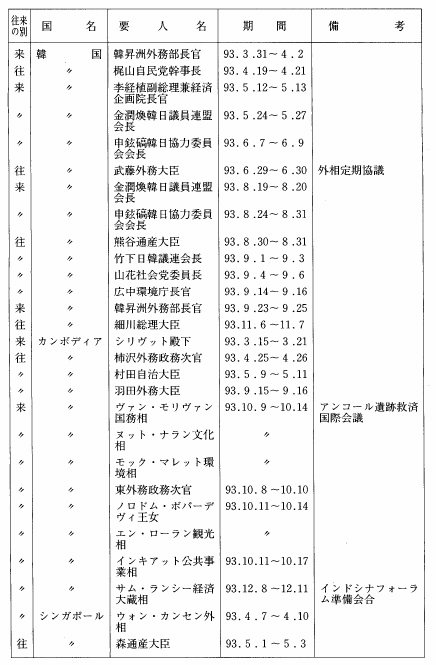
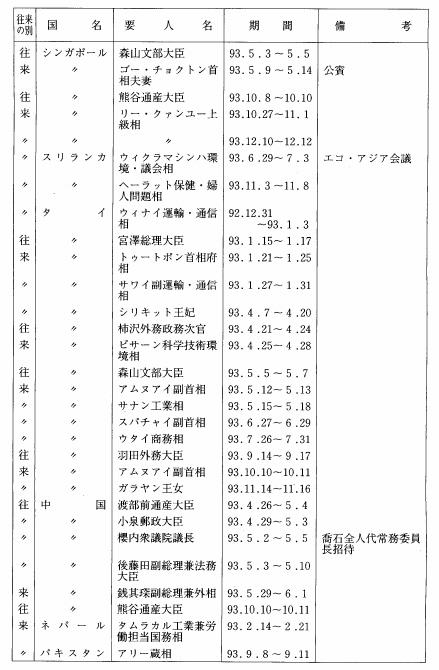

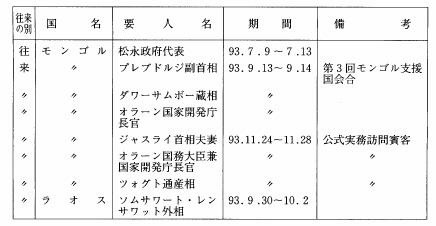
2. 北米
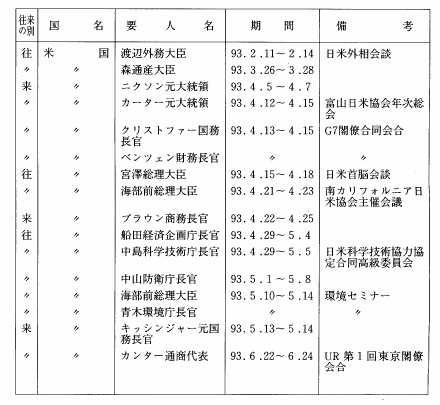
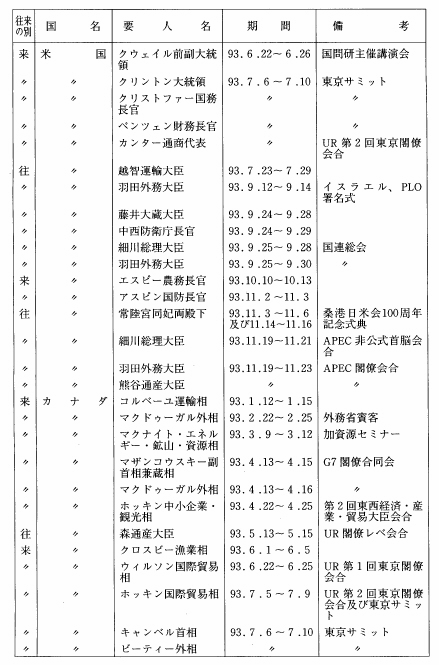
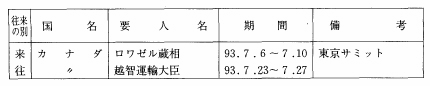
3. 中南米
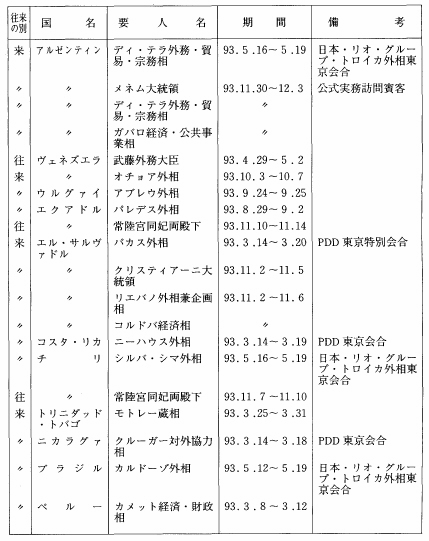
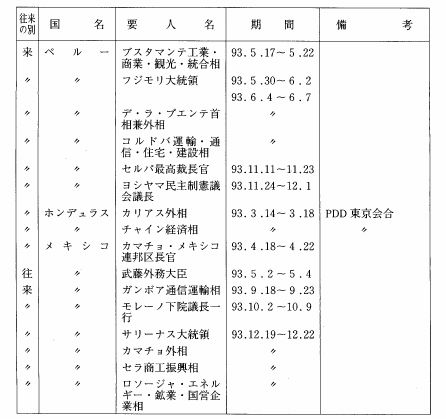
4. 欧州
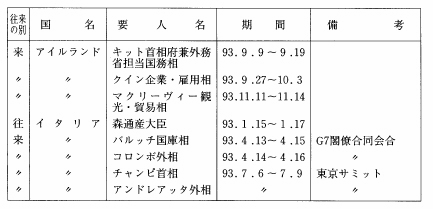
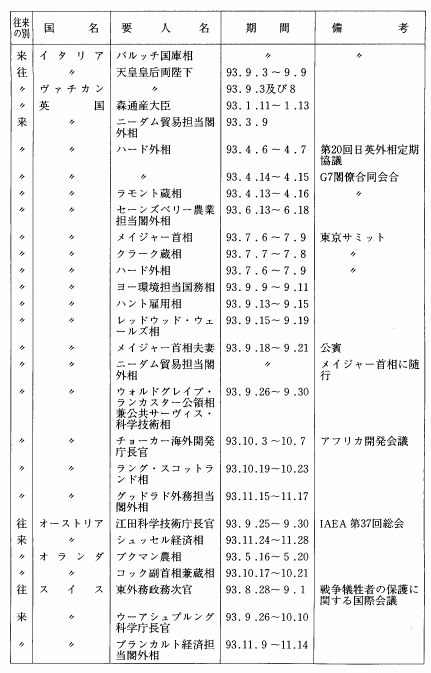
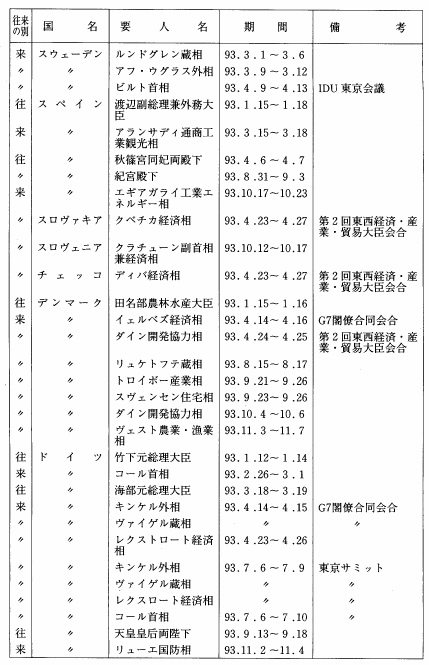
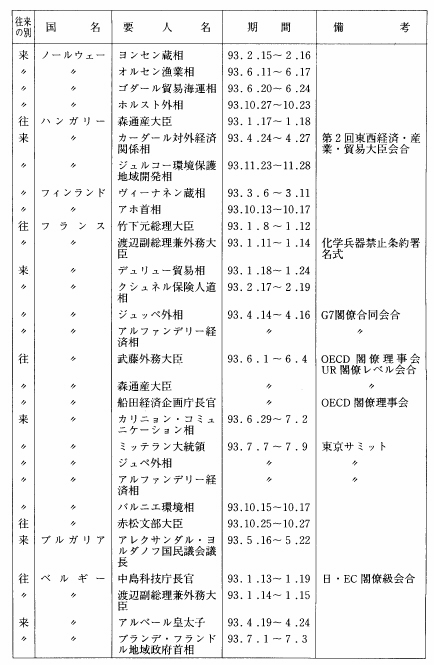
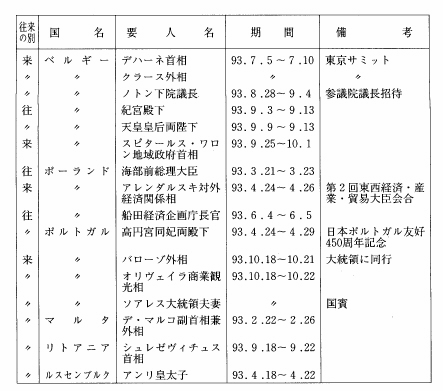
5. ロシア・NIS諸国
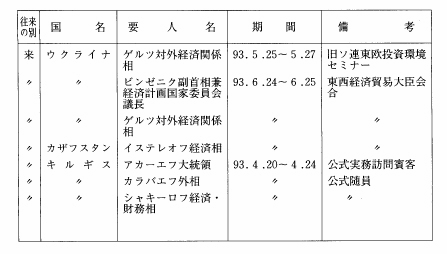
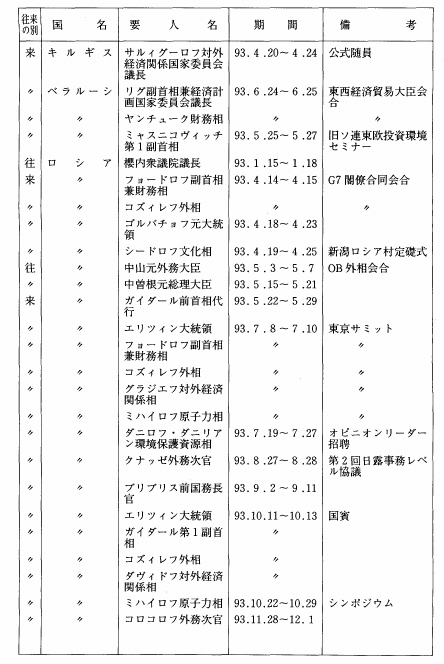
6. 大洋州
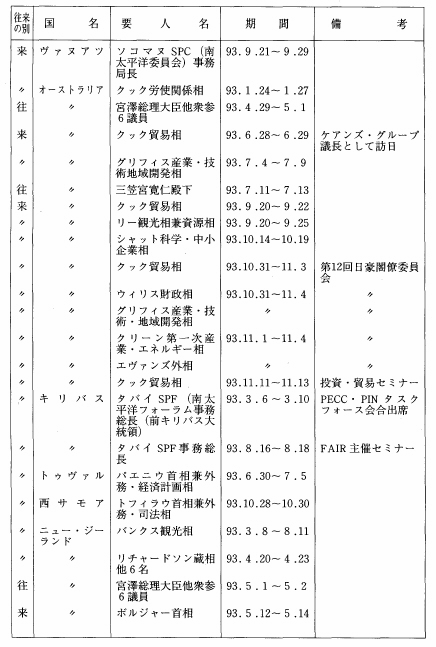
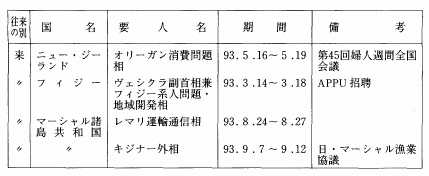
7. 中近東
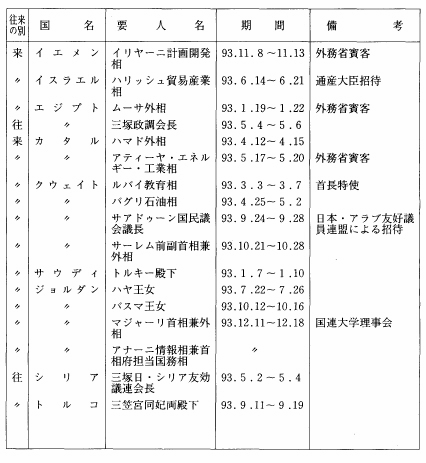
8. アフリカ
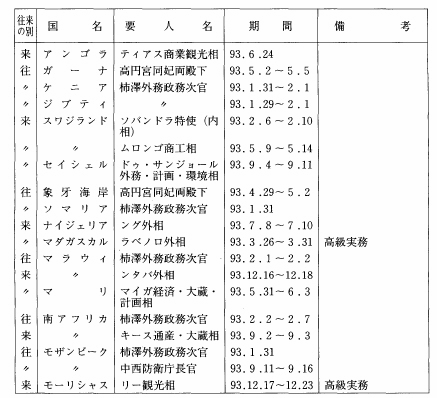
93.10.5~10.6 アフリカ開発会議に出席したアフリカ地域の首脳・閣僚ムセベニ大統領、キベジャ外相、マヤンジャ=ムカンギ大蔵経済企画相、カイジュカ通商産業相(ウガンダ)、デュリ計画・経済開発相(エティオピア)、ハイレ大蔵・開発相(エリトリア)、ローリングス大統領、ボッチウェイ大蔵・経済企画相、トトビ・クワキイ情報相、アダム食糧・農業相(ガーナ)、ワノン・デ・カルヴァロ・ベイガ経済調整相(カーボ・ベルデ)、ミンドウンビ外務協力仏語圏省担当副大臣(ガボン)、コドック計画・国家開発担当国務相、オコウダ大統領府担当相(カメルーン)、シラー外務・協力相(ギニア)、ゴメス・ディアス計画担当国務相(ギニア・ビサオ)、サイトチ副大統領兼計画国家開発相(ケニア)、カアビ・エル・ヤクルッティ大蔵・予算相(コモロ)、ブンクルー外務・協力・仏語圏担当相、ムアンベンガ商業・消費・中小企業相、ンバヤ科学技術担当国務相(コンゴー)、メイラ・リタ協力開発担当相(サントメ・プリンシペ)、ペンザ蔵相(ザンビア)、ジョン・カリム大蔵・開発・経済計画相(シエラ・レオーネ)、アブドゥ外相(ジブティ)、シャムヤリラ外相、マサヤ蔵相(ジンバブエ)、ド・サン・ジョレ外務・計画・環境相(セイシェル)、サーホ経済・大蔵・計画相(セネガル)、カブラン・ダンカン首相付経済・大蔵・計画担当相(象牙海岸)、マレチェラ首相兼第一副大統領、ムスヤ通商産業相(タンザニア)、ビンガバ経済・計画・統計・国際協力担当国務相、ドクナ蔵相(中央アフリカ)、イブニ・ウマール計画・協力相(チャド)、ハナチ国際協力・外国投資大臣付国務長官(テュニジア)、イェンチャブレ計画・国土整備相、フィアンヨ経済大蔵相(トーゴー)、ハムテニャ通商産業相(ナミビア)、セイニ外務・協力省付協力担当閣外相(ニジュール)、コンパオレ大統領、ガボレ議会担当国務相、サワドゴ計画担当閣外相(ブルキナ・ファソ)、チザ副首相(ブルンディ)、ソグロ大統領、ドスー外務・協力相、ドスー蔵相、タニョン計画相(ペナン)、マシーレ大統領、チエペ外相(ボツワナ)、チンマンゴ蔵相(マラウイ)、マイガ経済大蔵計画相(マリ)、ナバブシング副首相兼経済計画・開発相(モーリシアス)、ウールド・シディ計画相(モーリタニア)、モクンビ外相(モザンビーク)、エル・レーゾアニ運輸相(モロッコ)、バホロ大蔵・企画・人的資源開発相(レソト)、ルコゴザ情報相(ルワンダ)
9. 国際機関