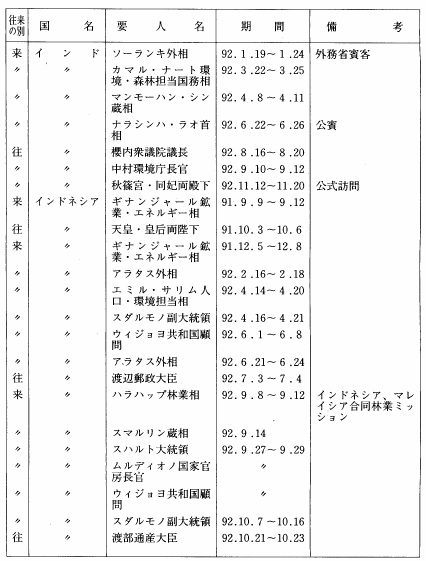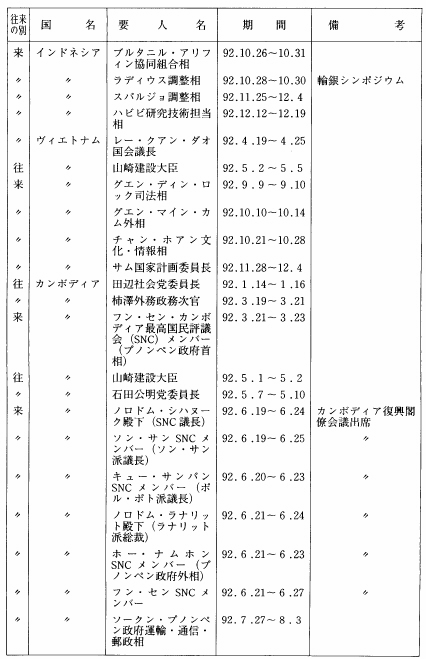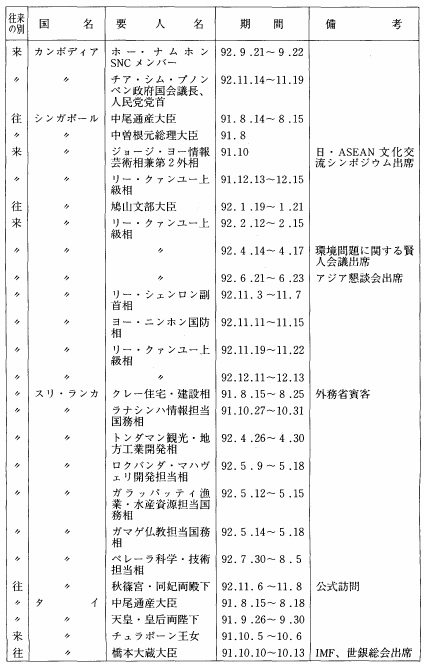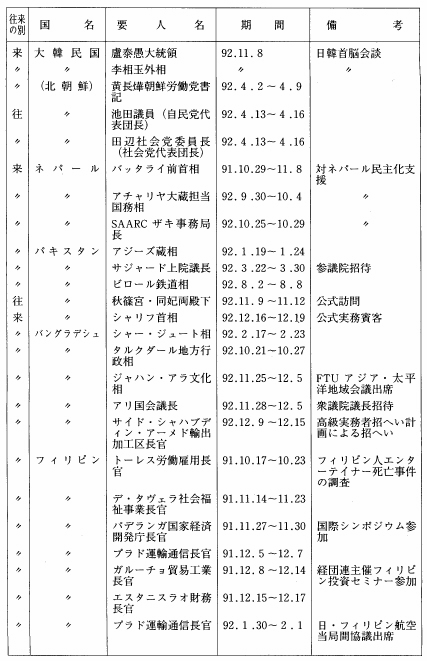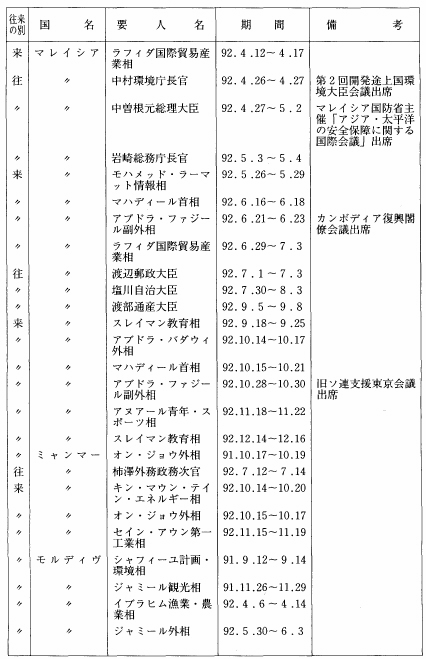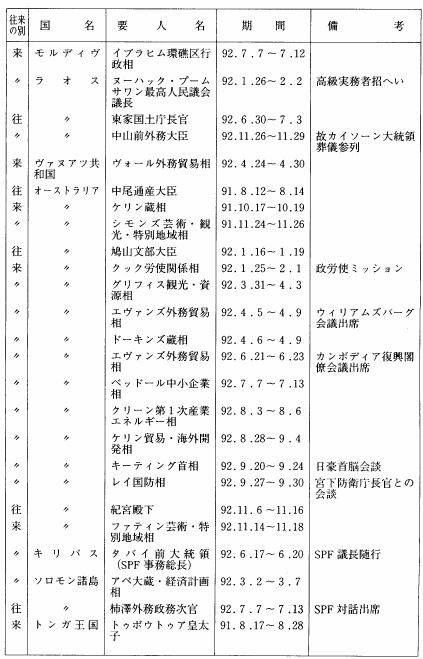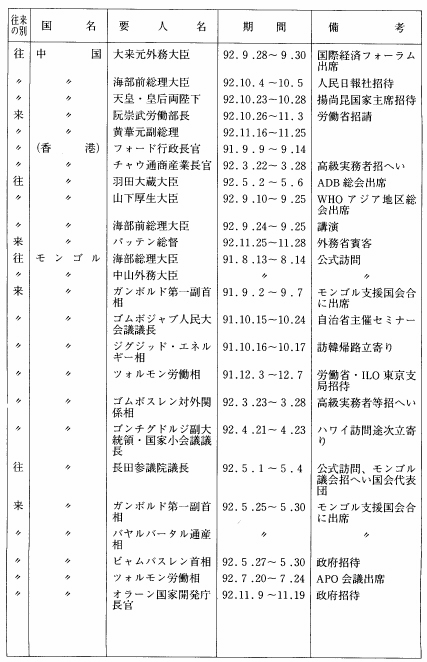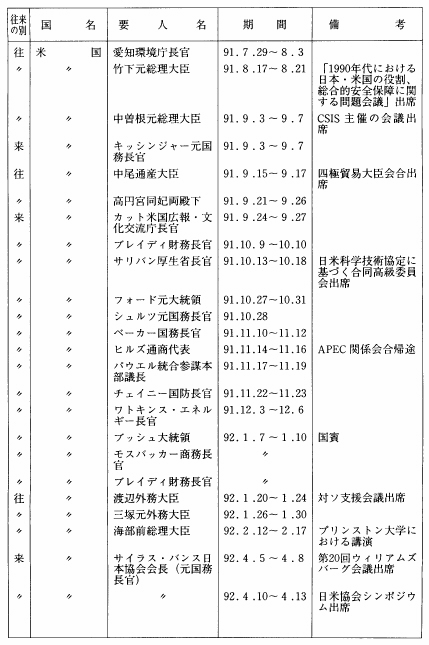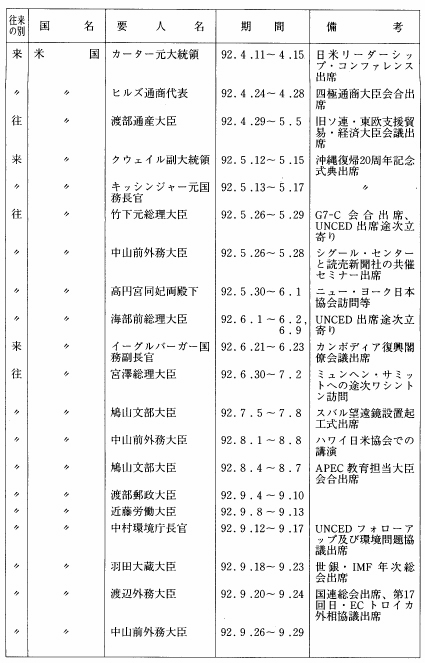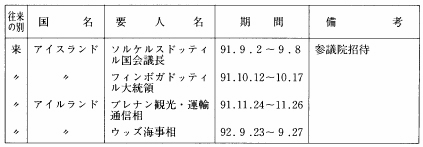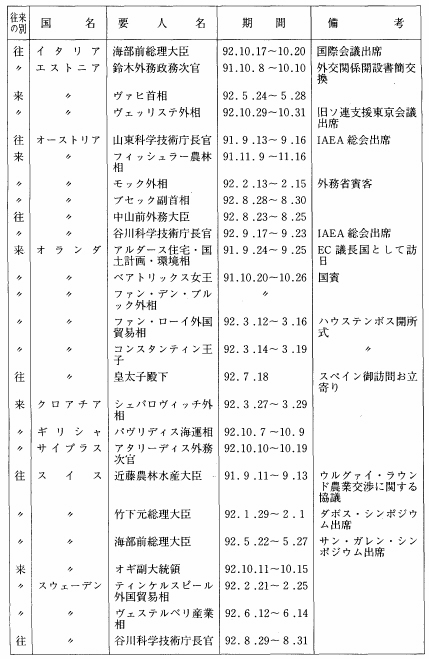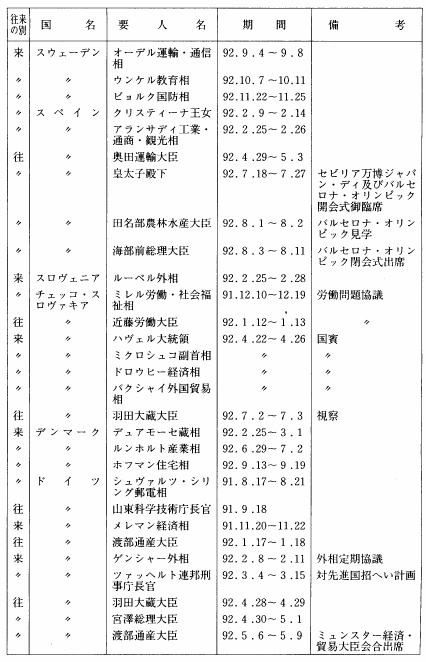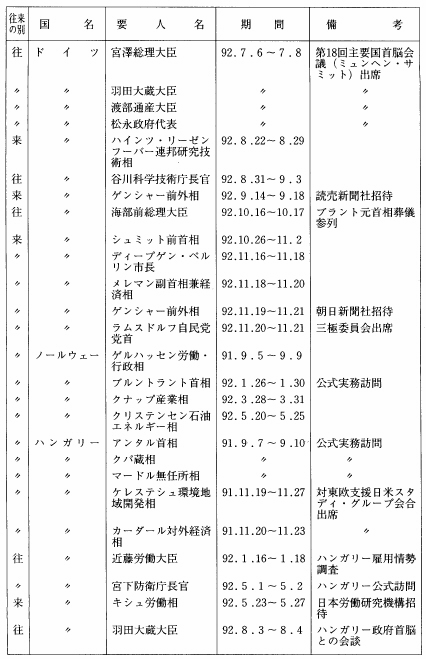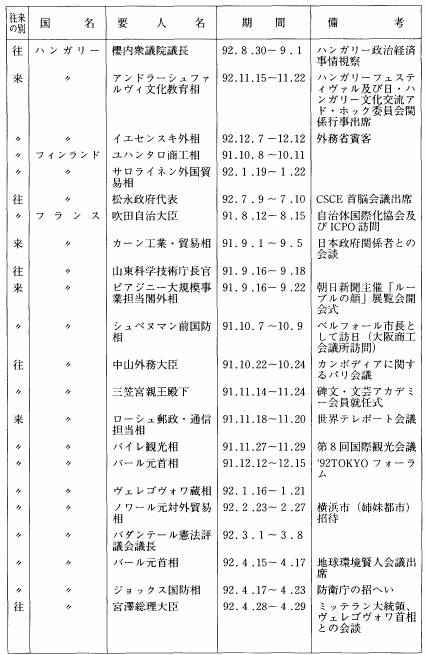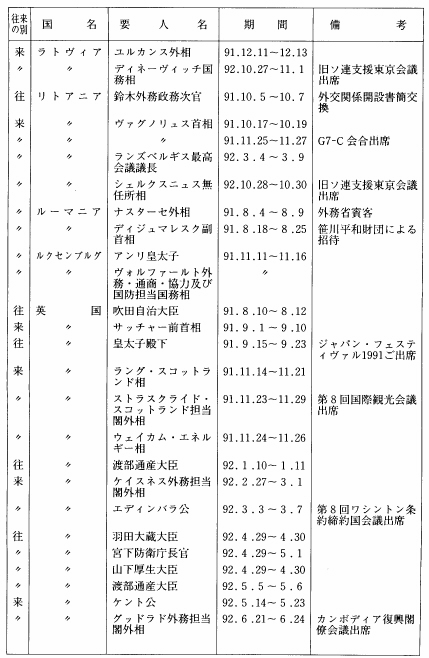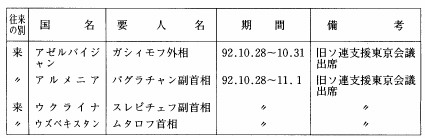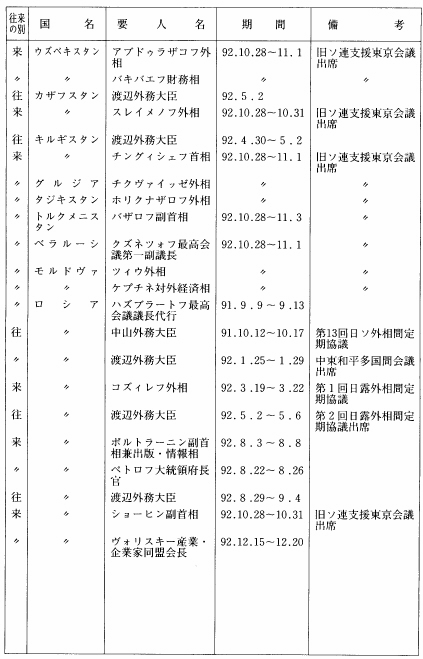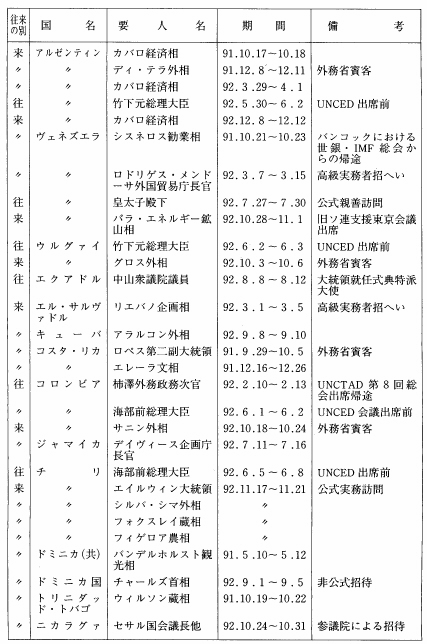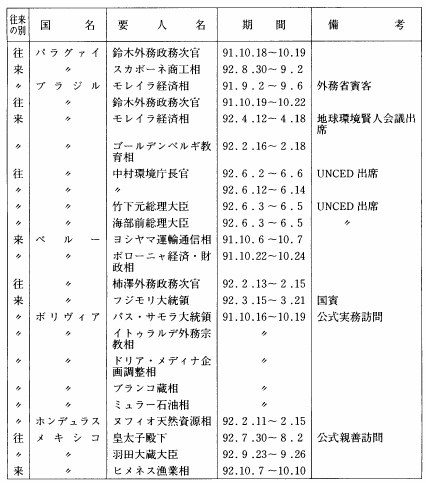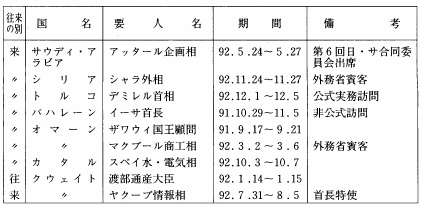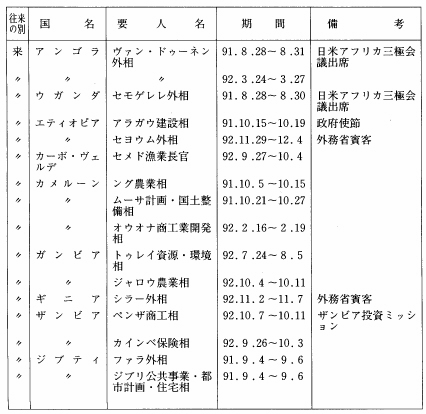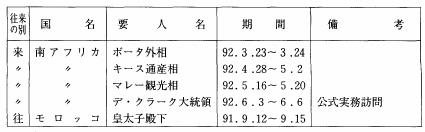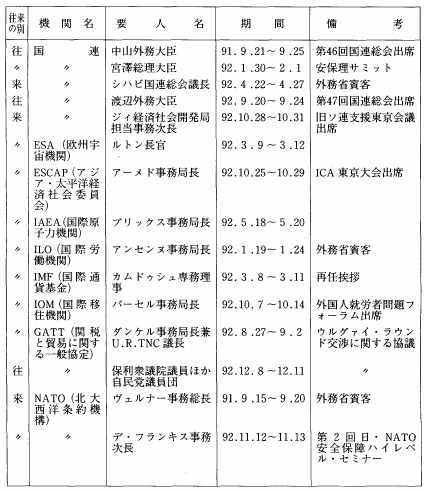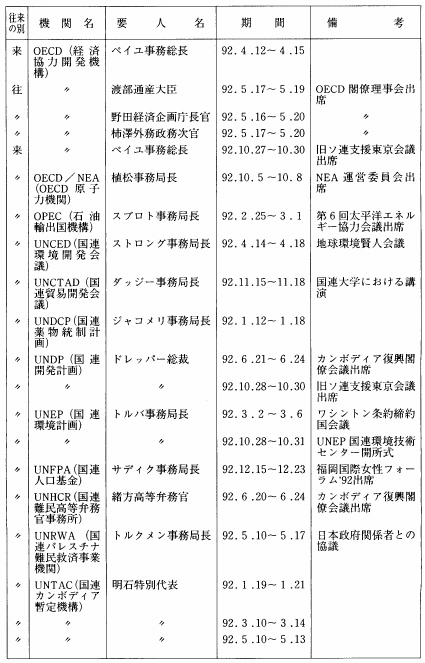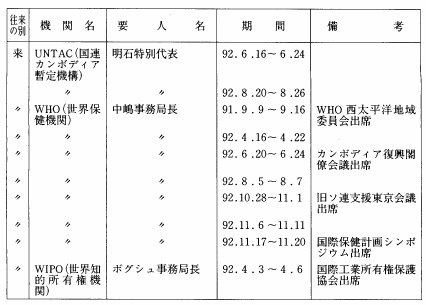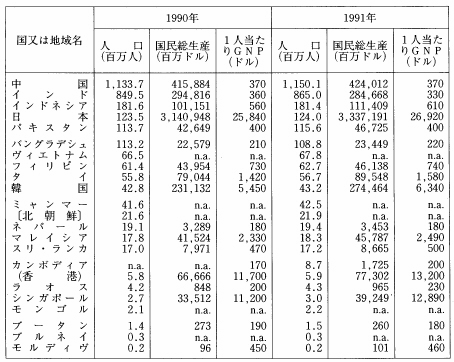
1. 経済関係
1. 一般的指標
(1) 各国の人口、国民総生産(GNP)及び1人当たりGNPの国際比較
(イ) アジア
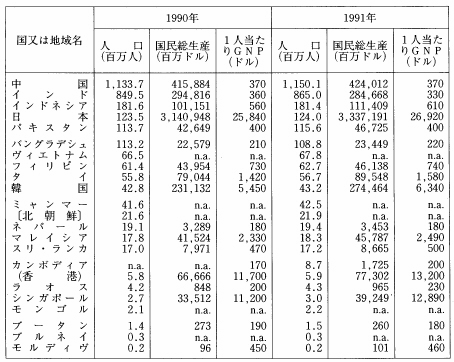


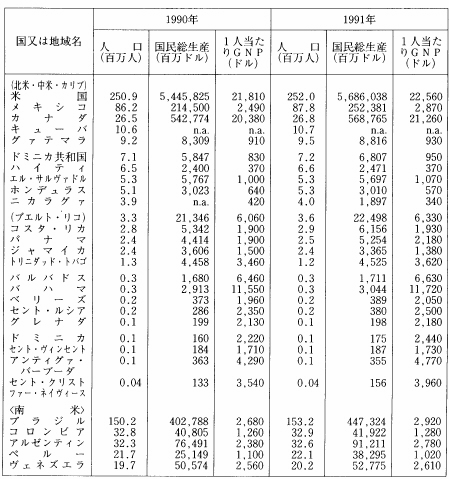
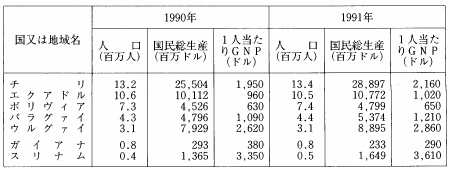
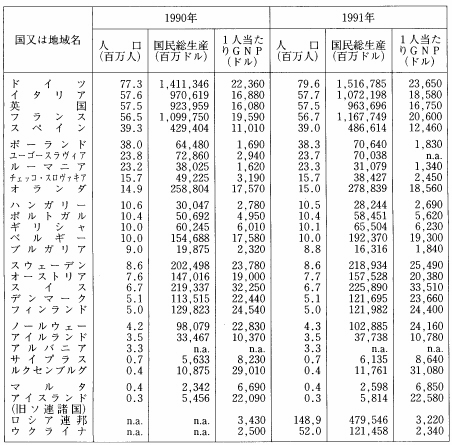
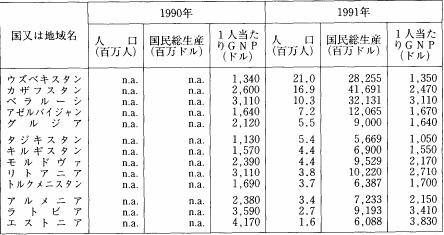
(注) ドイツの国民総生産と1人当たりGNPは,旧西独地域のみ。
ユーゴースラヴィアのデータは,旧ユーゴースラヴィアのもの。

(注) ジョルダンの国民総生産と1人当たりGNPは東岸のみ。
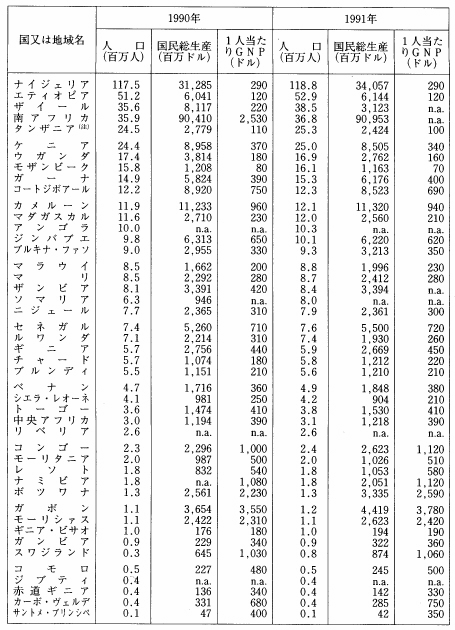
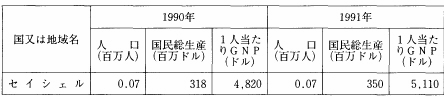
(注) タンザニアの国民総生産及び1人当たりのGNPは本土のみ。
(出所) 1990年の人口,国民総生産の数値は,世銀「ATLAS1991」より。
1990年の1人当たりGNP,1991年の全数値は,世銀「ATLAS1992」より。
(イ) 貿易
(a) 地域別貿易構成(1991年)
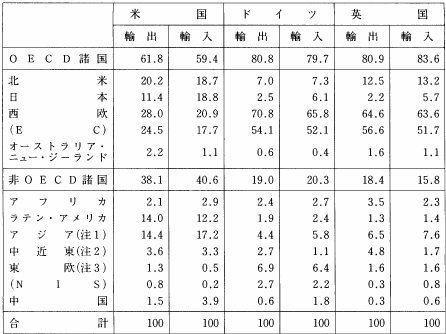
(注1) 中国を除く。
(注2) 北アフリカ諸国をアフリカに含める。
(注3) NIS,ユーゴースラヴィアを含む
・四捨五入の関係で構成比の合計は必ずしも100%にならないことがある。
(出所) OECD「Monthly Statistics of Forgine Trade」
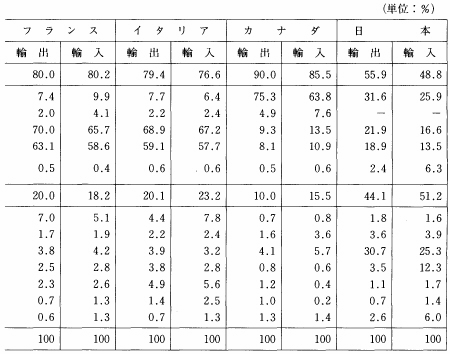
(i) 輸出
(単位:百万ドル)

(出所) IMF「International Financial Statistics」
(単位:百万ドル)

(出所) 同上 注:ドイツは90年7月以降旧東独地域の数値を含む
(単位:億ドル)
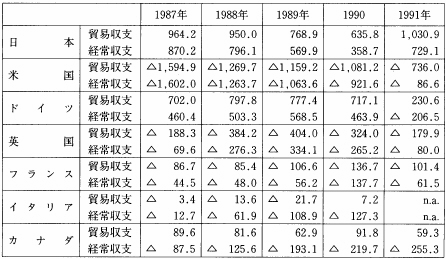
(出所) IMF「International Financial Statistics」
(注) ドイツは90年7月以降旧東独地域の数値を含む
(a) 消費者物価上昇率
(単位:%)
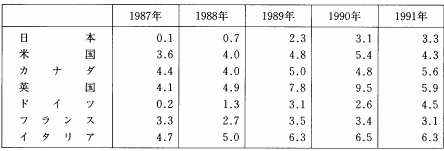
(出所) IMF「World Economic Outlook」
(注) ドイツは91年以降,統一ドイツ
(単位:%)

(出所) IMF「World Economic Outlook」
(注) ドイツは91年以降,統一ドイツ
(単位:%)
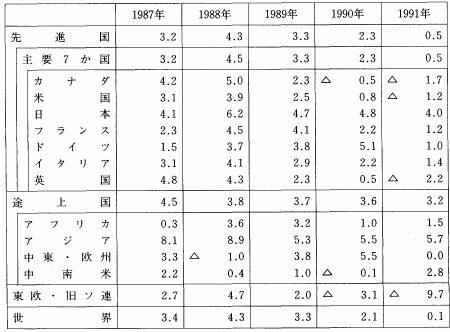
(出所) IMF「World Economic Outlook」 (注)
(あ) ドイツはGNPベース。
(い) ドイツは91年以降,統一ドイツ。
(1) 国際収支の推移
(単位:百万ドル)
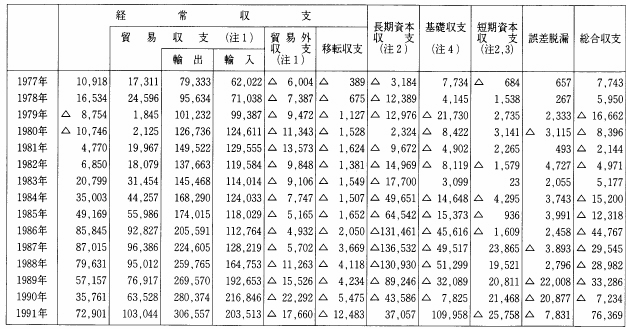
|
(注1) |
委託加工費,仲介貿易(ネット受取額)は,1979年6月まで貿易収支へ,同年7月以降貿易外収支へそれぞれ計上。 |
|
(注2) |
△は資本の流出(資産の増加および負債の減少)を示す。 |
|
(注3) |
金融勘定に属するものを除く。 |
|
(注4) |
現先取引は,短期資本収支へ計上。 |
|
(出所) |
日本銀行「国際収支統計月報」 |
(イ) 輸出(1991年)

(出所) 通関統計

(出所) 通関統計
(単位:百万ドル)
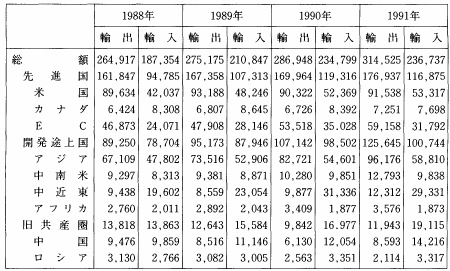
(出所) 通関統計
(注) ロシアの1990年以降は旧ソ連の計数
1. 日本の経済協力
(1) 開発途上国への資金の流れ
(支出純額ベース,単位:百万ドル)
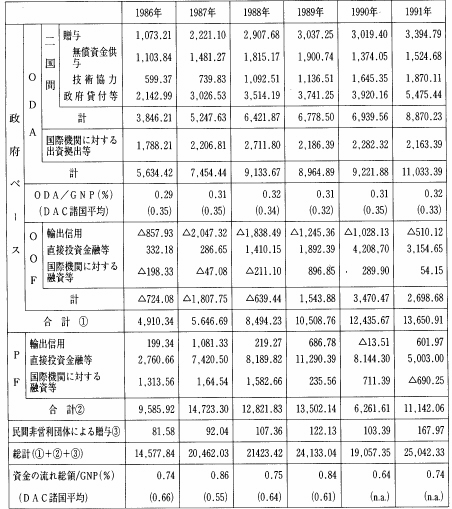
(注1) 1991年実績については暫定値(ODA実績は確定値)。
(注2) 民間資金の流れは居住者ベース(海外支店分は除く)
(注3) 国民総生産の額は1990年または確報値,91年は速報値。
(イ) 地域別
(支出純額ベース,単位:百万ドル)

|
(注) |
1. |
四捨五入の関係上,合計が一致しないことがある。また,「-」は実績なし。「△」は回収超過。 |
|
2. |
無償の分類不能は昭憲皇太后基金及び赤十字国際委員会等への拠出。技協の分類不能は各地域にまたがる調査団の派遣,留学生世話団体への補助金等の他,行政経費,開発啓発費を含む。 |

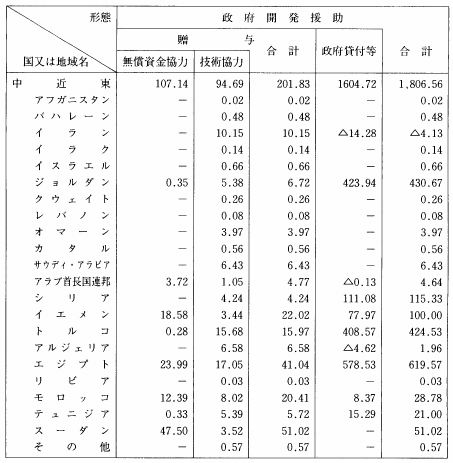
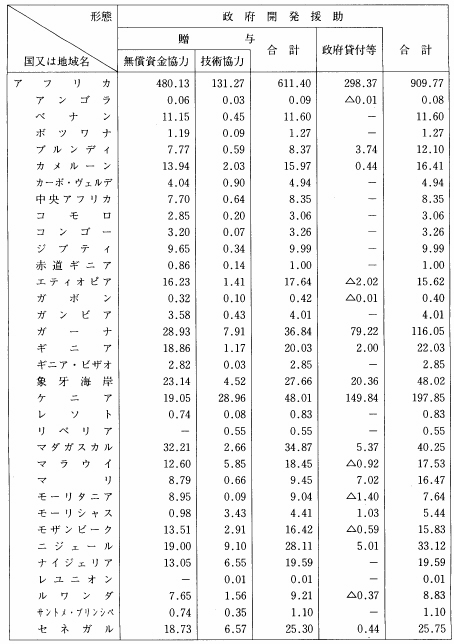
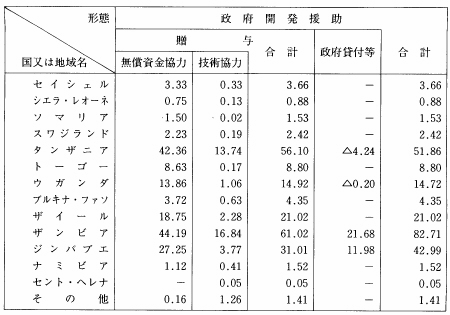
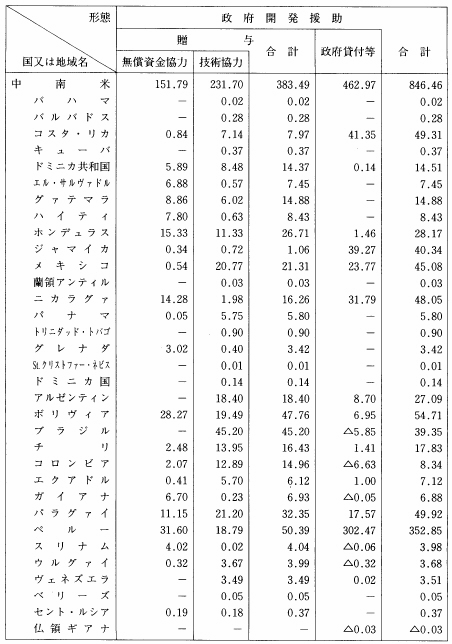

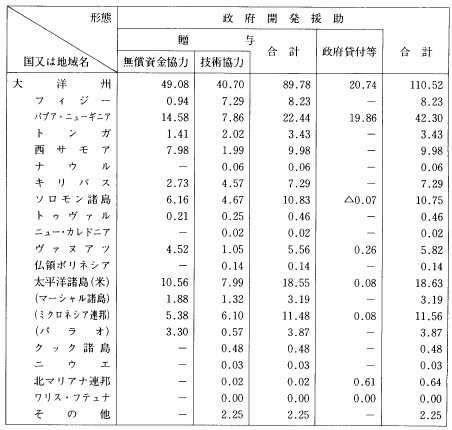
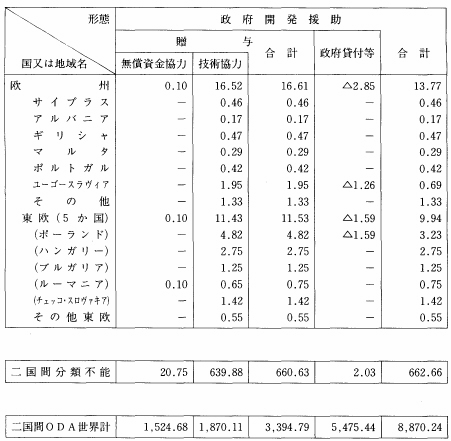
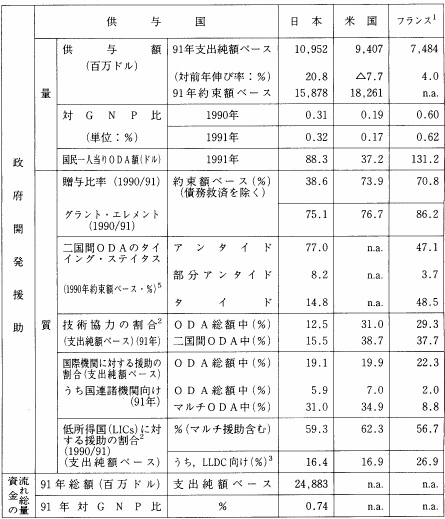
(注)1. 海外領土(TOM)向け実績を含み,海外県(DOM)向け実績を除く。
2. 行政経費,対NGO支援及び開発啓発を除く。
3. 国連基準による後発開発途上国47か国。
4. カッコ内は暫定値。
5. 91年の各国データは未判明。
(出典) DAC議長報告
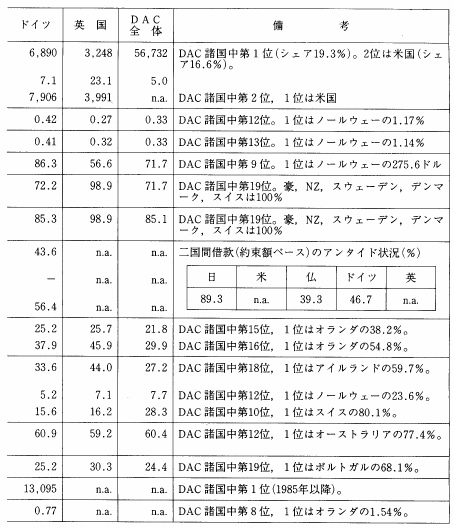
(4) 国際機関に対する我が国のODA実績(1987年~1991年)
(支出純額ベース,単位:百万ドル)
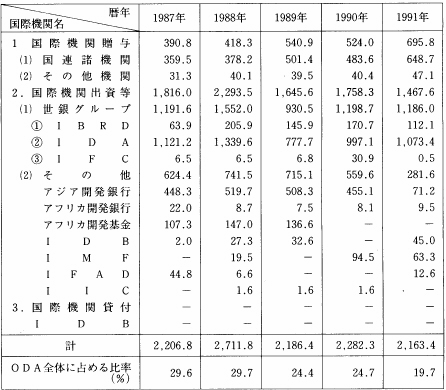
|
(注) |
「-」印は実績なし。 四捨五入の関係上,合計が一致しないことがある。 ポーランド,ハンガリー,チェコ,スロヴァキア,ブルガリア,ルーマニア向け実績も含まれる。 |
|
(出典) |
DAC資料 |
(支出純額ベース,単位:百万ドル)
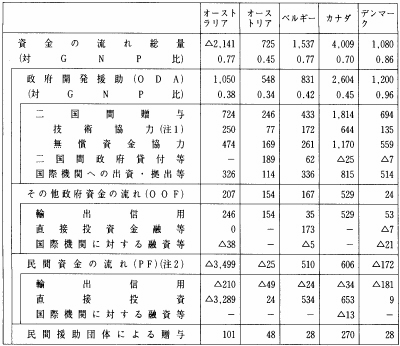
(出典) DAC議長報告。
(注1) 行政経費及び対NGO支援を除く。
(注2) 民間資金の流れは居住者ベース。(海外支店分は除く)。

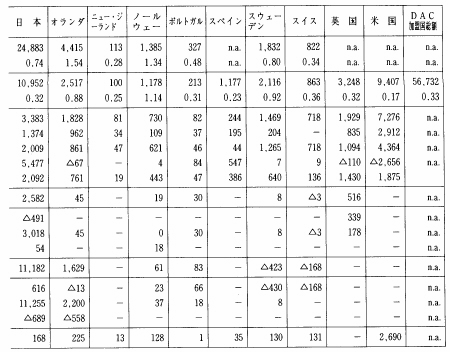
1. 国連・国連専門機関等の加盟国・加盟地域一覧表(1992年12月現在)
◎理事国(UNは安保理事国,UNESCOは執行委員国,WIPOは調整委員国)
○加盟国または地域 ×非加盟国または地域
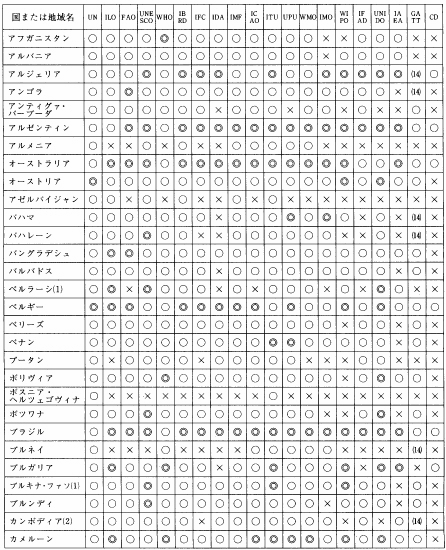
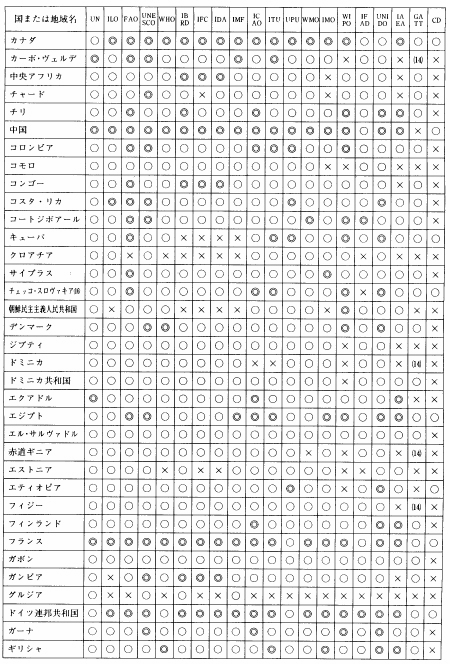
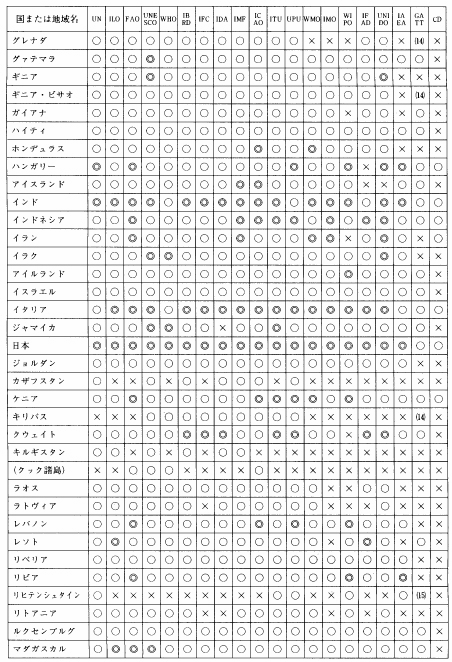
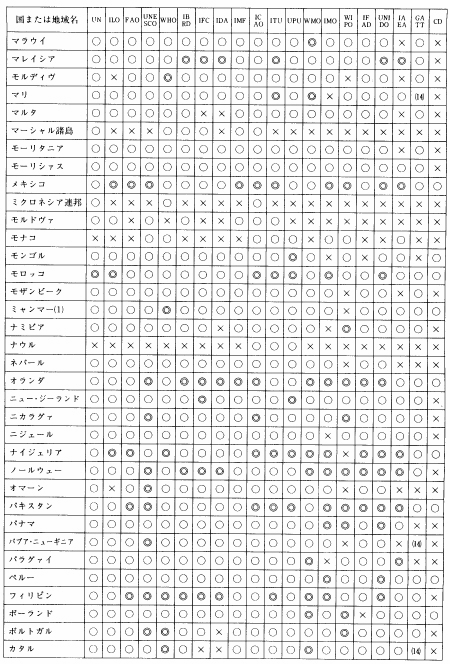
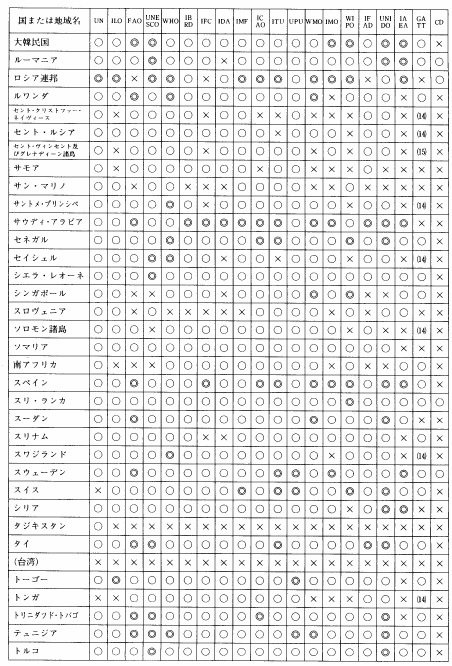
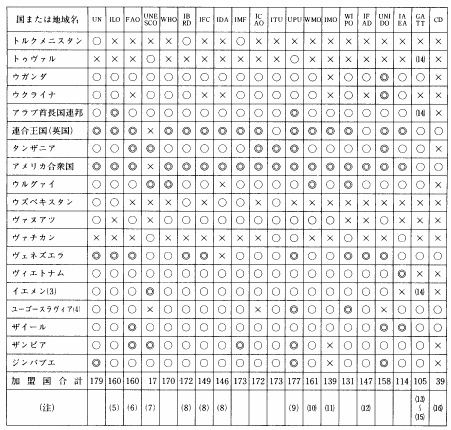
UN・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国際連合 ILO・・・・・・・・・・・・・・・・・国際労働機関 FAO・・・・・・・・・国際連合食糧農業機関 UNESCO・・国際連合教育科学文化機関 WHO・・・・・・・・・・・・・・・・・世界保健機関 IBRD・・・・・・・・・・・・国際復興開発銀行 IFC・・・・・・・・・・・・・・・・・国際金融公社 IDA・・・・・・・・・・・・・・・・・国際開発協会 IMF・・・・・・・・・・・・・・・・・国際通貨基金 ICAO・・・・・・・・・・・・国際民間航空機関 |
ITU・・・・・・・・・・・・・・・国際電気通信連合 UPU・・・・・・・・・・・・・・・・・・・万国郵便連合 WMO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・世界気象機関 IMO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国際海事機関 WIPO・・・・・・・・・・・・世界知的所有権機関 IFAD・・・・・・・・・・・・・・国際農業開発基金 UNIDO・・・・・・・・・・・・・国連工業開発機関 IAEA・・・・・・・・・・・・・・・・国際原子力機関 GATT関税および貿易に関する一般協定 CD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・軍縮会議 |
|
(1) |
白ロシアは1991年9月19日をもって国名を「ベラルーシ」,上ヴォルタは,1984年8月4日をもって国名を「ブルキナ・ファソ」,ビルマは1989年6月22日をもって国名を「ミャンマー」と変更した。 |
|
(2) |
国連を始めとする国際機関においてカンボディアを代表するのは最高国民評議会(SNC)である。 |
|
(3) |
南北イエメンは1990年5月22日に統合宣言を行った。 |
|
(4)(*) |
旧ユーゴースラヴィアが事実上解体した後,セルビア及びモンテネグロは新たに「ユーゴースラヴィア連邦共和国」(新ユーゴー)を編成したが,1992年9月22日,国連総会決議によって新ユーゴーは国連総会の作業への参加は拒否された。新ユーゴーの地位に関しては他の国際機関においても同様の問題がある。 |
|
(5) |
ILO理事会は,政府代表理事28人,労働者および使用者代表理事各14人から成っているが,◎は政府代表理事を出している国のみに付した。 |
|
(6) |
EEC(欧州経済共同体)は会議等に参加できるが,選挙活動及び法的事項には参加できない。 |
|
(7) |
UNESCOは170の加盟国に,3の準加盟地域(オランダ領アンティル,英領ヴァージン諸島,アルバ)を有する。 |
|
(8) |
IBRDの理事は,職権上,IDA,IFCの理事を兼務することになっている。 |
|
(9) |
UPU連合員177には,リストに記載されていない「連合王国政府がその国際関係を処理する海外領土」及び「オランダ領アンティル及びアルバ」が含まれる。 |
|
(10) |
WMO構成員としては,加盟国161のほかに,リストに記載されていない香港,仏領ポリネシア,ニュー・カレドニア,オランダ領アンティル(キュラサオ),英領カリビアの5つの領域がある(英領カリビアは執行理事国)。 |
|
(11) |
IMOは,137の加盟国のほかに,2つの準加盟地域(香港,マカオ)を有する。 |
|
(12) |
IFADは理事18人および代表理事の17人から成っているが,◎は理事を出している国のみに付した。 |
|
(13) |
GATT加盟国105には2地域(香港,マカオ)が含まれる, |
|
(14) |
事実上GATTが適用される国(地域) 新たな独立国などで従来宗主国がGATTを受諾し,適用していたものは,GATT第26条5項(C)に基づき,その対外通商関係につき完全な自治権を取得した旨の通報が旧宗主国により行われ,GATTに正式加盟するまで,相互主義に基づき事実上GATTの適用を受けている(ただし,上表中,カンボディアは,1962年6月5日にGATT第33条に基づき加入を認められていたが,まだ加入議定書を受諾しておらず,1958年11月17日の決定により事実上の適用を受けている)。 |
|
(15) |
リヒテンシュタインは,経済同盟国(スイス)が代わってGATTを受諾し,GATTが適用される。 |
|
(16) |
チェッコ・スロヴァキア共和国は93年1月1日にそれぞれチェッコ共和国,スロヴァキア共和国として独立。1月19日に両共和国は国連に加盟。これにより国連加盟国総数は180となった。 |
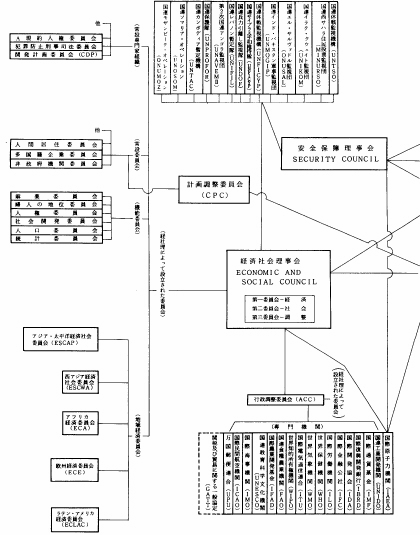
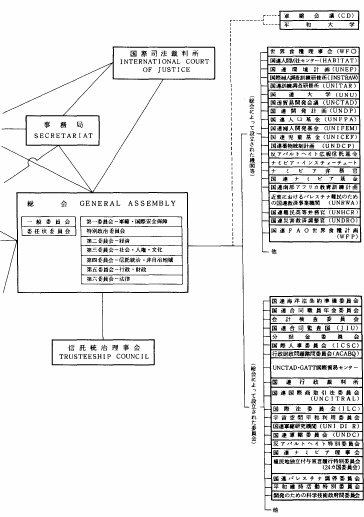
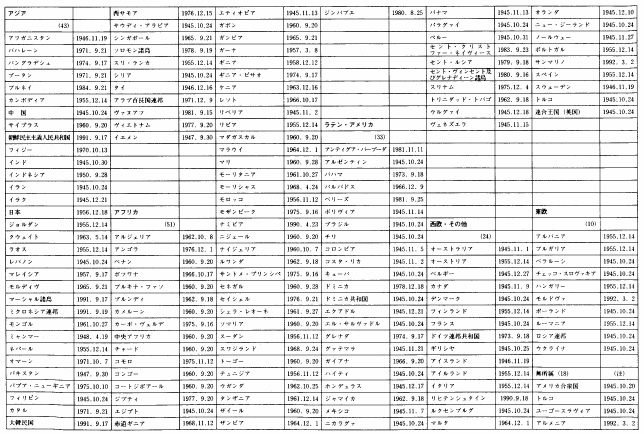
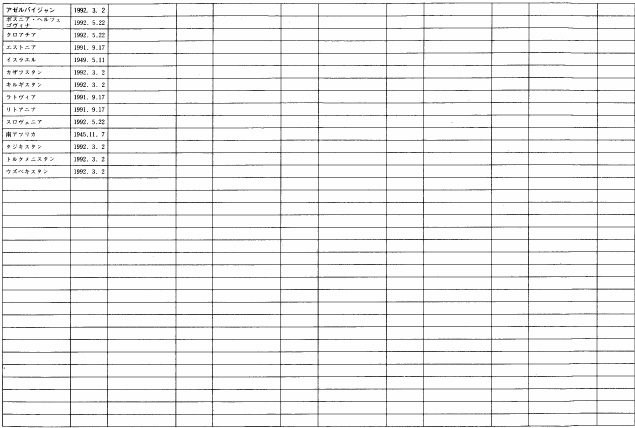
(注) アメリカ合衆国は会議・選挙目的には西欧・その他のグループに属する。
トルコはアジア及び西欧・その他の両グループに属するが,選挙では東欧グループに属する。
ユーゴースラヴィアはどのグループにも属さないが,選挙目的に於いては例外的に東欧グループに属する。
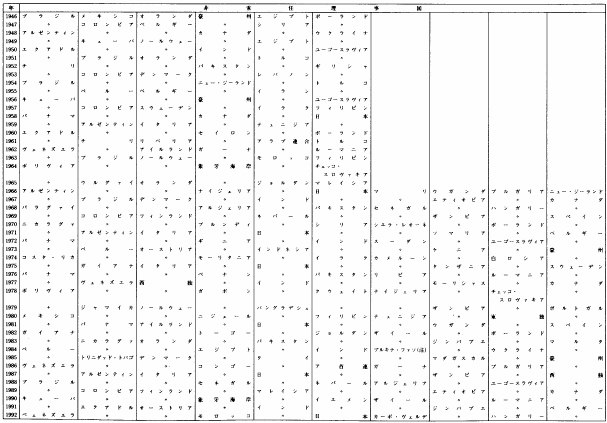
(注) 上ヴォルダは1984年8月4日をもって国名を「ブルキナ・ファソ」と変更した。
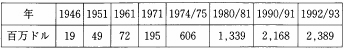
(注) 1974年以降は2年間予算をとっている。また,1992/93は当初予算。

|
(注) |
通常3年間は分担率を変更しない。また,本グラフ中の数字は小数点2位を四捨五入している。 ドイツの分担率については,89年までは西独の分担率で示した。 ロシアの分担率については,89年まではソ連の分担率(ウクライナ,白ロシアを含まない),92年はバルト三国を含む。 |
1991年3月末現在
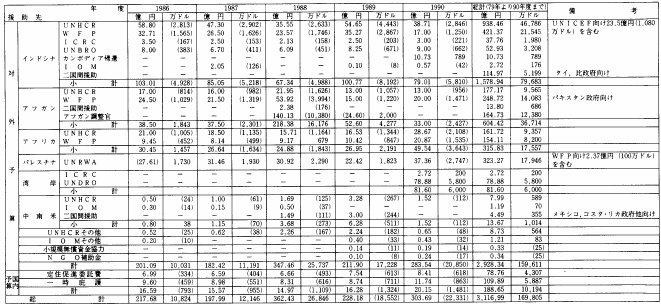
|
(注) |
換算は,その年の支出官ノートによる。86年度:1ドル=209円,87年度:1ドル=163円,88年度:1ドル=135円,89年度:1ドル=123円,90年度:1ドル=136円で換算。 |
1. 文 化 関 係
(1) 留 学 生
出身国(地域)別留学生数(91年5月1日現在,( )内は国費留学生数で内数)
|
1. 中 国19,625人(1,177人) 2. 韓 国 9,843人( 656人) 3. 台 湾 6,072人( - ) 4. マ レ イシア 1,742人( 262人) 5. 米 国 1,257人( 154人) 6. インドネシア 1,032人( 340人) |
7. タ イ 898人( 448人) 8. フ ィ リ ピ ン 477人( 271人) 9. 香 港 455人( 54人) 10. バングラデシュ 423人( 182人) その他 3,242人(1,675人) 計 45,066人(5,219人) |
(2) JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)国別招致数
(単位:人)

(単位:人)
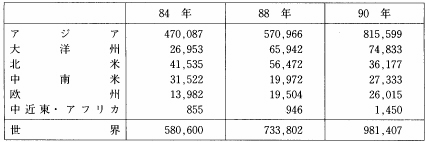
(出所) 国際交流基金資料
| ジャパン・ウィーク・イン・マルタ | 91年9月 |
| モスクワ日本週間 | 91年9月~11月 |
| ジャパン・フェスティバル(英国) | 91年9月~92年2月 |
| ロス・アンジェルス日本月間 | 91年10月~11月 |
| カナダ日本月間 | 91年10月~11月 |
| ポーランド日本文化月間 | 91年11月 |
| モントリオール日本文化紹介月間 | 92年1月~2月 |
| 中近東日本文化週間(ア首連,オマーン,カタル) | 92年2月 |
| 極東日本週間(ユジノサハリンスク,ウラジオストック) | 92年8月~9月 |
| アンカレッジ日本週間 | 92年9月~10月 |
| トロント・ジャパン・フェスト92 | 92年10月 |
| ブルガリア日本月間 | 92年10月~11月 |
| イスラエル日本文化祭 | 92年10月~93年3月 |
| 日印国交40周年記念事業 | 92年 |
| 日中国交正常化20周年記念行事 | 92年 |
| 東南アジア祭 | 92年8月~12月 |
| 東京国際演劇祭 | 92年8月~10月 |
| 東京国際映画祭 | 92年9月~10月 |
| アジアマニス | 92年9月 |
| 第3回C.I.O.F.F.アジア民族芸能祭 | 92年5月20日~5月24日北九州 |
| 中近東映画祭 | 92年10月 |
| '92年東京国際ブックフェア | 92年10月~11月 |
| 英国ロイヤル・オペラ,バレエ公演 | 92年5月~7月 |
| イスラエル映画祭 | 92年12月 |
地域別実績(交換公文署名ベース)
(単位:百万ドル)
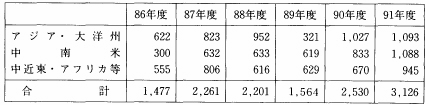
(イ) 国際交流基金92年度予算
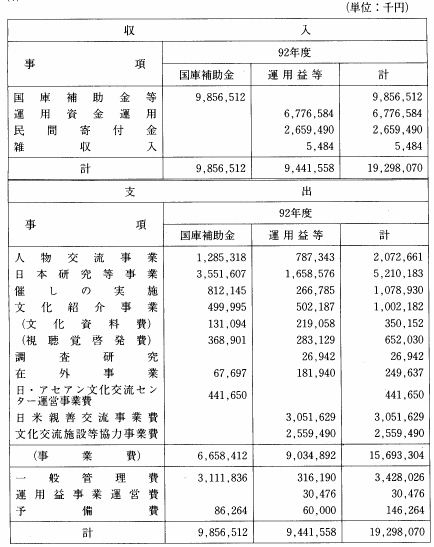
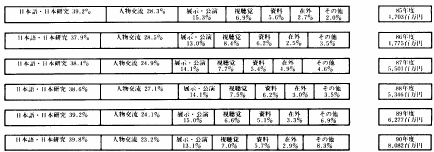
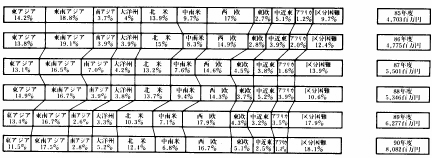
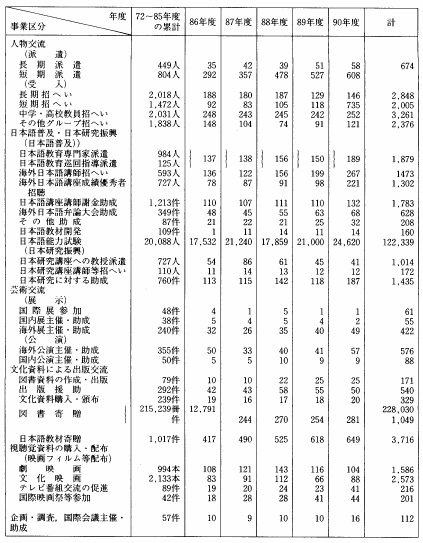
(1) 地方で開催する行事
(イ) 一口外務省
(口) ミニ外務省(91年10月日南,11月豊岡,92年1月柴田町,6月松山)
(ハ) 国際フォーラム(91年9月福岡,11月広島,新潟,92年2月仙台,7月山形)
(二) 国際化相談キャラバン(91年11月豊橋,津,92年2月熊本,5月和歌山)
(ホ) 国際化推進シンポジウム(91年8月宇部,9月京都,他年間20回程度)
(イ) 国際交流人材育成講座(92年1月及び7月)
(口) 地方の新聞社に対する国際情勢等説明会(91年11月,92年2月,3月,6月)
(1) 定期刊行物
(イ) 月刊「外交フォーラム」外務省編集協力・世界の動き社発行
(口) 月刊「世界の動き」外務省編集・世界の動き社発行
(ハ) 月刊「国際資源」外務省経済局編集協力・国際資源問題研究会発行
(二) 月刊「アピック」外務省協力・国際協力推進協会発行
(ホ) 隔月刊「外交」外交知識普及会発行
(へ) 隔月刊「Theインターナショナル・スポーツ」外務省対外スポーツ交流情報センター編集
(ト) 隔月刊「ワールド・プラザ」外務省国際文化交流情報センター編集
(イ) 「第18回主要先進国首脳会議-ミュンヘン・サミット」(事前広報)
(口) 「日米関係」(ブッシュ大統領訪日事前広報)
(ハ) 「もっと知りたい!国連平和維持活動Q&A」
(二) 「南極の話」
(ホ) 「われらの北方領土'92年版」
(ヘ) 「外務省」
(ト) 「海外生活の手引(北米編)」
(チ) 「海外生活の手引(東アフリカ編)」
(リ) 「世界の国一覧表'92年版」
(ヌ) 「第18回主要先進国首脳会議-ミュンヘン・サミット」(事後広報)
(ル) 「欧州連合の誕生と日本」
(ヲ) 「経済協力Q&A」(改訂版)
(ワ) 教師用ODAハンドブック
(力) 「世界の中の日本シリーズ1-国際社会で活躍する日本人-」
(ヨ) 「ザ・フォーラム'91-人賞者論文集」
全国で約700回開催
「国際フォーラム91 名古屋」(91年6月24日)
「国際フォーラム91 福岡」(91年9月23日)
「国際フォーラム91 広島」(91年11月16日)
「国際フォーラム91 新潟」(91年11月23日)
「国際フォーラム92 仙台」(92年2月29日)
「さわやかワイド:PKO」(91年7月15~19日)
「24時間テレビ~地球のために何ができるか~:ODA」(91年7月28日)
「ワールド・ビジネス・サテライト:PKO」(91年8月30日)
「中村敦夫ザ・サンデー:PKO」(91年11月17日)
「情熱ワイド!ブロードキャスター:日米関係」(92年1月11日)
「竹村健一の世相をきる:日米関係」(92年1月12日)
「プレステージ~日米関係改善への提案~」(92年1月22日)
「月曜特集:華麗なる宮殿・迎賓館のすべて」(92年2月17日)
「ビッグ・モーニング~日本人が狙われている~」(92年3月18日)
「トゥナイト:ODA質と理念を検証」(92年3月30日)
(経済協力アニメ・ビデオ)
「地球号SOS」
(1) 定期購入資料
(イ) Japan Echo(英語・仏語:年5回,スペイン語:年2回)
(口) Japan Pictorial(英語ほか10か国語:年4回)
(ハ) Look Japan(英語・スペイン語:月刊)
|
(イ) |
The Japan of Today(英語ほか15か国語) |
|
(口) |
Japan Today(英語・仏語・スペイン語・タイ語) |
|
(ハ) |
Facts About Japanシリーズ(英語ほか6か国語,歴史・憲法・政治・文化・スポーツ等個別資料24種類,国際教育情報センター編集) |
|
(二) |
政策広報資料(Japan's Northern Territories,Reaching,Out,Japan's Global Initiatives,Japan's Contributions Following the Gulf Crisis,Japan's Post Gulf International Initiatives,Japan's Environmental Endeavors,The japanese Expeienxe,The fore-front of the Environmental Movement in Japan,国際平和協力法パンフレット,日中友好20年,KEIRETSU,日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集,プルトニウム等) |
|
(ホ) |
Economic Development of Modern Japan(英語ほか3か国語),Japan's Cultural History(英語ほか13か国語)とその他の資料 |
(イ) 外務省企画海外広報映画(ビデオ)
|
(あ) |
「電子立国・日本の自叙伝」,「島に刻まれた事実-北方領土」,「日本国天皇陛下及其家族」,「日本の環境保全1992」,「日本のリサイクル運動」,「熱帯雨林の再生」,「野鳥を守る人々」,「クジラと共に生きる」,「湾岸危機と日本」 |
|
(い) |
TV用広報ビデオ「ジャパン・ビデオ・トピックス」毎月1本 |
(口) 「生け花」カレンダー
(ハ) 広報用写真
(あ) 現代日本紹介写真パネル
(い) 貸出し用写真「Japan in Slidse」
(う) 各種政策広報用写真
オピニオン・リーダー,報道関係者等の招待者数
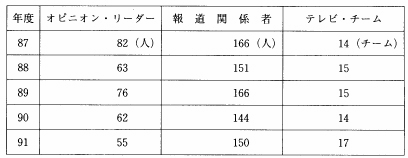
1. (1)地域別在留邦人数
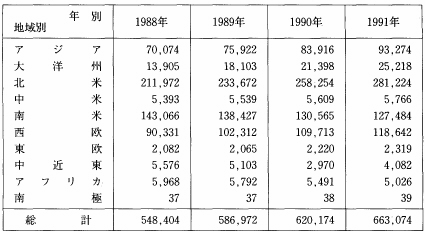
(出所) 外務省「海外在留邦人調査統計」
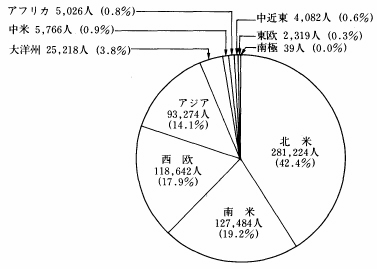
(出所) 上に同じ
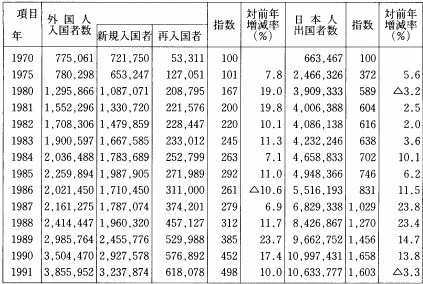
(出所) 法務省「出入国統計年報」
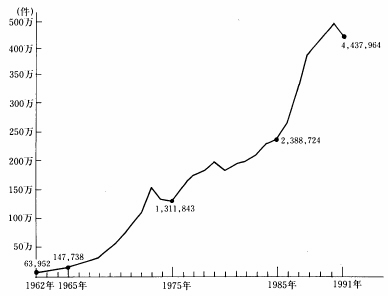
(注) 在外公館分を除く
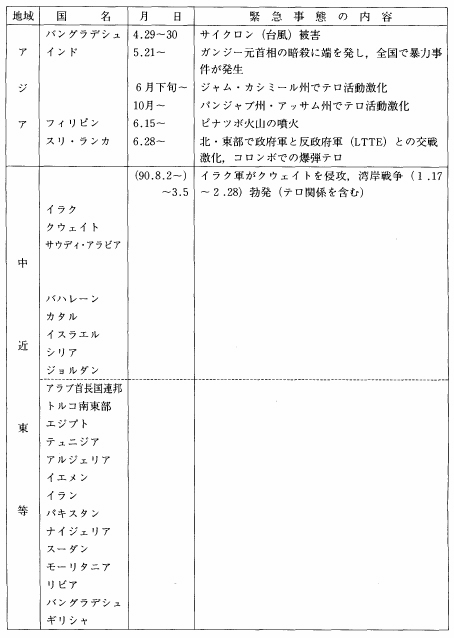
1991年の緊急事態事例(その2)
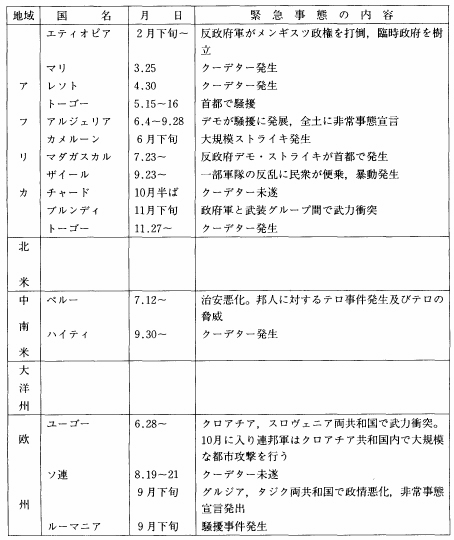
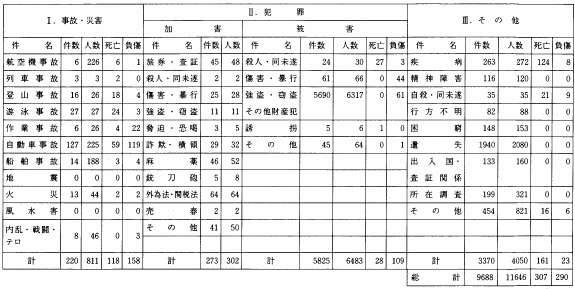
注:「件名」の説明
1.内乱・戦闘・テロ・・・・・本項目は特定邦人が巻き込まれたケースについてのみ集計し,不特定多数の邦人を巻き込む緊急事態については別途累計。
2.犯罪加害(旅券・査証)・・・不法滞在,不法就労等。
3.行方不明・・・・・・・・グループツアーからはぐれた者,旅行の帰国予定日に帰らない者,留学中の子弟と音信不通になった者などの消息調査等。
4.困窮・・・・・・・・・・旅行中所持金を紛失,費消した旅行者への本邦親元からの送金援助など。
5.出入国・査証関係・・・・・犯罪に分類されないもので,再入国トラブルの援助等。
6.所在調査・・・・・・・・不動産の相続登記手続き等に係る海外の在留邦人の住所調査等。

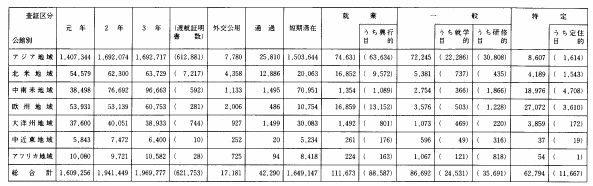
(91年8月~92年12月)
1. アジア・太平洋