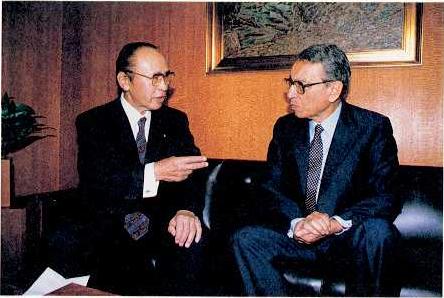
前節で述べたような転換期の諸問題を克服し、世界の平和と繁栄を確保するための日本の責任と役割は極めて重要である。日本の果たすべき役割は、その国力の増大に伴って、経済面に限らず、政治面に及ぶ上、地球的規模の問題をも含み顕著に拡大している。現に日本は、軍備管理・軍縮、地域紛争の解決、旧ソ連支援、開発途上国の民主化支援、中東和平、環境問題などの問題にも主体的に参画しており、また、92年の国際平和協力法の制定により、国連平和維持活動に本格的に参加するようになったが、今後このような貢献の必要性はますます強まろう。その際、国際協力のための官民の即応体制、例えば、医療の専門家や輸送手段を一層整備・強化することが期待される。
国際社会の相互依存関係の深まり、経済、科学技術、環境などの分野の相対的重要性の高まりという情勢の下で、今や日本の行動は、これからの国際秩序の構築に関わりのある問題のほとんどすべてに影響を与える。また、国際社会の期待に応え、このような問題に取り組んでいくことは日本の平和と繁栄を確保するためにも不可欠である。日本が世界的規模で経済活動を展開し、今日の繁栄を築きあげてくることができたのは、国民の英知と努力に加え、全体として世界の平和と安定が維持されてきたからであることを忘れてはならない。
日本外交がより世界的な広がりをもつものとなっている今日、日本は、国際社会に対し、どのような世界を目指し、そのためにどのような目標を追求しているのかを明らかにし、その国力にふさわしい指導力を発揮していかなければならない。このような努力を通じてこそ、日本は国際社会の中で「名誉ある地位」を占めることができると考えられる。
この点に関して、宮澤総理大臣は、これまでの施政方針演説等において、日本が世界の人々と共に追求すべき共通の目標として、平和、自由及び繁栄を挙げている。このような目標を実現するために、以下に見るように、世界経済の繁栄の確保、世界の平和と安定の確保、自由、民主主義といった普遍的価値の促進、環境問題や難民問題などの地球的規模の問題に対する積極的取組を指針として、日本外交を展開していくことが重要である。
先進国経済の回復が遅れている中にあって、世界経済の持続的成長のための政策協調の一環としての日本の役割は一層重要となっており、内需主導型経済運営の堅持、日本経済と世界経済の一層の調和を図っていくことが必要である。日本は92年8月に総事業規模10兆7,000億円にのぼる総合経済対策を決定したが、これは、日本経済を刺激するとともに、7月のミュンヘン・サミットにおける世界経済のより力強い持続的な成長を実現するための政策協調の合意にも応えるものであった。また、日本は、92年6月に今後の政策運営の長期的な指針として、労働時間の短縮、生活関連資本の整備や住宅建設の促進、内外価格差の是正などを内容とする生活大国5か年計画を策定した。この計画を通じ、国民生活の質を国力に見合ったものとし、日本経済の運営の力点を生産者重視から消費者や生活者重視に変えていくことは、日本経済の世界経済との調和の促進に資するものである。
また、日本は、戦後、GATTに基づく多角的自由貿易体制の下での世界貿易により最大の利益を享受してきた国の一つであり、新たな国際貿易のルール作りを目指すウルグァイ・ラウンド交渉を早期に成功させ、多角的自由貿易体制を維持・強化することが死活的に重要である。交渉は既に最終段階にあるが、日本としても交渉の成功に向け引き続き努力していかなければならない。
開発途上国や旧東側諸国の発展は世界全体の繁栄と不可分の関係にある。開発途上国及び中・東欧諸国や旧ソ連諸国を世界経済体制の中に統合し、世界経済全体の規模を広げることは、世界経済の発展を確保していくためにも重要である。また、地球環境問題や難民問題といった地球的規模の問題は、先進民主主義諸国だけで解決できるものではなく、旧東側諸国や開発途上国による取組や協力が不可欠であり、先進国と旧東側諸国、開発途上国は相互依存関係にある。
日本は開発途上国の飢餓や貧困などの問題に取り組み、これらの国が進めている経済・社会開発や住民の福祉向上のための努力を積極的に支援してきている。91年の日本の政府開発援助(ODA)の実績は1兆4,840億円であり、総額では世界第1位である。また、日本は87年から92年まで開発途上国に対する資金の流れを促進するために総額650億ドルの資金還流計画を実施した。ODAは日本がその国際的な責任と役割を果たしていく上で重要な政策手段であり、今後とも、その量的拡充と質的改善に努めていく必要がある。
転換期の世界の平和と安定を確保するための重要な課題として、核兵器などの大量破壊兵器及びミサイルの拡散を防止し、また、通常兵器の移転の透明性を増大させるとともに、その適切な抑制を図ることが重要である。戦後一貫して平和主義を掲げ、非核三原則、武器輸出三原則といった独自の政策をとってきた日本がこの分野において指導的役割を果たすことは国際的にも重要である。
通常兵器については、日本などの提案により移転の透明性向上を目的とした国連軍備登録制度が92年1月に成立したことを受け、92年の6月には軍備の透明性の向上を図るための会合を東京で開催するなどその円滑な実施のために貢献した。
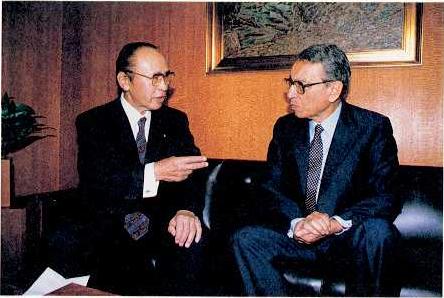
国連本部におけるブトロス=ガーリ国連事務総長と渡辺外務大臣の会談(92年9月)
また、日本は92年4月に成立した原子力関連資機材輸出規制枠組みの事務局を引き受けることとした。旧ソ連諸国については、日本は、ロシア以外の国が非核兵器国として核兵器不拡散条約(NPT)に早期に加入するよう働き掛けを行い、また、旧ソ連諸国からの大量破壊兵器関連の科学者・技術者の流出を防止するために設立される国際科学技術センターに対し、2,000万ドルの資金協力を表明している。91年に続き、92年6月に日本で国連軍縮会議を開催したのも、軍備管理・軍縮の分野において積極的役割を果たそうという意欲の現れである。
国連などの場を通じ、地域紛争の防止、解決のための国際的努力に参画していくことも重要な政策課題である。このため、日本は、国連の平和維持活動に積極的に協力しており、資金面での協力に加えて、既にカンボディア及びアンゴラには平和協力隊を派遣した。先に述べたように、国連の平和維持活動の重要性は一層高まっており、日本としては、十分な資金協力と人的貢献を行っていくことが必要である。また、日本は、92年以来国連安全保障理事会非常任理事国として、世界各地の地域紛争の問題に取り組んでおり、旧ユーゴースラヴィア及びソマリアにおける民族紛争により生じた被災民に対し、それぞれ2,000万ドルを超える人道援助を行い、また、ソマリアについては、人道上の救援活動のための安全な環境を確立することを目的とする安全保障理事会決議794を受けて設立された国連ソマリア信託基金に対して1億ドルの拠出を行った。さらに、中東和平については、地域の諸問題に関する多国間協議において、環境問題作業部会の議長を務めるなどの建設的関与を行っている。カンボディア問題については、92年6月に東京でカンボディア復興閣僚会議を開催し、1.5億ドルから2億ドルの支援を表明するとともに、和平協定の完全な実施を確保するための外交努力をタイを始めとする関係諸国と共に行っている。

カンボディア復興閣僚会議後の記者会見(左より、UNTAC明石特別代表、シアヌーク殿下、柿澤政務次官、ドレーバー共同議長)(92年6月)
また、国際の平和と安全のための国連の機能を強化するためには、国連自身が時代の変化に適合して変革していくことが必要であり、特に平和維持機能の中核を担う安全保障理事会の信頼性と実効性を強化していくことが重要である。日本は、このような問題意識を92年1月の安全保障理事会首脳会議において提起し、9月の国連総会においては、国連自らがこの問題の取組を開始すべきであるとの提案を行った。
特に、アジア・太平洋地域における平和と安定の確保は、日本外交の一つの柱である。この地域の安全保障のためには、米国の存在が不可欠の重要性を有しており、日本は在日米軍に対する最大限の接受国支援を行ってきている。また、北方領土問題、朝鮮半島問題、カンボディア問題といった個々の地域における紛争や対立を解決するとともに、東南アジア諸国連合(ASEAN)拡大外相会議を活用して域内各国相互の信頼感を高めるために全域的な政治対話を促進することが重要であり、日本は、このような二本立ての取組の必要性を92年7月の宮澤総理大臣の米国訪問などの機会に主張してきている。こうした考えに立って、日本は、カンボディア問題などに取り組むとともに、7月のASEAN拡大外相会議における政治・安全保障問題についての議論に積極的に参加した。さらに、この地域における将来の安全保障協力のあり方についても、日本は域内諸国との対話を進めている。また、開発途上国の多いこの地域では、経済開発を通じて域内諸国の政治的、社会的強靭性を高め、地域の安定を高めることが重要であり、日本は、そのODAの5割以上をこの地域に充てている。
真の平和は、単に紛争がないというだけにとどまらず、自由、民主主義、人権といった価値を保障するものでなければならない。このような観点から、日本は、旧ソ連、中・東欧、アジア、中南米などにおける民主主義と市場経済導入のための改革に対する支援を重視し、積極的な協力を実施している。
91年8月の保守派によるクーデターの失敗以降、旧ソ連諸国において市場経済化、民主化を目指す改革が本格化した。対日関係においては、「法と正義」に基づく外交を推進し、勝者と敗者の関係を乗り越えていかなくてはならないとの明確なメッセージがソ連(当時)よりもたらされるに至り、日本は、10月、25億ドルからなる支援策を決定した。日本は、これを始めとして、次の支援策を実施しており、日本の支援総額は約30億ドルに達する。
第1に、市場経済への円滑な移行を促すための技術的支援として、研修員の受入れ、専門家の派遣等を積極的に実施している。
第2に、緊急人道支援として、無償支援の分野では90年12月、92年1月にそれぞれ10億円、65億円の食糧、医薬品等の供与を決定し、これらを実施した。さらに、92年10月には、1億ドルの緊急人道支援を決定した。有償支援の分野では、90年12月に発表した食糧、医薬品等の1億ドルの日本輸出入銀行(輸銀)融資については、92年9月に関連文書の交換が行われた。また、上記25億ドルの支援策には食糧、医薬品、輸送手段等のための5億ドルの輸銀融資が含まれている。
第3に、貿易経済活動円滑化のための支援として、25億ドルの支援策の中で、18億ドルの貿易保険引受け及び2億ドルの輸銀信用供与を行う用意がある旨表明した。
以上のような二国間での支援のほか、日本は、多数国間での協力として、92年10月の旧ソ連支援東京会議の主催、国際科学技術センターの活動のための2,000万ドルの拠出、240億ドルの支援策における貢献、債務繰り延べにおける協力等の支援を行っている。
89年11月のベルリンの壁崩壊以来の中・東欧諸国の改革努力に対して、日本は技術支援、食糧援助、金融支援などを積極的に実施してきており、日本の支援総額は約45億ドルに達する。また、アジアにおいては、モンゴルの改革努力を支援するため、日本は、世界銀行との共同議長の下、91年9月の第1回モンゴル支援国会合に続き、92年5月に第2回会合を東京で開催した。
日本はODAの実施に際しても、自由、民主主義といった普遍的価値の促進を重視している。92年6月に決定した政府開発援助大綱の中で、被援助国の軍事支出、大量破壊兵器等の開発・製造、武器の輸出入等の動向とともに、民主化の促進、市場経済導入努力、基本的人権及び自由の保障状況に十分に注意を払うことを原則とした。原則に盛られた諸項目は、日本外交全体で取り組むべき課題であるが、外交政策の重要な手段である援助を通じてもこれらの価値の実現を図っていく必要がある。これは、被援助国政府が、原則に盛られた諸項目等を内容とする「良い統治」(開かれた民主的な統治)を実現していかなければ、いくら援助を続けても、途上国において持続的成長を遂げることが困難であるとの考えによる。
同時に、旧東側諸国や開発途上国に対する支援に当たっては、欧米諸国を始めとする先進国も今日の人権や民主主義、市場経済の実現には長い年月を要したことも踏まえ、性急に結論を求めるのではなく、対話を通じてその進展を着実に促していくことが重要である。
以上に加え、世界の平和、自由及び繁栄を長期的に確保していくためには、環境問題、難民問題等の地球的規模の問題に取り組んでいくことが重要である。日本はこれらの問題の解決を重要な政策目標としており、政府開発援助大綱においても、環境問題を始めとする地球的規模の問題への取組を重点事項としている。また、これらの問題については、対症療法のみに頼るのではなく、問題発生の根源に取り組むことが重要である。
地球環境問題については、日本は92年6月の国連環境開発会議(UNCED)及びその準備過程において気候変動枠組条約等の作成や森林問題その他環境と開発に係る諸問題への対応に当たり、先進国と開発途上国との間の調整のため建設的役割を果たすなど、この会議の成功に貢献した。また、日本は、ODAの供与を通じた開発途上国の環境保全及び環境問題への対処能力の向上を重視しており、この会議においては、92年度より5年間にわたり環境分野への援助を9,000億円から1兆円を目途として大幅に拡充し、強化することに努めることを明らかにした。今後は、UNCEDにおける合意を誠実に実施することが重要である。さらに、地球環境問題の根本的な解決のためには、問題の一因となっている人口の増加といった問題に一層真剣に取り組むとともに、成長と環境保全の両立を図るために技術革新を進めていくことが重要である。
難民問題については、日本は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの国際機関を通じ、あるいは二国間援助によって、インドシナ難民、アフガン難民、カンボディア難民、ミャンマー回教徒難民、パレスチナ難民、アフリカ難民、旧ユーゴースラヴィア避難民などに対し、資金協力、食糧援助などの難民援助を実施してきている。92年の日本のUNHCRに対する拠出額は1億1,900万ドルであり、その額は米国に次ぎ各国中世界第2位である。しかし、難民問題の根本的な解決のためには、国連や関係国が難民発生の原因である紛争の未然防止に努めることや紛争を平和的に解決するための外交努力を強化することが不可欠である。