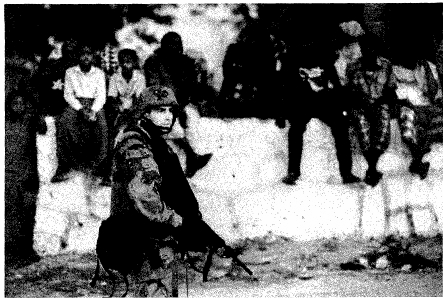
第1節 転換期の国際情勢
1. 概 観
91年12月のソ連の解体により、東西冷戦は終わり、世界は歴史の転換期に特有の不安定な時期を迎えた。その後の世界の動きを見ると、ロシアの不安定な状況、兵器拡散問題、旧ユーゴースラヴィアにおける紛争の激化などの問題に加え、先進国経済の低迷、依然として深刻な開発途上国の問題といった暗い材料も多い。先進民主主義諸国では、一時、冷戦の終結により、世界の将来に対する期待感が広がったが、これは長くは続かず、その後の国際情勢の展開、経済・社会問題の深刻化の中で、先行きに対する不安感、不透明感が増大している。こうした中で、国際社会は協調して転換期の諸問題を克服していくことが求められている。
(1) 旧 ソ 連
ソ連において85年にゴルバチョフ政権が誕生して以来、欧州を中心に東西関係は大きく変化してきたが、91年8月のソ連における保守派のクーデターとその失敗、さらに12月のソ連の解体により、ソ連共産主義は国家イデオロギーとしての権威を失い、東西冷戦構造は消失した。
ソ連の解体後に誕生した独立国家共同体(CIS)においては、ロシアがソ連と継続性を有する同一の国家として認識され、CISの中で指導的地位を占めた。ロシアのエリツィン大統領は、大胆な民主化と経済改革に乗り出し、共産党組織の解体を進め、さらに、92年1月に価格自由化などの急進的な経済改革に着手した。また、ロシアは、国際通貨基金(IMF)に加盟するべく、急進的な改革を目指した「経済改革メモランダム」を3月にIMFに提出し、6月にはIMFに正式に加盟した。さらに、6月には、「経済改革深化プログラム」を策定したが、これらは経済改革に対するロシア指導部の熱意を示すものであった。
ロシアは先進民主主義諸国との外交を強化しており、エリツィン大統領は、92年2月に米国を訪問したのに続き、6月にも米国を訪問し、その際、米露両国が基本的諸価値を共有しつつ協力関係を進めるという「パートナーシップと友好のための憲章」が発出された。また、ロシアは、英国、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア、韓国、中国との間でも類似の文書を発出し、関係を強化しようとしている。
このような中で、ロシアは先進民主主義諸国にとり、対立関係にある国家としてではなく、国際社会の建設的なパートナーとなろうと努力している国として認識されつつある。ロシアの改革に対する国際的な支援の努力は更に促進され、支援の対象分野が拡大するとともに、支援の枠組みは強化された。92年1月のワシントン会合に始まり、5月のリスボン会合、10月の東京会合と旧ソ連支援調整国際会議が相次いで開催されるとともに、今後の支援の調整のために、ロシア以外の旧ソ連諸国を対象とする国別調整グループの設置が合意された。また、92年7月のミュンヘン・サミットにおいては、240億ドルの金融支援、技術的支援、旧ソ連諸国への市場開放などの包括的な支援策が打ち出されるとともに、旧ソ連型原子力発電所の安全性向上のための行動計画が合意された。
しかし、ロシアが様々な不安定要因を抱えていることにも注意しなければならない。国内的には、年間4桁台のインフレ、大幅な生産低下など経済問題が益々深刻化する一方、経済改革に対する国内の抵抗は根強く、IMFとのスタンド・バイ取極をめぐる交渉は難航している。また、ロシアの政治体制は三権分立、法の支配などの原則を含む新憲法作成作業が遅々として進まず、大統領と議会の対立、民族主義派の台頭など、民主化が定着したとはなお言えない。旧ソ連諸国との関係でも、沿ドニエストル、タジキスタン、アブハジアなどにおける民族問題が、ロシアにとって在外ロシア人の保護や旧ソ連諸国の政治的安定の観点から大きな問題となっている。さらに、ロシアと先進民主主義諸国との関係強化が進む一方、日本との関係では、北方領土問題が未解決であり、92年9月のエリツィン大統領の突然の訪日延期決定の後、日露関係改善の努力が続けられている状況である。
このようなロシアの状況が今後どう変わっていくかを予測するのは難しい問題である。しかし、依然として膨大な量の核兵器及び近代兵器を有しており、また、多くの民族を抱えるロシアが不安定化すれば、世界に深刻な問題を及ぼすことは間違いなく、ロシアの問題は転換期の世界が直面する最大の課題の一つである。
冷戦の終焉を背景に、北大西洋条約機構(NATO)は、東側ブロックに対抗する軍事機構としての性格を大きく変化させ、91年12月には旧東側諸国に対する協力を目的とした北大西洋協力理事会(NACC)が発足した。また、米露両国の首脳は、お互いに潜在敵国とみなさないことを明らかにし、両国は核軍縮に積極的に取り組んでいる。91年9、10月の戦術核の廃棄などを内容とする米ソ核軍縮提案に続き、92年1月にも米国とロシアは核軍縮提案を行い、6月の米露首脳会談においては、双方の戦略核弾頭数を現保有量の約3分の1にまで削減することを含む画期的な内容の戦略兵器削減合意が達成された。この合意は、第2次戦略兵器削減条約(STARTII)となり、93年1月の米露首脳会談で署名された。
このように米露間の核軍縮が進められている一方、兵器の拡散問題に対する国際的な取組の重要性が増大している。一部の開発途上国においては、米ソ二極構造の下での抑制が失われた結果、核兵器、化学兵器等の大量破壊兵器やミサイルの拡散の危険性はむしろ増大している。湾岸危機の際のイラクや北朝鮮の核開発疑惑はこの例である。また、旧ソ連諸国の現下の不安定な状況の中で、これら諸国から大量破壊兵器に関連する物質や科学者・技術者の流出の危険性があることも深刻な問題である。さらに、ロシアとウクライナの確執は、旧ソ連諸国の核兵器の管理に対する懸念を惹起している。
このような問題に対しては、まず、核兵器不拡散条約(NPT)を始めとする国際的な不拡散体制への各国の参加を促進して、その普遍性を高めることが重要であり、91年から92年にかけ南アフリカ共和国、中国、フランス等がNPTにそれぞれ加入したこと、92年秋に国連総会で化学兵器禁止条約が採択されたことは、こうした方向に向けての好ましい動きである。また、不拡散体制の実効性を強化することも重要であり、このため、国際原子力機関(IAEA)による特別査察制度の活用や大量破壊兵器関連資機材の輸出管理体制の整備が図られている。さらに、旧ソ連諸国からの兵器や技術の拡散防止については、輸出規制調整委員会(ココム)協力フォーラムなどによる国際的な努力が行われており、また、大量破壊兵器関連の科学者・技術者に平和目的の研究プロジェクトを提供する国際科学技術センターが日本、米国、欧州共同体(EC)等の協力により設立されることとなった。
同時に、通常兵器の国際的な移転について、その透明性を増大させ、適切な抑制を行うことが重要になっている。各国の安全保障環境に応じた自衛のための通常兵器取引は必要であるが、無制限な通常兵器の移転は国家間の不信感や懸念を高めたり、地域の不安定化をもたらす可能性があるからである。この問題への対応にあたっては、まず、兵器移転の透明性を向上することが必要との観点から、91年に、日本は、EC諸国等と共同で、国連軍備登録制度の創設を提案し、同年の国連総会でこれが決定された。また、米国、英国、フランス、中国、ロシアの5主要武器供給国は、併せて世界全体の武器の8割以上を供給していると言われており、通常兵器の移転問題において主要な責任を負う立場にあるが、この5か国が91年10月に地域の緊張を高める、あるいは不安定化させるような兵器移転の自制などを内容とする通常兵器移転ガイドラインに合意したことも注目される。また、開発途上国の経済発展のため必要な資源を確保するという観点からも過剰な軍事支出や兵器取引を抑制することが必要であり、日本が92年6月に決定した政府開発援助大綱にはこのような考えが盛り込まれている。さらに、中・東欧諸国、旧ソ連諸国に対し、その経済改革において軍民転換を進めることを求めていくことが必要であり、一部先進民主主義諸国においても、冷戦の終結による武器市場の縮小に対応して、軍民転換の円滑な促進が課題となりつつある。
米ソないし米露協調の進展という近年の国際環境の中で、世界各地において地域紛争の解決に向けての動きが見られた。91年10月のカンボディア和平合意の達成、同月の中東和平会議の開催を受けて92年1月に開始された中東地域の諸問題解決に向けた中東和平多国間協議、92年1月のエル・サルヴァドル和平合意、90年秋以降の朝鮮半島における南北対話の一定の進展などは、いずれもこのような好ましい動きである。
しかし、冷戦の終焉により、世界の全ての紛争が直ちに解決の方向に向かうわけではない。インドとパキスタンとの間のカシミール問題やギリシャとトルコとの間のサイプラス問題など、米ソ対立と直接の関係なく発生した紛争は依然として解決されておらず、中東和平問題についても、アラブ諸国とイスラエルとの間の直接交渉が開始されたとはいえ、引き続き粘り強い取組が求められている。また、アジア・太平洋地域においては、北方領土問題、朝鮮半島問題、南沙諸島問題などの未解決の問題が依然として残っている。
また、注意すべきことは、二極構造が崩壊した後、民族・部族対立や宗教的対立などに根差す紛争が発生する危険がかえって増大していることである。旧ユーゴースラヴィアやソマリア、旧ソ連諸国内における紛争はその典型である。しかも、このような紛争は、発生の原因が局地的であり、しかも複雑であるため、外部から行使し得る影響力には限界があり、その根本的解決には長期間を要する。旧ユーゴースラヴィア問題については、ボスニア・ヘルツェゴヴイナ等において、EC、欧州安全保障・協力会議(CSCE)、国連による幾多の調停努力及び和平工作、さらには国連平和維持隊の派遣にもかかわらず、まだ解決の目途は立っていない。しかし、このような紛争への対応は、歴史の転換期における国際社会のあり方を示す試金石となるものであり、日本としても、直接の利害関係がないからといって、決しておろそかにすることはできない。
冷戦終焉後、国連は、東西間のイデオロギー対立から解放され、国際の平和と安全の維持という本来の機能を取り戻してきており、特に、上述のような地域紛争に対応する上での国連の諸活動の重要性が増大している。国連平和維持活動は、1948年以来28件が設立されているが、そのうち半分以上の15件が88年以降に集中している。国連平和維持活動の規模も大きくなっており、カンボディアに派遣されている国連カンボディア暫定機構(UNTAC)や旧ユーゴースラヴィアに派遣されている国連保護隊(UNPROFOR)にはそれぞれ2万人以上の人員が投入されている。また、活動内容も多様化しており、停戦監視にとどまらず、文民による行政監視、食糧や物資の配給などの人道支援活動の支援も行うようになっている。
このように、世界各地の紛争を解決する上での国連の役割に対する期待が高まる中で、国連の平和維持機能のあり方をめぐる議論が活発化している。92年1月に行われた国連安全保障理事会首脳会議は、国連事務総長に対し、予防外交、平和の創出及び平和の維特に係る国連の能力の強化についての分析及び勧告を作成するよう要請し、これを受けて、ブトロス=ガーリ国連事務総長は、92年6月に「平和のための課題」と題する報告書を提出した。この報告書においては、信頼醸成、事実調査、早期警戒、仲介、調停、和平工作、紛争の拡大防止、平和維持活動、紛争解決後の復興・復旧といった一連の過程における国連の役割についての多くの興味ある提言が盛り込まれており、平和執行部隊の創設や予防的展開構想など、検討を要する問題も含まれているが、今後の国連のあり方を示すものとして注目される。
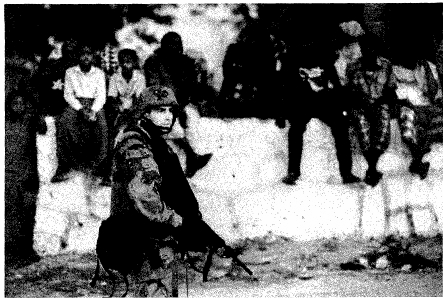
ソマリアの統一タスクフォースに参加する米軍海兵隊(92年12月)(AP)
この関連で、ソマリアにおいては、飢餓に直面する人々を救援するための人道上の活動によっても状況が一向に好転しない中で、92年12月、国連安全保障理事会は、人道上の救援活動のための安全な環境を確立するため、国連加盟国に対し、必要なあらゆる手段をとる権限を与える決議を採択した。この決議に基づき、米国を中心とする多くの国がソマリア国内の秩序の回復に努めているが、これは国際の平和と安定のための新たな協力形態として注目される。
このように、国連による平和のための努力は多様化しつつあり、国連の努力を支える国連加盟国の支援はますます重要になってきている。我が国としても、国連に対する協力を一層強化していくことが求められていると言える。
転換期の諸問題に取り組んでいく上で、世界経済の活力を維持・強化していくことがこれまで以上に重要になっており、特に、世界の平和と繁栄に主要な責任を有する先進民主主義諸国の経済の持続的成長を確保することは重要な課題である。しかしながら、近年、先進国経済は低迷しており、91年の経済協力開発機構(OECD)加盟国の実質経済成長率は0.8%に低下し、このうち米国経済は-1.2%、英国は-2.2%のマイナス成長に陥った。これは、先進国経済が83年から90年まで戦後最長の8年間連続の拡大局面(この間のOECD加盟国全体の実質経済成長率は平均で約3.6%)を経験したことと対照的である。
先進国経済の回復が遅れている中で、92年7月のミュンヘン・サミットにおいては、より力強い持続的成長の実現のための政策協調が合意されたが、92年、93年のOECD加盟国の実質経済成長率見通しはそれぞれ1.5%、1.9%にとどまっている。また、失業者はOECD加盟国全体で93年末には約3,400万人に達することが見込まれており、麻薬、犯罪、移民問題の深刻化ともあいまって、多くの先進国で、経済・社会問題が、経済の低迷の下で浮き彫りとなっている。世界経済の活力を担う先進国経済の回復は、世界全体の繁栄と発展のための基礎であり、そのためには、米国、日本、ドイツなどの主要国の景気回復とともに、世界経済の将来への信認を確保し、世界貿易の拡大と発展を図るためにウルグァイ・ラウンド交渉を早期に妥結することが求められている。
このような状況の下で、先進民主主義諸国においては、程度の差こそあれ、国内の経済・社会問題への対応に対する不満が現職の指導者や既存の政治体制に対する批判となって現れてきている。例えば、米国においては、湾岸戦争における勝利と冷戦の終焉によりブッシュ政権への支持率は一時世論調査で史上最高と言われる水準にまで上昇したが、景気の低迷と先行きへの不安が広がる中で、米国国民の関心が国内の経済・社会問題に集まり、92年11月の大統領選挙において12年振りに民主党政権が誕生することとなった。
冷戦が終わったことにより、東西イデオロギーの文脈にとらわれずに開発途上国の問題に取り組むことが可能になっている。第2次大戦後の開発途上国の独立の過程において、西側資本主義に対する反帝国主義的思想を歴史的背景として植民地解放運動が展開されたという事情もあり、南北問題は東西関係においてイデオロギー化されがちな面があった。しかし、冷戦が終わった今日、イデオロギーの問題から離れて、世界全体の平和と繁栄を確保していく上で不可欠の問題として、開発途上国の問題に本格的に取り組むことが必要となっている。
開発途上国の側では、アジア(モンゴル、ネパール、バングラデシュ等)、中南米(ニカラグァ、エル・サルヴァドル等)、アフリカ(ザンビア等)においては、民主化の推進、市場経済の導入に向けての真摯な努力が行われている国も見られる。また、最近の国連における動きや92年9月の非同盟首脳会議に見られるように、開発途上国の中で、先進国との対話を重視する姿勢が示されるなど、より穏健な建設的対話路線も出ている。さらに、一部の開発途上国の間では相互に貿易、投資等の面で協力を進めようとする動きもあり、92年11月に行われたG-15首脳会議(注:開発途上国間の協議・協力のための首脳レベルの会合の場)においては、このような、いわゆる南南協力の重要性についての認識が示された。
全体として、開発途上国の貧困、累積債務、人口増加などの問題は悪化しているのが実情である。例えば、先進国と途上国との所得格差は30年前と比べ拡大しており、また、90年、91年における開発途上国の1人当たり所得の伸びはマイナスとなった。開発途上国全体の債務残高も、91年末で約1兆3,510億ドルと推計されており、返済能力が回復していない債務国は依然として数多い。さらに、92年の世界の人口は55億人であるが、2050年には100億人に達すると見られており、このうち9割以上が開発途上国におけるものである。
ただし、開発途上国の状況は、国ごとに異なり、これら諸国を一体としてとらえることはできないことに注意する必要がある。例えば、アジアの一部の開発途上国が比較的高い成長を達成し、また、中南米において経済回復の展望が出てきている国があるのに対し、91年のアフリカの1人当たりの成長率は-2.0%である。したがって、開発途上国問題への取組にあたっては、各国の経済社会状況に応じたきめの細かい対応が必要である。
他方、先進国の側では、開発途上国の債務問題解決のための方策を種々打ち出してはいるものの、多くの国における財政困難を背景として、援助疲れや旧ソ連諸国、中・東欧諸国への関心の傾斜も見られ、開発途上国問題が昨今の先進国首脳の各種発言からともすれば欠落しがちであることは憂慮される。
以上のような問題に加えて、環境、難民等の地球的規模の問題も深刻である。このような問題は、その影響が国境を越えて他の国に及ぶため、一国のみによっては解決できず、国際協力によって取り組むことが不可欠なものである。

ミュンヘン・サミットにおける各国首脳(92年7月)
地球環境問題については、近年の国際的な関心の高まりを背景に、国連やサミット等の場を通じて具体的な取組が打ち出されており、92年の6月にブラジルで行われた国連環境開発会議(UNCED)においては、環境と開発に関するリオ宣言、21世紀に向けての行動計画であるアジェンダ21、及び森林についての原則声明が採択され、さらに、気候変動に関する国際連合枠組条約及び生物の多様性に関する条約が署名のため開放された。また、これを受けて7月のミュンヘン・サミットにおいては、UNCEDのフォローアップの重要性が強調され、国連総会においては、そのための機構として持続可能な開発委員会の概要がほぼ決定された。
今日、世界に存在している難民の数は1,800万人以上と言われており、その数は引き続き増加している。また、近年の問題として、冷戦終了後、地域紛争の表面化に伴い、旧ユーゴースラヴィアやソマリア等において新たな難民・避難民が発生している。このような難民問題は、人道的な問題であるのみならず、周辺地域の政治的安定にも係る問題であり、地域紛争と同様に、難民の発生の防止、一時保護、帰還、再定住の促進について包括的な取組が必要となっている。
(1) 多数国間協調の重要性
東西対立という戦後の国際政治を長年規定してきた枠組みが解消し、また、経済面でのグローバリゼーションの進展、さらには、環境問題などの地球的規模の問題の重要性の高まりという状況の下で、多数国間の協調と協力がますます重要となってきている。このような認識は、92年7月のミュンヘン・サミットにおいても、東西の対立に代わり、また南北の違いを越えた「新しいパートナーシップの形成」として示されたところである。あらゆる分野で相互依存関係が著しく深化している今日、一国で平和を壊し、あるいは協調努力を阻害することはできても、米国を含めいかなる国も国際社会の抱える課題を一国で解決することはできず、また、いわゆる「一国平和主義」や「一国繁栄主義」は事実上不可能な状況になっている。実際、以下の例に見るように、近年、重要で緊急の様々な国際問題に対して、国連などの国際機関において、あるいは多数国間の協調と協力によって真剣な取組が行われている。そのような状況の中で、日米欧の先進主要国間での協力に加えて、今日世界で最も活力あふれる地域であるアジア・太平洋地域の諸国も国際協調のパートナーとして、その役割が浮上しつつある。
多数国間での取組の最も顕著な例は旧ソ連諸国に対する支援であり、サミット参加国を始め、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、経済協力開発機構(OECD)等の国際機関による支援が推進されており、92年10月に日本の主催で開催した旧ソ連支援東京会議には、欧州、北米、アジア、大洋州、中東などから70か国、19国際機関及び欧州共同体(EC)が参加した。また、旧ソ連型原子力発電所の安全性確保の問題については、欧州、北米、日本が中心となって取り組んでいる。さらに、旧ソ連諸国の大量破壊兵器関連の科学者・技術者の流出問題に対応するために設置される国際科学技術センターは、日本、米国、EC、ロシアが共同で設立することとなった。
中東和平問題については、和平問題の直接の当事者はイスラエル、パレスチナ・ジョルダン合同代表団、レバノン、シリアであるが、中東地域の諸問題に関する多国間協議には、これらに加え、米国、ロシア、日本、EC、カナダ、湾岸協力理事会(GCC)諸国(アラブ首長国連邦、オマーン、カタル、クウェイト、サウディ・アラビア、バハレーン)、マグレブ諸国(アルジェリア、テュニジア、モロッコ、リビア)など約40か国が参加し、軍備管理、経済開発、水資源、環境、難民のそれぞれの問題について作業部会を設置して協議を積み重ねてきている。
カンボディア問題については、91年10月のパリ会議には、日本、米国、英国、フランス、ロシア、中国、ヴィエトナム、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国など19か国が参加し、さらに、92年6月の日本の主催によるカンボディア復興閣僚会議には32か国及び12国際機関が参加した。
旧ユーゴースラヴィアの問題については、92年7月、ジュネーヴにおいて、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の主催で、紛争被災民のための人道援助国際会議が開催され、約60か国及び関係国際機関の代表が出席した。さらに、8月にロンドンで開催された旧ユーゴースラヴィアに関する国際会議には日本も含め20か国以上が参加し、紛争の政治的解決及び人道援助努力を強化することで合意した。
さらに、92年1月に冷戦後の国連のあり方を議論するために国連安全保障理事会首脳会議が開催されたこと、また同年6月に行われた国連環境開発会議(UNCED)に182か国もの国が参加したことも多数国間協調による国際問題への取組の重要性についての国際社会の共通の認識を示すものである。
このような多数国間協調は、内政と外交の一体性という観点からも重要である。民主主義体制の下では国際社会の課題への取組に当たっても、国内世論の理解と支持を得ることが不可欠であり、特に、国際政治の急速な動きに対して、国内政治をどのように調和させていくかが重要な課題となっている。このためには、各国が緊密な協議を通じて、国際世論、国内世論に対して、共通の課題と進むべき方向を明確に提示していくことが一層重要となっている。
このような多数国間での協調努力とともに、政治、経済両面において地域的な協力を目指す動きも拡大しつつある。ECの統合を一層進めるため、92年2月に署名された欧州連合条約(マーストリヒト条約)は、市場統合にとどまらず、経済・通貨統合、さらに政治統合をも目指したものであり、EC加盟12か国においてその批准作業が進められている。欧州安全保障・協力会議(CSCE)は政治面における地域協力の顕著な例であり、ヴァンクーヴァーからウラジオストクまでと言われるように、北米、欧州全体、旧ソ連諸国を包含する広大な地域協力機構となっている。冷戦の終焉後、CSCEは、東西間の交渉の場から共通の価値観を基礎とする域内協力の場へとその性格を変え、欧州における軍備管理・軍縮、紛争の防止とその解決、人権保護などの面で重要な役割を果たしつつ、新しい世界秩序のあり方を模索している。日本は、92年7月に域外国でありながら基本的価値観を共有する国としてCSCEに特別参加した。経済面では、92年8月に合意された北米自由貿易協定(NAFTA)は、米国、カナダ、メキシコの3か国(人口合計3億6,000万人、GDP合計6兆2,000億ドル)を合わせた自由貿易地域であり、ECよりやや大きい規模となる。
このような地域協力ないし地域統合は、各地域ごとに異なる政治、経済情勢を背景としてそれぞれの地域に適合する協力を推進することを目的とし、ひいては、その活動が世界全体に貢献することが期待される。しかし、このような動きは、各国の関心が地域内の問題に限定されることを助長するものであってはならず、国連や関税及び貿易に関する一般協定(GATT)といった世界的なシステムとの整合性をもって進められる必要がある。政治面では、国連憲章は、紛争解決における地域的機関の役割を認める一方で、地域的機関による活動は国連安全保障理事会に対し通報しなければならないことを規定しており、また、例えば、CSCEの側においては自らを国連憲章第8章の「地域的取極」に基づく機関と位置付け、補完的な協力の強化を行っている。経済面では、地域協力・地域統合は、GATTに基づく多角的自由貿易体制と整合し、世界経済、貿易の拡大に資するものでなければならない。アジア・太平洋地域では、92年1月にASEAN諸国はASEAN自由貿易地域(AFTA)の創設に合意している。また、域内の諸国や地域との経済関係を緊密化させ、地域の経済開発を促進するものとして、アジア・太平洋経済協力(APEC)の重要性が高まっている。他方、一部の諸国においては、ウルグァイ・ラウンドの困難や欧米の地域統合に対する懸念を背景として東アジア経済協議体(EAEC)構想の提唱といった動きが見られる。
多数国間協調において日本、北米諸国、西欧諸国は特に重要な責任と役割を有する。これらの諸国は、今日の国際社会の指導理念である自由、民主主義、市場経済といった基本的価値観を共有しており、また、世界の国民総生産(GNP)の7割を占めている。このような関係にある日米欧諸国が二国間関係を越えて、それらの基本的価値観に基づく世界の平和と繁栄のために密接に協力することは極めて重要であり、今やこれらの諸国の密接な協力なしには、世界が直面する諸問題に有効に対処することは困難になっている。旧東側諸国や開発途上国の民主化、市場経済の導入に対する支援は、正に日米欧が協力して取り組むべき良い例である。実際、日本は地理的に遠く離れた中・東欧諸国にも支援を行い、また、欧州諸国もアジアにおけるカンボディア復興に参画するというように、日米欧は、世界全体の平和と繁栄の見地から多数国間協調を行っている。このような日米欧の責任と役割の高まりを背景に、サミットなどの場における政策協調は政治、経済両面にわたり一層重要になってきている。