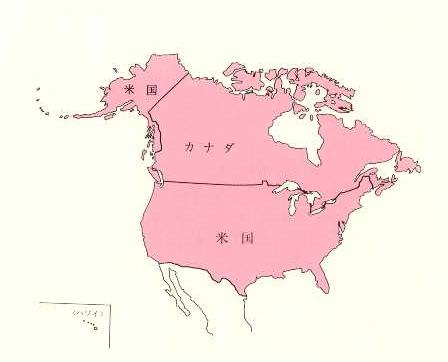
第2節 北 米
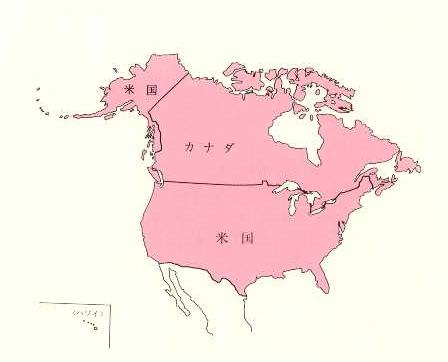
1. 内 政
湾岸危機は、米国内にも様々な影響を及ぼしたが、任期半ばに入ったブッシュ大統領は、この危機への対応に手腕を発揮し、その指導力に対する評価を高めた。しかし、クウェイトの解放が実現し、中東情勢が落ち着きを見せる一方で、90年半ば以降、景気後退局面に入ったこともあり、米国内では、経済運営や米国の競争力の強化、教育、犯罪や麻薬対策等の山積する国内問題に再び国民の関心が向けられた。また、公民権法の改正の是否、ヒスパニック系住民の騒擾等の人種問題や社会問題も大きく取り上げられた。
90年11月には連邦上下両院の議員や36州の州知事を改選する中間選挙が行われ、多数党である民主党が両院で若干の議席を伸ばす一方、州知事選挙では増税問題等により党派のいかんを問わず現職知事に対する有権者の批判が見られ、15州で現職知事を擁する政党が敗れた。
92年の大統領選挙では、ブッシュ大統領の再選は確実という見方が多い中で、これに対抗して民主党がどう対応するかが注目されている。
(1) 景気後退の傾向と経済の先行きに対する不安の高まり
90年春以降、米国国民の間で米国や米国経済の先行きに対する不安感の高まりが見られた。その背景には、景気後退の兆し、貯蓄貸付組合の救済等の国内問題、行政府と民主党議会指導部との間で持たれた予算サミットのもたつき、増税論議等があると考えられている。ブッシュ大統領は、米ソ関係の推進等の対外政策では高い支持を維持したものの、このような国内問題や経済問題については適切に対応していないと見る向きもあった。
(2) 湾岸危機への対応と大統領のリーダーシップの発揮
しかし、90年8月から91年初めにかけてブッシュ政権、議会及び国民にとって最大の課題は湾岸危機への対応であった。
イラクのクウェイト侵略に対して、ブッシュ大統領は、即座にサウディ・アラビアを防衛するため同国への派兵を決定して国民の支持を得る一方、イラクの侵攻を冷戦後の新しい国際秩序に対する挑戦と位置付け、断固とした姿勢で対応した。ヴィエトナム戦争以来最大の海外派兵となったことに米国国民の間には懸念も見られたが、イラクの行為に対する反感は強く、ブッシュ大統領が経済制裁の実施、武力行使を容認する国連安保理決議678の採択、イラクとの直接交渉の提案、ソ連との協調等、問題の解決を目指す措置を逐次とったにもかかわらず、イラクがクウェイトから撤退しないこともあって、武力行使もやむを得ないという見方が国民の間に広がった。
一方、議会は、大統領の対応を基本的には支持しつつも、ヴィエトナム戦争の経験や宣戦布告に関する憲法上の議会の大権に対する考慮から当初は武力行使については慎重論が根強く、90年11月の大統領による兵力増派の決定に対して、民主党を中心に引き続き経済制裁の効果に期待すべきであるという意見が多く出された。また、保守派の一部にも軍事介入について懐疑論が見られた。最終的には、行政府の説得もあり、米国議会は91年1月に僅差であるが武力行使を承認する決議を採択した。
武力行使を開始して以降、まず、1か月以上にわたる航空攻撃によりイラク軍を弱体化させた後に、地上戦に移った結果、地上戦をわずかな被害を出しただけで短期に成功させることができたことから、ブッシュ大統領の指導力に対する評価は一気に高まり、支持率が一時は90%(3月のワシントン・ポスト/ABC調査)と歴代最高を記録した。米国国民も、米国の軍事力や技術力の圧倒的な優位を目の当たりにし、自信を回復した。
(3) 90年中間選挙一有権者の政治家に対する不満
90年11月の中間選挙では、湾岸危機の最中に行われたにもかかわらず、中東情勢は争点とされず、大方の予想どおり民主党が上下両院で議席を若干増やして(上院1議席増、下院8議席増)、同党の優位を一層確かなものとした。共和党は直前の悲観的な予測に比べれば議席の減少を最小限にとどめたとは言えるが、大統領の高い人気や持続する経済成長を拠りところに同党が年初に抱いていた楽観的な見通しに比べると後退感は否めなかった。
連邦議員選挙については、全国的な争点はなく現職有利という従来の傾向が見られたが、現職候補の得票率は低下を示した。州知事選挙では、悪化する州財政を背景に増税を主張した現職政党の候補が15州で敗れた。このような結果は、選挙前に有権者の間で広まっていると見られていた政治家に対する不満が実際の投票に表れたものと受けとめられている。
なお、90年国勢調査(10年ごとに実施)では、人口は南部及び西部で増加が顕著であることが明らかになり、この結果を反映した各州の連邦下院議員の定数(435名)の再配分及び選挙区の再区割りの結果は、早ければ92年の選挙において適用される。
(4) 内政への関心の移行と政策課題
ブッシュ大統領は、91年1月末に行った一般教書演説で、湾岸危機への対処に当たって国民の団結を訴えるとともに、国内面でも、同じ不屈の精神で米国の再生に取り組むことを訴えた。ブッシュ政権の国内政策と経済政策は、経済成長の維持、米国の将来に対する投資(競争力の強化)及びすべての米国国民に対する機会の増大を3本柱としている。このような姿勢に立って、ブッシュ大統領は、金融制度改革案、陸上輸送網整備法案、教育に関する米国2000年戦略、国家エネルギー戦略、包括犯罪対策法案、国家麻薬戦略 III、公民権法改正案等の政策を次々と発表し、4月中旬より積極的に国内遊説を行った。これらの政策は、巨額の財政赤字に対応するため、90年秋に包括的な財政赤字削減策が法律で決められ、新規の支出増には厳しい制約が課されているという状況の中で打ち出されたものである。
湾岸危機後は、景気後退が明確となり、対外危機に臨んだのと同じ意欲で国内問題に立ち向かうべきであるという雰囲気の中で、国内問題に対する関心が高まっていった。有識者の多くから米国自身の状況に対して懸念が表明され、政策の優先順位を見直して国内問題に取り組むべきであるという主張が聞かれた。
また、人種問題や社会問題が関心を集めた。ワシントンでは黒人警察官とヒスパニック系住民の間の騒擾が起こり、少数民族間の対立として大きく報道された。議会では、職場における差別の挙証責任は雇用者ではなく被雇用者にあるとする89年の連邦最高裁判決は修正すべきであるとの主張に基づき、このための公民権法改正案が先議会(89年1月~91年1月)に引き続き審議されたが、大統領が、民主党案は訴訟を増やし、結果として企業が雇用割当制(適性によらず一定の比率の少数民族を採用したり、昇進させたりすること)を採用することを招来すると批判したため、民主党の反発を招いた。また、リベラル派でアフリカ系米国人のマーシャル連邦最高裁判事の後任として、大統領が保守派のアフリカ系米国人であるトマス判事を任命したことから、上院の承認審議の行方が91年秋以降の内政案件の焦点の1つとなっている。
(5) 92年の大統領選挙
ブッシュ大統領は再出馬の正式表明を行っていないが、対外政策面で確立した指導力を背景に、不整脈という健康上の懸念を払拭して、再選の体制づくりを行っていくと見られている。一方民主党側は、湾岸危機やブッシュ大統領の高い人気等の影響により、これまでの大統領選挙に比べて出足が遅く、91年8月現在、正式に立候補を表明したのはソンガス元連邦上院議員のみである。立候補を検討中と見られる連邦議員や州知事の夏明けの動きとともに、同党がどのような選挙メッセージを打ち出してくるかが注目される。
(6) 経 済
米国経済は90年7月、82年から始まった平和時最長の景気拡大に終りを告げて、景気後退局面に入った。最近の経済成長率の推移を見ると、89年の第2四半期から1%前後の低い伸びが続き、90年の第4四半期には4年半振りのマイナス成長を記録し、さらにこれに続く91年の第1四半期もマイナス成長となった。また、雇用情勢を見ると、90年8月以降は製造業や建設業での雇用者数の減少に加えて、サービス業でも雇用が伸び悩んだため、失業率が悪化している。なお物価は、湾岸危機による原油価格の急騰により大幅に上昇したが、91年に入り、原油価格の安定等に伴って落ち着きを取り戻している。
世界経済の不安定要因である「双子の赤字」のうち、財政赤字については、87年度以降は多少なりとも改善の方向にあったが、90年度には一転して赤字が急増し、ピークに迫る2,205億ドルに達した。このような状況の下で、ブッシュ大統領は、90年5月に行政府と議会の首脳による予算サミットの開催を呼び掛け、抜本的な財政赤字削減策の検討に着手した。予算サミットにおける交渉は難航を極めたが、90年11月、5年間で約5,000億ドルの赤字の削減を含む包括的な赤字削減策が最終的に決定した。今後の財政赤字について行政府は、91年度に過去最大の2,822億ドルを記録し、92年度には更に赤字が拡大して3,483億ドルに達するとしており、今後の動向を注視する必要がある。
もう一つの赤字である貿易赤字については、90年は8月以降の中東情勢による輸入石油価格の上昇から、それまでの赤字縮小傾向に反転が見られたものの、堅調な輸出の伸びを受けて、通年では前年より77億ドル改善して1,017億ドルへと縮小した。これは3年連続の改善であり、しかも83年の524億ドル以来の低水準である。91年に入って貿易収支の改善傾向はより顕著になっており、対欧州共同体(EC)諸国、対アジアNIEs及び対石油輸出国機構(OPEC)諸国の貿易収支は大幅に改善してきている。対日収支も改善しているが、その改善の速度が他の地域に比べて低いことから、米国の貿易赤字全体に占める対日赤字の割合は拡大している。
2. 外 交
(1) 東西関係の変容と新しい国際秩序の構築
89年に東欧一帯を覆った変動の嵐と、それに伴うベルリンの壁の崩壊、及びソ連の内政・外交両面における変化は、東西対立を前提とした冷戦構造を変容させた。90年から91年にかけて米国は、このような変化を踏まえ、新しい国際秩序を構築するために一層の努力を払った。具体的には、ソ連との間では対話と協調の関係を定着化させることに務めたし、欧州については、統一ドイツの北大西洋条約機構(NATO)帰属や、欧州通常戦力(CFE)条約の成立のために努力した。
このような状況の中で、90年8月に発生したイラクによるクウェイト侵略は、この1年の米国外交にとって最大の試練となった。しかし、米国は東西関係の変化を最大限活用し、これまで中東をめぐり対立的な立場に立つことの多かったソ連と共同歩調をとり得た。これは、武力行使を容認する国連安保理決議の採択や、それに基づく多国籍軍の武力行使などにおいて、米国の指導力の発揮を容易にした。このように、東西の緊張緩和が、地域紛争の解決に好ましい状況を作り出している。
(2) 対ソ連外交
米ソ関係は、89年5月にブッシュ大統領が表明した封じ込めを越えてソ連を世界に迎え入れていくという基本的な考え方に沿って、対立から協調へと質的変容を遂げつつある。特に90年及び91年には、ワシントン(90年5~6月)、ヘルシンキ(90年9月)、パリ (90年11月、CSCE首脳会議)及びモスクワ(91年7月)において4度に及ぶ首脳会談が開催され、これらの機会に最恵国待遇の供与を含む通商協定やCFE条約、あるいは9年越しの交渉の成果である戦略兵器削減条約(START)等、幾つかの重要な条約への署名が行われた。
これらの会談を通じて注目されることは、両国が地域紛争についても協調して対処する姿勢を打ち出したことであり、中でもヘルシンキ会談では、米ソ両国が一致して湾岸危機に対処するという意思をフセイン大統領に伝えることに合意した。また、欧州安全保障・協力会議(CSCE)首脳会議の機会に開催されたパリ会談でも、湾岸情勢に多くの時間が費やされたと言われている。モスクワにおける首脳会談で、ブッシュ大統領が、米ソ関係は敵対関係からパートナーの関係へ変容しつつあると強調したのも、そうした背景を踏まえてのことであり、この会談では、湾岸危機後の中東地域の安定と中東和平を目指して、91年10月に米ソの共催で中東地域会議を開催するということでも合意を見た。
また、91年7月のモスクワ会談では、史上初めて戦略兵器の削減を約束するSTARTの署名が行われ、東西関係は、戦略的にも安定が強化された。他方、この会談では、ソ連の経済問題に多くが費やされ、ブッシュ大統領から、対ソ支援策の一環として、90年に署名した米ソ通商協定の議会手続の開始や、対ソ貿易信用枠の撤廃等、経済関係の拡大に向けて諸提案が行われた。このようにモスクワ会談は、米ソ関係が新時代に入ったことを随所でうかがわせるものであったが、ソ連国内の経済的、政治的な混迷は、今後とも米ソ関係の行方に不透明な要素を投げ掛け続けることになろう。
(3) 湾 岸 危 機
湾岸危機におけるブッシュ政権の対応の特色は、軍事的には米軍を中心とする多国籍軍の構築を通じて、また、外交的には国連を舞台とした外交努力を通じて、西側同盟国のみならずアラブ諸国やソ連までも糾合した形で幅広い対イラク連合の形成に努めたことである。「サダムはこの紛争をイラク対米国の図式にしようとして失敗した。今夜、5大陸の28か国がサダム・フセインに対抗している」という、武力行使開始時のブッシュ大統領の演説にもあるように、この試みは成功し、軍事作戦の成功ともあいまって戦闘を短期に勝利に導くことを可能にした。
さらにブッシュ政権は、アラブ諸国を対イラクで結集させた勢いで、永続的な中東和平の枠組み作りに乗り出した。この構想は、91年7月のモスクワにおける首脳会談で前述のとおり米ソ共催で和平会議を10月に開催することについて両国の合意が成立し、その直後に、それまで会議に難色を示していたイスラエルが参加の意思を表明したことで急瀘現実味を帯びたものとなってきており、ベーカー国務長官を中心とした関係者の間で調整作業が続けられている。
(4) 対アジア政策
アジアについてブッシュ政権は、韓ソ外交関係樹立等の動きに対して一定の評価をしつつも、アジア・太平洋地域におけるソ連の軍事力近代化努力の継続や、地域紛争発生時における米軍の緊急展開の必要性も踏まえ、地域の安定を確保し、同盟国に対する責任を果たしていくためには同地域における米軍のプレゼンスを継続していく必要があるとの姿勢を維持している。
米中関係については、米国議会などが依然中国の人権状況や武器移転等に対し厳しい姿勢を示しているが、米国政府が中国との対話を拡大していくことの重要性を認識し、銭其深外文部長の訪米(90年11月)以降、政府高官を中国に派遣し、中国との対話を維持し、関係改善を模索している。91年9月に失効する在フィリピン米軍基地の利用については、90年9月以来の交渉の結果、91年7月に、クラーク空軍基地の返還(92年9月)とスービック海軍基地の存続(10年間)で合意に達した。ただ、批准を含めた国内手続きは今後の課題である。
3. 日本との関係
(1) 全 般
(イ) 湾岸危機と日米関係
湾岸危機とこれへの対応は、日米関係にも大きな影響を与えた。米国は、イラクによるクウェイト侵略は国際社会における法の支配に対する重大な挑戦であり、国際社会がこの危機に適切に対処し得るかどうかに冷戦後の国際秩序の将来がかかっているとの認識に立って湾岸地域へ大規模な兵力を展開し、各国に対しても共同行動や応分の協力を求めた。これに対し日本は、憲法の枠内でできる限りの協力を行うとの観点から、資金協力を中心とした一連の中東貢献策を決定し、実施していったが、米国国内では、日本は人的な貢献を行うことに躊躇していると受け止め、日本は米国と危険を分かち合おうとしないとの失望感が広まるとともに、当初の資金協力は不十分であり、かつ、遅きに失しているとして不満が高まった。
しかしその後、90年中に行われた多国籍軍に対する20億ドル相当の資金協力に加え、91年1月には90億ドル相当の追加拠出が決定され、増税等必要な財源措置について国会の承認を得て3月に実施されたこともあり、日本の資金協力は米国に対するものだけでも最終的には約100億ドルの規模となった。さらに、4月にはペルシャ湾への自衛隊の掃海艇の派遣も実現した。このような日本の努力もあり、湾岸危機の終結とともに、日本の貢献に対する米国の不満も次第に静まっていった。
(ロ) 全面的な協力関係への復帰
湾岸危機の間も、日米の経済関係や安全保障関係は着実な進展を見たが、日米関係全体としては、両国とも危機への対応に多くの時間を割かざるを得なかったため、当初91年の早い時期に実現が期待されていたブッシュ大統領の訪日の日程を確定することができなかったことを始めとして、様々な影響が出た。しかし、湾岸危機がクウェイトの解放という形で収束を見た後、この事件の教訓を活かすためにも、日米関係をなるべく早期に全面的な協力関係に戻し、グローバル・パートナーとしての協力を着実に進めていこうとの動きが開始された。3月下旬には中山外務大臣が訪米し、ベーカー国務長官との間で湾岸危機後の日米関係と

ケネパンク・ポートにおける日米主脳会談(91年7月)
国際問題に関する日米の協力について会談を行い、さらに、4月4日にはカリフォルニア州ニューポート・ビーチにおいて日米首脳会談が行われた。
この日米首脳会談においては、日米の貿易不均衡が是正される傾向にあること、諸懸案が着実な解決を見ていること、在日米軍駐留経費について新たな特別協定が合意されたこと等を背景として、日米関係の基礎的条件は良好であることが確認された。また、会談後の共同記者会見において、ブッシュ大統領が日米関係の重要性とその強化の必要性を訴えたことは、湾岸危機への対応をめぐって一部に存在していた日米間の感情的なわだかまりを取り除く上で極めて有意義であった。
ロンドン・サミットを目前にした7月11日、ブッシュ大統領の招待に応じ海部総理大臣はメイン州ケネバンクポートの大統領の別荘を訪れ、対ソ支援問題を中心としたロンドン・サミットの主要課題等について話合いを行った。その機会に、日本が表明した90億ドル相当の資金協力がすべて米国向けに行うことを約束したものであったかどうかをめぐる日米間の理解の相違については米国が日本の主張を受け入れる形で決着し、また、ブッシュ大統領は91年秋に訪日する意向を明らかにした。これは、日米関係が湾岸危機の影響を乗り越え、グローバル・パートナーとして一層の協力を進めていく体制が整ったことを示している。
(ハ) 21世紀に向けた協力関係の構築
日米のグローバル・パートナーシップは、湾岸危機という大きな試練を経て、単なる抽象概念ではなく、実質を多く伴ったものとしていかなければならないとの考えが日米双方において強まった。既に日米両国は、アジア・太平洋、東欧、中南米等広範な地域において、平和の確保と自由及び民主主義の確立のために協力を進めてきているが、日本側について見れば、これにとどまらず、日本がその持ち味を活かした幅広い国際的な貢献を進んで行っていくことが、日米関係の文脈でも極めて重要であることが明確となっている。すなわち、冷戦構造の崩壊という国際秩序の大きな変革の中で、新しい国際秩序の主要な担い手になろうとしている日本が米国と共にいかなる世界を作りたいと考え、また、その実現のためいかに協力していくことができるかについて、日本としての具体的な考え方を明確にしていくことが重要となっているのである。例えば、湾岸危機において日本が世論の糾合に手間どった経験を踏まえて、国連平和維持活動への参加等の人的貢献の分野でどのような役割を果たそうとしているのか、また、ウルグアァイ・ラウンドの成功に日本がいかに貢献するのかを具体的に示していく必要がある。その上で、日米両国が21世紀に向けてどのような協力と協調の関係を築き上げていくべきかについて、更に幅広い国民的理解を得る努力が日米双方で必要とされている。今後、行われる予定のブッシュ大統領の訪日は、そのための重要な機会を提供するものとなろう。
(2) 経 済 関 係
両国経済は、近年ますます緊密化し、その相互依存関係は貿易、直接投資、金融、技術等の多様な分野で著しく深まってきている。具体的には、90年の日本の全貿易額の約27%は米国との貿易であり、米国の全貿易額の約16%は日本との貿易である。また、日米はそれぞれ相手国に対して最大級の直接投資を行っている国であり、90年の直接投資について見れば、対日直接投資の約24%は米国が、対米直接投資の約47%は日本がそれぞれ行っている。
また、日米両国は、世界の国民総生産(GNP)の約40%を占め、両国の経済関係は単なる二国間経済関係にとどまることなく、世界経済に大きな影響を及ぼすものとなっている。それだけに両国は、世界経済の安定的な発展に大きな責任を有している。このような認識を踏まえて、日米両国は主要国首脳会議(サミット)、経済協力開発機構(OECD)、関税と貿易に関する一般協定(GATT)等において国際経済の運営について協力を進めてきている。冷戦後の新しい国際経済秩序の構築に向けて日米の協力関係は増々重要性を増している。
このように、日米間の強い相互依存関係及び両国経済が世界経済の中で占める大きな比重という巨視的視点から見れば、両国の経済パートナーシップは基本的に健全であり、これを一層強化していくことが重要である。
確かに、日米間には種々の経済摩擦はあるが、これに目を奪われるあまり、このように基本的に良好な経済関係の基調を見失ってはならない。
両国の経済関係は、国際情勢と両国の相対的地位の変化の中で新しい挑戦に直面している。かつて絶対的優位を享受していた米国経済の競争力が相対的に低下してきていること、とりわけ、(あ)改善傾向にあるものの依然として大幅な貿易不均衡が存続していること、(い)景気後退から脱したとは言え、景気の回復は比較的弱いと予測されること、及び(う)先端技術分野を始めとして米国企業が日本企業との熾烈な競争にさらされていること等から、米国国内には焦燥感が募ってきている。ソ連の軍事的脅威の低下と裏腹の問題として日本の経済力や技術力に対する警戒感が米国国内に強まっていることが種々の世論調査に示されている。このことから、米国国内には市場を閉鎖し米国産業を保護するべきではないかという保護主義の圧力が依然として強く、ここ数年来の米国政府の対日要求は広範囲に及んでいる。
このような状況の中で、90年から91年にかけての日米経済関係の進展は、多少の息をつく余裕を与えるものとなった。米国の対日貿易赤字がピークであった87年の563億ドルから、88年と89年に引き続き、90年では411億ドルと大きく改善したこと、日米構造問題協議のフォローアップの第1回年次報告書が91年5月に取りまとめられたこと、建設、半導体、電気通信、海亀等の主要な個別案件が決着したこと等は、米国の厳しい雰囲気を和らげるのに役立った。
他方、日本においては、米国の巨額に上る財政赤字が更に拡大していることに示されるように、米国は自分の問題を自分で解決せず、他国のせいにしているといった批判の声も高まってきている。
今後の日米経済関係の運営においては、個別の問題(日本側の自動車部品及び自動車、外国人弁護士、コンピューター調達等)について、それが日米関係全般の信頼関係を損うことのないよう話合いを通じて解決していくべきである。また、日本の経済制度や経済構造の妥当性に係る問題については、米国が日本に注文をつけているかどうかにかかわらず、日本自身の問題として是々非々で進んで改革、解決を図っていくとの基本的姿勢をとることが重要である。同時に、日本として米国が改善すべき問題(丸太等の輸出規制、直接投資規制等)については改善を図るよう米国の側にある問題点を一層率直に指摘していくことが必要である。
そのような観点から、日米構造問題協議は日米間の協議に新しい視点を導入することになった。日米両国は、この協議において、互いに問題点を指摘し合う双方通行の原則で協議を行い、今後の日米経済関係を一層均衡のとれた形で運営していく上で第一歩を踏み出した。日本側から言えば、米国がこの協議で明らかにしたように競争力を強化し、財政赤字を解決していくことが世界的にリーダーシップを発揮していくために不可欠であり、このことが前述の対日脅威感の解消につながっていくことが期待される。米国側からすれば、系列や排他的取引慣行といった日本の歴史や制度に根ざした問題に日本が一層積極的に対応することが、一層開放的で公正な日本経済につながるということであろう。このように相互に高め合うような仕組みが重要である。
以上の方針は、当面の課題とともに中長期的な課題への対応に妥当するものである。とりわけ、日本の経済制度については公正性や透明性を高めるよう改善を図り、日本の経済が国際的な規範にのっとったものであることを明確に示すことが重要である。同時に、幅広く各層の米国民に対し日本経済について一層客観的かつ説得力のある形で広報していくことも必要である。また、日米経済の相互依存関係においては、摩擦の生じることはむしろ当然の現象であり、過剰に反応することなく冷静に対処していくという姿勢が、政府のみならず、報道機関を含めた国民全体に求められる。このような努力を通じ、両国の経済関係を健全な競争と協力を基調として活力にあふれる形で発展させていくことができるのである。
(3) 安全保障関係
(イ) 日米安保体制が果たしてきた役割
今日現行日米安保条約の締結から30年余りが経ったが、米国との安全保障体制により国の平和と安全を確保するという日本の選択が正しかったことは、歴史が最も雄弁に物語っていると言えよう。この30年余りの間に、日本は、一人当たり国民所得、世界貿易に占める割合等の数字統計で見て米国に比肩する経済大国に成長した。この成果は、戦後米国が自由世界の指導国として築いた国際秩序に、日本が米国との同盟関係を通じて参加する道を選ぶことによって、初めて手に入れることができたものである。日米安保条約に具現された米国の明確な日本防衛の意思とそれを裏打ちするアジア・太平洋地域における米国の確固たるプレゼンスは、国際社会が激動する中にあって、日本に平和で安定した国際環境をもたらしてきた。また、日本は、米国の強い支援を背後に、戦後の国際経済体制がもたらす利益を十二分に享受し、いち早く西側先進工業国の仲間入りを果たしたが、これも日米安保体制が象徴する自由世界の一員という日本の基本的立場があったからにほかならない。日米安保体制を基盤とする米国との同盟関係が存在しなければ、主要先進民主主義国としての今日の日本はあり得なかったと言えよう。
(ロ) 在日米軍駐留経費負担
日本には、日米安保条約に基づいて、日本の安全及び極東における国際の平和と安全のために、現在約4万8,000人の米軍が駐留している。在日米軍の駐留は日米安保体制の核心であるが、この駐留にかかる諸経費の負担について、政府は、在日米軍の効果的な活動を確保し、日本の安全保障にとり不可欠な日米安保体制の円滑な運用を図っていくことが極めて重要であるとの観点から、自主的にできる限りの努力を行ってきている。
具体的には、政府は、在日米軍の施設及び区域について、1979年度から隊舎や住宅の建設等を行い、米国側に提供してきている(91年度予算額は歳出ベースで約957億円)。他方、在日米軍日本人従業員(現在約2万2,000人)の労務費については、1978年度から一部経費を負担してきた。しかし、80年代の日米両国を取り巻く経済情勢の変化に対処するため、政府は、87年、米国との間で地位協定第24条について特別の措置を定めるいわゆる特別協定を締結し、退職手当など8種類の手当の一部を負担し、また、88年には、この特別協定を改正し、90年度予算で特別協定の対象とする手当の全額を負担することとした。
さらに政府は、91年度以降の中期防衛力整備計画の策定作業の中で検討した結果、90年12月、在日米軍の駐留支援について新たな措置を講ずることを決定した。その決定を受け、91年1月、新たな在日米軍駐留経費特別協定が中山外務大臣とベーカー国務長官との間で署名され、国会の承認を得て、同年4月に発効した。
この新たな在日米軍駐留経費特別協定は、91年度から始まる5年間を経て、米国側が現在負担している在日米軍従業員の基本給等及び光熱水料等の100%を日本側が負担できることについて定めている。95年度末に在日米軍従業員の基本給等及び光熱氷料等のすべてを負担することとした場合には、日本は、在日米軍駐留経費の総額の約50%を負担することとなると見込まれる(注1)。日本は、今回の新たな措置による負担分を含め、91年度の在日米軍駐留経費として全体で約4,771億円(注2)を負担している。
今回の特別協定は、日米安保体制の効果的な運用に寄与するのみならず、日米関係全般にとって極めて重要な意義を有するものと言えよう。
(ハ) 緊密な協議と協力
日米安保体制の円滑な運用とその信頼性の向上を図っていくためには、日米両国が間断なき対話を行っていくことが不可欠である。
このような対話のための日米間の協議機構の一つとして、1960年1月の日米安保条約の署名に際し、岸総理大臣とハーター国務長官の間の往復書簡により、日米安全保障協議委員会(SCC)が設けられ、1982年1月までの間に18回開催された。他方、この往復書簡においては、SCCの日本側構成員は、外務大臣と防衛庁長官、米国側は、駐日大使と太平洋軍司令官とされていたが、90年6月、日米安保条約締結30周年記念行事に出席するため訪米した安倍晋太郎特派大使に対し、ベーカー国務長官から、SCCの米側構成員を国務・国防両長官の閣僚レベルとする用意があるという提案があった。この提案を受けて、90年12月、SCCの構成員の変更に関する書簡が交換され、米国側構成員は、国務長官と国防長官に変更された。
この書簡の交換は、SCCの場において日米の外務及び防衛担当の4閣僚が協議することを可能とし、SCCを再活性化させ、安全保障の分野における日米間の協力関係を一層発展させていく上で大きな意義を有するものである。
(ニ) アジア・太平洋地域における米軍の再編問題
米国は、東アジア・太平洋地域に配備した約12万6,000人(グアムを除く)の米軍について、財政赤字の増大と国際情勢の変化を背景に、段階的な調整を行っている。具体的には、90年4月に米行政府が議会に提出したアジア・太平洋地域の戦略的枠組みに関する報告において、米国は、引き続き太平洋国家として、アジア・太平洋における前方展開戦略、二国間の安全保障取極を基本的に維持していくとともに、戦略情勢を十分見極めながら、90年代の10年間を3段階(90~92年、93~94年、95~99年)に分けて段階的に米軍の調整を進めていくことを明らかにしている。
現在、米国は、アジア・太平洋地域における米軍の調整の第1段階として、同地域における全体兵員数の約1割に当たる約1万5,000人の兵員削減を計画し、その一部を実施しつつある。このうち在日米軍については、約4,800人程度が削減される予定である(同時期において、在韓米軍は約7,000人、在比米軍は約3,500人が削減される予定)。
他方、米国は、その同盟国に対するコミットメントは不変であり、米軍の前方展開政策は維持されることを明らかにしている。特に、米国は、日米関係が米国のアジア・太平洋地域における戦略の要であると認識しており、上述のアジア・太平洋地域の戦略的枠組みに関する報告書は、日本においては若干の兵員の削減以上には、現在の配備態勢に変化が生じることは想定していない旨述べている。
(ホ) 安全保障及び防衛面での米国との技術交流
日米安保体制の下において、日米両国は相互に協力してそれぞれの防衛力を維持し、発展させることとされており、これまで日本は防衛力整備のため、米国から技術の供与を含め各種の協力を得ている。近年日本の技術水準が向上してきたことを始めとする新しい状況を考慮すれば、日本としても、防衛分野における米国との技術の相互交流を図ることが、日米安保体制の効果的な運用を確保する上で極めて重要になっている。
このような観点から、政府が90年末に決定した91年度からの中期防衛力整備計画においても、日米共同研究開発等の推進が明記されている。安全保障及び防衛面における日米間の主要な技術交流としては航空自衛隊の次期支援戦闘機(FS-X)の共同開発及び戦略防衛構想(SDI)研究への参加が挙げられる。
航空自衛隊のFS-Xについては、共同開発作業の円滑な実施を図るためその関連武器技術の米国に対する供与が決定され、現在、共同開発作業が本格的に進められている。日米の優れた技術を結集するFS-Xの共同開発は、日米間の相互交流案件として極めて大きな意義を有するものであり、日米の信頼関係に基づき円滑に実施していくことが重要である。なお、FS-Xの共同開発については、91年度からの中期防衛力整備計画においても、その推進が明記されている。
米国のSDIは、非核の防御手段によって弾道ミサイルを無力化し、究極的に核兵器の廃絶を目指す兵器システムについて判断材料を得るための研究計画である。87年7月に締結されたSDI研究に対する日本の参加に関する日米政府間の協定に基づき、88年11月から当初1年間の予定で、日本の企業がSDI研究計画の一環である西太平洋地域ミサイル防衛構想の研究に参加したが、この研究はその後も継続され、現在92年4月までの予定で行われている。
1. 内 政
マルルーニー政権をめぐる国内情勢は、ケベック州のカナダ憲法体制への参加を中心とする憲法改正問題、財貨・サービス税(消費税)の導入、景気の悪化等をめぐり厳しい状況にある。
特に、憲法改正問題については、90年6月、ケベック州のカナダ憲法体制への参加を目的とする連邦及び各州の首相間の合意(ミーチレイク合意)の批准が不成立に終わって以来、連邦及び各州政府の間でこの問題を検討するための各種委員会が設置され、解決策が模索されている。他方、連邦や各州の利害や視点は必ずしも一致しておらず、また、ケベック州内では分離独立を求める動きが見られ、妥協点は容易に見出し難い状況にあると言える。
こうした中で、マルルーニー政権は91年4月、大幅な内閣改造を実施し、政権発足以来外相を務めたクラーク大臣を憲法問題担当相に任命するなど、92年または93年に予想される次期総選挙を控え、体制の強化を図った。
経済面では、財政赤字が引き続きカナダ経済の足かせとなり、さらにインフレの影響もあって、政府は厳しい金融引締め政策、大幅な歳出の削減を実施した。こうした政策に加え、米国経済の後退が要因となって、カナダ経済は、90年第2四半期より景気後退期に入ったが、91年に入り、国内金利の着実な引下げや米国経済の回復もあり、景気は回復に向かっており、91年後半には景気後退期を脱するという見方が有力である。
2. 外 交
一方、対外関係では、引き続き対米関係の維持と強化に重点が置かれた。90年にはマルルーニー首相は、ブッシュ大統領と4回にわたる首脳会談を行うなど、緊密な個人的関係を維持している。対外経済面でも、実施後2年目の米加自由貿易協定の円滑な実施に努力する一方、91年2月には新たに米国、メキシコ及びカナダの3か国首脳間で北米自由貿易協定の交渉を開始することに合意し、交渉の第1回会合を6月にトロントで開催した。
また、湾岸危機に際しては、カナダは、国連の平和維持機能に対する貢献という従来の枠組みを越えて、危機発生直後の90年8月10日、駆逐艦2隻、補給艦1隻、飛行中隊1個中隊の派遣を決定したほか、難民救済等のための資金協力、医療団の派遣等の貢献を行った。
3. 日本との関係
マルルーニー首相は、89年に「太平洋2000年戦略」を発表するなど、近年日本を始めとするアジア・太平洋諸国との関係の強化に意欲を示しており、91年5月には、日本を訪問した。これは、86年5月の同首相の公式訪問以来、5年振りのもので、日加両首脳の個人的関係を更に強化し、良好な二国間関係の一層の発展を図る上で大きな意義があった。マルルーニー首相の訪日中には、在京カナダ大使館新庁舎の落成式が行われたほか、福岡と名古屋におけるカナダ領事館の開設等が発表された。また、両国首脳は長期的な日加両国のパートナーシップのあるべき姿について提言を行うことを目的とする「日加フォーラム2000」の設置に合意した。このフォーラムは両国の有識者により構成され、92年末までに報告と提言を両国首脳に提出することとなっており、21世紀に向けて両国の協力関係が一層幅広く発展していくことが期待される。国際場裡において独自の政策を進めるカナダとの協力を深めることは、日本が今後国際社会で一層積極的な役割を果していく上でも有益であると思われる。
また、カナダとの経済関係は、日本の諸外国との二国間経済関係の中でも最も安定的かつ均衡した関係にあり、基本的に良好に推移している。貿易関係は順調に発展しており、また、対加投資も順調に伸び、対加直接投資残高は、90年上半期に50億ドルを上回った。
(注1) 現時点における経費に関する予測及び為替相場による。
(注2) 提供普通財産借上げ試算額及び厚木航空基地周辺の防音工事助成関連予算を含む。