
第4章 各地域の情勢と日本との関係
第1節 アジア・太平洋

1. 概 観
アジア・太平洋地域は、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国及び新興工業国・地域(NIEs)を中心に順調な経済発展を続けており、世界で最も活力にあふれる経済地域になっている。このことは、国内の政治的・社会的な強靭性を強めるとともに、各国間の相互依存関係を高めており、地域全体の安定化に寄与している。また、朝鮮半島問題とカンボディア問題で重要な進展が見られるほか、韓国の北方外交の成功、中国のインドネシアとの国交正常化及びシンガポールとの外交関係の樹立、モンゴルにおける民主化と市場経済の導入、ネパールやバングラデシュの民主化といった望ましい動きが出ている。中国の情勢は落ち着きを取り戻しつつあり、中越関係にも進展が見られる。さらに、91年1月に開始された日朝国交正常化交渉は8月で4回を数え、日ソ関係も同年4月のゴルバチョフ大統領の訪日により一定の進展を見た。
他方、この地域の多くの国が依然として開発途上の段階にあることに変わりはなく、それだけに先般の湾岸危機により、南西アジアを始めとする多くのアジア諸国も中東の周辺諸国と同様大きな経済的悪影響を被った。また、宗教、民族、歴史等、東西対立の観点のみでは律せられない多様かつ複雑な要素を孕んでいるこの地域の主要な政治的対立や紛争は依然として未解決である。ソ連の新思考外交もこの地域では欧州におけるほど顕著には発揮されていない。ただし、91年8月以来のソ連の大変革はアジアにも必然的に影響を及ぼしてくるものと思われる。
この地域の平和と安定にとって重要なことは、経済の発展、地域的な紛争や対立の解決、及び多様性を踏まえた相互依存関係の発展のための協力である。日本は従来より、この地域の安定のためには経済発展が何よりも重要であるとの観点から、この地域に対する経済面での協力を重視し、例えば政府開発援助(ODA)の分野ではその重点対象をアジア地域に置いてきた。このような日本の努力はこの地域の平和と繁栄に大きく貢献してきたし、今後ともこの面で努力していく方針に変わりはない。これらの努力に加え、今後とも一層強化すべきは、カンボディア問題や朝鮮半島問題等の地域紛争や対立の解決に向けて直接、間接に貢献していく政治面、外交面での努力であり、また、アジア・太平洋経済協力(APEC)に象徴されるこの地域の多数国間の協力や協議に積極的な役割を果たしていくこと、及び各国の民主化や経済開放、市場経済への移行の努力を支援していくことである。世界が変革期にある中で、日本が果たすことを期待されている国際貢献は、今や経済の分野のみならず、政治面においても大きくなっている。日本は、過去の歴史に対する正しい認識の下に、平和国家にふさわしい積極的な貢献を行っていかなければならない。
2. 地域協力の動き
アジア・太平洋地域では、各国及び地域の政治、経済、社会、文化における相違を踏まえつつ、経済的な相互依存関係の強化が追求されており、地域協力の動きが強まっている。92年には創設25周年を迎えるASEANは、加盟諸国の経済発展と政治的安定を背景に、アジア・太平洋地域において発言力を強めるとともに、この地域の重要な安定要因となっている。特に政治面では、カンボディア問題の解決に積極的な努力を行うなど、活発な活動を展開しており、また、経済面でも、加盟諸国の間の経済発展段階に相当の違いがあるという現実を踏まえつつ、域内協力の増進に引き続き取り組んでいる。日本は、このようなASEANの成熟を踏まえ、ASEANとの関係の強化に努めるとともに、今後はさらに、広くアジア・太平洋地域の平和と繁栄のために共に考え、共に努力する関係をASEANとの間で発展させていきたいと考えている。
89年に発足したAPECは、アジア・太平洋地域の一層の経済発展を目的として着実に進展を遂げ、おおむね軌道に乗ったと言える。この1年間、貿易や投資に関する統計の整備、貿易の促進、投資や技術移転の拡大、人材の養成、エネルギー、海洋資源の保全、通信という7つの分野について、数次の高級事務レベル協議及び専門家会合が開催されて具体的作業が進んでいるほか、新たに運輸、観光、漁業の3つの分野が追加された。また、APEC発足以来の懸案であった中国、台湾及び香港の同時参加が、91年8月の高級事務レベル協議の場で基本的に合意された。世界に開かれた協力という基本理念に立って、この地域の有する潜在力が十分に発揮されるように、APECを一層推進していくことが重要であり、日本もこれに積極的に貢献していく考えである。
なお、90年12月にマレイシアのマハディール首相により、日本を含む東アジア地域において経済協力グループを結成しようという構想(EAEG構想)が提案されるなど、ASEANを中心に地域の経済協力を強化する試みが行われている。
また、欧州を中心に緊張緩和が進んでいることを背景に、アジア・太平洋地域の政治や安全保障の問題に対する関心が高まっている。このような中、アジア・太平洋地域の諸国の間で、政治対話の必要性について認識が高まり、既に政府や民間のレベルで種々の対話の動きが顕著になっている。
90年9月には中山外務大臣の提唱により、ニュー・ヨークにおいて、インドネシアのアラタス外相との共催で、アジア・太平洋外相会合が開催された。この会合には、アジア・太平洋地域の15か国(日本、インドネシア、マレイシア、フィリピン、シンガポール、タイ、韓国、中国、モンゴル、ヴィエトナム、ラオス、米国、カナダ、豪州、ソ連)の外相が出席し、湾岸危機、カンボディア問題、朝鮮半島情勢、国際経済問題等に関して活発な意見交換を行った。アジア・太平洋地域に位置する重要な諸国の外相が体制を越えて一堂に会し、現下の諸問題について討議した画期的な会合であった。
アジア・太平洋地域における日本の政治的役割が拡大するにつれて、それが軍事的分野にまで広がっていくのかといった不安や懸念がこの地域の一部に生まれている。このような状況の下で、日本の外交政策の真の目的について、日本の考えを卒直に説明することは、日本にとっても域内諸国にとっても重要になっている。こうした認識の下に中山外務大臣は、91年7月のASEAN拡大外相会議の席上、ASEAN拡大外相会議の場を利用して、友好国の間で安心感を高めるための政治対話とでも言うべき対話を始めてはどうかと提案した。この提案の趣旨については関係国の理解が得られ、具体的な進め方について現在ASEAN側で検討中である。
また、南西アジア地域においても、85年に発足した南アジア地域協力連合(SAARC)が、近年の国際秩序の根本的変化を踏まえて、その協力を本格化していく兆しが出ている。
こうした地域協力や地域対話の場は、従来この地域の中心であった二国間の努力や対話とあいまって、この地域の平和と繁栄の増進に貢献していくことが期待されるが、日本は地域の一員として引き続き積極的な努力を行っていく方針である。
1. 概 観
朝鮮半島では、依然として軍事休戦ラインを挟んで南北間で政治的、軍事的対峙が続いている。他方、90年後半から、韓国とソ連の国交樹立、韓国と中国の貿易事務所の相互設置、分断後初の南北首相会談の実現、南北国連加盟に向けた動きなどに象徴されるように、世界的な東西和解の流れが、この地域にも着実に及びつつあり、朝鮮半島分断の背景にある東西対立の構造的変化が生じている。
このような動きの中で、日朝関係にあっては、90年9月の自民党と社会党両党の代表団の訪朝を機に、長年の懸案であった第18富士山丸の船員の帰国が実現し、また、日朝国交正常化交渉が開始される運びとなった。日本は、韓国との友好協力関係の維持と強化を基本としつつ、日朝国交正常化交渉に誠実に臨んでいる。
2. 韓 国
(1) 内 政
90年12月末、虜泰愚大統領は国務総理、大統領秘書室長を含む大幅な内閣改造を断行し、大統領としての任期の後半期に臨んだが、内政は必ずしも平穏ではなかった。新年早々、与野党議員3名が民間団体より資金援助を受けて外遊した事件、ソウル近郊の宅地特別分譲に絡む疑惑事件が相次いで発覚し、特に、後者の事件では、与野党議員5名と大統領秘書官などが収賄などの容疑で逮捕された。また4月末、デモ中の学生が戦闘警察官の殴打によって死亡する事件が発生し、1か月近くにわたり大規模な反政府デモが行われ、焼身自殺も相次ぎ、結局5月末に国務総理と4閣僚の更迭という形で事態の収拾が図られた。
虜泰愚大統領の民主化公約の一つであった地方議会議員選挙は、地方都市と郡、区については91年3月に、大都市と道については6月に30年振りに予定どおり実施された。特に、政党の候補公認が認められた6月の選挙は、5月の反政府デモなどによる政治的混乱の直後に行われたが、かえって国民の安定化志向が高まったことなどにより、与党民自党が総議席の65%を占める圧勝に終わった。
経済面では、韓国はNIEsの一員として80年代半ばから活力にあふれる成長を続けてきたが、89年以降、賃金の上昇等を背景に輸出は伸び悩んでいる。一方、90年には民間消費や建設投資等の内需の伸びに支えられて9%の実質経済成長率を記録し、一人当たり国民総生産(GNP)も5,569ドルに達し、90年代半ばに経済協力開発機構(OECD)に加盟する可能性も内外で議論されている。他方、輸出が不振を続ける中で内需が旺盛なことから機械類などの輸入が急増し、90年の貿易収支は18億5,000万ドルの入超となり、85年以来5年振りの赤字を記録した。
(2) 外 交
社会主義諸国との関係の改善を図る韓国の北方外交は、ソ連や東欧諸国の改革の動きともあいまって着実な成果を挙げてきた。ソ連との間では、90年6月にサン・フランシスコで虜泰愚大統領とゴルバチョフ大統領の首脳会談が実現したのに続き、9月にはニュー・ヨークにおける韓ソ外相会談で外交関係が樹立された。その後、12月に虜泰愚大統領がソ連を公式訪問し、また、91年4月にはゴルバチョフ大統領が訪日の帰途に韓国の済州島を訪問したことから、1年足らずの間に3度も韓ソ間で首脳会談が持たれることとなった。
また、中国との間では、90年10月に大韓貿易振興公社と中国国際商会との間で査証発給などの限定的な領事機能をも備えた貿易事務所の設置が合意され、91年に入り、ソウルと北京に各々事務所が開設されるなど、関係改善が見られている。
このような韓ソ間の動きなどを背景に、南北朝鮮間では、90年9月に南北分断以来初めての南北首相会談がソウルで開催された。その後、10月及び12月にも各々平壌及びソウルにおいてこの会談が開催され、多角的な交流や協力を実施する問題と、政治的、軍事的な対決状態を解消する問題について話合いが行われた。これらの会談では、南北双方の基本的な考え方の相違から具体的な成果は得られなかったが、会談の開催自体に大きな意義があった。その後91年2月、北朝鮮は米韓合同軍事演習の実施を理由に平壌における第4回会談を一方的に中断するに至ったが、7月に行われた北朝鮮の提案によりいったん8月末に会談が開催される運びとなった。しかし、ソ連政変の直後の8月20日、北朝鮮は韓国内でのコレラ発生を理由に会談の開催場所を板門店に変更するよう提案し、その後南北双方の話し合いの結果、第4回会談の開催が10月に延期されることとなった。なお、体育分野などでは交流が一部実現し、南北のサッカー大会が90年10月に平壌とソウルで開催されたほか、91年4月に千葉で開かれた第41回世界卓球選手権大会及び6月にポルトガルで開かれた第6回世界青少年サッカー大会に南北朝鮮は統一チームを派遣した。
また、米国との関係にあっては、91年7月に虜泰愚大統領が米国を訪問し、ブッシュ大統領との間で、朝鮮半島をめぐる新しい情勢などについて意見交換を行った。
国連加盟問題については、91年4月に韓国は、北朝鮮が南北朝鮮の国連への同時加盟に応じない場合は、91年秋の国連総会の前に単独で国連への加盟を申請する方針を表明し、積極的な外交を展開した。これに対し北朝鮮は、南北朝鮮が別々の議席で国連に加盟することは、国際的に「二つの朝鮮」を認めさせることとなり、朝鮮半島の分断の固定化につながるとして強く反対し、加盟するのであれば南北朝鮮が単一の議席で加盟するべきであると主張してきた。しかしその後、日本や米国を始めとして多くの国が、南北朝鮮の同時加盟が望ましいが、北朝鮮がこれを拒否し続ける場合は韓国の単独加盟を支持するという立場を明らかにしていった。このような中で、北朝鮮は難局を打開するため政策を変更し、暫定的措置として韓国とは別個に国連に加盟するとの方針を発表し、91年7月、国連事務局に加盟申請手続を行うに至った。北朝鮮が、このような発表を行った背景には、韓国が単独で加盟申請を行った場合、これに中国が拒否権を行使することは期待できないと判断するに至ったことや、日本を始めとする関係諸国からの働き掛けが功を奏したことがあると考えられる。
両国の加盟申請を受け、8月には安全保障理事会において南北朝鮮の加盟勧告決議が採択された。そして、9月に開会された第46回国連総会において加盟承認決議が採択され、南北朝鮮の国連への加盟が実現した。
日本は、かねてより朝鮮半島の統一に至る過渡期の措置として南北朝鮮が国連に同時に加盟することが、国連の普遍性の原則を高めるとの見地からも望ましいとの立場をとってきており、日朝国交正常化交渉の場においても、南北朝鮮の同時加盟が望ましい旨働き掛けを行ったところであり、南北朝鮮の国連加盟が実現したことを歓迎している。南北朝鮮の国連同時加盟は従来の南北朝鮮の関係の枠組みを大きく変化させるものであり、これによって、今後、朝鮮半島の緊張緩和が一層促進されることが強く期待される。
(3) 日本との関係
90年5月、虜泰愚大統領の訪日が実現し、日韓首脳会談が行われた。この会談は日韓両国が過去の歴史について一区切りをつけ、21世紀へ向けて世界的視野に立った協力を行う日韓新時代を構築していく上で大きな成果を挙げた。その後も、日韓定期閣僚会議(11月、ソウル)、海部総理大臣の韓国訪問(91年1月)、日韓外相定期協議(4月、東京)が行われた。
特に、海部総理の韓国訪問においては、長年の懸案であった在日韓国人三世問題に円満な決着が図られ、日本は、在日韓国人について2年以内に指紋押捺を行わないこととするなど幾つもの分野で抜本的な施策を講じる方針を表明した。また、未来志向的な日韓協力関係の方向性を示す日韓新時代の三原則、すなわち(あ)日韓両国のパートナーシップの強化へ向け交流、協力、相互理解を増進すること、(い)アジア・太平洋における平和と和解、繁栄と開放のために貢献すること、(う)グローバルな諸問題の解決を協力して推進することについて意見の一致を見た。
日韓両国は、このような原則を踏まえ、21世紀に向けた未来志向的な新しい関係を構築するための努力を行っている。具体的には、従来より行っている青少年を中心とする交流を一層拡充し、日本国民の韓国に対する理解を深めるための啓発事業として日韓21世紀誠信交流事業を推進している。また、地方間の交流を促進するため日韓自治体交流促進会議の設置にも合意した。さらに、6月には、未来志向的な日韓関係を考える日韓アジア局長会議を初めて開催した。アジア・太平洋経済協力(APEC)やサミット等で扱われる地域的ないしは地球的な問題についても日韓双方で緊密な連携と協力を行っている。
同時に、幾つかの二国間の懸案を解決するための努力も行われている。韓国の対日貿易赤字は、構造的な要因に加え、韓国の輸出競争力の低下により、90年には57億5,000万ドルに達している。また、韓国は、輸出競争力を強化するため日本に対し高度な産業技術の移転を求めている。これらの問題は、91年6月に行われた日韓貿易産業技術協力委員会の場で話し合われたが、日本は、産業技術の移転は基本的に民間企業の間の問題であり、政府としては可能な範囲で協力していくとの立場を伝えている。
また、漁業問題については、韓国漁船の日本近海における不法操業の問題が一向に解決しない状況の中で、現行の自主規制措置が91年末で一応の期限を迎えることになっているので、その後の日韓漁業関係のあり方を協議するため実務者協議を91年4月から7月までに3回開催した。資源の保存及び操業秩序の確立のため両国間で率直な話し合いを行っているが、不法操業の現状に対する双方の認識の差も大きく、今後とも難航が予想される。
韓国との間でその帰属につき争いのある竹島は、法的にも歴史的にも日本固有の領土であることは明らかであり、韓国に対しては、随時日本側の立場を踏まえて抗議を行っている。最近では、90年11月の日韓定期閣議会議の際の外相会談、91年4月の日韓外相定期協議等の機会に、この問題を韓国側に提起してきている。
3. 北 朝 鮮
(1) 内 政
北朝鮮では、90年5月の最高人民会議第9期第1回会議で金日成
91年初頭の金日成主席の「新年の辞」は、統一問題に重点を置き、統一の緊急性を強調するとともに、統一は併呑したり、併呑されたりしない原則に基づくべきであることに言及しているが、これは、西ドイツによる東ドイツの吸収という形でドイツが統一されたことに対する警戒の表われであると思われる。
経済の回復を示す動きは、特に見られなかった。「新年の辞」でも、目立った経済成果を発表しておらず、91年4月の最高人民会議で採択された91年度予算は、前年比4.5%の伸びで、90年度予算における前年比を大幅に下回り、経済は依然として困難な状況から脱していないものと思われる。
(2) 外 交
北朝鮮は、ソ連及び中国と同盟関係を維持し、東欧諸国との間でも緊密な関係を持ってきたが、ソ連や東欧諸国の改革の動きと韓国の北方外交の成功という変化の中で、現実を直視した外交へ転換を迫られている。
ソ連との関係では、韓ソ国交樹立を「ドルで外交関係を売り買いした背信行為」であるとして激しく非難したほか、中国代表団を招いた朝鮮労働党創立45周年記念行事にソ連代表団を招待しなかったなど、北朝鮮側の不快感を示す事例が見られたが、朝ソ両国とも基本的には両国関係の維持に努めている模様である。
中国との間では、ソ連との間に比べ相対的に緊密な関係を維持し、折に触れて社会主義体制を堅持していくことを中国と確認している。他方、91年5月の李鵬総理訪朝の際、韓国の国連加盟問題に関し、中国側が北朝鮮の意向に沿う態度を示さなかったものと思われ、両国関係にも変化が出始めている。
金日成主席は、91年の「新年の辞」でアジアは新たな発展段階に入っているとの認識を示し、アジア諸国との協力関係の発展の重要性を強調し、その後、対日外交を含めアジア外交を活発化させた。また、国連外交では、韓国の単独加盟の可能性が高まるのに対抗して、91年5月、国連に加盟する旨の声明を発表し、7月に加盟手続をとり、9月に加盟が実現した。北朝鮮は、85年に核不拡散条約に加入しながら、この条約上の義務である国際原子力機関(IAEA)との保障措置協定の締結を依然として怠っており、国際的に核開発の懸念を招いている。
(3) 日本との関係
日本にとって北朝鮮との国交正常化は、残された二つの戦後処理問題の一つである。隣国でありながら唯一国交のない状態が続いているが、90年以来、日朝関係は関係改善と正常化に向けて大きく動き出している。90年9月、自民党と社会党両党の代表団が訪朝した結果、日朝間において長年の懸案であった第18富士山丸の船員2名の抑留問題が解決され(注)、北朝鮮側より国交正常化交渉を行おうとの提案がなされた。日本側はこれに応じ、90年11月以降、両国は国交正常化交渉のための予備会談を北京で3回にわたり開催した。日朝双方は予備会談において、(あ)基本問題、(い)経済的諸問題、(う)国際問題、(え)その他双方が関心を有する問題の4つの議題の下で正常化交渉を始めることに合意し、91年1月末にこの交渉を開始した。
日朝の国交正常化には、戦後処理という二国間の側面と、国交正常化が朝鮮半島の平和と安定に資するものとなることが重要であるという国際的な側面があるが、日本は、日朝の国交正常化がこれら二つの側面を有しているということを十分に踏まえつつ、交渉に臨んでいる。
これまで行われた交渉においては、特に、経済的諸問題と国際問題について双方の立場が対立している。経済的諸問題について北朝鮮は、日本と北朝鮮は戦争関係にあったとして、交戦関係に基づく賠償を要求し、また、戦後45年間についても日本が北朝鮮に損失を与えたとして、戦後も含め補償を要求している。しかし、日本は、日本統治時代の36年間については、財産・請求権の問題として処理されるべきであり、戦後について日朝関係が不正常であったのは、東西対立を背景とする冷戦構造、朝鮮半島情勢、北朝鮮の政策等によるもので日本が責任を負う筋合いのものではないと主張している。また、国際問題に関し、日本は、北朝鮮が加入している核不拡散条約上の義務であるIAEAとの保障措置協定の締結を北朝鮮が拒否していることが核開発の懸念を醸成しているとして、北朝鮮が速やかに同協定を締結し、履行するべきであると主張している。これに対し北朝鮮は、この問題は北朝鮮と米国の間の問題であり、米国は北朝鮮に対し核兵器を使用しない旨の法的拘束力のある保証を与えるべきであり、また、韓国には米国の核兵器が存在しており、これらの核兵器も同時に査察を受けるべきであるなど、IAEAとの保障措置協定の締結とは直接関係のない政治的条件を主張し、同協定の締結を拒否してきた。その後、91年6月に至り、北朝鮮は同協定の締結に向けて一定の手続を進める意向を明らかにしたが、その後も従来の政治的条件に言及するなど、同協定を無条件に締結し、履行する意図を示しておらず、今後とも北朝鮮の動向を注視し、保障措置協定の締結と履行を求めていく必要がある。
なお、いわゆる大韓航空機爆破事件の犯人である金賢姫
1. 中 国
(1) 内 政
中国指導部は、最近のソ連、東欧諸国をめぐる状況をも念頭に置きつつ、経済力の向上なくしては中国の社会主義体制の存続はあり得ないとの危機意識に立って経済面での改革に取り組んでいる。89年の6. 4事件(天安門事件)以降、中国政府は党指導力の強化や思想工作の強化等の政治面での引締め政策を継続してきたが、これは経済改革を推進するためには国内の政治的安定と団結が不可欠の前提であるとの中国指導部の基本認識に基づいているものと思われる。
中国指導部は社会主義体制を維持していくためには、国民の支持が不可欠であることを強く認識し、党と国民の関係の強化や、国民の関心の高い汚職や腐敗行為の防止、治安の改善、民生の向上等に向けて諸措置を積極的にとった。他方、国民の中にある反政府的な動きには引き続き強い警戒感を有しており、90年9~10月に北京で開催された第11回アジア競技大会や91年の6. 4事件2周年などの際には厳戒体制を敷いて警備に当たった。
経済面においては、90年12月の共産党13期中央委員会第7回全体会議(七中全会)及び91年3~4月の7期全国人民代表大会第4回会議において、1978年末以来の改革・開放路線を推進するという基調を堅持することを再確認するとともに、改革を積極的に支持している鄒家華国務委員兼国家計画委員会主任及び朱鎔基上海市長を副総理に登用することを決定するなど、経済改革を強力に推進する動きが見られた。
具体的には、87年以来の深刻なインフレを克服するために経済調整政策が実施され、89年後半にはこれが一層強化された結果、インフレの抑制や総需給格差の是正については一定の成果が見られた。例えば、小売物価上昇率は89年には17.8%であったが、90年には2.1%に下がった。その反面、工業生産伸び率が89年の8.5%から90年第1四半期には0%に低下したことに見られるように、急激な引締め政策によって経済が停滞した。このような事態を打開するため、90年に入って引締めが若干緩和され、90年の国民総生産(GNP)伸び率は5.2%、工業生産伸び率は7.8%、農業生産伸び率は7.6%を記録し、経済成長計画目標は達成された。こうした状況を背景として、90年末の七中全会では2000年までにGNPの倍増を目標とする長期経済計画の基本方針が決定され、これに基づいて91年4月、経済効率の向上、産業構造の改善を重点目標として掲げた国民経済及び社会発展第8次5か年計画及び10か年計画要綱が全人代において採択された。なお、91年5月後半から華中・華南地区で発生した大規模な水害が経済成長に及ぼす影響が懸念されている。
貿易面では引き続き輸入抑制と輸出振興が推進され、貿易収支は89年には66億ドルの赤字であったが、90年には87億ドルの黒字に好転した。観光による外貨収入も、アジア競技大会等が開催されたこともあり、90年に入りほぼ88年の水準に戻った。西側諸国の中国に対する直接投資や直接借款等も90年後半以降は増加傾向にあり、対外開放政策の進展に伴い沿海地区を中心に投資事業が進んでいる。
(2) 外 交
中国は6.4事件以来冷却化していた西側先進諸国との関係の修復に引続き努力するとともに、経済建設を推進するためには安定した国際環境が不可欠であるとの観点から、ソ連及びアジア近隣諸国との関係の強化を図ってきた。中国は、新国際秩序はいまだ形成されておらず、世界は多極化の傾向にあると見ており、このような認識に基づいて、国際社会における中国独自の立場を模索している。
90年10月に欧州共同体(EC)が武器禁輸を除く対中措置を解除し、それ以降、スペイン、英国、フランス、イタリアの外相が次々と訪中するなど、欧州諸国との関係は大幅な改善を見た。こうした動きを受けて91年9月には英国のメイジャー首相、イタリアのアンドレオッティ首相といった首脳の訪中が行われた。他方、米国との関係は90年11月に銭其琛外文部長がブッシュ大統領と会見するなど、若干の改善も見られたが、91年に入り、米国議会において、中国に対する最恵国待遇の更新をめぐり、中国国内の人権問題、米中経済関係、武器移転問題等が強い関心を集め、米中関係は停滞した。しかし、その後、ブッシュ大統領が中国に対する最恵国待遇を無条件で更新することを決定し、中国側も中東の武器管理に関する米国の提案に協力することを表明するなど、両国の間で関係の改善が模索されている。
91年8月のソ連の政変とそれに続くソ連国内の変動は中国指導部に少なからざる衝撃を与えたものと推測されるが、中国は一貫してソ連や東欧諸国の内政に対する不干渉の態度を堅持してきている。ただし、中国はソ連の政局の安定と経済の回復は中ソ両国及びアジア・太平洋地域のいずれにも有益であるとの見解を91年初めより表明してきており、現在もこうした見解に変化はないものと見られる。なお、91年5月には江沢民総書記が1957年の毛沢東の訪ソ以来34年振りに中国の総書記としてソ連を訪問し、中ソ国境東部に関する協定を取り決め、両国の善隣友好関係を発展させていくことをうたった共同声明を発出した。
アジア近隣諸国との関係は引き続きおおむね順調に進展している。中国は韓国との経済交流を促進するため、90年12月、貿易事務所の相互設置を取り決めるとともに、91年6月、韓国と北朝鮮の国連への同時加盟を支持する旨を表明した。モンゴルとの関係では、91年1月のオチルバト人民革命党(与党)議長の訪中に続いて、4月にジャダムバー国防相がモンゴル軍最高指導者として30年振りに訪中した。中国からは、91年8月に楊尚昆国家主席がモンゴルを訪問した。ヴィエトナムとの関係では、90年9月ザップ副首相が訪中し、また、91年8月には北京で中越外務次官級会談が行われ、関係改善に向け大きく動き出そうとしている。また、ASEAN諸国との関係も活発であり、90年12月には李鵬総理がマレイシアとフィリピンを、91年6月には楊尚昆国家主席がインドネシアとタイをそれぞれ訪問し、同年7月には東南アジア諸国連合(ASEAN)外相会議に中国から銭其琛外文部長がゲストとして初めて参加した。
中近東諸国との関係では、湾岸危機に際して中国は国連安全保障理事会の決議におおむね賛成票を投じ、また、湾岸危機後も中東での軍備管理に前向きの対応を示すなど、国際協調を重視する姿勢を示した。91年7月には李鵬総理がエジプトを始めとする中東諸国を歴訪した。
(3) 日本との関係
日中関係は日本の外交の主要な柱の一つであり、中国との間で良好にして安定した関係を維持し、発展させていくことは、日中両国にとってのみならず、アジア・太平洋の平和と安定のためにも重要である。自由民主主義国である日本としては、89年の6.4事件における軍の実力行使は人道上の見地から容認することはできないとの立場をとっている。他方、累次のサミットでも明確にしてきたように、中国の孤立化は好ましくないとの基本認識を有しており、改革・開放政策に基づいた中国の近代化建設の努力にはできる限り協力するとの基本方針をとっている。
日中関係は6.4事件により一時後退したものの、日中双方の努力により着実に改善を見ている。90年1月には日中間のハイ・レヴェルの要人往来として6.4事件後初めて鄒家華国務委員兼国家計画委員会主任(当時)が、7月には李鉄映国務委員兼国家教育委員会主任が、また、11月には呉学謙副総理が訪日した。その間、日本からは90年9月のアジア競技大会開幕式に保利文部大臣が出席した。91年に入り、橋本大蔵大臣、中尾通商産業大臣がそれぞれ訪中し、4月には中山外務大臣が訪中した。中国からは6月に銭其琛国務委員兼外交部長が訪日した。その後、8月には海部総理大臣が中国及びモンゴルを訪問した。この訪問はこれまでの閣僚級の往来を総括し、両国関係を再構築するとともにこれを新たな段階に押し上げ、92年の国交正常化20周年につなげるとの積極的意義を有するものであった。
また、日中間の経済関係も、90年後半以降の中国情勢の鎮静化や中国と西側諸国の関係改善に伴い、改善の方向にある。90年7月のヒューストン・サミット以降、政府は6年間で総額8,100億円の供与をめどとする第三次円借款を徐々に実施に移してきており、91年8月に海部総理大臣が訪中した際には、91年度分として1,296億円の円借款を供与する意図を表明した。日中貿易は中国が貿易収支改善のため輸入を抑制した結果、89年後半以降は日本の対中輸出が落ち込み、90年には、約59億ドルの赤字を記録するなど、日本側の赤字が拡大していたが、90年末頃より中国が輸入規制を緩和したため、91年に入って日本の対中輸出は回復しつつある。日中貿易の安定化のため、90年12月に民間ベースで日中長期貿易取決めが更新され、91年3月には政府間でも日中貿易協定に基づく第6回日中貿易混合委員会を開催した。このほか、投資面では、90年7月、日中投資保護協定に基づく第1回日中投資合同委員会を開催し、また、90年10月及び91年7月には日中間の技術移転促進を目的とした日中技術交流会議を開催した。
2. 香港、台湾
日本は、香港が97年以降も英中共同宣言及び香港基本法に基づき、現在の経済的自由を享受しながら繁栄と安定を維持していくことが、アジア・太平洋ひいては国際社会全体にとって肝要であると認識している。この関連で、91年7月、懸案となっていた香港新空港建設問題について英中間で合意が成立したことを歓迎している。
台湾との関係については、日本は1972年の日中共同声明の立場を堅持しつつ対応しており、今後ともこのような立場に変更はない。台湾経済の持続的成長は、今やアジア・太平洋地域全体の繁栄にとり重要な要素となっており、政府は、日中関係の基本的枠組みの中で、こうした台湾との関係を進めてきている。
3. モ ン ゴ ル
モンゴルにおいては、ソ連や東欧諸国の民主化や改革の影響を受け、89年末以来、民主化と国内改革の動きが急速に進展してきている。特に、90年3月、与党人民革命党内の旧指導者が総辞職し、改革派が主導権を握るとともに、議会において複数政党制が採用され、それに伴って党と政府の完全分離の原則も打ち出された。5月には大統領制への移行と恒常的議会の設置が人民大会議で決定され、7月には史上初の自由選挙が実施された。その結果、野党との連合による新政府が成立し、対外開放政策によって西側諸国との関係を強化し、市場経済への移行を含む経済体制の改革を実施に移すことにより直面している経済危機を克服するため与野党が一丸となって努力している。
モンゴルは国内各派の対話を通じ、以上のような大胆かつ急速な変革を、極めて穏健な方法で実現してきている。サミットの場においてもこのようなモンゴルの努力は高く評価ざれ、サミット参加国はモンゴルに対する支援が必要であることにつき意見が一致している。
日本との関係では、90年2月、モンゴルのソドノム首相が訪日したが、これはモンゴル首相として初めての西側諸国訪問であった。モンゴルからは、さらに11月にオチルバト大統領が訪日した。91年8月、海部総理大臣は日本の総理大臣として初めて、また、西側首脳としても初めてモンゴルを訪問し、モンゴルの民主化や経済改革を積極的に支援していくことを表明し、両国関係は更に深まった。また、9月、日本と世界銀行の共同議長の下に、東京でモンゴル支援国会合が開催された。この会合には14か国及び5つの国際機関が参加し、91年度においてモンゴルが必要とする資金を充足する支援が表明される等、大きな成果を収めた。
1. 概 観
東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国は、前述のように、おおむね順調な経済発展を遂げ、東南アジア、ひいてはアジア・太平洋地域の重要な安定要因となっている。日本との間においても、政治、経済、文化等、幅広い分野において関係を深めている。海部総理大臣が91年4月末から5月初旬にかけて、マレイシア、ブルネイ、タイ、シンガポール、フィリピンを訪問し、シンガポールで日本の外交の針路を明確に示す政策演説を行ったこと、その後中山外務大臣が6月にインドネシアを訪問し、7月にマレイシアで開かれたASEAN拡大外相会議に出席し、さらにフィリピンを訪問したことは、このような関係強化の努力の一環である。また、9月末から10月初めには、天皇・皇后両陛下がタイ、マレイシア、インドネシアを御訪問されることになっている。
ASEAN諸国は、東西冷戦の終焉や湾岸危機の影響もあり、最近、政治や安全保障の問題に対する関心を強めており、91年7月のASEAN拡大外相会議でも、これらの問題に多くの時間を割いて活発な意見交換を行った。また、フィリピンとタイは共同で91年6月にマニラで学識者を中心とした安全保障セミナーを開催し、日本からも参加があった。両国はさらに、11月にバンコックで同様のセミナーを開催する予定である。
また、ASEAN諸国は、冷戦構造の解消を踏まえて、ソ連や中国との関係の進展を模索し、外交の幅を広げる努力を行っており、91年7月のASEAN外相会議の開会式に両国をゲスト参加の形で招待した。
インドシナ地域においては、最大の懸案であるカンボディア問題が解決の方向に動いている。また、ヴィエトナムとラオスにおいて経済改革の諸施策が講じられ、自由経済を目指す動きが出てきている。日本は、カンボディア和平の達成に最大限の努力を続ける決意であり、和平が達成した後には、カンボディア、ひいてはインドシナの復興を目的とするカンボディア復興に関する国際会議を、適当な時期に日本において開催する用意があることを明らかにしている。
2. インドネシア
内政は、基本的には、平穏に推移した。90年にイスラム教徒の知識人を糾合した全インドネシア・イスラム知識人協会が結成された。91年に入り、92年の総選挙と93年の正副大統領選挙に向けて政治への関心が高まっており、また、民主主義フォーラムが結成されるなど、民主化を求める動きが活発化している。
経済面では、過度の石油依存経済からの脱却を目指した経済構造調整が奏功し、経済成長率は88年は5.7%、89年は7.4%となっており、順調に成長を続けていた。過去2~3年に大幅な伸びを示した非石油・非ガス製品の輸出の伸びは鈍化したものの、石油・ガス輸出が大幅に増加するとともに、海外からの直接投資、国内投資が大幅に増加したため、90年の実質国内総生産(GDP)成長率は7.4%となった。一方、経済の活発化によってインフレ圧力が増大し(90年の物価上昇率は9.53%)、また投資の増加による資本財や中間財を中心とした輸入が急速に増加したことから強力な金融引締めが行われた。90年の貿易総額は前年比23.3%増の475億ドルとなった。なお、湾岸危機の影響によって国外からの送金が停止し、観光客が減少した。また、91年6月の対インドネシア援助国会合では参加国や国際機関より前年度比5%増の総額47億5,000万ドルに上る援助の意図表明があった。
ここ1年のインドネシア外交は、カンボディア問題の解決と中国との外交関係の再開を主要課題として進められた。カンボディア問題の解決のため、アラタス外相はパリ会議の共同議長として活発な外交を展開した。例えば、91年6月にカンボディア問題の解決に向けジャカルタにおいてカンボディア4派の会合を開催した。また、中国との関係では90年8月の李鵬総理のインドネシア訪問によって、1967年に凍結された外交関係が再開され、90年11月にはスハルト大統領が初めて中国を訪問した。また、その帰路、大統領は、ヴィエトナムを初めて訪問した。
このほか、スハルト大統領は、91年6月にメッカ巡礼、7月にドイツ訪問を行った。
インドネシアは、石油や天然ガスの供給や投資などを通じて、日本と強い経済的相互依存関係にあり、日本にとって重要な航路が通る地域に位置し、東南アジアにおいて大きな政治的発言力を有していること等から、非常に重要な存在である。同国の開発ニーズも大きいことから、日本としてはその安定と発展のために経済協力を中心として従来より最大限の協力を実施している。このような姿勢を反映し、両国政府間では引き続き要人の往来が頻繁に行われた。90年11月、即位の礼に参列するため訪日したスハルト大統領は海部総理大臣と首脳会談を行った。また、91年6月には中山外務大臣がインドネシアを訪問し、アラタス外相等とカンボディア問題等につき意見交換を行った。経済を中心に発展してきた両国関係を更に幅広い均衡のとれたものとするためには、二国間の政治対話がますます重要になるという観点から、同年3月には、ジャカルタにおいて第1回外交高級事務レベル協議を開催した。
3. シンガポール
内政面では、90年11月、リー・クァンユー首相は、ゴー・チョクトン第一副首相兼国防相に政権を委譲した。ゴー新首相は、政策面ではリー前首相を引き継ぐことを表明しており、内政及び外交の基本に変更はないと見られるが、政治スタイルについては対話の政治による独自のスタイルを打ち出すと述べており、リー前首相の強い個性と指導力による政治とは一味違ったアプローチが出てくるものと見られる。
経済面では、湾岸危機の影響をほとんど受けることなく、経済成長率は8.3%を記録した。経済成長はすべての分野にわたっており、内外需とも好調で、力強い成長基調にある。
外交面では、シンガポールは、周辺国に対する配慮から、中国との外交関係の樹立はインドネシアと中国の国交正常化後に行う旨をかねてより表明してきたが、90年8月にインドネシアが中国との国交を正常化したことを受け、同年10月に中国と外交関係を樹立した。また、シンガポールは、東南アジア地域における米軍の存続に寄与するのであれば、米軍の軍事施設を国内に受け入れる用意があるとの意思を表明していたが、90年11月、シンガポールと米国は、米軍によるシンガポール軍事施設の使用の拡大につき合意した。
日本とシンガポールの間には大きな懸案もなく、政府は官民双方における幅広い交流を一層活性化させることにより、良好な関係を促進するよう努めている。90年11月のリー・クァンユー首相(当時)及びウォン・カンセン外相の訪日があり、日本からは91年5月に海部総理大臣がシンガポールを訪問すること等により高いレベルで間断ない対話を行った。また、民間レベルでも、投資が増大し、シンガポールを訪れる日本人が90年には99万人に達するなど、経済分野、人的交流面でも活発な交流が行われた。
4. タ イ
88年8月に成立したチャチャイ内閣は、軍部との協調関係及び経済の好調に支えられ、比較的順調に国政の運営を行ってきたが、90年に入り、各種利権をめぐる閣僚間の対立、汚職問題などが表面化し、軍部との協調関係も破綻し、これらの問題をめぐって対立が深刻化した。チャチャイ首相は90年後半に3回にわたる内閣改造を実施し、難局の打開を図ろうとしたが事態の改善には至らず、91年2月23日、軍部は国民の信頼を失った政府にこれ以上政権を委ねることはできないとの理由によりクーデターを敢行し、直ちに全権を掌握した。
政変は無血かつ無暴力のうちに短期間に収束した。プーミポン国王は政変と新政権に事後承諾を与え、また、タイ国民の人心もチャチャイ政権末期の状況に倦んでいた側面もあり、クーデターに対して総じて冷静な受け止め方を示した。その後、暫定憲法の公布を経て、3月6日、文民を主体とするアナン内閣が成立した。今後、同暫定憲法に基づき設置された国家立法議会が恒久憲法を起草し、91年中、遅くとも92年4月までにはこの恒久憲法に基づいて総選挙が実施される予定である。アナン内閣は、総選挙の実施に向けた民政移管の推進と、国内経済の効率的運営を柱とした積極的な経済政策に努力してきており、これまでのところ、その政策は国民の間で好感を持たれていると言える。
クーデター後アナン新内閣は、タイの国際的なイメージの回復を最重要課題として、日本や米国等との関係の維持と発展に努めている。また、周辺諸国との善隣友好関係の構築と維持、経済協力関係の推進にも力を注いでおり、最近、ラオス等との関係に改善が見られている。カンボディア問題に関しては、カンボディア各派首脳間での意思疎通の促進に努めるなど、引き続き重要な役割を果たしてきている。
90年のタイ経済は、湾岸危機による石油価格の上昇の影響が懸念されたが、官民双方の適切な対処によりその影響は最小限に食い止められた。輸出の拡大及び内外よりの活発な投資活動等に支えられ、88年以来3年連続の2けた成長を達成した。他方、消費財、原材料及び資本財輸入の増加により、貿易赤字は拡大する傾向にあり、物価上昇圧力も高まっている。
日本との関係では、ワチラロンコーン皇太子殿下及びチャチャイ首相(当時)が90年11月の即位の礼に参列するために訪日したほか、日本からは、90年8月に中山外務大臣が、91年4月に海部総理大臣が、タイを訪問し、活発な交流を継続した。海部総理大臣の訪問は、クーデター後初めての先進国首脳によるタイ訪問となったが、首脳会談において、アナン首相は早期に民政移管を実現するとの決意を表明するとともに、タイの基本政策に変化がないことを強調した。このような意図の表明を踏まえ、両首脳は今後とも両国の協力関係を更に発展させ、強化していくことが重要であるとの点で一致した。
日本との貿易では、近年の活発な直接投資の結果として、90年においても資本財を中心とする日本からの輸入が増加しており、タイの対日貿易赤字は約50億ドルに上った。また、投資面では、90年の日本からの投資は前年比で約24%減少しており、85年9月以降の円高等を背景とした投資の急増は山を越えた模様である。
5. フィリピン
内政面では、89年12月の国軍不満分子等による大規模なクーデター未遂事件以降、政情は不安定化した。しかも、ルソン島における大地震(90年7月)や湾岸危機等、種々の外的要因により経済状況が悪化したこともあり、90年後半はアキノ政権にとり困難な時期となった。このような状況の下で、90年10月にはミンダナオ島で、アキノ政権が成立してから7回目の反乱事件が発生したが、アキノ政権は断固たる姿勢をもって対処し、この危機を乗り切った。その後91年に入り、政情は相当落ち着きを見せてきており、政局の焦点は92年5月に予定されている次期大統領選挙へと移ってきている。
経済面では、フィリピンは過去2~3年の間、5~6%台の比較的高い成長率を達成していたが、90年に入り、上述の天災等の影響もあり減速傾向を示した。さらに同年8月の湾岸危機の発生により、エネルギーの大半を中東地域からの輸入原油に依存するフィリピンは原油価格の高騰の影響をまともに受け、貿易収支が悪化し、外貨準備が減少し、インフレが進んだ。さらに、中東地域に約60万人いると言われるフィリピン人出稼ぎ労働者のうち多数が帰国し、または他の地域に避難したことにより本国への外貨送金が減少し、国内の失業が増大した。これらの経済的困難が続いた結果、経済成長率は89年の5.7%から90年には3.7%へと大幅に低下した。しかしながら、アキノ政権がこの経済困難を乗り切るため種々の対応策を講じたことと、国民の間に一致団結して危機を乗り越えようという意識が強まったこと等があいまって、当初心配されたような社会的、経済的混乱は生じなかった。91年2月には香港で対比多国間援助構想(MAI)の下での第2回援助国会合が開催され、参加国や国際機関から合計33億ドルの援助の意図表明が行われ、また、6月にはパリ・クラブでフィリピンに対する債務の繰延べが合意されたこともあり、フィリピン経済は何とか最悪の状況を脱しつつある。ただし、同国は依然として、巨額の累積債務、外貨の不足、高い失業率、インフレ、貧富の格差等の経済問題を抱えており、経済の再建が引き続きアキノ政権にとり最大の課題となっている。なお、91年6月のピナトゥボ火山の大噴火は極めて大きな被害をもたらしており、再建の途上にあるフィリピン経済に更に新たな重荷を課すこととなった。
外交面では、91年9月以降の在フィリピン米軍基地の存続につき90年9月以降、米国との間で交渉を行ってきた。91年7月に、クラーク空軍基地等は米側がフィリピン側に返還し、スービック海軍基地を最低10年間存続させることで基本的合意が成立し、8月にはその合意を含む米比友好協力安全保障条約が署名された。この条約は8月下旬にフィリピン上院に提出され、審議されてきたが、9月16日上院により批准を否決された。これを受けて10月2日、アキノ大統領は、在フィリピン米軍の撤退期間を3年以内とする行政協定の締結に向けた交渉を米国政府との間で進めたい旨発表した。なお、アキノ大統領は引き続き国内問題に専念するとの立場から、90年11月に即位の礼に参列するために日本を訪問した以外には外遊しなかった。
日本は、上記のように困難な状況にある経済を再建しようと努力している同国をできる限り支援することをフィリピンに対する政策の基本としている。91年5月に海部総理大臣が、また7月に中山外務大臣がそれぞれフィリピンを訪問した際にも、繰り返しこのような立場を表明している。また、91年2月の第2回対比多国間援助構想会合において、フィリピンに対する最大の援助国となっている日本は90年度分として総額約2,053億円の政府開発援助(ODA)の供与について意図を表明した。他方、民間レベルにおいても、両国間の貿易額や投資額は順調な増加を示しており、特に90年の日本からの投資額は大幅に増加し、外国からの投資では、89年に続き第1位であった。
6. ブ ル ネ イ
ブルネイの内政は引き続き安定的に推移しているが、依然石油や天然ガスの生産のみに依存する経済体質に変わりはなく、経済構造を転換する具体的な動きは見られない。
外交面では、ASEAN中心の外交を展開するとともに、湾岸危機の際には、一貫して国連決議を支持した。
ブルネイは石油の約3割、天然ガスの全量を日本に輸出しており、両国は相互依存関係にある。ブルネイは経済構造の転換を図ろうとしており、特に技術移転の面で日本に大きな期待を寄せているが、日本もできる限りの協力を行っていく方針である。政府レベルの交流では、90年11月の即位の礼にボルキア国王兼首相、ジェフリ蔵相が参加した。また、91年4月には海部総理大臣がブルネイの完全独立後、日本の総理大臣として初めてブルネイを訪問した。この首脳会談では、日本がペルシャ湾に掃海艇を派遣することに対し、ボルキア国王より、強い支持が表明された。
7. マレイシア
マレイシアでは、90年10月に下院が解散され、総選挙が実施された。この総選挙では、今までにない強力な野党連合が結成され、さらに、立候補届け出の締切り後に、与党連合の一部が野党連合に転じたことなどにより、勝敗を決めるとされる憲法改正に必要な3分の2の議席を与党が確保できるかが危ぶまれた。しかし、結果は与党連合が180議席のうち127議席を確保する勝利を収めた。ただし、総選挙と同時に実施された半島部各州の州議会選挙のうち、クランタン州では野党が全議席を獲得した。総選挙勝利の勢いをかってマハディール首相は、90年11月の与党連合第一党の統一マレイ国民組織党役員選挙で総裁に無投票で当選し、その地位を一層安泰にした。
経済は順調で、90年の国民総生産(GNP)成長率は10.0%となった。外国からの投資も順調な伸びを示し、90年の対マレイシア海外投資は前年比83%の伸びを示した。91年6月には、新経済政策(71~90年)が期限を迎えたため、91年から2000年までの長期的経済の指針となる新開発政策が下院に提出され可決された。この政策の主たる目標は、新経済政策と同様に貧困の撲滅と社会の再編成にあり、このような目標を達成するため、高い成長率の維持を前提として、人的資源の育成、科学や技術の振興に重点を置くとしている。
外交面では、90年末まで国連安全保障理事会の非常任理事国を務めた。また91年7月にはASEAN外相会議及びASEAN拡大外相会議がクアラ・ルンプールで開催された。
日本との関係では、マレイシア側は順調に進んでいる経済発展を一層促進するために、東方政策(注)を柱とする人づくり、資金協力、投資等の面で日本に大きな期待を寄せており、日本もこれに可能な限り応えるよう努めている。政府レベルでの交流は、91年4月、海部総理大臣がマレイシアを訪問し、東方政策に対する協力等につきマハディール首相と意見を交換した。また、同年5月にはアブドラ外相が訪日した。経済面では、90年も引き続き日本がマレイシアにとり最大の貿易相手国となり、両国の貿易量は前年比18%増加した。また、日本はマレイシアに対する第2位の投資国であり、90年には日本からの投資は前年比で67%増加した。
8. ヴィエトナム
内政面では、91年6月末に第7回共産党大会が開催され、グエン・ヴァン・リン書記長の退陣を含む大幅な人事の刷新が行われたが、同時に、ドー・ムオイ新書記長の下で、経済の自由化や開放化を柱とする刷新政策の継続と強化が確認された。また、この党大会では、ソ連や東欧諸国の変革に関連して共産党の一党支配を堅持し、政治的多元主義は導入しないという方針が確認されたものの、同時に国会の権限強化など民主化に向けた動きも次第に強まってきている。
経済面では、90年の原油生産は前年比17%増の270万トンとなり、米の輸出が前年比11%増の150万トンとなるなど、明るい面もある一方で、失業者の増大、石油製品、肥料等、一部物資のソ連がらの供給削減、国営企業の不振等、マイナス要因も多く、一人当りGNPが推定で200ドルと言われる貧困状態から脱却し得ないでいる。
外交面では、89年9月末の在カンボディア越軍の撤退を発表した後、カンボディア問題に関しては、カンボディア人自身が解決すべき国内的問題しか残されていないとの立場をとってきているが、国際社会は、依然としてヴィエトナムが問題解決のために果たすべき役割は少なくないと考えている。中国との関係については、90年9月の成都における中越首脳会談、北京アジア大会へのヴォー・グエン・ザップ副首相の派遣を通じ関係改善に努め、国境地域で民間交易も盛んになった。こうした中、91年7月、レ・ドック・アイン党政治局員・国防相、続いて8月、グエン・ジー・ニエン外務次官がそれぞれ訪中し、カンボディア問題の解決に努力することで基本的に合意するとともに、両国間の経済、貿易、交通、郵便関係の回復を含む正常化問題につき意見交換を行うなど、関係正常化へ向けて具体的な進展が見られた。
米国との関係の改善も大きな課題であり、90年9月に、国連総会に出席したグエン・コー・タック外相がベーカー国務長官と会談し、また、タック外相のワシントン訪問が実現するなど、関係改善に向けての一定の動きが見られた。これに対し米国は、対越関係の正常化に向けた段階的条件(ロード・マップ)を示したが、ヴィエトナム側が期待するような形での進展は見られていない。
カンボディア問題という制約の中にあっても、インドシナにおいて地理的、歴史的に重要な位置を占め、また、豊富な天然資源と質の高い労働力を背景に豊かな経済発展の可能性をもつヴィエトナムとの関係を中・長期的な観点から考えていくことは、日本の東南アジア政策全体にとり極めて重要である。このような観点から、1978年末のヴィエトナム軍のカンボディア侵攻以来、日越関係全体が停滞を余儀なくされる中で、政治対話、文化や学術面の交流、人的交流など関係の拡充のために努力が続けられてきた。
90年10月のタック外相の訪日及び91年6月の中山外務大臣の訪越は、正にこのような地道な努力の積み上げの上に実現したものである。特に中山外務大臣の訪越は、南北ヴィエトナム統一後初めての日本の外務大臣の訪越となり、この機会を通し日越関係の新時代の到来が確認された。中山大臣は訪越に当り、将来の日越関係を展望し、ヴィエトナムの開放化に対する支持を表明するとともに、これを積極的に支援すべく、知的支援を拡大する方針を伝えた。また、カンボディア問題解決に向けて双方が努力することでヴィエトナム側指導者と意見の一致を見た。日越間の貿易関係は、日本向け原油の輸出増もあり、近年著しく拡大してきている。日本企業のヴィエトナムに対する関心も年々高まってきている。
9. カンボディア
東南アジアにおける最大の不安定要因であるカンボディア問題については、89年のパリ会議以降その早期解決に向け関係国が様々な取組を行ってきた。日本も、同じアジアの一国としてカンボディア問題の早期解決に積極的に貢献するという立場から、特に紛争の直接の当事者であるカンボディア各派間の対話の促進に尽力してきた。これは、カンボディア問題の最終的解決のためにはカンボディア人自身が現実的な決断をすることが不可欠であるという考えによるものである。90年6月に日本が主催したカンボディアに関する東京会議は、こうした日本の努力の具体例であった。これまでのASEAN諸国との友好関係の構築を一つの例とし、カンボディア問題の解決を通じてインドシナ諸国との信頼関係を築くとともに、インドシナ諸国の地域としての発展に協力し、もって東南アジア全体の平和と安定に貢献することが、日本の東南アジアに対する外交の基本目標である。
カンボディア和平をめぐっては、カンボディアに関する東京会議において、シハヌーク殿下とフン・セン首相(プノンペン政権)が両派の均衡構成によるカンボディア最高国民評議会(SNC)の設置等をうたった共同声明に署名したものの、クメール・ルージュ派が反対したためSNCが直ちに発足を見るには至らなかった。しかし、その後の90年9、実質的活動ができない状況が続いた。
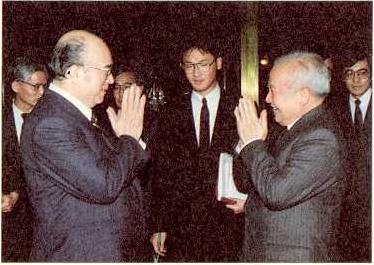
北京におけるシハヌーク殿下と中山外務大臣の会談(91年4月)
月のジャカルタにおけるカンボディア4派の会合では、クメール・ルージュ派が歩み寄りを見せ、東京会議の共同声明の合意に沿った形でSNCが正式に誕生することとなった。このような進展の背景には、中越間の対話の進捗があったとも言われるが、SNC自身は、その後、議長の選出に関する問題で各派が対立し
一方、国連安全保障理事会の常任理事国(P-5)は、90年1月以来非公式会合を重ねていたが、8月末の会合において、カンボディア和平の骨格を定めた枠組文書に合意し、これが前述のジャカルタ会合でカンボディア各派により受け入れられた。SNCが実質的活動を行えない状況の中、P-5は11月にパリ会議共同議長(インドネシア及びフランス)と共に、カンボディア人当事者に代わって包括的和平案を作成し、12月に共同議長がSNC参加者をパリに招いてこの和平案を提示した。
このパリ会合において、国民政府側は包括的和平案の全面受入れを表明したが、プノンペン政権側は、国連の大幅な関与による現政権の解体は、政治的混乱を招く可能性があり、武装を解除してしまえばクメール・ルージュ派による集団殺害の復活を防止することができないとして、包括的和平案の関連部分は受け入れ難いと主張した。そのため、詳細はパリ会議調整委員会の場及びSNCで継続討議されることとなった。実際にはその後、調整委員会とSNCのいずれも開催される見通しがないまま、和平に向けた動きは91年に入り再び暗礁に乗り上げた感が強まった。
日本は、このような状況が続けば、国際社会のカンボディア問題に対する関心が希薄となり、和平に向けた勢いが失われるとの判断から、パリ会議共同議長の努力を側面的に支援する形で、包括的和平案を補強するための非公式な考え方を示しつつ、プノンペン政権及び国民政府の両者と接触して事態の打開に努め、カンボディア人当事者も日本の努力を高く評価した。
他方、91年4月、パリ会議共同議長は国連事務総長と連名で、共同議長とSNCメンバーとの会合を近く開催することを前提に、それまでの間カンボディア各派が自発的に停戦を行うよう呼び掛け、この呼びかけに各派が応じる形で5月1日以降、曲がりなりにも武力行使の自粛が初めて実現した。
しかしながら、その後ジャカルタで開催された会合(6月2~4日)では、共同議長国がプノンペン政権側の主張を踏まえ、和平案の修正作業を開始することを提案したが、クメール・ルージュ派の頑固な対応により頓挫した。また議場外では、シハヌーク殿下とフン・セン首相がSNC議長の選出及び暫定停戦の延長に合意したが、クメール・ルージュ派がまたしても反対したために、ジャカルタ会合自体は和平の実質的進展につながらず、国際社会はクメール・ルージュ派の非妥協的態度に対する批判を強めることとなった。
こうした中で、シハヌーク殿下はフン・セン首相との協力関係に対する自信を強め、その後、タイのパタヤで開催された第2回SNC会合(6
|
カンボディア問題に関する日本の協力(91年前半)
|
月24~26日)及び北京でのSNC非公式会合(7月15、16日)を通じて卓越した指導力を発揮し、(あ)シハヌーク殿下のSNC議長への就任、(い)SNC本部のプノンペン設置、(う)暫定停戦の延長と外国からの援助の受取りの停止、(え)この暫定停戦の国連による監視の態様とその規模を決定するための調査団の派遣を国連事務総長に要請すること等につき合意が成立した。同調査団派遣の要請に対しては、国連は8月下旬にその派遣を決定した。
こうして12年に及ぶ内戦の末、カンボディア人指導者達の間に、ようやくカンボディア人自身で問題を解決しようとする気運が高まる中、90年9月に発足を見ながら実質的活動を成し得ずにいたSNCが本格的な機能を開始した。しかしながら、パタヤ及び北京の両会合では、プノンペン政権側が問題にしている包括的和平案の核心の部分である武装解除及び国連の具体的関与のあり方等についての詳細な議論が行われた訳ではなかった。その意味で8月26日から予定されていたSNC第3回会合(パタヤ)の行方が注目されたが、ここでも、シハヌーク殿下と同殿下を議長とするSNCは、各派の軍の取り扱いにつき、各派とも兵員の7割を動員解除、残り3割については武器とともに集結地域に留め置き、武器は同地域内で国連カンボディア暫定機構(UNTAC)の管理の下に置くこと、及びSNCとUNTACの権限関係につき、SNCメンバー間に合意が成立しない場合には、議長たるシハヌーク殿下が最終決定を下すこと等に合意した。
こうして、カンボディアの和平プロセスは、中越関係改善が一層進む中、シハヌーク殿下の指導力に、クメール・ルージュ派を含むカンボディア各派が柔軟に対応したことにより、大きな前進を遂げ、今後、パリ会議の再開に向け、大詰めの調整を迎えることとなった。
10. ミャンマー
ミャンマーでは、90年5月の総選挙の実施後1年以上が経過したが、政権委譲に至る手順や時期については不透明な状況が続いている。特にミャンマー政府は、政権委譲の前提として国家統一の観点から強固な新憲法を作成することが重要であるとして、憲法起草のため国会議員、各政党代表、各少数民族代表等からなる国民会議を開催するとしているものの、その開催時期や手続は依然明らかにされていない。他方、ミャンマー政府は開放経済政策を推進するという姿勢は示しているものの、硬直的な経済構造、金融財政政策面での経済運営上の問題等により経済困難の解決のめどは全く立っていない。
日本は、ミャンマー政府に対して総選挙の結果を踏まえ、政権委譲に向け具体的な日程を明らかにすることが重要である旨を種々の機会に伝えてきている。また、88年の政情の混乱以来、事実上実施を中断していた経済協力については、現在、実施可能なものから徐々に活動を再開しているが、新規案件の実施については、緊急的、人道的な性格のものを除き引続き情勢を見守ることとしている。
11. ラ オ ス
内政面では開放化政策に基づく経済改革が引き続き推進される中で、90年12月、ラオス人民民主共和国樹立15周年記念を迎えた。91年3月に5年振りに開催されたラオス人民革命党第5回大会では、カイソーン党議長を中心とする指導体制の維持、党の指導の下での政治・経済改革の促進等が確認された。法制面の整備も進捗し、91年8月、懸案の憲法が公布された。新憲法に基づき、カイソーン前首相が新大統領に選出され、新首相にはカムタイ前副首相兼国防相が就任した。
外交面では、ヴィエトナム、カンボディア(プノンペン政権)、ソ連等、社会主義諸国との連帯関係を強化するという基本政策に変化は見られなかったが、ソ連や東欧諸国との関係が微妙になったのに対し、中国、タイ及び西側先進諸国との関係は改善の方向に向かった。
ラオスはインドシナ三国の中では、今のところカンボディア問題から派生する制約のない唯一の国であり、また、市場原理を重視した経済改革や開放化を日本の経験から学びつつ推進していることもあり、日本としては将来のインドシナ政策全体を見据えつつ、経済協力を中心としてラオスとの良好な関係を構築することを重視している。
89年11月のカイソーン首相の訪日及び90年8月の中山外務大臣のラオス訪問を契機に両国関係は緊密の度を加え、その後は、政府間レベルのみならず、議会間や民間部門の交流も活発化している。日本はラオスの開放化政策を歓迎し、これを支援するために経済運営に関する専門家や法律専門家を派遣している。
1. 概 観
南西アジア諸国は、国際秩序の変革を受け、域外諸国との関係及び域内各国間の関係の両面において従来の政策の再検討を迫られている。また、湾岸危機は、南西アジア諸国に対し経済的に甚大な悪影響を与えたのみならず、イスラム教徒の感情を刺激し、各国の内政及び対外関係に多大な影響を与えた。このような中で、南西アジアの特色の一つである人種、民族、宗教、言語、文化等における多様性が各国の国内政情を一層複雑なものとしており、90年4月以来、ネパール、パキスタン、インド、バングラデシュの4か国で政権の交代があった。91年5月のラジーブ・ガンジー元インド首相の暗殺もこのような不安定性を典型的に示す現象の一つと言えよう。
他方、南西アジア地域においてはネパール及びバングラデシュにおける民主化の進展、インドとパキスタンの間の信頼醸成のための外務次官級協議の開始と継続、南アジア地域協力連合(SAARC)による地域協力の本格化の兆し等、好ましい動きも見られる。これらの動きは、南西アジア諸国において、一般的に現実的な政策指向が強まってきていることを反映していると言えよう。
南西アジア諸国は従来よりいずれも極めて親日的である。90年11月の即位の礼には南西アジア諸国はいずれも極めて高いレベルの代表を参列させた。さらに、近年、日本の著しい経済発展等を背景として、経済面はもちろんのこと、政治面でも日本に一層大きな役割を求める気運が高まってきている。南西アジアが大きな転換点に立っている現在、各国の対日期待感に応えて日本が時機を失うことなくこの地域のために寄与していくことの意義は大きい。日本は、このような観点から、南西アジアにおける好ましい動きを積極的に支援してきた。このような例としては、インド・パキスタン間でカシミール問題を対話によって平和的に解決するよう両国に働き掛けたこと、ネパールにおける民主的な憲法の起草の参考に供するため日本国憲法に関連する資料や情報を提供したこと、バングラデシュ及びネパールにおける選挙に超党派国会議員による監視団を派遣したこと、SAARCによる域外諸国との協力のあり方の検討の参考に供するため日本とASEANの協力関係に関する資料を提供したことなどが挙げられる。なお、国連が関与していない外国の選挙に日本が監視団を派遣し、また日本の国会議員が外国の選挙の監視を行ったのは91年2月のバングラデシュ総選挙の際が初めてである。
また、日本と南西アジアとの関係は従来経済協力を中心とする偏った関係となっていたが、90年4~5月に海部総理大臣が南西アジア諸国を訪問した際、日本はこの関係を政治、経済、文化等の分野を含めて幅と深みのある関係とするよう努力するとの方針を表明した。このような観点から外務省において91年度から南西アジア・フォーラムを開催し、各界有識者から日本と南西アジア諸国との関係を幅と深みのあるものとするための助言を得ることとした。
2. イ ン ド
90年8月、シン首相が後進階層に対して公的雇用の一定の割合を留保するという政策(リザベーション政策)を実施すると発表したことに対し、インド北部を中心に焼身自殺を含む学生や知識人等による反対運動が広がり、さらに10月末にかけてラーマ生誕寺建設問題(注)をめぐりヒンドゥー・イスラム両教徒間の衝突が激化する中で、シン政権を閣外から支えていたインド人民党が閣外協力を撤回したため、11月にシン政権は崩壊した。その後、与党人民党(ジャナタ・ダル)を離党し社会主義人民党を結成したシェーカル氏がコングレス党の閣外協力を得て首相に就任したが、シェーカル政権もまた少数与党政権であり、結局91年3月、コングレス党の国会審議の拒否により、シェーカル首相は辞意を表明するに至り、総選挙が5月下旬に3回に分けて実施されることとなった。
1回目の投票が行われた直後の5月21日、ラジーブ・ガンジー元首相が爆弾テロによって暗殺されるという事件が発生し、残りの投票は6月に実施されることとなった。選挙の結果、コングレス党が過半数には満たないながらも第一党となり、ナラシンハ・ラオ氏が同党新総裁に選出され、同総裁が首相に就任した。
インド経済は従来より財政赤字と国際収支赤字の問題を抱えていたが、国内政局が安定しない中、湾岸危機による悪影響を受け、91年前半には、状況が極めて深刻化した。これに対し、日本は、アジア重視の立場から困難に直面した同国を支援するため、他の先進諸国に先立って、91年5、6月に合計3億ドル相当の新規円借款の供与に係る交換公文を締結した。
ラオ政権は、最優先課題は経済危機の克服であるとして、政権発足後、ルピー貨の切り下げを実施し、複雑な許認可制度による規制を大幅に削減する新産業政策を発表するなど、自由化の推進と経済立て直しのため思い切った措置をとっている。
インドとパキスタンの関係は90年前半はカシミール問題をめぐり緊張の度を高めたが、海部総理大臣が南西アジア訪問時に対話を働き掛けたことなどを受け、同年7月に両国の外務次官級会議が開始され、91年4月まで4回会談が継続されてきており、両国の信頼醸成の面で進展が見られている。
3. パキスタン
90年8月のブットー首相の解任後、ジャトイ前野党連合代表による暫定政権の下で10月に総選挙が行われた結果、イスラム民主同盟が過半数を制し、11月にシャリフ同党党首が首相に就任した。
新政権はブットー政権と異なり、国会に安定的基盤を有し、また一応軍部の信頼も得て発足し、さらにシャリフ首相自身が実業家出身であることを背景に自由化や規制緩和を進める積極的な経済政策を打ち出すなど、当初は順調な滑り出しを見せた。
しかし、シャリフ政権は3つの大きな問題に直面した。第1は湾岸危機の政治的、経済的影響である。すなわち、湾岸危機が深まるとともに、イスラム原理主義政党や宗教指導者等を中心とする反米・親イラクのデモや集会が国内各地で展開され、サウディ・アラビアに1万1,000人の兵士を派遣していたパキスタン政府としてはこの対応に苦慮した。また、石油価格の高騰等により財政赤字と貿易赤字は一層深刻化した。第2はパキスタンの核開発疑惑に伴う米国の対パキスタン軍事・経済援助の停止である。第3は国内治安情勢の悪化である。パキスタン政府はシンド州等で治安を改善するために抜本的な措置をとり得るよう憲法を改正した。
シャリフ政権としては、国内においては治安の改善を含む政権基盤の安定化、外交面では対米関係の改善及びインド新政権との良好な関係の樹立等の課題を抱えている。
4. ネ パ ー ル
90年当初から高揚を見せたネパールの民主化運動を受けて、同年4月に国王は複数政党制の導入を宣言した。その後11月には主権在民、複数政党制、基本的人権等をうたった新憲法が公布され、同憲法の下で、91年5月に32年振りに複数の政党が参加した総選挙が実施されるに至った。総選挙の結果、ネパール・コングレス党が単独過半数を確保し第一党となり、5月同党の新党首となったコイララが首相に任命された。
日本はネパールの民主化を支援するため、日本国憲法に関する資料や情報の提供、ネパール選挙管理委員会が使用する車両の供与、超党派国会議員からなる選挙監視団の派遣等の協力を行ってきている。
5. バングラデシュ
90年10月に反政府統一学生戦線が結成されて以来、主要野党もこれに足並みを揃え、エルシャド大統領の退陣、自由かつ公正な選挙の実施等を要求する反政府運動が激化した。これに対しエルシャド大統領は、11月末に国家非常事態宣言を布告したが、軍が中立を維持したこともあり、野党勢力の要求に全面的に応じて、12月に辞任を決意し、アーメド最高裁判所長官を新副大統領(大統領代行)に任命した。これによりエルシャド政権は、バングラデシュ最長の8年9か月で終幕を迎えた。
アーメド暫定政権の下で91年2月末に総選挙が全体として自由かつ公正に行われ、その結果、野党であったバングラデシュ民族主義者党(BNP)が第一党となり、3月にジアBNP党首が新首相に就任した。なお日本は、非常事態宣言の公布後、関係者の政治的対話による事態の収拾と民主主義の過程への早期復帰を求める立場を公表し、平和的な政権交代に貢献した。また、総選挙に対しては超党派国会議員から成る選挙監視団を派遣した。ジア政権は、湾岸危機の経済的悪影響を克服し得ない中、4月末にバングラデシュ独立以来最大規模のサイクロン災害に遭遇した。今後ジア政権は、議院内閣制への移行等の政治的問題に加え、経済基盤の復興等の問題に取り組む必要がある。
6. スリ・ランカ
スリ・ランカにおいては政府軍とタミル人ゲリラ(LTTE)との紛争が続く中、91年1月に両者の停戦が実現したが、これが延長されず事態の平和的解決の糸口はつかめていない。また、インドのガンジー元首相の暗殺にLTTEの関与した疑いが強まっており、これまでLTTEに対し同情的であったインドは、今後LTTEに対する自国内での取締りを強化すると見込まれる。スリ・ランカ政府軍とLTTEとの戦闘が一段落すれば、停戦及び政治交渉の実現の可能性があろう。他方、同国経済は湾岸危機の悪影響を比較的早急に脱し、順調な回復振りを見せている。
7. ブ ー タ ン
一般に政情は安定していると見られているが、近年行われているブータン服着用の義務化や国語であるゾンカ語教育の普及等のブータン化政策に対し、南部のネパール系住民の一部に反政府運動が見られた。91年に入り、事態は一応鎮静化している。
8. モルディヴ
88年のクーデター未遂事件以降、社会情勢は概ね平静に推移している。90年11月、第5回SAARC首脳会議の主催国となり、南西アジア地域の協力関係の推進に貢献した。
1. 豪 州
90年3月の総選挙において四選を果たしたホーク労働党政権の内政上の最大の課題は、従来の資源依存型の経済を、製造業を中核とする国際競争力を持った経済へと転換することにある。このため、83年以来8年を数えるホーク政権は、関税の引下げ、産業再編成、労働市場の弾力化を含む経済構造改革を積極的に推進している。
83年に不況を脱出して以来、ホーク政権は抑制的な財政政策をとりつつ、経済構造改革を進めた結果、国内経済は順調に推移し、83年度に国内総生産(GDP)の7.1%を占めていた財政赤字は、89年度にほぼ均衡し、10%を超えていたインフレ率も、90年第4四半期には4.9%まで下がった。
しかし、87年に好転した経済が過熱気味になったのを受け、88年央以来更に引締めを行った結果、90年半ばより景気は大幅に鈍化し、高金利(91年6月現在、公定歩合は11%)と高い失業率(91年6月現在、9.3%)の下で国内経済は厳しい状況にあり、労働党政権の支持率は漸次減少している。この中で、91年5月末、与党労働党内でホーク首相とキーティング蔵相の指導権争いが表面化したが、党内選挙の結果、ホーク首相の続投が決まりキーティングは蔵相を辞任し、問題は一応の収束を見た。
豪州は、近年、アジア・太平洋の一員としてこの地域の平和と安定のために寄与しようという姿勢を強めている。日本との関係は伝統的には豊富な鉱物資源と大きな農業生産力を持つ安定的な資源供給国として、日本の経済発展にも大きな役割を担ってきた(注1) 。また、政治的にも、先進民主主義国として日本と共通の利害を有している。このため、両国関係は相互補完型貿易関係を基軸に順調に発展してきている。すなわち、日本にとり豪州は輸入面で第3位、総輸入額の5.3%(90年)を占め、量的にも重要な貿易相手国であるが、貿易の内容を分析する貿易相互補完度で見ると、主要貿易相手国の中でも一番高い数値を示している(注2)。
他方、豪州から見ると、日本は総貿易の約23%を占める最大の貿易相手国である。日本の対米貿易は総貿易の約27%であり、豪州にとっての日本は、日本にとっての米国のような最重要の貿易相手国であることを示している。
国内経済改革の推進に当たっても、日本の技術面、資金面での貢献に対する豪側の期待は高い。特に、マルチ・ファンクション・ポリス事業(注3)を始めとする研究分野や製造業分野に対する日本の投資に対する期待は強い(注4)。
上述のように、豪州は、欧州の一員からアジア・太平洋国家へとその位置付けを変化させており、特に、日本との関係強化を対外政策の柱の一つとして重視している。また、環境問題、軍備管理・軍縮等の全地球的な問題の解決やカンボディア問題の解決、アジア・太平洋経済協力(APEC)の推進等の地域の問題に積極的に取り組む中で、日本との協力と協調を重視している。このような豪州の姿勢は、日本が国際政治の分野においても、その経済力にふさわしい積極的な役割を果たすことに対して90年9月に訪日したホーク首相が積極的な支持を強調したことにも表われている。
さらに、91年5月、キャンベラにおいて開催された第11回日豪閣僚委員会には、日本側から中山外務大臣を始めとする閣僚6名と政務次官2名が、また、豪州側からは閣僚9名が出席し、過去最大の規模となった。これもまた、両国間の友好協力関係の着実な進展とともに、幅の広がりを象徴するものであった。会合の内容においても両国は二国間問題のみならず、アジア・太平洋地域の問題、環境、軍縮、ウルグァイ・ラウンド等の全地球的な諸問題についても、引き続き協調し、協力して取り組んでいくことが確認され、両国の「建設的パートナーシップ」の構築に向け更に協力していくことが合意された。豪州は、日本にとり今やかけがえのないパートナーとなっている。
2. ニュー・ジーランド
ニュー・ジーランドにおいては、90年9月、パーマー首相が辞任し、同月の労働党議員総会でムーア首相が選出されたが、10月27日に行われた総選挙では、ボルジャー党首に率いられた国民党が大勝し、6年振りに国民党政権が誕生した。
同政権は、外交面では非核政策を踏襲しつつも、この政策により悪化した米国との関係の改善を進める努力を行ってきている。また、湾岸危機に際しては、多国籍軍を全面的に支持し、空軍輸送機2機及び医療チームを派遣した。91年5月には、マッキノン対外関係貿易相が訪米し、対米関係の一層の改善を試みたが、防衛・安全保障面での両国関係に見るべき進展はなかった。
経済面では、ニュー・ジーランドは、農産物輸出国で構成されるケアンズ・グループの主要な一員として、ウルグァイ・ラウンド交渉の成功に向け、積極的に交渉に臨んでいる。
日本とニュー・ジーランドは、共にアジア・太平洋地域に位置する友邦国であり、また、民主主義的政治理念と自由主義的貿易体制といった価値を共有している。さらに両国は、相互補完的な経済・貿易構造を基盤に相互に安定的な貿易相手国となっている。ニュー・ジーランドは、日本にとり、農産物の安定的供給国としての地位を占めている(注)。一方、ニュー・ジーランドにとり日本は輸出先としては第2位(金額で16.3%)、輸入先としては第3位(同15.0%)の貿易相手国である。近年、ニュー・ジーランドの対日貿易黒字基調が続いているが(90年は約5億米ドル)、豪州同様に、国際競争力のある経済を実現していくため、貿易・投資面で日本に対する期待は大きい。
91年4月、ニュー・ジーランドを訪問した中山外務大臣は、ボルジャー首相、マッキノン副首相兼対外関係貿易相等と会談し、国際政治、経済問題、新政権下の両国関係等につき意見交換を行った。特に、ニュー・ジーランド側よりは、掃海艇の派遣等の湾岸危機における日本の貢献策に対する支持が表明された。また、ニュー・ジーランドは、その地政学的位置と歴史的背景から、南太平洋島峡国との関係が深く、これらの諸国に影響力を有していることから、日本との間で同地域に関する意見交換を継続している。
3. 南太平洋島嶼国
南太平洋地域は、日本に近接する広大な海域を有する地域であり、この地域の平和と安定、域内諸国との友好的な関係の維持及び発展は、日本の平和と安全にとり重要な意味を持っている。
各島嶼国は、近年、域内共通の関心事項につき協力して対処する傾向を強めている。南太平洋の地域協力機関を代表する南太平洋フォーラム(SPF)及び南太平洋委員会(SPC)は、小規模、拡散性等に起因する島嶼国の経済的脆弱性を克服するための努力を行っており、日本は、これらの機関との関係の強化に努めている。具体的には、SPFに対しては89年より毎年域外国との対話に参加し、これに専門家を派遣し、88年度より毎年SPF事務局に40万ドルを拠出している。また、SPCに対しては、総会等にオブザーバーとして出席し、SPC施設に対する小規模無償資金協力を供与した。また、島嶼国にとり重要な水産資源の一つであるビンナガマグロに関して90年10月に開催された第3回資源管理体制協議に日本は積極的に参加した。
なお、パプア・ニューギニアにおいては、88年末のブーゲンビル鉱山の地主が土地補償を要求したことに端を発し、90年5月ブーゲンビルの分離独立宣言にまで発展したブーゲンビル問題が、依然として解決を見ていない。また、フィジーにおいては、87年のクーデターを経て成立した暫定政府により90年7月新憲法が公布されるなど、独立以来の政治体制に変化が現われてきている。
| (注) | 北朝鮮に抑留されていた第18富士山丸の船員2名は、朝鮮労働党創立45周年式典に参加した自民党と社会党両党の代表団と共に90年10月に帰国した。 | |
| (注) | 日本及び韓国の発展や、特にその労働倫理を学ぼうととする人づくり政策で、81年にマハディール首相が提唱したもの。 | |
| (注) | 北インドのヒンドゥー教の聖地アヨッディアのイスラム教モスクのある場所にヒンドゥー寺院を立てようとする運動をめぐるヒンドウー教徒とイスラム教徒の対立。 | |
| (注1) | 90年の日本の石炭、鉄鉱石、天然ガスの輸入に占める豪州の割合はそれぞれ48.6%、39.0%、7.7%。 | |
| (注2) | 貿易相互補完度とは、ある国の輸出構造と他国の輸入構造の適合度を示すもので87年の統計では、日本との貿易相互補完度は豪州が2.21、ASEANが1.59、米国が0.98、西欧諸国が0.77。 | |
| (注3) | 南豪州アデレード市に職、住、遊、学を集めた未来型多機能都市を建設する計画 | |
| (注4) | 豪州に対する日本の投資額は、90年の届出ベースで諸外国中第1位の36億7,000万ドルだが、不動産・サービス関連投資が約52%を占めている。 | |
| (注) | 90年、ニュー・ジーランドは日本のキウイの総輸入量の99%、羊肉の総輸入量の52%を供給。 | |