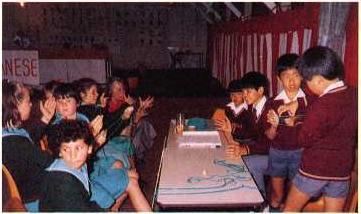
第6節 国際社会と日本
戦後四十数年を経て、わが国は国際社会の主要な構成員としての自覚を持ち、その信奉する自由と民主主義という基本的価値を軸に、他の先進国とともに世界の平和と繁栄のため努力している。しかし、諸外国においては、日本や日本人が必ずしも十分かつ適正に理解されているとはいい難く、またわが国が諸外国の期待と関心に未だ十分に応えていないと見られている場合もある。
外務省が実施している各国における対日世論調査の結果等によれば、基本的にはどの地域においても、わが国との経済的相互依存関係、世界の平和と繁栄へのわが国の貢献等を背景に、わが国を信頼できる友好国として評価しており、特に経済協力に象徴的にみられるごとく、わが国の果たすべき役割に対する期待感も強いといえる。
他方でその期待感の裏返しとして、わが国が経済大国としての国際的責任を十分果たしていないとの声も強い。最近では、わが国との間の貿易不均衡是正が進まないことへの不満、あるいは科学技術面における日本の躍進に対する脅威感等を背景として、特に先進諸国の間に日本の市場が閉鎖的であり、不公正な国だとのイメージが拡大しつつある。しかも最近の対日批判の中には、経済分野の問題につき、その原因として社会、文化面にさかのぼって議論するものもあり、「日本は価値観及びルールを異にする異質社会である」として、日本文化、社会のあり方、また日本人の考え方自体までが問題であるとの議論がなされる傾向さえ見られる。
日本企業の海外進出が増大している今日、日本のイメージは政府の努力に加え、民間の活動、とりわけ地域社会と直接コンタクトを有する日系進出企業や在留邦人の行動によって大きく左右されている。日本企業の海外進出、とりわけ生産拠点が建設されることは、現地における雇用の創出、技術移転を促し、現地社会から歓迎されている反面、進出先で閉鎖的な日本人社会を形成し、日本の生活習慣等を持ち込み、現地社会の生活習慣、商習慣等に対する配慮を欠く等、現地社会との摩擦が生じている例も増加しつつある。海外での邦人社会の規模、影響力が大きくなるに従い、邦人が現地社会と融和していく努力を行うことがますます重要となってきている。
わが国が国際社会との係わりを深め、また「世界に開かれた日本」の立場を進めていく過程において、人及び物の海外進出と並行して、わが国への人及び物の流入も増加し、国民生活の様々な分野に影響を生じてきている。人の往来についてみても、88年における訪日外国人の数は
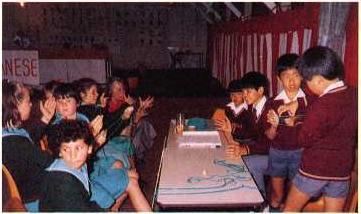
現地の子どもたちと交流する日本人学校の生徒たち(パース)
(海外子女教育振興財団提供)
196万人であり、78年の84万人に比し2倍以上の増加となっている。他方、海外渡航者についても、78年の352.5万人から88年は842万人まで急増した。この結果、わが国の制度・慣習や日本人の意識面においても国際化が進んできている。さらに東京などの大都市のみならず地方においても、地方自治体における国際交流専管課の設置、姉妹都市提携数の増加、地方での各種国際交流行事の増加、民間の国際交流団体の活動の活発化等がみられ、わが国社会全体の国際化の動きが高まっている。これらの活動は、わが国全体の国際化を草の根レベルにおいてまで推進するものとして重要であり、外務省としても、これらの活動に各種支援・協力を行ってきている。
他方、急速な「国際化」にまだ十分に対応できていない面もある。例えば、アジアからの「ヒト」の流入は、不法就労者の伸びをもたらし、88年にはスリ・ランカ人の研修生問題(3月)、フィリピン人の公開興業者問題(6月)、さらに、中国人の就学生問題(11月)等は、二国間の問題にまで発展した。アジアの近隣諸国からわが国に対し就労機会を求める動きがみられ、一部の国の政府からは、わが国の労働市場の開放を打診してきている。
しかし、こうした外国人労働者問題は、単なる労働問題ではなく、わが国社会の基本的あり方に深く係わる問題であり、その取り扱いをめぐって、国内でも活発な議論が行われており、その対策については模索の段階にある。
わが国が国際社会において大きな影響力を行使し得る立場になればなるほど、わが国の政治・経済政策の決定プロセスが、さらには日本企業、日本人の海外進出が急増している現状下においては、政府のみならず、日本人一人ひとりが如何なる理念に基づき、現実に如何なる行動をとるかが問われてくるといえよう。わが国の制度・慣習や日本人の意識の変化は、急速に変化する現実に十分に対応できておらず、このギャップが増大すればするほど、諸外国との摩擦が増大することとなる。
今後の課題は、国内的には、これから、ますます増加する「国際化」の波に速やかに対応しつつ、対外的受容性と包容力を備えた社会を創出していくことである。また、海外に進出した日本企業、在留邦人は「Good Corporate Citizen(良き企業市民)」として地元社会から受け入れられる存在となり、現地社会との融和に心がけることが必要である。例えば地域社会における慈善活動への寄付等の経済的な貢献に加え、ボランティア活動、PTA活動、そのほか地域の各種活動への積極的参加等、いわゆる現地社会の人々とともに汗を流していく努力が重要といえる。さらに企業としては現地人の幹部登用、マイノリティ、女性への配慮等も重要である。こうした地道な努力の積み重ねにより、各々の地域社会における信頼感を醸成することが可能となろう。
外務省は、こうした課題に対して様々な活動を行っている。国内では86年2月に外務省内に設置した「国際化相談センター」が、地方自治体や民間国際交流団体などから寄せられる国際交流・国際化に関する相談に応じたり、「一日外務省」、「ミニ外務省」、「国際化相談キャラバン」等を国内各都市で開催したり、国際交流団体が開催する国際化推進シンポジウムに対する協力を通じ、地方の国際化への支援活動を行うとともに、出版物の刊行、各種講演会の実施等を通じ、わが国の国際社会においておかれている状況につき、広く啓発活動を行っている。また、海外広報に関する官民合同会議、国際シンポジウム等を東京において開催し、進出企業による現地社会との融和活動の重要性について、進出企業本社の意識啓蒙を行っている。
海外では、進出企業の地域社会との融和促進を目的として、「広報文化官民会議」を開催しているほか、日本総合紹介週間等の日本紹介の大型広報文化行事を民間及び開催地の現地団体と協力して実施することにより、在留邦人と地域社会の人たちとの個人的な信頼関係を築き上げる触媒的な役割を果たすよう努力している。
さらに、近年、海外に渡航・滞在する邦人が増加している現状を踏まえ、これら邦人が海外において十分活躍し得るよう、安全確保、医療体制の整備、子女教育対策等、在留邦人の保護・支援体制の整備にも努力している。