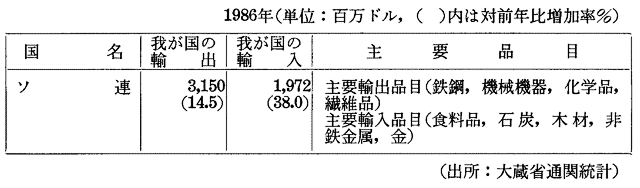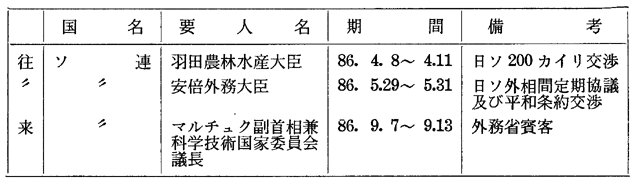
第6節 ソ連・東欧地域
1. ソ連
(1) 内外情勢
(イ) 内政
(a) ゴルバチョフ書記長は,86年2~3月の第27回党大会において,党人事を固めるとともに2000年に至る「ゴルバチョフ路線」を策定した後,ソ連社会経済発展の「加速」,「建て直し」(ペレストロイカ),さらに「社会主義的民主主義の強化」へと社会改革の範囲を拡大深化する政策を実施している。
(b) ゴルバチョフ書記長は,4月に発生したチェルノブイリ原発事故を処理し,6月には第12次5ケ年計画を審議する中央委総会を開催,また,地方視察(7月末に極東,9月に北コーカサス,本年2月にバルト地方)を行うなど精力的な活動を行いつつ,「グラスノスチ」(情報公開)路線を推進し,さらに,ソ連社会の全面的な変革と活性化をめざす「ゴルバチョフ路線」への国民の参加を呼びかけてきた。また,87年1月末には,人事政策を討議する中央委総会を3回の延期の後に開催し,政権基盤をさらに固めることにある程度成功している。
(c) この間,トップの人事では,クナエフ政治局員とジミャニン書記を解任するとともに,新たにスリュニコフ政治局員候補を書記(経済部長)に,ヤコブレフ書記を政治局員候補に,ルキヤノフ中央委総務部長を書記にそれぞれ選出して自己の基盤をさらに強化した模様である。なお,クナエフのカザフ共和国党第一書記解任直後にカザフの首都アルマアタで発生した暴動は,ソ連の民族問題の複雑さを示すものであった。
中堅レベルの人事では,党・国家機関,軍・治安組織等も大部分を入れかえているが,地方の地区および中・小都市の第一書記レベルになると,新人はようやく三分の一を超えた程度にとどまっており,トップから末端組織に至るまで党の人事を刷新することは今後の課題となっている。
(d) ゴルバチョフ書記長の社会改革は,ソ連社会に一定の変化をもたらしており,政治・社会面では,党・国家機関の「民主化」(秘密投票,複数候補制の導入など),「情報公開」の強化(大事故,麻薬・売春犯罪,KGB機関の過失の報道等),人権の擁護(サハロフ等政治犯の釈放,行政訴訟法の制定準備),女性や非党員の登用が始まっている。また,経済面では,国営企業法や個人労働活用法の制定,ソ連の企業が外国企業と直接貿易を行うことを可能にする措置等によって経済活動の活性化をはかろうとしている。文化面の措置としては,党・国家関係機関の総入れ替えとともに,発禁作品(パステルナーク作rドクトル・ジバゴ」等)の公開,映画・文学等を通ずる非スターリン化の再開,西側との文化交流の活発化など様々な試みが展開されている。ゴルバチョフ書記長が実施している諸改革は,同書記長も言明しているとおり,社会主義の枠内において行なわれているものであり,「民主化」「自由化」「情報公開」等の諸面において一定限界を有しており,また,その目的は,社会主義制度を維持しつつ,その効率化,活性化を目的とするものと考えられる。
(e) ゴルバチョフ改革は,既存の権力グループにとって特権の縮小とはく奪を意味するとともに,国民の生活レベルでは節酒や規律強化を強いられるわりには目に見える成果がなく生活の改善が遅々として進まないという事態に至る可能性があり,また,改革に伴って物価上昇等の諸問題の発生も予想される。ゴルバチョフ書記長自身も,改革に対する積極的,消極的抵抗が極めて強いことを認めており,現在の第12次5ヶ年計画(1986~90年)は,ゴルバチョフ路線の成否を左右する重大な期間になるとみられる。
(ロ) 外交
ゴルバチョフ政権になってからもソ連の外交目標は不変であり,自国の安全保障の確保が第一義的重要性を有する。このため対米関係の再構築が最大の課題であり,この再構築が自己に有利な方向で行ない得るように,対米ポジションの強化を念頭に,直接の相手国たる米国に加えて,西側諸国,中国等アジア諸国に対する多極的な外交攻勢をさらに活発化させている。
また,自国の経済活性化に資するとの観点からも,本年1月に合弁事業法を発表するなど西側との経済交流の推進に意欲的である。
(a) 対米・対西欧関係
対米関係については,85年11月のジュネーヴでの米ソ首脳会談以降,両国間で種々やりとりが行われたが,86年10月,ゴルバチョフ書記長訪米の準備会合として,レイキャヴィクにおいて2度目のレーガン・ゴルバチョフ会談が行われた。この会談では,軍備管理問題に関し,戦略兵器,INFの分野では歩み寄りがみられたが,SDIの問題で対立し,ゴルバチョフ書記長が,それまでの政策を変え,戦略兵器,INF及び宇宙兵器の3つの問題をパッケージとしてリンクさせることに固執したために,最終的に何らの合意も達成できなかった。しかし,本年2月末,ゴルバチョフ書記長は,INFを他の問題と切り離して個別に交渉するとの以前のソ連側立場に戻る態度を表明したことから,ゴルバチョフ書記長訪米へ向けての今後の米ソ軍備管理交渉を中心とした米ソ関係の成り行きが注目される。
西欧諸国に対しては,ソ連は,グロムイコ前外相の下での「対米偏重」のイメージの払拭に努め,西欧各国ときめ細かく対応しつつ西欧重視の姿勢をみせている。他方,西欧諸国もソ連との対話を推進しようとの動きがみられ,ソ連と西欧との間で要人の往来(7月,ミッテラン仏大統領訪ソ,シェヴァルナッゼ外相訪英,ゲンシャー西独外相訪ソ,本年2月アンドレオッティ伊外相訪ソ,3月,サッチャー英首相訪ソなど)が行われた。
(b) 対東欧関係
ゴルバチョフ書記長は,党大会出席などの機会に東欧諸国を歴訪(4月東独,6月ハンガリー,6~7月ポーランド)し,各国首脳と会談を行ったほか,レイキャヴィクの米ソ首脳会合後の11月にモスクワにおいて書記長レベルのコメコン首脳会合を開催した。ソ連は,東側陣営の結束を固めるためにソ連内外政策についての東欧諸国の理解とりつけに力を注いでいるとみられる。
また,11月のブカレストにおける首相ないし副首相クラスの第42回コメコン総会に引き続き前述のコメコン首脳会合が開催されたが,ソ連は,種々の問題点を抱えるコメコンの改革をはかり,域内の経済協力の推進をめざしているとみられる。
(c) 対アジア関係
ゴルバチョフ書記長は,7月末のウラジオストック演説において,ソ連はアジア太平洋国家であるとの立場を鮮明に.し同地域に対する高い関心を示した。しかし,同演説に盛られた太平洋会議,信頼醸成措置,非核地帯構想等は旧来の提案の焼直しであり,特段の新味はみられない。
ゴルバチョフ書記長は,対中関係改善に意欲をみせ,上述のウラジオストック演説において,中国の「3つの障害」のうち2つ(モンゴル駐留ソ連軍の撤退とアフガニスタンよりのソ連軍の撤退)に対して若干柔軟な姿勢をみせ,その後ある程度の具体的措置をとった。また,本年2月には外務次官級の国境交渉が9年ぶりに再開され,その継続が合意された。さらに中ソ間では人的交流や貿易等の実務分野において進展がみられる。しかし,中国は,「3つの障害」をめぐってソ連が採った措置の実質的意義に懐疑的であり,特にカンボディア問題については不満の意を再三表明しており,総じて慎重な対応ぶりをみせている。
ソ朝関係では,金日成主席が,84年5月,23年ぶりに訪ソしたのに続いて86年10月に訪ソし,その他党・政府・軍関係の要人往来が行われた。各分野での関係緊密化がはかられているとみられる。ゴルバチョフ書記長が,11月,アジア諸国の中で初めてインドを訪問した。インドとの友好関係をさらに強固なものにせんとした訪印の成果は,ソ連にとってまずまずのものであったとみられる。 アジア・太平洋地域重視のウラジオストック演説を背景に,シェヴァルナッゼ外相は,本年3月,豪州・アジア諸国を歴訪した。この狙いは,当該地域におけるソ連の政治的ポジションの強化にあったとみられるが,全体としては具体的成果は得られなかった。
ソ連は,6月にヴァヌアツと外交関係を樹立するなど,南太平洋に対する関心を強めている。
(d) その他の地域
ソ連は,中東和平については引き続き国際会議方式を提唱している。
アフガニスタン問題については,10月,ソ連の一部撤退が一応実施されたが,質量とも実質的意味のあるものとみられていない。
中南米では,ニカラグア支援,キューバとの関係強化(シェヴァルナッゼ外相が,10月,カナダ・メキシコとともに訪問。カストロ第一書記は11月訪ソ)が主な動きである。
アフリカについては,エティオピア,アンゴラとの友好関係に変化はないとみられる。
(ハ) 経済
(a) かつては2けた台の成長率であったソ連経済も,70年代末から80年代初めには3%前後にまで落ち込んだ。ゴルバチョフ書記長は,このようなブレジネフ時代の負の遺産を克服すべく,国内経済の再建に利するような国際環境の追求,個人の労働意欲の発揚,科学技術成果の導入及び経済改革の断行によって,2000年までに国民所得の倍増を果たすことを基本的な経済戦略としている。
86年2月の第27回党大会は,このような路線を確定したものであり,同党大会後,下記(b)のような一連の改革措置がとられているが,旧来からの惰性及び改革への抵抗が根強いこともあって,これら諸措置が必ずしもスムーズに動き出しているとは言い難く,それなりの成果をみるまでにはかなりの時間を要するものとみられる。
なお,86年の経済実績は比較的好調であったが,これは,経済改革が功を奏したというより,規律強化等の短期的な要素によるものとみられている。
(b) 主な改革措置
(i) 機構改革(省庁の統廃合。複数の省の上に立つ大部門省の設置。ゴスプラン等の機能強化)
(ii) 機械製作部門の重視(同部門に対する重点投資。特に,遅れているハイテク分野の重視)
(iii) 企業の自主権強化(87年2月,破産規定をも含む「国家企業法」の草案を発表。独立採算制の徹底化が基軸)
(iv) 個人業の法制化(11月法律制定。87年5月から実施)
(v) 品質管理の改善(国家機関による厳しい品質管理制度の導入)
(vi) 農業(集団請負方式,家族請負方式等の推進。野菜・果物について,国家への調達義務量の70%を超えた分については,コルホーズ市場等で自由に販売することが可能)
(vii) 対外経済(ソ連の企業が直接外国の企業と輸出入取引を行うことが可能。87年1月「合弁企業」に関する国内法を発表)
(c) 1986年の実績
(i) 生産国民所得の対前年伸び率は,4.1%増で計画値の3.9%を上回り,鉱工業生産も4.9%伸びて計画値の4.3%を上回った。農業総生
産についても対前年比5.1%増と,86年の経済実績は比較的好調であった。
(ii) 燃料・エネルギー分野。石油生産は,83年をピーク(616百万トン)にして減少傾向をたどり・85年には6億トン台を割ったが・86年は615百万トンにもち直した。天然ガスは,対前年比7%増と引き続き好調であった。原子力では,チェルノブイリ事故の影響のため,原子力発電量の計画遂行率は93%と落ち込んだ。
(iii) 穀物生産は,2億1010万トンと8年ぶりに2億トンの大台を超えた。
(iv) 外国貿易。対先進資本主義諸国貿易は,原油価格とドルの下落によって,総額が減少し,バランスも大幅に悪化した。対コメコン諸国貿易は,数年来の増加傾向が続いている。
(2) 我が国との関係
(イ) 北方領土問題
(a) 5月末,安倍外務大臣は,1月に再開された外相間定期協議及び領土問題を含む平和条約交渉を定着化させるために訪ソした。安倍外務大臣はシェヴァルナッゼ外相との同交渉において,北方領土問題に対する我が国の基本的立場をその法的・歴史的側面をも含め明確かつ詳細に主張した。すなわち,(i)歯舞・色丹については,1956年の日ソ共同宣言で平和条約締結後の引き渡しが約束されている。他方,国後・択捉については,国交回復交渉の経緯,松本・グロムイコ書簡,共同宣言の規定ぶりから,平和条約交渉の中で話し合われることになっている。ソ連は,1960年に至って,日米安保条約締結により情勢が変ったと主張しているが,厳粛な国際約束の内容を一方的に変更することはできない。そもそも,日ソ共同宣言が,既に日米安保条約が存在し日本に外国軍隊が駐留していたことを前提として締結されたものである。(ii)1973年の日ソ共同声明では,「第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結する」ことの必要性がうたわれ,この「未解決の諸問題」の中に4島が含まれていることが田中・ブレジネフ会談で確認されている。平和条約締結後に歯舞・色丹を日本に引き渡すことが合意されている状況の中でのこの確認は,国後・択捉につき平和条約交渉の中で話し合うという1956年の共同宣言の合意が改めて確認されたことである。(iii)北方領土は,いまだかつて外国の領土となったことはなく,また,サンフランシスコ平和条約にいう千島列島にはこの北方領土は含まれない。(iv)北方領土問題を解決して平和条約を締結することが日ソ関係発展の上に決定的に大きな意味をもつ,ことなどを強く主張した。
これに対し,シェヴァルナッゼ外相は,ソ連の立場についての詳細は1月の平和条約交渉の際述べたので繰り返さないとしつつ,「1950年代から60年代にかけて日本は米国の同盟者として登場するようになり情勢が変わったが・この事実は今でも変わっていない。日本側の「領土問題」についての立場のため平和条約を締結する条件は未だ熟していない。このような状況を考慮してソ連は善隣協力条約の締結を提案している。」旨述べた。
さらに,安倍外務大臣は,ゴルバチョフ書記長との2時間にわたる会談の際にも北方領土問題を解決して平和条約を締結することが日ソ関係の将来にとって最も重要である旨主張したが,同書記長は,「この問題は,国境不可侵の原則にかかわるもので,第二次大戦の結果として既に合法性が与えられている問題である。第二次大戦の結果,世界は変っており,そういう問題は解決されている。しかし,話し合い,対話は続けていこう。」と述べた。
このように,この問題に対するソ連の立場は依然として厳しく従来の域を出なかった。しかし,領土問題を含む平和条約交渉を次の東京における外相間定期協議の際に継続していくことが合意された。
(b) 倉成外務大臣は,9月の国連総会出席の際にシェヴァルナッゼ外相と会談し,北方領土問題を未解決のまま放置しておくことは日ソ両国のためにならないこと,戦後40余年を経たにもかかわらず平和条約が日ソ間で締結されていない状況は極めて異常であり,この状況の是正を強く望んでいることを主張したほか,国連総会一般討論演説において,北方領土問題に対する我が国の基本的立場を国際世論に訴えた。
(c) このほか,政府としては,日ソ事務レベル協議(11月,モスクワ)など機会あるごとに,北方4島一括返還による領土問題解決をソ連側に強く主張してきている。
(ロ) ゴルバチョフ書記長来日問題
86年1月及び5月の日ソ外相間定期協議の際,両国最高首脳の相互訪問が原則的に合意された。過去の往来の経緯(日本側総理は4度訪ソ。他方ソ連側最高首脳の来日はなし)にかんがみ,まずゴルバチョフ書記長が先に来日するのが妥当とするのが我が国の基本的立場である上,同書記長も来日の意欲を示しており,かかる状況を背景に,倉成外務大臣は,8月,ソ連側に対して,「出来れば年内,遅くとも1月末まで」の同書記長来日を提案した。しかし,12月初めになっても,ソ連側から具体的来日時期の提示はされず,同書記長の1月までの来日は実施し得ないことが日ソ間の外交ルートで了解・確認された。今後は,ソ連側より来日時期の提案がなされることになる。
(ハ) 墓参問題
5月の日ソ外相間定期協議の際の話し合いを踏まえ,7月初め,旅券及び査証を必要としない身分証明書方式による墓参の枠組につき,我が国の北方領土問題についての立場を害しない形で日ソ間で合意が成立し,8月,11年ぶりに北方墓参(歯舞群島の水晶島,色丹島)が実施された。また樺太墓参は7月末から8月初めにかけて,ソ連本土墓参は9月に実施された。
ソ連も,12月,我が国への墓参(長崎,松山,泉大津)を実施した。
(ニ) 日ソ経済関係
(a) 日ソ貿易
83,84年と2年続けて減少を記録した日ソ貿易は,85年に回復に転じたが,86年には,この傾向が定着し,輸出が31億5,000万ドル(対前年比14.5%増),輸入が19億7,200万ドル(対前年比38.0%増)となり,往復で51億2,200万ドル(対前年比22.5%増)となった。
輸出の増加は主として機械機器類の増加及び鉄鋼の回復によるもので,機械機器類の中でも荷役機械,建設・鉱山用機械,輸送用機器が大幅に増加している。鉄鋼についても,84年,85年と不振であったが86年には前年より32%増加した。輸入では,魚介類,木材,非鉄金属,石炭が伸び,また,金は前年の2・5倍と大幅に増加した。一方で,石油及び石油製品,化学品,機械機器は減少した。
(b) モスクワ日本産業総合展
10月,モスクワにおいて,我が国産業の現状を紹介する「モスクワ日本産業総合展一86」が日ソ経済委員会等の主催で10日間にわたり開催された。政府は,村田衆議院議員を特派大使として同総合展に派遣した。
(ホ) 日ソ漁業関係
(a) 日ソ200カイリ交渉
日ソそれぞれの200カイリ水域における相手国の漁船による87年の漁獲量等を協議する日ソ漁業委員会は,11月下旬から12月上旬にかけて東京で開催され,相互性に基づく無償部分(双方20万トン)と金銭支払を伴う部分(日本側のみ10万トン,12億9千万円支払)とに初めて区別されて合意が達成された。
(b) 日ソさけ・ます交渉
ソ連系さけ・ますの87年の漁獲にかかわる日ソさけ・ます交渉は,87年2月,モスクワで行われ,ほぼ前年並みの漁獲量24,500トン,漁業協力金37億円で妥結した。
(ヘ) 国会議員の訪ソ
山口衆議院外務委員長は,8月,5名の衆議院外務委員会の議員とともに訪ソし,ザグラージン党中央委国際部第一副部長,ペトロシャンツ原子力利用委議長,アルバートフ米加研究所長等と会談した。
桜内日ソ友好議員連盟会長は,9月に訪ソし,ヴォス民族会議議長,クルグローワ対文連議長等と会談した。
(ト) マルチュク副首相の来日
9月,マルチュク副首相兼科学技術国家委員会議長(当時,現科学アカデミー総裁)は外務省賓客として来日し,中曽根総理大臣,倉成外務大臣,三ツ林科学技術庁長官等と会談し,日ソ関係の諸問題について意見交換を行ったほか,我が国の科学技術関連施設等を視察した。
(チ) 日ソ文化協定,日ソ映画祭
(a) 5月の日ソ外相間定期協議の際,相互主義に基づく拡大均衡の形での文化交流の進展をめざす日ソ文化協定が安倍・シェヴァルナッゼ両外相間で署名された。
(b) 4月,ソ連映画祭が東京,大阪,福岡で開催され,11月中旬から12月初めにかけて,日本映画祭がモスクワ,レニングラード,ナホトカの各地で開催された。
<要人往来>
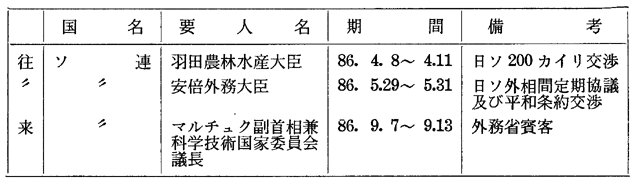
<日ソ貿易>