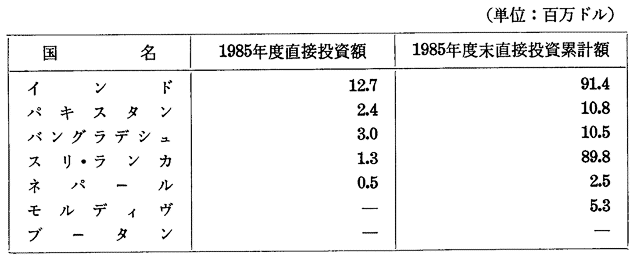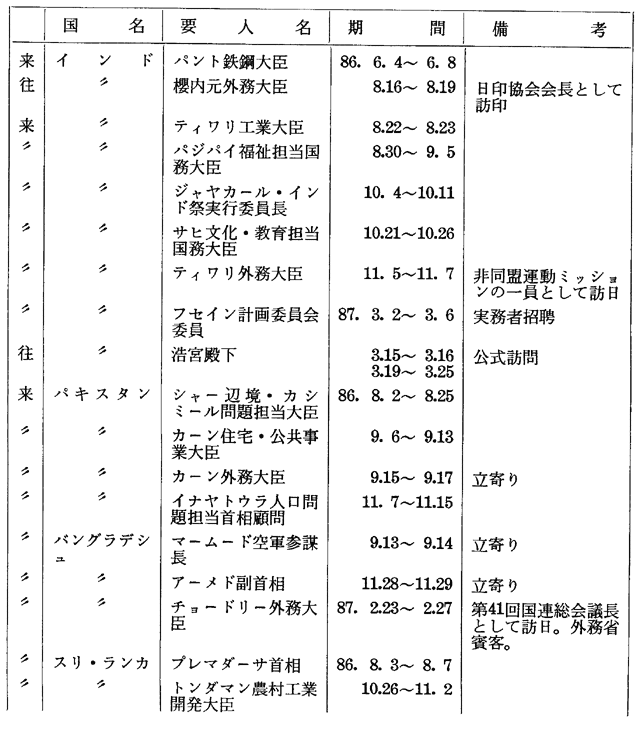
5. 南西アジア地域
南西アジア地域は,北にソ連,中国と接し,南にはインド洋を擁し,東の東南アジアと西の中東とを結ぶ地政学的にも重要な地域である。この地域の7か国は,全て民政下(パキスタンは85年12月に,バングラデシュは86年11月にそれぞれ民政に移管した)にあり,非同盟運動加盟国かつ開発途上国(うち4か国はLLDC)である。
従来よりインド対周辺国という関係図式で特徴付けられていた南西アジア地域であるが,84年10月に政権についたラジーブ・ガンジー=インド首相は,域内諸国との関係改善に積極的姿勢を示した。この域内大国インドの善隣友好政策もあって,85年を通して域内諸国間の関係の緊密化の気運が高まり,85年12月には南アジア地域協力連合(SAARC)が発足した。
(1) 内外情勢
(イ) 概要
南西アジア地域情勢は,いくつかの不安定化要因を包蔵しつつ,全体として安定的に推移して来ているが過去1年間には次の通りの動きが見られた。
85年を通じ高まった印パ関係改善の気運も86年2月頃から,パンジャブ問題の混迷化(印は「パ」がシク教徒テロリストを支援しているとして非難。)、パキスタンの核開発問題,米国の対パ軍事援助問題,印パ双方による軍事演習(印パ国境付近)等の諸要因により次第に減退し,印パ関係は後退した。ただし,この間にも11月のSAARC第3回首脳会議の際にガンジー=インド首相とジュネジョ=パキスタン首相の会談が行われ,また,本年2月には,ハック=パキスタン大統領が訪印し,ガンジー首相と会談するなど両国間の対話は続けられた。
また,スリ・ランカにおける民族問題については政治的解決の見通しが立たぬまま推移した。
他方,南西アジア地域における安定化要因であるSAARCに関しては,上記首脳会議での決定を受け,本年1月にネパールに常設事務局が開設された。
また,バングラデシュにおいては86年11月民政移管が実現した。
(ロ) インド
(a) 内政
2年目を迎えたガンジー政権下で,パンジャブ及びアッサムの地域民族問題に関する合意が実施の段階で頓挫し,また,グルカ人の自治拡大運動等新たな民族問題の崩芽がみられた。ガンジー首相は頻繁な内閣改造によって対抗勢力の排除を試みる等党内の政権基盤は磐石なものとなっておらず,かかる状況も反映してか87年3月の州選挙においてもケララ州,西ベンガル州で与党ガンジー派コングレス(I)党が敗退した。10月には米国防長官が初めて訪印する等経済・技術分野を中心に西側諸国との連携の深まりが見られた。
(b) 外交
経済・技術分野を中心に西側諸国との連携の深まりが見られ,10月には,ワインバーガー米国防長官が,米国防長官としては初の訪印を行った。他方,11月にはゴルバチョフ・ソ連書記長が初のアジア訪問として訪印し,印ソ間の緊密な関係が再確認された。
中国との間では軍隊による国境侵犯問題をめぐって非難の応酬が行われた。
なお,ガンジー首相は,非同盟運動前議長としてジンバブエ非同盟首脳会議(9月)においてムガベ新議長を側面から支援するとともに,11月にバンガロールにてSAARCの第3回首脳会議を主催した。
(c) 経済
86年度の印経済は,穀物生産につき1.5億トン程度の豊作が見込まれると共に,工業生産も前年度比6.3%の伸びをみせるなど比較的良好な実績を示し,外貨準備も700億ルピー前後と安定的に推移した。しかし,消費者物価上昇率が年率10%とインフレ再発の気配をみせているほか,財政赤字拡大や公共部門の経営悪化が続いている。
また,印経済の構造的欠陥といえる農工業インフラ不整備,内外貨不足といった状況はさほど改善されていない。
(ハ) パキスタン
(a) 内政
85年12月末に戒厳令が撤廃され,86年には,ハック現体制にとって民政移管後の最初の年であった。
4月にベナジール・ブット=パキスタン人民党(PPP)共同委員長の帰国を契機に,野党勢力は,ハック大統領の退陣と総選挙の実施を求め反政府運動を行い,また7月及び8月にも反政府運動を繰り広げたが,野党側の不統一もあって有効な運動を展開できず,結局ハック大統領とジュネジョ首相は,民政移管後の最初の試練を乗り切った。
(b) 外交
過去1年はインドとの関係で多くの展開のみられた年であった((イ)「概要」参照)。
アフガニスタン問題に関しては,パキスタン政府とアフガニスタンとの間で国連を通じる間接交渉が最近では87年2月より3月にかけて行われた。また,間接交渉に先立ち,87年2月ヤクブ・カーン外相がアフガニスタン問題につき,協議するため訪ソした。
米パ関係については,86年7月にジョネジョ首相が訪米し,先に両国政府間で原則的に合意をみていた経済・軍事援助(87年10月から6年間にわたり総額40.2億ドル)等につき協議が行われた。同援助計画は米議会の承認を得る必要があるがパキスタンが核開発を行っているとの報道もあり(同国政府は否定),米議会での審議の帰すうが注目されている。
なお,ハック大統領は86年9月にジンバブエでの第8回非同盟首脳会議に出席し,また,87年1月にイスラム会議機構首脳会議(於クウェイト)に出席した。
(c) 経済
85/86年度(85年7月~86年6月)は,農業生産が,綿花及び小麦が過去最高を記録したこと等により,前年度比6.5%増大し,また,工業生産は8.2%増と前年に続いて好調を持続したため,GDP実質成長率は7.5%を達成した。
貿易面では,輸出が29.39億ドル(前年度比19.6%増),輸入が59.29億ドル(同1.3%減)となり,貿易収支赤字幅が前年より5.62億ドル減少した。海外出稼ぎ労働者による送金は6.1%増の25.95億ドルとなり,経常収支は11.45億ドルの赤字となった。
(ニ) バングラデシュ
(a) 内政
86年は,バングラデシュにとり民政に復帰した重要な年であった。
エルシャド大統領は,5月に懸案の国会選挙を実施し,軍を退役した上で大統領選挙に立候補し,圧倒的大差で大統領に選出された(86年10月)。右国政選挙の実施を受け,82年3月以来の戒厳令施政の合法化を図る第7次憲法修正法案が,86年11月10日に国会で可決され,エルシャド大統領は同日,戒厳令を撤廃し,同国は約4年7か月振りに民政に復帰した。
(b) 外交
86年6,7月,エルシャド大統領はSAARC議長国首脳として加盟国すべてを歴訪,二国間関係及びSAARC協力関係の促進に努めた。
なお,チョードリー同国外相は第41回国連総会(86年9月から)議長に選出された。
(c) 経済
85/86年度(85年7月~86年6月)のGDP成長率は,過去最高の食糧穀物生産(推定1,612万トン)等により前年比実質4.9%となり,同国経済は順調な成長の方向に向いつつあるが,主要輸出品目の原ジュート・ジュート製品,紅茶の国際価格の低迷が続き,貿易収支好転の見通しは暗い。
(ホ) スリ・ランカ
(a) 内政
86年6月,スリ・ランカ政府は公認政党会議で大幅な地方自治権委譲を内容とする新政治解決案を発表する一方,タミル過激派に対しても同案を交渉のベースとすべくインドを通じ働きかけを行ったが,過激派側はタミル人の固有の領土と主張する北部・東部両州の統合を交渉の前提とすることに固執し同案の受入れを拒否した。
その後の「ス」印両国間の交渉の結果,東部州より一部をシンハラ地域として切り離した上で北部東部両州を制度的に結びつけるとする,いわゆる12月19日提案が急浮上し,現在インドの仲介の下,過激派に対する働きかけが行われている。
(b) 外交
86年のスリ・ランカ外交は前年同様シンハラ・タミル民族問題に深く係わるインドとの関係を中心に展開し,11月にインドで開催されたSAARC首脳会議の際にも本問題につきジャヤワルダナ大統領とガンジー印首相との会談が行われた。
(c) 経済
86年の経済は,紅茶,ココナツ等の主要産品の国際市況価格の低迷による輸出の伸び悩みが見られたが,GNP成長率(4%)等の基調においては85年と大きく異なるものではなかった。なお,民族問題の長期化は軍事費の膨張をもたらし,当国経済の圧迫要因となっている。
(ヘ) ネパール
(a) 内政
国王親政体制を支える非政党制政治制度である「パンチャーヤット制度」を採用している。現行憲法下で2回目の総選挙が86年5月に平穏裡に実施され,6月にはマリチ・マン・シンを首班とする新内閣が発足した。
(b) 外交
ビレンドラ国王は,非同盟首脳会議及びSAARC首脳会議に出席したほか,西独を公式訪問した。なお,87年3月の時点で「ネパール平和地帯」提案に対する支持国は83か国に達している。
(c) 経済
85/86年度(85年7月~86年6月)の経済は,経済調整策が奏功したこと,天候に恵まれたこと等から良好な実績を示し,実質国内生産(GDP)成長率は4.2%を達成し,経常収支は2.1億ドルの黒字となった。
(ト) モルディヴ
現在任期二期目の終盤を迎えつつあるガユーム大統領は堅実な政策運営を展開し,安定した基盤に立っている。
ガユーム大統領はサウジアラビア等中東諸国訪問する等活発な外交を展開し,またガンジー印首相,エルシャド・バングラデシュ大統領がモルディヴを訪れた。
経済については,主力の観光農業が,1986年5月のスリ・ランカでの航空機爆破事件後一時的に悪影響を受けたが,その後好転している。
(チ) ブータン
国王親政体制の下に近代化,民主化が進められ,開発計画が鋭意推進される等政情は安定している。国王は87年7月開始予定の第6次開発計画策定のため積極的に国内巡行を行っている。
対外関係については門戸開放政策を推進し,87年1月末までに我が国を含め合計13か国と外交関係を持つに至った。なお,ワンチュク国王は9月のジンバブエでの非同首脳会議及び11月のインドでのSAARC首脳会議に出帯した。
(2) 我が国との関係
我が国と南西アジア諸国は,伝統的に友好関係を維持してきているが,87年3月に浩宮殿下がネパール,ブータン及びインドをそれぞれ公式訪問され,友好親善関係の促進に大きく貢献される等,この1年も我が国と南西アジア諸国との関係緊密化が進んだ。
インドとの関係では,86年を通じ,第5回日印貿易協議(5月),日印科学技術協力第1回合同委員会(9月),日印外務事務レベル協議(12月)がそれぞれ開催された。なお,11月にはティワリ外相が非同盟諸国ミッションの一員として訪日した。
パキスタンとの関係では,7月に第3回目・パ合同委員会が開催された。
バングラデシュとの関係では,86年2月にチョードリー外相が国連総会議長との立場で外務省賓客として訪日し,倉成外務大臣と会談した。
スリ・ランカとの関係では,86年8月に非公式訪問したプルマダーサ首相が中曽根内閣総理大臣との間で意見交換を行った。
<要人往来>
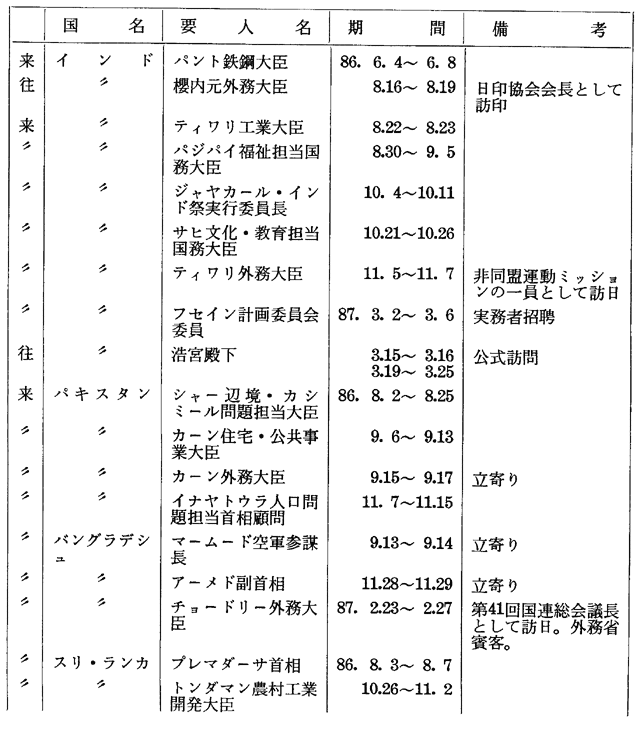

<貿易関係>
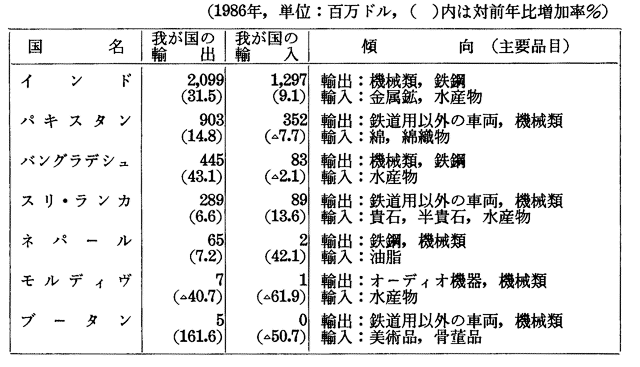
<民間投資>