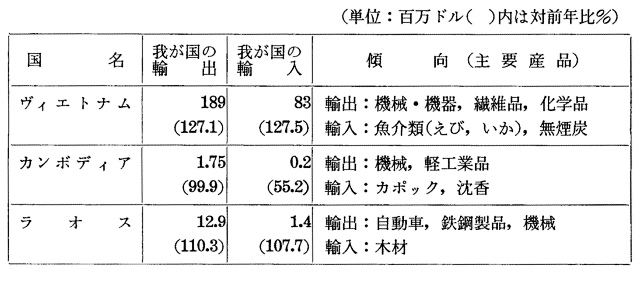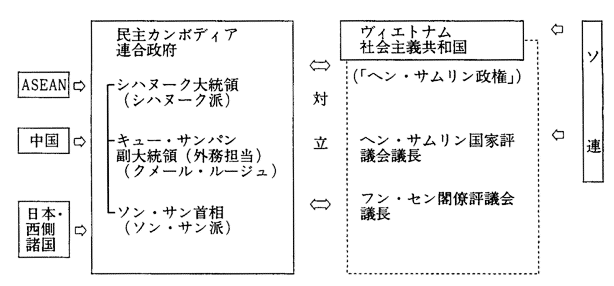
4.インドシナ地域
インドシナ地域では依然ヴィエトナムのカンボディアヘの武力介入が続いており,これに反対する民主カンボディア連合政府との間で戦闘状態が続いた。
ヴィエトナム側は累次のインドシナ3国外相会議で1990年までのヴィエトナム軍完全撤退をうたい,第三国を通じ民主カンボディアとヘン・サムリン側との交渉を提案する等数々の外交攻勢をかけているものの,「ヘンサムリン政権」の既成事実化を追求する基本的立場に変化はみられなかった。
これに対しASEAN側はカンボディア問題の根源はヴィエトナムの武力介入にあるとの立場からヴィエトナムと民主カンボディア側を当事者とする交渉を主張しており,依然和平への糸口は見出されなかった。
他方86年12月のヴィエトナム指導部の交代,経済改革の動き,ラオスによる対中国及びタイとの関係改善の動き等新たな要素も出てきており,中ソ関係の動向も合わせ今後のインドシナ諸国の動向が注目される。
(1) 全体の構図
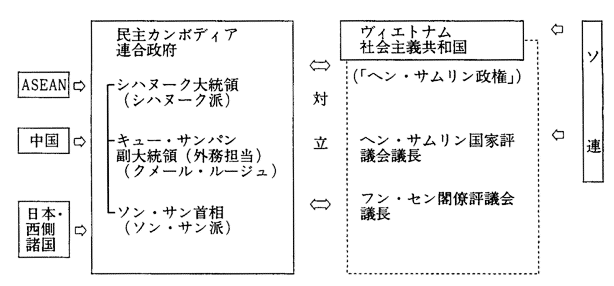
(2) 民主カンボディア及びヴィエトナム・ヘン・サムリン側双方の基本的立場
民主カンボディア連合政府 |
ヴィエトナム社会主義共和国及び「ヘン・サムリン政権」 |
1. ヴィエトナム軍の撤退の過程につきヴィエトナムと交渉。 2. ヴィエトナム軍の第一段階撤退の後,ヘン・サムリン派と交渉,民主カンボディア三派にヘン・サムリン派を加えた4派連合政府を樹立。 3. 四派連合政府が国連監視団の監督の下に自由選挙を実施。 |
1. 民主カンボディア三派とヘン・サムリン「政権」との交渉。 2. ポル・ポット派等に対する諸多国の援助停止等を条件にヴィエトナム軍は撤退(1990年までに完全撤退)。 3. ポル・ポット派の排除に基づく国民和解,ヴィエトナム軍撤退後の選挙につき反対派の個人又はグループと協議。 |
(3) 軍事情勢図
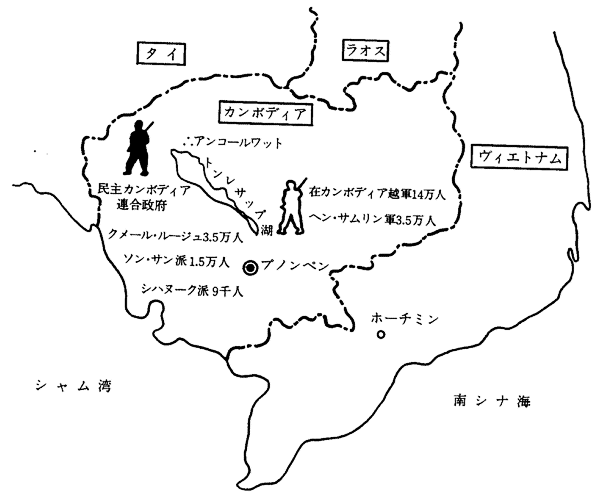
(1) 内外情勢
(イ) ヴィエトナム
(a) 内政
(i) 86年の内政上の大きな特徴としては,経済政策の行詰りや指導部の老齢化を背景として,党・政府首脳の人事異動が目まぐるしく行われたことが挙げられる。まず,1月に経済運営の失敗を背景にチャン・フォン副首相が解任されたのに続き,6月にはトー・フー筆頭副首相(政治局員)を含め経済関係閣僚7名の更迭など計9名に及ぶ大幅な内閣改造が行われた。ついで7月にはホー・チ・ミンの死去(69年)以来17年にわたり党最高指導者だったレ・ズアン書記長が死亡し,後任人事が注目されたが,党大会を12月に控えていたこともあり政治局第2位のチュオン・チン国家評議会議長(元首)が書記長を兼務するという最も無難ともいえる選択が行われた。
(ii) 第6回党大会(12月)では開催直前まで党首脳人事をめぐって様々な動きがあった模様であるが,結局チュオン・チン,ファム・ヴァン・ドン閣僚評議会議長(首相),レ・ドゥック・トの有力3政治局員がそろって政治局から引退し,あらたに設けられた党中央委顧問のポストに就くこととなり,新書記長には経済改革派の中心人物ともくされるグエン・ヴァン・リンが就任した。これに伴う政治局(14名)人事も引退3名,解任3名,候補よりの昇格2名,新任は候補を含め5名という大幅なものとなり,新書記長体制ともいうべき実務型の陣容となった。他方,政府首脳人事については,党大会直後の国会では異動が見送られたものの,87年2月には,新任13名を含む計21名に及ぶ閣僚の人事異動と行政機構改革が断行され,行政面においても経済困難に対処した実務型への衣がえが進んだ。
(iii) 87年4月,第8期国会議員選挙が行われた。
(b) 外交
(i) ラオス,カンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との「特別な関係」とソ連との協力関係を重視するヴィエトナムの外交基本姿勢は,86年においても貫かれた。特に対ソ関係は年末の党大会政治報告において「対外政策の礎石」と位置づけられ,要人の往来も活発に行われた。すなわち,レ・ズアン書記長(2月),チュオン・チン書記長(8月および11月)が訪ソ,他方,ソ連からもルイシコフ首相(7月),リガチョフ政治局員(12月),シェワルナッゼ外相(87年3月)が訪越した。
さらに,ソ連の対越援助については,党大会に出席したソ連代表は,86年から90年の5か年で前5か年の2倍となる旨公表した。
(ii) 他方,カンボディア問題をめぐり対立状態にある中国との関係には改善のきざしはうかがえなかった。ヴィエトナム側は,8月にハノイで開かれた第13回インドシナ三国外相会議等の機会に中国に対し「いつ,いかなるレベルでも,どこでも話し合う用意がある」と呼びかけを行っているが,中国側はこれに応じる姿勢を示さず,また,両国国境地帯では軍事衝突が断続的に続いている。
(iii) ヴィエトナムは,近年ヴィエトナム戦争中の行方不明米兵捜索(MIA)問題解決のための協力を通じ対米関係の改善をはかるとの方針のもとに,米国との対話を続けてきたが,86年においても同問題に関する米越専門家定期会合が数次にわたり開催されたほか,米側からMIA高級ミッション(1月)が訪越した。ヴィエトナム側は,このほかにも米国との接触拡大に努力し,米議会代表団(1月および2月),チルドレス米国家安全保障会議(NSC)局長(7月),ヴァンス元国務長官(10月)の訪越が実現した。
(iv) カンボディア問題についてヴィエトナム側は1990年までにカンボディア駐留中のヴィエトナム軍を全面撤退させる方針を繰り返し表明したが,「ヘン・サムリン政権」の存続とポル・ポット派の排除を求める基本姿勢に実質的変化はうかがえず,民主カンボディア連合政府との交渉を拒否する姿勢にも変化は見られなかった。
(c) 経済
(i) 86年は第4次経済5か年計画(86~90年)の第1年目にあたっていたが,同計画を審議する党大会の開催が86年末となったため,86年については単年計画として実施された。党大会における経済報告によれば,同年における生産実績は食糧が1,859万トンと目標(2,000万トン)を大きく下回り,81年に導入した新経済政策による増産が限界に直面しつつあることを示唆した。他方,鉱工業関係では,「石炭・肥料等が生産目標を達成,電力・セメントは不振」と発表されたが,いずれも具体的数値は明らかにされず,各部門にわたって生産が低迷していることがうかがわれた。
(ii) 85年の経済改革実施に伴う経済混乱は86年に入っても有効な施策が打ち出せないままさらに拡大する様相を示した。かかる混乱を収拾するため,経済関係閣僚の入替えが行われたほか,政策面では11月に通貨切り下げ(対ドル・レートを1ドル=15ドンから80ドンヘ)を断行,また,農・工・商の各分野にわたる「家庭内生産」を奨励する「家庭内経済」制度を遂次導入し生活消費財の増産をはかることとなった。
(iii) 第4次経済5か年計画の概要は第6回党大会(12月)で発表され,重点項目として食糧・消費財・輸出品の増産をはかるとの方向が示された。また,87年の食糧生産目標は1,920万トンと低目に設定された。
(ロ) カンボディア
(a) 国内情勢
(i) 1978年12月のヴィエトナムのカンボディアヘの武力介入に端を発したカンボディア問題は既に8年余を経過したが依然政治解決の糸口がつかめておらず,「カ」国内では主として民主カンボディア抵抗勢力とヴィエトナム軍との間の武力衝突が続いている
(ii) 地方に退避した民主カンボディア政府はタイ・カンボディア国境地帯を中心に,ゲリラ戦を展開し,82年7月にはそれまで独自の抗越活動を行っていたシハヌーク派,ソン・サン派勢力を結集し,民主カンボディア三派連合政府を結成,徐々に「カ」国内の軍事活動を強化してきた。84年末から85年3月にかけてのヴィエトナム軍の大規模攻勢により,タイ・カンボディア国境地域の主要拠点を失ったもののこれを機にむしろ,カンボディア国内で広範囲にわたってゲリラ活動を展開している模様である。
(iii) 他方ヴィエトナムは79年1月に擁立したいわゆる「ヘン・サムリン政権」を軍事的に支援するとともに,主としてソ連,東欧諸国等からの経済支援の下で「ヘン・サムリン政権」の既成事化を図ってきている。「ヘン・サムリン政権」は政治的にも軍事的にもヴィエトナムの強い影響下におかれている。
(b) 外交
(i) 82年の連合政府結成以来民主カンボディアはASEAN諸国と協力し,シアヌーク大統領を中心にカンボディア問題の包括的政治解決に対する国際的な支持獲得のため活発な外交活動を展開した。86年の国連総会ではヴィエトナム軍の撤退とカンボディアの民族自決を柱とする包括的政治解決を求めるカンボディア情勢決議が前年を上回る圧倒的多数で採択された。なお民主カンボディアの国連における代表権は86年も無投票で承認された。
(ii) 86年3月,民主カンボディア連合政府は北京において(イ)ヴィエトナムとの間でのヴィエトナム軍の二段階撤退に関する合意(ロ)民主カンボディア三派とヘン・サムリン派との間の交渉による四派連合政府の樹立(ハ)同連合政府による国連監視下での自由選挙等を含む8項目の包括的政治解決案を発表し右提案はASEAN諸国をはじめ,日本を含む(iii) 他方,ヴィエトナム側は86年10月オーストリアを通じシハヌーク民主カンボディア大統領に対し民主カンボディアとヘン・サムリンとの交渉を提案したが,シハヌーク大統領は,民主カンボディアとヴィエトナムとの交渉が先決であるとしてこれを拒絶している。
(iv) 87年3月,ソ連のシエヴァルナッゼ外相は,タイ,オーストラリア,インドネシア,及びインドシナ諸国を歴訪したが,中ソ関係の改善にとり中国側が最大の障害とし,ASEAN諸国との関係拡大にも障害となるカンボディア問題について,情勢打開の方途を探ることが右歴訪の一つの目的とみられており,今後の動向が注目される。
(ハ) ラオス
(a) 内政
(i) 86年は,11月に第4回党大会が開催され,従来よりのカイソーン書記長下の体制が確認された。また同年は第2次経済・社会開発5か年計画(86年~90年)の初年度としても重要な年であった。
(ii) 政情は安定的に推移し,治安も全般的には問題なく,地方での反政府活動も組織的な規模のものはみられなかった。
(b) 外交
(i) ヴィエトナム,カンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との「特別な関係」とソ連等社会主義諸国との協力関係の強化を柱とする外交姿勢に変化はなく,87年3月にはシェワルナッゼソ連外相がヴィエンチャンを訪問した。
(ii) 他方,ラオスは,中国,タイとの関係改善にも意欲を示し,86年11月及び87年3月にタイと第1,2回高級実務者会議,86年12月に中国と外務次官級会談を開催した。
タイとの間では,第1回会議においてタイ側より対ラオス禁輸措置の緩和が提示される等の成果がみられたが,第2回会議においては,国境問題に関する両国の立場の違いにより具体的成果は得られなかった。
また,中国との外務次官級会談では,具体的成果はあがらなかったものの,次回会談につき,ラオス側が中国側からの同国訪問・会談開催の招請を受諾し,対話継続が合意された。
(iii) このほか,我が国をはじめ,豪州,スウェーデン等との間では経済協力を中心に良好な関係が継続したが,米国との関係では,85年に見られたような要人会談等関係改善への目立った動きは見られなかった。
(c) 経済
86年においては,前年に引続き食糧の自給の一応の達成等の成果をみたが,財政赤字,都市部における消費物資の価格高騰等の問題が継続した。
第4回党大会決議においては,市場原理を大幅に活用する新経済政策が打ち出され,経済の活性化が図られている。
(2) 我が国との関係
(イ) ヴィエトナム
カンボディア問題をめぐる政治情勢を反映し,依然停滞した状況が継続したが,その中にあってヴォー・ドン・ザン外務担当国務大臣の本邦立寄りの機会に政治対話が行われたほか,12月の第6回党大会における政治報告において我が国を含む西側5か国の名前を列挙し友好関係の強化・拡大を希望する旨表明された。
(ロ) カンボディア
(i) 我が国は引き続き民主カンボディア連合政府を支持し,いわゆる「ヘン・サムリン政権」は承認していない。
(ii) 我が国はカンボディア問題の早期解決が東南アジア平和と安定のためにも不可欠との立場からカンボディアからのすべての外国軍隊の撤退とカンボディア人の民族自決を柱とする包括的政治解決を求める方針を堅持しており,立場を同じくするASEAN諸国の外交努力を支援するとともにヴィエトナムとの対話を継続した。
(iii) 我が国はかかる外交努力の一環として86年6月,ASEAN拡大外相会議において安倍外務大臣(当時)より「共存のための対話」の必要性を強調するとともにカンボディアに真の平和が訪れた際にはインドシナ復興のための経済技術協力を行う用意がある旨を明らかにした。
(ハ) ラオス
我が国は,西側諸国との関係拡大に努めるラオス側の姿勢に応え,従来両国関係は順調に推移した。我が国は,東南アジア唯一の後発開発途上国(LLDC)である同国の経済・社会開発に貢献するため,無償援助を中心とする協力を実施しており,ラオスも,同国に対する最大の西側援助国たる我が国への期待感を一層高めている。
(3) 難民問題
(1) 概況
(イ) 75年のインドシナ政変を契機としたインドシナ難民問題は,ヴィエトナムのカンボディア介入翌年の79年当時の危機的状況から脱してはいるものの,依然として毎月1,000~2,000人のヴィエトナム難民がボート・ピープルとして流出しているなど,長期化傾向にある。
(ロ) これまでに約170万人のインドシナ難民が国外に流出しているが,このほかにも脱出中に海中に没した者も多数いると言われ,これらを含めると相当数が祖国を脱したことになる。これらのインドシナ難民のうち,これまでに約120万人が,米国,フランス,カナダ,豪州等に定住しているが,約15万人が依然としてタイ等の東南アジア諸国に滞留している。また,タイ・「カ」国境には,84年末のヴィエトナム軍による乾季攻勢等により,流出した約26万人の避難民が保護を受けているなど難民問題は依然として東南アジア地域の不安定要因となっている。
(ハ) インドシナ難民問題の根本的解決のためには,まず,インドシナ問題の解決とインドシナ三国の安定が必要であるが,これに至るまでの解決策として,本国自主帰還,一次庇護国における定住及び第三国定住等が考えられている。もっとも前二者の促進にも困難があり,第三国による定住引取りが主要な解決策となっているのが現状である。ただし,インドシナ難民問題の長期化と受入れ国の国内事情などの理由により,西側諸国による定住難民引取りにも種々問題が生じている。
(2) 我が国の対応
(イ) 我が国は,大量のインドシナ難民が発生した79年以来,資金協力,一次庇護及び定住難民引取り等の難民援助を積極的に進めてきている。資金協力については86年度に約2,500万ドルを拠出し,この結果,79年以降の累計援助総額は約5億2千万ドルを超えた。
(ロ) 他方,一次庇護については,86年中に約350人のボート・ピープルが新たに上陸した。この結果75年以降の上陸総数は約8,800人を超し,このうち約930人が我が国に滞留中である。
一方,我が国の定住難民の受入れについては,我が国に上陸したボート・ピープルの中から定住した者,東南アジア諸国のキャンプより定住した者等を含め86年3月末現在5,001人に達している。
<要人往来>
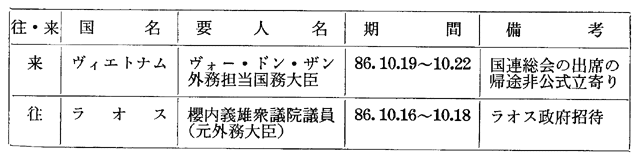
<貿易関係>