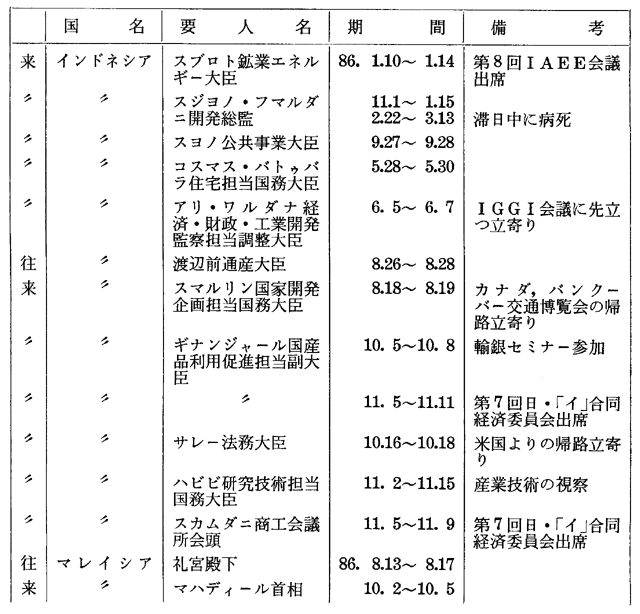
3. 東南アジア諸国連合(ASEAN)6か国及びビルマ
86年の東南アジア地域(インドシナ地域を除く)の情勢は,全体として見れば,安定的に推移したといえる。政治面ではフィリピンで20年間続いたマルコス政権に代わるアキノ新政権が成立したことが注目された。また,マレイシア,タイでは総選が行われ挙マレイシアにおいては与党,タイにおいては現プレム首相支持政党が各々勝利を収めた。
経済面では,依然として石油等一次産品の価格低迷が続く中で,これら産品の輸出への依存度が高いインドネシア及びマレイシア並びに対外債務問題を抱えるフィリピンは,いずれも本格的経済回復を示すに至らなかった。ビルマも外貨事情が悪化し債務返済問題に直面した。シンガポールは,円高等の影響により輸出環境が改善し,86年には前年のマイナス成長からプラス成長に転じた。また,タイ経済は,製品輸出拡大等から相対的に堅調に推移した。
(1) 内外情勢
(イ) インドネシア
(a) 内政
86年は,87年4月の総選挙を控え,パンチャシラ(国是五原則)体制の総仕上げ及び総選挙参加団体(開発連合党(PPP),ゴルカル(職能グループ)及びインドネシア民主党(PDI)の3団体)の選挙準備等が進められたが,総じて平穏に推移した。
国軍の再編成については6月にトゥリ・ストゥリスノ陸軍参謀長の就任等があり,国軍はムルダニ総司令官を除き,すべて新世代となり,世代交代が完了した。また,パンチャシラの徹底化については,全ての主要団体が年末までに社会団体法(85年成立)に従いパンチャシラ唯一原則を受入れ,一段落した。
他方,5月に一連の選挙手続が開始されるとともに,選挙参加団体もそれぞれ選挙準備に着手した。与党的存在であるゴルカルの選挙準備先行と着実な成果が目立ち,ゴルカルが圧倒的に優勢との見方が支配的である。
また10月スハルト大統領は事実上の大統領選出馬表明を行い,88年3月の5選はほぼ確実視されるに至っている。
(b) 外交
インドネシアは,従来よりASEANとの連帯及び非同盟積極自主外交を標傍するとともに,米国,日本及びEC等西側諸国との協調を通じ開発を進め,もって国家としての強靱性の強化を図るとの基本路線をとっているが,86年においても基本的にはこの路線を踏襲した。
86年の主な動きとしては,スハルト大統領一族批判の豪紙報道(4月)を契機に対豪関係が冷却化したほか,レーガン大統領が東京サミット出席の途次バリ島でスハルト大統領及びASEAN外相と会談し(4~5月),アキノ比大統領(8月),ミッテラン仏大統領(9月),ガンジー印首相(10月)が相次いでインドネシアを訪問したこと等が挙げられる。
なお,対中関係については,11月ESCAP主催途上国間技術協力国際会議に出席するため「イ」政府ミッションが訪中したことが注目されたが,国交正常化自体は未だ先のこととみられている。
(c) 経済
85年度に輸出の7割及び国家歳入の6割を石油・天然ガスに依存していたインドネシアでは,85年以降原油輸出価格が急速に下落したため,86年度には近年はじめての減額予算(対前年度比7%減)を編成するとともに,86年も引き続き非石油・ガス産品の輸出促進,税収源の拡大と徴税の効率化,民間投資促進等の努力を行なった。しかしながら予算上25ドル/バーレルと想定した原油価格が一時は10ドル以下に下落したため,歳入欠陥を補うことを主たる目的として,9月にはルピア貨の切下げ(対米レート45%)が行われた。
インフレの抑制,米等食糧増産等はほぼ順調であったが,石油,ガスに対する依存が大きいためスハルト政権が標榜する開発政策は大幅な停滞を余儀なくされており,特に86年より開発プロジェクトの実施に必要な内貨にも不足を来たし諸外国より資金の借入れに努めている。
(ロ) マレイシア
(a) 内政
(副首相の辞任)
2月に,ムサ・ヒタム副首相が突如副首相及び連合与党中第一党の統一マレイ国民組織(UMNO)副総裁辞任の書簡をマハディール首相に送付したことは,かねてより取沙汰されていた両者の不仲が事実であったことを示した。最終的には,ムサ・ヒタムは党の慰留に応じ,副首相の職は辞任したものの,党副総裁の地位には留まることとなり,また,副首相には中立的で老練なガファールババ連合与党国民戦線(BN)幹事長が任命され,一応党の団結は保たれた。
(サバ州情勢)
サバ州では,85年4月の州議会選挙で勝利を収めたサバ統一党(PBS)が政権を握って以来,州都コタ・キナバルを中心に爆発事件等が頻発し,夜間外出禁止措置がとられる等政情不安が長期化していたが,86年5月に実施された再度の州議会選挙においてPBSが圧勝するとともに6月にはBNへの加入が承認され,州政権の基盤は強固なものとなった。
(総選挙)
引き続く経済低滞,85年来の内政上の諸問題を抱えたマハディール政権は任期を一年残して下院を解散し,8月2日,3日総選挙を実施した。当初,与党国民戦線(BN)の苦戦も予想されたが,実際は憲法改正に必要な議席数として勝利の目安となっていた下院総議席(177議席)の3分の2(118議席)を大きく上回る議席を獲得し,また同時選挙が実施された11州議会全てにおいてもBNが過半数を占め圧勝した。
(b) 外交
86年は総選挙の年でもあり,要人の往来は少なく,マハディール首相自身の外遊も9月の非同盟諸国首脳会議及び国連総会出席にとどまった。また,元首・首相クラスの外国要人としては,ウィーロック・ノールウェー首相(1月),ヴァィツゼッカー西独大統領(2月),ラウレル比副大統領兼外相(5月),シアヌークCGDK大統領(8月),リー・シンガポール首相(8月),ボルキア・ブルネイ国王(10月),A・バーバラ・マルタ大統領(11月),オザール・トルコ首相(11月)等が訪「マ」した。
ASEAN諸国のうち比との関係はアキノ政権成立後もサバ領有権問題が解決に向わず,引き続き低調に終始し,また,シンガポールとの関係は11月のヘルツオグ・イスラエル大統領訪「シ」をめぐり一時期,対「シ」抗議運動が展開される等緊張が高まった。
なお,マレイシアは5月上旬,東京サミットと同時期に南々サミットを開催し,途上国間の団結を誇示した。
(c) 経済
86年のマレイシア経済は,主要一次産品価格の厳しい落ち込み及び内需の低迷の影響により,85年同様低調で実質GDP成長率は1%に留まった。
貿易収支は,輸出入とも前年に比べ減少し,輸出の減少幅が輸入のそれを上回ったため,85年の89億リンギの黒字から84億リンギの黒字へと縮小した。他方,貿易外収支の赤字幅が85年の107億リンギから96億リンギヘと縮小したため,経常収支の赤字幅は85年の18億リンギから86年では12億リンギヘと改善した。
(ハ) フィリピン
(a) 内政
86年のフィリピンは,フィリピン国民の圧倒的支持を得て,2月にマルコス大統領に代わり政権の座に就いたアキノ大統領の下で,フィリピン政府が,左右両派の政治勢力の揺さぶりを受けつつも,政情の安定,経済の再建のための努力を払った1年であった。11月,アキノ大統領は,クーデター計画の噂の中,政権批判を繰り返していたエンリレ国防相を解任するとともに,軍の不満の対象となっていた左派閣僚を更迭するなど内閣の改造を実施した。
また,11月27日,政府は,国内の共産主義勢力との間で60日間の暫定停戦協定に合意し,両者間で和平交渉が断続的に行われたが,議題案をめぐり意見が対立したこと,また87年1月22日に,政府側警備当局が左派系農民デモに発砲し多数の死傷者が出たこと等により,結局,交渉は決裂した。
また,1月27日,軍の一部によるクーデターが発生し,放送局が占拠されるなどしたが,鎮圧され,関係者は全員逮捕された。
しかしながら,アキノ新政権は,事実上同政権に対する信任投票という性格を有した新憲法草案への国民投票(87年2月2日)において8割近い賛成票を得て圧勝し,「合法政権」としての地位を獲得するとともに,政情安定化に向け,新たなスタートを切ることになった。
(b) 外交
外交面では,いくつかの活発な動きが見られた。
対米関係については,9月,アキノ大統領が訪米しレーガン大統領と会談した。米国よりも多くの要人が訪比した。
ソ連との関係では,6月に,比ソ両国の国交樹立10周年が祝われた。
また,10月には,シャハニ外務次官が,同年4月のカピッツァ外務次官による訪比の答礼として訪ソした。
中国との関係では,6月,ラウレル副大統領兼外相が訪中した。
このほか,ラウレル副大統領兼外相が訪欧(7月,スペイン,西独,ベルギー)し,また,アキノ大統領が8月,インドネシア及びシンガポールを訪問した。また,外国よりは,豪州のホーク首相,シンガポールのリー首相等が訪比した。
(c) 経済
新政権発足後,物価鎮静化(86年通年0.76%),金利低下,外貨準備の改善(86年末現在,24.6億ドル),経済成長率のプラスヘの転換(86年通年0.13%)等明るい材料もあったが,対外累積債務は,約278億ドル(同9月末現在)にのぼっており,また,失業率も依然として高かった(86年7月末現在11.2%)。
他方,10月,IMFは,フィリピンに対し,総額422百万SDRの新規融資を行うことを承認した。また,87年1月には,パリにおいて対比債権国会議(22日)及び対比援助国会議(27及び28日)が開催され,同国の債務救済及び今後の対比援助方針につき協議が行われた。また,フィリピン政府は,同年,3月27日,外国の民間債権銀行団との間で債務の繰り延べにつき合意した。
(ニ) シンガポール
(a) 内政
指導者層の世代交替は86年においても前年を引き続き着実に進められた。特にゴー・チョク・トン第1副首相及びリー・シエン・ロン商工相の役割増大が注目された。ゴー副首相についてはASEAN及び欧州を歴訪し,またリー商工相については一昨年より懸案となっていた経済委員会報告書とりまとめの手腕を高く評価され,2月には商工担当国務相から商工相代行へ,さらに12月には商工相へと昇格し,急速に政府部内の地位を固めた。
(b) 外交
86年の「シ」外交は,内政面で特段の問題がなかったことから,85年に引き続きリー首相の首脳外交を中心に活発に展開した。
リー首相は1月にビルマ,タイ,4月に豪,ニュー・ジーランド,フィジー,6月に韓国,台湾,7月にフィリピン,8月にマレイシア,ブルネイ,10月に日本,そして12月に台湾,香港を訪問し,近隣諸国との関係強化に努めた。外国要人の訪「シ」については,ノールウェー首相(1月),ビルマ首相(4月,9月),シュルツ米国務長官(6月),シアヌーク大統領及びアキノ比大統領(8月),田中国副総理(10月),イスラエル大統領(11月)が主なものであった。
(c) 経済
85年に独立以来初めてのマイナス成長を記録したシンガポール経済も,86年2月にリー・シエン・ロン現商工相を長とする経済委員会より出された勧告に基き「シ」政府がとった敏速な対応により,86年には1.9%と,低成長ながらもプラス成長に転じ,不況の底を打って景気回復に向い始めた。かかる急速な経済好転をもたらした要因としては,従来の高賃金政策を抜本的に見直し,競争力を強化するなど,国内環境をいち早く整備したこと及び日本の急激な円高が「シ」にとりプラスに作用したこと等が挙げられる。
(ホ) タイ
(a) 内政
86年3月中旬より,内紛を抱える社会行動党をはじめとする政党再編成の動きが活発化し,5月,与党社会行動党の一部議員の造反等により政府提出案件が否決されるや,プレム首相は下院を解散,7月27日の総選挙で国民の信を問うた。総選挙の結果,プレム首相を支持する民主党,タイ国民党,社会行動党が上位三党を占め,8月11日,軍及び国王の信任を得て,上記3党に民衆党を加えた4党による第5次プレム連立内閣が成立した。
今回の下院解散劇の背景には,ここ数年来のプレム首相とアーティット国軍最高司令官兼陸軍司令官との間のリーダーシップ争いが介在していたが,5月プレム首相が政局の流動化に力を得て政治への介入姿勢を強めたアーティット司令官を陸軍司令官職から解任し,総選挙においてもアーティット最高司令官と気脈を通じプレム再任阻止を唱える反プレム派が振るわなかったことから,プレム首相に軍配が上げられる形でほぼ決着がついた(アーティット司令官はこの後8月に退役した)。
さらに,プレム首相はアーティット陸軍司令官の後任に,チャワリット陸軍参謀長を抜てき,軍部のプレム支持体制の一層の強化が図られた。
第5次プレム内閣は,成立早々スキャンダルによる閣僚の引責辞任という事態に見まわれ,また,与党内に民主党の内紛をはじめとする足並みの乱れを抱えつつも,軍部や国王の支持,さらには下半期の比較的良好な経済情勢を背景におおむね安定的に政局運営を図っている。
(b) 外交
外交面では86年においても自国の安全保障に直接結びつくカンボディア問題が引き続きタイにとって最大の懸案となったが,同時に農産品貿易をめぐる対米経済摩擦を背景に,輸出品の販路の拡大等経済外交も積極的に展開された。
カンボディア問題に関しては,ASEAN加盟国の結束は引続き維持され,3月に民主カンボディア連合政府が発表した「8項目提案」については,これを支持することで加盟国の共同歩調がとられた。またタイを中心にASEANによる民主カンボディア連合政府に対する政治的・外交的支援がASEAN外相会議,国連の場等で積極的に展開された。さらに86年10月にはガンジー・インド首相,ヴォー・ドン・ザン越外務担当相,11月,田紀雲中国副総理の訪問,87年3月にはシェヴァルナッゼ・ソ連外相のタイ立寄り,シン・インド外務担当相の訪タイ等「カ」問題をめぐり,タイと関係国との接触もひんぱんに行われた。特にシティ外相は,同5月に訪ソを予定しており,今後タイ・ソ間での,カンボディア問題の取扱い及び貿易等経済面での関係進展が注目される。
対米関係については,政治面では懸案であった戦争予備備蓄に関する話し会いも進展するなど引き続き良好な関係が維持されたが,経済面では米国新農業法の導入がタイにおいて厳しい対米批判を惹起するなど対立の契機がみられた。
対中関係は,カンボディア問題に対する共通の利害を基礎に引き続き良好に推移した。
ラオスとの間では,近年国境紛争(三村問題)をめぐりぎくしゃくした関係が続いたが,86年11月及び87年3月に両国の高級実務者会議が開催され,両国関係のあり方につき協議が行われた。かかる協議を通じ実務面ではタイの対ラオス禁輸措置が一部緩和されるなど一定の成果を挙げたが,三村領有権等につき見解の対立は続いており,全面的な関係改善には至っていない。
(c) 経済
86年のタイ経済は,85年に引き続き一次産品価格の低迷の影響を受けたものの,原油価格の下落,金利の低下及び円高等の好要因を背景に景気回復のきざしを示し,実質経済成長率は85年の3.2%を上回る3.5%の伸びを達成した。特に,輸出関連産業は好調で国内投資も徐々に回復しつつある。
貿易収支は,工業製品等の輸出好調に加えて原油価格の下落及び最近までの不況を反映した輸入減少等の要因で,大幅に改善した。経常収支は,貿易収支の改善及び観光収入の堅調もあって20年振りに黒字に転じた。
また,輸出所得の増加により債務返済比率の上昇にも歯止めがかかり(81年14.8%,85年21.9%,86年20.2%(暫定)。但し,公的債務及び民間債務の両者を含む),70年代後半以降深刻化しつつあった対外債務累積の問題にも改善のきざしが現れた。
タイ政府は,財政支出抑制と対外債務管理強化の観点から,83年以来引き締め基調の経済政策を継続して来た。86年に入り貿易収支が改善したこと等を反映して公定歩合の引き下げなど引き締め緩和の動きもみられたが,財政赤字問題が依然未解決であるため,引き締め基調の経済政策に基本的に変化はみられなかった。
(ヘ) ブルネイ
(a) 内政
ブルネイは,84年1月1日に英国から完全独立を果たし,以来,独立国家としての体制造りを推進している。国政は,世襲制の国王を元首とする立憲君主制を基本政体としている。86年の内政上の最も重要な出来事は,この国の首都がその名によって呼ばれるようになってから既に久しい王父スリ・ブガワンの逝去であった。同王父は,「現代ブルネイの創設者」ともいわれ,50年代から60年代にかけての在位中には,ブルネイの官僚機構制や社会インフラ等の国内諸体制の基本を形成する上で大きな貢献をした。王父の逝去後,時日を経ずして政府の省編成自体の改変を含む閣僚等の人事異動がなされたが,これを契機として内政・外交上重要な変化がもたらされるとはみられていない。
なお,86年2月には国王及び政府の政策支持をうたったブルネイ国民統一党が発足した。
(b) 外交
86年は,前年に引き続き外交面での展開は比較的地道に,しかし着実に行われた。
ブルネイの対外政策の基本は,ASEANを中心に域内の安定に努めるとともに,国防については英国との防衛取極を中心に近隣の英連邦諸国との緊密な協力を図っていくというものである。この観点より,86年11月にASEAN労働大臣会議が成功裏に主催されたことなどが注目される。
(c) 経済
経済活動の中心は石油及び天然ガスであり,同資源により高い所得水準(85年1人当たりGDPは1万6,135米ドル)を維持している。
(ト) ビルマ
(a) 内政
86年のビルマ情勢は政局面では,ネ・ウィン・ビルマ社会主義計画党総裁の監督を受けたサン・ユ大統領を中心とする現集団指導体制下で安定的に推移した。国内治安面では,ビルマ共産党及びカレン族等の少数民族の各武装反乱勢力が依然として国境付近において活動を継続しているが,政府軍もこれら武装反乱勢力の掃討,鎮定努力を行っており,これらの勢力は国内の安定を脅すには至っていない。
(b) 外交
外交面では,86年度においても,非同盟中立を堅持し,あらゆる国と友好関係,特に,近隣諸国との善隣友好関係を発展させ,自主外交路線を推進するという同国の対外政策の基本を維持している。ビルマの対外関係上,最も重要な中国とは,4月のマウン・マウン・カ首相の訪中をはじめ,各方面の交流が促進されたほか,経済協力についても前年に引き続き緊密な関係が保たれた。
また,ASEAN及び南西アジア諸国等の近隣諸国とは,サン・ユ大統領がバングラデシュ(11月),マウン・マウン・カ首相がシンガポール(9月),タイ(87年4月)を訪問,他方ティワリ・インド外相(12月),ハミード・スリランカ外相(87年1月)等が訪緬する等要人の交流の促進が図られた。
対米関係は,要人の交流は低調であったが,農業開発を中心とする経済技術協力は順調に進められた。一方,ソ連との関係は,基本的に前年度に比し変化はなく,スポーツ,文化等の交流が行われた。
日本,西独をはじめとする西側先進諸国との関係は経済技術協力を中心として前年に引き続き緊密であった。
(c) 経済
86年のビルマ経済は前年に引き続き,厳しい状況に直面した。
貿易面では,米等主要輸出産品の国際価格の低迷,さらには,輸出産品の多角化の遅れ等を背景として,輸出は,前年同様に不振を極め,外貨事情が悪化した。このため,政府は輸入節減策を強いられ,多くの資本材,原材料,部品を輸入に依存している当国経済に大きな影響を与えている。
また,外貨事情の悪化は同国の対外債務の返済をも厳しいものにしており,87年3月の人民議会への報告によれば債務返済比率(いわゆるデット・サービス・レシオ)は48%という高率に上っている。
86年度から始まった第5次4か年計画においては,このような厳しい経済環境を反映して,計画期間中の国内総生産(GDP)成長率を年平均4.5%,初年度の86年度を3.6%と低めの数値に設定している。
(2) 我が国との関係
(イ) インドネシア
86年は安倍外務大臣,スブロト鉱業エネルギー相,スヨノ公共事業相,コスマス・バトゥバラ住宅担当相,アリ・ワルダナ経済・財政・工業担当調整相,スマルリン国家開発企画担当相,ギナンジャール国産品利用促進担当副大臣,サレー法相,ハビビ研究技術担当国務相等の両国関係の往来が活発に行われた。貿易面では,86年も貿易収支は「イ」側の黒字(「イ」の対日輸出73.1億ドル,輸入26.6億ドル)であるが,「イ」は非石油・ガス産品の輸出振興のため,日本の資金的・技術的協力を求めて来ている。投資面では86年には我が国を含む諸外国からの対「イ」投資が減少したため,「イ」側より投資の拡大について,我が国の協力を求めてきており,「イ」側も投資環境の改善に努力がみられた。また,「イ」側のイニシアティブによる科学技術分野の「イ」政府派遣留学生は,86年は69名派遣され計97名が留学中である。
(ロ) マレイシア
86年の日・「マ」貿易は,「マ」が大幅黒字を計上したが,総額では輸出・輸入とも減少し,対「マ」直接投資も低滞気味に推移した。これに加え,85年9月以降の急速な円高により,「マ」の対日円建債務返済負担が急増すると共に,日本からの輸入部品価格が大幅に上昇するとの影響を被った。
我が国は,86年4月,「マ」関心品目であるパーム油の特恵関税を0%に引下げるとともに,手工業によるバティック染綿織物の特恵対象化を行い,さらに,年末には円借款供与条件改善を決定した。
また,第2回目・「マ」コロキアムが6月18日~20日東京において開催され,政治・経済等両国が関係する広範囲な分野にわたって,日・「マ」両国の有識者が有意義な意見交換を行った。
(ハ) フィリピン
日比両国間の関係は,新政権成立後の混乱の影響を受けつつも,貿易,投資,経済協力,文化交流の増進のための努力が行われる一方,活発な要人往来がみられた。86年には,竹下大蔵大臣(4月,アジア開発銀行総会出席),安倍外務大臣(6月,ASEAN拡大外相会議出席)及び福田元総理大臣等が訪比した一方,フィリピンより,アキノ大統領,ラウレル副大統領兼外相等多くの要人が訪日し,両国間の相互理解の一層の増進が図られた。
特に11月にアキノ大統領が国賓として来日した際には,中曽根総理大臣より同大統領に対し,我が国はフィリピン政府により進められている新たな国造りの努力に対し支援を惜しまない旨の意向を表明した。
また,貿易面では,86年の対日輸出が12億2,070万ドル,対日輸入が,10億8,800万ドルとなり,比側の出超となった。
なお,11月15日に三井物産マニラ支店長誘拐事件が発生したが,87年3月31日,同支店長は4か月半ぶりに無事救出された。
(ニ) シンガポール
日本・シンガポール関係は近年安定した良好な関係を維持してきているところ,86年においてはかかる良好な関係を基盤としてシンガポールの経済不振打開の観点から我が国に対し一層大きな関心と期待が寄せられた。
特に日本の対米経済関係の進展がシンガポールを含む世界全体に好影響を及ぼすとして,日本の一層の市場開放等による良好な日米関係維持に期待が示された。
86年の人的交流として特筆すべきは,リー首相が公賓として我が国を10月に公式訪問したことである。3年振りの日本・シンガポール首脳会談では,両国で特段の懸案もないことから,もっぱら国際経済情勢,特に不況に直面するASEANの経済状況が話し合われ,同地域の経済回復に果す日本の役割への期待が強く表明された。
貿易分野では,日本・シンガポール貿易の総額は86年シンガポール貿易総額の12.5%,60.2億米ドルに達し,我が国はシンガポールにとり米国に次ぐ貿易相手国となっている。シンガポールの日本への輸出は14.6億米ドルと対前年比8.2%減,他方日本からの輸入は45.6億米ドルと前年比18.6%増となり,貿易収支は我が国の31.1億米ドルの出超となっている。
なお,86年の日本の対シンガポール投資は急激な円高の進展を背景に好調に推移し,シンガポールに対する外国投資総額の34%を占め,米国を抜いて第1位となった。
(ホ) タイ
日・タイ関係は全体として極めて良好で,広範な分野で緊密な関係が維持された。
その中で,最大の懸案となっている貿易不均衡問題は,日・タイ双方の協調的努力及び円高の影響等により大幅に改善した。また,円高が進む中で政治的安定性及び投資環境等タイの投資先としての比較優位性に関心が持たれ,我が国からの投資意欲が高まる傾向がみられた。
また,87年は日・タイ間の正式な国交を樹立した日・タイ修好宣言の調印百周年にあたるため,両国において数々の記念行事の準備が進められているところ,このような行事を通じ,相互理解と友好関係が一層促進されることが期待される
(ヘ) ブルネイ
我が国は,ブルネイの最大の貿易相手国(85年のブルネイの全輸出入量に占める対日輸出・対日輸入の割合は,それぞれ61%及び20%)であり,ブルネイ産原油の約6割及びLNGの全量が我が国に引き取られている。
ブルネイの国造りに対して,我が国は技術協力,教員派遣等を通じ積極的な協力を行っている。
86年3月に,ブルネイ独立以来の懸案であった在本邦ブルネイ大使館が開館の運びとなり,また,6月より,我が国とブルネイとの間で一部査証につき14日を超えない期間につき相互免除が行われることとなった。
(ト) ビルマ
我が国とビルマとの関係は86年においても引き続き友好裡に推移し,経済協力を中心とした緊密な関係が維持された。9月には,マウン・マウン・カ首相がチョウ・ティン副首相兼国防相,イエ・ガウン外相等を帯同し公賓として訪日し,両国関係の一層の促進に寄与した,さらに86年1月に東京で開催された第6回ビルマ援助国会議出席のため,トゥン・ティン副首相兼計画財務相が訪日したのをはじめ,我が国からは浜野外務政務次官(87年1月)等が訪緬する等要人の交流が,前年に引き続き活発に行われた。
<要人往来>
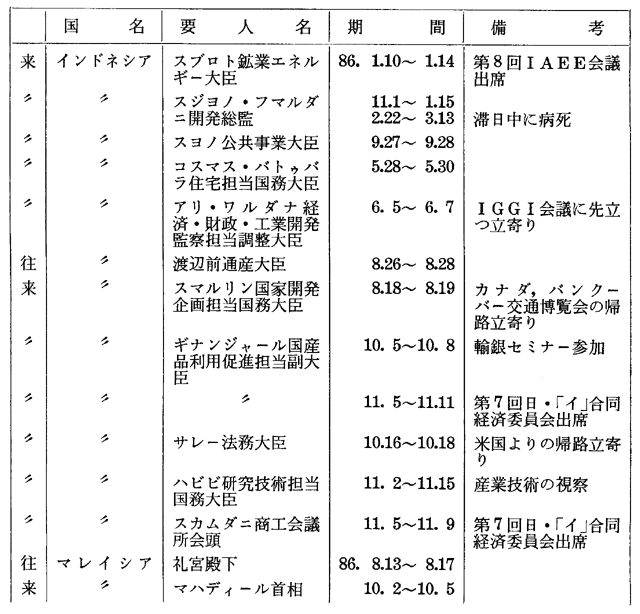
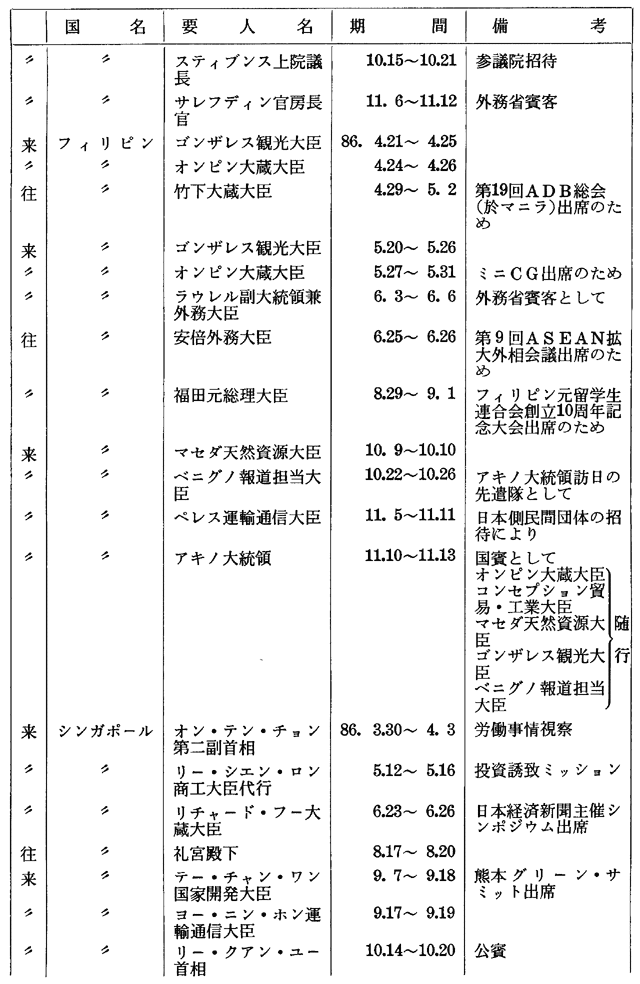
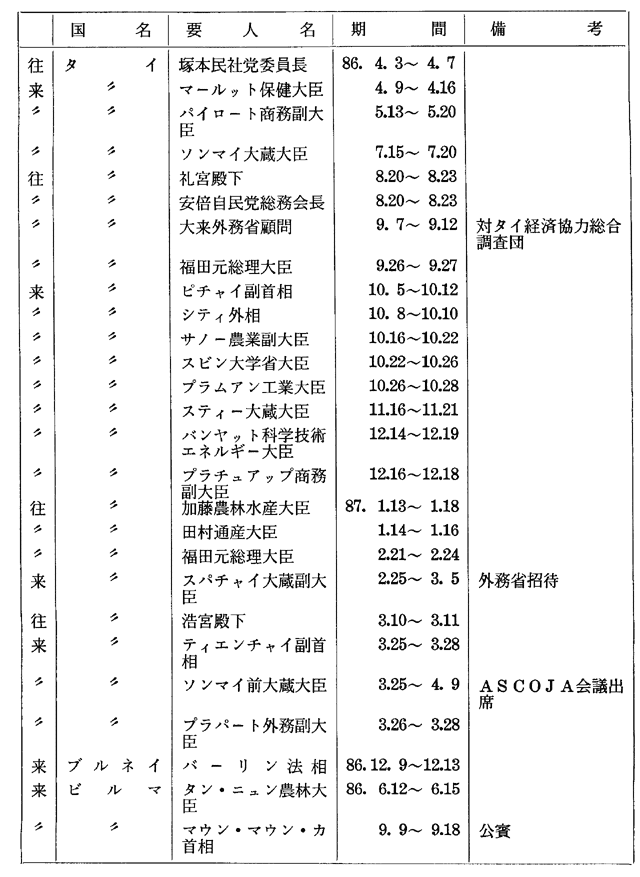
<貿易関係>
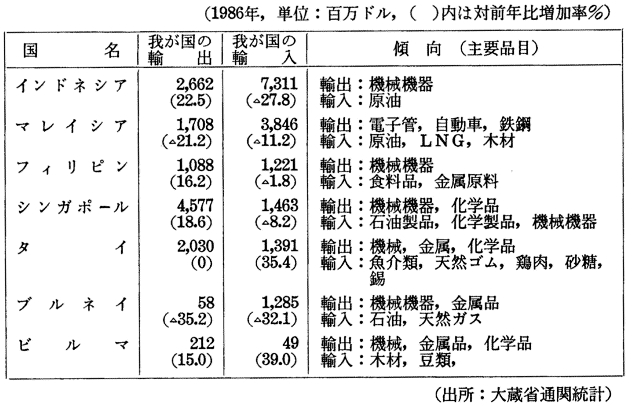
<民間投資>
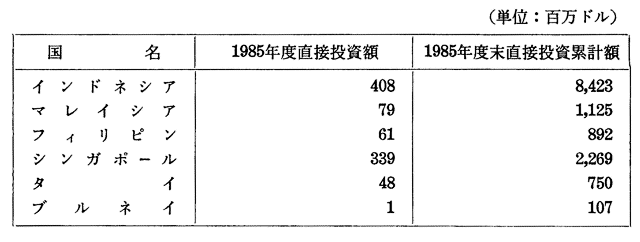
(3) 東南アジア諸国連合(ASEAN)
本年で設立20周年を迎えるASEANは,東南アジア地域の安定と発展のために多大の実績を上げている。我が国としてもASEANをひろくアジア太平洋地域における安定勢力として重視し,ASEAN諸国との友好関係の増進,同諸国の発展への協力を我が国外交政策の重要な柱として進めてきている。
(イ)地域協力の状況
ASEAN諸国は,社会・文化・政治・経済等の面で多様性を有しつつも,同地域の発展のために各種の分野において域内協力の強化に努めている。
政治面では,東南アジアの安定にとり大きな脅威であるカンボディア問題の解決の目途が立たない中で,ASEANは結束を維持し同問題の風化を妨ぎ,ASEANの和平努力に対する国際社会の支持強化を図るべく,国連等の場で積極的な外交努力を展開した。かかるASEANの和平努力は,86年6月の東京サミット参加国より支持(中曽根総理の議長総括中で言及)され,また,同年秋の国連総会におけるカンボディア情勢決議案(例年通りASEAN諸国を中心とする共同提案)に対する圧倒的多数の支持(115票)にもつながった。
経済面では,近年の一次産品価格の下落等の影響を受けて85年に経済成長及び国際収支等の面で困難に直面していたASEAN諸国の経済は,86年には,一部に成長回復のきぎしが見られたが,全体としては依然として低調に推移している。かかる状況の下でASEAN諸国は,各々経済構造の高度化・輸出競争力の増大等を目指した努力を行っており,また,ASEAN全体として域内特恵制度の拡充,ASEAN工業合弁事業(AIJV)の振興等の域内協力を進めている。
(ロ) 域外諸国とASEANとの関係
域外先進諸国との間では,ASEAN拡大外相会議(ASEAN諸国に加え,日本,米国,豪州,カナダ,ニュー・ジーランド,ECが参加)の定期的開催に加え,関係国と以下のごとき個別会議が開かれ意見交換等が行われた。
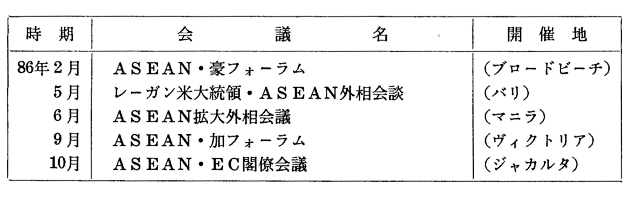
(ハ) 我が国との関係
近時困難な経済試練に直面するASEAN諸国は,域内協力を含む自助努力を通じて問題の克服に努めている。我が国としてもかかるASEAN側の努力に対し,出来る限り協力して行くこととしている。
86年6月マニラで開催されたASEAN拡大外相会議の際に安倍外務大臣(当時)は,我が国の対アジア政策につき演説を行い,(i)平和国家としての日本の貢献,(ii)間断なき対話と,心と心のふれ合いを通ずる相互理解の促進,及びこれによる相互信頼の確立,(iii)変動する情勢に効果的に対応するASEANと日本の協力関係の確立,を三本柱とする我が国の施策を発表し,ASEAN側から高い評価を得た。
さらに12月に開催されたASEAN貿易投資観光促進センターの理事会において,同センターの設立協定が87年5月よりさらに5年間延長されることとなり,また常設展示場の池袋より銀座への移転が決定され,これを機会に活動の強化が図られている。