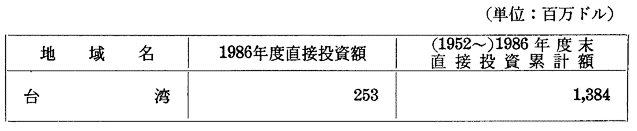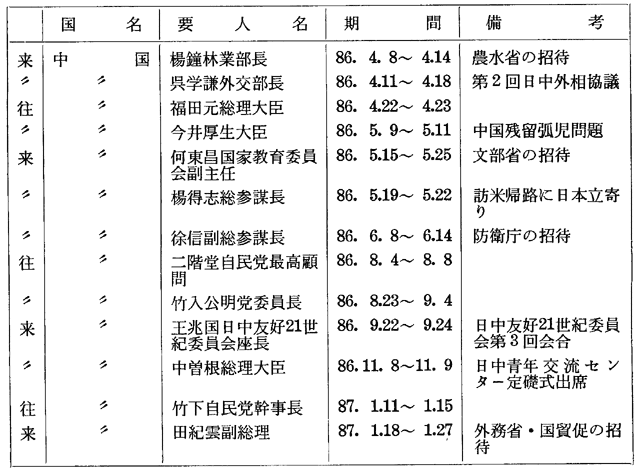
2. 中国
中国は近代化建設を最優先課題として対外開放政策及び経済体制改革を積極的に推進しており,第6次5カ年計画を超過達成した後86年からは,第7次5カ年計画(86~90年)に着手した。
隣国中国との間に良好で安定した関係を維持発展させることは,我が国外交の重要な柱の一つであり,日中両国の友好協力関係の発展は両国にとって重要であるばかりでなく,アジアひいては世界の平和と安定にとっても重要である。我が国はこのような観点から両国の友好協力関係発展のため努力するとともに,中国の近代化に向けての努力に対し,できるだけの協力をしている。
86年11月,中曽根総理大臣は日中青年交流センター定礎式出席のため訪中し,中国首脳との会見で,双方がさらに両国の友好協力関係を発展させていくことで認識の一致をみた。
87年1月,胡ヨウ邦総書記が辞任したが,中国指導部は胡辞任によっても日中関係を含む中国の対外,対内基本政策に変化はない旨表明している。
(1) 内外情勢
(イ) 内政
(a) 全般
87年1月の胡ヨウ邦総書記の辞任は,中国を指導する中国共産党のトップの突然の辞任であったため,注目をあびたが,中国首脳は現行の内政基本政策は不変であることを繰り返し強調している。
85年6月決定された兵員100万人削減は87年3月基本的に達成された。また,86年10月頃より「村」レベルでの整党が進められる中で,87年初より県・郷レベルの選挙が全国的に進められている。
(b) 胡ヨウ邦総書記の辞任
87年1月16日の中国共産党中央政治局拡大会議において,胡ヨウ邦総書記は,「党の集団指導原則に違反し,重大な政治原則の問題において誤りを犯した」として,総書記辞任を申し出,受け入れられた。
後任には趙紫陽総理が総書記代理を兼任することとなった。
辞任の直接のきっかけは86年末全国的規模に広がった「民主と自由」を要求する学生デモに対する指導上の誤りにあるとされ,87年初より「ブルジョア自由化」反対闘争が開始された。
(c) 政治体制改革
経済体制改革の進展を阻害する官僚主義や仕事の非能率等の要因を除去すること,即ち,政治体制改革の必要性が6月より指摘され,折から「百花斉放,百家争鳴」方針の30周年にあたっていたこともあり,各方面からの発言が相次いだ。しかし86年末になって,政治体制改革は複雑で影響する範囲が広く,多くの人々の利害関係にもかかわる問題であるので,慎重に進めるべきであるとされ,1年程度の調査研究を経て草案をとりまとめることとなった。
(d) 精神文明建設
86年9月28日開催された党第12期中央委員会第6回全体会議において,「社会主義精神文明建設の指導方針に関する決議」が採択された。精神文明の建設は,経済体制改革,政治体制改革とともに,現行基本政策である経済建設を支える3つの柱の1つとされている。
(e) 全国人民代表大会
第6期全人代第5回全体会議が87年3月25日より4月11日まで開催され,趙紫陽総理の政府活動報告等が採択された。
(ロ) 外交
(a) 全般
中国はいわば全方位外交ともいうべき活発な外交活動を展開しているが,86年には特に対欧州関係の進展が注目され,また対ソ関係にも新たな動きがみられた。87年1月の胡ヨウ邦総書記辞任後,中国首脳は従来の対外開放政策,外交政策に変化がない旨繰り返し強調している。
(b) 対ソ関係
ゴルバチョフ書記長は7月のウラジオストック演説で中国側が提起している「三つの障害」につき一応前向きな姿勢を見せたところ,9月トウ小平主任は同演説に対し「新しい,積極的な点がある」と評する一方,同演説が「歩み出した一歩は大きくない」と述べ,また,「三つの障害」の中でカンボディア問題が最重要であり,ソ連が越のカンボディア侵略を停止させ,カンボディアからの撤退問題で着実な一歩を踏み出すならば自ら訪ソしてもよいと述べた。10月第9回中ソ外務次官級協議(銭其シン―ロガチョフ)が開催され,「地域問題」についても話し合われた。9月のニューヨークにおける中ソ外相会談の合意をふまえて87年2月,9年ぶりに中ソ国境交渉がモスクワで再開された。
また,モスクワ(7月)と北京(12月)でそれぞれ経済貿易展が開かれ首相な三要人が参観した。86年の中ソ貿易は前年比37%増の26億米ドル(中国側発表)となった。
(c) 対米関係
米中関係は全般的に順調に進展している中で,5月楊得志総参謀長,10月洪学智総後勤部長が訪米,同月ワインバーガー国防長官が訪中し,11月米海軍艦艇が新中国成立以来はじめて中国(青島)を訪問するなど軍事面での交流が目立った。また5月ベーカー財務長官が訪中,姚依林副総理が訪米し,87年3月シュルツ国務長官が3年ぶりに訪中した。86年の米中貿易は73億米ドルとなった。
(d) 対東欧関係
86年5月と87年3月に呉学謙外交部長は東欧5か国を歴訪し,東欧諸国からも9月から11月にかけて,ハンガリー,チェコ,ブルガリア,ポーランドの副首相が訪中した。さらに9月ヤルゼルスキ・ポーランド議長兼書記長,10月ホーネッカー東独議長兼書記長が相次いで訪中し,中国と東欧との関係は一挙に最高首脳レベルに格上げされた。東独議長訪中時に表明された「三つの尊重」(自国の国情に基づく社会主義建設,対外政策及び対中関係発展のための具体的段取りの3点を十分尊重)は東欧諸国に対する根本方針であることが強調された。
(e) 対西欧関係
呉学謙外交部長は86年5月と87年3月に西欧11か国を歴訪し,86年6月胡ヨウ邦総書記が英,西独,フランス,イタリアを,7月趙紫陽総理がギリシア,スペインをそれぞれ訪問し,10月エリザベス英女王,クラクシ・イタリア首相が訪中するなど精力的な対西欧外交が展開された。また,87年3月マカオ問題に関する中国・ポルトガル間の共同宣言が仮署名された。
(f) 対アジア関係
(i) 北朝鮮との関係では,6月北朝鮮の提案した軍事三者会談,朝鮮半島非核地帯構想に中国は直らに支持を表明し,7月中朝友好協力相互援助条約調印25周年を記念して中国の田紀雲副総理と北朝鮮の李鐘玉副主席の相互訪問が行われ,10月李先念主席が訪朝した。
韓国との関係では,9-10月のソウルにおけるアジア競技大会に中国は500人以上の大代表団(団長は国家体育運動委員会副主任)を直行便で送り込んだ。
(ii) モンゴルとの関係では8月劉述卿外交部副部長が中国の副部長としては22年ぶりにモンゴルを訪問し,また夏期モンゴルに航空機による北京―ウランバートル間路線が復活した。
(iii) 東南アジア関係では,田紀雲副総理(10月),楊得志総参謀長(87年1月),呉学謙外交部長(4月)の訪タイ,ワチラロンコン皇太子の訪中(2月)などタイとの交流が特に頻繁であった。インドシナとの関係では,9月在越中国大使が越の独立記念日に8年ぶりに参加したのに対し,越外相が在越中国大使の国慶節レセプションに出席し,まだ劉述卿外交部副部長が79年の関係悪化以来中国の政府高官として初めてラオスを訪問するなどの動きはあったが,関係正常化に向けての特段の進展はみられなかった。
(iv) インドとの関係では7~8月東部国境沿いのスムドロング渓谷の中国軍駐留をめぐって非難の応酬があり,この間7月に第7回中印国境交渉が開かれたが実質的進展はみられなかった模様である。またインドが87年2月中印国境沿いの係争地域にアルナチャル・プラデシュ州の正式設置を発表したことにつき中国は「中国の領土主権に対するゆゆしい侵犯である」と非難した。
(g) 対中南米関係
アルバ・ペルー首相(6月),オルテガ・ニカラグア大統領(9月),デラマドリ・メキシコ大統領(12月)が訪中し,87年2月べーリーズと外交関係を樹立し4月同国首相が訪中した。
(h) 対アフリカ関係
アフリカ諸国からはギニア首相(4月),カボヴェルデ首相(5月),マリ大統領(6月),ベナン大統領(12月),ジンバブエ首相(87年1月),ガボン大統領(2月),タンザニア大統領(3月)が相次いで訪中し,9月中国から李鵬副総理がアフリカ4か国を歴訪した。
(ハ) 経済情勢
(a) 86年の中国経済は「過熱」から「停滞」への大きな振れを余儀なくされた85年に比べ概して良好な状況で推移したと言うことが出来よう。
まず,工業生産においては85年における計画外基本建設の停止,金融引き締めなど一連の引き締め策により,年の前半伸び悩んだもののその後は引き締め策の手直しにより年央以降再び生産の伸びを速め年間では計画伸び率(8%)を上回った。また,農業面でも85年には,5年振りで減産となった穀物生産が増産に転じ,郷鎮(町村)企業の発展でもその生産額が初めて農業生産額を上回るなど見るべきものがあった。
また,副食品価格自由化などにより触発された前年の小売物価上昇(全国で8.8%,都市部では2けたの上昇率)も6%程度に落ち着いた。対外経済面では85年の大幅な輸入増が抑制されると同時に輸出面では大宗品目たる原油価格の下落にもかかわらず,非原油製品等が好調な伸びを示した結果,貿易赤字も若干改善,その拡大傾向に歯止めがかかったほか,外資導入面でも新規契約面では減退したものの投資実績では前年より増大するなど,86年の経済パーフォーマンスは比較的良好であったと言える。
しかし他方において国家財政収支が再び赤字に転じたこと,84年以来の貿易赤字に伴なう外貨不足の深刻化及び経済効率の低下などの問題は今後解決すべき課題として87年に持ちこされた。
(b) 86年の経済実績は,国民総生産額で9,380億元(2,717億米ドル)と前年比7.8%増(一人当たり国民総生産は885元(256米ドル)),うち,農業生産額が,3,947億元と前年比3.5%増(穀物生産高では3億91百万屯と同じく12百万屯増),工業総生産額が1兆1,157億元と同11.1%増(村営工業を除くと9.2%増)と順調な伸びを示した。
(c) 固定資産投資(全民所有制単位)は1,938億元,うち基本建設投資が1,152億元,前年比7.3%増と前年の投資過熱状況(85年は同44.6%増)はかなり鎮静化された。社会商品小売総額は4,950億元と同15%増(物価上昇分を調整した実質の伸びは8.5%増)。
(d) 貿易総額は通関統計によると738億米ドルと前年比6.1%増。うち輸出は309億米ドル,同13.1%増,輸入は429億米ドル,同1.6%増で輸出入バランスは120億米ドルの入超となったが他方,貿易外収支では56億1千万ドルの黒字(9.9%増)となった。
外資利用実績は69億90百万米ドル(借款及び直接投資)前年比,56.6%増となった。
(e) 国民の生活水準については農民1人当りの純収入が424元(123米ドル),勤労者の平均賃金は1,332元(386米ドル)とそれぞれ前年比実質で3.2%,8.4%の上昇となった。また,都市住民の可処分所得は828元(240米ドル)と実質13%増となった。
(f) 人口は86年末で10億60百万余,前年に比し1,476万人増(自然増加率1,408%)となった(以上国家統計局公表数字)。
(g) 経済体制改革面では,86年は引き続き工業部門の改革に重点が置かれ,工場長責任制の確立(現在国営企業の40%で実施)及び企業破産法制定などによる企業自主権の強化を通じる企業の活力増強・体質改善が進められた。また,マクロ経済調節手段としての金融体制改革もコール市場,短期債券市場の形成,銀行の企業化等試験的な段階ながら前進がみられた。さらに労働雇用面でも労働契約制を進める(86年末の契約労働者518万人)など経済改革も86年後半にはかなり活発な動きがみられた。
(h) 87年1月の胡ヨウ邦総書記の辞任による経済面に対する影響について中国側の公式態度は改革・開放政策には何等変更なしとするものであるが,87年3月に開催された全人代での政府活動報告で「経済体制の改革を断固として全面的に推進すべきである。国民経済の長期安定的な成長には,改革の推進と対外開放の拡大にも依拠しなければならない」とする一方で「経済体制全般の改革をもっと効果的に推進するため,ここ数年来の改革の経験を総括する。」とも述べられていることは今後改革がより慎重に進められるとも推測される。
(2) 我が国と中国との関係
(イ) 全般
86年には,呉学謙外交部長の訪日による第2回日中外相協議(4月),中曽根総理大臣の訪中(11月)等日中間の要人往来は前年に引き続き活発に行われたが,これは日中関係の深さと広がりを物語るものである。具体的には,右以外に,日本側からは,福田元総理大臣(4月),今井厚生大臣(5月),二階堂自民党最高顧問(8月),竹入公明党委員長(8月),竹下自民党幹事長(87年1月)等が訪中し,中国側からも,楊鐘林業部長(4月),徐信副総参謀長(6月),田紀雲副総理(87年1月)等が来日した。
特に,11月,我が国の無償資金協力により建設されている日中青年交流センターの定礎式出席のため2年半振りに訪中した中曽根総理大臣は中国首脳と会談し,中国の内外政策,日中関係等につき意見交換を行い,日中友好関係の一層の発展のため大きな成果を収めた。中曽根総理大臣は中国側指導者との間で良好で安定した日中関係が,日中両国のみならず,アジアひいては世界の平和と安定に寄与するものであり,両国が互いの国民感情を尊重しつつ友好協力関係を一層強固なものにしていかねばならないとの決意を再確認した。また,中曽根総理大臣は,87年より5年間を目処に新たに500名の中国青年を我が国に招待する「日中青年の友情計画」を発表した。
日中関係を21世紀に向けて安定的に発展させていくための方途を探ることを目的として発足した日中友好21世紀委員会は,9月に東京及び大磯で第3回会合を開催し,過去2回の会合で培ってきた双方委員の間の相互理解と相互信頼をさらに増進するとともに,長期安定的な日中関係発展のため活発かつ忌憚のない意見交換を行った。
このように,86年の日中関係は基本的に良好な発展の途をたどったが,他方,6月の教科書検定及び87年2月の光華寮判決については中国側より批判が寄せられた。これらの問題に関する我が国政府の一貫した立場は,我が国として日中共同声明,及び日中平和友好条約を今後とも遵守していくことにいささかの変わりもないということであり,様々の場でその旨中国側に説明している。
また,経済面では日中経済関係の目覚しい発展に伴ない貿易インバランスも顕著となり我が国の対中黒字幅は前年(60億米ドル)より減少したとは言え,86年で42億米ドルの日本側出超となった。
(ロ) 日中経済関係
(a) 86年の日中貿易は,往復約155億米ドル(対前年比約18%減)となった。貿易収支は引き続き我が国の出超(約42億米ドル)となったが,これは,85年急速に拡大した自動車,テレビ等に対する中国側の輸入抑制及び繊維製品,食糧品の対日輸出増大にもかかわらず,中国側の大宗輸出品目たる原油(85年には中国の対日輸出総額の34%を占める)の価格が急落したためである。
(b) 政府ベースの資金協力としては,84年度以降の新規円借款について,84年3月の中曽根総理大臣訪中時に協力を表明した鉄道,港湾,通信,水力発電の7プロジェクトに対し協力中で(84~90年の7年間に4,700億円を目途),このうち86年度分として806億円を限度とする額の供与に関する内容の交換公文が86年5月に署名された。
無償資金協力については,86年度協力分として,「日中青年交流センター建設計画(国債1期)」,「肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画」,「長春市浄水場整備計画」,「中日友好病院機材整備計画」「北京蔬菜研究センター機材整備計画」など中国の経済発展に寄与するプロジェクトに対し,合計約69億円を限度とする額の供与を実施することとした。
(c) 国際協力事業団(JICA)を実施機関とする政府ベースの技術協力としては,運輸交通,経営管理,農林業,保健医療をはじめとする広範囲の分野で研修員の受入れ,専門家の派遣,機材供与などを実施したほか,プロジェクト方式技術協力については,「中日友好病院」や「企業管理研修センター」などをはじめとして11件について協力中である。また,85年10月に署名された取極に従って86年12月に4名,87年3月に4名の青年海外協力隊が中国に派遣された。また,運輸交通,地域開発,エネルギー,農業開発,港湾開発,鉱物資源開発や工場近代化など幅広い分野を対象とする各種の開発調査協力が行われている。
(d) 日本輸出入銀行の第1次石油・石炭開発金融(総計4,200億円)については,これまでに3,508億円の融資契約が調印されている。84年12月には第2次融資として,石炭2プロジェクト,石油4プロジェクトに対し,5,800億円を限度として供与する内容の覚書が調印され,これまでに1,446億円の融資契約が調印されている。
(ハ) 人的往来と文化交流
日中間の人的往来は,72年(日中国交正常化当時)約9,000名であったが,86年には40万9,576名となった。この間両国閣僚レベルの往来も頻繁となり,86年11月には中曽根総理大臣が日中青年交流センター定礎式出席のため訪中している。86年度の要人の往来は下表のとおりである。
両国間の文化交流は,民間及び地方自治体ベースで盛んに行われているが,両国政府でも79年12月に締結された文化交流協定等に基づき順調に発展している。具体的には,我が国政府は青少年交流,中国人留学生の受入れ,中国の日本語教育に対する援助及び文化無償資金供与(11件,累計5億1,850万円)等の分野で協力している。また,86年11月中曽根総理大臣訪中の際,総理より87年度から向う5年間に毎年100名の中国青年を招聘することを表明している。
(ニ) 日中友好会館の建設
日中国交正常化10周年の記念事業として,我が国の政・財界及び関係団体を中心に,中国からの留学生・研修生等のための宿舎及び日中文化交流のための各種施設から成る「日中友好会館」を東京に建設する計画が策定された。この計画は,82年9月に政府首脳レベルで両国政府の建設支援が合意され,我が国政府は,建設関係費として83年度6,975万円,84年度6億9,750万円,85年度7億5,000万円,86年度4億8,275万円,累計で20億円の補助を行っている。現在既に会館のA棟(学生寮及び語学学校)が完成済み(85年3月)であり,残るB棟(各種文化交流施設ほか)については88年1月末迄に完工予定である。
(ホ) 中国残留日本人孤児問題
(a) 80年度から開始した孤児の訪日肉親調査は86年度を以っておおむね終了し,15回にわたり実施した右調査には計1,488名が参加,このうち553名の身元が判明した。
(b) 孤児が本邦へ永住帰国した後も中国へ留まる養父母等に対する扶養費について,86年5月,日中両国政府間で口上書を交換し,日本政府等が孤児に代わり,永住帰国した孤児1人当たりにつき,月額60元を15年間分,一括して支払うことが確認され,右送金が開始された。
<要人往来>
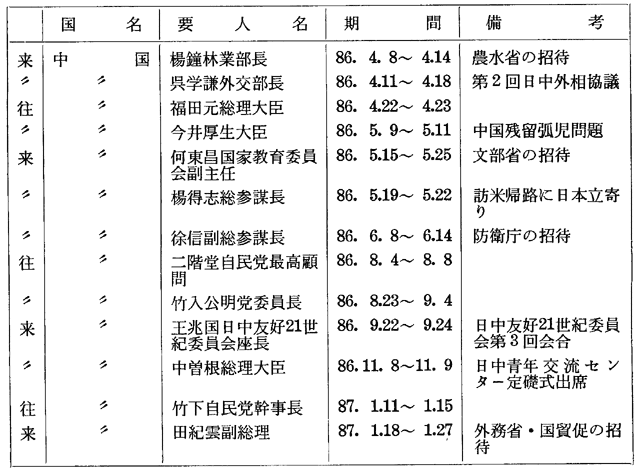
<貿易関係>
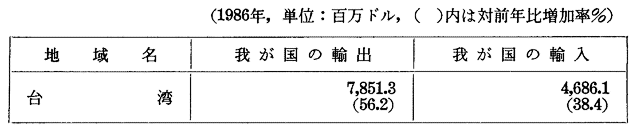
<民間投資>