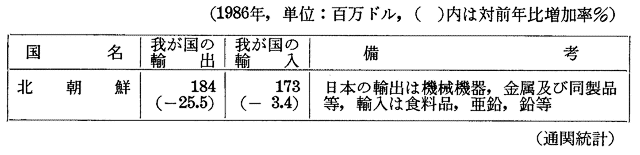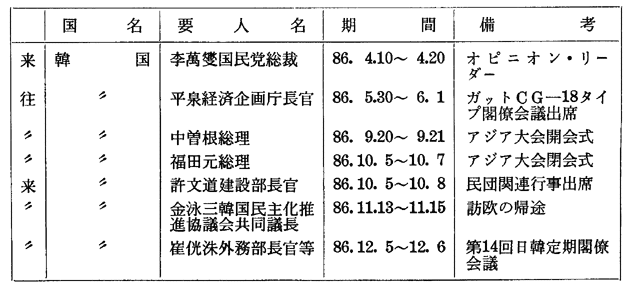
第3章 各国の情勢及び我が国との関係
第1節 アジア地域
86年のアジア地域の政治情勢は,国際関係においてはインドシナ半島での地域紛争の継続,朝鮮半島での南北対話の中断等の要素を内包しつつも,全体としては平穏裡に推移した。各国の内政面では,総じて安定を保ち,また,フィリピンにおけるアキノ新政権の成立が関心を集めた。
経済面では,中国は,近代化建設を最優先課題として引き続き対外開放政策及び経済体制改革を積極的に推進した。韓国をはじめとする新興工業国・地域(NICs)は,円高,石油価格低下,国際的低金利傾向等の恩恵を享受しておおむね順調な経済運営を行った。南西アジア経済も総じて堅調に推移した。他方,多くの東南アジア諸国では,近年の世界経済の低迷,石油・一次産品価格の低下等による経済困難から未だ本格的に脱するに至っていない。
1. 朝鮮半島
朝鮮半島の平和と安定は,我が国の安全と東アジアの安定にとって重要である。我が国としては,朝鮮半島の緊張緩和及び永続的平和の実現を強く希望しており,かかる観点より86年1月,北朝鮮側が一方的に中断した南北対話再開と88年のソウル・オリンピック成功のための環境造りに貢献すべく努力した。
我が国は,韓国との友好協力関係を引き続き重視している。
両国首脳の相互訪問の実現によって日韓関係には新たな章が開かれたが,その後も累次の外相会談,閣僚会議,各種実務者協議を通じ,あらゆるレベルにおける両国間の間断なき対話を維持しつつ,その成果をさらに発展させていくべく努めてきた。86年秋には,中曽根総理大臣がアジア大会出席のため訪韓したが,右訪問を通じ両国関係が盤石であることが明らかとなった。
北朝鮮との間には外交関係はないが,今後とも経済・文化等の分野における民間レベルの交流を積み重ねていく方針である。
(1) 韓国の情勢
(イ) 内政
(a) 86年は韓国政治の最大の懸案である憲法改正問題をめぐる与野党間の対立が先鋭化した。
86年4月に全斗煥大統領が自分の任期中(88年2月24日まで)の改憲に応ずる姿勢を示したことを契機に6月には国会に憲法改正特別委員会が設置された。
8月には与党(民正党)は議院内閣制,野党(新民党及び国民党)は大統領直選制による大統領中心制の改憲案を国会に提出した。
しかし,与野党の対立のため改憲特別委員会の審議が行われず,新民党は与野党の改憲案を直接国民投票にかけることを主張した。民正党は憲法違反としてこれを拒否したが,民正党も単独では国会在籍議員の3分の2に達しないため改憲を強行できなかった。
昨年末,李敏雨(イ・ミンウ)新民党総裁が民主化措置がとられることを条件に議院内閣制案を肯定的に検討すると発言したことから新民党は改憲路線をめぐって紛糾した。本年4月8日あくまでも大統領直選制をめざす金泳三(キム・ヨンサム),金大中(キム・デジュン)氏系議員が大量に新民党を脱党し,統一民主党を創ることになった。
新民党の分裂により話合いによる改憲が不可能と判断した与党は改憲を断念し,全斗煥大統領は4月13日,現行大統領間接選挙により政権移譲を行うことを発表した。
(b) 学生・反体制人の動き
86年も春頃より各大学で学生デモが断続的に発生したが,学生デモが左傾化,過激化の傾向を強めたため一般学生や市民の支持は得られず,量的拡大はみられなかった。
一方,在野の反政府団体も86年前半は新民党と協力して大統領直選制への改憲を求める運動を展開したが,後半には政府当局が反政府団体に対し解散措置をとったため全体としてまとまった動きができなかった。
本年1月に学生運動関連で取調べ中のソウル大生が警察官の拷問により死亡する事件が発生し,2月から3月にかけて全国的に追悼デモが行われたが,政府当局の厳しい規制もあり,それ以上には発展しなかった。
(ロ) 外交
(a) 首脳外交等
86年4月に全斗煥大統領が英国,西独,フランス,ベルギーを訪問し,87年1月に盧信永首相がオランダ,スペイン,ポルトガル,イタリー,デンマークを訪問した。
これら西欧訪問は,従来日米に偏りがちであった韓国外交の幅を広げることを目的としたものであり,各国首脳との間では,ソウル・オリンピック問題,国連加盟問題についての韓国の立場を支持することが確認された。
86年5月には英国首相,カナダ首相,6月にはシンガポール首相,中央アフリカ共和国大統領が訪韓した。9月には中曽根総理が訪韓し,アジア大会開会式に出席するとともに全斗煥大統領と会談した。
(b) 対米関係
86年の米韓関係は米国よりの市場開放要求が最大の懸案となっており,両国間で協議が行われた。また韓国の国内政局に関しては米国は与野党間の対話と妥協を求めるとの姿勢を保っており,シュルツ国務長官が86年5月及び87年3月に訪韓した。
(c) 社会主義諸国との関係
86年にはスポーツ分野を通じて中国,ソ連,東欧諸国との交流が促進された。
4月には各国国内オリンピック委員会総会がソウルで行われ,中国,ソ連,東欧諸国(アルバニアを除く)を含む152カ国が参加し,このうちソ連はスポーツ大臣,中国は体育委副主任を派遣し,88年のソウル・オリンピックヘの参加問題との関連で注目された。
また,9月にソウルで行われたアジア大会には中国は515名(うち選手385名)の代表団を北京より直行便で派遣し,単にスポーツ分野だけにとどまらない韓中関係発展への期待をもたせた。
(ハ) 経済
86年の韓国経済は,原油価格の低下,円高・ウォン安,国際的な金利の低下という国際経済環境の好転により,輸出が大幅な増加をみせたため,12.5%という77年以来の高成長を遂げた。
輸出は繊維,電子機器,機械類を中心に前年比14.7%増の347億ドルとなり,他方輸入は原油価格の低下を反映して同1.1%増の314億ドルに止ったため,貿易収支は建国史上初めて黒字に転換した。また,経常収支も47億ドルの黒字となったため,過去増加を続けていた対外債務も22億ドル減少し444億ドルの残高となった。
物価は引き続き安定しており,雇用情勢も若干改善した。
(2) 北朝鮮の情勢
(イ) 内政
金日成主席の指導体制が堅持される一方,子息金正日労働党政治局常務委員・秘書への後継体制の定着ぶりを示す報道がみられ,金日成主席は,5月革命偉業の継承問題が満足に解決された旨述べた。
11月に最高人民会議第8期代議員選挙,ついで12月最高人民会議第8期第1回会議が開催され,国家主席,国家指導機関の選出が行われたが,政務院総理の交替,経済部署の人事異動が行われたのみで,最高指導体制に変化はみられなかった。また,12月党中央委員会第6期第12回総会での人事措置も小幅のものにとどまった。(なお,11月には一時金日成主席死亡説が西側に流れ,北朝鮮内部の権力闘争がとりざたされたが,上述の人事移動はこれを否定する形となった。)
(ロ) 外交
86年も対非同盟諸国,対中・ソ外交を積極的に展開した。
金永南副総理兼外交部長ら政府・党要人が非同盟諸国を訪問し,第8回非同盟諸国首脳会議に朴成哲副主席が出席したほか,東欧諸国の要人を中心とする招待外交を展開した。
対中・ソ関係では,ソ連との関係が軍事面を中心にかなり進んだとみられているが,基本的には依然として中ソ両国との間でバランスを維持するとの政策の大わくを出ることはないと考えられる。ソ連とは,2月の姜成山総理の訪ソ,7月のソロビヨフ政治局員候補の訪朝と金渙政治局員の訪ソ,10月の金日成主席の訪ソ等のほか,各レベルの人事往来が活発に行われ,軍事面での交流もみられる等関係強化が進んだ。中国とは,7月の李鐘玉副主席の訪中,田紀雲副総理の訪朝,10月の李先念国家主席の訪朝等が行われたほか,9月に瀋陽に北朝鮮の総領事館が開設されるなど引き続き緊密な関係が維持された。
(ハ) 経済
人民経済発展第2次7ケ年計画は1984年に終了したが,引き続く85年,86年は「調整の年」として経済計画空白の年となった。その間,86年4月に発表された86年度予算の伸び率が過去最低の4.2%にとどまるなど北朝鮮経済の停滞がうかがわれたため,87年より開始されるべき第3次7ケ年計画の内容が注目されたが,86年12月の最高人民会議第8会期第1回会議における同計画の採択は見送られた。
(3) 南北関係
(イ) 南北対話
84年秋以来断続的に行われて来た南北間の対話(赤十字本会談,経済会談,国会会談予備接触)は,86年1月チームスピリットを理由に北朝鮮側が中断を通告して以来中断されたまま(IOC仲介のスポーツ会談のみ開催)となり,対話の再開をめぐり双方が提案の応酬をするという展開となった。北朝鮮は,北・韓・国連軍による軍事当局者会談を提案(6月)し,年末よりは高位級政治・軍事会談を引き続き提案するなど,軍事問題に比重を置いたアプローチを行う一方,韓国は,中断中の会談の再開及び金剛山ダムをめぐる水資源会談の開催を提案し,その成果如何では総理会談を行うとの立場であり,双方の主張には差異がみられた。
なお,88年オリンピックの開催をめぐる第3回スポーツ会談(6月)において,IOCは,4種目(うち2種目は決勝まで)の北朝鮮開催案を提示したが,これに対する北朝鮮側の立場は必ずしも明白でない。
(ロ) 軍事情勢
大規模な軍事力が非武装地帯を挾んで対峙している朝鮮半島においては,基本的に緊張状態が続いているが,銃撃事件(8月),金日成死亡説(11月)等の事案が発生したにもかかわらず,概して平穏であった。
この間,北朝鮮は装備の機械化・近代化等により軍事力の強化を図っていると思われ,特にソ連との軍事的接近の動きが注目された。これに対し,韓国は自主国防力の強化及び米韓相互防衛体制の堅持という方針のもとに,米国の支援を得て韓国防衛のための全体的継戦能力を強化した。
一方,朝鮮半島における南北双方の信頼醸成のため,米韓両国はチームスピリット87の実施に際し,例年と同様北朝鮮側に演習の事前通報及び参観招請を行った。他方,北朝鮮は同半島の緊張緩和のためとして軍事三者会談(6月),高位級政治・軍事会談(87年1月)等の提案を行っており,今後の双方の対応が注目されている。
(4) 我が国と韓国との関係
(イ) 概観
(a) 65年の国交正常化以来日韓関係は着実な発展をみせ,ますます良好かつ密接なものとなっており,両国間で広範な分野にわたって交流と協力が行われている。
84年の全大統領の歴史的訪日の成果の延長上に,累次にわたる外相会談及び閣僚会談が行われ,高いレベルでの間断なき対話が維持されたほか,各種の政府間実務者協議を通じて,在日韓国人待遇問題,貿易不均衡問題,漁業問題等両国間の諸問題につき突込んだ意見交換が行われた。
最近では,86年夏の第二次教科書問題,藤尾前文部大臣発言問題など,日韓関係に悪影響を及ぼす事件が起ったが,同年秋の中曽根総理のアジア大会(於ソウル)出席により,日韓友好協力関係は,今は揺ぎない程成熟していることが明らかとなった。
(b) 中曽根総理大臣のアジア大会出席
中曽根総理大臣は,全斗煥大統領よりの招請を受け,アジア大会の開会式出席のため86年9月20~21日,ソウルを訪問した。
今次訪韓の目的は,88年のソウル・オリンピック及びその前哨戦としてのアジア大会への協力の一環として,同大会の成功裡の開催に祝意を表するとともに,最大限の支援を行うというものであったが,かかる目的は十分に達せられ,このことにより両国の親善の実が挙げられたことは大きな成果であった。
また,総理訪韓直前には,日韓関係に悪影響を及ぼしかねない事態が生じたが,今次訪韓を通じて日韓友好協力関係は不変であり,盤石であることが確認された。
(c) 日韓定期閣僚会議
第14回日韓定期閣僚会議が86年12月5~6日,東京で開催された。
この会議においては,朝鮮半島情勢につき集中的な討議が行われ,同半島の情勢が厳しく,緊張緩和が必要であるとの点で双方の基本的認識が一致したほか,日韓関係の幅広い分野において将来にわたる建設的な関係を構築するために,88年を目途に「賢人会議(仮称)」を設置する方向で合意をみた。
(ロ) 在日韓国人の待遇問題
在日韓国人の待遇問題については,86年8月に東京において「在日韓国人の待遇に関する実務者協議」が開催された。また,87年3月にはソウルにおいて「在日韓国人子孫の日本での居住に関する日韓会議」が開催され,いわゆる三世以下の在日韓国人の問題につき事務レベルでの意見交換が行われた。
(ハ) 貿易
86年の日韓貿易は,日本の輸出が105億ドル,輸入が53億ドルと総額で前年比40%以上の大幅増を示した。また,対韓貿易黒字も大きく拡大したため,貿易不均衡問題が2国間の主要懸案としてより大きくクローズアップされることとなった。我が国は,86年11月の第19回日韓貿易会議,12月の第14回日韓定期閣僚会議の場等において,政府間協議を行った。
(ニ) 産業技術協力
日韓両国間では,民間企業間の技術提携,直接投資を通じ技術移転が行われているが,政府レベルにおいても我が国は経済協力の枠組の中で韓国に対する数々の技術協力を行っている。86年度の「韓国技術者研修計画」では139名の研修生の受入れを行い,また同年4月には韓国の中堅技術者の養成を目的とした「企業技術訓練院」の設立に協力することに合意した。
(ホ) 科学技術協力
日韓科学技術協力協定に基づき設置された日韓科学技術協力委員会の第1回会合が,86年8月4日,5日の両日ソウルにおいて開催され,その結果,新たに24のテーマを今後積極的に推進することで合意した。
(ヘ) 漁業問題
西日本及び山陰沖水域での韓国漁船の操業問題に関し,我が国は,機会あるごとに,韓国漁船による領海・漁業専管水域内での不法操業の根絶等を,韓国に強く働きかけてきたが,韓国漁船の違反操業は根絶されるに至っていない。87年3月末には第21回日韓漁業共同委員会が開催され,これ等の問題についても話合いが行われた。
また,北海道沖水域での韓国漁船操業問題については,83年11月から韓国側が実施してきた自主規制措置が86年10月末で期限切れを迎えることとなっていたので,同年7月下旬より5回にわたる実務者協議と2回の日韓水産庁長官・庁長会談を行い,本件を含む日韓漁業問題全般について話合いを行った。
しかし,日韓双方の見解の隔たりは大きく,同自主規制措置の期限切れまでに決着をつけることができなかった。このため,日韓両国は,済州島沖南西水域で日本側が,また,北海道沖で韓国側がそれぞれ自国漁船に対し行っている自主規制措置を最長1年を限度として暫定延長した。両国間ではその後も本件問題解決のための協議を続けている。
(ト) 大陸棚共同開発
大陸棚共同開発区域では,物理探査の結果を踏まえ,これまで7か所で試掘が実施されたが,いずれも商業化可能量の石油・天然ガスを発見するに至っていない。
(チ) 竹島問題
我が国は,韓国による竹島の不法占拠に対し,従来から繰り返し抗議しており,86年11月の海上保安庁巡視船の調査結果に基づき抗議を行ったほか,各種会議の機会にも,この問題を積極的に韓国側に提起している。
<要人往来>
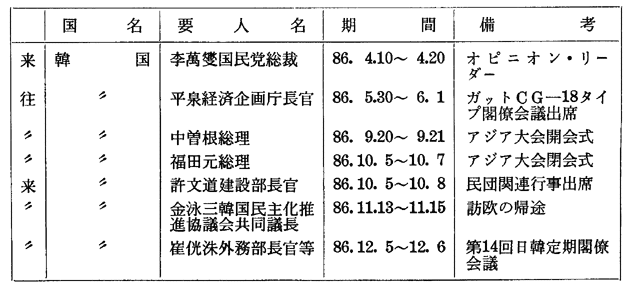
<貿易関係>
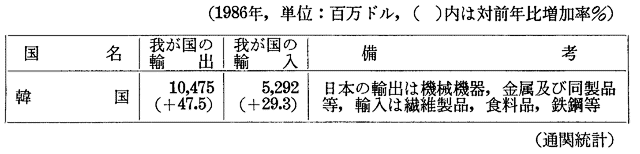
<民間投資>
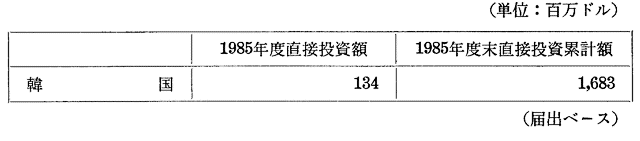
(5) 我が国と北朝鮮の関係
(イ) 概観
我が国と北朝鮮の間には外交関係はないが,貿易,経済,文化などの分野では民間交流が行われている。86年における主な動きは次の通りである。
(ロ) 漁業関係
北朝鮮周辺水域における我が国漁船の漁業活動については,日朝民間関係者間の民間漁業暫定合意が82年6月に失効し中断したが,84年10月15日に両国民間関係者の努力により従来とほぼ同様の合意が成立し操業が行われていた。しかし,同合意も86年12月31日に期限切れとなった。
右延長については,昨年後半より民間関係者が努力を続けているが,未だ合意が成立するに至っていない。
また,北朝鮮に拿捕された我が国漁船は,86年4月に1隻が釈放,送還され,現在,1隻もない。
(ハ) 人的交流
(a) 86年中の邦人の北朝鮮への渡航者数は,1,482名で,渡航目的は商用,親善交流等であった。
(b) 同期間中の北朝鮮人の入国者数は463名で,入国目的は商用,スポーツ等であった。
(c) 同期間中の在日朝鮮人に対する北朝鮮向け再入国許可数は5,042名で,その目的は親族訪問,学術・文化・スポーツ交流,商用等であった。
(ニ) 貿易
86年の日朝貿易は輸出入総額で3億5,700百万ドルとなり,前年比約16%減と大きく落ち込み,78年以来の低水準となった。
(ホ) ズ・ダン9082号事件
87年1月20日福井港に入港した北朝鮮船ズ・ダン9082号の乗員11名は,我が国政府による全員の意思確認の結果,2月7日台湾に向け出発した。政府としては,本件の処理にあたり,国際法,国際慣習にのっとり,人道的配慮及び本人達の自由意思を尊重するとの基本方針の下に,乗員達の安全,健康等に配慮しつつ,できる限り早い機会に同人達の希望に従い第三国に渡航できるよう最大限の努力を払った。一行はその後,台湾当局による意思確認を経た後,韓国に渡航した。
(イ) <要人往来>
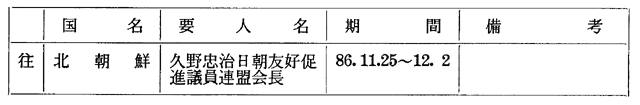
(ロ) <貿易関係>