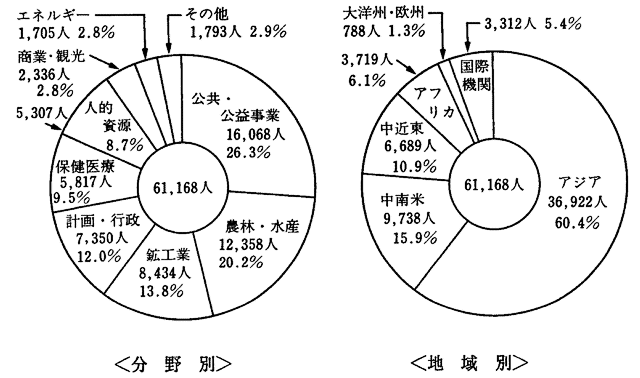
第2節 技術協力
1.概況
技術協力は,開発途上地域の経済・社会開発に必要な技術の移転を研修員受入れ,専門家派遣などを通じて行う経済協力の一形態であり,人と人との接触を通じて諸国民間の相互理解と親善が深められるという特色を持つ。
政府ベースの技術協力は,主に国際協力事業団(JICA)を通じて実施されており,同事業団は主として外務省の交付金により,条約その他の国際約束に基づく事業などを実施している。
85年におけるDACベースでの我が国の技術協力関係支出額(国際機関・民間を含む)は,5億4,900万ドル(1,309億円)に上り,対前年度比5.9%増となった。
我が国の技術協力実績をDACベースでの国際比較で見ると,84年の協力額(5億2,100万ドル)ではDAC加盟17か国中第4位であるがODA実績の割合では第15位であった。我が国としては,ODAの質的な改善を図るためにも,技術協力の質的充実に留意しつつ,今後とも量的拡充を重視していく必要がある。
2.国際協力事業団(JICA:JapanIntemationalCoope-ratoinAgeney)を通ずる政府ベースの協力
(1)研修員受入れ
研修員受入れ事業は,開発途上諸国の中堅技術者,行政官,研究者などを当該国政府または国際機関の要請に基づき,日本に受け入れて,我が国の進んだ技術を研修する機会を与える技術協力の最も基本的な形態である。
85年度中に新規に受け入れた研修員は,5,553名であった。これにより,我が国が54年以来政府ベースで受け入れた研修員は,合計6万1,168名に達した。
他方,JICAベース技術協力の一環として実施している第三国研修は,75年タイにおいて実施されて以来着実に拡大し,85年度には22件15か国(タイ,シンガポール,インドネシア,フィリピン,マレイシア,メキシコ,チリ,コス・タリカ,ペルー,ブラジル,エジプト,ケニア,象牙海岸,フィジー,及びパプア・ニューギニア)で実施されるに至った。第三国研修は,開発途上国が我が国の資金的,技術的協力を得て,当該国と自然的,社会的あるいは文化的環境を同じくする近隣諸国から研修員を招請し研修を実施するものであり,開発途上国間の技術協力を促進するとともに,より途上国の実情に即した研修を実施し得るという利点がある。
81年1月,鈴木内閣総理大臣がASEAN諸国を歴訪した際,「ASEAN人造りプロジェクト構想」との関連で提唱したJICAの附属機関としての「沖縄国際センター」は85年4月開館され,コンピューター,視聴覚技術等ASEAN向けの研修を主要な事業として実施している。
また,東京都内にての受入れ研修員の増加に対応すべく建設中であったJICAの「東京国際研修センター」も85年6月に開館された。
研修員受入れ(JICAベース,1954~85年度末累計実績)
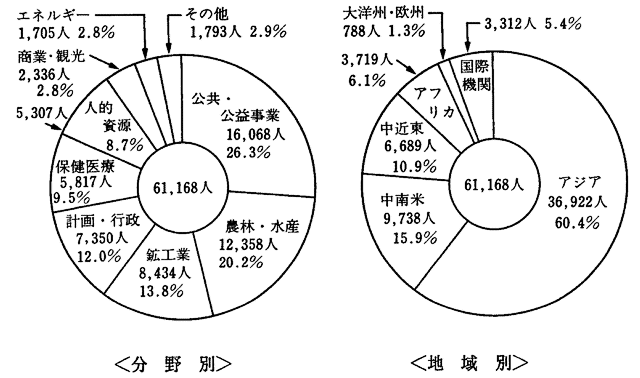
(2)専門家派遣
開発途上国の政府,政府関係機関,試験研究機関などにおける企画立案,調査研究,指導,普及活動,助言などの業務の実施を目的として専門家を派遣する専門家派遣事業は,研修員受入れ事業と並ぶ最も基本的な技術協力の形態である。
85年度中にJICAを通じて新規に派遣した専門家は,計6,842名であった。これによって,我が国が開発途上諸国への専門家派遣を開始した54年以来の総計は6万1,967名に達した。
また,技術協力の根幹をなすとも言える技術協力専門家の養成確保及びこれら専門家の現地活動の強化を図るため,JICAの機関として,83年10月に国際協力総合研修所を設立し,85年度においては,約1,525名の専門家
専門家派遣(調査団を含む)(JlCAベース,1954~85年度末累計実績)
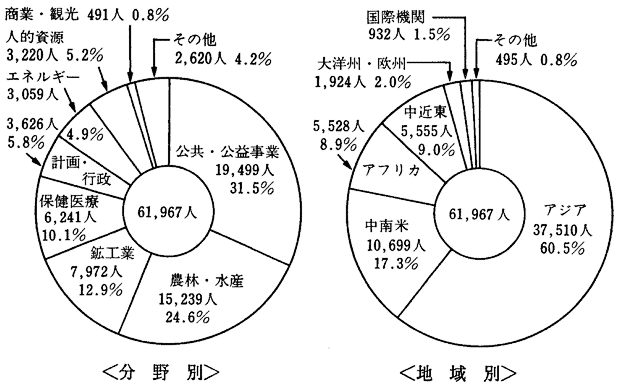
等に対し派遣前及び中期研修等を行い,26名の国際協力専門員(ライフワーク専門家)を確保した。
(3)機材供与
機材供与事業は,派遣専門家,帰国研修員,青年海外協力隊員が技術の指導,普及,移転を行うに当たり必要とされる機材を開発途上国の要請に基づき供与する事業である。なお,この事業は,後述のプロジェクト方式技術協力に伴う機材供与とは別のものであり,通常「単独機材供与」と呼ばれている。
85年度に供与した機材は,約束額ベースで13億9,800万円であった。84年度までの累計総額は,支出純額ベースで108億8,835万円であり,地域配分は,アジア・大洋州50.0%,中近東11.3%,アフリカ13.4%,中南米24.0%,その他1.3%となっている。
(4)開発調査
JICAによる開発調査は,開発途上国などの要請を受けて,当該国の経済,社会開発上有効と認められる公共的な開発計画に関して実施されるもので,フィージビリティ調査,マスタープラン調査,各種資源調査,地形図作成,地下水開発調査等の総称である。85年度は,203億円の予算規模(外務省予算及び通商産業省予算)をもって,225件にのぼる調査を行った(複数国にまたがるもの等を除く)。地域別にみると,アジア54%(うちASEAN40%),中近東12%,アフリカ9%,中南米24%,大洋州1%であり,分野プロジェクト方式技術協力とは,専門家の派遣,研修員の受入れ及び機材供与の3要素を効率的・有機的に組み合わせた総合的な技術協力である。本協力は,必要に応じ資金協力との連携も図りつつ,通常,活動の拠点となるセンタ、研究所などにおいて下記の分野における人造り協力(専門技術者等の養成)を行い,もって開発途上国に対する技術の移転・定着を図っている。
現在ASEAN5か国に対し協力中の「ASEAN人造りプロジェクト」は,本方式による代表的な技術協力の例である。
プロジェクト方式技術協力は,以下のとおり5事業に区分される。
(イ)センター協力
開発途上国の技術訓練センター等を拠点として,各種技術分野における人材の養成・訓練を行う。協力内容は,一般的な職業訓練とインフラ,鉱工業分野での技能者養成及び研究開発プロジェクトに大別される。
85年度には,59億4,000万円の予算規模をもって,19か国39件(ASEAN人造りプロジェクト5件を含む)の協力を行った。
(ロ)保健医療協力
開発途上国国民の健康の維持増進を図り,社会福祉の向上に寄与することを目的として,途上国で必要とされる医師,看護婦など保健医療部門の人材養成訓練を行う。協力内容は,基礎・臨床医学の研究,特定疾病の抑制対策,地域保健対策に大別される。
85年度には,41億3,400万円の予算規模をもって,26か国32件の協力を行った。
また,82年3月に発足した国際緊急医療体制により,84年12月から86年3月までの間にエティオピア飢餓被災民救済,メキシコ地震,コロンビア火山噴火及びペルー洪水に対し救急医療チームを派遣した。
(ハ)人口・家族計画協力
家族計画の広報普及活動,視聴覚教育活動,普及員の養成などを通じ,開発途上国の人口問題に寄与しようとするものである。
85年度においては,8億2,900万円の予算規模をもって人口増加に悩むアジアの5か国及び中米1か国を対象に協力を行った。
(ニ)農林業協力
開発途上国の産業構造の中で農業の占める比重は極めて高く,農林業開発への協力は,開発途上国の経済・社会開発上の最重要施策となっている。
本分野の協力は農業生産性向上のための技術の移転・普及に重点を置いて実施しており,内容も農業,食糧増産,畜産,林業,水産など多岐にわたっている。
85年度には,73億9,900万円の予算規模をもって,22か国51件の協力を行った。
(ホ)産業開発協力
開発途上国の地場産業の育成・振興を行うことを目的として,その計画作りから人材養成,適正技術の研究・開発にまで及ぶ総合的・多角的な協力を行う事業である。
85年度には,16億400万円の予算規模をもって,13か国14件の協力を行った。
(6)開発協力
(イ)開発投融資
(a)開発投融資の意義
JICAによる開発投融資は,我が国の民間企業等が開発途上地域などで行う経済協力に対する財政支援制度であり,政府ベースと民間ベースの経済協力の連携の強化及び資金協力と技術協力の結び付きの強化を図るものである。
(b)投融資業務の内容
JICAの投融資は,開発途上地域などの社会の開発並びに農林業及び鉱工業の開発に資する次の事業であって,日本輸出入銀行あるいは海外経済協力基金からの貸付けなどを受けることが困難と認められる事業を対象として,ほかの政府関係機関に比し相当緩和した条件の資金を供与するものである。
(i) 関連施設の整備
開発事業に付随して必要となる関連施設であって,周辺地域の開発に貢献する施設の整備事業,例えば,道路,橋梁,港湾施設,上下水道,市場,学校,病院,公民館,教会,訓練所などである。
(ii) 試験的事業
開発事業のうち試験的に行われるものであって,技術の改良又は開発と一体として行わなければ,その達成が困難な事業である。
(c)投融資事業の実績
85年度の投融資額は,関連施設の整備,試験的事業合わせて総額20億円となった。
(ロ)開発協力調査及び開発協力技術指導
前述の開発投融資の対象となる事業に対し必要な調査及び技術指導(専門家派遣及び研修員受入れ)を行っている。85年度は,29件の調査を実施するとともに,29人の専門家の派遣並びに21人の研修員を受け入れた。
(7)青年海外協力隊(JOCV:JapanOverseasCooperntionVol-Unteers)派遣
青年海外協力隊派遣事業は,我が国の開発途上国に対する技術協力の一環として開発途上国からの要請に基づき,技術を身につけた青年を派遣し,相手国の人々と生活を共にしながら,相手国の社会的・経済的発展に協力し,もってこれら諸国と我が国との親善関係を深めることを目的として,65年に開始された。
協力隊員の派遣は,我が国政府と相手国政府との間での派遣に関する基本取極に基づいて行われている。85年度においては,85年6月にルワンダ,10月には中国との間にそれぞれ派遣取極が締結され,86年3月末現在,派遣
青年海外協力隊派遣(JlCAベース・1965~85年度末累計実績)
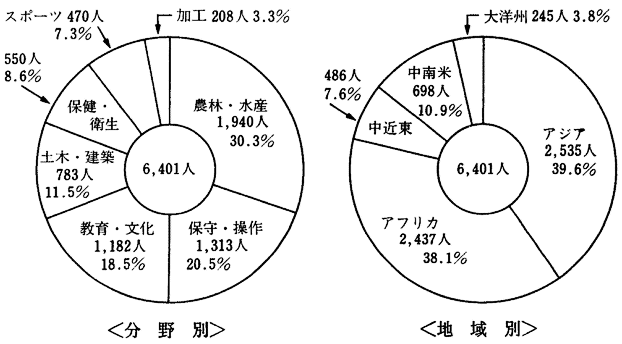
取極締結国は39か国となっている(うちカンボディア,ラオス,エル・サルヴァドル,インド及びウガンダの5か国には,現在は隊員を派遣していない)。
85年度には32か国に799名の隊員を派遣した。これにより65年以来85年末までに派遣した隊員の累計は36か国6,401名(うち女性隊員1,221名)となった。なお,86年3月末現在派遣中の隊員数は1,579名(うち女性隊員393名)となった。
(8)ASEAN青年招へい
ASEAN青年招へい事業は,83年5月,中曽根内閣総理大臣がASEAN諸国を歴訪した際提唱された「21世紀のための友情計画」に基づき,ASEAN各国より毎年150名の青年を5か年にわたり我が国に招へいするものである。85年度はASEAN諸国から合計778名(うちブルネイ30名)の青年を1か月間招へいし,研修並びに我が国青年との交流を行った。