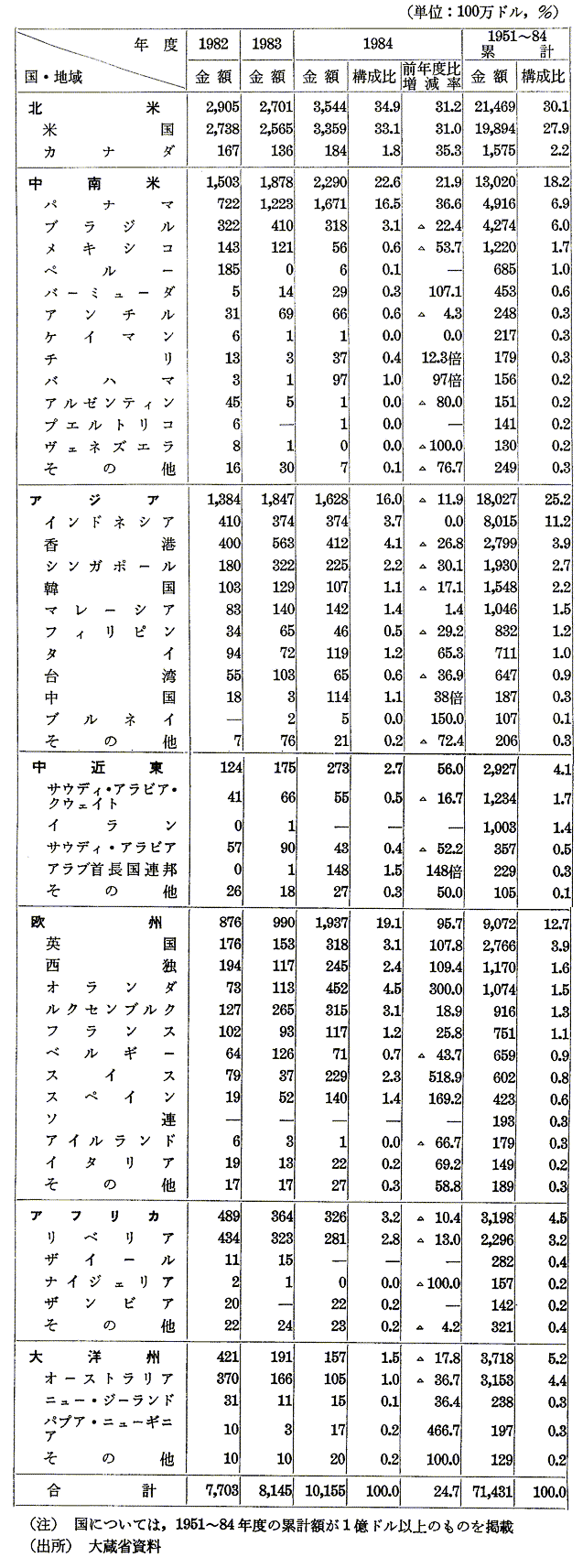
第3節 国際投資問題
1.我が国の投資概要(貿易から投資へ)
84年度の我が国の対外直接投資(届出ベース)は,101億5,500万ドルと前年度(81億4,500万ドル)比24.7%の増加となるとともに,過去最高であった81年度の89億3,100万ドルを上回り,史上初めて100億ドルの大台に乗った。
(1)地域別に見ると(表1),先進国向け投資は,北米向け投資が前年度比31.2%増の35億4,400万ドル,欧州向けが同95.7%増の19億3,700万ドルと急増したため,前年度比45.2%増の56億3,800万ドルとなり,構成比は54.5%と過半数を超えた。
他方,途上国向け投資は,中南米向けが同21.9%増の22億9,000万ドルであったが,アジア向けが同11.9%減の16億2,800万ドルとなったため,同5.9%増の45億1,700万ドルにとどまった。
(2)次に業種別に見ると(表2),製造業にあっては,鉄・非鉄部門が好調であったが全体では前年度比3.2%減となった。
一方,非製造業にあっては,金融・保険業向け投資が,金融の国際化に伴い,同78.7%増となったほか,商業及び運輸業が同20%以上増加したため,同38.7%増となった。
(3)この結果,84年度末現在の我が国の対外直接投資(届出累計額)は714億3,100万ドルとなるとともに,海外直接投資残高(表3)において,西独,オランダを抜き,米国,英国に次ぐ世界第3位の投資国となった。
(4)最近の我が国の対外直接投資の第1の特徴は,米国・欧州等の先進国向け投資(特に製造業向け投資)が増加傾向にあることである。
これは,欧米諸国との貿易摩擦が深刻化し,輸出に代わって海外で生産する気運が高まってきているためと考えられ,84年度においては,米国における鉄鋼分野,欧州における輸送機分野への投資の急増が,その顕著な例である。
第2の特徴は,アジア向け投資が伸び悩んでいることである。
より詳細には,非製造業向け投資が前年度比2.8%増であったのに対し,製造業向け投資が同30.1%と減少しており,製造業向け投資の伸び悩みが主因となっている。これは,70年代に見られたような大規模工業プロジェクトや大型資源開発プロジェクトが少なくなったためであるが,その他労働コストの上昇等各国それぞれ異なった要因も生じていることによる。
このように,我が国の対外直接投資のパターンは,従来の開発途上国での製造業向け投資に代表される低賃金追求型中心の投資から先進国製造業向け投資に代表される貿易摩擦回避型の投資へと変化を見せてきている。
我が国の経常収支黒字の背景に経済構造上の要因が見られる中で,直接投資の促進は重要な課題であり,今後ともこの傾向は強まっていくと思われる。他方,直接投資は,債務性が少なく,経済発展に重要な役割を果たすものであるところ,国際分業を促進し,累積債務問題解決にも資する開発途上国向け投資の増加も期待されている。
(5)OECDにおける討議
OECDの国際投資・多国籍企業委員会は国際的な投資交流の促進及び世界経済の発展に重要な役割を果たしつつある多国籍企業に関して,OECD加盟国間の協力を発展強化せしめることを目的としている。
近年,外国貿易の拡大と多様化及び資源の最適配分を実現する海外直接投資の増大によって,多国籍企業の役割はますます増大しており,他方多国籍企業はその圧倒的優位性のゆえに受入れ国経済に及ぼすマイナス効果も懸念されている。かかる観点から同委員会は76年,「国際投資及び多国籍企業に関する宣言」及び同附属書として「多国籍企業の行動指針」を採択した。同宣言に基づいて同委員会が取り扱っている海外投資問題は次のとおり。
(i) 「内国民待遇」自国内の外資系企業に対し,国内企業と同様の待遇を与えることにより産業,投資交流の促進を図ろうとするもので,サービス分野を中心に外資系企業に対する内国民待遇例外措置減少のためのレビューが行われている。
(ii) 「国際投資の促進,阻害要因」国際的な資本移動に対して促進あるいは抑制効果を及ぼす政策措置が自然な資本の流れを害するおそれがあるとの認識に立つもので,それら措置の最小化と措置に関する情報へのアクセス(各国措置リストの刊行と定期的レビュー)が図られている。
表1.日本の地域別海外直接投資実績(許可・届出ベース)
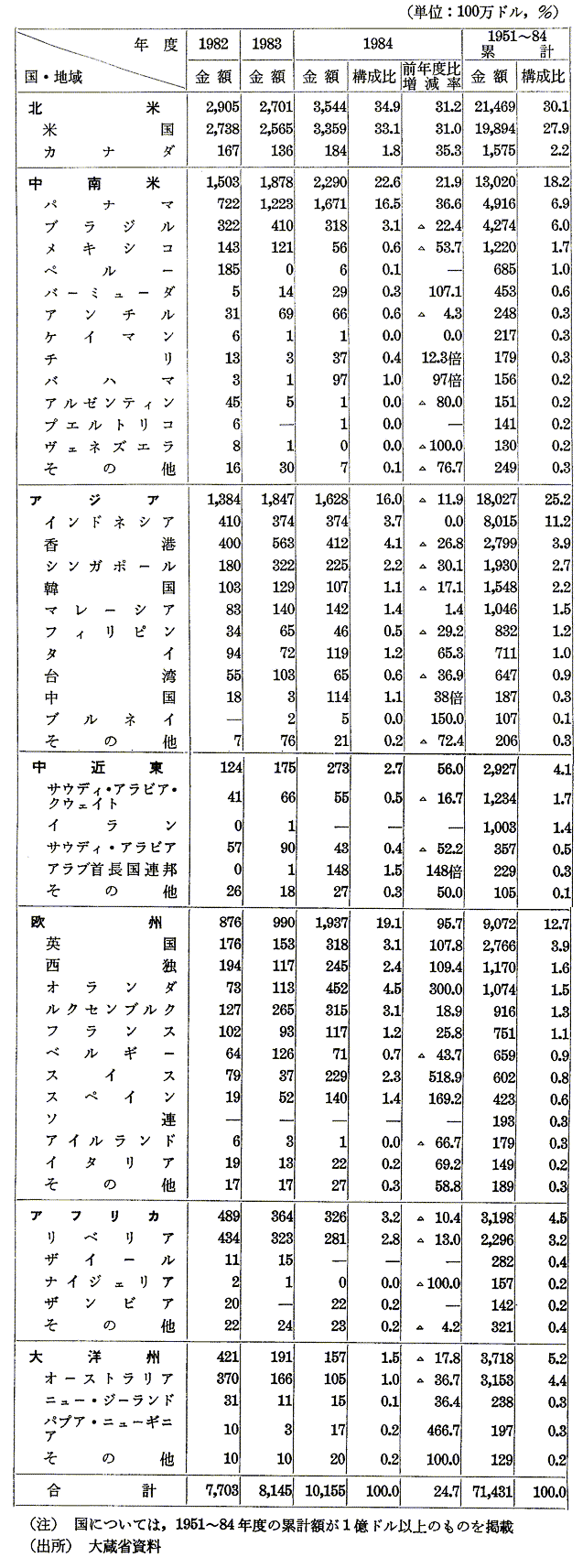
(注)国については,1951~84年度の累計額が1億ドル以上のものを掲載
(出所)大蔵省資料
表2.日本の業種別海外直接投資実績(許可・届出ベース)
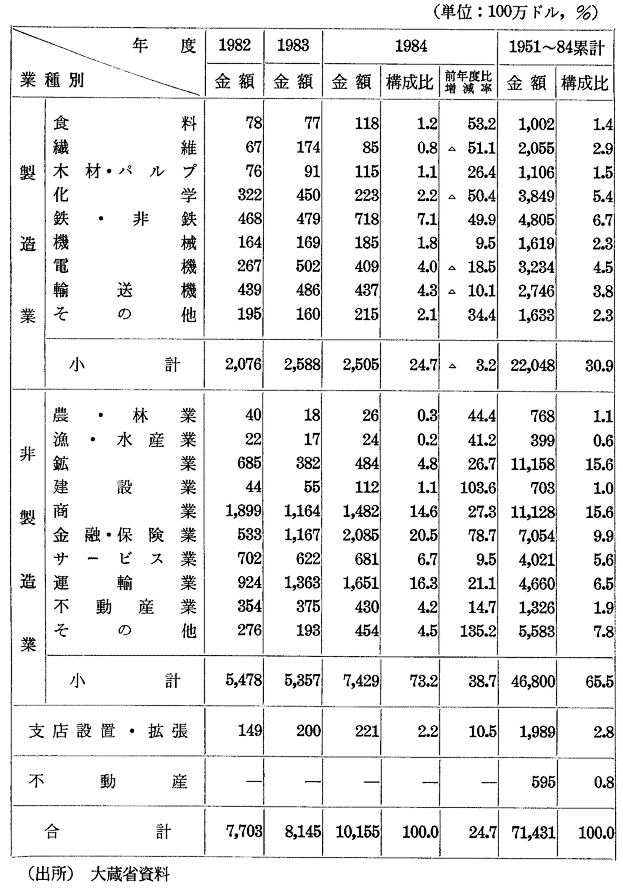
(出所)大蔵省資料
表3.世界の海外直接投資残高
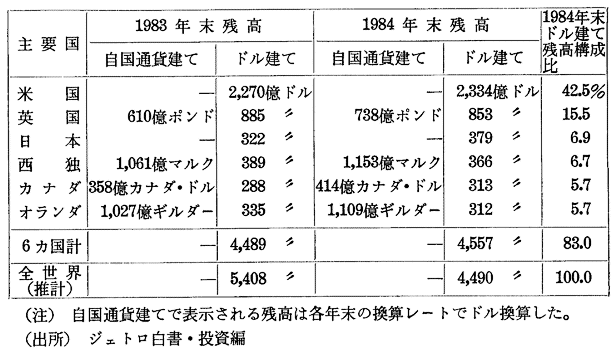
(注)自国通貨建てで表示される残高は各年末の換算レートでドル換算した。
(出所)ジェトロ白書・投資編
2.投資保護協定の締結の促進
(1)我が国の対外直接投資は,増加傾向にあり,今後とも一層活発に行われることが予想される。そもそも海外投資は,投資母国の経済に貢献するのみならず,資本・技術・経営手法の移転,雇用創出効果等により投資受入国の経済発展に資するとともに,経済的・人的交流を通じて両国関係を緊密化し,また貿易摩擦を緩和する役割を果たしている。昨今の貿易摩擦の
我が国の海外直接投資
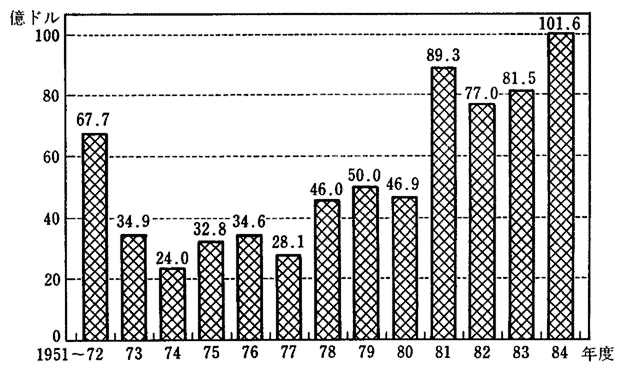
激化等に鑑み,かかる望ましい効果を有する海外投資を今後とも更に促進すべしとの指摘が各方面よりなされている。
(2)海外投資は一義的には民間企業の責任と判断に委ねられているものであるが,民間企業のみでは解決困難な問題もあり,投資母国及び投資受入国が協力して投資環境をできる限り良好なものに整備し,投資を推進する必要がある。
例えば投資受入国の政策が一定しない場合等は,投資家にとって予見可能性及び法的安定性が十分確保されないため投資阻害要因となる。投資保護協定は,事業活動に対する待遇,投資財産の保護に対する待遇等を規定しており,民間投資家に,投資についての予見可能性及び法的安定性を与えるもので,投資保険,税制等の施策と並んでこうした投資環境の整備のための諸施策の一環として重要である。
近年,我が国の海外投資が急増する中で,投資のみを対象として実体的及び手続規定を詳細に定める投資保護協定の必要性が認識されるに至ったが,昨今の我が国を取り巻く経済環境もあって,投資促進の一方策として同協定の重要性が更に高まってきている。
(3)我が国は,現在エジプト及びスリ・ランカとの間に投資保護協定を有しているが,上述の認識の下に,80年12月の日中閣僚会議及び81年1月の鈴木総理大臣のASEAN諸国訪問の際,中国及びASEAN諸国とも,それぞれ投資保護協定の締結交渉に入ることにつき合意に達し,鋭意交渉を行ってきた。